
フリーマン・ワイナリーがグロリア(Gloria)とユーキ(Yu-Ki)の二つの自社畑で「California Certified Organic Farmers(CCOF、カリフォルニア有機栽培農家)」の有機認証を取得しました。CCOFは米農務省の有機認証機関の一つです。
私たちの旅は常に、より健全なブドウ、生き生きとした土壌、そして西ソノマ・コーストをより明確に表現するワインづくりという、明確な目的意識に基づいていました。そして、私たちの挑戦はここで終わりではありません。——次は光風ヴィンヤードです。と、フリーマンは書いています。
オーガニックを選ぶか、それとも家に帰るか?
私たちは、オーガニックでより深いところまで行くことを選びます。
11月には、自社畑を新たに増やしたことも公表されています。セバストポール・ヒルズの畑で、10エーカーにピノ・ノワールとシャルドネ、1エーカーにリースリングを植えるとのこと。ほぼすべてを自社畑のブドウで賄えるようになるそうです。

また、12月3日にはパークハイアット東京のグランド・リオープンで、Yoshikiさんがフリーマンのアキコズ・キュベを楽しんだようです。10月には高市早苗新首相がトランプ米大統領を東京に招いたディナーでフリーマンの2022アキコズ・キュベが振舞われたとのこと。
逆風の多い中、活躍を広げているのは素晴らしいことです。

ガロに売却されて以降、一時は存続が危ぶまれていたレーヴェンズウッドが、復活してきています。そして、ガロは創設者のジョエル・ピーターソンを改めて「スピリット・ガイド」として契約しました。そのジョエルへのインタビュー記事が出ていました(Joel Peterson on Ravenswood’s Rebirth, GLPs and Recapturing Joy – Grape Collective)。
興味深かったのは3カ所。一つはガロでの役割、もう一つはラベルに書かれている「PFM」の3文字の秘密、最後はもう一人のジョエルのことです。
ガロでは試飲には参加していますが、ワイン造りには口を出していないとのこと。レーヴェンズウッド専任で4人を雇っているというから、結構人手をかけていますね。
そして、ガロが新たに裏ラベルに小さく入れた「PFM」の3文字ですが、実はレーヴェンズウッド立ち上げ時のエピソードに基づくものだったそうです。
最初の収穫で、ジョエルは4トンのブドウを何とか一人で収穫して、それを醸造を委託するジョセフ・スワンのワイナリーに運ぼうとしていました。天気予報は雨で、心配していたのですが、ブドウをトラックに積み込んでいる間、2羽の大ガラスが畑に飛んできてジョエルに歌いかけました。それのおかげで雨が降らなかったとジョエルは思っています。そして、最後のブドウを破砕機に入れた瞬間、雨が降り出しました。これは「 純粋なクソマジック」(pure fucking magic)だったという話をガロの人にしたところ、PFMの3文字がラベルに入ったとのことです。
そして、最後の「もう一人のジョエル」とは、ジョエル・ピーターソンの孫、モーガン・トウェイン・ピーターソンの息子であるジョエル・ハワード・ピーターソンのことです。現在5歳になる「若い方のジョエル」ですが、なんと今年初めてのジンファンデルのワインを造ったそうです。モーガンの初ワインである9歳よりも4年も早く! このワインもリリースするんでしょうかね?

シャンパーニュハウス「マム(Mumm)」がナパに作ったマム・ナパ(現在のオーナーはペルノ・リカール)をナパのトリンチェロ・ファミリーが買収することが発表されました。買収内容にはブランドのほか、ワイナリーやカーネロスのデヴォー・ランチ(Devaux Ranch)が含まれています。買収価格は明らかになっていません。2026年春に買収完了の予定です。
マムは1970年代末にスパークリングワインを造る土地を探しにワインメーカーが渡米、1983年に最初の米国製スパークリングワインをリリースしています。当初はドメーヌ・マムという名称で、1990年からマム・ナパになっています。
トリンチェロは今後、マム・ナパのスパークリングワインを米国、カナダ、メキシコ、カリブ諸島で販売する権利を得たとのこと。
トリンチェロ・ファミリー傘下のワイナリーには、ナパのトリンチェロのほか、サター・ホーム、メナージュ・ア・トロワ、シーグラス、ジョエル・ゴット、ナパ・セラーズ、チャールズ&チャールズ、スリー・シーヴス、カリフォルニア・ルーツなどがあります。

ヴィナスが先日公開した2025年の振り返り記事で、ダラ・ヴァレのマヤさんをワインメーカー・オブザイヤーに選んでいました。
世代交代は、交代する側にとっても交代される側にとっても簡単なことではないとし、マヤさんの経歴に触れた後に、2023年のダラ・ヴァレのワインが、これまでのダラ・ヴァレと比べてタンニンのマネジメントが非常に良くなっているとしています。
ちなみにレイティングはカベルネ・ソーヴィニヨンが100点、マヤが98点、MDV(ナパのいろいろな畑からのカベルネ・ソーヴィニヨンのブレンド)が98+、セカンドのコリーナが94点でした。
これを受けて、マヤさんがインスタグラムに投稿したのが下のもの。ちょうど30年前、1995年12月14日にがんで亡くなった父親を偲んで、マヤさんが小さいころからの家族の写真が出ています。
コメントには以下のような内容が書かれています。
これは信じられないほどの栄誉であり、この事業で成功を願ってくれた方々の支援と導きがなければ決して得られなかったものです。心から感謝するとともに、小さな家族経営のワイナリーとして成し遂げた成果を誇りに思います。しかし、この知らせを母と祝った後、父とこのマイルストーンを分かち合えないことに気づき、感情が込み上げてきました。私にできる最善は、父の遺志を尊び、彼の記憶を生き続けるよう、これからも懸命に努力し前進し続けることです。
マヤさん、おめでとうございます!

カリフォルニアワイン協会が2025年の収穫レポートを公表しました。その主な内容を紹介します。
2025年のカリフォルニアにおけるワイン用ブドウの収穫は、穏やかで安定した生育シーズンに支えられ、品質面で非常に高い評価を受けるヴィンテージとなっています。春は冷涼に始まり、夏も極端な高温に見舞われることがほとんどなく、成熟期から収穫期にかけても比較的温和な気候が続きました。この結果、ブドウは急激に糖度を上げることなく、ゆっくりとバランスよく成熟しました。
収穫開始時期は地域によって差がありましたが、多くの産地で例年より最大2週間ほど遅れました。9〜10月にかけて一部で降雨があったものの、収穫時期の判断や入念な選果、キャノピー管理によって品質低下を回避しています。特に水はけの良い畑では、降雨がかえって果実の表現力や風味の奥行きを高めたと評価されている。
収量については「平均〜やや少なめ」とする声が多くなっています。USDAは2025年のカリフォルニア全体のワイン用ブドウ生産量を約300万トンと予測しており、前年比では増加したものの、直近3年平均を下回っています。一方、カリフォルニア・ワイン用ブドウ生産者協会(CAWG)は、これよりやや低い250万トン弱と見積もっており、数量よりも品質重視の年であることが示唆されています。
ワインのスタイル面では、2025年は「エレガンス」「抑制」「テロワール表現」がキーワードとして繰り返し語られています。赤ワインは過度なパワーに寄らず、深みと構造を備えた洗練されたスタイルになり、白ワインは明るい酸と精密さが際立つと予想されている。糖度が比較的低い段階で収穫されたブドウが多く、結果としてアルコール度数は控えめになり、現代的な嗜好に合致したバランスの良いワインが期待されています。
以下では地域別の状況を紹介します。
ナパ・ヴァレー
ナパ・ヴァレーでは、冷涼なシーズンと十分な冬季降雨により、健全な樹勢と均一な成熟が実現しました。収量は予想以上に多く、品質も非常に高い年となりました。カベルネ・ソーヴィニヨンやカベルネ・フランは、低めの糖度でも十分なフェノール熟度と深い色調を示しています。晩夏の降雨はありましたが、水はけの良い畑ではむしろ風味の立体感を高める結果となりました。全体として、長期熟成に耐えるクラシックなスタイルが期待されています。
ソノマ・カウンティ
ソノマでは、冬から春にかけての安定した降雨と冷涼な夏が理想的な条件を生みました。シャルドネやピノ・ノワールは、酸と果実味のバランスに優れ、風味の純度が高い仕上がりです。収穫は平年並みの時期に始まりましたが、秋の降雨を見据えて多くの生産者が迅速に対応しました。その結果、全体的に非常に健全な果実が確保され、品質重視のヴィンテージとなっています。
ローダイ
ローダイでは、シーズン全体を通して冷涼で安定した気候が続きました。酸がしっかりと保持され、赤品種では濃い色調と深い風味が得られています。特にジンファンデルは、凝縮感とバランスに優れた仕上がりが期待されています。古木の収量はやや少なめでしたが、品質面での評価は非常に高い年です。
パソ・ロブレス
パソ・ロブレスでは、記録的に涼しい夏が成熟をゆっくりと進めました。カベルネ・ソーヴィニヨンは十分なハングタイムを確保でき、色調、構造、香味が向上しています。白ワインも非常にクリーンで成熟度が高く、全体として2023年ヴィンテージに近い高評価が見込まれています。
サンタ・バーバラ
サンタ・バーバラでは、低糖度ながら高い熟度を達成したことが特徴です。ピノ・ノワールは特に高品質で、自然な酸と低アルコールのエレガントなスタイルが期待されています。一部地域では山火事の煙の影響がありましたが、適切な選果によって品質は確保されました。
その他地域(サンディエゴ、テメキュラ、サスーン・ヴァレーなど)
南部や内陸の小規模産地でも、冷涼な気候の恩恵により良好な品質が報告されています。テメキュラでは収量は少なめでしたが、酸と品種特性が際立つ年となりました。サスーン・ヴァレーでは、一部で課題はあったものの、全体として安定した仕上がりです。
ソノマのロシアン・リバー・ヴァレーに、日系女性ドンナ・カトウによる新しいワイナリー「アドンナ(Adonna)」が設立されたという記事がForbesに出ていました。

ドンナ・カトウの座右の銘が「一期一会」。「日本の哲学である『一期一会』は、ブドウ畑の進化する性質、つまりブドウが最高の状態へと成熟していく中での季節の移り変わり、そしてどのヴィンテージも前年や来年とは同じではないという考え方を反映しています。私たちは、ブドウ畑の声をワインを通して表現し、それぞれのボトルに場所と時間の神聖さを捉えるよう、ワイン造りを工夫しています」と説明している。

ドンナ・カトウは生化学を学び、研究生物学者としてキャリアをスタートし、後にバイオテクノロジー・コンサルティング会社を設立して成功を収めました。UCデーヴィスの学生時代にブドウ栽培の入門クラスを受講したことがあり、ワイン造りに興味を持つようになりました。その後、乳がんと診断されたことをきっかけにキャリアを考え、土地とのつながりを求めてワイン造りを始めることにしました。ワイナリーを始めるにあたっては改めてブドウ栽培と醸造の修士を取得しています。
アドンナの畑「キャンフィールド・ヴィンヤード(Canfield Vineyard)」はロシアン・リバー・ヴァレーのセバストポール・ヒルズにあります。ゴールドリッジ土壌の土地です。

アドンナのラベルにはイチョウの葉が描かれています。イチョウは不屈の精神と長寿を象徴する植物として崇められているとのこと。また、彼女の4人の息子たちへの敬意も表しています。葉が円を描くのは自然の循環やワイン造り、人生の様々な段階をイメージしています。
アドンナのメインのワインはピノ・ノワールですが、ユニークなのはピノ・ノワールから白ワインも作っていることです。ピノ・ノワールのボディ感を保ちながら白ワインのフレッシュさもあるワインだそうです。

ドンナ・カトウの座右の銘が「一期一会」。「日本の哲学である『一期一会』は、ブドウ畑の進化する性質、つまりブドウが最高の状態へと成熟していく中での季節の移り変わり、そしてどのヴィンテージも前年や来年とは同じではないという考え方を反映しています。私たちは、ブドウ畑の声をワインを通して表現し、それぞれのボトルに場所と時間の神聖さを捉えるよう、ワイン造りを工夫しています」と説明している。

ドンナ・カトウは生化学を学び、研究生物学者としてキャリアをスタートし、後にバイオテクノロジー・コンサルティング会社を設立して成功を収めました。UCデーヴィスの学生時代にブドウ栽培の入門クラスを受講したことがあり、ワイン造りに興味を持つようになりました。その後、乳がんと診断されたことをきっかけにキャリアを考え、土地とのつながりを求めてワイン造りを始めることにしました。ワイナリーを始めるにあたっては改めてブドウ栽培と醸造の修士を取得しています。
アドンナの畑「キャンフィールド・ヴィンヤード(Canfield Vineyard)」はロシアン・リバー・ヴァレーのセバストポール・ヒルズにあります。ゴールドリッジ土壌の土地です。

アドンナのラベルにはイチョウの葉が描かれています。イチョウは不屈の精神と長寿を象徴する植物として崇められているとのこと。また、彼女の4人の息子たちへの敬意も表しています。葉が円を描くのは自然の循環やワイン造り、人生の様々な段階をイメージしています。
アドンナのメインのワインはピノ・ノワールですが、ユニークなのはピノ・ノワールから白ワインも作っていることです。ピノ・ノワールのボディ感を保ちながら白ワインのフレッシュさもあるワインだそうです。
ワシントン州で最大手のカスタム・クラッシュ・ワイナリー「コヴェントリー・ヴェール(Coventry Vale)」を所有するワイコフ家が、ワシントン最大のワイナリーであるシャトー・サン・ミシェルを買収しました。サン・ミシェルがワシントン州に拠点を置く民間企業に買収されるのは、50年以上ぶりとなります。今回の買収には、ワシントン州にあるセントミッシェルのワインブランド、施設、畑がすべて含まれています。
ワイコフ家は1978年からブドウ栽培を始め、1980年代からサン・ミシェルのパートナーとしてサン・ミシェルのワインを作ってきました。
「サン・ミシェルは長年にわたりワシントン州のワイン産業を牽引してきました。1980年代初頭からのパートナーとして、私たちはサン・ミシェル・ワイン・エステーツが誇る北西部を代表するワインブランドの卓越したポートフォリオを深く信頼しています。サン・ミシェルのチームと共に、そのリーダーシップをさらに強化し、ワイン造りの品質向上に投資し、ワシントン州のブドウ栽培農家とワシントン州産ワインを全国の消費者にお届けできることを楽しみにしています」と」とコベントリー・ベール・ワイナリーのCEO、コート・ワイコフ氏は述べています。
シャトー・サン・ミシェルは2021年にプライベート・エクイティ投資会社のシカモア・パートナーズに買収されていました。今回の買収はワシントン州のブランドを対象としており、サン・ミシェル傘下のオレゴンのワイナリーA to ZやErath、Rex Hillはシカモアに残ります。
ワイコフ家は1978年からブドウ栽培を始め、1980年代からサン・ミシェルのパートナーとしてサン・ミシェルのワインを作ってきました。
「サン・ミシェルは長年にわたりワシントン州のワイン産業を牽引してきました。1980年代初頭からのパートナーとして、私たちはサン・ミシェル・ワイン・エステーツが誇る北西部を代表するワインブランドの卓越したポートフォリオを深く信頼しています。サン・ミシェルのチームと共に、そのリーダーシップをさらに強化し、ワイン造りの品質向上に投資し、ワシントン州のブドウ栽培農家とワシントン州産ワインを全国の消費者にお届けできることを楽しみにしています」と」とコベントリー・ベール・ワイナリーのCEO、コート・ワイコフ氏は述べています。
シャトー・サン・ミシェルは2021年にプライベート・エクイティ投資会社のシカモア・パートナーズに買収されていました。今回の買収はワシントン州のブランドを対象としており、サン・ミシェル傘下のオレゴンのワイナリーA to ZやErath、Rex Hillはシカモアに残ります。
米国のTTB(酒類・タバコ税貿易管理局)が出しているワインの生産量のレポート「Wine Reports | TTB: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau」を少し調べてみました。

まず、2024年のワイン生産量の州別トップ11です。気になるところは2つ。5位にケンタッキーという、ワインでは耳慣れない州が入っていること。それから2位がニューヨークになっていることです。なお、単位は米ガロン(1ガロンは約3.8リットル)です。
TTBのデータには2012年からのものが入っているので、2024年の生産量2位から9位の州について、2012年からの推移のグラフを作ってみました。1位のカリフォルニアを除いたのは、それだけかけ離れて多いので、他の州の推移が分からなくなってしまうからです。

ニューヨーク州と、3位になったワシントン州を比べると、元々それほど大きな差があったわけではなく、過去にも2014年にニューヨーク州が2位になったことがありましたし、2021年や2023年もかなり小さな差でした。これからも年によって、順位の変動はありそうです。
一方、ケンタッキー州については2022年までは統計の数字がなく、2023年から急に5位に入ってきています。ケンタッキー州にもワイナリーはありますから、これまで単に統計から漏れていたのかもしれませんが、それにしても5位に入るほどの生産量があるとはちょっと思えない感じもします。大手ワイナリーの工場ができたなどの理由もあるのかもしれないと思いましたが、調べて範囲ではわかりませんでした。ちなみにソムリエ教本にも載っているバージニア州は9位です。
TTBのデータにはProduction(生産量)のほかにTaxable Withdrawals(課税対象の引き出し)、Tax Free Withdrawals(非課税の引き出し)、Stocks on Hand End-of-Period(期末在庫)の項目も入っています。課税対象の引き出しとは主に国内市場への出荷、非課税の引き出しとは主に輸出や加工用の出荷です。
そこで、生産量と課税対象の引き出しの推移をグラフにしてみました。

米国のワイン消費が2020年で頭打ちになったと言われていますが、赤い線の方を見るとそれがよく分かります。2024年は2020年と比べると22ポイントも減っています。生産量の方は2023年までは横ばいでしたが、2024年は大きく減っています。2024年から本格的な生産調整に入ってきているのだと思います。

Tax Free Withdrawals(非課税の引き出し)のグラフです。おそらく輸出が大部分だと思います。右肩上がりで増えてはいます。ただ、国内消費の減少分を補うほどまでにはなっていません。輸出比率(赤線)は上がってきてはいます。

まず、2024年のワイン生産量の州別トップ11です。気になるところは2つ。5位にケンタッキーという、ワインでは耳慣れない州が入っていること。それから2位がニューヨークになっていることです。なお、単位は米ガロン(1ガロンは約3.8リットル)です。
TTBのデータには2012年からのものが入っているので、2024年の生産量2位から9位の州について、2012年からの推移のグラフを作ってみました。1位のカリフォルニアを除いたのは、それだけかけ離れて多いので、他の州の推移が分からなくなってしまうからです。

ニューヨーク州と、3位になったワシントン州を比べると、元々それほど大きな差があったわけではなく、過去にも2014年にニューヨーク州が2位になったことがありましたし、2021年や2023年もかなり小さな差でした。これからも年によって、順位の変動はありそうです。
一方、ケンタッキー州については2022年までは統計の数字がなく、2023年から急に5位に入ってきています。ケンタッキー州にもワイナリーはありますから、これまで単に統計から漏れていたのかもしれませんが、それにしても5位に入るほどの生産量があるとはちょっと思えない感じもします。大手ワイナリーの工場ができたなどの理由もあるのかもしれないと思いましたが、調べて範囲ではわかりませんでした。ちなみにソムリエ教本にも載っているバージニア州は9位です。
TTBのデータにはProduction(生産量)のほかにTaxable Withdrawals(課税対象の引き出し)、Tax Free Withdrawals(非課税の引き出し)、Stocks on Hand End-of-Period(期末在庫)の項目も入っています。課税対象の引き出しとは主に国内市場への出荷、非課税の引き出しとは主に輸出や加工用の出荷です。
そこで、生産量と課税対象の引き出しの推移をグラフにしてみました。

米国のワイン消費が2020年で頭打ちになったと言われていますが、赤い線の方を見るとそれがよく分かります。2024年は2020年と比べると22ポイントも減っています。生産量の方は2023年までは横ばいでしたが、2024年は大きく減っています。2024年から本格的な生産調整に入ってきているのだと思います。

Tax Free Withdrawals(非課税の引き出し)のグラフです。おそらく輸出が大部分だと思います。右肩上がりで増えてはいます。ただ、国内消費の減少分を補うほどまでにはなっていません。輸出比率(赤線)は上がってきてはいます。
2018年に設立し、ボニー・ドゥーンやトード・フォロー、ラピス・ルナなどのブランドを所有するウォールーム・セラーズが、歴史的ブランド「SIMI(シミ)」をThe Wine Group(TWG)から取得しました。The Wine Groupがコンステレーション・ブランズから同ブランドを取得したのは25年6月のことで、半年足らずでの売却となりました。価格は公開されていません。
SIMIは1876年にソノマで設立された歴史あるワイナリー。1904年、父と叔父がインフルエンザで亡くなり、18歳でワイナリーを引き継いだイザベル・シミで知られています。禁酒法下では聖餐用のワインを販売し、禁酒法が廃止されると、ため込んでいた在庫のワインを放出して有名になりました。
その後も、女性のリーダーシップが続き、中でもワインメーカーだけでなく、社長として会社の経営も担ったゼルマ・ロングは有名です。直近も女性ワインメーカーのレベッカ・ヴァルスがワイン造りを担っています。
ウォールーム・セラーズはワインブランドを購入して、その価値を上げることに注力しています。ウォールーム・セラーズのワイン醸造ディレクター、ニコール・ウォルシュは、「イザベル、ゼルマ、そして私の先人たちであるSIMIの女性たちに深い敬意を抱いています。カリフォルニアワインの歴史におけるこの重要な伝統を引き継いでいくことを楽しみにしています」と語っています。

SIMIは1876年にソノマで設立された歴史あるワイナリー。1904年、父と叔父がインフルエンザで亡くなり、18歳でワイナリーを引き継いだイザベル・シミで知られています。禁酒法下では聖餐用のワインを販売し、禁酒法が廃止されると、ため込んでいた在庫のワインを放出して有名になりました。
その後も、女性のリーダーシップが続き、中でもワインメーカーだけでなく、社長として会社の経営も担ったゼルマ・ロングは有名です。直近も女性ワインメーカーのレベッカ・ヴァルスがワイン造りを担っています。
ウォールーム・セラーズはワインブランドを購入して、その価値を上げることに注力しています。ウォールーム・セラーズのワイン醸造ディレクター、ニコール・ウォルシュは、「イザベル、ゼルマ、そして私の先人たちであるSIMIの女性たちに深い敬意を抱いています。カリフォルニアワインの歴史におけるこの重要な伝統を引き継いでいくことを楽しみにしています」と語っています。


ナパヴァレーのサスティナブル認証プログラム「ナパ・グリーン」が認証済みの101のすべての畑で除草剤「ラウンドアップ」に代表される化学物質グリホサートを使った製品の排除に成功しました。2023年末に立てた目標を達成したことになります。ナパ・グリーンのエグゼクティブディレクター、アナ・ブリテン氏は「私たちは生産者と協力し、土壌から水、そして人々に至るまで、体系的に有益な農法を実施しています。ラウンドアップはこれら3つすべてにリスクをもたらします。ナパグリーンのメンバーは、可能性を示しています。世界中の生産者の心に響くことを願っています」と語っています。
グリホサートの廃止をサポートするために、ナパ・グリーンは雑草管理ツールキット、トレーニング ワークショップ、栽培者が畑固有の条件に合った代替手法を実施できるようにするための個別支援を含む包括的なサポート システムを開発しました。2024年にはサン・スペリー、チムニー・ロック、ポール・ホブス、コリソンの各ワイナリーに助成金を提供し、新しい草刈り機の調達と羊の放牧試験を実施しました。
次の目標としては、すべての合成除草剤の廃止を2027年末までに達成することが挙げられています。「除草剤からの転換は、農場労働者、土壌、そしてブドウの木の健康にとって不可欠です。これは、ワイン産業の再生を継続し、現代の消費者と繋がり、そして私たちが農業を営む地域社会と生態系の向上を目指す道のりにおける重要な一歩です」とナパ・グリーンでブドウ畑のプログラム・マネジャを務めるベン・マッキー氏は語っています。
カリフォルニア州ワイン用ブドウ栽培者協会(CAWG)が、各地の栽培者協会と協力し、カリフォルニアのブドウ畑の正確なデータベースを作成しました。Land IQという企業の技術を使い、リモートセンシング、人工知能、現地でのフィールド検証などの方法を活用して、これまでで一番正確なデータベースになったといいます。
この結果、2025年8月時点で477,475エーカーのブドウ畑が存在しており、2024年10月から2025年8月の間に38,134エーカーが伐採されたことが判明した。これは約7.3%に相当します。

郡ごとの、畑の面積と引き抜かれた面積のデータも公開されています。畑の減少率が10%を超えるのは、大部分が低価格ワインの産地であるセントラル・ヴァレーの郡ですが、サンタ・バーバラやモントレーも平均以上の8%台であり、高級ワインの産地であるナパも6.8%と比較的上位に入ります。
引き抜かれた面積の多い順で見ても、1位と2位はセントラル・ヴァレーのサンホアキンとフレズノですが、3番目がモントレー、以下ナパ、ソノマ、サン・ルイス・オビスポ(パソ・ロブレスやSLOコーストを含む)と有名産地が続きます。
また、別の記事によると、2025年の収穫ではナパのおよそ20%にあたる8000エーカーが、収穫せずに放置されてしまったといいます。現在の予測では、2025年のカリフォルニア全体の収穫量は250万トンを下回り、近年では最も少なくなりそうです。
2023年と2024年のナパは収穫量が多く、2025年はそのための調整という面もあるようです。クオリティが少しでも落ちるところは収穫されなかったと見られます。これを機会に植え替えが進むという見方もあります。
この結果、2025年8月時点で477,475エーカーのブドウ畑が存在しており、2024年10月から2025年8月の間に38,134エーカーが伐採されたことが判明した。これは約7.3%に相当します。

郡ごとの、畑の面積と引き抜かれた面積のデータも公開されています。畑の減少率が10%を超えるのは、大部分が低価格ワインの産地であるセントラル・ヴァレーの郡ですが、サンタ・バーバラやモントレーも平均以上の8%台であり、高級ワインの産地であるナパも6.8%と比較的上位に入ります。
引き抜かれた面積の多い順で見ても、1位と2位はセントラル・ヴァレーのサンホアキンとフレズノですが、3番目がモントレー、以下ナパ、ソノマ、サン・ルイス・オビスポ(パソ・ロブレスやSLOコーストを含む)と有名産地が続きます。
また、別の記事によると、2025年の収穫ではナパのおよそ20%にあたる8000エーカーが、収穫せずに放置されてしまったといいます。現在の予測では、2025年のカリフォルニア全体の収穫量は250万トンを下回り、近年では最も少なくなりそうです。
2023年と2024年のナパは収穫量が多く、2025年はそのための調整という面もあるようです。クオリティが少しでも落ちるところは収穫されなかったと見られます。これを機会に植え替えが進むという見方もあります。
前回は、高評価ワインのお薦めを紹介しましたが、今回はブラックフライデーセールからのお薦めです。
リカオーではリッジのワインがお買い得、リットン・エステートのプティ・シラー、スリーバレー、パガニ・ランチのジンファンデルといずれも5999円ですが、この中ではパガニ・ランチが一押し。ソノマ・ヴァレーの古木の畑で1890年に植樹されています。新しい樹でも1910年頃というから、基本100年以上の樹ばかりです。古木の畑の中でもこれだけ古い樹が多いのは珍しいとか。パーカー94点、ヴィナス93点と評価もかなり高いワイン。米国でも税抜きで50ドル程度するワインですから、日本で買う方が安いです。
しあわせワイン倶楽部では、人気の689のワインくじというユニークな企画を実施中。689はサブミッションやラムゼイなど、中価格帯中心にいろいろなブランドを持っています。その計15種をくじびきで、というのがこの企画。2398円と普通に689を買うよりも安く、一番高いものは7370円の「マスター・アンド・サーバント」。15種類注文したら、全部1本ずつ当たるそうです。とりあえず689買う代わりに試してみるのも楽しそうです。
先日紹介したサンタ・バーバラのプレスキール。セラー専科ではポイント10倍付くので、エントリー版のピノ・ノワールなら実質4000円台。ぜひお試しいただきたい。
リカオーではリッジのワインがお買い得、リットン・エステートのプティ・シラー、スリーバレー、パガニ・ランチのジンファンデルといずれも5999円ですが、この中ではパガニ・ランチが一押し。ソノマ・ヴァレーの古木の畑で1890年に植樹されています。新しい樹でも1910年頃というから、基本100年以上の樹ばかりです。古木の畑の中でもこれだけ古い樹が多いのは珍しいとか。パーカー94点、ヴィナス93点と評価もかなり高いワイン。米国でも税抜きで50ドル程度するワインですから、日本で買う方が安いです。
しあわせワイン倶楽部では、人気の689のワインくじというユニークな企画を実施中。689はサブミッションやラムゼイなど、中価格帯中心にいろいろなブランドを持っています。その計15種をくじびきで、というのがこの企画。2398円と普通に689を買うよりも安く、一番高いものは7370円の「マスター・アンド・サーバント」。15種類注文したら、全部1本ずつ当たるそうです。とりあえず689買う代わりに試してみるのも楽しそうです。
先日紹介したサンタ・バーバラのプレスキール。セラー専科ではポイント10倍付くので、エントリー版のピノ・ノワールなら実質4000円台。ぜひお試しいただきたい。
ナパヴァレーのサスティナブル認証団体Napa Greenが再生可能型の農法推進を掲げています。11月から「One Block Challenge」というプログラムを、再生可能型のブドウ造りを推進するRegenerative Viticulture Foundation(RVF)と共同で始めました。

One Block Challengeは、畑全体を一気に再生可能型に転換するのではなく、1ブロックだけを手始めにやってみようというもの。11月18日にはナパのOpus Oneで、11月19日にはソノマのBedrockで体験イベントを開催しました。
なお、RVFは再生可能型のブドウ栽培を推進していますが認証団体ではありません。認証団体としてはROC(Regenerative Organic Certified)が代表的ですが、現在はそれ以外にも複数の認証があり、Napa Greenもその一つになるようです。
再生可能型の栽培が話題になり始めてから、まだ3年弱ですが、知る人ぞ知るというものだったところから、業界全体の動きにまで変わりつつある勢いを感じます。

One Block Challengeは、畑全体を一気に再生可能型に転換するのではなく、1ブロックだけを手始めにやってみようというもの。11月18日にはナパのOpus Oneで、11月19日にはソノマのBedrockで体験イベントを開催しました。
なお、RVFは再生可能型のブドウ栽培を推進していますが認証団体ではありません。認証団体としてはROC(Regenerative Organic Certified)が代表的ですが、現在はそれ以外にも複数の認証があり、Napa Greenもその一つになるようです。
再生可能型の栽培が話題になり始めてから、まだ3年弱ですが、知る人ぞ知るというものだったところから、業界全体の動きにまで変わりつつある勢いを感じます。
年末のランキング発表シーズンが始まり、今年も注目のワインが出てきています。
ランキングの老舗であり一番話題になるのがワイン・スペクテーター。今年は1位はボルドーのシャトー・ジスコースでしたが、2位にオーベールのUV-SLシャルドネ、3位にリッジのリットン・スプリングス、4位にウィリアムズ・セリエムのピノ・ノワール「イーストサイド・ロード・ネイバーズ」、8位にウェイフェアラーのピノ・ノワールとトップ10に4本入りました。リッジのリットン・スプリングスのような伝統あるワインが入ってくるのは嬉しいです。
ただ、トップ10の中で、国内に同ヴィンテージが流通しているのはオーベールのUV-SLシャルドネ2023だけでした。3万円超える高額ワインではありますが、オーベールのシャルドネは劇旨なので飲みたい!
と、注目が集まるのはトップ10ですが、トップ100に入るだけでも大したものです。スペクテーターの年間レビュー本数が1万を超えているのですから、トップ100というのはわずか1%しか選ばれないわけですから。
トップ10から漏れた中でも注目は11位に入ったオレゴンのクリストム。マウント・ジェファーソン・キュベのピノ・ノワールは50ドルで、ここのワインの中では入門的な位置付けになります。50ドルでコスパが評価されたワインですが、実は国内では5000円台でも売られていて、米国で買うよりも安いのです。これはむちゃくちゃお買い得。
27位に入ったのはパイン・リッジの「シュナン・ブラン-ヴィオニエ」2024。このワイン、好きなんです。2000円台と価格も優しい。
51位に入ったキャッターウォールのカベルネ2023。キャッターウォールなんて名前は聞いたことがないという人が大半だと思いますが、造っているのはトーマス・リヴァース・ブラウンです。知る人ぞ知るワインですが、こういうのを掘り起こしてくるのはワイン・スペクテーターもやるなあという感じです。1万円以下のカベルネ・ソーヴィニヨンの中ではベストの一つでしょう。
年間ランキングとは別に、むちゃくちゃなコスパで驚いたのがフォーマンのカベルネ・ソーヴィニヨン2014。1万5000円くらいで売っている店もありますが、米国では130ドル以上するので、そのまま円換算したら2万円こえてしまいます(海外の価格は税抜きで書かれているので消費税まで入れるとそうなります)。このワイン、Vinousのアントニオ・ガローニが今年1月にレビューしていてなんと98点を付けています(それ以前だと2017年に94点を付けていました)。熟成の最初のピークに入ってきた旨書かれています。楽天では2012年や2011年も売っていて、これらも評価は結構高いですが、さすがに98点には達していないので、今買うならこれがベストでしょう。ちょうどよく熟成してこれだけ評価が高いワインはなかなか手に入りません。
最後はピノ・ノワール。一昨年のスペクテーターで年間2位だったのがスティーブ・キスラーが作るオキシデンタルのピノ・ノワール「フリーストーン・オキシデンタル」2021でしたが、このときのレイティングが94点。実は現行の2023点は95点とさらに評価は上がっていますが、価格は当時とほとんど変わりません。今、高級ピノ・ノワールを買うならお薦めの1本です(コスパではクリストムが圧倒していますが)。
ランキングの老舗であり一番話題になるのがワイン・スペクテーター。今年は1位はボルドーのシャトー・ジスコースでしたが、2位にオーベールのUV-SLシャルドネ、3位にリッジのリットン・スプリングス、4位にウィリアムズ・セリエムのピノ・ノワール「イーストサイド・ロード・ネイバーズ」、8位にウェイフェアラーのピノ・ノワールとトップ10に4本入りました。リッジのリットン・スプリングスのような伝統あるワインが入ってくるのは嬉しいです。
ただ、トップ10の中で、国内に同ヴィンテージが流通しているのはオーベールのUV-SLシャルドネ2023だけでした。3万円超える高額ワインではありますが、オーベールのシャルドネは劇旨なので飲みたい!
と、注目が集まるのはトップ10ですが、トップ100に入るだけでも大したものです。スペクテーターの年間レビュー本数が1万を超えているのですから、トップ100というのはわずか1%しか選ばれないわけですから。
トップ10から漏れた中でも注目は11位に入ったオレゴンのクリストム。マウント・ジェファーソン・キュベのピノ・ノワールは50ドルで、ここのワインの中では入門的な位置付けになります。50ドルでコスパが評価されたワインですが、実は国内では5000円台でも売られていて、米国で買うよりも安いのです。これはむちゃくちゃお買い得。
27位に入ったのはパイン・リッジの「シュナン・ブラン-ヴィオニエ」2024。このワイン、好きなんです。2000円台と価格も優しい。
51位に入ったキャッターウォールのカベルネ2023。キャッターウォールなんて名前は聞いたことがないという人が大半だと思いますが、造っているのはトーマス・リヴァース・ブラウンです。知る人ぞ知るワインですが、こういうのを掘り起こしてくるのはワイン・スペクテーターもやるなあという感じです。1万円以下のカベルネ・ソーヴィニヨンの中ではベストの一つでしょう。
年間ランキングとは別に、むちゃくちゃなコスパで驚いたのがフォーマンのカベルネ・ソーヴィニヨン2014。1万5000円くらいで売っている店もありますが、米国では130ドル以上するので、そのまま円換算したら2万円こえてしまいます(海外の価格は税抜きで書かれているので消費税まで入れるとそうなります)。このワイン、Vinousのアントニオ・ガローニが今年1月にレビューしていてなんと98点を付けています(それ以前だと2017年に94点を付けていました)。熟成の最初のピークに入ってきた旨書かれています。楽天では2012年や2011年も売っていて、これらも評価は結構高いですが、さすがに98点には達していないので、今買うならこれがベストでしょう。ちょうどよく熟成してこれだけ評価が高いワインはなかなか手に入りません。
最後はピノ・ノワール。一昨年のスペクテーターで年間2位だったのがスティーブ・キスラーが作るオキシデンタルのピノ・ノワール「フリーストーン・オキシデンタル」2021でしたが、このときのレイティングが94点。実は現行の2023点は95点とさらに評価は上がっていますが、価格は当時とほとんど変わりません。今、高級ピノ・ノワールを買うならお薦めの1本です(コスパではクリストムが圧倒していますが)。
多分、これ以上のワイン会は今後やらないだろうという豪華なワイン会を開きます。
メインとしてはハーラン・エステートが作る、グラン・クリュのカベルネ・ソーヴィニヨン「Bond」の2004年のワインを4種類出します。
場所はマンダリンオリエンタル東京のフレンチ・レストラン「シグネチャー」。食べログの東京のフレンチ・レストラン百名店に選ばれている名店です。ソムリエは今年ナパヴァレー・ヴィントナーズ・ジャパンのベスト・ソムリエ・アンバサダーに選ばれた山本麻衣花さんにお願いしています。
日時は2026年2月7日(土)19時から
価格は77,000円の予定です。9人限定です。
Bond以外のワインは未確定ですが、現在予定しているのは
Domaine Carneros Le Reve
Quintessa Illumination
Paul Lato East of Eden Chardonnay 2021
Calera Jensen 1996
など。1人1本の予定です。
これで最後というのは、このBondは数年前に2セット買って1セットは2年ほど前にピーター・ルーガーのワイン会で飲んでおり、これが残った1セットだからです。Bondの今の価格は1本15万ですから、同じように開催したら一人当たり10万を優に超えてしまいます。ピーター・ルーガーのときはアカデミー・デュ・ヴァンで募集したのですが、デュ・ヴァンを通すとどうしても高くなるので、今回は個人として開催することにしました。
あと、もし席が埋まらなかった場合はキャンセルさせていただく可能性があります。ご了承ください。
申し込みは、各種SNSのDMか、メールでお願いします。
Facebook
Andy Matsubara(アンディ松原)@ナパヴァレー・ベスト・エデュケーター2023(@andyma)さん / X
Instagram
メインとしてはハーラン・エステートが作る、グラン・クリュのカベルネ・ソーヴィニヨン「Bond」の2004年のワインを4種類出します。
場所はマンダリンオリエンタル東京のフレンチ・レストラン「シグネチャー」。食べログの東京のフレンチ・レストラン百名店に選ばれている名店です。ソムリエは今年ナパヴァレー・ヴィントナーズ・ジャパンのベスト・ソムリエ・アンバサダーに選ばれた山本麻衣花さんにお願いしています。
日時は2026年2月7日(土)19時から
価格は77,000円の予定です。9人限定です。
Bond以外のワインは未確定ですが、現在予定しているのは
Domaine Carneros Le Reve
Quintessa Illumination
Paul Lato East of Eden Chardonnay 2021
Calera Jensen 1996
など。1人1本の予定です。
これで最後というのは、このBondは数年前に2セット買って1セットは2年ほど前にピーター・ルーガーのワイン会で飲んでおり、これが残った1セットだからです。Bondの今の価格は1本15万ですから、同じように開催したら一人当たり10万を優に超えてしまいます。ピーター・ルーガーのときはアカデミー・デュ・ヴァンで募集したのですが、デュ・ヴァンを通すとどうしても高くなるので、今回は個人として開催することにしました。
あと、もし席が埋まらなかった場合はキャンセルさせていただく可能性があります。ご了承ください。
申し込みは、各種SNSのDMか、メールでお願いします。
Andy Matsubara(アンディ松原)@ナパヴァレー・ベスト・エデュケーター2023(@andyma)さん / X

ナパヴァレー・ヴィントナーズが2025年の収穫について、業界のメンバーを集めて座談会を開きました。2025年のナパの生育シーズンは、全体的に涼しく、雨が多く、猛暑の日がほとんどないものでした。ワインは長期熟成が可能で、バランスが良く、エレガントでクラシックなスタイルになりそうです。
「フェノールの成熟が糖度の蓄積よりも早かったため、この生育期は本当に楽しかったです。アルコール度数を抑えながらも非常にバランスの取れたワインが出来上がるでしょう」と、コンティニュアム(Continuum)の栽培ディレクターであるアシュトン・ロイトナー氏は述べています。
「けた外れに色が濃くなりました。これは品質の優れた指標です」と、ボーリュー・ヴィンヤード(Beaulieu、BV)のジェネラルマネージャー兼シニアワインメーカーであるネイト・ワイス氏は説明します。
フィリップ・メルカの会社として様残なワイナリーのコンサルタントを請け負うアトリエ・メルカ(Atelier Melka)のパートナー兼ワイン醸造ディレクターであるマーヤン・コシツキー氏は「発酵初期に非常に高い色素抽出を確認しました。全体的にタンニンがやや柔らかくなったことで、浸軟期間を延長し、ワインに美しい重厚感とテクスチャーを与えることができました」と付け加えます。ロイトナー氏は、種子のタンニンの含有量が少ないことで「苦味を生じさせることなく、果皮との接触期間を延長できた」と付け加えました。
温暖な気候と安定した成熟ペースも、土地の個性を際立たせました。「涼しいヴィンテージでは、栽培地域間の違いがより顕著になります。今年はAVA間の差異がより顕著に表れる年の一つです」と、ホール(Hall)のワインメイキング担当副社長、ミーガン・ガンダーソン氏は述べています。
ガンダーソン氏は、ナパ・ヴァレーは品質の高さで知られていると述べ、このヴィンテージへの熱意を語りました。「どこで収穫し、どこで収穫しなかったかは、すべて品質次第です。業界は常に変化しており、私たちはそれに適応しながら在庫を適正に保ち、毎年最高品質のワインを生産することに注力しています」
忍耐が報われ、力よりもバランスと繊細さを重視した収穫となりました。
「カリフォルニア・クリスマス」(原題:A California Christmas)という映画がNetflixで配信されています。ソノマの牧場を舞台にしているとのことです。映画を観る限りではおそらくカーネロスなのかなあと思います。

カリフォルニア・クリスマス - Netflix
ネタバレになってしまうので、詳しくは紹介しませんが、ワインは結構重要な役割を果たします。ただ、突っ込みどころもいろいろあるのはご愛敬。2時間足らずの映画ですし、気楽に楽しく(子供と見るのは一部ちょっとというシーンもあります)見られるので、ワイン片手に観るのもいいでしょう。
ただ、配信は12月13日で終了ということなので、クリスマスにはもう観られません。お早めにどうぞ。
ちなみに、続編もあるようで、そちらはまだ配信終了にはなりません。

カリフォルニア・クリスマス - Netflix
ネタバレになってしまうので、詳しくは紹介しませんが、ワインは結構重要な役割を果たします。ただ、突っ込みどころもいろいろあるのはご愛敬。2時間足らずの映画ですし、気楽に楽しく(子供と見るのは一部ちょっとというシーンもあります)見られるので、ワイン片手に観るのもいいでしょう。
ただ、配信は12月13日で終了ということなので、クリスマスにはもう観られません。お早めにどうぞ。
ちなみに、続編もあるようで、そちらはまだ配信終了にはなりません。
今年、都光が輸入を始めたサンタ・バーバラのワイナリー「プレスキール(Presquil)」。セールスのディレクターであるトニー・チャ氏が来日してソムリエ協会でセミナーを行い、私は通訳として参加させていただきました。ワインの試飲はちゃんとできておりませんが、ワイナリーの紹介をしておきたいと思います。

プレスキールはルイジアナ州出身のマーフィー家が2007年にサンタ・バーバラのサンタ・マリア・ヴァレーに設立したワイナリー。小高い斜面に、シャルドネとピノ・ノワールなど7種類のブドウを植えています。栽培ではSIPというサスティナビリティ―の認証を得ています。また、直近ではサンタ・リタ・ヒルズの銘醸畑サンフォード&ベネディクトの隣に土地を取得。シャルドネとピノ・ノワールを植えています。このほか、アボカドを育てていたり、ワイナリーにホテルを作ったりなど、手広く活動しています。
ワインメーカーは南アフリカ出身のディエター・クロンジェ。2015年からはブルゴーニュのドメーヌ・デュジャックのジェレミー・セイスがコンサルタントとして参画しています。

現在のワインのラインアップは10種類強。国内にはこのうち8種類が輸入されています。
・プレスキール サンタ・バーバラ・カウンティ ピノ・ノワール 2023 希望小売価格5,000円+税
・プレスキール サンタ・バーバラ・カウンティ シャルドネ 2023 希望小売価格4,700円+税
・プレスキール・ヴィンヤード ガメイ 2024 希望小売価格6,500円+税
・プレスキール・ヴィンヤード アリゴテ 2023 希望小売価格7,000円+税
・プレスキール・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2023 希望小売価格11,000円+税
・プレスキール・ヴィンヤード シャルドネ 2023 希望小売価格8,800円+税
・サンフォード&ベネディクト・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2021 希望小売価格13,500円+税
・サンフォード&ベネディクト・ヴィンヤード シャルドネ 2021 希望小売価格10,000円+税
下がサンタ・バーバラ・カウンティ・シリーズで、ここのエントリー・ライン。上が単一畑シリーズでフラッグシップになります。
サンタ・バーバラ・カウンティ・シリーズはシャルドネとピノ・ノワール、ソーヴィニョン・ブラン、シラーでフレッシュで日常的に飲むワインを目指しています(ソーヴィニョン・ブラン、シラーは未輸入)。また、ワインには自社畑のブドウも結構使われています。エントリー版といっても品質はかなり高いです。
単一畑シリーズはテロワールを表現するワイン。自社畑のほか、サンタ・リタ・ヒルズのサンフォード&ベネディクトのシャルドネとピノ・ノワールもあります。同じシャルドネ、ピノ・ノワールでも自社畑のものは軽やかさがありエレガントなのに対し、サンフォード&ベネディクトはがっしりとストラクチャーのあるワインになっており、色合いもかなり異なります。醸造はほぼ同じであり、まさにテロワールが反映されたワインです。
シャルドネとピノ・ノワール以外では自社畑のアリゴテとガメイも輸入されています。中でも受講者の関心が高かったのがガメイでした。当初は軽いスタイルのワインを目指してカルボニック・マセレーションも使っていましたが、かなり品質の高いガメイができるため、クリュ・ボージョレタイプのワインに変えたとのことでした。ラベルが軽いタッチなのは当初のコンセプトの名残だとか
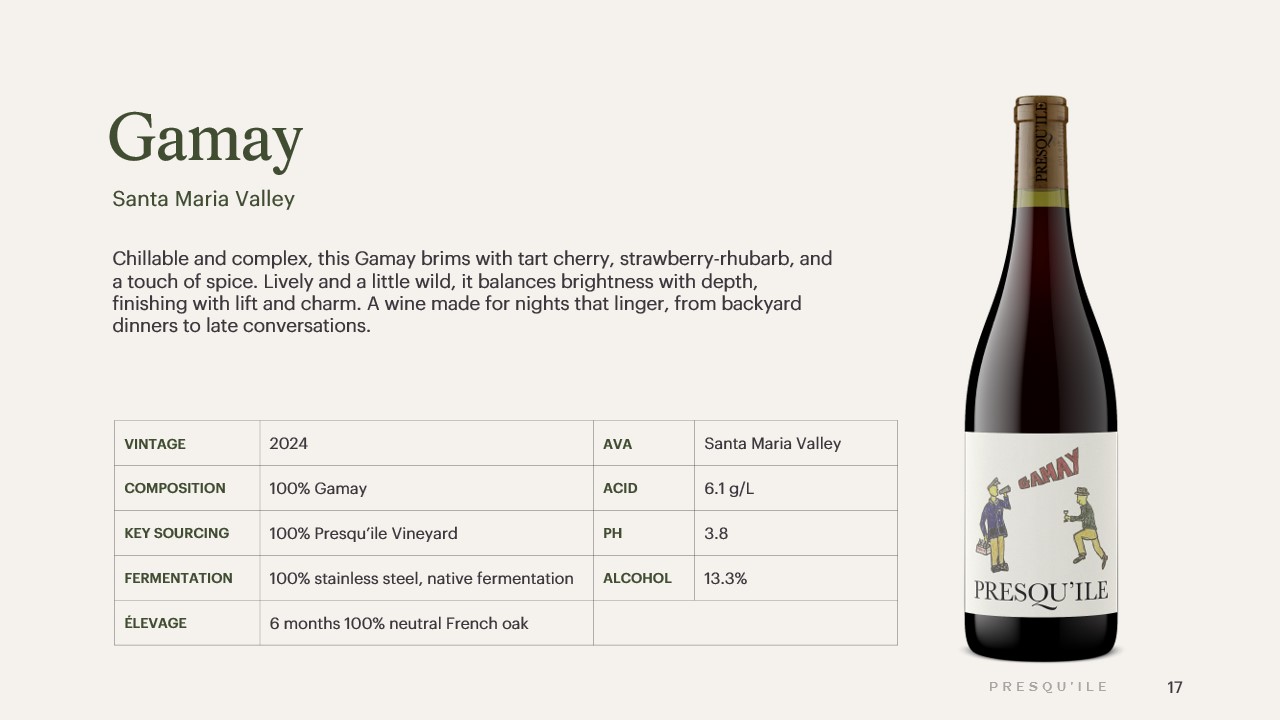
プレスキールのワイン、現在は都光のリカーショップである「リカーマウンテン」や、楽天の「セラー専科」「CAVE de L NAOTAKA」などで販売されています。今後は他のショップにも広げていく予定です。
まずは、リーズナブルな価格のサンタ・バーバラ・カウンティものから試していただきたいと思います。
なお、通訳のできについては、ブルゴーニュの生産者の名前がいくつか聞き取れないところがあり、反省しております(きっと聞いている人たちの方が分かっていたでしょう)。質疑応答が活発にあり、それはすごく良かったと思います。


プレスキールはルイジアナ州出身のマーフィー家が2007年にサンタ・バーバラのサンタ・マリア・ヴァレーに設立したワイナリー。小高い斜面に、シャルドネとピノ・ノワールなど7種類のブドウを植えています。栽培ではSIPというサスティナビリティ―の認証を得ています。また、直近ではサンタ・リタ・ヒルズの銘醸畑サンフォード&ベネディクトの隣に土地を取得。シャルドネとピノ・ノワールを植えています。このほか、アボカドを育てていたり、ワイナリーにホテルを作ったりなど、手広く活動しています。
ワインメーカーは南アフリカ出身のディエター・クロンジェ。2015年からはブルゴーニュのドメーヌ・デュジャックのジェレミー・セイスがコンサルタントとして参画しています。

現在のワインのラインアップは10種類強。国内にはこのうち8種類が輸入されています。
・プレスキール サンタ・バーバラ・カウンティ ピノ・ノワール 2023 希望小売価格5,000円+税
・プレスキール サンタ・バーバラ・カウンティ シャルドネ 2023 希望小売価格4,700円+税
・プレスキール・ヴィンヤード ガメイ 2024 希望小売価格6,500円+税
・プレスキール・ヴィンヤード アリゴテ 2023 希望小売価格7,000円+税
・プレスキール・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2023 希望小売価格11,000円+税
・プレスキール・ヴィンヤード シャルドネ 2023 希望小売価格8,800円+税
・サンフォード&ベネディクト・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2021 希望小売価格13,500円+税
・サンフォード&ベネディクト・ヴィンヤード シャルドネ 2021 希望小売価格10,000円+税
下がサンタ・バーバラ・カウンティ・シリーズで、ここのエントリー・ライン。上が単一畑シリーズでフラッグシップになります。
サンタ・バーバラ・カウンティ・シリーズはシャルドネとピノ・ノワール、ソーヴィニョン・ブラン、シラーでフレッシュで日常的に飲むワインを目指しています(ソーヴィニョン・ブラン、シラーは未輸入)。また、ワインには自社畑のブドウも結構使われています。エントリー版といっても品質はかなり高いです。
単一畑シリーズはテロワールを表現するワイン。自社畑のほか、サンタ・リタ・ヒルズのサンフォード&ベネディクトのシャルドネとピノ・ノワールもあります。同じシャルドネ、ピノ・ノワールでも自社畑のものは軽やかさがありエレガントなのに対し、サンフォード&ベネディクトはがっしりとストラクチャーのあるワインになっており、色合いもかなり異なります。醸造はほぼ同じであり、まさにテロワールが反映されたワインです。
シャルドネとピノ・ノワール以外では自社畑のアリゴテとガメイも輸入されています。中でも受講者の関心が高かったのがガメイでした。当初は軽いスタイルのワインを目指してカルボニック・マセレーションも使っていましたが、かなり品質の高いガメイができるため、クリュ・ボージョレタイプのワインに変えたとのことでした。ラベルが軽いタッチなのは当初のコンセプトの名残だとか
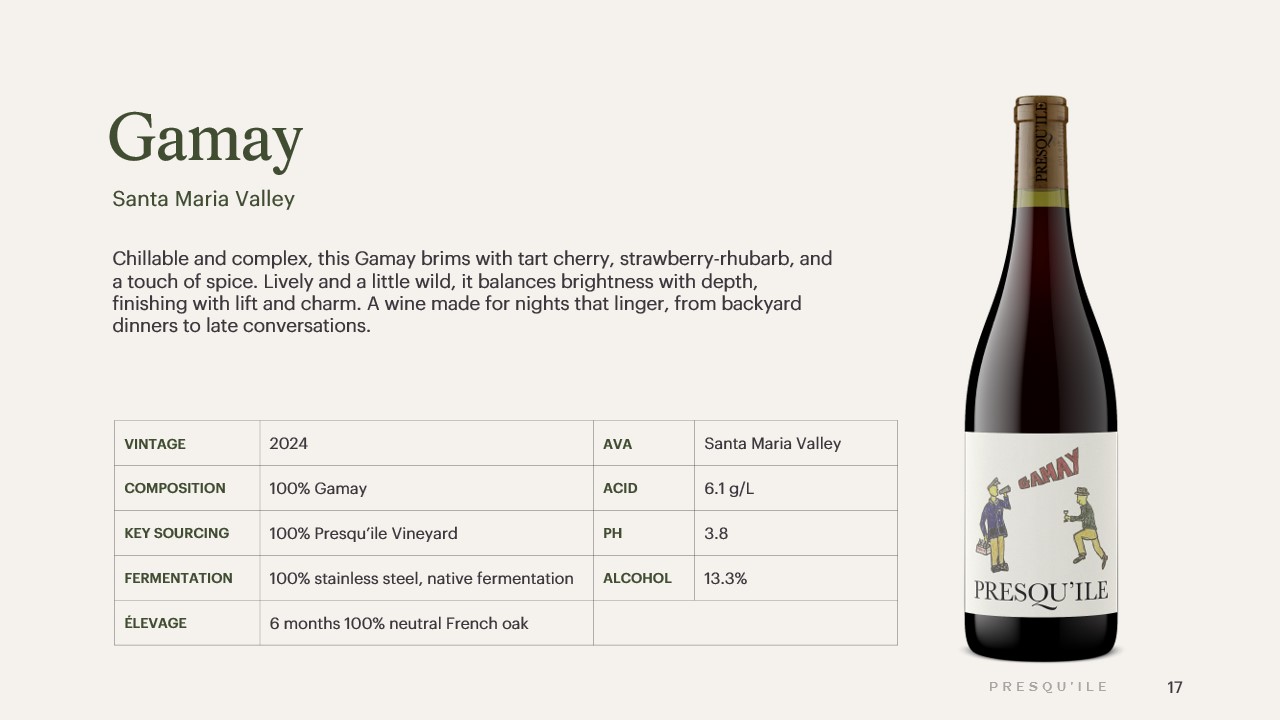
プレスキールのワイン、現在は都光のリカーショップである「リカーマウンテン」や、楽天の「セラー専科」「CAVE de L NAOTAKA」などで販売されています。今後は他のショップにも広げていく予定です。
まずは、リーズナブルな価格のサンタ・バーバラ・カウンティものから試していただきたいと思います。
なお、通訳のできについては、ブルゴーニュの生産者の名前がいくつか聞き取れないところがあり、反省しております(きっと聞いている人たちの方が分かっていたでしょう)。質疑応答が活発にあり、それはすごく良かったと思います。
ワインスペクテーターの年間トップ10、2位までが発表されました。カリフォルニアは8位にウェイフェアラーのピノ・ノワール、4位にウィリアムズ・セリエムのEastside Road Neighbors、3位にリッジのリットン・スプリングスと入りましたが、セリエムは日本輸入なし、ウェイフェアラーとリッジは国内の現行ヴィンテージではないというところで、ちょっと残念。
ようやく2位でオーベールのUV-SLヴィンヤード、シャルドネ2023が入りました。こちらは国内在庫あり。もちろんオーベールですから、値段は安くありませんが。
ようやく2位でオーベールのUV-SLヴィンヤード、シャルドネ2023が入りました。こちらは国内在庫あり。もちろんオーベールですから、値段は安くありませんが。
ジョセフ・フェルプスのデイビッド・ピアソン社長が来日し、食事を一緒にする機会をいただきました。
ピアソン氏とは昨年春にセミナーでお会いして以来です。
知られざる先進ワイナリー、ジョセフ・フェルプスの魅力を探る
ジョセフ・フェルプスは2022年にLVMHの傘下に入り、オーパス・ワンのCEOを長年務めてきたピアソン氏を社長に迎え入れました。ジョセフ・フェルプスのインシグニアはワインの品質ではナパのトップクラスを長年続けており、オーパス・ワンにも劣らない実績を上げていましたが、マネジメントやブランド構築という点では必ずしもうまく行っていませんでした。そういったことからオーパス・ワンのブランドを築き上げたピアソン氏を選んだようです。
今回は、ざっくばらんにいろいろな話をしながらランチを楽しみました。話の中で興味深かったのは「ラ・プラス・ド・ボルドー」経由での輸出をやめたということ。「ラ・プラス・ド・ボルドー」利用には功罪あるので、ブランド構築を行っている今のタイミングではそれをやめておくというのは、理解できます。
食事中のワインはインシグニアで2022、2021、2019の直近3ヴィンテージ(2020は山火事の影響でなし)に、2016年というラインアップでした。なお、ジョセフ・フェルプスはソノマ・コーストでピノ・ノワールやシャルドネも作っていますが、今回は在庫がなかったそうです。
以下、簡単にワインの感想を記します。
2022 カシスにブルーベリー、ベーキング・スパイス。香りと余韻が素晴らしい。果実の甘やかさに豊かな酸。熱波の年で苦労したワイナリーが多い中、これだけきれいな酸があるのはさすがです。ジョセフ・フェルプスはナパの各地に自社畑を持っており、この年はやや冷涼な畑のブドウの比率を上げているようです。
2021 ブルーベリーにブラックベリー、わずかにレッド・チェリー。バランスよく、パワフルで凝縮感を感じるワイン。
2019 甘やかな果実味に、グラファイトなどの鉱物的な味わい。コーンスープのようなまろやかさ。2021年と比べると、いい意味で軽さを感じるワイン。
2016 第一印象はパーフェクト。すべてが整っているワイン。素晴らしい。
敢えて点数を付けるなら、2022と21は96、19は98、16は100。
ピアソン氏の指揮でこれからジョセフ・フェルプスがどう変わっていくか、期待したいと思います(あまりラグジュアリーになってしまうのは庶民的には困りますが)。








ピアソン氏とは昨年春にセミナーでお会いして以来です。
知られざる先進ワイナリー、ジョセフ・フェルプスの魅力を探る
ジョセフ・フェルプスは2022年にLVMHの傘下に入り、オーパス・ワンのCEOを長年務めてきたピアソン氏を社長に迎え入れました。ジョセフ・フェルプスのインシグニアはワインの品質ではナパのトップクラスを長年続けており、オーパス・ワンにも劣らない実績を上げていましたが、マネジメントやブランド構築という点では必ずしもうまく行っていませんでした。そういったことからオーパス・ワンのブランドを築き上げたピアソン氏を選んだようです。
今回は、ざっくばらんにいろいろな話をしながらランチを楽しみました。話の中で興味深かったのは「ラ・プラス・ド・ボルドー」経由での輸出をやめたということ。「ラ・プラス・ド・ボルドー」利用には功罪あるので、ブランド構築を行っている今のタイミングではそれをやめておくというのは、理解できます。
食事中のワインはインシグニアで2022、2021、2019の直近3ヴィンテージ(2020は山火事の影響でなし)に、2016年というラインアップでした。なお、ジョセフ・フェルプスはソノマ・コーストでピノ・ノワールやシャルドネも作っていますが、今回は在庫がなかったそうです。
以下、簡単にワインの感想を記します。
2022 カシスにブルーベリー、ベーキング・スパイス。香りと余韻が素晴らしい。果実の甘やかさに豊かな酸。熱波の年で苦労したワイナリーが多い中、これだけきれいな酸があるのはさすがです。ジョセフ・フェルプスはナパの各地に自社畑を持っており、この年はやや冷涼な畑のブドウの比率を上げているようです。
2021 ブルーベリーにブラックベリー、わずかにレッド・チェリー。バランスよく、パワフルで凝縮感を感じるワイン。
2019 甘やかな果実味に、グラファイトなどの鉱物的な味わい。コーンスープのようなまろやかさ。2021年と比べると、いい意味で軽さを感じるワイン。
2016 第一印象はパーフェクト。すべてが整っているワイン。素晴らしい。
敢えて点数を付けるなら、2022と21は96、19は98、16は100。
ピアソン氏の指揮でこれからジョセフ・フェルプスがどう変わっていくか、期待したいと思います(あまりラグジュアリーになってしまうのは庶民的には困りますが)。
シュレーダーのセミナー後は、コンステレーション傘下のナパの高級カベルネとして、マウント・ヴィーダーと、ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーの試飲がありました。

マウント・ヴィーダー2021
マウント・ヴィーダーは、その名の通りナパの西側の山であるマウント・ヴィーダーにあるワイナリーです。標高300~480mのところに畑があります。昼の気温はヴァレーフロアより低く、朝晩は高くなるマイルドな気候になります。斜面の畑は収量が少なく、作業も大変なので山のワインは高くなりがちですが、ここは今でも13000円と比較的リーズナブルな価格です。
マウント・ヴィーダーの特徴である杉の風味やハーヴ、凝縮感が強く、タンニンも強いですがバランスのいいワインです。
この後は、ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーのワインです。コンステレーション・ブランズが、ト・カロンのブランドを最大限に活用すべく、2017年に立ち上げたブランドで、当初のワインメーカーはアンディ・エリクソン。2023年からはトニー・ビアージになっています。造っているワインは三つあり、一番スタンダードなものが「ハイエスト・ビューティ」。この名前は「ト・カロン」というギリシャ語を英語にしたものです。二つ目は「エリザズ・キュヴェ」。カベルネ・フランとカベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドです。エリザというのは、ト・カロンのあるオークヴィルの隣のヨントヴィルの名前の基となったジョージ・ヨントの妻の名前で、ト・カロンのカベルネ・フランのブロックがある辺りを一時期所有していたとのこと。三つ目は「H.W.C.」でト・カロンの畑を作ったハミルトン・ウォーカー・クラブの頭文字を取ったものです。100%カベルネ・ソーヴィニヨンで単一ブロック、単一クローンというワイン。
今回はハイエスト・ビューティの2021、エリザズ・キュヴェの2021、そしてエリザズ・キュヴェの2019年でした。

ハイエスト・ビューティー2021
シュレーダーと比べるとエレガントな造りで、赤い果実味と少しブルーベリーの風味。タニックでパワフル。

エリザズ・キュヴェ2021
赤い果実味が優性で、シルキーなテクスチャー

エリザズ・キュヴェ2019
2021と比べると青い果実味も強く感じます。スムーズなテクスチャー
マウント・ヴィーダー2021
マウント・ヴィーダーは、その名の通りナパの西側の山であるマウント・ヴィーダーにあるワイナリーです。標高300~480mのところに畑があります。昼の気温はヴァレーフロアより低く、朝晩は高くなるマイルドな気候になります。斜面の畑は収量が少なく、作業も大変なので山のワインは高くなりがちですが、ここは今でも13000円と比較的リーズナブルな価格です。
マウント・ヴィーダーの特徴である杉の風味やハーヴ、凝縮感が強く、タンニンも強いですがバランスのいいワインです。
この後は、ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーのワインです。コンステレーション・ブランズが、ト・カロンのブランドを最大限に活用すべく、2017年に立ち上げたブランドで、当初のワインメーカーはアンディ・エリクソン。2023年からはトニー・ビアージになっています。造っているワインは三つあり、一番スタンダードなものが「ハイエスト・ビューティ」。この名前は「ト・カロン」というギリシャ語を英語にしたものです。二つ目は「エリザズ・キュヴェ」。カベルネ・フランとカベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドです。エリザというのは、ト・カロンのあるオークヴィルの隣のヨントヴィルの名前の基となったジョージ・ヨントの妻の名前で、ト・カロンのカベルネ・フランのブロックがある辺りを一時期所有していたとのこと。三つ目は「H.W.C.」でト・カロンの畑を作ったハミルトン・ウォーカー・クラブの頭文字を取ったものです。100%カベルネ・ソーヴィニヨンで単一ブロック、単一クローンというワイン。
今回はハイエスト・ビューティの2021、エリザズ・キュヴェの2021、そしてエリザズ・キュヴェの2019年でした。
ハイエスト・ビューティー2021
シュレーダーと比べるとエレガントな造りで、赤い果実味と少しブルーベリーの風味。タニックでパワフル。
エリザズ・キュヴェ2021
赤い果実味が優性で、シルキーなテクスチャー
エリザズ・キュヴェ2019
2021と比べると青い果実味も強く感じます。スムーズなテクスチャー
ナパのシュレーダーの2023年ヴィンテージお披露目のマスタークラスに参加してきました。説明はジェイソン・スミスMS。奥さんは日本人で娘さんは日本でアメリカンスクールに通っていたという日本通の方でもあります。実は今回、写真を撮り忘れてしまったので、一昨年の写真を上げておきます。

今回のマスタークラスでの試飲ワインは以下のもの。これ以外に、フリー試飲でいくつか追加で飲んでいます。これについては後述します。

ヴィンテージの差異があまりないと思われているカリフォルニアですが、2020年以降はそういった「常識」が通用しないほどふり幅の大きいヴィンテージが続いています。
2020年は山火事でナパの全域に煙が広がり、多くのワイナリーが赤ワインの醸造を諦めた年です。シュレーダーもその一つでした。2021年は干ばつで非常に凝縮したブドウができた年。とても濃いワインになりました。2022年は9月に熱波がやってきた年。46℃ほどの猛烈な暑さが5日間続きました。ここまで暑くなるとブドウも身の危険を感じて成長を止めて(シャットダウン)しまいます。シャットダウンで色やストラクチャーが抜けてしまうため、生産者にとっては苦労したヴィンテージです。選果を丹念にした結果、収穫量は例年より4割も少なくなってしまったそうです。一方、2023年は非常に涼しい年。例年の3週間遅れというくらい生育が遅れましたが、幸いなことに10月に入っても、雨はほとんど降らず、コンディションを落とさないまま、収穫できたといいます。
シュレーダーのワインは、ナパのオークヴィルのト・カロン・ヴィンヤードのカベルネソーヴィニヨンを使っています。同じコンステレーションブランズ傘下にあるロバート・モンダヴィが入手した銘醸畑中の銘醸畑です。
ト・カロンの名が付く畑はコンステレーションブランズのほか、ベクストファー家が管理するベクストファー・ト・カロンがあり、以前はシュレーダーはそちらのブドウを使っていましたが、2022年以降はモンダヴィの方のト・カロンだけを使っています。また、オーパス・ワンはト・カロンの一部の区画を専用に使っています。
シュレーダーの最初のヴィンテージは1998年ですが、注目を集めるようになったのは2000年に上記のベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードのブドウを入手してからです。また、同年からワインメーカーがトーマス・リヴァース・ブラウンになっています。今やコンサルタント・ワインメーカーとして引く手あまたのトーマスですが、最初にワインメーカーになったのがこのシュレーダー。それまで数年はジンファンデルで有名なターリーで、セラー・ラットと呼ばれるような下働きだったのです。シュレーダー創設者のフレッド・シュレーダーはナパのカフェで彼と知り合い、ワインメーカーに抜擢したのですが、それは慧眼と言わざるを得ません。
2001年には、ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードのカベルネ・ソーヴィニヨンをさらにカベルネのクローン別にCCS、RBSと違うワインに仕込むことを始めました。そこからうなぎ上りに評価が上がっていったのです。これまでに評論家から得た100点はなんと41回。そのほかに、ダブル・ダイヤモンドでのワイン・スペクテーター「ワインオブザイヤー」などの栄冠があります。
さて、最初の試飲はダブル・ダイヤモンドのカベルネ・ソーヴィニヨン2023です。ダブル・ダイヤモンドはシュレーダーのセカンドの位置づけで、ト・カロン以外に「オークヴィル・ステーション」という畑のブドウを使っています。また、ト・カロンの中でも若木のブドウを使っています。シュレーダーのワインが希望小売価格9万円もするのに対して、こちらは1万4800円と6分の1以下の価格です。
醸造では52%新樽を使っています。残りの樽は前年にシュレーダーで使ったものです。開けたてから美味しいワインに仕上げているといいます。一方、シュレーダーは100%新樽。ダナジューとタランソーという高級樽メーカーのものを使っていますが、なかでもダナジューは自社で輸入しているそうです。
以前のダブル・ダイヤモンドはちょっと甘やかさが前面に出る感じがありましたが、2023年は涼しい年だったせいか酸が高くこれまでよりもバランスがいいワインに仕上がっています。タンニンは柔らかく、スムーズな飲み心地。プラムにレッド・チェリー、トーストや焼き栗の風味。コスパはかなり高いと思います。
2本目からはシュレーダーのワイン。カベルネ・ソーヴィニヨン ト・カロン・ヴィンヤード 2023です。通称「シュレーダー シュレーダー」。スタンダード的な位置付けですが、他のワインと価格は同じです(90000円)。シュレーダーの中では一番軽い味わいで赤果実の風味が出ます。
ダブル・ダイヤモンドとの一番の違いは香りの強さで、グラスに顔を近づけなくても果実の香りが漂ってきます。レッド・チェリーにブルーベリー、プラムなどの熟した果実、芳醇で少し甘やか、ダブル・ダイヤモンドよりタンニンの強さはしっかりと感じますが柔らかさもあり、今でも美味しいワインです。

3本目と4本目は、ト・カロンの中でも山裾に近く、水はけがよくて高品質のブドウが採れるというモネステリ―・ブロックの2023年と2022年です。名前の由来は隣に修道院があることから。
シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン モナステリー・ブロック 2023
シュレーダー シュレーダーが香りから柔らかさを感じるのに対し、こちらはやや固さを感じる香り。青い果実。タンニンかなり強く、飲み頃までは数年かかりそう。開いている感じではないですがそれでも爆発的な果実味があり、余韻も長い。非常にポテンシャルの高いワイン。
シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン モナステリー・ブロック 2022
2023年と比べると果実味は少し低い。ストラクチャー強く、かなりタニックでとがっています。こちらも柔らかくなるのにまだ数年かかりそうです。非常に余韻も長く超熟型であることをうかがわせます。クオリティは23年の方が上ですが、長期間の熟成にはこちらが向いているかもしれません。
5本目と6本目は「ヘリテージ・クローン」の2023年と2022年です。ヘリテージ・クローンはブドウの房が握りこぶしの半分くらいしかない、レアなクローンを使ったワインです。あまりにもブドウが小さいので1アーカーあたり1トン程度しか収穫できません(通常2トンを下回ると極めて少ないと言われます)。
シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン ヘリテージ・クローン 2023
モナステリー・ブロックの青果実に対して、こちらは赤果実の香りが強く、素晴らしい酸がありしなやかなテクスチャーがあります。タンニン強くパワフルで、もしかしたら飲み頃はモナステリー・ブロックよりも先かもしれません。
シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン ヘリテージ・クローン 2022
こちらも赤果実の香りが強く、パワフルなワイン。2023年と比べると、こちらの方が飲み頃は早く来そうで、今でも十分美味しく飲めます。ヘリテージ・クローンとモナステリー・ブロックはかなり個性が違うので好みが分かれそうですが、個人的にはヘリテージ・クローンを高く評価します。
最後のワインは、2021年のオールド・スパーキー。オールド・スパーキーはシュレーダーのトップ・キュベで素晴らしい樽だけを集めて作るワイン。マグナムボトルだけというワインです。価格は20万円。2021年はベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードのブドウを使った最後のヴィンテージです。
シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン オールド・スパーキー 2021
とにかく濃密な果実味に圧倒されます。バランスよく、むちゃくちゃ美味しい。30年は熟成するだろうとのこと。
なお、2023年はシュレーダー25周年でオールド・スパーキーのスペシャル・ボトルが作られます。全世界で250本。専用のケースに入れられ、価格は40万円超とのこと。



なお、コンステレーションブランズ傘下のマウント・ヴィーダーやト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーの試飲も別途ありましたが、そちらは別記事で。
今回のマスタークラスでの試飲ワインは以下のもの。これ以外に、フリー試飲でいくつか追加で飲んでいます。これについては後述します。
ヴィンテージの差異があまりないと思われているカリフォルニアですが、2020年以降はそういった「常識」が通用しないほどふり幅の大きいヴィンテージが続いています。
2020年は山火事でナパの全域に煙が広がり、多くのワイナリーが赤ワインの醸造を諦めた年です。シュレーダーもその一つでした。2021年は干ばつで非常に凝縮したブドウができた年。とても濃いワインになりました。2022年は9月に熱波がやってきた年。46℃ほどの猛烈な暑さが5日間続きました。ここまで暑くなるとブドウも身の危険を感じて成長を止めて(シャットダウン)しまいます。シャットダウンで色やストラクチャーが抜けてしまうため、生産者にとっては苦労したヴィンテージです。選果を丹念にした結果、収穫量は例年より4割も少なくなってしまったそうです。一方、2023年は非常に涼しい年。例年の3週間遅れというくらい生育が遅れましたが、幸いなことに10月に入っても、雨はほとんど降らず、コンディションを落とさないまま、収穫できたといいます。
シュレーダーのワインは、ナパのオークヴィルのト・カロン・ヴィンヤードのカベルネソーヴィニヨンを使っています。同じコンステレーションブランズ傘下にあるロバート・モンダヴィが入手した銘醸畑中の銘醸畑です。
ト・カロンの名が付く畑はコンステレーションブランズのほか、ベクストファー家が管理するベクストファー・ト・カロンがあり、以前はシュレーダーはそちらのブドウを使っていましたが、2022年以降はモンダヴィの方のト・カロンだけを使っています。また、オーパス・ワンはト・カロンの一部の区画を専用に使っています。
シュレーダーの最初のヴィンテージは1998年ですが、注目を集めるようになったのは2000年に上記のベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードのブドウを入手してからです。また、同年からワインメーカーがトーマス・リヴァース・ブラウンになっています。今やコンサルタント・ワインメーカーとして引く手あまたのトーマスですが、最初にワインメーカーになったのがこのシュレーダー。それまで数年はジンファンデルで有名なターリーで、セラー・ラットと呼ばれるような下働きだったのです。シュレーダー創設者のフレッド・シュレーダーはナパのカフェで彼と知り合い、ワインメーカーに抜擢したのですが、それは慧眼と言わざるを得ません。
2001年には、ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードのカベルネ・ソーヴィニヨンをさらにカベルネのクローン別にCCS、RBSと違うワインに仕込むことを始めました。そこからうなぎ上りに評価が上がっていったのです。これまでに評論家から得た100点はなんと41回。そのほかに、ダブル・ダイヤモンドでのワイン・スペクテーター「ワインオブザイヤー」などの栄冠があります。
さて、最初の試飲はダブル・ダイヤモンドのカベルネ・ソーヴィニヨン2023です。ダブル・ダイヤモンドはシュレーダーのセカンドの位置づけで、ト・カロン以外に「オークヴィル・ステーション」という畑のブドウを使っています。また、ト・カロンの中でも若木のブドウを使っています。シュレーダーのワインが希望小売価格9万円もするのに対して、こちらは1万4800円と6分の1以下の価格です。
醸造では52%新樽を使っています。残りの樽は前年にシュレーダーで使ったものです。開けたてから美味しいワインに仕上げているといいます。一方、シュレーダーは100%新樽。ダナジューとタランソーという高級樽メーカーのものを使っていますが、なかでもダナジューは自社で輸入しているそうです。
以前のダブル・ダイヤモンドはちょっと甘やかさが前面に出る感じがありましたが、2023年は涼しい年だったせいか酸が高くこれまでよりもバランスがいいワインに仕上がっています。タンニンは柔らかく、スムーズな飲み心地。プラムにレッド・チェリー、トーストや焼き栗の風味。コスパはかなり高いと思います。
2本目からはシュレーダーのワイン。カベルネ・ソーヴィニヨン ト・カロン・ヴィンヤード 2023です。通称「シュレーダー シュレーダー」。スタンダード的な位置付けですが、他のワインと価格は同じです(90000円)。シュレーダーの中では一番軽い味わいで赤果実の風味が出ます。
ダブル・ダイヤモンドとの一番の違いは香りの強さで、グラスに顔を近づけなくても果実の香りが漂ってきます。レッド・チェリーにブルーベリー、プラムなどの熟した果実、芳醇で少し甘やか、ダブル・ダイヤモンドよりタンニンの強さはしっかりと感じますが柔らかさもあり、今でも美味しいワインです。
3本目と4本目は、ト・カロンの中でも山裾に近く、水はけがよくて高品質のブドウが採れるというモネステリ―・ブロックの2023年と2022年です。名前の由来は隣に修道院があることから。
シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン モナステリー・ブロック 2023
シュレーダー シュレーダーが香りから柔らかさを感じるのに対し、こちらはやや固さを感じる香り。青い果実。タンニンかなり強く、飲み頃までは数年かかりそう。開いている感じではないですがそれでも爆発的な果実味があり、余韻も長い。非常にポテンシャルの高いワイン。
シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン モナステリー・ブロック 2022
2023年と比べると果実味は少し低い。ストラクチャー強く、かなりタニックでとがっています。こちらも柔らかくなるのにまだ数年かかりそうです。非常に余韻も長く超熟型であることをうかがわせます。クオリティは23年の方が上ですが、長期間の熟成にはこちらが向いているかもしれません。
5本目と6本目は「ヘリテージ・クローン」の2023年と2022年です。ヘリテージ・クローンはブドウの房が握りこぶしの半分くらいしかない、レアなクローンを使ったワインです。あまりにもブドウが小さいので1アーカーあたり1トン程度しか収穫できません(通常2トンを下回ると極めて少ないと言われます)。
シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン ヘリテージ・クローン 2023
モナステリー・ブロックの青果実に対して、こちらは赤果実の香りが強く、素晴らしい酸がありしなやかなテクスチャーがあります。タンニン強くパワフルで、もしかしたら飲み頃はモナステリー・ブロックよりも先かもしれません。
シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン ヘリテージ・クローン 2022
こちらも赤果実の香りが強く、パワフルなワイン。2023年と比べると、こちらの方が飲み頃は早く来そうで、今でも十分美味しく飲めます。ヘリテージ・クローンとモナステリー・ブロックはかなり個性が違うので好みが分かれそうですが、個人的にはヘリテージ・クローンを高く評価します。
最後のワインは、2021年のオールド・スパーキー。オールド・スパーキーはシュレーダーのトップ・キュベで素晴らしい樽だけを集めて作るワイン。マグナムボトルだけというワインです。価格は20万円。2021年はベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードのブドウを使った最後のヴィンテージです。
シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン オールド・スパーキー 2021
とにかく濃密な果実味に圧倒されます。バランスよく、むちゃくちゃ美味しい。30年は熟成するだろうとのこと。
なお、2023年はシュレーダー25周年でオールド・スパーキーのスペシャル・ボトルが作られます。全世界で250本。専用のケースに入れられ、価格は40万円超とのこと。
なお、コンステレーションブランズ傘下のマウント・ヴィーダーやト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーの試飲も別途ありましたが、そちらは別記事で。
柳屋でカリフォルニアのお得カベルネ系ワインが6本セットになったてんこ盛りセットが送料無料で売られています。
1本目のリンカーンは「ナパの上級カベルネが輸入停止で3000円の激安」で紹介したワイン。この記事の後、インポーターさんにショップから問い合わせがいくつも来たそうですが品切れ。柳屋が在庫を全部持っているようです。
2本目のビッグスムースは昨年話題になったワイン。「現地価格より全然安い、ローダイのコスパカベルネ」という記事で紹介しています。この2本、どちらも現地価格より安いコスパワイン。
3本目のエンパシーは、中身がプリズナーのレッドブレンド?と噂されるワイン。これだけはカベルネ・ソーヴィニヨンも入っていますが、ジンファンデルなども使われています。このエンパシーというワインはワインショップのオーナーからアントレプレナーになったゲイリー・ヴェイナチェックのブランドで、いろいろなワイナリーからワインを仕入れてエンパシーのブランドで販売しており、このワインに関しては、外箱がプリズナー傘下のブランドだったことから噂が広がったものです。ちなみにプリズナーの赤なら今は1万円を超えるねだん。それだけでこのセット6本分くらいになってしまいます。味わいも果実味たっぷりでプリズナー系のワインであることは間違いありません。
4本目のフランシスカンは5年ほど前まではナパのカベルネ・ソーヴィニヨンのど定番だったワイン。ブランドが売却されたことで日本への輸入が途絶えていましたが、再開されました。今回はナパではなくカリフォルニア広域のワインになっていますが、バランスの良さは失われていません。
5本目のランチ32は、私が1000円台のコスパワインを挙げるときに必ず選ぶワイン。モントレーのコスパ王シャイドが作るブランドです。
6本目のブレッド&バターはシャルドネが超有名なワインですが、カベルネも秀逸です。
カリフォルニアワイン好き、カベルネ好きだったら絶対に飲んでおきたいワインばかりが集まっており、お得感は半端ないです。どれも美味しいことは請け負いますので、だまされたと思って買ってみてください。
1本目のリンカーンは「ナパの上級カベルネが輸入停止で3000円の激安」で紹介したワイン。この記事の後、インポーターさんにショップから問い合わせがいくつも来たそうですが品切れ。柳屋が在庫を全部持っているようです。
2本目のビッグスムースは昨年話題になったワイン。「現地価格より全然安い、ローダイのコスパカベルネ」という記事で紹介しています。この2本、どちらも現地価格より安いコスパワイン。
3本目のエンパシーは、中身がプリズナーのレッドブレンド?と噂されるワイン。これだけはカベルネ・ソーヴィニヨンも入っていますが、ジンファンデルなども使われています。このエンパシーというワインはワインショップのオーナーからアントレプレナーになったゲイリー・ヴェイナチェックのブランドで、いろいろなワイナリーからワインを仕入れてエンパシーのブランドで販売しており、このワインに関しては、外箱がプリズナー傘下のブランドだったことから噂が広がったものです。ちなみにプリズナーの赤なら今は1万円を超えるねだん。それだけでこのセット6本分くらいになってしまいます。味わいも果実味たっぷりでプリズナー系のワインであることは間違いありません。
4本目のフランシスカンは5年ほど前まではナパのカベルネ・ソーヴィニヨンのど定番だったワイン。ブランドが売却されたことで日本への輸入が途絶えていましたが、再開されました。今回はナパではなくカリフォルニア広域のワインになっていますが、バランスの良さは失われていません。
5本目のランチ32は、私が1000円台のコスパワインを挙げるときに必ず選ぶワイン。モントレーのコスパ王シャイドが作るブランドです。
6本目のブレッド&バターはシャルドネが超有名なワインですが、カベルネも秀逸です。
カリフォルニアワイン好き、カベルネ好きだったら絶対に飲んでおきたいワインばかりが集まっており、お得感は半端ないです。どれも美味しいことは請け負いますので、だまされたと思って買ってみてください。
日本ワインブドウ栽培協会(JVA)が輸入した苗木からのワインを試飲するセミナーに参加してきました。
代表理事の鹿取みゆきさんとは、私の従兄が鹿取さんと大学の同級生だったという縁もあり、ずいぶん前からSNSでは交流がありましたが、実際にお会いするのはこれが初めてでした。というか、こそっと参加していようと思ったら簡単に見つけられてしまいました。

この協会は日本ワインの未来のために、世界基準のワインの苗木の原木園を作ろうとしており、クラウドファンディングには私もわずかながら支援させていただきました。
日本ワインについては、ワイナリー数が増え、品質が向上し、ファンも年々増えている様相です。余市のドメーヌ・タカヒコを筆頭に、入手困難銘柄もどんどん出てきています。その中で、協会の問題意識は以下のようなところにあります。

ウイルス感染比率が半分近いというのはさすがに驚きました。ウイルスに感染すると、収量が3割から5割ほども低下し、着色不良や糖度が十分に上がらないなどの問題が起こります。ちなみに、ブドウの葉は紅葉しないので、秋に畑に行って紅葉していたら、それはウイルスに感染している樹です。また、感染した樹からウイルスを取り除くことはできないので、ウイルスがない苗木に植え替えることしかありません。
ただ、現状ではウイルスがない苗木を調達するのも難しいのです。畑から取ってきた枝で接ぎ木をするのでは、ウイルスがないと保証はできません。そのためにもウイルスがない苗木を作る原木園が必要なのです。
使える品種の少なさも、米国の8分の1ほどとかなり深刻です。これでは適切な品種やクローンを選ぶのはかなり難しいと言わざるを得ないでしょう。
ということで、JVAでは米国などから苗木を輸入して増やすことをしています。

既に27の品種と12種の台木を輸入しており、今回はその中から6品種について試飲をしていきます。栽培や醸造は大分県の安心院葡萄酒工房で行っています。

ワイナリーとしては、病気への強さや生産性なども品種選びの重要な要素になると思いますが、純粋にできたワインの品質だけで見ると、今回はアルヴァリーニョが素晴らしかったです。今回の苗木はポルトガル由来のクローンだそうです。酸の豊かさと厚みのある果実の味わいが魅力的で、これはまた飲みたいと思いました。安心院にはこのアルヴァリーニョ以外にもいくつかのアルヴァリーニョの畑があり、それぞれ全く違う味わいになるということで、そのあたりも興味深いです。温暖な環境でも酸が落ちにくい特徴を持つアルヴァリーニョは、カリフォルニアでも注目の品種の一つですが、日本ではさらに可能性があるような気がしました。

赤は白に比べるとちょっと難しいところがありました。安心院のワインメーカーの古屋浩二さんによると、カベルネ系の品種は安心院では色づきが悪いということで、カベルネ・ソーヴィニヨンは抜いてしまったそうです。今回はカベルネ・フランがありましたが、これも色づきは十分ではなかったようでした。
色づきが悪いのは気温のためだそうで、お話を伺ってみると、昼間の気温はカリフォルニアの温暖産地であるパソ・ロブレスあたりとそれほど変わらないようでしたが、夜の気温も高いのが難点だそうです。九州ではカベルネ系は難しいということでしたが、プティ・ヴェルドは割といいものができるそうで、品種の違いはいろいろと大事だと思いました。
赤の中では、タナは凝縮感あり、いい出来でした。品種特性的に非常にタンニンが強いため、万人受けするワインとはいいがたいかもしれませんが、ブレンドなどでも可能性はあるように思いました。ただ、個性としてはプティ・ヴェルドと被る部分もあるので、どういうワインに仕上げるのがいいのかは悩ましいかもしれません。
気候変動で、今年のような夏の暑さが平常になることを想定すると、これまで以上に品種選びやクローン選びは重要になってきそうです。JVAの果たす役割も大きくなるだろうと思いました。
代表理事の鹿取みゆきさんとは、私の従兄が鹿取さんと大学の同級生だったという縁もあり、ずいぶん前からSNSでは交流がありましたが、実際にお会いするのはこれが初めてでした。というか、こそっと参加していようと思ったら簡単に見つけられてしまいました。
この協会は日本ワインの未来のために、世界基準のワインの苗木の原木園を作ろうとしており、クラウドファンディングには私もわずかながら支援させていただきました。
日本ワインについては、ワイナリー数が増え、品質が向上し、ファンも年々増えている様相です。余市のドメーヌ・タカヒコを筆頭に、入手困難銘柄もどんどん出てきています。その中で、協会の問題意識は以下のようなところにあります。
ウイルス感染比率が半分近いというのはさすがに驚きました。ウイルスに感染すると、収量が3割から5割ほども低下し、着色不良や糖度が十分に上がらないなどの問題が起こります。ちなみに、ブドウの葉は紅葉しないので、秋に畑に行って紅葉していたら、それはウイルスに感染している樹です。また、感染した樹からウイルスを取り除くことはできないので、ウイルスがない苗木に植え替えることしかありません。
ただ、現状ではウイルスがない苗木を調達するのも難しいのです。畑から取ってきた枝で接ぎ木をするのでは、ウイルスがないと保証はできません。そのためにもウイルスがない苗木を作る原木園が必要なのです。
使える品種の少なさも、米国の8分の1ほどとかなり深刻です。これでは適切な品種やクローンを選ぶのはかなり難しいと言わざるを得ないでしょう。
ということで、JVAでは米国などから苗木を輸入して増やすことをしています。
既に27の品種と12種の台木を輸入しており、今回はその中から6品種について試飲をしていきます。栽培や醸造は大分県の安心院葡萄酒工房で行っています。
ワイナリーとしては、病気への強さや生産性なども品種選びの重要な要素になると思いますが、純粋にできたワインの品質だけで見ると、今回はアルヴァリーニョが素晴らしかったです。今回の苗木はポルトガル由来のクローンだそうです。酸の豊かさと厚みのある果実の味わいが魅力的で、これはまた飲みたいと思いました。安心院にはこのアルヴァリーニョ以外にもいくつかのアルヴァリーニョの畑があり、それぞれ全く違う味わいになるということで、そのあたりも興味深いです。温暖な環境でも酸が落ちにくい特徴を持つアルヴァリーニョは、カリフォルニアでも注目の品種の一つですが、日本ではさらに可能性があるような気がしました。
赤は白に比べるとちょっと難しいところがありました。安心院のワインメーカーの古屋浩二さんによると、カベルネ系の品種は安心院では色づきが悪いということで、カベルネ・ソーヴィニヨンは抜いてしまったそうです。今回はカベルネ・フランがありましたが、これも色づきは十分ではなかったようでした。
色づきが悪いのは気温のためだそうで、お話を伺ってみると、昼間の気温はカリフォルニアの温暖産地であるパソ・ロブレスあたりとそれほど変わらないようでしたが、夜の気温も高いのが難点だそうです。九州ではカベルネ系は難しいということでしたが、プティ・ヴェルドは割といいものができるそうで、品種の違いはいろいろと大事だと思いました。
赤の中では、タナは凝縮感あり、いい出来でした。品種特性的に非常にタンニンが強いため、万人受けするワインとはいいがたいかもしれませんが、ブレンドなどでも可能性はあるように思いました。ただ、個性としてはプティ・ヴェルドと被る部分もあるので、どういうワインに仕上げるのがいいのかは悩ましいかもしれません。
気候変動で、今年のような夏の暑さが平常になることを想定すると、これまで以上に品種選びやクローン選びは重要になってきそうです。JVAの果たす役割も大きくなるだろうと思いました。
中川ワインの試飲会から美味しかったワインを紹介します。飲み頃カベルネが素晴らしい、ナパのトネラ・セラーズも併せてごらんください。

コスパワインで知られる家族経営のワイナリー「マックマニス」。2023ヴィンテージではメルローとジンファンデルが良かったです(価格はどの品種も2200円)。メルローは芳醇で酸もあり、バランスよくできています。ジンファンデルは果実味が素晴らしい。

新商品のハンテッド ジンファンデル2023(2500円)。果実味爆発系のジンファンデルです。

トリムはナパの老舗ワイナリー「シニョレッロ」が作る普及価格帯のブランド。シャルドネ2023(3000円)は、果実味はもちろんのこと、いきいきとした酸が印象的で美味しい。

ジャム・セラーズの「バター」シャルドネNV(3900円)は、いわゆるブレッド&バター系のシャルドネですが、濃厚だけでなく酸もあってバランスいい味わい。

ソノマのドライクリーク・ヴァレーで質実剛健なワイン造りをするペドロンチェリ。ソーヴィニョン・ブラン2024(3300円)は、フレッシュな味わい。美味しい。ジンファンデル2022(3400円)はジューシーで酸もあり、バランスがいい。

スターモントはナパの人気ワイナリー「メリーヴェール」の普及価格帯ワイン。シャルドネ2022(3800円)はサンタ・バーバラ46%、メンドシーノ43%、ソノマ11%と、冷涼地域のブドウを使ったワインで酸のキレがいいワイン。

オー・ボン・クリマが中川ワイン用に作る「ミッションラベル」のシャルドネ2023(4500円)とピノ・ノワール2023(4500円)。シャルドネはバランスよくおいしい。ピノ・ノワールも酸がきれいでコスパ高いです。

アルマ・デ・カトレアは前ウェイフェアラーのビビアナ・ゴンザレス・レーヴが作る、エントリーレベルのワイン。ソーヴィニョン・ブランはワインスペクテーターの年間トップ100にも入ったことがあります。2024年のソーヴィニョン・ブラン(4800円)は華やかな香りで1ランク上のソーヴィニョン・ブラン。

ベッドロックの自社畑などのブドウを使ったソーヴィニョン・ブラン。リッチで芳醇。酸もありうまい。

ポストマーク カベルネ・ソーヴィニヨン2022(3800円)。リッチな果実味にしっかりとしたタンニン。バランスもよく、価格以上の満足度。

デコイの上級版リミテッドのカベルネ・ソーヴィニヨン パソ・ロブレス2022(4400円)。問答無用で美味しい。

ナパハイランズのリザーブ・カベルネ・ソーヴィニヨン2022(12000円)。通常版の倍の価格ですが、それだけのクオリティを持っています。

ハドソンのシャルドネ3種。いずれも2022年。レギュラーのシャルドネ(13000円)は高級シャルドネの中ではコスパ高いワイン。リッチな樽感も心地よい。
限定品のリトルビット(20000円)はミネラル感にあふれた味わい。もう一つのシーシェル(20000円)はリッチでスパイシー、むちゃくちゃいいです。限定品ではリトルビットが好みのことが多いのですが、今回はシーシェルに軍配を上げます。

同じくハドソンからカベルネ・フランブレンドのオールド・マスター2020(24000円)。しなやかでエレガント。

ホーニッグのソーヴィニョン・ブラン2024(4000円)。さわやか系のソーヴィニョン・ブランでコスパいいです。

紹介するまでもないワインですが、オー・ボン・クリマのピノ・ノワール ノックス・アレキサンダー2020とイザベル2022(共に9800円)です。ノックスはしっかりしたボディが特徴、イザベルはエレガントで複雑味があります。

サンタ・ルシア・ハイランズの雄「ピゾーニ家」がピゾーニ・ヴィンヤード以外の畑のブドウから作るブランドがルチア(Lucia)です。エステートシャルドネ2023(9500円)はリッチな果実味がすばらしい、エステートピノ・ノワール2023は10000円。リッチで酸もきれい。

ナパでリッチなカベルネ・ソーヴィニヨンを作るビーヴァン・セラーズのシャルドネ リッチー・ヴィンヤード(12000円)。ビーヴァンらしい樽をしっかりきかせたワイン。うまいです。

ピゾーニによる、ピゾーニ・ヴィンヤードのシャルドネ2023(17000円)。ピゾーニのピノはいくつかのワイナリーが作っていますが、シャルドネはごくわずかしか植わっておらず、ピゾーニ自身とポール・ラトだけが作っています。これもリッチですがバランスもよく美味しい。

今回の試飲会には「スタッフお薦め」コーナーがあり、そこのワインです。右はシェアード・ノーツのソーヴィニョン・ブラン「約束の石2023」(14000円)。シェアード・ノーツは前述のビビアナ・ゴンザレス・レーヴが夫であるピゾーニのジェフ・ピゾーニと作るソーヴィニョン・ブラン専業ワイナリーで、ボルドータイプの「師匠の教え」とロワールタイプの「約束の石」があります。ロワールタイプは酸の広がりとミネラル感が身上。素晴らしいです。
中央はリース(Rhys)のシャルドネ マウント・パハロ2018(18000円)。サンタ・クルーズ・マウンテンズらしい鮮烈な酸があり、ミネラル感あふれる味わい。
右はナパのシュレーダーなどで知られるトーマス・リヴァース・ブラウンがソノマ・コーストで作るアストンのピノ・ノワール「ブラウン・ラベル2021」(8500円)。ブラウン・ラベルはセカンドの位置付け。酸の高さと濃厚な果実味がソノマ・コーストらしいピノ・ノワール。

サンタ・リタ・ヒルズの一番冷涼なところでピノ・ノワールを作るドメーヌ・ド・ラ・コート。DDLC2023(12000円)はエントリー的存在。複雑さもありとても美味しい。ブルームス・フィールド2023(18000円)は全てが整った美味しさ。


最後は「スペシャルワイン」のコーナーから。
ブリリアント・ミステイク「ポエット&ミューズ2021」(52000円)はリッチで華やか。おいしい。ザ・マスコット2020(29000円)はバランスよく、タンニンもしっかり。コスパ高いです。
コスパワインで知られる家族経営のワイナリー「マックマニス」。2023ヴィンテージではメルローとジンファンデルが良かったです(価格はどの品種も2200円)。メルローは芳醇で酸もあり、バランスよくできています。ジンファンデルは果実味が素晴らしい。
新商品のハンテッド ジンファンデル2023(2500円)。果実味爆発系のジンファンデルです。
トリムはナパの老舗ワイナリー「シニョレッロ」が作る普及価格帯のブランド。シャルドネ2023(3000円)は、果実味はもちろんのこと、いきいきとした酸が印象的で美味しい。
ジャム・セラーズの「バター」シャルドネNV(3900円)は、いわゆるブレッド&バター系のシャルドネですが、濃厚だけでなく酸もあってバランスいい味わい。
ソノマのドライクリーク・ヴァレーで質実剛健なワイン造りをするペドロンチェリ。ソーヴィニョン・ブラン2024(3300円)は、フレッシュな味わい。美味しい。ジンファンデル2022(3400円)はジューシーで酸もあり、バランスがいい。
スターモントはナパの人気ワイナリー「メリーヴェール」の普及価格帯ワイン。シャルドネ2022(3800円)はサンタ・バーバラ46%、メンドシーノ43%、ソノマ11%と、冷涼地域のブドウを使ったワインで酸のキレがいいワイン。
オー・ボン・クリマが中川ワイン用に作る「ミッションラベル」のシャルドネ2023(4500円)とピノ・ノワール2023(4500円)。シャルドネはバランスよくおいしい。ピノ・ノワールも酸がきれいでコスパ高いです。
アルマ・デ・カトレアは前ウェイフェアラーのビビアナ・ゴンザレス・レーヴが作る、エントリーレベルのワイン。ソーヴィニョン・ブランはワインスペクテーターの年間トップ100にも入ったことがあります。2024年のソーヴィニョン・ブラン(4800円)は華やかな香りで1ランク上のソーヴィニョン・ブラン。
ベッドロックの自社畑などのブドウを使ったソーヴィニョン・ブラン。リッチで芳醇。酸もありうまい。
ポストマーク カベルネ・ソーヴィニヨン2022(3800円)。リッチな果実味にしっかりとしたタンニン。バランスもよく、価格以上の満足度。
デコイの上級版リミテッドのカベルネ・ソーヴィニヨン パソ・ロブレス2022(4400円)。問答無用で美味しい。
ナパハイランズのリザーブ・カベルネ・ソーヴィニヨン2022(12000円)。通常版の倍の価格ですが、それだけのクオリティを持っています。
ハドソンのシャルドネ3種。いずれも2022年。レギュラーのシャルドネ(13000円)は高級シャルドネの中ではコスパ高いワイン。リッチな樽感も心地よい。
限定品のリトルビット(20000円)はミネラル感にあふれた味わい。もう一つのシーシェル(20000円)はリッチでスパイシー、むちゃくちゃいいです。限定品ではリトルビットが好みのことが多いのですが、今回はシーシェルに軍配を上げます。
同じくハドソンからカベルネ・フランブレンドのオールド・マスター2020(24000円)。しなやかでエレガント。
ホーニッグのソーヴィニョン・ブラン2024(4000円)。さわやか系のソーヴィニョン・ブランでコスパいいです。
紹介するまでもないワインですが、オー・ボン・クリマのピノ・ノワール ノックス・アレキサンダー2020とイザベル2022(共に9800円)です。ノックスはしっかりしたボディが特徴、イザベルはエレガントで複雑味があります。
サンタ・ルシア・ハイランズの雄「ピゾーニ家」がピゾーニ・ヴィンヤード以外の畑のブドウから作るブランドがルチア(Lucia)です。エステートシャルドネ2023(9500円)はリッチな果実味がすばらしい、エステートピノ・ノワール2023は10000円。リッチで酸もきれい。
ナパでリッチなカベルネ・ソーヴィニヨンを作るビーヴァン・セラーズのシャルドネ リッチー・ヴィンヤード(12000円)。ビーヴァンらしい樽をしっかりきかせたワイン。うまいです。
ピゾーニによる、ピゾーニ・ヴィンヤードのシャルドネ2023(17000円)。ピゾーニのピノはいくつかのワイナリーが作っていますが、シャルドネはごくわずかしか植わっておらず、ピゾーニ自身とポール・ラトだけが作っています。これもリッチですがバランスもよく美味しい。
今回の試飲会には「スタッフお薦め」コーナーがあり、そこのワインです。右はシェアード・ノーツのソーヴィニョン・ブラン「約束の石2023」(14000円)。シェアード・ノーツは前述のビビアナ・ゴンザレス・レーヴが夫であるピゾーニのジェフ・ピゾーニと作るソーヴィニョン・ブラン専業ワイナリーで、ボルドータイプの「師匠の教え」とロワールタイプの「約束の石」があります。ロワールタイプは酸の広がりとミネラル感が身上。素晴らしいです。
中央はリース(Rhys)のシャルドネ マウント・パハロ2018(18000円)。サンタ・クルーズ・マウンテンズらしい鮮烈な酸があり、ミネラル感あふれる味わい。
右はナパのシュレーダーなどで知られるトーマス・リヴァース・ブラウンがソノマ・コーストで作るアストンのピノ・ノワール「ブラウン・ラベル2021」(8500円)。ブラウン・ラベルはセカンドの位置付け。酸の高さと濃厚な果実味がソノマ・コーストらしいピノ・ノワール。
サンタ・リタ・ヒルズの一番冷涼なところでピノ・ノワールを作るドメーヌ・ド・ラ・コート。DDLC2023(12000円)はエントリー的存在。複雑さもありとても美味しい。ブルームス・フィールド2023(18000円)は全てが整った美味しさ。
最後は「スペシャルワイン」のコーナーから。
ブリリアント・ミステイク「ポエット&ミューズ2021」(52000円)はリッチで華やか。おいしい。ザ・マスコット2020(29000円)はバランスよく、タンニンもしっかり。コスパ高いです。
アケイシア(Acacia)の名前で長年親しまれていたカルメール・ワイナリーが売却されました。
ナパの元アケイシア、ソノマのメドロック・エームズが売却対象に
こちらの記事で、売却対象になっていることは公開されていましたが、North America Real Estate Investment Group (NAREIG) が売却が成立したと発表しました。売却前のオーナーはナパのPejuでした。
購入者が誰だかは明らかになっていませんが、SFクロニクル紙によると中国人の実業家が買ったとのことです。
ナパの元アケイシア、ソノマのメドロック・エームズが売却対象に
こちらの記事で、売却対象になっていることは公開されていましたが、North America Real Estate Investment Group (NAREIG) が売却が成立したと発表しました。売却前のオーナーはナパのPejuでした。
購入者が誰だかは明らかになっていませんが、SFクロニクル紙によると中国人の実業家が買ったとのことです。
しあわせワイン俱楽部がワインくじの第6弾としてナパのワインのくじをやっています。1万1000円とやや高価ですが、中身がすごい。
なんと、特賞(500本のうちの1本)はシュレーダーの「オールド・スパーキー」。ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードの最高のロットだけを使って作るトップキュベ。マグナムだけで、通常価格は17万6000円(しあわせワイン俱楽部で、以下同)。実は、シュレーダーはコンステレーションブランズ傘下に入ったことで、ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードは打ち切りになり、ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードを使ったオールド・スパーキーはこれが最後のヴィンテージという貴重なワイン。
1等の2本(5本ずつ)はスローンのセカンドワイン「アスタリスク」と、ベクストファー・ジョルジュ・ザ・サードのブドウを使ったパーチェスのカベルネ。
2等以下も魅力的なワインが続きます。108本と一番本数が多いのが3等のダックホーン メルロー「スリー・パームス」(1万5345円)というのはびっくり。ナパというかカリフォルニアを代表するメルローで、ワインスペクテーターのワイン・オブ・ザ・イヤーにも選ばれた憧れのワインですよ! その次に本数が多い96本がスカーレットのカベルネ(1万8117円)。その次の72本が2等のヘス「アイロン・コーラル」(1万9800円)。ヘスはマウント・ヴィーダーとヴァレーフロアに畑を持っていますが、そのいいとこどりをしたワイン。
この3つで半分を超えますが、一番安いダックホーンが当たったとしても4000円もお得です。年末年始に向けてちょっといいワインを準備したくなる季節。とても豪華でお得なくじだと思います。
なんと、特賞(500本のうちの1本)はシュレーダーの「オールド・スパーキー」。ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードの最高のロットだけを使って作るトップキュベ。マグナムだけで、通常価格は17万6000円(しあわせワイン俱楽部で、以下同)。実は、シュレーダーはコンステレーションブランズ傘下に入ったことで、ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードは打ち切りになり、ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードを使ったオールド・スパーキーはこれが最後のヴィンテージという貴重なワイン。
1等の2本(5本ずつ)はスローンのセカンドワイン「アスタリスク」と、ベクストファー・ジョルジュ・ザ・サードのブドウを使ったパーチェスのカベルネ。
2等以下も魅力的なワインが続きます。108本と一番本数が多いのが3等のダックホーン メルロー「スリー・パームス」(1万5345円)というのはびっくり。ナパというかカリフォルニアを代表するメルローで、ワインスペクテーターのワイン・オブ・ザ・イヤーにも選ばれた憧れのワインですよ! その次に本数が多い96本がスカーレットのカベルネ(1万8117円)。その次の72本が2等のヘス「アイロン・コーラル」(1万9800円)。ヘスはマウント・ヴィーダーとヴァレーフロアに畑を持っていますが、そのいいとこどりをしたワイン。
この3つで半分を超えますが、一番安いダックホーンが当たったとしても4000円もお得です。年末年始に向けてちょっといいワインを準備したくなる季節。とても豪華でお得なくじだと思います。
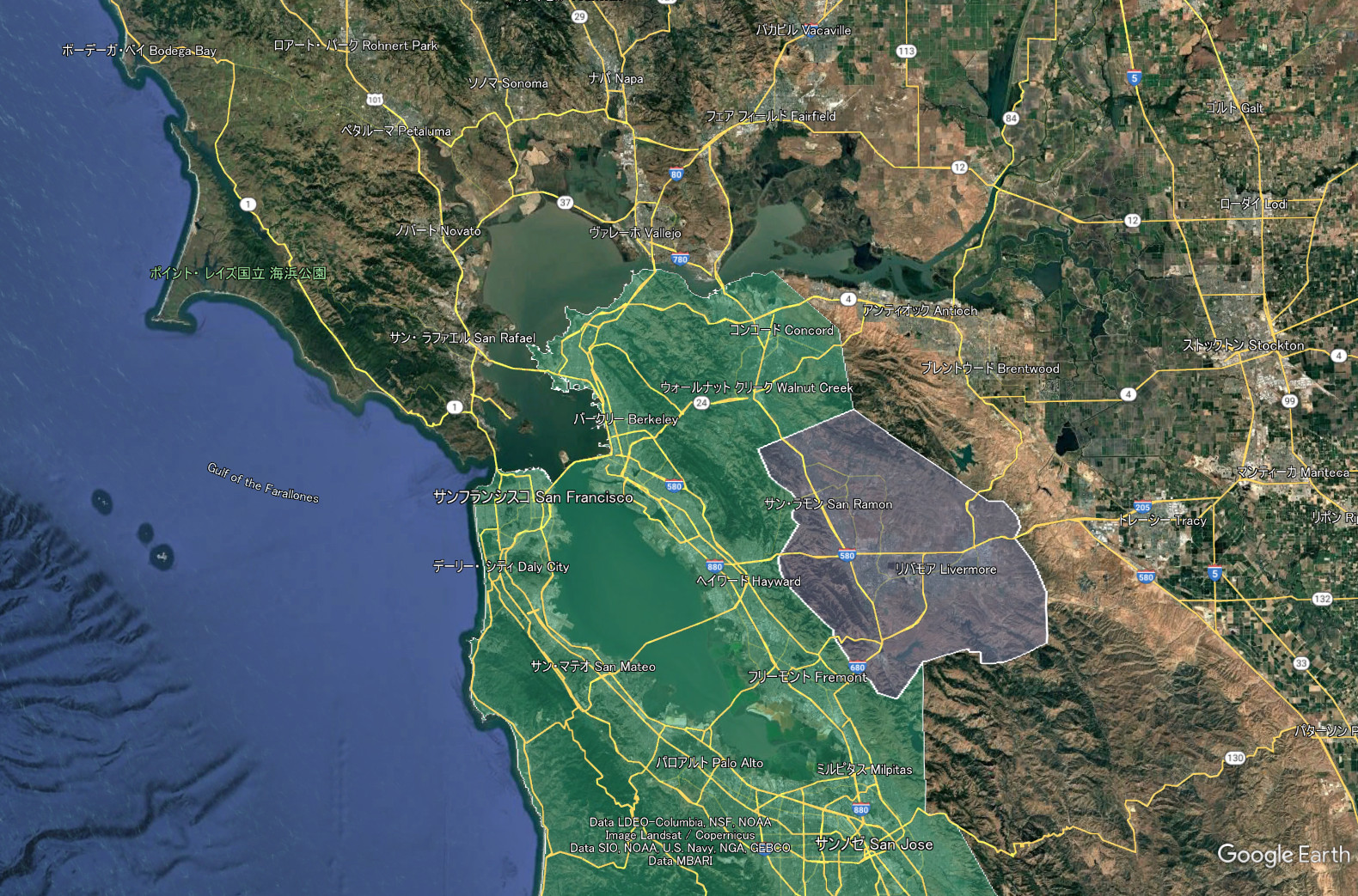
リバモア・ヴァレー(Livermore Valley)というAVAをご存じでしょうか。カリフォルニアワインに割と詳しい人でも「どこ?」と思うかもしれません。サンフランシスコ湾の東側でなだらかな丘陵地帯です。中央の盆地にあるリバモア市は千葉の四街道市と姉妹都市になっており、ローレンス・リバモア研究所で知られています。
実は、リバモア・ヴァレーはカリフォルニアワインの歴史においては重要な場所の一つです。ウェンテ(Wente)はシャルドネのクローンで知られており、コンキャノン(Concannon)はシャトー・マルゴーからのカベルネ・ソーヴィニヨンや、シャトー・ディケムからのセミヨンを持ち込んだ
ウェンテは家族経営のワイナリーとしてカリフォルニアで一番長い歴史を持っており、特にシャルドネの「ウェンテ・クローン」はカリフォルニアのシャルドネの7割を占めると言われるほど重要になっています。
これまではシャルドネとカベルネ・ソーヴィニヨンを中心とする地域でしたが、近年この地域で注目されているのがカベルネ・フランです。今年2月には「Cab Franc Guild」という団体も発足しています。コンキャノンでは「カベルネ・フラン・シティ」と名付けた新しいワイン・センターを建築中です。
リバモアの環境団体であるトライ・ヴァレー・コンサーバンシー(TVC)は2020年、歴史あるリバモア・ヴァレーのワイン産業の生産的な未来を保証する最良のブドウを特定するプロジェクトを始めました。依頼したのはUCデーヴィス。その報告書では、ソーヴィニヨン・ブランとカベルネ・フランが、ブドウの栽培条件が優れていることと、リバモア・ヴァレーのワインカントリーへの観光客を惹きつける可能性があることから、看板品種の候補として推奨されていました。
それ以前から、カベルネ・フランは作られていましたが、この報告書をきっかけにさらにカベルネ・フランを植える生産者が増えており、前述のギルドも作られました。
スティーブン・ケント・ワイナリー(Steven Kent Winery)のスティーブン・ミラソーは2023年に、「CabFranc-a-Palooza」というイベントを始めました。今年のイベントには500人ほどが参加したそうです。
カベルネ・フランはナパでも存在感を少しずつ増やしており、注目のブドウ品種の一つになっていますが、生産量がカベルネ・ソーヴィニヨンと比べてずっと少ないことからムーブメントになるほどの力はなさそうです。現状で、リバモアがナパを超える名産地になるかどうかは不明ですが、カベルネ・フランを旗印にかかげる産地はロワールを除くとほとんどありませんから、興味深い存在になる可能性はあると思います。
ただ、日本においてはリバモアのワインで輸入されているのはウェンテくらいであり、ウェンテはまだこの動きには追随していないので、リバモアのフランを飲むチャンスはなかなかなさそうなのが残念です。
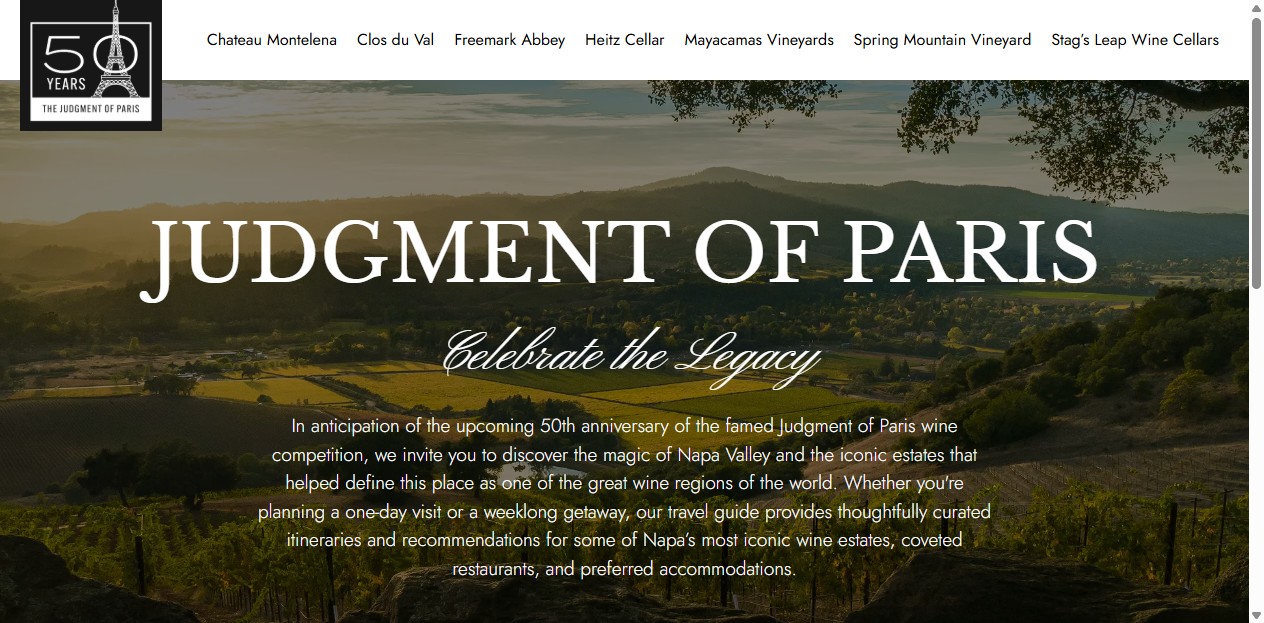
来年2026年は「パリスの審判」から50周年。これを祝して、イベントに参加したワイナリーのうちナパヴァレーの7ワイナリーが特設サイトをオープンしました。
Judgment of Paris 50th Anniversary | Napa Valley Wine Travel Guide
具体的なイベントはこれから明らかになっていきますが、以下のようなものが予定されています。
• パリスの審判の時代に関連したライブラリー ヴィンテージやレアワインをフィーチャーした特別なテイスティングフライトと垂直テイスティング。
• オリジナルのワインセラー、伝統的なブドウ園、アーカイブ資料を紹介する歴史ツアーとストーリーテリング。
• ナパバレーのトップレストランやリゾートと提携した特別な料理とワインのイベント。
• 旅行者向けに、セルフガイド式の訪問またはコンシェルジュが企画した体験のためのテーマ別旅程。
参加ワイナリーと、そこで予定されているイベントは以下の通り(今後追加されます)。
• シャトー・モンテレーナ(Chateau Montelena)
白ワイン部門で優勝したワイナリーで歴史書に足を踏み入れましょう。ゲストは、「ボトルの裏側にある物語」体験や、蔵出しヴィンテージやエステートを紹介する「グラスの中の遺産」テイスティングを楽しめます。
• スタッグス・リープ・ワインセラーズ(Stag's Leap Wine Cellars)
フランスの審査員を驚かせた 1973SLV カベルネ・ソーヴィニヨンの産地であるスタッグス・リープ・ワイン・セラーズでは、その有名なブドウ畑と熟成向きの赤ワインにスポットライトを当てた「エステート エクスペリエンス」と「FAY の探究」のテイスティングを提供します。
• クロ・デュ・ヴァル(Clos du Val)
ゴエレ家とワインメーカーのベルナール・ポルテが世界中を調査して見つけたのがスタッグス・リープ・ディストリクト。そこでクロ・デュ・ヴァルを創業し、パリスの審判に1972年のカベルネ・ソーヴィニヨンが提供されました。クロ・デュ・ヴァルでは、特別な「10年間を振り返る試飲会」と「ヒロンデル・ハウス・エステート試飲会」を開催します。
• フリーマーク・アビー(Freemark Abbey)
唯一赤ワインと白ワインの両方のカテゴリーに出展したワイナリーです。お客様は、「アペラシオン・テイスティング」また「ディケイズ・テイスティング」から選べます。
• ハイツセラー(Heitz Cellar)
ナパ初の単一畑カベルネ・ソーヴィニヨンで世界的に有名になったハイツ・セラーは、セントヘレナの歴史的な敷地内で「ナパ・ヴァレーの伝統」と「マーサズ・ヴィンヤードの伝統」のテイスティングを提供します。
• マヤカマス・ヴィンヤーズ(Mayacamas Vineyards)
マウント・ヴィーダーの高台に位置するマヤカマスでは、壮大な景色と「エステート クラシック」や「エステート リザーブ」のテイスティングを通してクラシックなスタイルのワインをお楽しみいただけます。オプションでナパのダウンタウンでの体験もお楽しみいただけます。
• スプリングマウンテンヴィンヤード(Spring Mountain Vineyard)
歴史あるブドウ畑と素晴らしい植物園を持つスプリング マウンテン ヴィンヤードでは、「パリスの審判」テイスティングと、さらに大規模な「スプリング マウンテン エクスプローラーズ」エステート体験を提供しています。
中川ワインの試飲会にナパのトネラ・セラーズ(S.R. Tonella Cellars)の当主であるスティーブ・トネラ氏が来ておりました。今回、3種類のワインが新入荷しています。

トネラは、ナパのラザフォードの西側のベンチに小さな畑を持っています。20世紀初頭にまでさかのぼる歴史ある畑ですが、トネラがワインを造り始めたのは2010年と、ごく最近のことです。それ以降も、評論家のレビューなどもほとんど出ておらず、知る人ぞ知るといったワイナリーです。

ワイナリーとしてよりも、栽培家としての歴史の方がずっと長いトネラですが、ユニークなのがここの剪定法。バーティカル・コルドンと呼ぶ方法で、通常は横向きに成長するようにワイヤーで誘引されるところが、縦向きにコルドンがあります。この形は初めて見ましたが、近年はゴブレットやカリフォルニア・スプロールと呼ばれるタイプの剪定をするところが少しずつ増えています。温暖化への対応で、必要以上に日を当てないことや、灌漑をなくしたり減らしたりするのが目的となっています。手入れの手間はかかりますが、栽培に力を入れているところでは、今後も増えてきそうです。

輸入されているワインは3種類。一番右はリザーブ・ソーヴィニヨン・ブラン2022(12000円)。ボルドースタイルのソーヴィニョン・ブランで、アロマティックな香りと、かすかな樽香、しっかりとコクのあるソーヴィニョン・ブランです。
中央は自社畑のブドウを使ったカベルネ・ソーヴィニヨン2019(20000円)。ちみつなタンニンが、いわゆる「ラザフォード・ダスト」を思わせます。ダークなフルーツとしなやかなテクスチャー。ヴィンテージが少し古いこともあり、こなれた味わいでバランスがいいワインです。
左はリザーブ・プロプライエタリーBDXブレンド2019(25000円)。カベルネ・ソーヴィニヨン68%にカベルネ・フランが22%、マルベック8%、プティヴェルド2%。コーヒーやココアなど濃厚な風味が印象的ですが、これも2019年で6年熟成しておりバランスの良さが秀逸です。
トネラ・セラーズ、ナパの高級カベルネの中では比較的リーズナブルな価格で、特に今回は少し熟成して飲み頃に入ったワインが輸入されているので、機会があったらぜひ試してみてください。
トネラは、ナパのラザフォードの西側のベンチに小さな畑を持っています。20世紀初頭にまでさかのぼる歴史ある畑ですが、トネラがワインを造り始めたのは2010年と、ごく最近のことです。それ以降も、評論家のレビューなどもほとんど出ておらず、知る人ぞ知るといったワイナリーです。
ワイナリーとしてよりも、栽培家としての歴史の方がずっと長いトネラですが、ユニークなのがここの剪定法。バーティカル・コルドンと呼ぶ方法で、通常は横向きに成長するようにワイヤーで誘引されるところが、縦向きにコルドンがあります。この形は初めて見ましたが、近年はゴブレットやカリフォルニア・スプロールと呼ばれるタイプの剪定をするところが少しずつ増えています。温暖化への対応で、必要以上に日を当てないことや、灌漑をなくしたり減らしたりするのが目的となっています。手入れの手間はかかりますが、栽培に力を入れているところでは、今後も増えてきそうです。
輸入されているワインは3種類。一番右はリザーブ・ソーヴィニヨン・ブラン2022(12000円)。ボルドースタイルのソーヴィニョン・ブランで、アロマティックな香りと、かすかな樽香、しっかりとコクのあるソーヴィニョン・ブランです。
中央は自社畑のブドウを使ったカベルネ・ソーヴィニヨン2019(20000円)。ちみつなタンニンが、いわゆる「ラザフォード・ダスト」を思わせます。ダークなフルーツとしなやかなテクスチャー。ヴィンテージが少し古いこともあり、こなれた味わいでバランスがいいワインです。
左はリザーブ・プロプライエタリーBDXブレンド2019(25000円)。カベルネ・ソーヴィニヨン68%にカベルネ・フランが22%、マルベック8%、プティヴェルド2%。コーヒーやココアなど濃厚な風味が印象的ですが、これも2019年で6年熟成しておりバランスの良さが秀逸です。
トネラ・セラーズ、ナパの高級カベルネの中では比較的リーズナブルな価格で、特に今回は少し熟成して飲み頃に入ったワインが輸入されているので、機会があったらぜひ試してみてください。
布袋ワインズに続いてはアイコニックワイン・ジャパンの試飲会からです。このインポーターは特に2000円台から5000円くらいのレンジにいいワインをたくさん持っているので、覚えておくといいと思います。

カーボニストは新世代のスパークリング・ワイン専業ワイナリー。ペティアンのスパークリングや、シャルドネやピノ・ノワール以外の品種を使ったスパークリング・ワインなどを作っています。右のカーボネーション V2 ブリュット・ナチュール(4700円)は41% アルバリーニョ、 21%ピノ・ノワール、, 14%シャルドネ、 11% プリミティーボ、 7%カリニャン、 4.5%ピノ・グリージョ、 1.5% シュナン・ブランというユニークな構成。瓶内二次発酵なのですが、ディスゴージせず、二次発酵のまま出荷しています。澱が少なくなるよう、酵母の量を抑えているとのこと。アルバリーニョによるさわやかな酸味に加え、複雑味もあり美味しい。
左はクラブ エクストラ・ブリュット オレンジ 2023(6000円)。一次発酵でオレンジワインにした瓶内二次発酵ワイン。コクがあり美味しい。ラベルに描かれている通り、カニに合わせたいワイン。

数年前にピノ・ノワールが大人気でバズったアルタマリア。今回のピノも悪くなかったですが、この2015年というバックヴィンテージのシャルドネ(3400円)がよかったです。まだ果実味もありますが、テクスチャーのしなやかさが素晴らしい。コスパ抜群です。

ソロモン・ヒルズとビエン・ナシードはどちらもサンタ・バーバラのサンタマリア・ヴァレーにある銘醸畑でミラー家が管理しています。ビエン・ナシードはオー・ボン・クリマを初め、数多くのワイナリーが使っている畑。ソロモン・ヒルズはビエン・ナシードと比べると無名ですが、ビエン・ナシード以上に冷涼なところにある畑。今回はソロモン・ヒルズのシャルドネ2021(12300円)とビエン・ナシードのピノ・ノワール2021(16400円)が出ていました。シャルドネは酸と果実味が素晴らしく、ピノ・ノワールはアーシーでちょっとダークな果実味が魅力的です。

メルヴィルのエステートのシラー2019(8000円)とピノ・ノワール2020(8000円)。ピノ・ノワールはしっかり系の味わい。シラーはスパイシーで素晴らしい。

ストルプマンは先日記事を書いたサシ・ムーアマンがワインメーカーをしていたワイナリー。ラブユーバンチ2022(4900円)はサンジョヴェーゼをマセラシオン・カルボニックを使って発酵させた面白いワイン。軽くジューシーな味わい。パラマリア・シラー2023(5300円)はここの定番シラーでむちゃくちゃうまい。サンジョヴェーゼ2022(6500円)は果実感とコクがありラブユーバンチと対照的な味わい。

ユニオン・サクレはセントラル・コーストの様々な畑から、エレガントなスタイルのワインを造っているワイナリー。リースリングやゲヴェルツトラミネールなど、冷涼系の白ワインを特に得意としています。ラベルも軽快感がありおしゃれ。右のブラン・グリ2023(3300円)はピノ・ブランとピノ・グリを半々ずつ使ったオレンジワイン。酸がきれいでジューシー。中央は40デイズ・オレンジ2023(2800円)。40%ゲヴェルツトラミネール、30%ピノ・ブラン、20%ピノ・グリ、10%シルヴァーナという構成で名前の通り、スキンコンタクトを40日間とかなり長くしています(ブラン・グリは14日間)。スキンコンタクトが長い分、コクや複雑味が増していて非常に美味しい。左のドライ・リースリング2023(4100円)は果実味豊かで酸もきれい。

ユニオン・サクレからもう一つ、カベルネ・ソーヴィニヨン2024(2800円)。これはコスパがすごいです。2023年はちょっと味わいが軽くてピーマンの味わいもありますが、2024年はリッチでバランスもいい。個人的には2024年がお薦め。

フィールド・レコーディングスはセントラル・コーストで非常にコストパフォーマンスが高いワインを造っているワイナリーです。スキンズは米国で一番売れているオレンジワインとのこと。新ヴィンテージの2024(3800円)は、例年よりちょっと味わい軽めですが美味しい。もう一つの「どうもありがとう(ミスター・ラマート)2024」(3900円)はピノ・グリのオレンジワイン。ラマートとはイタリアで造られているオレンジワインで「銅(ラマート)」色になることから名付けられたそうです。バランスよく非常に飲みやすい。ちなみにワインの名前はスティックスの曲「ミスター・ロボット」に出てくる歌詞「ドモアリガト、ミスター・ロボット」をもじったものだと思うので、ワインの名前も「ドモアリガト」にした方がよかったのではないかとちょっと思いました。

右のワインはスーパーマリオをもじったと思われるスーパーナリオ。スーパーナリオ(ネッビオーロ)、スーパーナリオ#2(78%コルヴィナ、22%ロンディネッラ)、スーパーナリオ#3(マルヴァシア・ビアンカ)とあり、写真は#2(6400円)。予想以上にエレガントで美味しい。左のフラン2023(4000円)はカベルネ・フラン。カベルネ・フランの入門的にいいワイン。フラン=ピーマンではないのですよ。

イソップ童話に描かれる動物や昆虫などをリアルに描いたラベルが印象的なファブリスト。右のシャルドネ2023(3800円)は冷涼なSLOコーストのブドウを使い、酸がきれい。中央のテンプラニーリョ2023(3800円)はバランスよい味わい。左のパソ・ロブレス プリザーブ(3800円)はジンファンデル中心のブレンド。リッチで果実感もいいワイン。

新入荷のマクプライス・マイヤーズ(McPrice Myers)。2000円台から3000円台が中心で、どれもきれいで美味しいワイン。非常にコスパ高いです。どれもお薦めです。

5年ほど前まで、日本でも大人気だったフランシスカン。その後、ブランドの移行で輸入が途絶えていましたが、久々のお目見えです。以前はナパのワインでしたが、今回はすべて広域のカリフォルニアになっています。その代わり価格はいずれも2800円とリーズナブル。ソーヴィニョン・ブラン、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨンがあり、個人的には今回は白の2種が好印象。

サンタ・ルシア・ハイランズでピュアなワインを造るモーガン。ソーヴィニョン・ブラン2018(3900円)は香り華やか。アンオークト・シャルドネ2023(5000円)はピュアでエレガント。

コブのワインは「エレガント系カリピノ/シャルの最先端 コブのワインを味わう」で詳しく紹介していますが、カリフォルニアのシャルドネやピノ・ノワールの中でもフィネスが感じられるワイン。

カモミはいまさら紹介不要な人気ワイナリーです。シャルドネ・ナパ・ヴァレー2023(3500円)はリッチでなめらかな味わい。赤はナパからカリフォルニアになり価格は2500円。バランスよくスパイス感もあります。

右のナパ1847カベルネ・ソーヴィニヨン2023(6700円)はクラシックで、凝縮感ある味わい。左のラザフォード・ロード・カベルネ・ソーヴィニヨン2023(7500円)はリッチでしなやか。

最後はナパの中堅ワイナリー「ホワイトホール・レーン」。右のシャルドネ2022はソノマのブドウを使っており、リッチな樽感とバランスがいいワイン。左のトレ・レオーニはカベルネ・ソーヴィニヨンなどのブレンド。このヴィンテージはマルベックとメルローをブレンドしています。酸がきれいで美味しい。
カーボニストは新世代のスパークリング・ワイン専業ワイナリー。ペティアンのスパークリングや、シャルドネやピノ・ノワール以外の品種を使ったスパークリング・ワインなどを作っています。右のカーボネーション V2 ブリュット・ナチュール(4700円)は41% アルバリーニョ、 21%ピノ・ノワール、, 14%シャルドネ、 11% プリミティーボ、 7%カリニャン、 4.5%ピノ・グリージョ、 1.5% シュナン・ブランというユニークな構成。瓶内二次発酵なのですが、ディスゴージせず、二次発酵のまま出荷しています。澱が少なくなるよう、酵母の量を抑えているとのこと。アルバリーニョによるさわやかな酸味に加え、複雑味もあり美味しい。
左はクラブ エクストラ・ブリュット オレンジ 2023(6000円)。一次発酵でオレンジワインにした瓶内二次発酵ワイン。コクがあり美味しい。ラベルに描かれている通り、カニに合わせたいワイン。
数年前にピノ・ノワールが大人気でバズったアルタマリア。今回のピノも悪くなかったですが、この2015年というバックヴィンテージのシャルドネ(3400円)がよかったです。まだ果実味もありますが、テクスチャーのしなやかさが素晴らしい。コスパ抜群です。
ソロモン・ヒルズとビエン・ナシードはどちらもサンタ・バーバラのサンタマリア・ヴァレーにある銘醸畑でミラー家が管理しています。ビエン・ナシードはオー・ボン・クリマを初め、数多くのワイナリーが使っている畑。ソロモン・ヒルズはビエン・ナシードと比べると無名ですが、ビエン・ナシード以上に冷涼なところにある畑。今回はソロモン・ヒルズのシャルドネ2021(12300円)とビエン・ナシードのピノ・ノワール2021(16400円)が出ていました。シャルドネは酸と果実味が素晴らしく、ピノ・ノワールはアーシーでちょっとダークな果実味が魅力的です。
メルヴィルのエステートのシラー2019(8000円)とピノ・ノワール2020(8000円)。ピノ・ノワールはしっかり系の味わい。シラーはスパイシーで素晴らしい。
ストルプマンは先日記事を書いたサシ・ムーアマンがワインメーカーをしていたワイナリー。ラブユーバンチ2022(4900円)はサンジョヴェーゼをマセラシオン・カルボニックを使って発酵させた面白いワイン。軽くジューシーな味わい。パラマリア・シラー2023(5300円)はここの定番シラーでむちゃくちゃうまい。サンジョヴェーゼ2022(6500円)は果実感とコクがありラブユーバンチと対照的な味わい。
ユニオン・サクレはセントラル・コーストの様々な畑から、エレガントなスタイルのワインを造っているワイナリー。リースリングやゲヴェルツトラミネールなど、冷涼系の白ワインを特に得意としています。ラベルも軽快感がありおしゃれ。右のブラン・グリ2023(3300円)はピノ・ブランとピノ・グリを半々ずつ使ったオレンジワイン。酸がきれいでジューシー。中央は40デイズ・オレンジ2023(2800円)。40%ゲヴェルツトラミネール、30%ピノ・ブラン、20%ピノ・グリ、10%シルヴァーナという構成で名前の通り、スキンコンタクトを40日間とかなり長くしています(ブラン・グリは14日間)。スキンコンタクトが長い分、コクや複雑味が増していて非常に美味しい。左のドライ・リースリング2023(4100円)は果実味豊かで酸もきれい。
ユニオン・サクレからもう一つ、カベルネ・ソーヴィニヨン2024(2800円)。これはコスパがすごいです。2023年はちょっと味わいが軽くてピーマンの味わいもありますが、2024年はリッチでバランスもいい。個人的には2024年がお薦め。
フィールド・レコーディングスはセントラル・コーストで非常にコストパフォーマンスが高いワインを造っているワイナリーです。スキンズは米国で一番売れているオレンジワインとのこと。新ヴィンテージの2024(3800円)は、例年よりちょっと味わい軽めですが美味しい。もう一つの「どうもありがとう(ミスター・ラマート)2024」(3900円)はピノ・グリのオレンジワイン。ラマートとはイタリアで造られているオレンジワインで「銅(ラマート)」色になることから名付けられたそうです。バランスよく非常に飲みやすい。ちなみにワインの名前はスティックスの曲「ミスター・ロボット」に出てくる歌詞「ドモアリガト、ミスター・ロボット」をもじったものだと思うので、ワインの名前も「ドモアリガト」にした方がよかったのではないかとちょっと思いました。
右のワインはスーパーマリオをもじったと思われるスーパーナリオ。スーパーナリオ(ネッビオーロ)、スーパーナリオ#2(78%コルヴィナ、22%ロンディネッラ)、スーパーナリオ#3(マルヴァシア・ビアンカ)とあり、写真は#2(6400円)。予想以上にエレガントで美味しい。左のフラン2023(4000円)はカベルネ・フラン。カベルネ・フランの入門的にいいワイン。フラン=ピーマンではないのですよ。
イソップ童話に描かれる動物や昆虫などをリアルに描いたラベルが印象的なファブリスト。右のシャルドネ2023(3800円)は冷涼なSLOコーストのブドウを使い、酸がきれい。中央のテンプラニーリョ2023(3800円)はバランスよい味わい。左のパソ・ロブレス プリザーブ(3800円)はジンファンデル中心のブレンド。リッチで果実感もいいワイン。
新入荷のマクプライス・マイヤーズ(McPrice Myers)。2000円台から3000円台が中心で、どれもきれいで美味しいワイン。非常にコスパ高いです。どれもお薦めです。
5年ほど前まで、日本でも大人気だったフランシスカン。その後、ブランドの移行で輸入が途絶えていましたが、久々のお目見えです。以前はナパのワインでしたが、今回はすべて広域のカリフォルニアになっています。その代わり価格はいずれも2800円とリーズナブル。ソーヴィニョン・ブラン、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨンがあり、個人的には今回は白の2種が好印象。
サンタ・ルシア・ハイランズでピュアなワインを造るモーガン。ソーヴィニョン・ブラン2018(3900円)は香り華やか。アンオークト・シャルドネ2023(5000円)はピュアでエレガント。
コブのワインは「エレガント系カリピノ/シャルの最先端 コブのワインを味わう」で詳しく紹介していますが、カリフォルニアのシャルドネやピノ・ノワールの中でもフィネスが感じられるワイン。
カモミはいまさら紹介不要な人気ワイナリーです。シャルドネ・ナパ・ヴァレー2023(3500円)はリッチでなめらかな味わい。赤はナパからカリフォルニアになり価格は2500円。バランスよくスパイス感もあります。
右のナパ1847カベルネ・ソーヴィニヨン2023(6700円)はクラシックで、凝縮感ある味わい。左のラザフォード・ロード・カベルネ・ソーヴィニヨン2023(7500円)はリッチでしなやか。
最後はナパの中堅ワイナリー「ホワイトホール・レーン」。右のシャルドネ2022はソノマのブドウを使っており、リッチな樽感とバランスがいいワイン。左のトレ・レオーニはカベルネ・ソーヴィニヨンなどのブレンド。このヴィンテージはマルベックとメルローをブレンドしています。酸がきれいで美味しい。
もう1カ月も過ぎてしまいましたが、布袋ワインズさんの試飲会から美味しかったワインを紹介します。

初お目見えのワイン「ユンヌ・ファム」のスパークリング・ワイン。シャルマ方式。ピノ・ノワール8割だけどすっきりさわやか。高級感はありませんが2200円という価格は嬉しい。

元アップルのザンダー・ソーレン氏のワイナリー。ソノマ・コーストのピノ・ノワール2022(9000円)は、果実のジューシーさが素晴らしい。

ブラックスミスのワインはコスパで裏切ることがないというのが私のこれまでの印象。このナパヴァレーのメルロー・リザーブ(5500円)もメルローらしいやわらかさと、味わいを引き締めるタンニン、複雑さを与えるハーブの風味のバランスが良く、価格以上の満足度。

フラワーズのシャルドネ・ソノマ・コースト2023(10400円)。酸のキレが抜群でバランスよく美味しいシャルドネ。

フラワーズのフラッグシップのピノ・ノワール「シー・ヴュー・リッジ」2021(16000円)。これはむちゃくちゃうまいです。赤果実の風味にきれいに伸びる酸。つややかで艶やか。フォートロス・シービューの良さが出ています。

新規輸入のワイナリー「パウンド・ケーキ(Pound Cake)」。シャルドネはブレッド・アンド・バター系の濃厚タイプ。樽がしっかり効いて蜜やバターの風味。酸もあってバランスはとれている。2500円はお買い得。ピノ・ノワールもチャーミングでスパイス感があり、この価格は安いです。

こちらも新規の「センタード(Centered)」。シャルドネ2021(5500円)はフルーツ爆弾系。やわらかくてリッチ。おいしいです。

ジェイのロゼ・スパークリング(9400円)。昔から好きなんです(値段は上がっちゃったけど)。ピノ・ノワール主体で果実味のしっかり出たスパークリング・ワイン。


ジョエル・ゴットは米国でも人気ですが、どれもコスパよく本当にはずれのないブランドです。特に良かったのはシャルドネ2021(4200円)とシャルドネ・ナパ・ヴァレー2022(7000円)。普通のシャルドネも高級感ある味わい。ナパ・ヴァレーは樽感しっかりあり、なめらかなテクスチャーが一層の高級感を出しています。
コスパではカベルネ・ソーヴィニヨン815 2022(3900円)とジンファンデル2022(3000円)が良かったです。

ナパの良心的なワイナリーというと一番に名前が挙がるだろうと思うのがトレフェッセン。セカンドのエシュコル・レッド・ワイン2022(5900円)はリッチで複雑味もあり価格以上の味わい。写真がひどくて割愛しましたが、リースリングとエシュコルのシャルドネも良かったです。

もう一つトレフェッセンからドラゴンズ・トゥース2021(9900円)。マルベックとプティ・ヴェルドが主体というユニークなワイン。以前は赤いドラゴンが描かれたラベルでしたが、ドラゴンのデザインは透かしのような形に変わりました。濃厚でパワフル、余韻の長いワイン。個人的にはすごく好きです。


こちらも定番のシャトー・モンテレーナ。ソーヴィニョン・ブラン(9800)はセミヨンもブレンドされたボルドー系の味わい。少し樽感もあります。新規輸入のセカンドワイン「スタンディング・ジャーニー(Standing Journey)」シャルドネ2023(8000円)はなめらかで酸と果実味が美味しい。シャルドネ2022(16000円)はテクスチャーとバランスがさらに良いです。
赤ではジンファンデル2021(9800円)が良かったです。エレガントでバランスの取れたジンファンデル。美味しい。

新入荷のスタック・ハウスのソーヴィニョン・ブラン2024(6600円)。近年のカリフォルニアのソーヴィニョン・ブランの高品質化は目を見張るものがありますが、これも果実感とテクスチャー良く美味しいです。ボルドー系のスタイル。

ヴァリュー系のブランドからスリー・シーヴズのピノ・ノワール2022(2200円)とキャッスル・ロックのドレサージュ・シャルドネ2019(2600円)。2000円台のピノ・ノワールは以前はチャーミングなだけのものが多かったのですが、最近はチャーミングさに少しスパイス感が加わったものが増えている印象。これも実はプティ・シラー9%とシラー7%がブレンドされていて、それがスパイス感やワインの味わいの強さになっています。純粋なピノ・ノワールの美味しさとは少し違うかもしれませんが、ワインとして美味しい。ドレサージュ・シャルドネはリッチ系でコスパ高いです。

最後はレイク・カウンティのシャノン・リッジのソーヴィニョン・ブラン2022(2900円)とカベルネ・ソーヴィニヨン2022(2900円)。レイク・カウンティはナパの北側に隣接した郡で、新たな開発の難しくなったナパを補完する存在としても重要度を増しています。ソーヴィニョン・ブランはリッチでかなり美味しい。カベルネ・ソーヴィニヨンもやや甘やか系でリッチな味わい。どちらもコスパ高いワインです。
初お目見えのワイン「ユンヌ・ファム」のスパークリング・ワイン。シャルマ方式。ピノ・ノワール8割だけどすっきりさわやか。高級感はありませんが2200円という価格は嬉しい。
元アップルのザンダー・ソーレン氏のワイナリー。ソノマ・コーストのピノ・ノワール2022(9000円)は、果実のジューシーさが素晴らしい。
ブラックスミスのワインはコスパで裏切ることがないというのが私のこれまでの印象。このナパヴァレーのメルロー・リザーブ(5500円)もメルローらしいやわらかさと、味わいを引き締めるタンニン、複雑さを与えるハーブの風味のバランスが良く、価格以上の満足度。
フラワーズのシャルドネ・ソノマ・コースト2023(10400円)。酸のキレが抜群でバランスよく美味しいシャルドネ。
フラワーズのフラッグシップのピノ・ノワール「シー・ヴュー・リッジ」2021(16000円)。これはむちゃくちゃうまいです。赤果実の風味にきれいに伸びる酸。つややかで艶やか。フォートロス・シービューの良さが出ています。
新規輸入のワイナリー「パウンド・ケーキ(Pound Cake)」。シャルドネはブレッド・アンド・バター系の濃厚タイプ。樽がしっかり効いて蜜やバターの風味。酸もあってバランスはとれている。2500円はお買い得。ピノ・ノワールもチャーミングでスパイス感があり、この価格は安いです。
こちらも新規の「センタード(Centered)」。シャルドネ2021(5500円)はフルーツ爆弾系。やわらかくてリッチ。おいしいです。
ジェイのロゼ・スパークリング(9400円)。昔から好きなんです(値段は上がっちゃったけど)。ピノ・ノワール主体で果実味のしっかり出たスパークリング・ワイン。
ジョエル・ゴットは米国でも人気ですが、どれもコスパよく本当にはずれのないブランドです。特に良かったのはシャルドネ2021(4200円)とシャルドネ・ナパ・ヴァレー2022(7000円)。普通のシャルドネも高級感ある味わい。ナパ・ヴァレーは樽感しっかりあり、なめらかなテクスチャーが一層の高級感を出しています。
コスパではカベルネ・ソーヴィニヨン815 2022(3900円)とジンファンデル2022(3000円)が良かったです。
ナパの良心的なワイナリーというと一番に名前が挙がるだろうと思うのがトレフェッセン。セカンドのエシュコル・レッド・ワイン2022(5900円)はリッチで複雑味もあり価格以上の味わい。写真がひどくて割愛しましたが、リースリングとエシュコルのシャルドネも良かったです。
もう一つトレフェッセンからドラゴンズ・トゥース2021(9900円)。マルベックとプティ・ヴェルドが主体というユニークなワイン。以前は赤いドラゴンが描かれたラベルでしたが、ドラゴンのデザインは透かしのような形に変わりました。濃厚でパワフル、余韻の長いワイン。個人的にはすごく好きです。
こちらも定番のシャトー・モンテレーナ。ソーヴィニョン・ブラン(9800)はセミヨンもブレンドされたボルドー系の味わい。少し樽感もあります。新規輸入のセカンドワイン「スタンディング・ジャーニー(Standing Journey)」シャルドネ2023(8000円)はなめらかで酸と果実味が美味しい。シャルドネ2022(16000円)はテクスチャーとバランスがさらに良いです。
赤ではジンファンデル2021(9800円)が良かったです。エレガントでバランスの取れたジンファンデル。美味しい。
新入荷のスタック・ハウスのソーヴィニョン・ブラン2024(6600円)。近年のカリフォルニアのソーヴィニョン・ブランの高品質化は目を見張るものがありますが、これも果実感とテクスチャー良く美味しいです。ボルドー系のスタイル。
ヴァリュー系のブランドからスリー・シーヴズのピノ・ノワール2022(2200円)とキャッスル・ロックのドレサージュ・シャルドネ2019(2600円)。2000円台のピノ・ノワールは以前はチャーミングなだけのものが多かったのですが、最近はチャーミングさに少しスパイス感が加わったものが増えている印象。これも実はプティ・シラー9%とシラー7%がブレンドされていて、それがスパイス感やワインの味わいの強さになっています。純粋なピノ・ノワールの美味しさとは少し違うかもしれませんが、ワインとして美味しい。ドレサージュ・シャルドネはリッチ系でコスパ高いです。
最後はレイク・カウンティのシャノン・リッジのソーヴィニョン・ブラン2022(2900円)とカベルネ・ソーヴィニヨン2022(2900円)。レイク・カウンティはナパの北側に隣接した郡で、新たな開発の難しくなったナパを補完する存在としても重要度を増しています。ソーヴィニョン・ブランはリッチでかなり美味しい。カベルネ・ソーヴィニヨンもやや甘やか系でリッチな味わい。どちらもコスパ高いワインです。
サンタ・バーバラのサンディ(Sandhi)とドメーヌ・ド・ラ・コート(Domaine de la Côte)、オレゴンのイヴニングランド(Evening Land)を共同で経営してきたラジャ・パーとサシ・ムーアマンが、別々の道を歩みだすことになりました。これら3つのワイナリーは、サシ・ムーアマンが引き続きワイン造りを行い。ラジャ・パーはSLOコーストのカンブリアにあるフェラン・ファーム(Phelan Farm)に専念します。

ラジャ・パー

サシ・ムーアマン
二人の出会いは2000年代初頭。当時マイケル・ミナのレストラン・グループ(現在はサンフランシスコを中心に世界中で30ほどのレストランを経営しています)のワイン・ディレクターだったラジャ・パーに、ストルプマンのワインメーカーだったサシ・ムーアマンが会いにいったのだそうです。二人はクラシックな昔ながらのワイン造りに魅了され、オレゴンでコント・ラフォンや著名ソムリエのラリー・ストーンらとイヴニングランドを2006年に立ち上げ、2012年からは二人による経営になりました(資本上は彼らのワイナリーはすべてテキサスのベンチャーキャピタリストが所有しているようです)。
並行して2013年にドメーヌ・ド・ラ・コートとサンディを設立、同年にはラジャ・パーがIPOB(In Pursuit of Balance)を立ち上げ、カリフォルニアのワイン業界の風雲児になってきました。
これらのワイナリーの実質的なワイン造りはこれまでもサシ・ムーアマンが担ってきました。ラジャ・パーは2017年ころから冷涼なSLOコーストの農場の一部に切り開いた畑におけるブドウ栽培に注力するようになりました。このフェラン・ファームにおけるラジャ・パーの肩書は「ファーマー」になっています。
二人のワイナリーではシャルドネとピノ・ノワールを作っていますが、フェラン・ファームでは元ものシャルドネとピノ・ノワールを接ぎ木によってフランスのジュラやサヴォワ地区原産の15種類のブドウを植え替えました。植えた品種はモンデュース(Mondeuse)、サヴァニャン・ヴェール(Savagnin Vert)、サヴァニャン・ジョーヌ(Savganin Jaune)、プルサール(Poulsard)、アルテス(Altesse)、トゥルソー(Trousseau)、ガメイ・ノワール(Gamay Noir)など。
不耕起の有機栽培で、醸造時にはSO2不使用など、自然派なワイン造りを行っています。
参考:ラジャ・パーの新プロジェクト、ユニークなワインを飲んでみた
コロナ禍で、ラジャ・パーはカンブリアに移住し、実質的には既にパートナーシップはなくなっていました。今回、ラジャ・パーは「ただブドウを育てたいんです。シンプルな暮らし、静かな暮らしがしたいんです」と語っており、今後もフェラン・ファームに注力するものと思われます。

ラジャ・パー

サシ・ムーアマン
二人の出会いは2000年代初頭。当時マイケル・ミナのレストラン・グループ(現在はサンフランシスコを中心に世界中で30ほどのレストランを経営しています)のワイン・ディレクターだったラジャ・パーに、ストルプマンのワインメーカーだったサシ・ムーアマンが会いにいったのだそうです。二人はクラシックな昔ながらのワイン造りに魅了され、オレゴンでコント・ラフォンや著名ソムリエのラリー・ストーンらとイヴニングランドを2006年に立ち上げ、2012年からは二人による経営になりました(資本上は彼らのワイナリーはすべてテキサスのベンチャーキャピタリストが所有しているようです)。
並行して2013年にドメーヌ・ド・ラ・コートとサンディを設立、同年にはラジャ・パーがIPOB(In Pursuit of Balance)を立ち上げ、カリフォルニアのワイン業界の風雲児になってきました。
これらのワイナリーの実質的なワイン造りはこれまでもサシ・ムーアマンが担ってきました。ラジャ・パーは2017年ころから冷涼なSLOコーストの農場の一部に切り開いた畑におけるブドウ栽培に注力するようになりました。このフェラン・ファームにおけるラジャ・パーの肩書は「ファーマー」になっています。
二人のワイナリーではシャルドネとピノ・ノワールを作っていますが、フェラン・ファームでは元ものシャルドネとピノ・ノワールを接ぎ木によってフランスのジュラやサヴォワ地区原産の15種類のブドウを植え替えました。植えた品種はモンデュース(Mondeuse)、サヴァニャン・ヴェール(Savagnin Vert)、サヴァニャン・ジョーヌ(Savganin Jaune)、プルサール(Poulsard)、アルテス(Altesse)、トゥルソー(Trousseau)、ガメイ・ノワール(Gamay Noir)など。
不耕起の有機栽培で、醸造時にはSO2不使用など、自然派なワイン造りを行っています。
参考:ラジャ・パーの新プロジェクト、ユニークなワインを飲んでみた
コロナ禍で、ラジャ・パーはカンブリアに移住し、実質的には既にパートナーシップはなくなっていました。今回、ラジャ・パーは「ただブドウを育てたいんです。シンプルな暮らし、静かな暮らしがしたいんです」と語っており、今後もフェラン・ファームに注力するものと思われます。
半月ほど前のニュースですが、ナパのチャールズ・クリュッグで、アンジェリーナ・モンダヴィがワイン造りの総責任者に就任しました。アンジェリーナは、ロバート・モンダヴィの弟ピーターの孫にあたり、米国に移住してきたチェザーレ・モンダヴィから数えると第4世代ということになります。これまでもコンサルティング・ワインメーカーとして一部のワインに携わってきましたが、今回ポートフォリオ全体に責任を持つことになりました。女性のワイン造り責任者はチャールズ・クリュッグとしては初めてです。
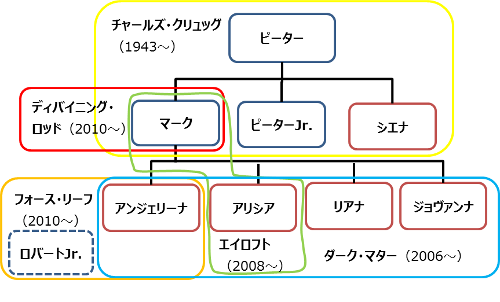

アンジェリーナはオーストラリアのアデレード大学でワイン造りの修士号を取得しており、カリフォルニアだけでなく、オーストラリアやアルゼンチンでもワインを造ってきました。35ヴィンテージの経験があるといいます。
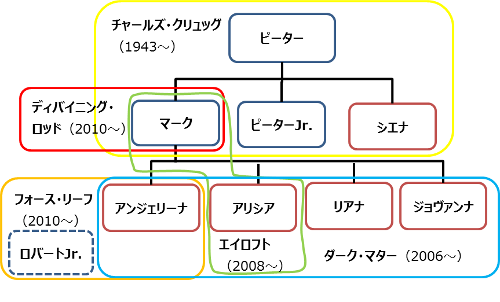

アンジェリーナはオーストラリアのアデレード大学でワイン造りの修士号を取得しており、カリフォルニアだけでなく、オーストラリアやアルゼンチンでもワインを造ってきました。35ヴィンテージの経験があるといいます。
二十数年来の友人であり、ナパヴァレー・ヴィントナーズのコーチや、さまざまなセミナーでの通訳などでお世話になっている山本香奈さんのお店「イルドコリンヌ」が8周年ということでパーティに参加してきました。
イルドコリンヌのパーティでは定番のたこ焼き(香奈さんのご主人は関西出身なので)食べ放題のほか、ワインは飲み放題(一部の高額ワインはチケット制)。大盤振る舞いのイベントです。
私が参加した28日は、カリフォルニア&ナパヴァレーワイン・アンバサダーの山本麻衣花さんのミニセミナーもありました。さらにはアンダーズ東京の森覚ソムリエも「たこ焼きを焼くために参加」。ソムリエとしての仕事は一切せずに、たこ焼きを焼かれていました(笑)。しかも別の用事があるとのことで終わったあとも急いで帰られて、本当にたこ焼きを焼くだけでした。
私は普通に客として参加していたのですが、山本麻衣花さんにお願いされて急遽ミニセミナー(というかこの日のワインの紹介)を一緒にさせていただきました。
もちろん準備も何もしていなかったので、かなり適当におしゃべりしましたが、しゃべりすぎたようで最後は巻きが入ってしまいました。すみません。
先日終了したキャップストーンの同級生も何人か参加し、楽しく過ごさせていただきました。
イルドコリンヌ、西馬込というちょっとマイナーな場所にありますが、ワイン会なども落ち着いた雰囲気の中でできて料理も美味しく、いい店です。今後もがんばってください。
オレゴンのチュハレム・マウンテンズ(Chehalem Mountains)AVAにあるアデルスハイム(Adelsheim)から創設者のデイビッド・アデルスハイムさんが来日し、セミナーを開催しました。アデルスハイムは国内輸入が途絶えていて、オルカ・インターナショナルが輸入を開始したタイミングでの来日です。
オレゴンのワイン造りの歴史は意外と短く、現在の主要産地であるウィラメット・ヴァレーでピノ・ノワールの栽培が始まったのは1965年と60年前になります。アデルスハイムは1971年に土地を購入、72年から植樹をして78年が商用ワイナリーとして最初のヴィンテージとなりました。オレゴンでは初期からのワイナリーの一つであり、後述するように特にシャルドネ栽培では歴史的な功績があります。ウィラメット・ヴァレーAVAの設立にも大きく貢献しており、まさにオレゴンワイン業界の重鎮です。
と、すごい方なのですが、ご本人はいたって控えめで自分の功績についても、ひけらかすようなところは1ミリもなく。私からしたら、もっとアピールしたらいいのにと思ってしまうほどなのですが、そのあたりも含めてオレゴンらしいなと感じました。
設立後、夫妻でワイナリーを所有していましたが、1994年にジャックとリンのロアッカー夫妻との共同所有になり、2017年にロアッカー夫妻の単独所有、そして夫の死によって現在はリン・ロアッカーさんがオーナーとなっています。デイビッド・アデルスハイムさんは創設者という位置付けでワイナリーに残っています。
アデルスハイムの生産量は3万5000ケース。およそ4分の3はピノ・ノワールで、シャルドネが2割弱。残りはロゼやスパークリング、わずかにシラーやピノ・ブランも作っています。

アデルスハイムはウィラメット・ヴァレーの中のシュヘイラム・マウンテンズAVAに8つほどの畑を持っています。
シュヘイラム・マウンテンズはその名の通り北西方向から南東方向に山脈になっています。AVAの中にはさらに2つのAVAがあります。北側の上の地図で黄緑色のところはローレルウッド・ディストリクトで、ここは玄武岩の上に、コロンビア・ヴァレーの方から砂や粘土やシルトが風で運ばれてきた「ラス土壌」と呼ばれる土壌がかぶさっています。比較的保水力のある土壌です。もう一つ南西のコーナーにあるのがリボン・リッジAVAでここはほぼ海洋性の堆積性土壌。丘の中腹で安定した気温が特徴です。
シュヘイラム・マウンテンズのこれら二つのAVAに属さないところは火山性の玄武岩土壌が多くなっています。アデルスハイムは両サブAVAおよび玄武岩土壌のところにも畑を持っています。
アデルスハイムの畑はLIVEというオレゴンのサスティナブル認証およびサーモン・セーフという認証を取っています。2017年からは除草剤不使用です。
前述のようにアデルスハイムはピノ・ノワールとシャルドネを育てています。
ピノ・ノワールはオレゴンの生産量の約3分の2を占めており、オレゴン全体の最重要品種です。一方、白ワインでは現在ピノ・グリが13%でシャルドネが7%とピノ・グリが少しリードしています。一般的にはピノ・ノワールと組み合わせるといったらシャルドネをまずイメージする人が多いでしょうから、少し意外に思われる方もいると思います。実は、これでもシャルドネはだいぶ増えてきており、以前はもっとピノ・グリの方が多かったのです。
オレゴンにおけるワイン産業が発展し始めた1960年代から70年代、オレゴンではあまりいいシャルドネができませんでした。それがピノ・グリの後塵を拝した理由なのですが、なぜオレゴンでいいシャルドネができなかったかというと、当時植えられていたシャルドネはカリフォルニアから来たクローンで、それがオレゴンの気候にあまり合っていなかったのでした。そこでもっと品質のいいクローンをブルゴーニュから取り寄せようと骨を折ったのがデイビッド・アデルスハイムさんなのです。その甲斐あって、シャルドネの生産は徐々に増えただけでなく品質も上がっています。今年はオレゴンのシャルドネにDecanter誌が初めて100点を付けたことでも話題になりました。
デイビッドさんに、クローンの件について質問したところ、上記のような説明をいただいた後「重要な一歩だったけどゴールではない。あるひとつのクローンが最適ということではない」と、これまた謙虚な答えをいただきました。
さて、試飲に移ります。現在輸入されているのはシャルドネとピノ・ノワール。それぞれ広域AVA(ウィラメット・ヴァレー)、シュヘイラム・マウンテンズAVAの「ブレイキング・グラウンド」、単一畑と3レベルになっています。
Willamette Valley Chardonnay 2022(6160円、税込み希望小売価格、以下同)
フレッシュで酸の高さが印象的ですが、柑橘に白桃のようなまったりした感じもあり、バランスよく仕上がっています。
Chahalem Mountains Breaking Ground Chardonnay 2021(9350円)
55%玄武岩、28%堆積土壌、17%レス土壌の畑から作ったシュヘイラム・マウンテンズAVAらしさを表したシャルドネです。
酸は高いですが、フレッシュで鋭い酸というよりも丸みのあるテクスチャーを感じます。かんきつに白桃、麦わらやぬれた石のニュアンス。ウィラメット・ヴァレーと比べると複雑さが格段に増しています。
Ribbon Springs Vineyard Chardonnay 2021(11880円)
堆積性土壌のリボン・リッジの畑です。ピノ・グリからシャルドネに接ぎ木で替えてみたところ非常にいいブドウができたとのこと。
緊張感ある味わい。シュヘイラム・マウンテンズよりもテクスチャーの滑らかさをより感じます。青リンゴやレモン、ミネラル感ある味わい。今飲むより、数年熟成した方が良くなりそうです。
ピノ・ノワールに移ります。
Willamette Valley Pinot Noir 2022(8800円)
アデルスハイムの生産量の半数を占める主要ワインです。
フレッシュでジューシー。なめらかなテクスチャーにレッド・チェリーやフランボワーズの赤果実ときれいな酸。バランスよく美味しい。
Chahalem Mountains Breaking Ground Pinot Noir 2021(11880円)
47%玄武岩、26%海洋性堆積土壌、27%レス土壌という比率です。
ウィラメット・ヴァレーより滑らかなテクスチャー、酸高く引き締まった味わい。赤果実に加えて少し黒果実の味わいが入りボディに厚みがあります。
単一畑は2種。
Ribbon Springs Vineyard Pinot Noir 2021(18260円)
華やかで酸豊か、柔らかく優しい味わい。
Quarter Mile Lane Vineyard Pinot Noir 2022(25300円)
1972年に植樹された一番古い畑。火山性土壌。
リボン・スプリングスよりもパワフルで緊張感ある味わい。複雑で上品。素晴らしい


オレゴンのワイン造りの歴史は意外と短く、現在の主要産地であるウィラメット・ヴァレーでピノ・ノワールの栽培が始まったのは1965年と60年前になります。アデルスハイムは1971年に土地を購入、72年から植樹をして78年が商用ワイナリーとして最初のヴィンテージとなりました。オレゴンでは初期からのワイナリーの一つであり、後述するように特にシャルドネ栽培では歴史的な功績があります。ウィラメット・ヴァレーAVAの設立にも大きく貢献しており、まさにオレゴンワイン業界の重鎮です。
と、すごい方なのですが、ご本人はいたって控えめで自分の功績についても、ひけらかすようなところは1ミリもなく。私からしたら、もっとアピールしたらいいのにと思ってしまうほどなのですが、そのあたりも含めてオレゴンらしいなと感じました。
設立後、夫妻でワイナリーを所有していましたが、1994年にジャックとリンのロアッカー夫妻との共同所有になり、2017年にロアッカー夫妻の単独所有、そして夫の死によって現在はリン・ロアッカーさんがオーナーとなっています。デイビッド・アデルスハイムさんは創設者という位置付けでワイナリーに残っています。
アデルスハイムの生産量は3万5000ケース。およそ4分の3はピノ・ノワールで、シャルドネが2割弱。残りはロゼやスパークリング、わずかにシラーやピノ・ブランも作っています。

アデルスハイムはウィラメット・ヴァレーの中のシュヘイラム・マウンテンズAVAに8つほどの畑を持っています。
シュヘイラム・マウンテンズはその名の通り北西方向から南東方向に山脈になっています。AVAの中にはさらに2つのAVAがあります。北側の上の地図で黄緑色のところはローレルウッド・ディストリクトで、ここは玄武岩の上に、コロンビア・ヴァレーの方から砂や粘土やシルトが風で運ばれてきた「ラス土壌」と呼ばれる土壌がかぶさっています。比較的保水力のある土壌です。もう一つ南西のコーナーにあるのがリボン・リッジAVAでここはほぼ海洋性の堆積性土壌。丘の中腹で安定した気温が特徴です。
シュヘイラム・マウンテンズのこれら二つのAVAに属さないところは火山性の玄武岩土壌が多くなっています。アデルスハイムは両サブAVAおよび玄武岩土壌のところにも畑を持っています。
アデルスハイムの畑はLIVEというオレゴンのサスティナブル認証およびサーモン・セーフという認証を取っています。2017年からは除草剤不使用です。
前述のようにアデルスハイムはピノ・ノワールとシャルドネを育てています。
ピノ・ノワールはオレゴンの生産量の約3分の2を占めており、オレゴン全体の最重要品種です。一方、白ワインでは現在ピノ・グリが13%でシャルドネが7%とピノ・グリが少しリードしています。一般的にはピノ・ノワールと組み合わせるといったらシャルドネをまずイメージする人が多いでしょうから、少し意外に思われる方もいると思います。実は、これでもシャルドネはだいぶ増えてきており、以前はもっとピノ・グリの方が多かったのです。
オレゴンにおけるワイン産業が発展し始めた1960年代から70年代、オレゴンではあまりいいシャルドネができませんでした。それがピノ・グリの後塵を拝した理由なのですが、なぜオレゴンでいいシャルドネができなかったかというと、当時植えられていたシャルドネはカリフォルニアから来たクローンで、それがオレゴンの気候にあまり合っていなかったのでした。そこでもっと品質のいいクローンをブルゴーニュから取り寄せようと骨を折ったのがデイビッド・アデルスハイムさんなのです。その甲斐あって、シャルドネの生産は徐々に増えただけでなく品質も上がっています。今年はオレゴンのシャルドネにDecanter誌が初めて100点を付けたことでも話題になりました。
デイビッドさんに、クローンの件について質問したところ、上記のような説明をいただいた後「重要な一歩だったけどゴールではない。あるひとつのクローンが最適ということではない」と、これまた謙虚な答えをいただきました。
さて、試飲に移ります。現在輸入されているのはシャルドネとピノ・ノワール。それぞれ広域AVA(ウィラメット・ヴァレー)、シュヘイラム・マウンテンズAVAの「ブレイキング・グラウンド」、単一畑と3レベルになっています。
Willamette Valley Chardonnay 2022(6160円、税込み希望小売価格、以下同)
フレッシュで酸の高さが印象的ですが、柑橘に白桃のようなまったりした感じもあり、バランスよく仕上がっています。
Chahalem Mountains Breaking Ground Chardonnay 2021(9350円)
55%玄武岩、28%堆積土壌、17%レス土壌の畑から作ったシュヘイラム・マウンテンズAVAらしさを表したシャルドネです。
酸は高いですが、フレッシュで鋭い酸というよりも丸みのあるテクスチャーを感じます。かんきつに白桃、麦わらやぬれた石のニュアンス。ウィラメット・ヴァレーと比べると複雑さが格段に増しています。
Ribbon Springs Vineyard Chardonnay 2021(11880円)
堆積性土壌のリボン・リッジの畑です。ピノ・グリからシャルドネに接ぎ木で替えてみたところ非常にいいブドウができたとのこと。
緊張感ある味わい。シュヘイラム・マウンテンズよりもテクスチャーの滑らかさをより感じます。青リンゴやレモン、ミネラル感ある味わい。今飲むより、数年熟成した方が良くなりそうです。
ピノ・ノワールに移ります。
Willamette Valley Pinot Noir 2022(8800円)
アデルスハイムの生産量の半数を占める主要ワインです。
フレッシュでジューシー。なめらかなテクスチャーにレッド・チェリーやフランボワーズの赤果実ときれいな酸。バランスよく美味しい。
Chahalem Mountains Breaking Ground Pinot Noir 2021(11880円)
47%玄武岩、26%海洋性堆積土壌、27%レス土壌という比率です。
ウィラメット・ヴァレーより滑らかなテクスチャー、酸高く引き締まった味わい。赤果実に加えて少し黒果実の味わいが入りボディに厚みがあります。
単一畑は2種。
Ribbon Springs Vineyard Pinot Noir 2021(18260円)
華やかで酸豊か、柔らかく優しい味わい。
Quarter Mile Lane Vineyard Pinot Noir 2022(25300円)
1972年に植樹された一番古い畑。火山性土壌。
リボン・スプリングスよりもパワフルで緊張感ある味わい。複雑で上品。素晴らしい
ソノマのロシアンリバー・ヴァレーにあるエイコーン(Acorn)・ワイナリーが売却されました。エイコーンはアレグリア(Alegría)・ヴィンヤードという1890年代に植樹された古木のジンファンデルの畑を持っています。アレグリアはかつてはリッジやローゼンブラムがワインを造っていたこともありました。
これまでのオーナーのナックバウアー夫妻が畑を買ったのは1990年のこと。最初は栽培だけをしていましたが、1994年にエイコーンを設立してワイン造りを始めました。ただ、老齢化のため近年は売却を模索していたようです。

ただ、手間がかかり、収量は少ないのにワインの価格はリーズナブルなレベルの古木のジンファンデルはビジネス的には難しい位置付けです。事業継承には苦労するワイナリーが少なくありません昨年は似た状況だったカーライルが売却をせずに廃業を選びましたし、それ以前にはラジエ・メレディスが無償でワイナリーを売却するといったこともありました。
今回、ワイナリーを買ったのはメリッサ・モホルト・シーベルト。近隣のエンシャント・オーク・セラーズ(Ancient Oak Cellars)のオーナーです。
実はナックバウアー夫妻はワイナリーを売却したかったものの、畑は手放したくないという事情がありました。畑のところに自宅があるというのも理由の一つです。そこで、メリッサは夫妻からワイナリーのブランドだけを購入し、夫妻からブドウを買ってワインを造るという形でエイコーンのワインを続けることにしたのです。こういった形での継承は今まで意外になかったようでユニークなスタイルのようです。売却価格は明らかにしていません。
メリッサはエイコーンとエンシャント・オークの両ブランドで続けていくことになります。

左が前オーナーのビル・ナックバウアー、右がメリッサ・モホルト・シーベルト。
これまでのオーナーのナックバウアー夫妻が畑を買ったのは1990年のこと。最初は栽培だけをしていましたが、1994年にエイコーンを設立してワイン造りを始めました。ただ、老齢化のため近年は売却を模索していたようです。

ただ、手間がかかり、収量は少ないのにワインの価格はリーズナブルなレベルの古木のジンファンデルはビジネス的には難しい位置付けです。事業継承には苦労するワイナリーが少なくありません昨年は似た状況だったカーライルが売却をせずに廃業を選びましたし、それ以前にはラジエ・メレディスが無償でワイナリーを売却するといったこともありました。
今回、ワイナリーを買ったのはメリッサ・モホルト・シーベルト。近隣のエンシャント・オーク・セラーズ(Ancient Oak Cellars)のオーナーです。
実はナックバウアー夫妻はワイナリーを売却したかったものの、畑は手放したくないという事情がありました。畑のところに自宅があるというのも理由の一つです。そこで、メリッサは夫妻からワイナリーのブランドだけを購入し、夫妻からブドウを買ってワインを造るという形でエイコーンのワインを続けることにしたのです。こういった形での継承は今まで意外になかったようでユニークなスタイルのようです。売却価格は明らかにしていません。
メリッサはエイコーンとエンシャント・オークの両ブランドで続けていくことになります。

左が前オーナーのビル・ナックバウアー、右がメリッサ・モホルト・シーベルト。
アカデミー・デュ・ヴァン2025年秋冬講座で11月1日開講の「カリフォルニア〜品種で産地を探検しよう」。実はまだ開講が決まっておりません。このまま不催行になるのはかなり悲しいので、講座の狙いと魅力、私の思いを書いておきたいと思います。
青山校 カリフォルニア〜品種で産地を探検しよう | ワイン初心者からソムリエ資格取得まで - ワインスクール アカデミー・デュ・ヴァン
これまでカリフォルニア全体を地域ごとに学ぶ講座や、ナパやソノマといった地域を深堀するものなど、地域を中心にした講座を比較的多くやってきました。また、昨年はシャルドネに特化して地域ごとにワインを見ていくという講座もありました。
一回に一つの地域というのは教えるのは楽ですが、地域間の違いというのは少し分かりにくいような気がして新しい試みとして出しているのが今回の講座です。
1回に一つの品種を取り上げて、その品種についてカリフォルニアの各地のワインを試飲して、テロワールによる違いや、逆に共通するものを感じてほしいという狙いです。
マニア向けの講座かというとそうではありません。むしろ、ワイン・エキスパートを今年受験しています、とかSTEP-1を取りましたといった人たちが受けてくれたら嬉しいです。
ワイン・エキスパートを受験している人は、今まさにテイスティングの練習をしていると思いますが、例えばカリフォルニアのシャルドネだったら、樽がしっかり効いていて色が濃く、酸がやや低いといった特徴から導き出すように教わるだろうと思います。試験的にはそれで間違っていないですが、そういった特徴があるのは、試験に出題されるような2000円台とかの価格帯の話であって、カリフォルニア全体が同じ特徴を持つわけではありません。一つの州で日本やフランスよりも広く、気候のバリエーションも大きいです。フランスワインを語るときにボルドーとブルゴーニュを同じ特徴で語る人はいないと思いますが、同じようにカリフォルニアも一つの特徴では語れないのです。
一方で、ニューワールドではEUのような品種の規制はありませんから、いろいろな品種がいろいろな土地で個性を持って作られることになります。それらを飲むことで、カリフォルニアの多様性を感じてほしいのです。
また、カリフォルニアに詳しい人にとっても、ワインをブラインドで試飲して地域を当てるというのはそんなに簡単なことではないですし、当たれば満足感も高い、またそれを考える過程だけでも非常に勉強になると思います。
最後にもう一つ。
いろいろ講座の内容について書きましたが、結局は講座の魅力の8割は試飲するワインが美味しいかどうかだと思っています。多分私の話は半年後には1割も覚えていないかもしれませんが、それでもワインが美味しくて満足してもらえれば大成功です。なので、限られた予算の中でどれだけ講座の内容に即し、そして美味しいワインを出せるかに一番力を入れています。美味しいカリフォルニアワインを知って、それを今後の購入などに生かしてもらえたら教師冥利に尽きます。
なので、初めの方を読んでそんなめんどくさいことは知らんと思った人でも、美味しいワインを飲むためと思って受講いただけたら嬉しいです。
講座内容
第1回ソーヴィニヨン・ブラン
第2回ジンファンデル
第3回シャルドネ
第4回シラー
第5回ピノ・ノワール
第6回カベルネ・ソーヴィニヨン
青山校 カリフォルニア〜品種で産地を探検しよう | ワイン初心者からソムリエ資格取得まで - ワインスクール アカデミー・デュ・ヴァン
申し込みお待ちしております。
青山校 カリフォルニア〜品種で産地を探検しよう | ワイン初心者からソムリエ資格取得まで - ワインスクール アカデミー・デュ・ヴァン
これまでカリフォルニア全体を地域ごとに学ぶ講座や、ナパやソノマといった地域を深堀するものなど、地域を中心にした講座を比較的多くやってきました。また、昨年はシャルドネに特化して地域ごとにワインを見ていくという講座もありました。
一回に一つの地域というのは教えるのは楽ですが、地域間の違いというのは少し分かりにくいような気がして新しい試みとして出しているのが今回の講座です。
1回に一つの品種を取り上げて、その品種についてカリフォルニアの各地のワインを試飲して、テロワールによる違いや、逆に共通するものを感じてほしいという狙いです。
マニア向けの講座かというとそうではありません。むしろ、ワイン・エキスパートを今年受験しています、とかSTEP-1を取りましたといった人たちが受けてくれたら嬉しいです。
ワイン・エキスパートを受験している人は、今まさにテイスティングの練習をしていると思いますが、例えばカリフォルニアのシャルドネだったら、樽がしっかり効いていて色が濃く、酸がやや低いといった特徴から導き出すように教わるだろうと思います。試験的にはそれで間違っていないですが、そういった特徴があるのは、試験に出題されるような2000円台とかの価格帯の話であって、カリフォルニア全体が同じ特徴を持つわけではありません。一つの州で日本やフランスよりも広く、気候のバリエーションも大きいです。フランスワインを語るときにボルドーとブルゴーニュを同じ特徴で語る人はいないと思いますが、同じようにカリフォルニアも一つの特徴では語れないのです。
一方で、ニューワールドではEUのような品種の規制はありませんから、いろいろな品種がいろいろな土地で個性を持って作られることになります。それらを飲むことで、カリフォルニアの多様性を感じてほしいのです。
また、カリフォルニアに詳しい人にとっても、ワインをブラインドで試飲して地域を当てるというのはそんなに簡単なことではないですし、当たれば満足感も高い、またそれを考える過程だけでも非常に勉強になると思います。
最後にもう一つ。
いろいろ講座の内容について書きましたが、結局は講座の魅力の8割は試飲するワインが美味しいかどうかだと思っています。多分私の話は半年後には1割も覚えていないかもしれませんが、それでもワインが美味しくて満足してもらえれば大成功です。なので、限られた予算の中でどれだけ講座の内容に即し、そして美味しいワインを出せるかに一番力を入れています。美味しいカリフォルニアワインを知って、それを今後の購入などに生かしてもらえたら教師冥利に尽きます。
なので、初めの方を読んでそんなめんどくさいことは知らんと思った人でも、美味しいワインを飲むためと思って受講いただけたら嬉しいです。
講座内容
第1回ソーヴィニヨン・ブラン
第2回ジンファンデル
第3回シャルドネ
第4回シラー
第5回ピノ・ノワール
第6回カベルネ・ソーヴィニヨン
青山校 カリフォルニア〜品種で産地を探検しよう | ワイン初心者からソムリエ資格取得まで - ワインスクール アカデミー・デュ・ヴァン
申し込みお待ちしております。
パソ・ロブレスで高級シラーなどを作るブッカー(Booker)が、ワイン造りのプロセスでCCOFオーガニックの認証を得ました。

Senior Winemaker Molly Lonborg
ブッカーは既に、栽培でCCOF認証を取っており、再生可能有機認証のROCも取得しています。これでワイン造り全般にわたってオーガニックの認証を得たことになります。
ワイン造りでオーガニック認証を得るためには、使用するすべての原材料がオーガニック認証を受けている必要があります。化学薬品、防腐剤、SO2の添加は認められません。小麦などグルテンを含む製品も使われないためグルテンフリーであり、実質的にヴィーガンにも対応することになります。
また、これらが実際に守られていることを検査を受けて証明しなければならず、それも毎年必要だとのことです。
ワイン造りではSO2無添加というところが大きなネックになるため、栽培でオーガニック認証を取るところは増えても醸造で取るところはほとんどなかったのが現状です。
勇気ある一歩を踏み出したブッカーの今後に注目です。

Senior Winemaker Molly Lonborg
ブッカーは既に、栽培でCCOF認証を取っており、再生可能有機認証のROCも取得しています。これでワイン造り全般にわたってオーガニックの認証を得たことになります。
ワイン造りでオーガニック認証を得るためには、使用するすべての原材料がオーガニック認証を受けている必要があります。化学薬品、防腐剤、SO2の添加は認められません。小麦などグルテンを含む製品も使われないためグルテンフリーであり、実質的にヴィーガンにも対応することになります。
また、これらが実際に守られていることを検査を受けて証明しなければならず、それも毎年必要だとのことです。
ワイン造りではSO2無添加というところが大きなネックになるため、栽培でオーガニック認証を取るところは増えても醸造で取るところはほとんどなかったのが現状です。
勇気ある一歩を踏み出したブッカーの今後に注目です。
ナパのハーラン・ファミリーには、大きく3つの柱のブランドがあります。その中でも特殊な立ち位置にあるのがボンド(Bond)です。残りの二つ、ハーラン・エステートとプロモントリーはどちらも自社の単一畑から、その名のワインを生み出しています。それに対してボンドは、自社畑ではなく5つの契約畑からカベルネ・ソーヴィニョン100%の5つのワインを造っています。
今回は、ボンドのマックス・カースト支配人が来日し、マスタークラスで五つの畑のワイン、およびセカンドのメイトリアーク(Matriarch)の2021年を水平テイスティングしました。
ハーラン・エステートおよびボンドの誕生は、ハーランの創設者であるビル・ハーランと、カリフォルニアワインの父と言われるロバート・モンダヴィとの結びつきによるものです。1980年代に、ロバート・モンダヴィは世界最高の産地を勉強するという目的でビル・ハーランらとボルドーとブルゴーニュにツアーに行きました。ボルドーでは1級シャトーをめぐり、100年以上同じ家族が経営していることに感銘を受けて、ビル・ハーランはハーラン・エステートのコンセプトである家族経営で200年かけて超一流ワイナリーを築き上げるという「200年プラン」を書きました。現在はその41年目にあたります。
一方、ブルゴーニュではグラン・クリュの畑を試飲して、同じ品種なのにテロワールによって味が異なることや、斜面の中腹の畑が最高のブドウを生み出すことを学びました。当時のナパの畑は、いわゆるヴァレーフロアの平地の畑がほとんどで、それ以外には山の上にいくつかの畑があるくらいでした。そこで、斜面の畑をナパ中から探し回って「グラン・クリュ」となる畑を見つけたのがボンドです。つまり、ボルドーのコンセプトからハーラン・エステートが生まれ、ブルゴーニュのコンセプトからボンドが生まれたのです。
ちなみに、以前ビル・ハーランから伺った話ではボンドの畑を選ぶために70もの畑と契約してワインを実際に造ってみて、最終的に使う畑を決めていったそうです。ボンドで実際にワインを造り始めるまで12年もかけて畑を選んでいったといいます。なお、Bondという名前はビル・ハーランの母親の旧姓です(初耳でした)。セカンドのMatriarch(メイトリアーク)は女主人という意味です。

こうして1996年に最初に選ばれた畑がVecina(ヴァシーナ)とMelbury(メルバリー)でした。(最初のヴィンテージは1999年)。その後、2001年のヴィンテージからSt. Eden(セント・エデン)、2003年からPluribus(プルリバス)、2006年からQuella(クエラ)が加わっています。計画では最終的に6つのグラン・クリュを選ぶとしていて、マックス・カースト支配人によると、残り一つがいつになるかはまだ分からないとのこと。
実は1年前に現オーナーのウィル・ハーランが来日したときに、ボンドの6つめの畑について聞いてみたことがあるのですが、そのときは「もうじき(soon)」と言っていました。それをマックスさんにぶつけてみたところ「ウィルはその質問にはもうじきと答えるんだけど、そのもうじきが、1年なのか20年なのかは分からないんだよね」ということでした。マックスさんやワインメーカーのコーリー・エンプティングはまだしばらくかかりそうという印象を持っているそうですが、本当にすぐに決まる可能性がないとも言えないようです。前述のように、Bondを立ち上げるときにも10年以上のリサーチ期間があったわけなので、ハーラン家にとっては10年くらいは「もうじき」なのかもしれません。
前述のように、ボンドの畑は自社のものではなく契約畑ですが、栽培はハーラン自身で行っています。ボンドの畑の多くはハーランだけが使用していますが、ヴァシーナはオークヴィルにあるヴァイン・ヒル・ランチ(Vine Hill Ranch)の畑。ハーランはここの一番山寄りのブロックを専用で使っており、ここも自社で栽培しています。
ハーラン/ボンドの品質を支えているのが栽培チームです。栽培は外部の会社を使うワイナリーも多い中で、ハーランの栽培チームは社員として働いています。ヴァインマスターというプログラムがあり、試験を受けて4段階昇進していく仕組みになっています。最後の試験に通ると、一人当たり1.5ヘクタールほどのブロックをすべて責任を持って管理することになります。その知識は、担当のブロックの樹の性質や状況などをすべて説明できるレベルで、隣の樹との違いや、冬季のブドウを見てもどこにブドウの房ができるかを言えるとのこと。まるで盆栽のように樹の手入れをするとも言われています。ファーミングというよりガーデニングだともいいます。こういったことから、マックス・カーストさんはテロワールという言葉を人と土地とのコネクションだと考えているそうです。
写真が緑がかっているのは撮影した角度の関係です。
ボンドの醸造設備はオークヴィルのハーラン・エステートの近辺の山の中にあります。ファンシーさやゴージャスさはなく、醸造に徹した質実剛健なワイナリーです。どのワインにも共通するプログラムとしては、天然酵母で発酵し、28カ月新樽と旧樽を合わせて熟成、ボトル詰めしてからさらに1年間熟成させて出荷します。収穫から出荷まで4年というのはナパの標準より1年程度長くなっています。ただ栽培と同じように、細かいトリートメントについては畑やヴィンテージなどブドウの状態で調整をしています。
今回は2021年のワインですが、近年のヴィンテージをおさらいすると、2019年は冬にたっぷり雨が降った年。気温もマイルドで、前年の2018年と並んで非常にいいヴィンテージと言われています。2020年は9月の山火事の影響が大きく、赤ワインを造らなかったワイナリーもたくさんあります。ただ、比較的高温が早くから続いたことから、ハーランやボンドでは山火事の前に収穫が済んでいました。結果として非常にエレガントなスタイルになりました。そして2021年は干ばつの2年目で冬の間に200ミリ程度しか雨が降りませんでした(カリフォルニアは冬が雨季で、大半の雨は冬に降ります)。そのため、果実が小さく皮が厚くなり、パワフルなワインになったそうです。
ボンドで特徴的なのはそのラベルです。ラベルには畑の名前と、畑をイメージした色が塗られた円が描かれています。それ以外はどのワインも同じで、ブドウの品種名や畑のAVAは書かれておらず、Napa Valley Red Wineとだけ記されています。ボンドのワインはすべてカベルネ・ソーヴィニヨン100%であり、いちいちそれを記す必要はないということだそうです。
テイスティングに移ります。
最初はセカンドワインのメイトリアーク(Matriarch)です。メイトリアークは、単一畑のワインを選んだ後に残ったワインをブレンドしたもので、単一畑ものと比べると、果実味が強く、長期熟成よりも若いうちに飲むスタイルのワインになります。
赤い果実にブルーベリー、リコリスに、少し土っぽいニュアンス。濃縮感強く、ストラクチャーしっかりで余韻の長さを感じます。ストラクチャーの強さはヴィンテージの特徴によるものでしょうか。ファーストとは違うとはいえ、非常にレベルの高いカベルネ・ソーヴィニヨンです。
クエラに進みます。クエラはセント・ヘレナの東方、ナパヴァレーを見下ろす南西向きの急斜面にある畑です。ドイツ語で「分水嶺」の意味があり、かつてはここで水が湧いていたとのこと。五つの畑の中では一番温暖ですが、できるワインはエレガントになります。表土はトゥファと呼ばれる火山灰の固まったもので、下の方は過去の川底で石がゴロゴロしています。
仕立てはダブルコルドンのVSPで、植樹した1990年代に流行っていたスタイルです。
赤い果実から青系果実の風味、タンニンはかなり強いですが非常になめらか、酸高くミネラル感があります。マックス・カーストさんは「筋肉質のバレーダンサー」とその酒質を表していました。
メルバリーはクエラ同様、ナパの東側の丘陵地です。直線距離では2kmくらいですが、10kmくらいドライブする必要があります。畑はレイク・ヘネシーの北側で、斜面の向きは東から南東になります。土壌は粘土質の岩盤に堆積土壌が積もり、石が混じります。植樹は1989年と一番古く、深くまで根が張り巡らされています。
メルバリーの畑はオーガニックで栽培され、自然のままをキープしています。耕起しない、ドライファーミングなどを実践しています。ワインメーカーのコーリー・エンプティングは福岡正信の自然農法に大きな影響を受けており、その思想を年々取り入れていっています。それによって、従来よりも2~3週間収穫が早まり、2021年は9月上旬に収穫が終わっています。
メルバリーはなめらかさやしなやかさのあるテクスチャーが特徴的。これは表土の粘土質に由来するもののようです。カベルネ・ソーヴィニヨンというよりもメルロー的なテクスチャー。赤い果実は感じず、ブルーベリーやブラックベリーのニュアンス。マックス・カーストさんは紅茶やバラの花をクラッシュした香りやシナモンなどを感じると言っていました。また、クエラとメルバリーはカベルネ・ソーヴィニヨンらしくないとも言っていました。
単一畑の三つ目はセント・エデンです。セント・エデンはオークヴィルのヴァレーフロアの東寄り、スクリーミング・イーグルから400mほど北に行ったところにあります。五つの畑の中で一番標高が低く、夜は一番寒く、昼は一番暑くなります。完熟して酸が残るのが特徴です。プリチャード・ヒルから落ちてきた火山性の赤い土壌が特徴です。
セント・エデンはやや北向きの斜面になっています。この写真は三つの畑に見えますが、全部セント・エデンです。植樹したときの流行りが列の向きや剪定方法に反映されています。一番手前は1984年に植樹されておりダブルコルドンで列の向きは東西になっています。日当たりの良さを重視しています。
その上はダブルギィヨで南北の列方向になっています。その上が一番新しいセクションでまだ台木を植えた段階なのですが、ゴブレットやカリフォルニアスプロールと言われる形にしていきます。ブドウの樹の競争を促進することと、ブドウの実に日陰を作り、灌漑なしでの栽培を行うためにこの形にしています。1エーカーあたり4000本と、ナパとしてはかなりの密植です。欧州のゴブレットと違うのは、フルーツゾーンと呼ばれる果実を付ける位置は高くしていること。将来はハーランやプロモントリーもこの形になるだろうとのことです。なお、若い樹のブドウはメイトリアークには入れず、サードワインのマスコットに使われます。
完璧なカベルネ・ソーヴィニヨンがあるとしたらこのワインかなと感じました。パワフルでシルキーなタンニン、果実味と酸の高度なバランス。非の打ち所がありません。
次はヴァシーナです。前述のように畑はVine Hill Ranch。その一番山寄りのブロックをボンドが使っています。セント・エデンと同じオークヴィルの畑ですが、セント・エデンが東寄りでヴァカ山脈の火山性土壌であるのに対して、ヴァシーナはオークヴィルの西側の沖積扇状地。ドミナスやト・カロンからそれぞれ1km程度、ハーラン・エステートからも数百mという近さです。サンパブロ湾からの風が吹き抜けるため、ボンドの畑の中ではここが一番涼しくなっています。東向きの斜面で午前の日照をしっかり浴びますが、山が迫っているため午後は早くから日陰になります。
2021年に収穫は8月末から始まり9月16日に終了したとのこと。ここもゴブレット仕立てになっています。
オークヴィルの西側というと、前述のト・カロンやベクストファー・ト・カロンが代表的な畑。ハーランもそうですし、マーサズ・ヴィンヤード、ドミナスのユリシーズなど綺羅星のような畑が並びます。ヴァシーナもト・カロンに通じるような芳醇さや、ストラクチャー、ブラックペッパーやハーブの風味があります。かなりパワフルなのはヴィンテージの特徴もあると思いますが、ココア・パウダーのようなタンニンもまた心地よいワイン。個人的にはやはりオークヴィルの西側のイメージをそのまま具現化したワインだと感じており、その中でもトップクラスは間違いないでしょう。今回のセミナーでもこれが一番好きという人が多かったと思います。
五つの畑の最後がプルリバス。ナパヴァレーとソノマの間にあるマヤカマス山脈側のAVAは南からマウント・ヴィーダー、スプリング・マウンテン、ダイヤモンド・マウンテンとなっていて、プルリバスはスプリング・マウンテンにあります。マヤカマスの畑はほとんどが他の畑から隔絶されたところにあり、プルリバスも例外ではなく隣接する畑はなくレッドウッドの森に囲まれています。栽培は無灌漑。五つの畑の中では一番標高が高いところにある畑です。
杉や腐葉土、セージなどの風味に、赤い果実とブラックプラム、タンニンの強さはこれが一番感じます。酸のフレッシュさも印象的。「山カベ」と呼ばれるスタイルとして、個性的で素晴らしいワインです。個人的には五つの単一畑ワインの中でこれが一番好きでした。
最後に、2011年のプルリバスが振舞われました。2011年は冷涼な年で、ナパでは珍しくブドウが完熟しない畑もあったのですが、熟成すると非常にいいニュアンスを出してきていると言われています。
マッシュルームに腐葉土やハーブなど熟成によるアロマがあふれてきます。タンニンは2021年よりもこなれています。これも熟成によるものでしょう。きれいに熟成して美味しく飲めますが、まだ数年は熟成していくのではないかと感じました。
リンカーン・セラーズのカベルネ・ソーヴィニヨンが税別3000円弱と、激安になっています。残念ながら輸入停止によるものだそうです。元の価格は6000円ですが、6000円でもコスパは高いと感じられるクオリティでした。ブドウはドミナスなどがあるヨントヴィルのものを使っています。
価格3000円程度というと、人気の689セラーズより300円ほど高い感じですが、689のレッドワインはジンファンデルが4割近く入っており、カベルネ・ソーヴィニヨンは3割弱。柔らかな味わいを求めるなら689がいいですが、本格的なカベルネ・ソーヴィニヨンの味わいとは全く別物です。
また、ナパの人気カベルネ・ソーヴィニヨンというとナパ・ハイランズがありますが、こちらは5000円程度。また、ヨントヴィルなどの地域ものではなく、ナパヴァレー広域のワインになります。格的にも実際の味わい的にもリンカーン・セラーズが上回ります。ナパらしいカベルネ・ソーヴィニヨンを求める方にはお薦めです。
価格3000円程度というと、人気の689セラーズより300円ほど高い感じですが、689のレッドワインはジンファンデルが4割近く入っており、カベルネ・ソーヴィニヨンは3割弱。柔らかな味わいを求めるなら689がいいですが、本格的なカベルネ・ソーヴィニヨンの味わいとは全く別物です。
また、ナパの人気カベルネ・ソーヴィニヨンというとナパ・ハイランズがありますが、こちらは5000円程度。また、ヨントヴィルなどの地域ものではなく、ナパヴァレー広域のワインになります。格的にも実際の味わい的にもリンカーン・セラーズが上回ります。ナパらしいカベルネ・ソーヴィニヨンを求める方にはお薦めです。
Wine to Styleのニュー・カリフォルニア試飲会で美味しかったワイン(前編)の続きです。

グリーン&レッドは、カリフォルニア料理のパイオニアであるシェ・パニーズでハウスワインとして長年使われているワイナリーで、ナパのジンファンデルをメインで作っています。ジンファンデル ティップ・トップ・ヴィンヤード2018は標高540~600mの山の上の畑。野菜中心の料理であるシェ・パニーズで使われていることでわかるように、エレガントさがあるワイン。複雑さもあり一般にイメージするジンファンデルとは一線を画しています。実はアルコール度数は15.4%もあるのですが、それを感じさせないバランスの良さがあります。

スクライブはニュー・カリフォルニア系でも人気の高いワイナリーの一つ。イケメン兄弟がワインを造っています。ピノ・ノワール カーネロス2023(8900円)は果実味がきれいで、うまみもたっぷり。微笑みが出るようなワイン。

ペイザンはアイ・ブランド&ファミリー(I. Brand &Family)の兄弟ブランド。イアン・ブランドという人がモントレーで作るワインです。ペイザンは廉価版のブランド。シャルドネ ジャックス・ヒル2023(4200円)は酸がきれいでバランスよいワイン。コスパ抜群です。

こちらはアイ・ブランド&ファミリーのワイン。カベルネ・フラン デローズ・ヴィンヤード2022(7800円)。シエネガ・ヴァレーというちょっとマイナーな産地(カレラの山の麓になります)。少しピラジンを感じます。酸高く、グリップ感があっておいしいカベルネ・フラン。

ウルトラバイオレットはPoeというワイナリーでも有名なサマンサ・シーンという女性醸造家のワイナリー。このカベルネ・ソーヴィニョン2022(3300円)はなんといってもコスパで他の追随を許さないワイン。エレガントさや花の香りもあり、ミディアム・ボディで美味しい。

アルノー・ロバーツはダンカン・アルノーとネイサン・ロバーツによるワイナリーです。ニュー・カリフォルニアを代表するワイナリーといってもいいでしょう。ネイサンの祖母はロバート・モンダヴィの奥さんのマルグリットで、ラベルのデザインもマルグリットによるものです。このワインはシエラ・フットヒルズのエル・ドラドのガメイ・ノワール2023(5800円)。ジューシーな果実味にこくのあるうま味、それでいて軽やかな味わいで美味しい。

アルノー・ロバーツのワインの中でも人気の高いのがこのトゥルソー(2022年、7500円)。奥行きがある味わい。素晴らしい。

パックスは、シラーの名手であるパックス・マーリーによるワイナリー。シラーではヴィナスで100点も取っています。これはエル・ドラドのシラー2022(5900円)。酸高くスパイシーで、冷涼感のあるシラー。

最後はメートル・ド・シェのワイン。Wine to Styleのページには以下のように説明があります。
####
カリフォルニアのナチュール・ムーヴメントを切り開いた先駆者「スコリウム・プロジェクト」のアシスタント・ワインメーカーとして長年活躍したアレックス・ピッツ(Alex Pitts)が独立し、レオ・スティーンで醸造を学び、ナパでミシュラン三つ星の「メドーウッド」でソムリエをしていたマーティン・ウィンター(Martin Winter)とタッグを組んで2012 年に設立したブランドです。2019 年には米国の全国紙『San Francisco Chronicle』にて、Winemakers to Watch(最も注目すべき醸造家)に選ばれ、今最も勢いがある若手コンビです。
「メートル・ド・シェ」はフランス語(主にボルドー)で醸造責任者を意味する言葉です。現在では独立して自身のワイナリーの経営だけで生活ができるようになりましたが、「メートル・ド・シェ」設立当初は二人とも別のワイナリーの醸造責任者やアシスタントとして仕事を掛け持ちしていました。そんな苦しい中、自分たちにセラーで働くチャンスを与えてくれて、醸造や栽培の知識を共有してくれた恩師がいたからこそ現在の自分が居るという意味で、労いの気持ちを表現したブランド名です。つまり、「メートル・ド・シェ」とはアレックスとマーティンがワインの業界に入るきっかけとなった役職名であり、彼らの原点なのです。
1883 年に描かれたイラストがラベルに採用されていて、ローマ神話における自由の女神「リーベルタース」とカリフォルニアのシンボルであるハイイログマが乾杯をしています。カリフォルニアが州旗としてハイイログマを採用したのが1911 年なので、この絵はその前に描かれたものになります。樽の側面にはゴールドラッシュ発生時(1848 年)に長い道のりを経てアメリカ西海岸にたどり着いた帆船とクワを持つ労働者が描かれています。もともとのオリジナルのイラストには樽の側面に「見つかった!」を意味する「Eureka」の文字があり、ワイン木箱の側面にはそれぞれ「Mission」、「Pineau」、「Riesling」、「Zinfandel」と書かれていましたが、そのままでは米国酒類タバコ税貿易管理局からの許可が降りなかった為、「Eureka」の文字を削除し、木箱の側面には実際に中に入っているワインに使われたブドウ品種が記載されています。
####
個人的には今回ここのワインがどれもとても良かったです。右からシュナン・ブランのスパークリング・ワイン(6800円)、シャルドネ ウィーラー・ヴィンヤード 2021(6300円)、レッド・テーブル・ワイン2022(4900円)、ジンファンデル スタンピード・クレメンツ・ヒルズ2022(6200円)、カベルネ・ソーヴィニョン ガラ・マウンテン2020(8200円)。
シュナン・ブランのスパークリングはあまり飲んだことありませんが、果実味豊かでバランスもよく美味しい。シャルドネもバランスタイプ。レッド・テーブル・ワインはリッチ感があり、タンニンが味を引き締めていてとても美味しい。ジンファンデルも華やかな香りでエレガントで素晴らしい。カベルネはややリッチ。これもいいです。
グリーン&レッドは、カリフォルニア料理のパイオニアであるシェ・パニーズでハウスワインとして長年使われているワイナリーで、ナパのジンファンデルをメインで作っています。ジンファンデル ティップ・トップ・ヴィンヤード2018は標高540~600mの山の上の畑。野菜中心の料理であるシェ・パニーズで使われていることでわかるように、エレガントさがあるワイン。複雑さもあり一般にイメージするジンファンデルとは一線を画しています。実はアルコール度数は15.4%もあるのですが、それを感じさせないバランスの良さがあります。
スクライブはニュー・カリフォルニア系でも人気の高いワイナリーの一つ。イケメン兄弟がワインを造っています。ピノ・ノワール カーネロス2023(8900円)は果実味がきれいで、うまみもたっぷり。微笑みが出るようなワイン。
ペイザンはアイ・ブランド&ファミリー(I. Brand &Family)の兄弟ブランド。イアン・ブランドという人がモントレーで作るワインです。ペイザンは廉価版のブランド。シャルドネ ジャックス・ヒル2023(4200円)は酸がきれいでバランスよいワイン。コスパ抜群です。
こちらはアイ・ブランド&ファミリーのワイン。カベルネ・フラン デローズ・ヴィンヤード2022(7800円)。シエネガ・ヴァレーというちょっとマイナーな産地(カレラの山の麓になります)。少しピラジンを感じます。酸高く、グリップ感があっておいしいカベルネ・フラン。
ウルトラバイオレットはPoeというワイナリーでも有名なサマンサ・シーンという女性醸造家のワイナリー。このカベルネ・ソーヴィニョン2022(3300円)はなんといってもコスパで他の追随を許さないワイン。エレガントさや花の香りもあり、ミディアム・ボディで美味しい。
アルノー・ロバーツはダンカン・アルノーとネイサン・ロバーツによるワイナリーです。ニュー・カリフォルニアを代表するワイナリーといってもいいでしょう。ネイサンの祖母はロバート・モンダヴィの奥さんのマルグリットで、ラベルのデザインもマルグリットによるものです。このワインはシエラ・フットヒルズのエル・ドラドのガメイ・ノワール2023(5800円)。ジューシーな果実味にこくのあるうま味、それでいて軽やかな味わいで美味しい。
アルノー・ロバーツのワインの中でも人気の高いのがこのトゥルソー(2022年、7500円)。奥行きがある味わい。素晴らしい。
パックスは、シラーの名手であるパックス・マーリーによるワイナリー。シラーではヴィナスで100点も取っています。これはエル・ドラドのシラー2022(5900円)。酸高くスパイシーで、冷涼感のあるシラー。
最後はメートル・ド・シェのワイン。Wine to Styleのページには以下のように説明があります。
####
カリフォルニアのナチュール・ムーヴメントを切り開いた先駆者「スコリウム・プロジェクト」のアシスタント・ワインメーカーとして長年活躍したアレックス・ピッツ(Alex Pitts)が独立し、レオ・スティーンで醸造を学び、ナパでミシュラン三つ星の「メドーウッド」でソムリエをしていたマーティン・ウィンター(Martin Winter)とタッグを組んで2012 年に設立したブランドです。2019 年には米国の全国紙『San Francisco Chronicle』にて、Winemakers to Watch(最も注目すべき醸造家)に選ばれ、今最も勢いがある若手コンビです。
「メートル・ド・シェ」はフランス語(主にボルドー)で醸造責任者を意味する言葉です。現在では独立して自身のワイナリーの経営だけで生活ができるようになりましたが、「メートル・ド・シェ」設立当初は二人とも別のワイナリーの醸造責任者やアシスタントとして仕事を掛け持ちしていました。そんな苦しい中、自分たちにセラーで働くチャンスを与えてくれて、醸造や栽培の知識を共有してくれた恩師がいたからこそ現在の自分が居るという意味で、労いの気持ちを表現したブランド名です。つまり、「メートル・ド・シェ」とはアレックスとマーティンがワインの業界に入るきっかけとなった役職名であり、彼らの原点なのです。
1883 年に描かれたイラストがラベルに採用されていて、ローマ神話における自由の女神「リーベルタース」とカリフォルニアのシンボルであるハイイログマが乾杯をしています。カリフォルニアが州旗としてハイイログマを採用したのが1911 年なので、この絵はその前に描かれたものになります。樽の側面にはゴールドラッシュ発生時(1848 年)に長い道のりを経てアメリカ西海岸にたどり着いた帆船とクワを持つ労働者が描かれています。もともとのオリジナルのイラストには樽の側面に「見つかった!」を意味する「Eureka」の文字があり、ワイン木箱の側面にはそれぞれ「Mission」、「Pineau」、「Riesling」、「Zinfandel」と書かれていましたが、そのままでは米国酒類タバコ税貿易管理局からの許可が降りなかった為、「Eureka」の文字を削除し、木箱の側面には実際に中に入っているワインに使われたブドウ品種が記載されています。
####
個人的には今回ここのワインがどれもとても良かったです。右からシュナン・ブランのスパークリング・ワイン(6800円)、シャルドネ ウィーラー・ヴィンヤード 2021(6300円)、レッド・テーブル・ワイン2022(4900円)、ジンファンデル スタンピード・クレメンツ・ヒルズ2022(6200円)、カベルネ・ソーヴィニョン ガラ・マウンテン2020(8200円)。
シュナン・ブランのスパークリングはあまり飲んだことありませんが、果実味豊かでバランスもよく美味しい。シャルドネもバランスタイプ。レッド・テーブル・ワインはリッチ感があり、タンニンが味を引き締めていてとても美味しい。ジンファンデルも華やかな香りでエレガントで素晴らしい。カベルネはややリッチ。これもいいです。
インポーターWine to Styleが、ニュー・カリフォルニアに絞った試飲会を開催しました。そこから良かったワインを報告します。
ニュー・カリフォルニアっていったい何? という人もいると思うので簡単に解説します。ニュー・カリフォルニアとは2013年に当時SFクロニクル紙のワイン担当だったジョン・ボネが書いた「New California Wine」という本に端を発するワインのスタイルです。これより数年前にIPOB(In Pursuit of Balance)という団体で、濃厚でアルコール度数の高いカリフォルニアワインへのアンチテーゼとして、エレガントでアルコール度数が低く、食事に合わせやすいワインを造るという運動が起こっており、ニュー・カリフォルニアはその流れを汲むものでした。テロワールを重視し、濃厚さや味わいの強さよりもバランスの良さを求めるスタイル。また、ヴァルディギエやトゥルソーなど、マイナーな品種やごく少量作られている古い畑のブドウなどに取り組む生産者、いわゆる自然派的なワイン造りをする生産者などが含まれます。
Wine to Styleは以前からニュー・カリフォルニア系の生産者のワインを積極的に輸入しており、今回は久しぶりにニュー・カリフォルニアに限定した試飲会となりました。
参考:以前4社で行った試飲会の記事はこちら
ニュー・カリフォルニア試飲会でおいしかったワイン(前編)
ニュー・カリフォルニア試飲会でおいしかったワイン(後編)

フェイラは、以前ターリーのワインメーカーだったエーレン・ジョーダンのワイナリー。ターリーがむちゃくちゃ濃厚だった時代のワインメーカーですが、自身のワイナリーではバランスを重視したワインを造っています。このソノマ・コーストのピノ・ノワール2023(6800円)とDayブランドのジンファンデル2022(5300円)はコスト・パフォーマンス抜群。どちらもきれいな味わいです。

タトーマーはリースリングの名手として知られるワイナリーですが、サンタ・バーバラのピノ・ノワール2021(5900円)とサンタ・リタ・ヒルズのクステンニーベルピノ・ノワール2022(6800円)を紹介します。サンタ・バーバラはとてもエレガント、サンタ・リタ・ヒルズはうまみがあり、柔らかなテクスチャーのワインです。

サンディはオレゴンのイヴニングランドやサンタ・バーバラのドメーヌ・ド・ラ・コートを持つラジャ・パーとサシ・ムーアマンがもう一つサンタ・バーバラで営むワイナリー。ドメーヌ・ド・ラ・コートが自社畑なのに対し、サンディは買いブドウでコスパの高さが光ります。シャルドネ・セントラル・コースト2021(4900円)は酸高く、複雑さもあり、コスト・パフォーマンス抜群。

ロマンスは、上記のサンディのワインですが、これだけラベルが大きく異なっています。畑はドメーヌ・ド・ラ・コートのもので、自社畑みたいなものというちょっと変わった位置付けのワインです。ロマンス・ピノ・ノワール2021(18000円)は非常に高いレベルでバランスの取れたワイン。酸もきれいでうまみもあります。素晴らしい。

マヤカマスはクラシックな造りで知られる老舗ワイナリー。クラシックな造りがニュー・カリフォルニアに分類されるのも面白いです。シャルドネ2022(1万3000円)は、ほどよい樽感も魅力です。

センティアムは、ロバート・モンダヴィの次男でナパのプレミアムワイン「コンティニュアム」を作るティム・モンダヴィの次女キアラが作るソーヴィニヨンブランのワイナリー。ブドウはメンドシーノから調達しています。16000円は、カリフォルニアのソーヴィニヨンブランの中でもかなり高価ですが、のびやかな酸ときれいな果実味や複雑さが非常に魅力的。高級ソーヴィニヨンブランとして十分なクオリティを持っています。ヴィンテージは2023年。

もはや、カリフォルニアのエレガント系ピノ・ノワールのトップを走るといっても過言ではないほど高い評価を受けているのが、レイン(Raen)。上記のキアラの兄弟であるカルロとダンテがソノマ・コーストで作っています。全房発酵にこだわりを持っているのも特徴。ロイヤル・セント・ロバート2023(16000円)は、こくと奥行きが素晴らしいワイン。
以下は後編で。
ニュー・カリフォルニアっていったい何? という人もいると思うので簡単に解説します。ニュー・カリフォルニアとは2013年に当時SFクロニクル紙のワイン担当だったジョン・ボネが書いた「New California Wine」という本に端を発するワインのスタイルです。これより数年前にIPOB(In Pursuit of Balance)という団体で、濃厚でアルコール度数の高いカリフォルニアワインへのアンチテーゼとして、エレガントでアルコール度数が低く、食事に合わせやすいワインを造るという運動が起こっており、ニュー・カリフォルニアはその流れを汲むものでした。テロワールを重視し、濃厚さや味わいの強さよりもバランスの良さを求めるスタイル。また、ヴァルディギエやトゥルソーなど、マイナーな品種やごく少量作られている古い畑のブドウなどに取り組む生産者、いわゆる自然派的なワイン造りをする生産者などが含まれます。
Wine to Styleは以前からニュー・カリフォルニア系の生産者のワインを積極的に輸入しており、今回は久しぶりにニュー・カリフォルニアに限定した試飲会となりました。
参考:以前4社で行った試飲会の記事はこちら
ニュー・カリフォルニア試飲会でおいしかったワイン(前編)
ニュー・カリフォルニア試飲会でおいしかったワイン(後編)
フェイラは、以前ターリーのワインメーカーだったエーレン・ジョーダンのワイナリー。ターリーがむちゃくちゃ濃厚だった時代のワインメーカーですが、自身のワイナリーではバランスを重視したワインを造っています。このソノマ・コーストのピノ・ノワール2023(6800円)とDayブランドのジンファンデル2022(5300円)はコスト・パフォーマンス抜群。どちらもきれいな味わいです。
タトーマーはリースリングの名手として知られるワイナリーですが、サンタ・バーバラのピノ・ノワール2021(5900円)とサンタ・リタ・ヒルズのクステンニーベルピノ・ノワール2022(6800円)を紹介します。サンタ・バーバラはとてもエレガント、サンタ・リタ・ヒルズはうまみがあり、柔らかなテクスチャーのワインです。
サンディはオレゴンのイヴニングランドやサンタ・バーバラのドメーヌ・ド・ラ・コートを持つラジャ・パーとサシ・ムーアマンがもう一つサンタ・バーバラで営むワイナリー。ドメーヌ・ド・ラ・コートが自社畑なのに対し、サンディは買いブドウでコスパの高さが光ります。シャルドネ・セントラル・コースト2021(4900円)は酸高く、複雑さもあり、コスト・パフォーマンス抜群。
ロマンスは、上記のサンディのワインですが、これだけラベルが大きく異なっています。畑はドメーヌ・ド・ラ・コートのもので、自社畑みたいなものというちょっと変わった位置付けのワインです。ロマンス・ピノ・ノワール2021(18000円)は非常に高いレベルでバランスの取れたワイン。酸もきれいでうまみもあります。素晴らしい。
マヤカマスはクラシックな造りで知られる老舗ワイナリー。クラシックな造りがニュー・カリフォルニアに分類されるのも面白いです。シャルドネ2022(1万3000円)は、ほどよい樽感も魅力です。
センティアムは、ロバート・モンダヴィの次男でナパのプレミアムワイン「コンティニュアム」を作るティム・モンダヴィの次女キアラが作るソーヴィニヨンブランのワイナリー。ブドウはメンドシーノから調達しています。16000円は、カリフォルニアのソーヴィニヨンブランの中でもかなり高価ですが、のびやかな酸ときれいな果実味や複雑さが非常に魅力的。高級ソーヴィニヨンブランとして十分なクオリティを持っています。ヴィンテージは2023年。
もはや、カリフォルニアのエレガント系ピノ・ノワールのトップを走るといっても過言ではないほど高い評価を受けているのが、レイン(Raen)。上記のキアラの兄弟であるカルロとダンテがソノマ・コーストで作っています。全房発酵にこだわりを持っているのも特徴。ロイヤル・セント・ロバート2023(16000円)は、こくと奥行きが素晴らしいワイン。
以下は後編で。
楽天スーパーセールでお買い得になっているカリフォルニアワインをまとめておきます。
リカオーで、ウッドブリッジの缶がセール。ウッドブリッジに缶があるの知らなかったのですが1本187mlが6本なので、通常の1.5本分で1020円はいいですね。こういうのが家にあるとちょっと飲みたいときに重宝します。
同じくリカオーで、リッジのジンファンデル系がかなり安いです。中でも驚いたのはパガニ・ランチが5000円台ということ。1900年頃に植えられた古木の畑で、リッジ以外にベッドロックやビアーレ、セゲシオなどジンファンデルの名手たちがこぞってブドウを買っている銘醸畑です。しかも2022年はパーカー94点と非常に評価の高い年です。
リッジのエントリー版「スリー・ヴァレー」も安いです。
Cave de L Naotakaではオレゴンのドメーヌ・ドルーアンのピノ・ノワールが安いです。現地価格で40ドル台が5390円。2022年はVinous 93点とこれもいい年。
同じショップで、ナパの名門BVのフラッグシップ「ジョルジュ・ドゥ・ラトゥール・プライベートリザーブ」2019が1万5000円台と激安です。2019年はVinousで97+と非常に高い評価です。この倍の価格でも全然おかしくないワイン。
うきうきワインではダイアトムのシャルドネがセール価格。ダイアトムはグレッグ・ブリュワーが作るシャルドネ専門のワイナリー。あえて樽を使わないワインですが、シャルドネ好きだったら一度は飲まないといけないワインです。
次はダイアトムとは真逆のこてこて系シャルドネのセット。樽好きにはたまらないですね。
しあわせワイン俱楽部ではケンゾーがセールになっています。ロゼのYuiはお祝いのプレゼントにもいいですね。
ユニオン・サクレのオレンジは2割引。これ、美味しいですよ。
同じくしあわせワイン俱楽部から樽系シャルドネのセット。前述のものより、ちょっと高級で品のいい樽系が並んでいます。
リカオーで、ウッドブリッジの缶がセール。ウッドブリッジに缶があるの知らなかったのですが1本187mlが6本なので、通常の1.5本分で1020円はいいですね。こういうのが家にあるとちょっと飲みたいときに重宝します。
同じくリカオーで、リッジのジンファンデル系がかなり安いです。中でも驚いたのはパガニ・ランチが5000円台ということ。1900年頃に植えられた古木の畑で、リッジ以外にベッドロックやビアーレ、セゲシオなどジンファンデルの名手たちがこぞってブドウを買っている銘醸畑です。しかも2022年はパーカー94点と非常に評価の高い年です。
リッジのエントリー版「スリー・ヴァレー」も安いです。
Cave de L Naotakaではオレゴンのドメーヌ・ドルーアンのピノ・ノワールが安いです。現地価格で40ドル台が5390円。2022年はVinous 93点とこれもいい年。
同じショップで、ナパの名門BVのフラッグシップ「ジョルジュ・ドゥ・ラトゥール・プライベートリザーブ」2019が1万5000円台と激安です。2019年はVinousで97+と非常に高い評価です。この倍の価格でも全然おかしくないワイン。
うきうきワインではダイアトムのシャルドネがセール価格。ダイアトムはグレッグ・ブリュワーが作るシャルドネ専門のワイナリー。あえて樽を使わないワインですが、シャルドネ好きだったら一度は飲まないといけないワインです。
次はダイアトムとは真逆のこてこて系シャルドネのセット。樽好きにはたまらないですね。
しあわせワイン俱楽部ではケンゾーがセールになっています。ロゼのYuiはお祝いのプレゼントにもいいですね。
ユニオン・サクレのオレンジは2割引。これ、美味しいですよ。
同じくしあわせワイン俱楽部から樽系シャルドネのセット。前述のものより、ちょっと高級で品のいい樽系が並んでいます。
2020年の山火事「グラス・ファイア」でワイナリーや畑を焼失し、今年2月に閉鎖がアナウンスされたニュートン(Newton)ですが、再出発することがワイン・スペクテーターの記事で判明しました。
ワイナリー閉鎖の記事(ナパの名門ワイナリー「ニュートン」、48年の歴史に幕切れ)

在りし日のニュートン
ナパの歴史に名を遺すニュートンですが、特に有名なのは現在はコングスガードでトップ中のトップのシャルドネを作っているジョン・コングスガードがニュートンのワインメーカー時代に始めたアンフィルタードのシャルドネです。樽熟成や天然酵母発酵などブルゴーニュの伝統的な手法に習い、フィルターをかけずにボトル詰めしたシャルドネはその風味の豊かさや複雑さで一世を風靡しました。
2001年にLVMHが過半数の株式を取得してからは、主にマヤカマス山脈のさまざまなテロワールを生かしたカベルネ・ソーヴィニヨンを主力に置きました。美しい庭園など風光明媚なワイナリーで、日本版の『サイドウェイズ』など映画にも使われています。

(1989年の映画『ブラック・レイン』)
2020年の火事の後、再起を図っていましたが、今年2月にメーリング・リスト会員向けに閉鎖を発表していました。そのワイナリーを新たに購入したのがニック・リヴァノスとエリック・ブライアン・スーテという友人の二人組。スプリング・マウンテンのワイナリーと畑、それからブランドを購入しています。スプリング・マウンテン以外の畑は含まれていません。
二人はナパのデイヴィース(シュラムスバーグのワイナリー)のイベントで知り合い、友人になったそうです。スーテ氏は弁護士でカリストガにも畑とワイナリーがあり、ロスアンゼルスとナパを行き来しています。リヴァノス氏はカリフォルニアの酸ラモンで特殊潤滑油とオイルを製造するレンカート・オイルという会社を経営しています。二人はいつかナパで一緒にワイナリーを持ちたいと思っており、ニュートン購入の機会を得て興奮しているといいます。「私たちはベンチャーキャピタリストではありません。ただナパバレーとナパバレーのワインを愛する人間です。そして、このような歴史ある美しい土地を購入する機会を逃しませんでした」とスーテ氏は語っています。
ワイナリー閉鎖の記事(ナパの名門ワイナリー「ニュートン」、48年の歴史に幕切れ)

在りし日のニュートン
ナパの歴史に名を遺すニュートンですが、特に有名なのは現在はコングスガードでトップ中のトップのシャルドネを作っているジョン・コングスガードがニュートンのワインメーカー時代に始めたアンフィルタードのシャルドネです。樽熟成や天然酵母発酵などブルゴーニュの伝統的な手法に習い、フィルターをかけずにボトル詰めしたシャルドネはその風味の豊かさや複雑さで一世を風靡しました。
2001年にLVMHが過半数の株式を取得してからは、主にマヤカマス山脈のさまざまなテロワールを生かしたカベルネ・ソーヴィニヨンを主力に置きました。美しい庭園など風光明媚なワイナリーで、日本版の『サイドウェイズ』など映画にも使われています。

(1989年の映画『ブラック・レイン』)
2020年の火事の後、再起を図っていましたが、今年2月にメーリング・リスト会員向けに閉鎖を発表していました。そのワイナリーを新たに購入したのがニック・リヴァノスとエリック・ブライアン・スーテという友人の二人組。スプリング・マウンテンのワイナリーと畑、それからブランドを購入しています。スプリング・マウンテン以外の畑は含まれていません。
二人はナパのデイヴィース(シュラムスバーグのワイナリー)のイベントで知り合い、友人になったそうです。スーテ氏は弁護士でカリストガにも畑とワイナリーがあり、ロスアンゼルスとナパを行き来しています。リヴァノス氏はカリフォルニアの酸ラモンで特殊潤滑油とオイルを製造するレンカート・オイルという会社を経営しています。二人はいつかナパで一緒にワイナリーを持ちたいと思っており、ニュートン購入の機会を得て興奮しているといいます。「私たちはベンチャーキャピタリストではありません。ただナパバレーとナパバレーのワインを愛する人間です。そして、このような歴史ある美しい土地を購入する機会を逃しませんでした」とスーテ氏は語っています。

コスパワインで知られるモントレーのシャイド・ファミリーが、パンプキンスパイス入りのシャルドネを発売しました。昨年に続いて2回目で、秋限定で販売します。
米国では、ハロウィーンの季節にパンプキンパイを食べるのが定番となっています。パンプキンスパイスとはこのパイに使うスパイスで、シナモンやナツメグ、クローヴなどが使われています。
シャイドではハロウィーンの季節用ワインとして、最初は遊び心でパンプキンの中で発酵するワインを試してみたそうですが、それはうまくいかず、いろいろと作ってみたなかで、パンプキンスパイス入りのシャルドネが良かったようです。
昨年発売したものは、あっという間に完売し、評判になったとのこと。エグゼクティブ副社長のハイディ・シャイド氏は「パンプキン・スパイス・シャルドネは、従来のワインとは異なります。まさにそこがポイントです。親しみやすい方法で会話や好奇心、そして繋がりを刺激するワインを造り、人々が集い、人生を楽しみ、味わうという私たちの使命を反映しています」と語っています。
昨日の記事でも書いたように、ナパで発生したピケット・ファイアはこれまでのところ、5年前のグラス・ファイアほどの被害にはならずに済みそうです。今回燃えている地域はグラス・ファイアで燃えた地域とも重なっているのですが、何が違ったのでしょうか。
SFクロニクルの記事によると、いくつか理由があります。
一つは2020年はグラス・ファイア以外にも山火事が多く、消火に当たる人員が最初からひっ迫していたことです。この年はカリフォルニアの近代史で最も山火事の大きかった年であり、州の4%もの面積が焼失しました。特に8月の「オーガスト・コンプレックス・ファイア」は100万エーカーを超える初めての「ギガファイア」であり、ナパでも8月に大きな山火事が起きていました。それに比べると今年は消火に当たるリソースに余裕があったといいます。
このため、火災の初期から多くのリソースが投入されました。人員は2785名 (グラス・ファイアでは185名)、ヘリコプターは11機 (グラス・ファイアではゼロ)、消防車は251台 (グラス・ファイアでは10台)、ブルドーザーは 62台 (グラス・ファイアでは10台)、給水車は35台 (グラス・ファイアでは7台) でした。
気候も今年の方が穏やかでした。グラス・ファイアのときは気温が高く風が強かったため、火災がヴァレー・フロアを超えて広がりました。今回は風が弱く気温も低かったことが広がりを抑えました。また、グラス・ファイアで樹が枯れてしまった地域が燃えたため、燃料となる植生も少なくなっていました。
消防の装備も進化しています。夜間用ヘリコプター「ファイアホーク」の導入により、消火活動隊は水や消火剤を投下し、地上隊員の航行経路を確保することで、夜間を通して空中消火活動を継続することが可能になりました。
カリフォルニア州消防局のヘリタック隊によるヘリポート建設も大きな要因です。これにより、消火にあたる隊員が現場の近くで降りることができ移動時間を数時間も短縮できました。
これらに加えて地域の人間による対策も進んだことが、幸いしたようです。
SFクロニクルの記事によると、いくつか理由があります。
一つは2020年はグラス・ファイア以外にも山火事が多く、消火に当たる人員が最初からひっ迫していたことです。この年はカリフォルニアの近代史で最も山火事の大きかった年であり、州の4%もの面積が焼失しました。特に8月の「オーガスト・コンプレックス・ファイア」は100万エーカーを超える初めての「ギガファイア」であり、ナパでも8月に大きな山火事が起きていました。それに比べると今年は消火に当たるリソースに余裕があったといいます。
このため、火災の初期から多くのリソースが投入されました。人員は2785名 (グラス・ファイアでは185名)、ヘリコプターは11機 (グラス・ファイアではゼロ)、消防車は251台 (グラス・ファイアでは10台)、ブルドーザーは 62台 (グラス・ファイアでは10台)、給水車は35台 (グラス・ファイアでは7台) でした。
気候も今年の方が穏やかでした。グラス・ファイアのときは気温が高く風が強かったため、火災がヴァレー・フロアを超えて広がりました。今回は風が弱く気温も低かったことが広がりを抑えました。また、グラス・ファイアで樹が枯れてしまった地域が燃えたため、燃料となる植生も少なくなっていました。
消防の装備も進化しています。夜間用ヘリコプター「ファイアホーク」の導入により、消火活動隊は水や消火剤を投下し、地上隊員の航行経路を確保することで、夜間を通して空中消火活動を継続することが可能になりました。
カリフォルニア州消防局のヘリタック隊によるヘリポート建設も大きな要因です。これにより、消火にあたる隊員が現場の近くで降りることができ移動時間を数時間も短縮できました。
これらに加えて地域の人間による対策も進んだことが、幸いしたようです。
ナパのカリストガ近辺で8月21日に発生したピケット・ファイアは、1週間経った28日時点で6803エーカーと、ここ数日拡大が止まった状況です。コンテイン率も33%まで上がり、おそらくこのまま鎮火にむかうでしょう。

まだ安全だと言い切れる状況ではありませんが、今のところは少しほっとできる感じです。
この中で、ピケット・ファイアの被害額について最初の見積もりが発表されました。
ナパカウンティの農業委員は、ピケット・ファイアにより6500万ドル(約95憶円)の損害が発生し、そのほとんどがワイン産業への影響だと推定しています。1500エーカーのブドウ畑に影響があるとしており、うち20%は実際の火や熱による被害で、80%は煙の被害と見込んでいます。
一方で、ピケット・ファイアの発生原因はまだ分かっておらず、そちらも調査が進められています。現在、一つの可能性として捜査されているのはハンドレッド・エーカーの畑から発火したという説。もちろんブドウが自然発火することはありませんが、ワイナリーの契約労働者が、安全に冷却されたと信じていたオーブンから灰を取り出し、可燃物の山の上に置いたと捜査当局は疑っているといいます。畑の請負業者と管理者が火災調査官に供述したといいます。

まだ安全だと言い切れる状況ではありませんが、今のところは少しほっとできる感じです。
この中で、ピケット・ファイアの被害額について最初の見積もりが発表されました。
ナパカウンティの農業委員は、ピケット・ファイアにより6500万ドル(約95憶円)の損害が発生し、そのほとんどがワイン産業への影響だと推定しています。1500エーカーのブドウ畑に影響があるとしており、うち20%は実際の火や熱による被害で、80%は煙の被害と見込んでいます。
一方で、ピケット・ファイアの発生原因はまだ分かっておらず、そちらも調査が進められています。現在、一つの可能性として捜査されているのはハンドレッド・エーカーの畑から発火したという説。もちろんブドウが自然発火することはありませんが、ワイナリーの契約労働者が、安全に冷却されたと信じていたオーブンから灰を取り出し、可燃物の山の上に置いたと捜査当局は疑っているといいます。畑の請負業者と管理者が火災調査官に供述したといいます。
「ポール・ホブズの娘が新ブランド「ALH」でワインメーカーデビュー」という記事で紹介したALHのワインを試飲しました。正式な入荷は冬以降、価格は1万7000円を予定しています。

畑はナパのクームズヴィルにあるポール・ホブズの自社畑ネーサン・クームズ・エステート。クームズヴィルはナパのカベルネの産地としては一番気温が低いところであり、土壌的にはヴァカ山脈の南端で火山性の鉄分の多いところが多く、しっかりとストラクチャーのあるカベルネ・ソーヴィニヨンを生み出します。ポール・ホブズのここのカベルネ・ソーヴィニヨンはデカンター誌で100点を取るなど、クームズヴィルを代表するワインになっています。
ホブズのクームズヴィルのカベルネについては、以前の記事のテイスティング・コメントで「冷涼感を感じつつも、果実の風味としてはダークな黒果実。シルキーなテクスチャ、腐葉土。今飲んでも十分おいしいですが20年以上熟成させて飲んでみたいワイン」と書いています。
一方、ALHは同じ畑のワインですが、エレガントさが際立っています。赤い果実に、軽やかな酒質。豊かな酸。タンニンが全体を引き締めています。長期熟成というよりは、10年以内に飲みたいワインです。ホブズとは全く違うスタイルに仕上げてきているのが面白いワインでした。
畑はナパのクームズヴィルにあるポール・ホブズの自社畑ネーサン・クームズ・エステート。クームズヴィルはナパのカベルネの産地としては一番気温が低いところであり、土壌的にはヴァカ山脈の南端で火山性の鉄分の多いところが多く、しっかりとストラクチャーのあるカベルネ・ソーヴィニヨンを生み出します。ポール・ホブズのここのカベルネ・ソーヴィニヨンはデカンター誌で100点を取るなど、クームズヴィルを代表するワインになっています。
ホブズのクームズヴィルのカベルネについては、以前の記事のテイスティング・コメントで「冷涼感を感じつつも、果実の風味としてはダークな黒果実。シルキーなテクスチャ、腐葉土。今飲んでも十分おいしいですが20年以上熟成させて飲んでみたいワイン」と書いています。
一方、ALHは同じ畑のワインですが、エレガントさが際立っています。赤い果実に、軽やかな酒質。豊かな酸。タンニンが全体を引き締めています。長期熟成というよりは、10年以内に飲みたいワインです。ホブズとは全く違うスタイルに仕上げてきているのが面白いワインでした。
ピケット・ファイア(Pickett Fire)という山火事がナパで発生しています。現地時間の8月21日午後2時57分に発生し、23日午前8時11分時点で3993エーカー焼失。コンテイン率(山火事の外周の中で延焼を防いだ形になっている比率)は7%と、まだまだ鎮火は遠い状態です。

場所はカリストガの北東で、ハウエル・マウンテンの北西方向。一部の地域に避難勧告が出ています。現在のところ、ワイナリーやブドウ畑、家屋や人の被害はないようです。
今回の火事は現在のところ2020年のグラス・ファイアーと重なっており、草木はまだ十分に育っていない場所だとのこと。そのため、煙の被害なども今のところは大きくならなさそうです。

場所はカリストガの北東で、ハウエル・マウンテンの北西方向。一部の地域に避難勧告が出ています。現在のところ、ワイナリーやブドウ畑、家屋や人の被害はないようです。
今回の火事は現在のところ2020年のグラス・ファイアーと重なっており、草木はまだ十分に育っていない場所だとのこと。そのため、煙の被害なども今のところは大きくならなさそうです。
先日、ソノマ郡の「ワイン産業改善地区計画(WID)」に対して反対の声が上がっているという記事を書きました(物議を醸すソノマの「ワイン産業改善地区計画」)。実は、同様の計画は様々な郡で提案されており、既に実行に移されているところもあります。
ワイン・サーチャーではW.ブレイク・グレイ氏がこっらの動きをまとめた記事を書いています(Sonoma County Puts Wine Tax on Hold)。この記事によると、ソノマ郡での計画は現在一時保留という形になっているそうです。ソノマ・カウンティ・ヴィントナーズのマイケル・ヘイニー氏が辞任を表明するなど、将来の見通しは不透明です。
リバモア・ヴァレーとテメキュラでは2021年にWIDが設立されています。ローダイでも現在検討が進んでいます。
ローダイでは現在ワイナリーの直売に対して1.5%の課税を検討しており、3分の2ほどのワイナリーが賛成していますが、反対の声も根強くあります。興味深いのは、ローダイ・ワインという業界団体の活動資金は、実はワイン栽培農家だけが負担しており、ワイナリーは資金を提供していません。これは、ローダイが元々栽培家が多い地域だったということに由来していますが、ワイナリーだけがただ乗りする形は健全とは言えない気がします。
サンタ・クルーズ・マウンテンズではサンタ・クルーズ・マウンテンズ・ワイン生産者協会(SCMWA)がワイナリーのダイレクトセールスに1%の特別賦課金を加える案を提案。今月、サンタクルーズ郡監督委員会で承認されました。サンタ・クルーズ・マウンテンズはサンタクルーズ郡のほか、サンマテオ郡、サンタクララ郡にまたがっていますが、これらの郡に所属するワイナリーにも、サンタ・クルーズ郡と同様に運用することが定められています。
一方で、モントレーでは、業界団体の「モントレー郡ワイン生産者協会」自体が解散することが決定しました。これは郡全体のプロモーションを行う組織が存在しなくなるということです。サンタ・ルシア・ハイランズなど、AVAの業界団体はありますが、モントレーとして統括するところがなくなるのは地域としては大きな打撃のはずです。
カリフォルニアワインの消費動向レポートを毎年作成しているシリコンバレーバンクのロブ・マクミラン氏は、ワイン産業改善地区計画への反対の声に対してがっかりしているといいます。マクミラン氏はワインを宣伝する全米レベルのマーケティング・キャンペーン「WineRAMP」をコロナ禍で進めていましたが、最終的に資金が得られずに諦めた経験があります。このときはワインの売り上げがまだ右肩上がりで、マクミラン氏はそれが遠からず減少に転じると考えてこれを始めようとしたのですが、理解は得られませんでした。現在はこの3年間で売り上げが1割減っているという減速が明らかな状況ですが、それでもこの動きが進まないことに失望しています。
「ソノマで提案されているWIDに対する反応は、私にとってまたしても失望です。これはWineRAMPでの経験の繰り返しですが、今回は、変化のために何らかの行動を起こす必要があることは疑いようもないのに、反射的な反対運動が起きているのです」
ワイン・サーチャーではW.ブレイク・グレイ氏がこっらの動きをまとめた記事を書いています(Sonoma County Puts Wine Tax on Hold)。この記事によると、ソノマ郡での計画は現在一時保留という形になっているそうです。ソノマ・カウンティ・ヴィントナーズのマイケル・ヘイニー氏が辞任を表明するなど、将来の見通しは不透明です。
リバモア・ヴァレーとテメキュラでは2021年にWIDが設立されています。ローダイでも現在検討が進んでいます。
ローダイでは現在ワイナリーの直売に対して1.5%の課税を検討しており、3分の2ほどのワイナリーが賛成していますが、反対の声も根強くあります。興味深いのは、ローダイ・ワインという業界団体の活動資金は、実はワイン栽培農家だけが負担しており、ワイナリーは資金を提供していません。これは、ローダイが元々栽培家が多い地域だったということに由来していますが、ワイナリーだけがただ乗りする形は健全とは言えない気がします。
サンタ・クルーズ・マウンテンズではサンタ・クルーズ・マウンテンズ・ワイン生産者協会(SCMWA)がワイナリーのダイレクトセールスに1%の特別賦課金を加える案を提案。今月、サンタクルーズ郡監督委員会で承認されました。サンタ・クルーズ・マウンテンズはサンタクルーズ郡のほか、サンマテオ郡、サンタクララ郡にまたがっていますが、これらの郡に所属するワイナリーにも、サンタ・クルーズ郡と同様に運用することが定められています。
一方で、モントレーでは、業界団体の「モントレー郡ワイン生産者協会」自体が解散することが決定しました。これは郡全体のプロモーションを行う組織が存在しなくなるということです。サンタ・ルシア・ハイランズなど、AVAの業界団体はありますが、モントレーとして統括するところがなくなるのは地域としては大きな打撃のはずです。
カリフォルニアワインの消費動向レポートを毎年作成しているシリコンバレーバンクのロブ・マクミラン氏は、ワイン産業改善地区計画への反対の声に対してがっかりしているといいます。マクミラン氏はワインを宣伝する全米レベルのマーケティング・キャンペーン「WineRAMP」をコロナ禍で進めていましたが、最終的に資金が得られずに諦めた経験があります。このときはワインの売り上げがまだ右肩上がりで、マクミラン氏はそれが遠からず減少に転じると考えてこれを始めようとしたのですが、理解は得られませんでした。現在はこの3年間で売り上げが1割減っているという減速が明らかな状況ですが、それでもこの動きが進まないことに失望しています。
「ソノマで提案されているWIDに対する反応は、私にとってまたしても失望です。これはWineRAMPでの経験の繰り返しですが、今回は、変化のために何らかの行動を起こす必要があることは疑いようもないのに、反射的な反対運動が起きているのです」
米国地名委員会(US Board of Geographic Names=BGN)は2017年に認めた「To Kalon Creek」の名称を撤回する旨、8月14日に決定しました。

写真はMcDonaldのインスタグラムから
世界最高のカベルネ・ソーヴィニョンの畑といっても過言ではないほどの銘醸畑であるト・カロン・ヴィンヤード、その歴史をさかのぼると1868年にハミルトン・クラブという人が土地を購入してブドウ畑を作り、その名前として名付けたものでした。ギリシャ語で「最高の美しさ」という意味があります。
ハミルトン・クラブの死後は、マーティン・ステリングという人が所有し、その後イタリアン・スイス・コロニー、チャールズ・クリュッグを経てロバート・モンダヴィがその大部分を所有することになりました。ロバート・モンダヴィは1987年に「ト・カロン」の名前を商標登録し、現在はコンステレーション・ブランズがその権利を持っています。また、その一部はオーパス・ワン(コンステレーションとシャトー・ムートンの合弁)が所有する形になっています。
ただ、元々のト・カロンの全体をコンステレーションが持っているわけではありません。一部はボーリュー・ヴィンヤード(BV)を経て、アンディ・ベクストファーが購入しました。
シュレーダーはこの畑から2002年に「Beckstoffer Original To Kalon Vineyard」とラベルに銘打ったワインを出し、2003年にロバート・モンダヴィがそれを提訴、ベクストファー側もモンダヴィの商標は無効として反訴するということがありました。両社はその後和解し、ベクストファーはベクストファー・ト・カロンを畑の名前として使えることになりました。
このほか、マーティン・ステリング未亡人から一部を購入したヘドウィグ・デタートという人がおり、現在はその子孫が畑を二つに分け、デタート(Detert)およびマクドナルド(MacDonald)というワイナリーを興しています(ほかにもありますがここでは省略)。
この二つのワイナリーはト・カロンの名称を使えないのですが、マクドナルドのグレアム・マクドナルド(この人は現在若手の凄腕ワインメーカーとして知られています)が、ト・カロンは土地の名前であったはずなのにおかしいと考え、2017年にここを通る小川にト・カロン・クリークという名前を申請して許可されたのです。そのほとりに立つのが冒頭の写真です。

畑と小川の位置関係を示しました。
これに対して、ト・カロンが地名であるということになると困ると考えてコンステレーションが米国地名委員会に撤回の要望を出し、その決定が冒頭に挙げた結論になります。
ワイン・スペクテーターの記事によると、グレアム・マクドナルドは「危機に瀕しているのは、ト・カロンの遺産だけでなく、アメリカワインにおける土地の概念です。私たちのワインコミュニティは、その遺産の真正性を守らなければなりません。そうして初めて、私たちは土地に対する真の、何世代にもわたる敬意を築くことができるのです」と語っています。
また、アンディ・ベクストファーは「ト・カロン・クリークは存続すべきであり、利害関係のある関係者は皆、ト・カロン・ヴィンヤードを歴史的な場所として保存・保護することに注力すべきだ」と語っています。
裁判ではなく、控訴審があるわけではないので、今回の決定をこの後くつがえすのは難しいと思いますが、今後どうなっていくのでしょうか。

写真はMcDonaldのインスタグラムから
世界最高のカベルネ・ソーヴィニョンの畑といっても過言ではないほどの銘醸畑であるト・カロン・ヴィンヤード、その歴史をさかのぼると1868年にハミルトン・クラブという人が土地を購入してブドウ畑を作り、その名前として名付けたものでした。ギリシャ語で「最高の美しさ」という意味があります。
ハミルトン・クラブの死後は、マーティン・ステリングという人が所有し、その後イタリアン・スイス・コロニー、チャールズ・クリュッグを経てロバート・モンダヴィがその大部分を所有することになりました。ロバート・モンダヴィは1987年に「ト・カロン」の名前を商標登録し、現在はコンステレーション・ブランズがその権利を持っています。また、その一部はオーパス・ワン(コンステレーションとシャトー・ムートンの合弁)が所有する形になっています。
ただ、元々のト・カロンの全体をコンステレーションが持っているわけではありません。一部はボーリュー・ヴィンヤード(BV)を経て、アンディ・ベクストファーが購入しました。
シュレーダーはこの畑から2002年に「Beckstoffer Original To Kalon Vineyard」とラベルに銘打ったワインを出し、2003年にロバート・モンダヴィがそれを提訴、ベクストファー側もモンダヴィの商標は無効として反訴するということがありました。両社はその後和解し、ベクストファーはベクストファー・ト・カロンを畑の名前として使えることになりました。
このほか、マーティン・ステリング未亡人から一部を購入したヘドウィグ・デタートという人がおり、現在はその子孫が畑を二つに分け、デタート(Detert)およびマクドナルド(MacDonald)というワイナリーを興しています(ほかにもありますがここでは省略)。
この二つのワイナリーはト・カロンの名称を使えないのですが、マクドナルドのグレアム・マクドナルド(この人は現在若手の凄腕ワインメーカーとして知られています)が、ト・カロンは土地の名前であったはずなのにおかしいと考え、2017年にここを通る小川にト・カロン・クリークという名前を申請して許可されたのです。そのほとりに立つのが冒頭の写真です。

畑と小川の位置関係を示しました。
これに対して、ト・カロンが地名であるということになると困ると考えてコンステレーションが米国地名委員会に撤回の要望を出し、その決定が冒頭に挙げた結論になります。
ワイン・スペクテーターの記事によると、グレアム・マクドナルドは「危機に瀕しているのは、ト・カロンの遺産だけでなく、アメリカワインにおける土地の概念です。私たちのワインコミュニティは、その遺産の真正性を守らなければなりません。そうして初めて、私たちは土地に対する真の、何世代にもわたる敬意を築くことができるのです」と語っています。
また、アンディ・ベクストファーは「ト・カロン・クリークは存続すべきであり、利害関係のある関係者は皆、ト・カロン・ヴィンヤードを歴史的な場所として保存・保護することに注力すべきだ」と語っています。
裁判ではなく、控訴審があるわけではないので、今回の決定をこの後くつがえすのは難しいと思いますが、今後どうなっていくのでしょうか。
カナダのオタワ出身のパトリス・ブレトンが2003年に設立したナパのプレミアムなワイナリー、ヴァイス・ヴァーサ(Vice Versa)。このほどカリストガに新しいワイナリーとテイスティング・ルームをオープンしました。

約460平方メートルのワイナリーは、サンフランシスコを拠点とする建築家オーレ・ルンドバーグとレヴ・ベレズニッキー(ルンドバーグ・デザイン)によって設計され、ブレトンのミニマリズム的な美学と芸術的感性を反映しています。風景に溶け込むように設計されたコルテン鋼とコンクリートの建物は、丘の斜面に建てられています。内部は、ドラマチックな軸線が広々としたアーチ型の洞窟とプライベートテイスティングサロンへと続いており、大型ボトルと、ブラジル人アーティスト、ブルーノ・レオナルド・フランクリン・デ・メロによる厳選されたアートワークが展示されています。
また、カリストガにエステートのブドウ畑も作っています。主に樹齢30年のカベルネ・ソーヴィニヨンを栽培するこのエステート・ヴィンヤードは、カリストガ西部の涼しい地域に位置し、標高150メートルの岩だらけの白い凝灰岩土壌にあります。午後の海風により、この敷地は周辺地域よりも8~12°F(約2.7~4.6℃)低く保たれています。
ヴァイス・ヴァーサは2015年からフィリップ・メルカによるアトリエ・メルカがワイン造りを主導しており、現在はスペンサー・ケリーがワインメーカーとなっています。


約460平方メートルのワイナリーは、サンフランシスコを拠点とする建築家オーレ・ルンドバーグとレヴ・ベレズニッキー(ルンドバーグ・デザイン)によって設計され、ブレトンのミニマリズム的な美学と芸術的感性を反映しています。風景に溶け込むように設計されたコルテン鋼とコンクリートの建物は、丘の斜面に建てられています。内部は、ドラマチックな軸線が広々としたアーチ型の洞窟とプライベートテイスティングサロンへと続いており、大型ボトルと、ブラジル人アーティスト、ブルーノ・レオナルド・フランクリン・デ・メロによる厳選されたアートワークが展示されています。
また、カリストガにエステートのブドウ畑も作っています。主に樹齢30年のカベルネ・ソーヴィニヨンを栽培するこのエステート・ヴィンヤードは、カリストガ西部の涼しい地域に位置し、標高150メートルの岩だらけの白い凝灰岩土壌にあります。午後の海風により、この敷地は周辺地域よりも8~12°F(約2.7~4.6℃)低く保たれています。
ヴァイス・ヴァーサは2015年からフィリップ・メルカによるアトリエ・メルカがワイン造りを主導しており、現在はスペンサー・ケリーがワインメーカーとなっています。

ドミナス(Dominus)が新しい畑を取得したことが、ナパ郡の記録から判明しました(Dominus acquires vineyards in Yountville – Napa County Times)。
ドミナスはヨントヴィルの西側のベンチランドにナパヌック(Napanook)という自社畑を持っています。ドミナスおよび、セカンドのナパヌックはこの畑のブドウから造られています。このほか、1.5kmほど北側にユリシーズ(Ulysses)という畑があり、そちらはUlyssesのワインで使われています。
新たな畑はナパヌックの北側に隣接した2ブロックで、これまではマーカムが所有していました。86エーカーあり、今回の記録では3000万ドルで取得したようです。
ナパヌックは134エーカー(畑は102エーカー)、ユリシーズは40エーカーですから、畑の総面積が1.5倍ほどにも大きくなったことになります。

地図に畑の位置を「New Dominus」として記しました。
ドミナスはヨントヴィルの西側のベンチランドにナパヌック(Napanook)という自社畑を持っています。ドミナスおよび、セカンドのナパヌックはこの畑のブドウから造られています。このほか、1.5kmほど北側にユリシーズ(Ulysses)という畑があり、そちらはUlyssesのワインで使われています。
新たな畑はナパヌックの北側に隣接した2ブロックで、これまではマーカムが所有していました。86エーカーあり、今回の記録では3000万ドルで取得したようです。
ナパヌックは134エーカー(畑は102エーカー)、ユリシーズは40エーカーですから、畑の総面積が1.5倍ほどにも大きくなったことになります。

地図に畑の位置を「New Dominus」として記しました。
北カリフォルニアでは60年ぶりの涼しさとなった7月でしたが、ナパ・ソノマで収穫が始まっています。

ドメーヌ・シャンドンでは8月12日のナパのヨントヴィルの自社畑でムニエの収穫が始まりました。収穫量に関しては、降水量が少なく土壌温度が温暖なため、ブドウ畑では時期によって多少のばらつきはあるものの、順調に生育し、熟す見込みで、平均から例年より若干多い収穫量を予想しています。
シャンドンの主任ワインメーカー、ポーリン・ロートは「ナパ・ヴァレーのブドウにとって、全体的に涼しい夏の終わりとなりましたが、穏やかな生育環境は冷涼な気候のブドウとフレッシュで鮮やかなワインを育むのに有利です。カリフォルニアで干ばつや熱波に見舞われた数年間を何度も経験しましたが、今年の果実の品質と酸味は今のところ非常に優れています」と語っています。
ナパのホール・ファミリーではあと10日ほどでソーヴィニヨン・ブランの収穫を始める見込みです。「今シーズンは、生物季節学的データに基づくと、2023年と2024年の収穫期の間を推移しています。樹冠は非常に健全で、収穫量もバランスが取れています」とワインメーカーのミーガン・ガンダーソンは語っています。
ソノマではバーソロミュー・エステートが8月6日にソーヴィニヨン・ブランの収穫を始めました。このブドウはノン・アルコール飲料に使われる予定です。
ナパのスターリングのワインメーカーであるローレン・コピットは今シーズンの品質について次のように語っています。
「2025年の生育シーズンは、ブドウの成熟にとって理想的なシーズンでした。日中の最高気温が華氏70度後半から80度後半まで上昇したため、ブドウの木は順調に生育し、果実は順調に成長し、土壌の水分も良好でした。ブドウ畑は素晴らしい状態です。幸運にも、2023年と2024年は素晴らしい品質のヴィンテージに恵まれ、2025年もそれに続くでしょう。このシーズンは、傑出した赤ワインを生み出した2021年を思い出させます。今年も傑出したヴィンテージになると確信しています」

ドメーヌ・シャンドンでは8月12日のナパのヨントヴィルの自社畑でムニエの収穫が始まりました。収穫量に関しては、降水量が少なく土壌温度が温暖なため、ブドウ畑では時期によって多少のばらつきはあるものの、順調に生育し、熟す見込みで、平均から例年より若干多い収穫量を予想しています。
シャンドンの主任ワインメーカー、ポーリン・ロートは「ナパ・ヴァレーのブドウにとって、全体的に涼しい夏の終わりとなりましたが、穏やかな生育環境は冷涼な気候のブドウとフレッシュで鮮やかなワインを育むのに有利です。カリフォルニアで干ばつや熱波に見舞われた数年間を何度も経験しましたが、今年の果実の品質と酸味は今のところ非常に優れています」と語っています。
ナパのホール・ファミリーではあと10日ほどでソーヴィニヨン・ブランの収穫を始める見込みです。「今シーズンは、生物季節学的データに基づくと、2023年と2024年の収穫期の間を推移しています。樹冠は非常に健全で、収穫量もバランスが取れています」とワインメーカーのミーガン・ガンダーソンは語っています。
ソノマではバーソロミュー・エステートが8月6日にソーヴィニヨン・ブランの収穫を始めました。このブドウはノン・アルコール飲料に使われる予定です。
ナパのスターリングのワインメーカーであるローレン・コピットは今シーズンの品質について次のように語っています。
「2025年の生育シーズンは、ブドウの成熟にとって理想的なシーズンでした。日中の最高気温が華氏70度後半から80度後半まで上昇したため、ブドウの木は順調に生育し、果実は順調に成長し、土壌の水分も良好でした。ブドウ畑は素晴らしい状態です。幸運にも、2023年と2024年は素晴らしい品質のヴィンテージに恵まれ、2025年もそれに続くでしょう。このシーズンは、傑出した赤ワインを生み出した2021年を思い出させます。今年も傑出したヴィンテージになると確信しています」
WSETのディプロマを日本で4番目に取得し、ワインスクール講師やワインコンテストの審査員などで知られる沼田実さんが長野県辰野町でピノ・ノワールなどの栽培に取り組むキリノカヴィンヤードに訪問してきました。といっても行ったのは3か月半も前なのですが、なかなか記事に手が付けられなくて遅くなってしまいました。

沼田さんは20年間ピノ・ノワールの栽培に適した土地を探し続け、2020年にようやく見つけたのがこの土地。標高850メートルあり、霧訪山山麓に広がる南南東向きの斜面になっています。
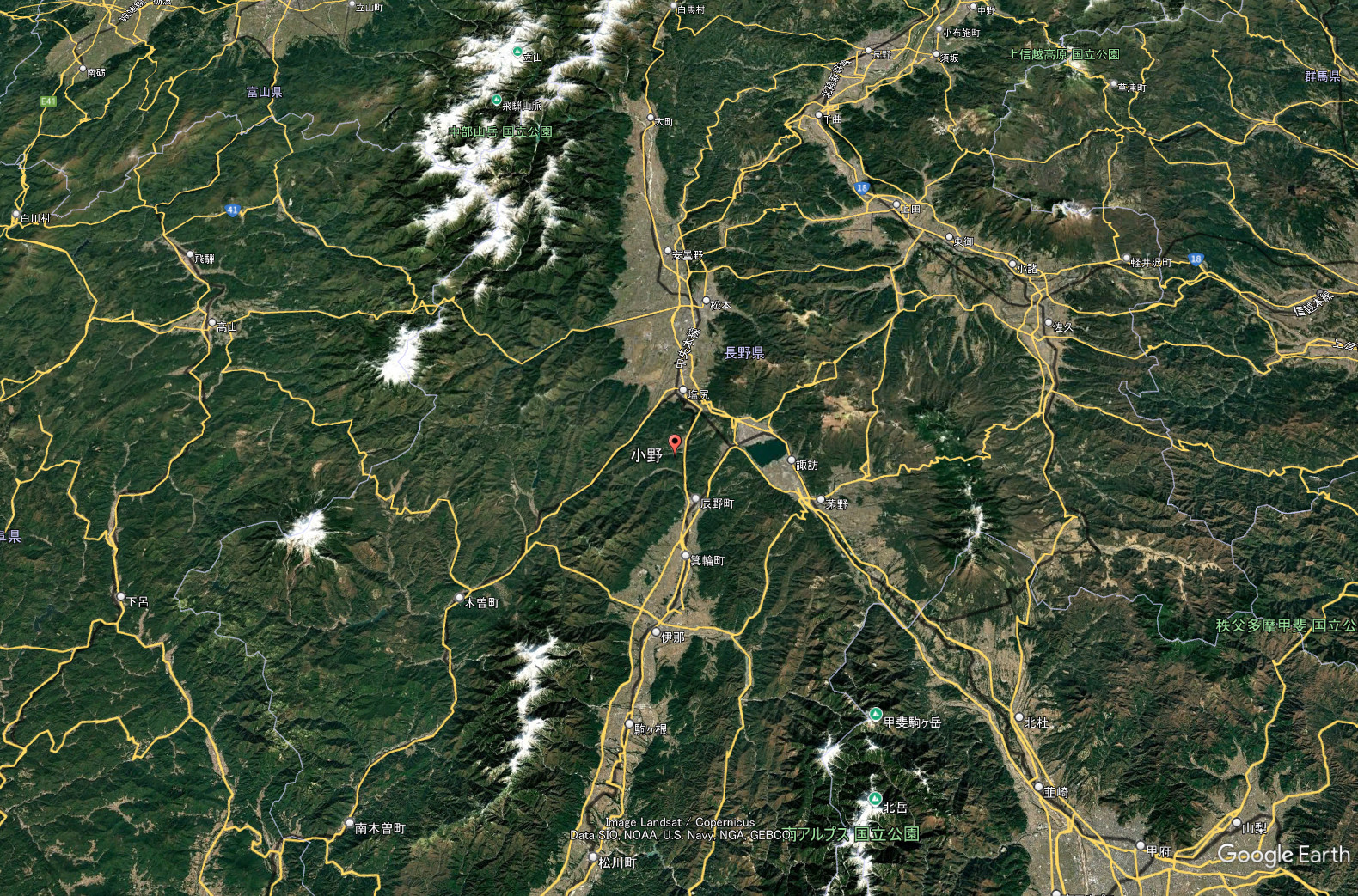
長野県は諏訪湖の南に赤石山脈(南アルプス)があり、諏訪湖の東には八ヶ岳があります。南西には赤石山脈の西側に天竜川が流れ、その西には木曾山脈(中央アルプス)があり、天竜川沿いに細い谷(伊那盆地、伊那谷)があります。また諏訪湖の北には塩尻を含む松本盆地などがあります。キリノカのある小野は、諏訪湖のある諏訪盆地と松本盆地、伊那谷に挟まれた山麓部。辰野町と諏訪市の間にある霧訪山(きりとうやま)の南斜面の畑で、北風からブドウ畑を守っています。春から秋は南北に細長い伊那谷を通って南から風が吹き、病害虫を防いでいます。畑の畝も、風通しを考慮して南北方向になっています。
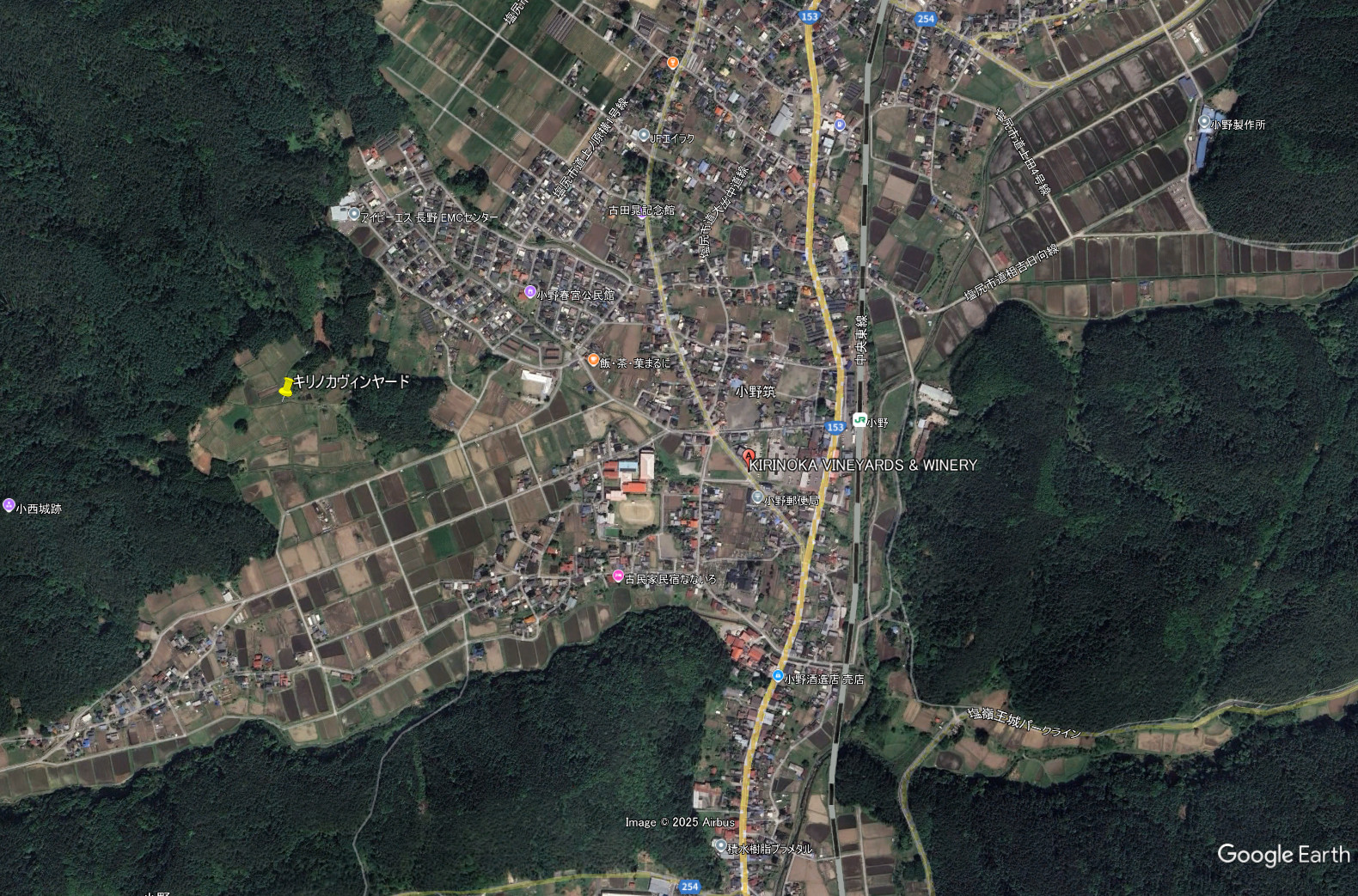
土壌はジュラ紀の海洋性のもの。ワイン用のブドウ栽培ではアルカリ性の土壌が望ましい(石灰岩はアルカリ性)とのことですが、火山性の土壌は大部分が酸性で、海洋性の土壌の方がいいと考えているそうです。ただ、表土に多い火山灰にはアルミニウムが含まれており、これがリン酸を固定してしまうそうです。そこで一般的にはとうもろこし、ひまわり、菜の花を植えてリンを吸わせてすき込んで循環させます。カリフォルニアだとマスタードが同じように使われています。ただここでは菜の花の時期は殺虫剤を撒く季節と重なってしまうという難点があるとか。現在はクローバーをカバークロップとして使っています。窒素固定の目的もありますが、他の雑草が生えてこないようにするという意味も大きいそうです。ちなみにシャルドネは畑の奥の方の東斜面に植えています。近くに石灰の採掘場があり、石灰質土壌ではないですが、カルシウム分が流れてくるので白向きだとか。ピノ・ノワールは鉄分が多い赤向きの土壌に植えています。
キリノカでは軽く耕起をすることで二酸化炭素を逃がしています。土の中の菌には良くない働きをするものもありますが、それらの多くは嫌気性(酸素を嫌がる)なのだとか。少し耕すことで好気性の性質のいい菌を増やしているそうです。カリフォルニアだと近年は畑を耕さないリジェネラティブが流行ってきていますが、土地が変われば考え方もまた変わるのだと、いろいろと勉強になります。
また、キリノカでは8月末くらいにサブソイラーという地面に振動を与える機械を使って土の内部に亀裂を作ります。これは水はけを良くするためのものです。他のワイナリーではあまり使っていないとか。カリフォルニアではピーター・マイケルがオークヴィルの畑で水はけ用のパイプを通す暗渠排水を入れている話などを聞いたことがありますが、費用が掛かりすぎるのと、耕したときに傷つける恐れがあるため、ここではちょっと簡易的なサブソイラーを使っているとのこと。
ただ、サブソイラーを入れるとトラクターなどが使えなくなるため作業性が悪くなります。ここは比較的高く売れるピノノワールだから、コストをかけてもペイできるのです。全てにおいてコスト、プライシング、マーケティングの組み合わせがあって1本のボトルになるというのも、言われてみれば当たり前ですが、見逃しがちなことです。
ピノ・ノワールの苗木のチョイスでも様々な考えがあります。日本ではMV6というクローンが栽培しやすいが、華やかさに欠けるのでそこまで需要があるか? スイス系のクローンは酸が強いのですが、温暖化のことを考えると重要性は増してきます。今は実際には777がメインで植えられています。
沼田さんの話で印象的だったのは、前述のように「コスト、プライシング、マーケティング」それとワインのクオリティの組み合わせを常に意識しているというところです。還暦を過ぎて数千万円の借金を背負ってというところで、ビジネスとして成り立つようにしていくのは並大抵の覚悟では足りないし、実際、2024年には霜の害でピノ・ノワールがほぼ全滅してしまうという大変な状況にも見舞われています。
最近は、ナチュラルワインを志すのが当たり前みたいな風潮も感じられるような気がするのですが、雨が多く気温も高い日本では病害との闘いは避けて通れないですし、きれいごとだけではビジネスとして成り立ちません。そういった話も隠さずに話していただけるのがとても考えさせられます。
最近は、ナチュラルワインを志すのが当たり前みたいな風潮も感じられるような気がするのですが、雨が多く気温も高い日本では病害との闘いは避けて通れないですし、きれいごとだけではビジネスとして成り立ちません。そういった話も隠さずに話していただけるのがとても考えさせられます。
さて、ワイナリーに戻ってテイスティングです。キリノカの初ヴィンテージは2023年で、この年のピノ・ノワールを「零」と「壱」という名前で2024年にリリースしました。2024年は前述のように自社畑がごくわずかしか収穫できず、購入ブドウによる「信州OGOSSO」シリーズのワインが中心になります。ピノ・ノワールは1万円を超えるプレミアムですが、OGOSSOは税込み3850円とかなりリーズナブルです。

Pinot Grigio/Chardonnay。まずはピノ・グリージョとシャルドネのブレンド。フレッシュで、柑橘やハーブの風味。アフターに苦み。温度が上がると少し蜜感が出てきてボリュームも感じます。基本はさっぱり系ですが応用範囲の広そうなワイン。

Rose Merlot。メルローのロゼです。ザクロやベリー系の風味。酸高くフレッシュな味わいに、軽くタンニンが味を引き締めます。ダイレクトプレスとセニエを組み合わせているということで、プロヴァンスのロゼと比べると少し力強さも感じます。これも何にでも合わせやすそうなワイン。

Pale Orange Chardonnay。シャルドネを使ったオレンジワインです。果実を破砕せずに1週間低温で醸し、その後果皮と一緒にアルコール発酵してからプレスしています。酸高くアプリコットやグレープフルーツのような風味。ライトで癖のないオレンジワインです。

Dolce Rosato Cabernet Sauvignin/Syrah。カベルネ・ソーヴィニョン2/3にシラー1/3を混醸で発酵させ、途中で発酵を止めて糖分を残しています。アセロラやクランベリージュースのような味わい。シナモンのようなスパイスの風味もあります。中華の八角などに合いそうです。
わずかに作られた2024年の自社畑のピノ・ノワールも試飲しました。
ドメーヌ・キリノカ ピノ・ノワール ロゼ キュヴェ 鴇羽(トキハ)はセニエ方式で作ったロゼ。チェリーやイチゴジャム、ちょっと青っぽさも感じます。
ロゼでないピノ・ノワールについては1ミクロンのフィルターをかけたものと5ミクロンのフィルターをかけたものを比べました。1ミクロンの方は、色がオレンジ色といってもいいくらいに薄く、果実味もあまり感じません。青っぽいトーンも感じられます。5ミクロンの方はイチゴの風味、ちょっと青さもありますがバランスよい味わいでした。フィルターの違いでもこれだけ味わいや色にも違いが出るのは驚きでした。


2023年の自社畑のピノ・ノワールです。以前にこれを飲んで感服したのが、ここを訪問した理由の一つです。
キュヴェ「零」は、300Lのフランス産オーク材新樽で7か月間熟成しています。一方、キュヴェ「壱」は、228Lのフランス産オーク材新樽で7か月間熟成しています。後は零の方は樽内でMLF、壱はタンク内でMLFしているとか。
零の方が甘やかさがあり、柔らかなテクスチャーを感じます。壱は引き締まった味わいで、ワインの余韻をより長く感じます。どちらも日本のピノ・ノワールとしては驚くほどにレベルの高いワインです。
また、季節を変えてうかがってみたいワイナリーです。
沼田さんは20年間ピノ・ノワールの栽培に適した土地を探し続け、2020年にようやく見つけたのがこの土地。標高850メートルあり、霧訪山山麓に広がる南南東向きの斜面になっています。
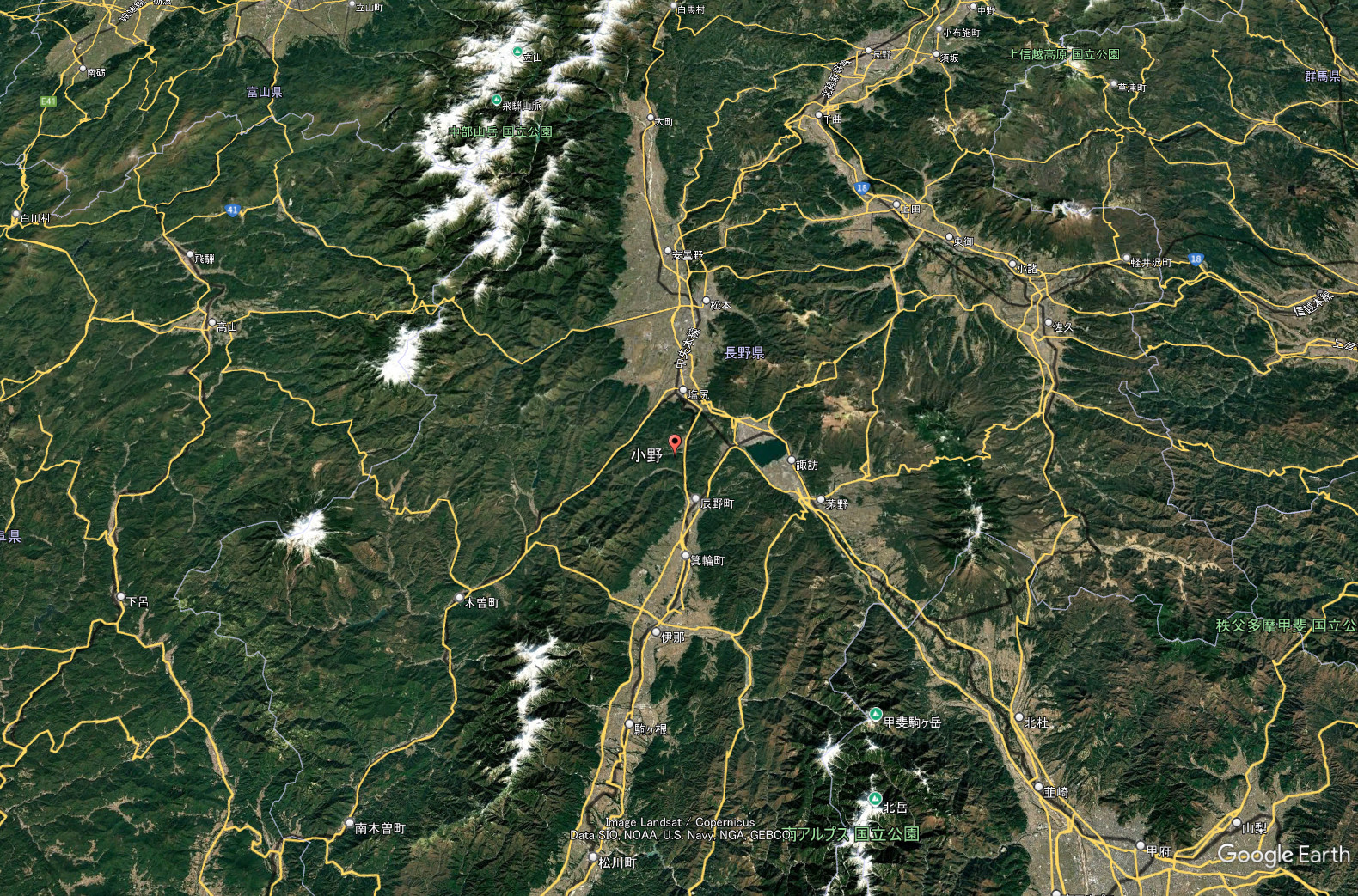
長野県は諏訪湖の南に赤石山脈(南アルプス)があり、諏訪湖の東には八ヶ岳があります。南西には赤石山脈の西側に天竜川が流れ、その西には木曾山脈(中央アルプス)があり、天竜川沿いに細い谷(伊那盆地、伊那谷)があります。また諏訪湖の北には塩尻を含む松本盆地などがあります。キリノカのある小野は、諏訪湖のある諏訪盆地と松本盆地、伊那谷に挟まれた山麓部。辰野町と諏訪市の間にある霧訪山(きりとうやま)の南斜面の畑で、北風からブドウ畑を守っています。春から秋は南北に細長い伊那谷を通って南から風が吹き、病害虫を防いでいます。畑の畝も、風通しを考慮して南北方向になっています。
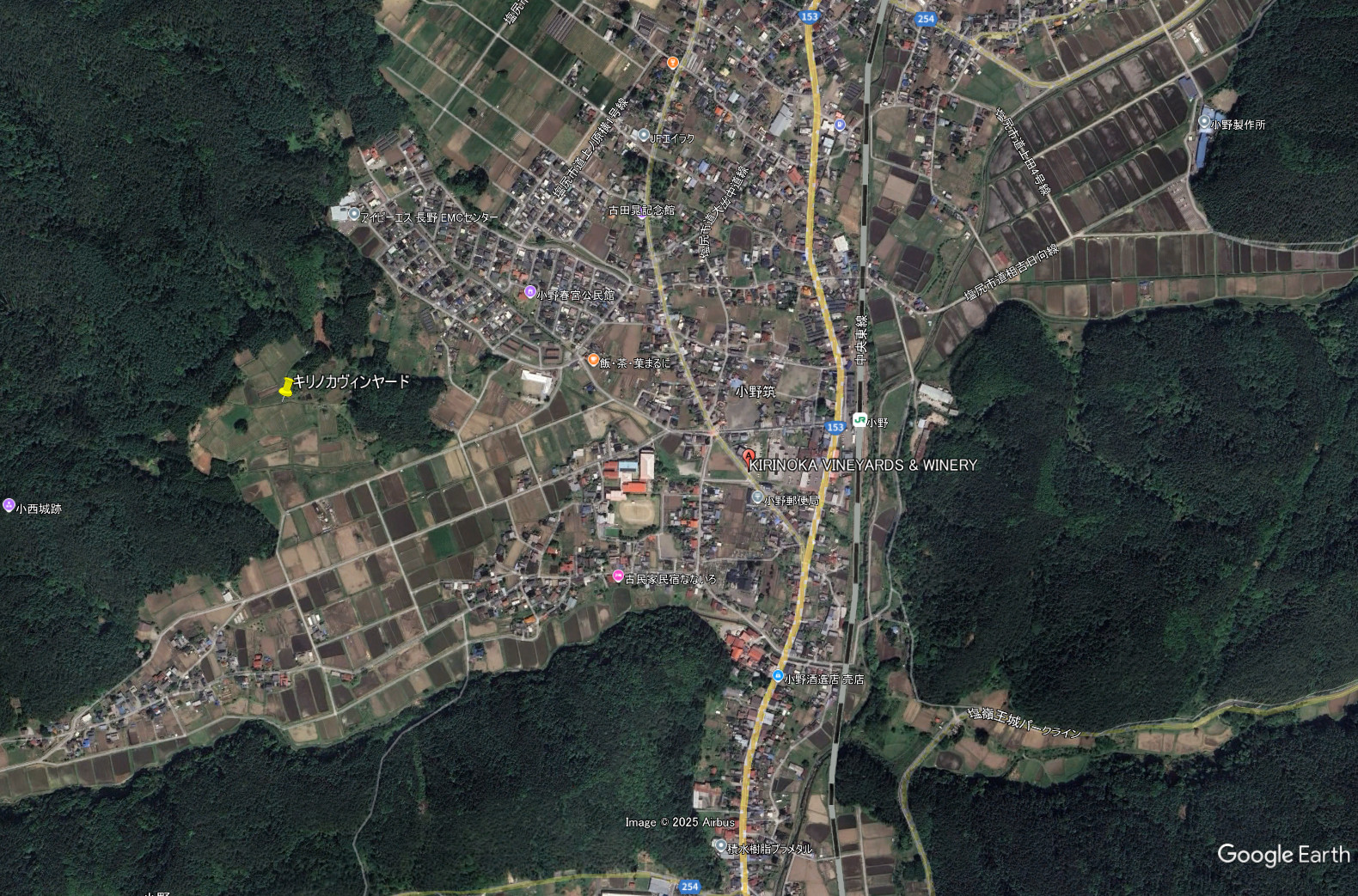
土壌はジュラ紀の海洋性のもの。ワイン用のブドウ栽培ではアルカリ性の土壌が望ましい(石灰岩はアルカリ性)とのことですが、火山性の土壌は大部分が酸性で、海洋性の土壌の方がいいと考えているそうです。ただ、表土に多い火山灰にはアルミニウムが含まれており、これがリン酸を固定してしまうそうです。そこで一般的にはとうもろこし、ひまわり、菜の花を植えてリンを吸わせてすき込んで循環させます。カリフォルニアだとマスタードが同じように使われています。ただここでは菜の花の時期は殺虫剤を撒く季節と重なってしまうという難点があるとか。現在はクローバーをカバークロップとして使っています。窒素固定の目的もありますが、他の雑草が生えてこないようにするという意味も大きいそうです。ちなみにシャルドネは畑の奥の方の東斜面に植えています。近くに石灰の採掘場があり、石灰質土壌ではないですが、カルシウム分が流れてくるので白向きだとか。ピノ・ノワールは鉄分が多い赤向きの土壌に植えています。
キリノカでは軽く耕起をすることで二酸化炭素を逃がしています。土の中の菌には良くない働きをするものもありますが、それらの多くは嫌気性(酸素を嫌がる)なのだとか。少し耕すことで好気性の性質のいい菌を増やしているそうです。カリフォルニアだと近年は畑を耕さないリジェネラティブが流行ってきていますが、土地が変われば考え方もまた変わるのだと、いろいろと勉強になります。
また、キリノカでは8月末くらいにサブソイラーという地面に振動を与える機械を使って土の内部に亀裂を作ります。これは水はけを良くするためのものです。他のワイナリーではあまり使っていないとか。カリフォルニアではピーター・マイケルがオークヴィルの畑で水はけ用のパイプを通す暗渠排水を入れている話などを聞いたことがありますが、費用が掛かりすぎるのと、耕したときに傷つける恐れがあるため、ここではちょっと簡易的なサブソイラーを使っているとのこと。
ただ、サブソイラーを入れるとトラクターなどが使えなくなるため作業性が悪くなります。ここは比較的高く売れるピノノワールだから、コストをかけてもペイできるのです。全てにおいてコスト、プライシング、マーケティングの組み合わせがあって1本のボトルになるというのも、言われてみれば当たり前ですが、見逃しがちなことです。
ピノ・ノワールの苗木のチョイスでも様々な考えがあります。日本ではMV6というクローンが栽培しやすいが、華やかさに欠けるのでそこまで需要があるか? スイス系のクローンは酸が強いのですが、温暖化のことを考えると重要性は増してきます。今は実際には777がメインで植えられています。
沼田さんの話で印象的だったのは、前述のように「コスト、プライシング、マーケティング」それとワインのクオリティの組み合わせを常に意識しているというところです。還暦を過ぎて数千万円の借金を背負ってというところで、ビジネスとして成り立つようにしていくのは並大抵の覚悟では足りないし、実際、2024年には霜の害でピノ・ノワールがほぼ全滅してしまうという大変な状況にも見舞われています。
最近は、ナチュラルワインを志すのが当たり前みたいな風潮も感じられるような気がするのですが、雨が多く気温も高い日本では病害との闘いは避けて通れないですし、きれいごとだけではビジネスとして成り立ちません。そういった話も隠さずに話していただけるのがとても考えさせられます。
最近は、ナチュラルワインを志すのが当たり前みたいな風潮も感じられるような気がするのですが、雨が多く気温も高い日本では病害との闘いは避けて通れないですし、きれいごとだけではビジネスとして成り立ちません。そういった話も隠さずに話していただけるのがとても考えさせられます。
さて、ワイナリーに戻ってテイスティングです。キリノカの初ヴィンテージは2023年で、この年のピノ・ノワールを「零」と「壱」という名前で2024年にリリースしました。2024年は前述のように自社畑がごくわずかしか収穫できず、購入ブドウによる「信州OGOSSO」シリーズのワインが中心になります。ピノ・ノワールは1万円を超えるプレミアムですが、OGOSSOは税込み3850円とかなりリーズナブルです。
Pinot Grigio/Chardonnay。まずはピノ・グリージョとシャルドネのブレンド。フレッシュで、柑橘やハーブの風味。アフターに苦み。温度が上がると少し蜜感が出てきてボリュームも感じます。基本はさっぱり系ですが応用範囲の広そうなワイン。
Rose Merlot。メルローのロゼです。ザクロやベリー系の風味。酸高くフレッシュな味わいに、軽くタンニンが味を引き締めます。ダイレクトプレスとセニエを組み合わせているということで、プロヴァンスのロゼと比べると少し力強さも感じます。これも何にでも合わせやすそうなワイン。
Pale Orange Chardonnay。シャルドネを使ったオレンジワインです。果実を破砕せずに1週間低温で醸し、その後果皮と一緒にアルコール発酵してからプレスしています。酸高くアプリコットやグレープフルーツのような風味。ライトで癖のないオレンジワインです。
Dolce Rosato Cabernet Sauvignin/Syrah。カベルネ・ソーヴィニョン2/3にシラー1/3を混醸で発酵させ、途中で発酵を止めて糖分を残しています。アセロラやクランベリージュースのような味わい。シナモンのようなスパイスの風味もあります。中華の八角などに合いそうです。
わずかに作られた2024年の自社畑のピノ・ノワールも試飲しました。
ドメーヌ・キリノカ ピノ・ノワール ロゼ キュヴェ 鴇羽(トキハ)はセニエ方式で作ったロゼ。チェリーやイチゴジャム、ちょっと青っぽさも感じます。
ロゼでないピノ・ノワールについては1ミクロンのフィルターをかけたものと5ミクロンのフィルターをかけたものを比べました。1ミクロンの方は、色がオレンジ色といってもいいくらいに薄く、果実味もあまり感じません。青っぽいトーンも感じられます。5ミクロンの方はイチゴの風味、ちょっと青さもありますがバランスよい味わいでした。フィルターの違いでもこれだけ味わいや色にも違いが出るのは驚きでした。
2023年の自社畑のピノ・ノワールです。以前にこれを飲んで感服したのが、ここを訪問した理由の一つです。
キュヴェ「零」は、300Lのフランス産オーク材新樽で7か月間熟成しています。一方、キュヴェ「壱」は、228Lのフランス産オーク材新樽で7か月間熟成しています。後は零の方は樽内でMLF、壱はタンク内でMLFしているとか。
零の方が甘やかさがあり、柔らかなテクスチャーを感じます。壱は引き締まった味わいで、ワインの余韻をより長く感じます。どちらも日本のピノ・ノワールとしては驚くほどにレベルの高いワインです。
また、季節を変えてうかがってみたいワイナリーです。
アイコニックワイン・ジャパンが新たに輸入を始めたマッシカン(Massican)とデナー(Denner)のワインを試飲してきました。

マッシカンは2009年にダン・ペトロスキー(Dan Petroski)が設立。ナパにありながら白ワインだけを作っているというユニークなワイナリーです。畑は持たず、購入したブドウでワインを造っています。特に自らのルーツであるイタリア原産の品種を使ったワインを得意としています。2019年にはワイン・エンスージアストの年間7位に選ばれるなど実力も折り紙付き。2023年には、E&Jガロに買収されて注目を浴びました。
ガロというと、昔ながらの低価格な「ジャグワイン」や、近年だと濃厚スタイルで人気の「ダークマター」など、マッシカンと対極的なワインの印象が強いですが、実はプレミアムなブレンドも多く抱えているのです。ただ、マッシカンの場合は、畑を持っておらず、ダン・ペトロスキーの才能とコネクションだけが頼りです。なお、ペトロスキーには5年間はマッシカンに在籍しないといけないという条件が課せられています。
ワインは右のジェミーナ(Gemmina)2023から試飲しました。60%グレコ、23%ファランギーナ、17%フィアーノという構成。価格は7900円。酸がきれいでホワイトペッパーなどのスパイスが印象的。ライムのような酸味が素晴らしい。
左のアニアはトカイ・フリウラーノ43%、リボッラ・ジャッラ34%、シャルドネ23%というユニークな構成。ジェミーナと比べると少し酸が低く、グリップ感のある味わい。アニスやグレープフルーツ、紫蘇などのハーブの味わいを感じます。6800円。
個人的にはジェミーナのキリっとした酸が好きです。マッシカンはラベルもセンス良くワインも個性的で美味しく、試していただきたいワインです。
もう一つのデナー・ヴィンヤーズはパソ・ロブレスのウィロー・クリーク・ディストリクトAVAにあります。

温暖なパソ・ロブレスですが、ウィロー・クリークは比較的太平洋に近く、テンプルトン・ギャップという山の切れ目からの風も入ります。標高も300~600mほどと比較的高く、パソ・ロブレスの中では冷涼な地域になります。2005年にロン・デナーが設立しました。認証は取っていませんが有機栽培やサスティナブルを実践し、天然酵母のみで発酵させるナチュラルな造りのワインです。シラーなどローヌ系品種のワインではパソ・ロブレスの中でもトップクラスの評価を得ているワイナリーです。ここも現在はガロの傘下に入っています。

ワインは2021年のものが4種類。ヴィオニエ、ディッチ・ディガー(Ditch Digger)というグルナッシュなどのブレンド、ダート・ウォーシッパー(Dirt Worshipper)というシラー中心のブレンド、マザー・オブ・エグザイル(Mother of Exile)というカベルネ系のブレンドです。
ヴィオニエ(11000円)は花の香りに厚みのあるボディ。白桃のトロっとしたテクスチャーが魅力的。どちらかというとフルボディのヴィオニエです。
ディッチ・ディガー(16800円)は今回一番驚いたワイン。パソ・ロブレスとは思えないほど、というと失礼な言い方ですが、エレガントさが際立っています。33%グルナッシュ、32%ムールヴェードル、22%シラー、5%サンソー、4%クノワーズ、2%タナ、2%カリニャン。ジューシーでザクロやレッド・チェリーなどの赤果実がきれいに広がります。ちょっと塩っぽい印象が全体を引き締めます。カリフォルニアのグルナッシュ系ワインでここまできれいなものは初めてです。
ダート・ウォーシッパー(16800円)は以前別ヴィンテージを飲んだことがあり、品質の高さは体験済みです。第一印象はスパイシー、黒コショウやコリアンダーなどのスパイスの風味が広がります。スミレの香り、ブルーベリー。フルボディですが、酸も高くパワフルというよりはエレガントな印象。ローヌ系を得意とするジェブ・ダナックが97点を付けただけのことはあります。88%シラーで、2番目に多いのがプティ・ヴェルドの7%というのがユニークです。
最後のマザー・オブ・エグザイル(16800円)はパソ・ロブレスのカベルネとしては酸が高くエレガント。スミレや赤と青の果実。ボディもおだやかでタンニンが全体を引き締めています。81%カベルネ・ソーヴィニョン、12%プティ・ヴェルド、4%カベルネ・フラン、3%タナ。
高級ローヌ系は、なかなか国内では評価されるのが難しい分野ですが、品質の高いワインなので、売れてほしいと思います。
マッシカンは2009年にダン・ペトロスキー(Dan Petroski)が設立。ナパにありながら白ワインだけを作っているというユニークなワイナリーです。畑は持たず、購入したブドウでワインを造っています。特に自らのルーツであるイタリア原産の品種を使ったワインを得意としています。2019年にはワイン・エンスージアストの年間7位に選ばれるなど実力も折り紙付き。2023年には、E&Jガロに買収されて注目を浴びました。
ガロというと、昔ながらの低価格な「ジャグワイン」や、近年だと濃厚スタイルで人気の「ダークマター」など、マッシカンと対極的なワインの印象が強いですが、実はプレミアムなブレンドも多く抱えているのです。ただ、マッシカンの場合は、畑を持っておらず、ダン・ペトロスキーの才能とコネクションだけが頼りです。なお、ペトロスキーには5年間はマッシカンに在籍しないといけないという条件が課せられています。
ワインは右のジェミーナ(Gemmina)2023から試飲しました。60%グレコ、23%ファランギーナ、17%フィアーノという構成。価格は7900円。酸がきれいでホワイトペッパーなどのスパイスが印象的。ライムのような酸味が素晴らしい。
左のアニアはトカイ・フリウラーノ43%、リボッラ・ジャッラ34%、シャルドネ23%というユニークな構成。ジェミーナと比べると少し酸が低く、グリップ感のある味わい。アニスやグレープフルーツ、紫蘇などのハーブの味わいを感じます。6800円。
個人的にはジェミーナのキリっとした酸が好きです。マッシカンはラベルもセンス良くワインも個性的で美味しく、試していただきたいワインです。
もう一つのデナー・ヴィンヤーズはパソ・ロブレスのウィロー・クリーク・ディストリクトAVAにあります。

温暖なパソ・ロブレスですが、ウィロー・クリークは比較的太平洋に近く、テンプルトン・ギャップという山の切れ目からの風も入ります。標高も300~600mほどと比較的高く、パソ・ロブレスの中では冷涼な地域になります。2005年にロン・デナーが設立しました。認証は取っていませんが有機栽培やサスティナブルを実践し、天然酵母のみで発酵させるナチュラルな造りのワインです。シラーなどローヌ系品種のワインではパソ・ロブレスの中でもトップクラスの評価を得ているワイナリーです。ここも現在はガロの傘下に入っています。
ワインは2021年のものが4種類。ヴィオニエ、ディッチ・ディガー(Ditch Digger)というグルナッシュなどのブレンド、ダート・ウォーシッパー(Dirt Worshipper)というシラー中心のブレンド、マザー・オブ・エグザイル(Mother of Exile)というカベルネ系のブレンドです。
ヴィオニエ(11000円)は花の香りに厚みのあるボディ。白桃のトロっとしたテクスチャーが魅力的。どちらかというとフルボディのヴィオニエです。
ディッチ・ディガー(16800円)は今回一番驚いたワイン。パソ・ロブレスとは思えないほど、というと失礼な言い方ですが、エレガントさが際立っています。33%グルナッシュ、32%ムールヴェードル、22%シラー、5%サンソー、4%クノワーズ、2%タナ、2%カリニャン。ジューシーでザクロやレッド・チェリーなどの赤果実がきれいに広がります。ちょっと塩っぽい印象が全体を引き締めます。カリフォルニアのグルナッシュ系ワインでここまできれいなものは初めてです。
ダート・ウォーシッパー(16800円)は以前別ヴィンテージを飲んだことがあり、品質の高さは体験済みです。第一印象はスパイシー、黒コショウやコリアンダーなどのスパイスの風味が広がります。スミレの香り、ブルーベリー。フルボディですが、酸も高くパワフルというよりはエレガントな印象。ローヌ系を得意とするジェブ・ダナックが97点を付けただけのことはあります。88%シラーで、2番目に多いのがプティ・ヴェルドの7%というのがユニークです。
最後のマザー・オブ・エグザイル(16800円)はパソ・ロブレスのカベルネとしては酸が高くエレガント。スミレや赤と青の果実。ボディもおだやかでタンニンが全体を引き締めています。81%カベルネ・ソーヴィニョン、12%プティ・ヴェルド、4%カベルネ・フラン、3%タナ。
高級ローヌ系は、なかなか国内では評価されるのが難しい分野ですが、品質の高いワインなので、売れてほしいと思います。

ソノマの主要業界団体であるソノマ郡ワイングロワーズ(Sonoma County Winegrowers)とソノマ郡ヴィントナーズ(Sonoma County Vintners)が共同で「ワイン産業改善地区計画」(Wine Improvement District=WID)の導入を提案しており、それが生産者の間で物議を醸しています。
ワイン需要の停滞によって、ソノマも大きな影響を受けています。それへの対策として導入を図っているのがこのWIDで、ワイナリーのテイスティングルームの売り上げから1~2%の課徴金を徴収するというものです。WIDの運営委員会は、1%課徴金を課したときに年間で400万ドルを生み出すと試算しています。この資金はソノマのマーケティング活動に使われる見込みです。
これまでに南カリフォルニアのテメキュラ・ヴァレーでWIDが導入されて、成果を上げたと言われています。
これに対して、小規模なワイナリーを中心に反対の声が上がっています。
反対の理由は
・課徴金は消費者から徴収するため、消費者のワイン離れを一層進めてしまうかもしれない
・テイスティング・ルームでの売り上げが大きな比率になる小規模なワイナリーほど負担が大きくなる
といったところになります。また、大きなワイナリーの中でも、ジャクソン・ファミリー・ワインズは、小規模な生産者が反対するものには賛成しないという立場です。
クラリス・ワイン・カンパニーのアダム・リーは、WIDへの嘆願書をChange.orgで公開しており、今現在706名が反対している状態です。
オンライン署名 · PETITION AGAINST THE WINE IMPROVEMENT DISTRICT (WID) IN SONOMA COUNTY - アメリカ合衆国 · Change.org
この嘆願書によると、成功していると言われているテメキュラにおいても、実は成功していると言われるのは数字の綾であるとのことです。
今後、WIDが承認されるには、生産量に基づいて加重された投票で51%のワイナリーが賛成する必要があり、その後、郡の監督委員会と9つの自治体の市議会の承認が必要と、まだまだ手順が多くあります。承認までには数年かかる可かもしれません。
レイル・ヴィンヤーズ(Lail Vineyards)のワインを一度に9本も飲むという貴重なワイン会に参加させていただきました。
レイルのワインはピーロートが輸入していますが、おそらく数は相当少ないので、市場で見かけることはあまりないと思います。知名度も「知る人ぞ知る」といったところだと思います。実際にはワイン・アドヴォケイトで100点を4本も取っており、名門の名にふさわしいワイナリーです。
レイルの話をするときに、避けて通れないのが「イングルヌック(Inglenook)」。現在はフランシス・フォード・コッポラ監督のワイナリーの名前として知られていますが、元々は19世紀にフィンランド出身の船乗り「グスタフ・ニーバウム」が設立したワイナリーでした。グスタフ時代も万博で銀メダルを得るなど、高い評価を得ましたが、その名を高めたのが禁酒法後の1939年からワイナリーを率いたジョン・ダニエル・ジュニアでした。グスタフの遠い親戚でしたが、幼いときに母親を亡くして、グスタフ未亡人に育てられたのでした。
ジョン・ダニエル・ジュニアは禁酒法後の、高品質ワインがほとんど作られなかった時代に、品質最優先でワインを造っていました。1941年のカベルネ・ソーヴィニョンは「史上最高の赤ワインの一つ」とまで呼ばれたのです。
ただ、品質が高いワインを造っても、その市場がないとどうしようもありません。資金繰りに苦しみ、1963年にはワイナリーを売却してしまい、69年に亡くなってしまいます。
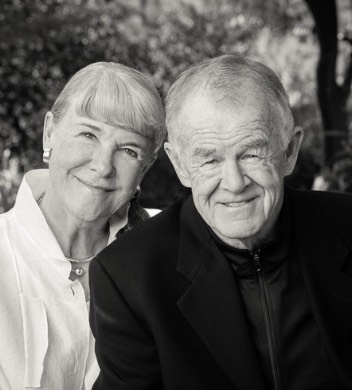
ジョン・ダニエル・ジュニアの長女のロビン・レイルが、レイルのオーナーなのですが、彼女は、ワイナリーの売却がとてもショックだったといいます。彼女に唯一残されたのが、ナパのヨントヴィルにある畑ナパヌック(Napanook)。この銘醸畑を使って、フランスのペトリュスのオーナー家であるムエックスと立ち上げたのがドミナス(Dominus)でした。その後、彼女はロバート・モンダヴィの下で働き、ビル・ハーランによるメルヴィルの設立にも参加します。ただ、これらもまた売却してしまい、1990年代に立ち上げたのがレイル・ヴィンヤーズなのです。
レイルのフラッグシップのカベルネ・ソーヴィニョンが「ジョン・ダニエル・キュベ」。いうまでもなく、偉大な父親に敬意を表して付けた名前です。ロビン・レイルがドミナスを手放してしまったことは、傍目からはもったいないという気もしますが、私が想像するには、ムエックスが主導権を握るドミナスではなく、自分の力で父親のレガシーを引き継ぎたかったのではないかと思います。
レイルの自社畑は二つ。そのうちナパのヨントヴィルにあるトーテム・ヴィンヤードは、イングルヌックが所有していた畑(ナパヌックをHighway29が横切る東側の区域)で、現在はソーヴィニヨン・ブランが植えられています。ナパのソーヴィニヨン・ブランの中でもトップクラスの品質と希少さを持つレイルの「ジョージア」がこの畑から造られています。
もう一つはハウエル・マウンテンの「モール・ヒル」という畑。こちらはカベルネ・ソーヴィニョンが植えられており、ジョン・ダニエル・キュベに使われています。ジョン・ダニエル・キュベにはこのほかカリストガやオークヴィル、スタッグス・リープ・ディストリクトから調達したブドウも使われています。
レイル・ヴィンヤーズのワインメーカーは設立当初からフィリップ・メルカ(今はその弟子のマーヤン・コシツキーも)が務めています。今や数十の顧客を抱えるフィリップ・メルカですが、実はメルカにとっても、レイルは初めてワインメーカーになったワイナリー。ロビン・レイルが見込んだ才能は間違いなかったのです。
前述のように、カベルネ・ソーヴィニョンのジョン・ダニエル・キュベとソーヴィニョン・ブランのジョージアがレイルの2大柱。このほかブループリントというセカンドのカベルネとソーヴィニヨン・ブランがあります。この日は、モール・ヒルの単一畑のカベルネ・ソーヴィニョンもありました。
まずは2022年のブループリント・ソーヴィニョン・ブランです。
青リンゴや洋ナシの風味。セカンドの位置づけですが柔らかくまったりとしたテクスチャーが高級感を感じさせます。アフターにちょっと苦みがあり、味を引き締めていました。
次は2016年のジョージアです。私も多分ジョージアを飲むのは初めて。
蜜のようなテクスチャーと、白桃。カモミールのスパイス感。パワフルでスケールの大きなワイン。ブループリントも十分美味しいですが、やっぱりこれはすごいです。
3本目は2021年のカベルネ・ソーヴィニョンのブループリント。
リッチでフルボディ。ブルーベリーの風味にヨーグルトのような乳酸菌のニュアンス。セカンドとは言え、レベル高いです。デカンター誌で95点というのはセカンドとしては破格の高評価。
ここから5ヴィンテージのジョン・ダニエル・キュベが続きます。
最初は1995年。レイルの最初のヴィンテージという貴重なワインです。
30年の熟成を経て、腐葉土やマッシュルームなどの第3アロマが顕著に出てきています。果実味も残っており、カシスの風味があります。酸がきれいでボルドー的なスタイルのワイン。
次は2009年。カシスなどの果実味がまだまだしっかりしています。熟成感も出てきていますが、もう少し熟成するともっと良くなるのではないかと思います。
次の2011年は2000年以降では一番冷涼で、ナパでカベルネ・ソーヴィニョンがしっかり成熟しなかったというレアな年。収量も少なく、ワインメーカーは今までで一番難しい年だったと言うことが多いですが、逆にこういう年は熟成感が早くでてきてきれいなワインになっていくケースも多くあります。ジョン・ダニエル・キュベの2011年も非常にバランスよく、酸が張っていて、緊張感のある味わい。ヨーグルトの風味や、カシスも感じられ、とてもいい熟成をしています。
次の2012年はジョン・ダニエル・キュベがワイン・アドヴォケイトで初めて100点を取った年。2011年と打って変わった良コンディションのヴィンテージですが、前年の不作を補うように収量を多く取ったワイナリーも多く、玉石混交のヴィンテージと言われていますが、これは間違いなく玉のワイン。これもまたバランスが素晴らしく、ザクロやレッド・チェリーなど赤い果実の風味がきれいです。スパイシーさやリコリスの甘やかさもあり、2012年のワインとしてはこれまで飲んだ中でベストに感じました。
ジョン・ダニエル・キュベの最後は2015年です。気温が高く、収量が少なかったため、非常に凝縮したワインができたヴィンテージと言われています。ジョン・ダニエル・キュベもこれまでのヴィンテージとはだいぶ異なる、モダンナパ的なスタイルでした。濃くパワフルでプルーンの果実味。ただ、濃いだけでなく酸もあるのでトータルとしては非常にナパらしい素晴らしいカベルネに仕上がっています。
レイルのワインの最後は2015年のモール・ヒル単一畑のマグナムという希少なワイン。畑の名前そのままで、ラベルにモグラが描かれています。前述のように2015年のスタイル自体がかなり熟度の高いものであったのに加えて、ナパの中でも気温が高く、乾燥してパワフルなワインができるハウエル・マウンテンなので、ジョン・ダニエル・キュベの2015年以上にパワフルに仕上がっています。照り付ける太陽を感じるようなハウエルマウンテンらしさのあるカベルネ・ソーヴィニョンでした。
ここまででも素晴らしいワイン三昧だったのですが、さらに参加者の差し入れで98年と99年のドミナスをいただきました。前述のように、ドミナスはイングルヌックを失った後に、ロビン・レイルが最初に参画したワイナリー。ドミナスの畑として知られているナパヌックは元イングルヌックの畑です。
1998年はエルニーニョのヴィンテージとして知られている、雨が多くて気温が低い難しい年でした。2011年の前の難しい年というと、まずこの年が上がると思います。98年のドミナスも果実味は弱く、マッシュルームなどの熟成香が中心の味わい。1999年はバランスよい仕上がり。もうだいぶ酔っぱらっているのでコメントがいい加減です。
貴重なワインの数々、ありがとうございました。
ポール・ホブズの娘のアグスティーナ(Agustina L. Hobbs)がALHというブランドでワインメーカーとしてデビューします。


最初のワインは2022年のカベルネ・ソーヴィニヨンで、ポール・ホブズの自社畑であるナパのクームズヴィルのネイサン・クームズ・エステートのブドウを使っています。ここの畑のカベルネ・ソーヴィニョンはクームズヴィルとして初めてのカベルネ・ソーヴィニョンでの「100点ワイン」になっています。
アグスティーナは15歳からワイナリーでボトリングの手伝いをし、ニューヨークのコーネル大学でブドウ栽培と醸造を学びました。その後、アルゼンチンとフランスで収穫の手伝いをし、香港と日本でビジネスも学んだとのこと。
アグスティーナは今回のプロジェクトについて「ALHは私たちの家族の伝統を受け継ぐだけではありません。私を形成した職人技、価値観、遺産に忠実でありながら、ワイン造りで私のビジョンを表現できる場所です。このワインは私が深く信じているワインであり、本物、品質、バランス、そしてカベルネ・ソーヴィニヨンの新鮮なテイストを大切にする人たちと分かち合えることに興奮しています」と語っています。
ちなみに、ポール・ホブズの2022年のクームズヴィルのワインと、ALHを比較すると
・ブドウ品種
PH(CS88%、PV6%、M4%、CF2%)
ALH(CS90%、M7%、CF3%)
・収穫
PH 9月13~10月10日
ALH 9月27日~10月4日
・酵母
PH 天然
ALH 天然
・樽熟成
PH フレンチオークの樽(新樽53%)で20カ月
ALH フレンチオークの樽(新樽29%)で18カ月
・清澄・フィルター
PH 清澄、フィルターなし
ALH 清澄なし
・マセレーション
PH 27日
ALH 不明
ALHの方が新樽率が低く、樽熟成の期間も2カ月短くなっています。また、収穫時期はPHの方が早く始まり、遅くまで続いています。
ALHのワインは8月1日から発売の予定となっています。価格は現状公表されていません。


最初のワインは2022年のカベルネ・ソーヴィニヨンで、ポール・ホブズの自社畑であるナパのクームズヴィルのネイサン・クームズ・エステートのブドウを使っています。ここの畑のカベルネ・ソーヴィニョンはクームズヴィルとして初めてのカベルネ・ソーヴィニョンでの「100点ワイン」になっています。
アグスティーナは15歳からワイナリーでボトリングの手伝いをし、ニューヨークのコーネル大学でブドウ栽培と醸造を学びました。その後、アルゼンチンとフランスで収穫の手伝いをし、香港と日本でビジネスも学んだとのこと。
アグスティーナは今回のプロジェクトについて「ALHは私たちの家族の伝統を受け継ぐだけではありません。私を形成した職人技、価値観、遺産に忠実でありながら、ワイン造りで私のビジョンを表現できる場所です。このワインは私が深く信じているワインであり、本物、品質、バランス、そしてカベルネ・ソーヴィニヨンの新鮮なテイストを大切にする人たちと分かち合えることに興奮しています」と語っています。
ちなみに、ポール・ホブズの2022年のクームズヴィルのワインと、ALHを比較すると
・ブドウ品種
PH(CS88%、PV6%、M4%、CF2%)
ALH(CS90%、M7%、CF3%)
・収穫
PH 9月13~10月10日
ALH 9月27日~10月4日
・酵母
PH 天然
ALH 天然
・樽熟成
PH フレンチオークの樽(新樽53%)で20カ月
ALH フレンチオークの樽(新樽29%)で18カ月
・清澄・フィルター
PH 清澄、フィルターなし
ALH 清澄なし
・マセレーション
PH 27日
ALH 不明
ALHの方が新樽率が低く、樽熟成の期間も2カ月短くなっています。また、収穫時期はPHの方が早く始まり、遅くまで続いています。
ALHのワインは8月1日から発売の予定となっています。価格は現状公表されていません。
北カリフォルニアを中心に、カリフォルニア全体が異例なほどの冷夏になっています(California's Cruel Cool Summer)。

ある記事によると、サンフランシスコの気温は1965年以来の低さとのことで、最高気温が華氏70度(約摂氏21度)を上回った日は6月で5日、7月もこれまで7日しかないとのこと。
冷夏の原因は、マリン・レイヤーと呼ばれる太平洋の湿った冷たい雲の塊が非常に強いこと。おそらく8月も今の涼しさが続くであろうとのことです。
北カリフォルニアの冷夏というと、今世紀に入ってからだと2011年が代表的な年。ナパではカベルネ・ソーヴィニョンが成熟しきらないという異例な年になりました。
ワインメーカーは口をそろえて「これまでで一番難しかった年」だと言い、ヴィンテージの評価もあまりよくありません。
一方で、10年を過ぎて熟成を見ると、温暖な年よりもきれいに熟成しているという意見も多々見られます。
生産者によっては、ブドウの房の周りの葉をよけて日当たりをよくするなどの対策を始めているところもあるそうです。ただ、9月10月に熱波が来ることも珍しくないので、リスクを伴う作業でもあります。どちらにしても生産者にとっては悩ましい夏になりそうです。

ある記事によると、サンフランシスコの気温は1965年以来の低さとのことで、最高気温が華氏70度(約摂氏21度)を上回った日は6月で5日、7月もこれまで7日しかないとのこと。
冷夏の原因は、マリン・レイヤーと呼ばれる太平洋の湿った冷たい雲の塊が非常に強いこと。おそらく8月も今の涼しさが続くであろうとのことです。
北カリフォルニアの冷夏というと、今世紀に入ってからだと2011年が代表的な年。ナパではカベルネ・ソーヴィニョンが成熟しきらないという異例な年になりました。
ワインメーカーは口をそろえて「これまでで一番難しかった年」だと言い、ヴィンテージの評価もあまりよくありません。
一方で、10年を過ぎて熟成を見ると、温暖な年よりもきれいに熟成しているという意見も多々見られます。
生産者によっては、ブドウの房の周りの葉をよけて日当たりをよくするなどの対策を始めているところもあるそうです。ただ、9月10月に熱波が来ることも珍しくないので、リスクを伴う作業でもあります。どちらにしても生産者にとっては悩ましい夏になりそうです。

スペインの研究者が、50歳から75歳までの「人生の妙味を知る」1万人の大人たちを対象に、「毎日ワインを飲むのは健康にいいかどうか」という、夢のような健康研究をスタートします(
You Can Get 4 Years of Free Wine to Help Scientists Study the Effects of Moderate Drinking)。4年間の追跡調査を行うこの件空に参加した人は4年分のワインとオリーブオイルを無料で得られるというワイン好きにとっては魅力的な話。
ただし、被験者は「毎日ワインを飲む」か「まったく飲まない」かのどちらかに勝手に分けられます。「まったく飲まない」に分けられた場合は、アルコールを摂取できませんし、ワインの代わりにノンアルコールのビールが提供されることになります。
また、最大の障壁はこの研究に参加する人はスペイン在住に限られること。もし、スペインに住んでいる方がいらっしゃったら、いkがでしょうか。
Columbia Gorgeの火事の続報ですが、日本にも輸入されているワイナリー「シンクライン(Syncline)」も大きな被害を受けています。畑は6エーカー以上焼失。ワイナリーは無事なようですが、立ち入りできないため状況は不明だそうです。畑で残ったブドウも、今年のワインには使えないだろうとのこと。濃い煙に長時間さらされており、煙汚染の影響を排除できないとワインメーカーは考えています。

暗いニュースが続いたところで、いい話も。
ワシントン州のドライの白ワインに、初めて評論家の100点が付きました。これまで赤ワインでは2006年にクィルシーダ・クリーク(Quilceda Creek)がワイン・アドヴォケイトで、デザートワインでは2012年のシャトー・サン・ミシェル(Chateau Ste. Michelle)のEroica Single Berry SelectがWine & Spirits誌で100点を取っています。

ドライの白ワインとして100点を取ったのは「2022 Tenor La Reyna Blanca Vineyard Chardonnay」。残念ながら国内には入っていないワイナリーです。100点を付けたのはジェブ・ダナック。なお、Wine Advocateでは93、Vinousでは94点となっています。
ジェブ・ダナックのコメントは「快楽的でフローラルな美しさとリッチなミッドパレットを持つ2022年のシャルドネ、ラ・レイナ・ブランカ・ヴィンヤードは、単一畑で20ヶ月の樽熟成を経て、111ケースのみ生産された極上のワインだ。白桃が主役で、スパイスの効いたオークの強さとみずみずしいテクスチャーが、表情豊かで複雑な深みとカルダモン、クローブ、マジパンの魅力的なミックスを引き立てている。このワインは本当に驚かされ、ボトルがなくなった後もずっとあなたの心に残るだろう。10~12年、いやそれ以上熟成させる価値がある」
畑はロイヤル・スロープAVAにあります。ロイヤル・スロープはコロンビア・ヴァレーの中でやや北の方にあるAVAで、標高が610フィートから1756フィートまでと、AVAの中でも300mほどの落差があり、南向きの斜面がずっと広がっています。この標高のため、温暖ですがやや冷涼感もあるようです。ワシントン州のシラーで初めて100点を取ったKヴィントナーズの「ロイヤルシティ」もこのAVAで、初シラー100点と初シャルドネ100点を生み出したことになります。

暗いニュースが続いたところで、いい話も。
ワシントン州のドライの白ワインに、初めて評論家の100点が付きました。これまで赤ワインでは2006年にクィルシーダ・クリーク(Quilceda Creek)がワイン・アドヴォケイトで、デザートワインでは2012年のシャトー・サン・ミシェル(Chateau Ste. Michelle)のEroica Single Berry SelectがWine & Spirits誌で100点を取っています。

ドライの白ワインとして100点を取ったのは「2022 Tenor La Reyna Blanca Vineyard Chardonnay」。残念ながら国内には入っていないワイナリーです。100点を付けたのはジェブ・ダナック。なお、Wine Advocateでは93、Vinousでは94点となっています。
ジェブ・ダナックのコメントは「快楽的でフローラルな美しさとリッチなミッドパレットを持つ2022年のシャルドネ、ラ・レイナ・ブランカ・ヴィンヤードは、単一畑で20ヶ月の樽熟成を経て、111ケースのみ生産された極上のワインだ。白桃が主役で、スパイスの効いたオークの強さとみずみずしいテクスチャーが、表情豊かで複雑な深みとカルダモン、クローブ、マジパンの魅力的なミックスを引き立てている。このワインは本当に驚かされ、ボトルがなくなった後もずっとあなたの心に残るだろう。10~12年、いやそれ以上熟成させる価値がある」
畑はロイヤル・スロープAVAにあります。ロイヤル・スロープはコロンビア・ヴァレーの中でやや北の方にあるAVAで、標高が610フィートから1756フィートまでと、AVAの中でも300mほどの落差があり、南向きの斜面がずっと広がっています。この標高のため、温暖ですがやや冷涼感もあるようです。ワシントン州のシラーで初めて100点を取ったKヴィントナーズの「ロイヤルシティ」もこのAVAで、初シラー100点と初シャルドネ100点を生み出したことになります。
ワシントン州とオレゴン州の境を流れるコロンビア川で、狭い渓谷になったのがコロンビア・ゴージ(The Columbia Gorge)というAVAです。コロンビア・ヴァレーの巨大な内陸の盆地と、海側を隔てる境のAVAでもあります。この地域で山火事「Burdoin Fire」が発生し、ワイナリーが一軒焼失しました。
上は、ワイナリーが焼失を報告したインスタグラムの投稿とその本文の訳です。ワイナリーの名前はBARO。ワシントン側にあります(コロンビア・ゴージはワシントン州とオレゴン州にまたがっています)。
火事は10700エーカー以上を焼き、少なくとも14個の家が焼失したとされています。最新情報では、コンテイン率はゼロ。まだ火勢をコントロールできていないようです。
訳
私たちは、これまで耐えてきたこと、そして私たちの前に待ち受けているすべてのことに対して、言葉もありません。
家族として、ビジネスとして、私たちには嘆くべきことがたくさんあり、また心から感謝すべきこともたくさんある=人命の安全、第一応答者への計り知れない感謝、ヒーローとして駆けつけてくれた隣人たち、そして我が家が助かったこと!
しかし、多くのものが失われた......。
隣人の家、土地、そしてBAROのワイナリーとセラー。
私たちは明日がどうなるか何も知らないが、誰が明日をその手に握っているかは知っている。
私たちの祈りと愛は、Burdoin火災で被害を受けたすべての人々、ライルのすべての人々、そして私たちのコミュニティのために戦っているすべての人々に送られ続けています。私たちは消防士とすべての第一応答者に永遠に感謝しています!
土曜日の夕方の写真。
上は、ワイナリーが焼失を報告したインスタグラムの投稿とその本文の訳です。ワイナリーの名前はBARO。ワシントン側にあります(コロンビア・ゴージはワシントン州とオレゴン州にまたがっています)。
火事は10700エーカー以上を焼き、少なくとも14個の家が焼失したとされています。最新情報では、コンテイン率はゼロ。まだ火勢をコントロールできていないようです。
小枝絵麻さんが「マジカルペアリング入門」という本を出版されました。同時に、この書籍を使ったペアリングのクラスも開講されます。
shop | 食卓が豊かになるショップ。 — food x wine + bridges
先日開かれた体験レッスンに参加してきました。
私としては、以前からNapa Valley Vintnersでお世話になっており、ペアリングのイベントや動画なども取っておりますので、絵麻さんの「方程式」を使ったペアリングには既になじみがありますが、そうでない人も多いと思いますので、まずは以前の記事や動画も参考になさってください。
ワインと食事のマリアージュに「ブリッジ食材」のマジック
今回のレッスンでは、①アルバリーニョを使ったオレンジワイン、②ややリッチなヴィオニエ、③エレガントなピノ・ノワールのロゼ、という近年人気のスタイルのワイン3つとのペアリングを体験しました。

絵麻さんのペアリング方程式の基本は、食材と調理法と味付けの足し算で料理の重さを出して、それとワインの重さを合わせるというもの。例えば、書籍に載っている「ヘルシーグリルチキン、レモンチーズ挟み」であれば、食材の鶏むね肉が1点、調理法がグリルで2点、チーズとレモン、ホウレンソウのフィリングが1点で計4点というのが料理の重さになり、ライトボディのワインを合わせることになります。
さらに、ペアリングをワンランクアップさせるのが「ブリッジ食材」でワインの味わいと共通性のある食材を料理に加えることで、より合いやすくします。
ややこしい、めんどくさいと思うかもしれませんが、むしろ自由度が上がっているように感じます。
これまでペアリングというと「牡蠣にシャブリ」とか「ブルーチーズにソーテルヌ」とか、決まった組み合わせのものだったり、料理の地方性とワインの地方性を合わせるなど必ずしも味わいと合うとは限らない組み合わせだったり、ちょっと窮屈に感じられることもありました。また、家で普段食べる料理に何を合わせたらいいか、ということにはこれらの組み合わせは答えをくれません。
絵麻さんのメソッドだと、ワインの選びかたも幅があるので、ペアリング的には白だけど今日はロゼの気分、みたいなことにも簡単に対応できます。家にあるのは鶏むね肉だけど、どうしても濃い赤が飲みたければ、調理法と合わせる素材の重さでワインに合うように仕立てられます。家の食材でワインを選んだり、ワインから調理法を選んだりと、自分の優先したいものからペアリングにつなげられるのです。
またこれだけだと、ペアリングとしては「悪くないけど普通」で終わってしまうかもしれませんが、これを見事なペアリングにまで変えてしまうのが「ブリッジ食材」です。これもそんなに難しいことではなく、極端なことを言えば、ちょっと塩を足したり、レモン汁をかける程度のことでも、合い方が変わってくるのです。このちょっとした工夫を取り入れることで、家での食事とワインの組み合わせが1ランク上のものになります。
この日のクラスではヴィオニエに「塩とヨーグルト」を合わせると味わいがより柔らかくなったり、オレンジワインに「アプリコットジャム+塩」がむちゃくちゃあったり、ロゼに「スイカと塩」が合ったりと、いろいろ発見がありました。
絵麻さんの教室に通うとそういった工夫が実際に味わって確かめることができ、また自分で作るときのヒントもたくさん得られます。
家庭でのワインライフをよりよくしたい人は、一度受講されてみてはいかがでしょうか。
shop | 食卓が豊かになるショップ。 — food x wine + bridges
先日開かれた体験レッスンに参加してきました。
私としては、以前からNapa Valley Vintnersでお世話になっており、ペアリングのイベントや動画なども取っておりますので、絵麻さんの「方程式」を使ったペアリングには既になじみがありますが、そうでない人も多いと思いますので、まずは以前の記事や動画も参考になさってください。
今回のレッスンでは、①アルバリーニョを使ったオレンジワイン、②ややリッチなヴィオニエ、③エレガントなピノ・ノワールのロゼ、という近年人気のスタイルのワイン3つとのペアリングを体験しました。
絵麻さんのペアリング方程式の基本は、食材と調理法と味付けの足し算で料理の重さを出して、それとワインの重さを合わせるというもの。例えば、書籍に載っている「ヘルシーグリルチキン、レモンチーズ挟み」であれば、食材の鶏むね肉が1点、調理法がグリルで2点、チーズとレモン、ホウレンソウのフィリングが1点で計4点というのが料理の重さになり、ライトボディのワインを合わせることになります。
さらに、ペアリングをワンランクアップさせるのが「ブリッジ食材」でワインの味わいと共通性のある食材を料理に加えることで、より合いやすくします。
ややこしい、めんどくさいと思うかもしれませんが、むしろ自由度が上がっているように感じます。
これまでペアリングというと「牡蠣にシャブリ」とか「ブルーチーズにソーテルヌ」とか、決まった組み合わせのものだったり、料理の地方性とワインの地方性を合わせるなど必ずしも味わいと合うとは限らない組み合わせだったり、ちょっと窮屈に感じられることもありました。また、家で普段食べる料理に何を合わせたらいいか、ということにはこれらの組み合わせは答えをくれません。
絵麻さんのメソッドだと、ワインの選びかたも幅があるので、ペアリング的には白だけど今日はロゼの気分、みたいなことにも簡単に対応できます。家にあるのは鶏むね肉だけど、どうしても濃い赤が飲みたければ、調理法と合わせる素材の重さでワインに合うように仕立てられます。家の食材でワインを選んだり、ワインから調理法を選んだりと、自分の優先したいものからペアリングにつなげられるのです。
またこれだけだと、ペアリングとしては「悪くないけど普通」で終わってしまうかもしれませんが、これを見事なペアリングにまで変えてしまうのが「ブリッジ食材」です。これもそんなに難しいことではなく、極端なことを言えば、ちょっと塩を足したり、レモン汁をかける程度のことでも、合い方が変わってくるのです。このちょっとした工夫を取り入れることで、家での食事とワインの組み合わせが1ランク上のものになります。
この日のクラスではヴィオニエに「塩とヨーグルト」を合わせると味わいがより柔らかくなったり、オレンジワインに「アプリコットジャム+塩」がむちゃくちゃあったり、ロゼに「スイカと塩」が合ったりと、いろいろ発見がありました。
絵麻さんの教室に通うとそういった工夫が実際に味わって確かめることができ、また自分で作るときのヒントもたくさん得られます。
家庭でのワインライフをよりよくしたい人は、一度受講されてみてはいかがでしょうか。
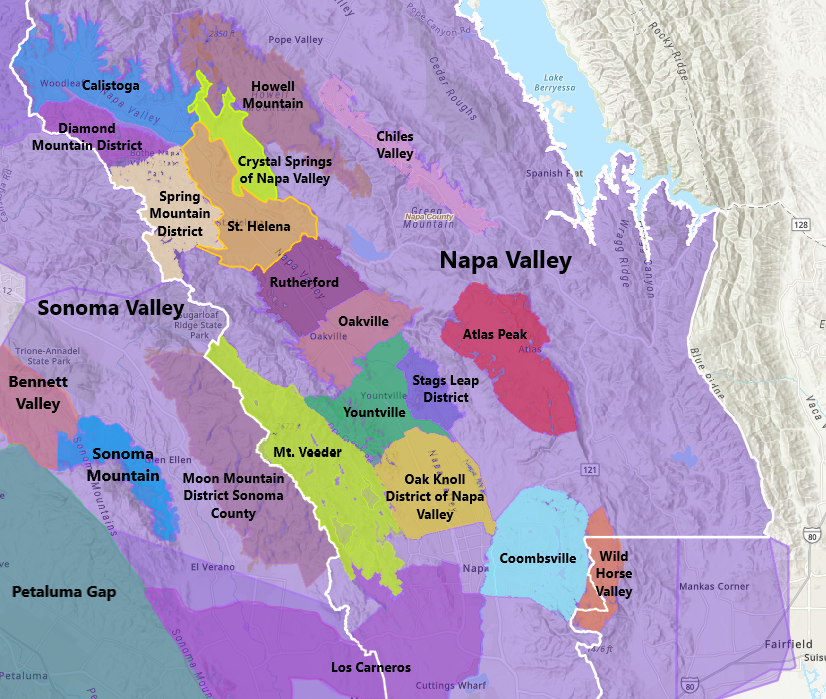
By Unknown author - TTB.gov, Public Domain, Link
ナパのチャイルズ・ヴァレー(上のマップで右上ピンクのAVAです)をご存じでしょうか。ナパにある程度詳しくても、チャイルズ・ヴァレーのワインを飲んだことがある人は少なさそうです。今回はチャイルズ・ヴァレーのマックスヴィル(Maxville)ワイナリーのCEOであるスコットさんが来日して、初代ナパヴァレー・ベスト・ソムリエ・アンバサダーの富満さんとセミナーと開いたセミナーに参加してきました。ちなみにスコットさんは前Silenusのジェネラルマネージャーで、日本語はペラペラです。

富満さんも、今年初めてチャイルズ・ヴァレーに行ったとのことですが、ナパヴァレーの中心部から車で30分くらいかかるそうです。途中で不安になるほどの田舎で、携帯電話の電波も通じません。
ヴァレーと名前が付いているように、ヴァカ山脈を越えた先の谷になります。標高はナパヴァレーのヴァレーフロアと比べれば高いですが、ハウエル・マウンテンなどの山のAVAと比べれば低いです。土壌も火山性の岩もありますが、シルトローム層など沖積世の土壌もあり、場所によって様々です。
AVAが策定されたのは1999年で、ナパの中では11番目と比較的遅くなっています。歴史を紐解くと1841年にジョセフ・バリンジャー・チャイルズという人がメキシコ総督から土地を譲り受けて入植し、製粉所を造ったというのが、この地に人が入っていった最初のようです。このあと、フランシス・シーバスという人に土地を一部売却し、その人がワイナリーを設立しました。人里離れたところでフィロキセラの被害もあまりありませんでしたが、禁酒法でブドウ栽培は中断し、1970年代にVolker Eisele(フォルカー・アイズリー)が設立されて、ようやく本格的なワイン造りが始まりました。AVAの申請もVolker Eiseleが中心になって行いました。現在でもワイナリーは5つくらいしかない知られざるAVAです。
気候的には、海から遠く暖かいのかと思っていましたが、夏でも夜には気温が10℃を下回るという意外なほどの涼しさです。霧も入ってくるのだそうです。また、風が強いのも特徴です。
Maxvilleはここで1025エーカーという広大な土地を所有しています。その中の625エーカーは「Napa Valley Land Trust」に登録してあり、その土地は永久に開発の対象外となっています。ワイナリーの設立は1974年で、近くを流れるMaxwell Creekという川と「ville」を組み合わせたそうです。ワイナリーは太陽光発電などを採用して自然と調和して作っていくことを狙っています。
4種類のワインを試飲しました。
2021 Malbec
黒っぽい果実味に土や埃のようなテクスチャー。酸高く、渋みもしっかりあります。オレンジピールのような風味も。洗練されたというよりもどっしりとした力強さを感じるワイン
2021 Merlot
ブルーベリーとレッド・チェリーの風味、酸もタンニンも高い。マルベックと比べると少しトーンが明るいが、力強さを感じるのは共通。酸の高さも共通する要素です。
2021 Cabernet Sauvignon
カシスに黒鉛、しなやかなタンニン。酸はマルベックやメルローと比べると柔らかでまろやか、全体になめらかなテクスチャーが印象的で素晴らしいカベルネ・ソーヴィニョン。
2022 High Valley Cabernet Sauvignon
やや廉価版のワイン。カシスにブラックベリー、酸豊かで芳醇。バランスよくできている
トミーはスモーキーなニュアンスがあると言っていました。
四つのワインに共通するのは、酸が味わいの中心にあること。夜間には10℃以下に下がるという冷涼さがもたらすものでしょう。Chiles Valleyのワインは非常にサンプルが少なく、ジンファンデル系が中心のため、ボルドー系品種はほぼ今回が初めての試飲となりました。とても興味深い産地です。
スコットさんに、今後力を入れたい品種を聞いてみたところカベルネ・フランとのこと。この冷涼感はカベルネ・フランにも非常に合うだろうと思います。
なお、Maxvilleは現在インポーター募集中です。

ソノマ・ヴァレーのムーン・マウンテンAVAにあるモンテ・ロッソ・ヴィンヤード(Monte Rosso Vineyard)がCCOF(California Certified Organic Farmers)の有機栽培認証を獲得しました。CCOFは米国農務省認定の有機認証機関の一つです。
モンテ・ロッソ・ヴィンヤードや1886年に植樹が始まった古い畑で「ヒストリック・ヴィンヤード・ソサイエティ」に登録されています。名前の通り、標高400mほどの山麓の畑で火山性の赤い土壌が特徴となっています。南向き斜面で完熟したブドウと豊かな酸とミネラル感がワインの特徴となっています。
サンフランシスコで食料品店を営んでいたエマニュエル・ゴールドスタインとビジネス・パートナーのベンジャミン・ドレイファスが畑の創設者。当初はジンファンデルとセミヨンが植えられ、その一部は現在も残っています。ゴールドスタインは1938年に畑をナパのルイス・M・マルティーニに売却しました。マルティーニは1940年に最初のカベルネの樹を植え、その樹は現在も実を付けています。植樹面積は250エーカーに広がり、ジンファンデル、カベルネ・ソーヴィニヨン、セミヨン、リースリングなど計10品種が植えられています。
2002年にルイ・M・マルティーニがE・J・ガロに売却され、現在もガロがオーナーとなっています。ルイ・M・マルティーニがカベルネ・ソーヴィニョンなどを作っているほか、ベッドロックなどが古木のジンファンデルから素晴らしいワインを造っています。

もう1カ月ほど前のニュースですが。
ナパの名門ワイナリー「アイズリー(Eisele)」の前オーナーだったアラウホ(Araujo)家(当時のワイナリー名もアラウホ)が、2013年の売却後に立ち上げたワイナリー「アセンド(Accendo)」を売却しました。アラウホ家は以前のバートとダフネの夫妻からグレッグとジェイミーの兄弟へと代替わりしていますが、今後は有機栽培の畑にこだわるトロワ・ノワ(Troix Noix)ブランドに注力します。
売却先はジャック・ビットナー(Jack Bittner)とベティネリ家(Bettinelli)。ビットナーは2年前までOvidのパートナーで、現在はエコトーン(Ecotone、旧名はトレヴィロス、Thorevilos)のパートナーになっています。エコトーンはエイブリューが長期リースしていましたが、2019年にそれが終了して現在はベティネリ家が畑を管理しています。
ベティネリ家はナパで350エーカーの畑を所有している大手の栽培家。アセンドはこれまでVine Hill Ranchなどからの買いブドウでワインを造ってきましたが、今後は「アセンド・エステート」として自社畑のブドウだけを使うようになります。
アセンドはアラウホ時代からワイン造りを手掛けており、近年は自身のキンズマン・イーズ(Kinsman Eades)でも注目されているナイジェル・キンズマン(Nigel Kinsman)がワインメーカー。キンズマンは今後もワインメーカーを続けます。
ナパのリンカーン・セラーズのカベルネ・ソーヴィニヨンが輸入停止で希望小売価格の6000円から半額以下の特価になっています。
税抜き2980円というのはいまどき「ナパヴァレー」AVAのカベルネでもなかなかありませんが、これは「ヨントヴィル」のブドウを使ったもの。しなやかなタンニンで深みのある味わい。とてもいいカベルネ・ソーヴィニョンです。
以前の試飲会レポ―とでは希望小売価格5800円のナパ・ハイランズと比べて以下のように書いています。
大お薦めです。
税抜き2980円というのはいまどき「ナパヴァレー」AVAのカベルネでもなかなかありませんが、これは「ヨントヴィル」のブドウを使ったもの。しなやかなタンニンで深みのある味わい。とてもいいカベルネ・ソーヴィニョンです。
以前の試飲会レポ―とでは希望小売価格5800円のナパ・ハイランズと比べて以下のように書いています。
ナパ・ハイランズのカベルネは完全に定番になりました。酸もあってバランスよくトータルでよくできたワイン。リンカーン・セラーズのカベルネ・ソーヴィニョン2019はナパのヨントヴィルのブドウを使っています。しなやかなタンニンでレベル高い。個人的にはこの二つではリンカーン・セラーズを推します。
大お薦めです。
チャールズ・クリュッグ(Charles Krug)の廉価ブランドであるCKモンダヴィが新ラベルを採用すると発表しました。

新ラベルは、アリシア・モンダヴィ(ロバート・モンダヴィの弟ピーターの孫娘の一人)がデザインしたもので、グルテン・フリーやヴィーガンといった情報をフロント・ラベルおよびバック・ラベルに入れています。また、モンダヴィ家の写真をコラージュして、その歴史を物語っています。
アリシアは次のように語っています。
「ワインには昔から神秘的な雰囲気が漂っています。それはワインの魅力の一部ではありますが、栄養成分は謎めいたものであってはいけません。我が家には糖尿病の病歴があり、私も最近グルテンアレルギーと診断されました。多くのワイン樽では、樽の密封にグルテンベースの製品が使用されています。微量のグルテンが添加されているとはいえ、グルテンに敏感な方は影響を受ける可能性があります。買い物をする際に必要な情報が不足していることがどれほどフラストレーションになるか、私自身も身をもって知っています。今回のリニューアルは、誠実さと分かりやすさへの私たちのコミットメントを反映しています」
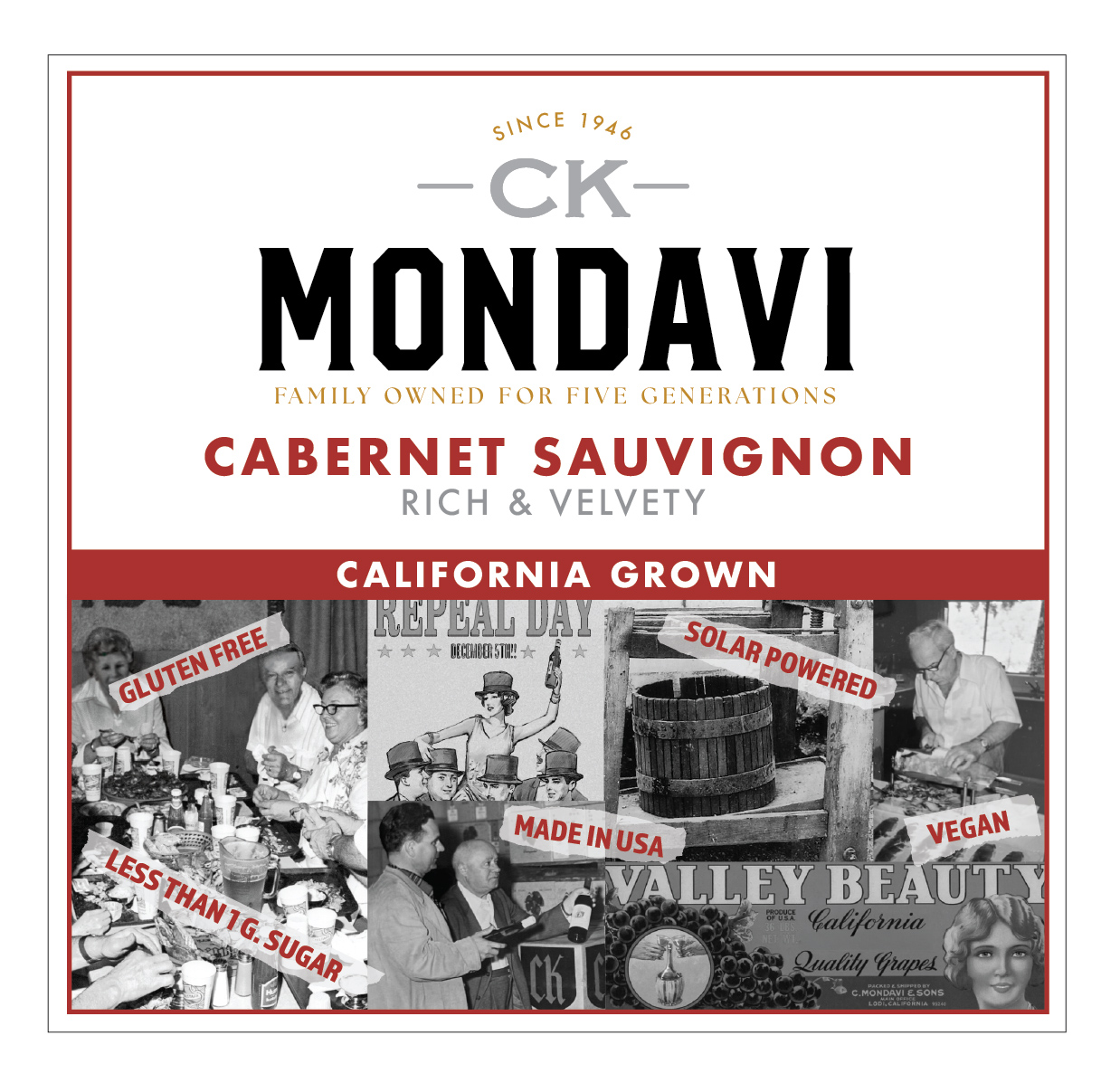
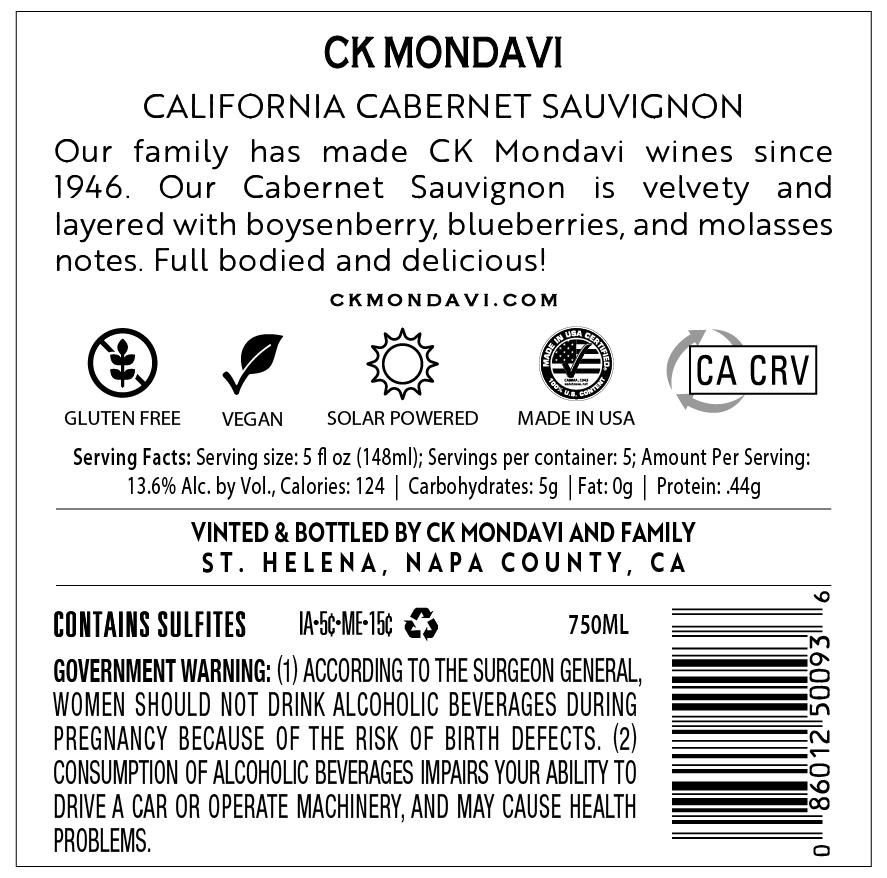


新ラベルは、アリシア・モンダヴィ(ロバート・モンダヴィの弟ピーターの孫娘の一人)がデザインしたもので、グルテン・フリーやヴィーガンといった情報をフロント・ラベルおよびバック・ラベルに入れています。また、モンダヴィ家の写真をコラージュして、その歴史を物語っています。
アリシアは次のように語っています。
「ワインには昔から神秘的な雰囲気が漂っています。それはワインの魅力の一部ではありますが、栄養成分は謎めいたものであってはいけません。我が家には糖尿病の病歴があり、私も最近グルテンアレルギーと診断されました。多くのワイン樽では、樽の密封にグルテンベースの製品が使用されています。微量のグルテンが添加されているとはいえ、グルテンに敏感な方は影響を受ける可能性があります。買い物をする際に必要な情報が不足していることがどれほどフラストレーションになるか、私自身も身をもって知っています。今回のリニューアルは、誠実さと分かりやすさへの私たちのコミットメントを反映しています」
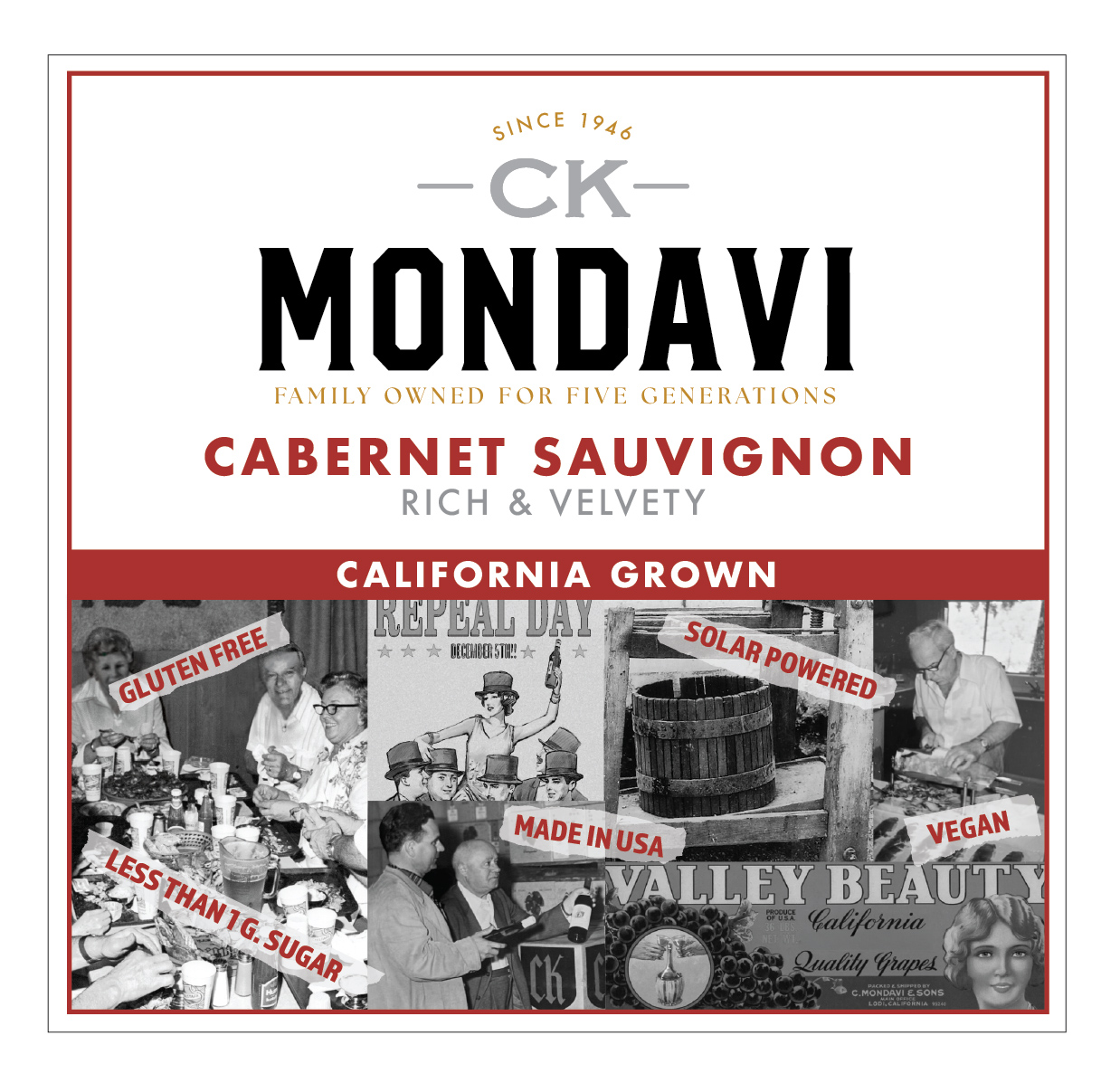
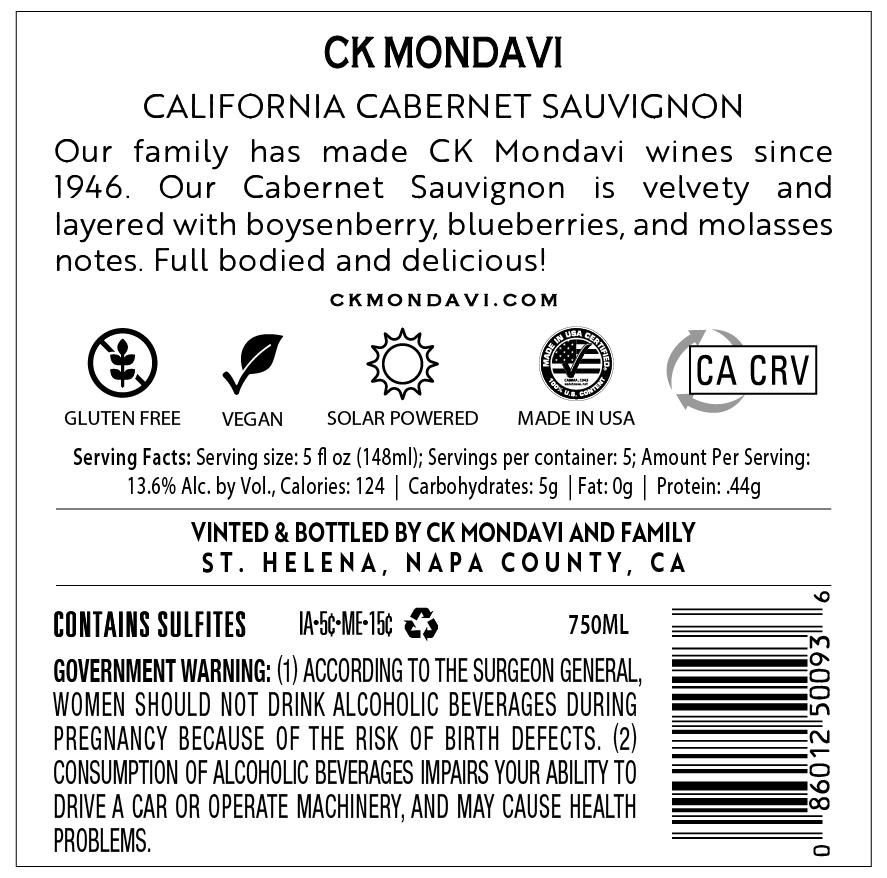

オーパス・ワン・ワイナリー(Opus One Winery)はラグジュアリー・ブランド向けのサスティナブル認証「バタフライ・マーク(Butterfly Mark)」を取得したと発表しました。この認証は、「ポジティブ・ラグジュアリー(Positive Luxury)」が運営するもので、環境・社会・企業統治(ESG)の分野で高い基準を満たした高級ブランドのみに与えられます。

オーパス・ワンは様々な形でサスティナブルに取り組んでおり、それらが評価された形になります。例えば以下のような取り組みが評価されています。
1. ナパ・グリーン認証(Napa Green)
2021年にナパ・グリーン・ワイナリーおよびナパ・グリーン・ヴィンヤードの両認証を取得した初のワイナリーとなりました。エネルギー節約、水の効率利用、廃棄物削減、社会的公平性への貢献が評価されています。
2. 再生可能型農業(Regenerative Viticulture)
カバークロップ(被覆作物)、羊による除草、ミツバチの導入など、土壌の健康と生物多様性を高める取り組みを実施しています。
3. 再生可能エネルギーの活用
全電力をMCE(地方エネルギー会社)の「Deep Green」プログラムを通じて100%再生可能エネルギーにしています。
4. 水資源管理
低流量の蛇口や雨水の貯水システムなど、水の使用を最小限に抑える技術を採用しています。
バタフライマークは2年に1回、再認証を受ける必要があり、今後も一層持続可能性を高めていく必要があります。

オーパス・ワンは様々な形でサスティナブルに取り組んでおり、それらが評価された形になります。例えば以下のような取り組みが評価されています。
1. ナパ・グリーン認証(Napa Green)
2021年にナパ・グリーン・ワイナリーおよびナパ・グリーン・ヴィンヤードの両認証を取得した初のワイナリーとなりました。エネルギー節約、水の効率利用、廃棄物削減、社会的公平性への貢献が評価されています。
2. 再生可能型農業(Regenerative Viticulture)
カバークロップ(被覆作物)、羊による除草、ミツバチの導入など、土壌の健康と生物多様性を高める取り組みを実施しています。
3. 再生可能エネルギーの活用
全電力をMCE(地方エネルギー会社)の「Deep Green」プログラムを通じて100%再生可能エネルギーにしています。
4. 水資源管理
低流量の蛇口や雨水の貯水システムなど、水の使用を最小限に抑える技術を採用しています。
バタフライマークは2年に1回、再認証を受ける必要があり、今後も一層持続可能性を高めていく必要があります。
しあわせワイン倶楽部でボドキン(Bodkin)の「ライト・スキンド」ジンファンデルが税込み2420円で売っています。ワイナリー価格は32ドル(税抜き)なので、実質5000円以上ですから、半額以下のお買い得品です。
ボドキンといえば、ソーヴィニヨン・ブランのスペシャリストとして知られており、オーナーでワインメーカーのクリストファー・クリステンセンはSFクロニクルの注目のワインメーカーにも選ばれている若手の注目株。
このワインは冷やして飲むような軽い赤を作りたいと考えて、メンドシーノのジンファンデルで作っています。スキン・コンタクトは36時間で、ロゼとしてはやや濃いめの色になっています。赤でもロゼでもないというところが、黒人と白人のハーフというクリストファー自身の出自と似ているということで、ラベルには家族の似顔絵が描かれています。
ボドキンといえば、ソーヴィニヨン・ブランのスペシャリストとして知られており、オーナーでワインメーカーのクリストファー・クリステンセンはSFクロニクルの注目のワインメーカーにも選ばれている若手の注目株。
このワインは冷やして飲むような軽い赤を作りたいと考えて、メンドシーノのジンファンデルで作っています。スキン・コンタクトは36時間で、ロゼとしてはやや濃いめの色になっています。赤でもロゼでもないというところが、黒人と白人のハーフというクリストファー自身の出自と似ているということで、ラベルには家族の似顔絵が描かれています。
5月に開催された「持続可能なパシフィック・ノースウェストワイン」のセミナーの覚書です。皆様に読んでいただく記事というよりは、自分のためのメモに近いものです。うまく記事にまとめられなくてすみません。
講師はBree Stock MW。昨年もパシフィック・ノースウェストの認定セミナーでお世話になりました。
まずは、オレゴンとワシントンについての基本的なことから。
95%の米国のワイン生産は西海岸ですがカリフォルニアが88%を占めており、1つのワイナリーでオレゴン(生産量5位)やワシントン(生産量2位)の全生産量を超えるような大手もあります。それに対してオレゴンとワシントンは小さなエステートの生産者が多く、栽培と醸造が近い関係にあるところが中心です。緯度で言うと緯42~49度と世界的に素晴らしい生産地が集まっている緯度帯です。
ワシントン州には21のAVAがありますが、その中で圧倒的に大きく、他のほとんどのAVAを包含しているのがコロンビア・ヴァレーAVAです。またコロンビア・ヴァレー、ワラワラ、コロンビア・ゴージュの三つのAVAはオレゴン州にも一部含まれています。
オレゴン州ではウィラメット・ヴァレーAVAの存在感が非常に強く、その中に含まれるネステッドAVAが増えています。
また、カリフォルニアやフランスから進出してきている生産者が増えており、サスティナビリティに根ざしたワイン造りを進めています。また、よりよいコミュニティ作りにも注力しているのが特徴です。サスティナブルについては、ただやっているというだけでなく、第三者認証によって示すのが重要になってきています。
認証としてはLIVE - Low Input Viticulture & Enologyがオレゴンで始まって現在はワシントンでも使われています。このほか水質保全を中心とするSalmon Safe、ワシントン州独自の認証で、Salmon Safeも含むSustainable WAなどが使われています。現在約半分のワイナリーがいずれかの認証を受けていますが、それを100%にしていきたいとのことです。このほか、企業の公益性を中心としたBコープという認証を受けているワイナリーもあります。
オーガニック、バイオダイナミック、最近では再生型にも注力している
ウィラメット・ヴァレーの玄武岩が母岩(保水性ある)
北の方では「ロス」ソイル 風によって運ばれる細かい土壌
ワシントンの土壌、バサルトのデポジット、ミズーラ洪水で運ばれる
カスケード山脈との標高差大きい
南向き斜面 ヤキマ 短い生育期間にたっぷり日照を受ける
マルベックやCSなどの熟すのが遅いブドウで重要
ワイン1
エロイカ リースリング コロンビア・ヴァレーAVA エンシャント・レイク XLC 2020
標高高いところの畑。大樽使用で20カ月シュールリーしてダイレクトプレス
青リンゴや濡れた石、ドライで酸高いリースリング
ワイン2
Phelps Creek Lynette Chardonnay 2019
オレゴンはこれまではピノ・ノワールの産地として知られてきましたが、近年はシャルドネの産地として評価されています。1970年代、80年代に植えられたシャルドネはカリフォルニアからのクローンで、オレゴンにあまり向いておらず、下火になってしまいました。1980年代に、デイヴィッド・アーデルシャイムなどが中心になって、ブルゴーニュからオレゴン大にピノとシャルドネのクローンを輸入できるようにして、シャルドネが増えてきました。
酸やや低く、ゆずやハチミツ、ブリオッシュ。ミネラル感ありますが、少し酸化が気になりました。
ワイン3
Adelsheim Breaking Ground Chardonnay
シェヘイレム・マウンテンズAVA
軽い樽感、ミネラル、酸高い、柑橘、バランス良く美味しい
ワイン4
Matthews Winery ソーヴィニヨン・ブラン 2022
再生型の認証も取っているワイナリー。Horse Heaven HillsとYakima Valley
ステンレススティールと樽を両方使っています。フルMLF
黄色い花や柑橘、ネクタリン、酸高くミネラル感ありおいしい
ワイン5
Grosgrain Vineyard Carignan 2022
ちょっとラスティックな赤果実、酸高く、凝縮感は低い。ちょっとナチュラル的なワイルドな風味
ワイン6
Grochau Cellars Gamay/Pinot 2023
ガメイはオレゴンの3%ですが増えています。ブルゴーニュより環境的には上かもしれません。
イチゴの香り、きれいな果実味、少し青果実も。タンニン低く、酸高い、ボディはミディアム
ワイン7
Granivlle Wines Koosah Vineyard Pinot Noir 2023
イオラ・アミティ・ヒルズで最も標高が高いところ(700フィート)に畑があります。オーガニック栽培。全房も使っていて柔らかく抽出しています。
赤い果実ときれいな高い酸、バランス良い、複雑さは強くないが美味しい
ワイン8
Ambar Estate Granville Pinot Noir 2022
ダンディ・ヒルズ、非常に涼しいヴィンテージ
再生型認証や有機認証取得
除梗して優しく抽出、スキンコンタクト21日 新樽30%
赤果実、レッドチェリー、少し黒果実、ミネラル感と複雑さ。ボディは強くないが複雑で美味しい
ワイン9
Boedecker Cellars Shea Vineyard Pinot Noir 2021
ヤムヒルカールトンの畑、50%新樽
レッドチェリーに濃厚なプラムの風味、熟した印象強い。酸は高くバランスはいい
ワイン10
Long Shardows Red Blend Piroutte 2020
カシスやブラックベリー、プラム、酸高く、ボディもやや強い、タンニンきめ細かい
ワインメーカーがフィリップ・メリカ
ワイン11
L'Ecole N.41 Ferguson Estate 2021
きれいで上品、タンニン強いがスムーズな味わい
ワイン12
Hedges Family Estate La Haute Cuvee 2020
沖積扇状地。最も暑く、風が強いAVA
煮詰めたプラム、濃く芳醇で酸高い。タンニン強くしなやか。ミネラル感、かなり良い
天然酵母、フレンチとアメリカンオーク 28カ月 新樽45%


講師はBree Stock MW。昨年もパシフィック・ノースウェストの認定セミナーでお世話になりました。
まずは、オレゴンとワシントンについての基本的なことから。
95%の米国のワイン生産は西海岸ですがカリフォルニアが88%を占めており、1つのワイナリーでオレゴン(生産量5位)やワシントン(生産量2位)の全生産量を超えるような大手もあります。それに対してオレゴンとワシントンは小さなエステートの生産者が多く、栽培と醸造が近い関係にあるところが中心です。緯度で言うと緯42~49度と世界的に素晴らしい生産地が集まっている緯度帯です。
ワシントン州には21のAVAがありますが、その中で圧倒的に大きく、他のほとんどのAVAを包含しているのがコロンビア・ヴァレーAVAです。またコロンビア・ヴァレー、ワラワラ、コロンビア・ゴージュの三つのAVAはオレゴン州にも一部含まれています。
オレゴン州ではウィラメット・ヴァレーAVAの存在感が非常に強く、その中に含まれるネステッドAVAが増えています。
また、カリフォルニアやフランスから進出してきている生産者が増えており、サスティナビリティに根ざしたワイン造りを進めています。また、よりよいコミュニティ作りにも注力しているのが特徴です。サスティナブルについては、ただやっているというだけでなく、第三者認証によって示すのが重要になってきています。
認証としてはLIVE - Low Input Viticulture & Enologyがオレゴンで始まって現在はワシントンでも使われています。このほか水質保全を中心とするSalmon Safe、ワシントン州独自の認証で、Salmon Safeも含むSustainable WAなどが使われています。現在約半分のワイナリーがいずれかの認証を受けていますが、それを100%にしていきたいとのことです。このほか、企業の公益性を中心としたBコープという認証を受けているワイナリーもあります。
オーガニック、バイオダイナミック、最近では再生型にも注力している
ウィラメット・ヴァレーの玄武岩が母岩(保水性ある)
北の方では「ロス」ソイル 風によって運ばれる細かい土壌
ワシントンの土壌、バサルトのデポジット、ミズーラ洪水で運ばれる
カスケード山脈との標高差大きい
南向き斜面 ヤキマ 短い生育期間にたっぷり日照を受ける
マルベックやCSなどの熟すのが遅いブドウで重要
ワイン1
エロイカ リースリング コロンビア・ヴァレーAVA エンシャント・レイク XLC 2020
標高高いところの畑。大樽使用で20カ月シュールリーしてダイレクトプレス
青リンゴや濡れた石、ドライで酸高いリースリング
ワイン2
Phelps Creek Lynette Chardonnay 2019
オレゴンはこれまではピノ・ノワールの産地として知られてきましたが、近年はシャルドネの産地として評価されています。1970年代、80年代に植えられたシャルドネはカリフォルニアからのクローンで、オレゴンにあまり向いておらず、下火になってしまいました。1980年代に、デイヴィッド・アーデルシャイムなどが中心になって、ブルゴーニュからオレゴン大にピノとシャルドネのクローンを輸入できるようにして、シャルドネが増えてきました。
酸やや低く、ゆずやハチミツ、ブリオッシュ。ミネラル感ありますが、少し酸化が気になりました。
ワイン3
Adelsheim Breaking Ground Chardonnay
シェヘイレム・マウンテンズAVA
軽い樽感、ミネラル、酸高い、柑橘、バランス良く美味しい
ワイン4
Matthews Winery ソーヴィニヨン・ブラン 2022
再生型の認証も取っているワイナリー。Horse Heaven HillsとYakima Valley
ステンレススティールと樽を両方使っています。フルMLF
黄色い花や柑橘、ネクタリン、酸高くミネラル感ありおいしい
ワイン5
Grosgrain Vineyard Carignan 2022
ちょっとラスティックな赤果実、酸高く、凝縮感は低い。ちょっとナチュラル的なワイルドな風味
ワイン6
Grochau Cellars Gamay/Pinot 2023
ガメイはオレゴンの3%ですが増えています。ブルゴーニュより環境的には上かもしれません。
イチゴの香り、きれいな果実味、少し青果実も。タンニン低く、酸高い、ボディはミディアム
ワイン7
Granivlle Wines Koosah Vineyard Pinot Noir 2023
イオラ・アミティ・ヒルズで最も標高が高いところ(700フィート)に畑があります。オーガニック栽培。全房も使っていて柔らかく抽出しています。
赤い果実ときれいな高い酸、バランス良い、複雑さは強くないが美味しい
ワイン8
Ambar Estate Granville Pinot Noir 2022
ダンディ・ヒルズ、非常に涼しいヴィンテージ
再生型認証や有機認証取得
除梗して優しく抽出、スキンコンタクト21日 新樽30%
赤果実、レッドチェリー、少し黒果実、ミネラル感と複雑さ。ボディは強くないが複雑で美味しい
ワイン9
Boedecker Cellars Shea Vineyard Pinot Noir 2021
ヤムヒルカールトンの畑、50%新樽
レッドチェリーに濃厚なプラムの風味、熟した印象強い。酸は高くバランスはいい
ワイン10
Long Shardows Red Blend Piroutte 2020
カシスやブラックベリー、プラム、酸高く、ボディもやや強い、タンニンきめ細かい
ワインメーカーがフィリップ・メリカ
ワイン11
L'Ecole N.41 Ferguson Estate 2021
きれいで上品、タンニン強いがスムーズな味わい
ワイン12
Hedges Family Estate La Haute Cuvee 2020
沖積扇状地。最も暑く、風が強いAVA
煮詰めたプラム、濃く芳醇で酸高い。タンニン強くしなやか。ミネラル感、かなり良い
天然酵母、フレンチとアメリカンオーク 28カ月 新樽45%
もう1カ月も前になりますが、杉本隆英・美代子夫妻がプロデュースするシャトー・イガイタカハが20周年を迎え、パーティが開かれました。

90名ほどが出席した豪勢なパーティで、ワインはもちろん尾崎牛のグリルなど料理も素晴らしかったです。そして、CWFC(カリフォルニアワインのファンクラブ)時代からの知り合いにもお会いできて旧交を温められました。


事前に、スピーチをお願いされていたので気楽に承諾していたのですが、スピーチに登場するのが尾崎牛の尾崎宗春さんや、俳優の石田純一さんなどすごい方ばかりで、一人普通の人ですみませんという感じでした。
その代わり、私にしかできない話をしようと、杉本さんとの最初の出会いや、CWFCの話などをさせていただきました。
CWFCでは私は副会長という肩書でした。杉本さんはワイン会を東京や関西、カリフォルニアなどで開き、麻布十番のCWGなどカリフォルニアワインのレストランというリアルの場を提供するのが得意ですし、杉本さんにしかできないこと。私は、サイトの「掲示板」でいろいろな方々からの質問に答えるオンライン担当、みたいな役割分担が自然にできて、それがCWFCがうまく運営されたいた(と思っています)理由ではないかと考えています。今も私は、相変わらずブログを書き、杉本さんはワイン造りをプロデュースしながら日本各地でワイン会を開くという、違う道を歩んでいますが、カリフォルニアワインを盛り上げたいという気持ちは今も共通で持っていると思います。
というようなことを話したと思います。

今後はインポーターであるワインライフ株式会社の方は、CWGからの番頭である菅原さんが社長として切り盛りするということで、杉本夫妻はこれまで以上にシャトー・イガイタカハにフォーカスしていくことになるそうです。
ますますのご活躍を祈念します。

90名ほどが出席した豪勢なパーティで、ワインはもちろん尾崎牛のグリルなど料理も素晴らしかったです。そして、CWFC(カリフォルニアワインのファンクラブ)時代からの知り合いにもお会いできて旧交を温められました。
事前に、スピーチをお願いされていたので気楽に承諾していたのですが、スピーチに登場するのが尾崎牛の尾崎宗春さんや、俳優の石田純一さんなどすごい方ばかりで、一人普通の人ですみませんという感じでした。
その代わり、私にしかできない話をしようと、杉本さんとの最初の出会いや、CWFCの話などをさせていただきました。
CWFCでは私は副会長という肩書でした。杉本さんはワイン会を東京や関西、カリフォルニアなどで開き、麻布十番のCWGなどカリフォルニアワインのレストランというリアルの場を提供するのが得意ですし、杉本さんにしかできないこと。私は、サイトの「掲示板」でいろいろな方々からの質問に答えるオンライン担当、みたいな役割分担が自然にできて、それがCWFCがうまく運営されたいた(と思っています)理由ではないかと考えています。今も私は、相変わらずブログを書き、杉本さんはワイン造りをプロデュースしながら日本各地でワイン会を開くという、違う道を歩んでいますが、カリフォルニアワインを盛り上げたいという気持ちは今も共通で持っていると思います。
というようなことを話したと思います。
今後はインポーターであるワインライフ株式会社の方は、CWGからの番頭である菅原さんが社長として切り盛りするということで、杉本夫妻はこれまで以上にシャトー・イガイタカハにフォーカスしていくことになるそうです。
ますますのご活躍を祈念します。

UCデーヴィスが学生が造ったワインを初めて市販します。ワインのブランドは「Hilgard631」。Hilgardは土壌科学者、ブドウ栽培家、そしてカリフォルニア農業の成功の基盤を築き続けてきた大学農業試験場(AES)の初代所長を務めたユージン・ヒルガード博士に敬意を表して名付けられました。631という数字は、UCデーヴィスのLEEDプラチナム認証を受けた教育研究ワイナリーのストリート・アドレスです。このワイナリーは、持続可能性においてこの栄誉を世界で初めて獲得したワイナリーです。
2021年に成立した州法で、ワインを非営利団体に移管して販売する方法が合法になりました。売り上げは学生の奨学金に当てられます。
ブドウ畑はUCデーヴィスの周辺のほか、ナパのオークヴィルのかつてのト・カロン・ヴィンヤードの一部だったオークヴィル・ステーションがあります。オークヴィルの畑からはカベルネ・ソーヴィニヨンとソーヴィニヨン・ブランを販売します。ワインのラベルも学生がカスタムで制作しています。
なお、販売は6月24日、25日、26日、7月10日、24日の五日間。午後2時から午後4時にデーヴィスの教育研究ワイナリーで行います。事前予約などはなく、先着順での販売です。
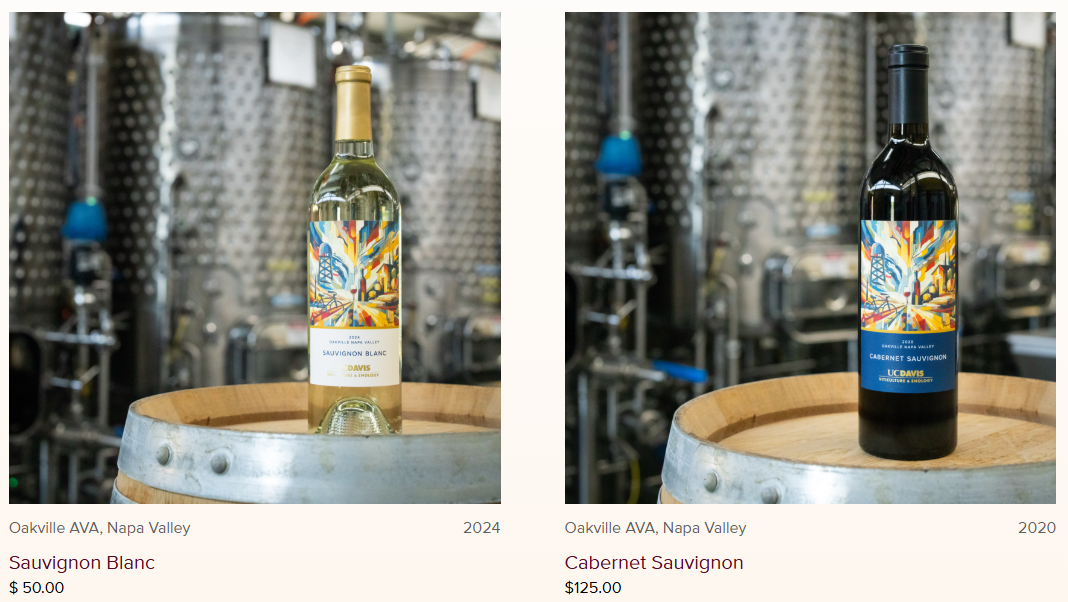

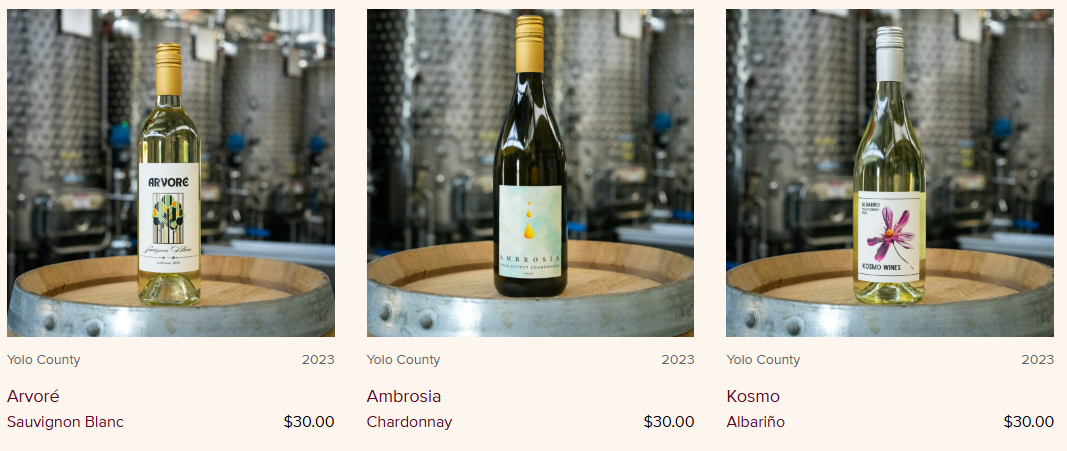
国内未輸入のナパのワイナリー「INNOVATUS(イノヴェータス)」のセミナーに参加してきました。


INNOVATUSの創設者でワインメーカーのセシル・パークさんは韓国・ソウルの出身。大学を出て2001年に米国に来るまではワインを口にしたこともなかったといいます。そこからUC Davisでワイン造りを勉強し、2007年に韓国人としてはナパ初のワインメーカーになりました。カスタム・クラッシュとして有名なNapa Wine Co.のラボで働き、様々な有名なワイナリーやハイジ・バレットなどのワインメーカーとの経験や試飲を積み重ねました。また、ナパとソノマで40を超える畑を見てきており、有機栽培やサスティナブルの栽培についてもエキスパートです。

ワイナリー名は「イノベーション(変革)」のラテン語。ラベルにはグリフィン(上半身が鷲または鷹で、下半身がライオンという伝説上の生き物)が描かれています。これはナパの起業家精神やセシルのこれまでの歩みの象徴です。韓国出身の女性ワインメーカーとして、日本におけるアキコ・フリーマンさんのようになりたいとのことでした。
変革の意味を持つワイナリー名とマッチする、このワイナリーらしいワインがCuvee(キュヴェ)という赤ワイン。2020年のものを試飲しましたが、57%ピノ・ノワール、37%シラー、6%カベルネ・フランというユニークな構成です。
ピノ・ノワールとシラーのブレンドというと、2000年代前半のピノ・ノワール・ブームで濃いピノ・ノワールがはやったころには、少量のシラーをブレンドしたピノ・ノワールというのが時折見られましたが、ここのように4割近くもシラーを入れるのを見たことがありません。ピノ・ノワールはカーネロス、シラーはカリストガ、カベルネ・フランはオークヴィルと、ナパの有名産地のブドウを使っています。
第一印象は甘草やプルーンの甘い香りでブラック・ペッパーなどのスパイシーさもありシラーらしさが感じられます。ストラクチャーもありますが、重厚なワインではなく、軽やかさが感じられます。美味しいし、面白い。ジェームズ・サックリングが92点を付けています。
白ワインではヴィオニエを作っているのがユニークです。ヴィオニエはナパでは2%にも満たない品種。ヨントヴィルの畑のブドウを使っています。2023年のヴィオニエはサックリング93点。
白い花の香りや白桃など、ヴィオニエらしさがムンムンとしています。アロマティックでバランスよく魅力的。ヴィオニエとして、特別感はありませんが、ナパのヴィオニエという希少価値はあります。
もう一つユニークなのがヴィオニエでスパークリングも作っていることです。100%カーネロスのヴィオニエを使い、瓶内二次発酵による本格的なスパークリング・ワイン。ドサージュは1%以下とドライな造りです。元々スチルワインのヴィオニエにするつもりで造っていたのですが、一次発酵が終わったところで、ピュアさと酸の強さから、スパークリングに向くのではないかと思って作ったワインだそうです。
イースト感少しあり、香りも豊かでフレッシュ。シャルドネベースのスパークリングと比べるとちょっとリッチな感じはあるかなあと思いますが、ヴィオニエらしい香りはあまり感じられませんでした。ユニークなワインだけに、味わい的にももう少しユニークさが欲しい感じはします。ある参加者は、瓶内二次発酵でなく炭酸ガス注入とかで、ヴィオニエのスパークリングにしてみた方が面白いのではないかという意見を言っており、確かにその方が味わいのユニークさは出るかもしれないと思いました。
あとの2本は品種的には珍しいものではありません。
2021年のジンファンデルはソノマヴァレーの86歳の樹齢の畑から。5%カベルネ・ソーヴィニョンを加えて味を引き締めています。
ザクロやレッドチェリーの赤果実の香り。口に含むとブルーベリーっぽさもあります。酸高くタンニンもあり、美味しいジンファンデルです。全房25%使用。
最後は2018年のカベルネ・ソーヴィニヨン。ラザフォードのブドウを使っています。
スパイシー、タニックで華やかなカベルネ・ソーヴィニヨン。美味しいですが、群雄割拠のナパのカベルネの中で特別感を出すのは難しいところに感じました。
キュヴェなどまた飲みたいと思わせてくれるワインもあり、輸入元が出てくることを期待しております。


INNOVATUSの創設者でワインメーカーのセシル・パークさんは韓国・ソウルの出身。大学を出て2001年に米国に来るまではワインを口にしたこともなかったといいます。そこからUC Davisでワイン造りを勉強し、2007年に韓国人としてはナパ初のワインメーカーになりました。カスタム・クラッシュとして有名なNapa Wine Co.のラボで働き、様々な有名なワイナリーやハイジ・バレットなどのワインメーカーとの経験や試飲を積み重ねました。また、ナパとソノマで40を超える畑を見てきており、有機栽培やサスティナブルの栽培についてもエキスパートです。

ワイナリー名は「イノベーション(変革)」のラテン語。ラベルにはグリフィン(上半身が鷲または鷹で、下半身がライオンという伝説上の生き物)が描かれています。これはナパの起業家精神やセシルのこれまでの歩みの象徴です。韓国出身の女性ワインメーカーとして、日本におけるアキコ・フリーマンさんのようになりたいとのことでした。
変革の意味を持つワイナリー名とマッチする、このワイナリーらしいワインがCuvee(キュヴェ)という赤ワイン。2020年のものを試飲しましたが、57%ピノ・ノワール、37%シラー、6%カベルネ・フランというユニークな構成です。
ピノ・ノワールとシラーのブレンドというと、2000年代前半のピノ・ノワール・ブームで濃いピノ・ノワールがはやったころには、少量のシラーをブレンドしたピノ・ノワールというのが時折見られましたが、ここのように4割近くもシラーを入れるのを見たことがありません。ピノ・ノワールはカーネロス、シラーはカリストガ、カベルネ・フランはオークヴィルと、ナパの有名産地のブドウを使っています。
第一印象は甘草やプルーンの甘い香りでブラック・ペッパーなどのスパイシーさもありシラーらしさが感じられます。ストラクチャーもありますが、重厚なワインではなく、軽やかさが感じられます。美味しいし、面白い。ジェームズ・サックリングが92点を付けています。
白ワインではヴィオニエを作っているのがユニークです。ヴィオニエはナパでは2%にも満たない品種。ヨントヴィルの畑のブドウを使っています。2023年のヴィオニエはサックリング93点。
白い花の香りや白桃など、ヴィオニエらしさがムンムンとしています。アロマティックでバランスよく魅力的。ヴィオニエとして、特別感はありませんが、ナパのヴィオニエという希少価値はあります。
もう一つユニークなのがヴィオニエでスパークリングも作っていることです。100%カーネロスのヴィオニエを使い、瓶内二次発酵による本格的なスパークリング・ワイン。ドサージュは1%以下とドライな造りです。元々スチルワインのヴィオニエにするつもりで造っていたのですが、一次発酵が終わったところで、ピュアさと酸の強さから、スパークリングに向くのではないかと思って作ったワインだそうです。
イースト感少しあり、香りも豊かでフレッシュ。シャルドネベースのスパークリングと比べるとちょっとリッチな感じはあるかなあと思いますが、ヴィオニエらしい香りはあまり感じられませんでした。ユニークなワインだけに、味わい的にももう少しユニークさが欲しい感じはします。ある参加者は、瓶内二次発酵でなく炭酸ガス注入とかで、ヴィオニエのスパークリングにしてみた方が面白いのではないかという意見を言っており、確かにその方が味わいのユニークさは出るかもしれないと思いました。
あとの2本は品種的には珍しいものではありません。
2021年のジンファンデルはソノマヴァレーの86歳の樹齢の畑から。5%カベルネ・ソーヴィニョンを加えて味を引き締めています。
ザクロやレッドチェリーの赤果実の香り。口に含むとブルーベリーっぽさもあります。酸高くタンニンもあり、美味しいジンファンデルです。全房25%使用。
最後は2018年のカベルネ・ソーヴィニヨン。ラザフォードのブドウを使っています。
スパイシー、タニックで華やかなカベルネ・ソーヴィニヨン。美味しいですが、群雄割拠のナパのカベルネの中で特別感を出すのは難しいところに感じました。
キュヴェなどまた飲みたいと思わせてくれるワインもあり、輸入元が出てくることを期待しております。

ジャン・シャルル・ボワセのワイナリーであるナパのレイモンド(Raymond)とソノマのデローチ(DeLoach)が木曜日と日曜日に無料テイスティングを提供すると発表しました。テイスティング・フィーが高騰する中での大胆な方策が注目されます。
「私たちは、人々をワインの世界へと導くために存在しています。教育と楽しみが、あらゆる年齢層の次世代のワイン消費者を刺激する力になると信じています。私たちのワイナリーは、つながり、インスピレーション、知識、そして興奮を生み出すプラットフォームです」とジャン・シャルル・ボワセは語っています。
テイスティングの監修を務めたのはボワセ・コレクションのゲスト体験担当副社長のクレア・トゥーリーMW(写真右)。「今こそ、ワインコミュニティがオープンで、インクルーシブで、魅力的で、刺激的な存在であることを世界に発信することが、これまで以上に重要になっています」と語っています。
デローチではワイナリーとロシアン・リバー・ヴァレーのつながりを紹介する試飲でピノ・ノワールとシャルドネ、ジンファンデルが提供されます。ビオディナミなどの栽培についても解説しています。
レイモンドではソーヴィニョン・ブラン、シャルドネ、メルロー、カベルネ・ソーヴィニョンから3種類が提供されます。ビオディナミの畑から自然の劇場、そしてプライベートな香水感覚庭園までを巡り、自然の美しさと静けさに囲まれたワイナリーツアーとワインの試飲で締めくくる「感覚の旅:ブドウ園、庭園、ワイナリーの没入型ツアー」など、新たな没入型体験を生み出しました。
6月6日と7日にオークション・ナパヴァレーが開かれました。総落札額は650万ドルで、これらは地域のチャリティ用、具体的には青少年のに使われます。6日のバレル・オークションはルイ・M・マルティニで、7日のライブ・オークションはシャンドンで行われました。入札はリアルのほかオンラインでも受け付けました。バレル・オークションでは700人を超える人がオンラインで入札したといいます。

土曜日のライブ・オークション上位ロットには、シャペレー・ヴィンヤード、プリド・ウォーカー、カーディナル、アルファ・オメガ、シェーファー、ピーター・マイケル、Bセラーズ、ダリオッシュ、セブン・ストーンズ、エルマンからの出品が含まれていました。
金曜日のバレル・オークションでは、アンティノリとスタッグス・リープ・ワインセラーズ、アルファ オメガとブシェーヌ、サン・スペリーとシャネル、ダリオッシュとザ ・ワールド、ケンゾー・エステートが上位ロットでした。

土曜日のライブ・オークション上位ロットには、シャペレー・ヴィンヤード、プリド・ウォーカー、カーディナル、アルファ・オメガ、シェーファー、ピーター・マイケル、Bセラーズ、ダリオッシュ、セブン・ストーンズ、エルマンからの出品が含まれていました。
金曜日のバレル・オークションでは、アンティノリとスタッグス・リープ・ワインセラーズ、アルファ オメガとブシェーヌ、サン・スペリーとシャネル、ダリオッシュとザ ・ワールド、ケンゾー・エステートが上位ロットでした。
18世紀に遡る歴史を持つというブルゴーニュのド・モンティーユ家(現代のワイン造りは1947年から)。現在の当主のエティエンヌは挑戦的な人で、最近では北海道でもワイン造りを始めていますが、彼がブルゴーニュ外で最初に作ったワイナリーがサンタ・バーバラのラシーヌ(Racines)です。そのエティエンヌが来日し、セミナーに参加してきました。


実は、ブルゴーニュのド・モンティーユのスタッフは半数以上はフランス以外の国の人だそうです。彼らは皆、世界でシャルドネややピノ・ノワールがどう栽培されているのかについて非常に興味を持っています。さまざまなバックグラウンドの人たちの専門知識を資産としています。その一人が米国出身のワインメーカーであるブライアン・シーヴ。2010年にド・モンティーユのセラーマスターになりました。
ブライアンなどと、どこがピノ・ノワールとシャルドネに向いているか、エレガントでフレッシュなシャルドネとピノ・ノワールが作れるのか考えました。フランスではマコンやラングドック、ジュラなども可能性はあると思いましたが、素晴らしいポテンシャルを持ったテロワールはどこにあるかを、まず米国で始めてみよう、だめだったら南半球を探してみよう、ということになりました。
そこで、エティエンヌとブライアンは1カ月かけて米国西海岸の4カ所の産地を回りました。その4カ所はオレゴンのウィラメット・ヴァレー、カリフォルニアのソノマ・コースト、サンタ・クルーズ・マウンテンズ、そしてサンタ・バーバラのサンタ・リタ・ヒルズです。ワインを試飲し、畑を見て回りました。どこも素晴らしいワインを作っていましたが、中でももっとも面白いのはサンタ・リタ・ヒルズだと思いました。その理由は、この4カ所のうちで一番冷涼であることと、土壌の多様さです。
サンタ・リタ・ヒルズはこの4カ所の中で一番南にあります。それでも一番冷涼なのは太平洋からの冷気を直接浴びる産地だからです。カリフォルニアの沿岸は寒流が流れており、海水の温度は非常に低くなります。ただ沿岸に沿って南北に沿岸山脈があり、それによって冷気が遮られるため、内陸の気温は高くなります。サンタ・リタ・ヒルズのところは沿岸山脈が東西向きになり、西からの冷気が遮るものなく入ってきます。これが、サンタ・リタ・ヒルズが北の産地よりも冷涼になる理由です。
ただ、内陸に進むとどんどん気温が上がります。1マイル(1.6km)内陸に行くと華氏で1度(摂氏0.4度ほど)気温が上がると言われています。したがって畑がどこにあるかが非常に重要になります。
第2の理由の土壌の多様さですが、サンタ・リタ・ヒルズには三つの主要な土壌があります。一つは砂、一つは粘土、そして三つ目が石灰質の土壌です。石灰質といってもブルゴーニュに見られる石灰岩ではなく、珪藻による珪藻土ですが、化学的特徴は似ています。余談ですが、サンタ・リタ・ヒルズでエレガントなシャルドネを造るワイナリーの名称「ダイアトム(Diatom)」は珪藻という意味です。
米国では数少ない石灰質の土壌があることと畑の向きや海からの距離で多様性が生まれるといったテロワールによって、この土地を選びました。
ワイナリーの設立は2016年、ワイン造りは2017年に始まりました。ウェンズロー(Wenzlau)とド・モンティーユ・エステート(De Montille Estate)の二つの自社畑があります。ウェンズローの方は既に単一畑ものが出ていますが、ド・モンティーユの方は植樹が2019年と若く、今後自社畑としてリリースしていく予定です。それ以外に、銘醸畑として知られるサンフォード&ベネディクト(Sanford & Bennedict)やラ・リンコナーダ(La Rinconada)など様々な栽培家からブドウを調達していると言います。ワインの醸造はサンタ・リタ・ヒルズ西側のロンポックにあるワイン・ゲットーという多くのワイナリーが集結している一種のカスタム・クラッシュで行っています。2026年には専用の醸造設備とテイスティングルームもできるとのことです。

ワインの試飲に入ります。
最初はスパークリングです。ラシーヌにはエティエンヌとブライアンのほか、シャンパーニュのピエール・ペテルスの醸造家で、様々なコンサルティングも手掛けているロドルフ・ペテルスも参画しています。ブラン・ド・ブランのエクストラ・ブリュットが造れるところを探していて、海からの潮風で塩味のニュアンスが出るサンタ・リタ・ヒルズが好適地だと考えたそうです。ロドルフは完璧主義で、収穫時のpHや醸造などについて極めて細かく指示を出しており、その通りに作っています。
1. NV Grand Reserve Chardonnay Sparkling Wine Sta. Rita Hills(希望小売価格、税抜き1万2500円、以下同)
ノンヴィンテージですが、今回のものは2020年をベースにして2018年と2019年のリザーブ・ワインが半分使われています。リザーブのワインはソレラになっているそうです。ドサージュは4g/Lとエクストラ・ブリュットになっています。畑は自社畑のウェンズローのほか、サンフォードが持つサンフォード&ベネディクトとラ・リンコナーダ、ザ・ヒルトが持つベントロック(Bentrock)のシャルドネを使っています。
イーストやブリオッシュ、青リンゴやレモンの香り。酸高く泡のきめ細かさを感じます。フレッシュでアフターに少し塩っぽさがあります。とてもきれいなブラン・ド・ブランらしいスパークリング。
エティエンヌがこのワインを家で友人に振る舞うと、ほとんどの人がシャンパーニュのブラン・ド・ブランだと思うそうです。最近はネタバレしてしまって、引っかかってくれなくなってしまったそうですが。
スパークリングとしては2026年に単一畑、単一ヴィンテージのものを出す予定です。2018年のワインでディスゴージまで6年熟成させています。より深い味わいになっているとのことです。
スパークリングの後はシャルドネ4種です。一つはサンタ・リタ・ヒルズのAVAもので、あとの3つは単一畑です。シャルドネの醸造はブルゴーニュとほとんど同じ手順を踏みます。収穫は夜間、人手で摘んでいます。ゆっくりとプレスし、澱とのコンタクトを長く保ちます。発酵は半分は小樽で半分は600Lのパンチョンを使います。樽はフランス製です。新樽はAVAもので10%、単一畑では20~25%。澱とともにステンレスタンクに移して5カ月熟成して瓶詰めします。
瓶詰め前に清澄をかけますが、面白いのはそのときにサンプルをブルゴーニュに送って、ブルゴーニュでどのように清澄するのかを決めているのだそうです。
AVAもののサンタ・リタ・ヒルズ・キュベはこのAVAの3種類の土壌のブドウをブレンドしています、このAVAのテロワールが感じられるワインです。
2. Sta. Rita Hills Cuvee Chardonnay 2020(1万500円)
熟した柑橘の風味、オレンジピールのようなちょっとした苦み、クリーム・ブリュレ。酸やや高くクリーミーで美味しい。
3. Wenslau Vineyard Chardonnay 2020(1万7500円)
ウェンズラウは砂質の土壌です。
クリーミーでフレッシュ、よりハーブの香りやアフターの塩味が感じられます。白桃の熟したニュアンスもあり、個性的です。
4. Bentrock Vineyard Chardonnay 2020(2万円)
ベントロックはザ・ヒルトの畑でサンタ・リタ・ヒルズの中では西寄りの涼しいところにあります。ここはアルカリ性の土壌です。
鮮烈な酸があり、柑橘の風味とハーブの香りが強く感じられます。一番ミネラル感が感じられるワイン
5. Sanford&Benedict Chardonnay 2020(2万円)
サンフォード&ベネディクトはサンタ・リタ・ヒルズで一番古い畑であり、銘醸畑として知られています。土壌は粘土質です。
少しオイリーなニュアンス、柑橘から白桃を感じます、他のシャルドネよりちょっとボリューム感があります。
4つのシャルドネに共通するのはフレッシュ感とミネラル感。アルコール度数は12.8~13.2(S&B)と現在のブルゴーニュよりも低くなっています。
ピノ・ノワールの試飲に移ります。
ピノ・ノワールのワイン造りもブルゴーニュとほぼ同じです。全房をやや多く使うのが特徴です。30%程度使っているとのこと。新樽率は15~20%。優しい抽出をこころがけていて、果帽の管理ではパンチダウンよりもポンピングオーバーを多くやるそうです。パンチダウンは果帽に圧力をかけることになるので全房の茎からの抽出が強くなってしまいます。ポンピングオーバーの方が自然な抽出ができるとのこと。
試飲ワインはシャルドネと同様、4種類です。
6. Sta. Rita Hills Cuvee Pinot Noir 2020(1万1500円)
シャルドネ同様、三つの土壌のブドウを組み合わせています。
ラズベリーやクランベリー。ちょっとグリップ感というか青っぽさを感じるのは全房のためでしょうか、エレガントですがチューイーな魅力もあります。
7. Saint Rose Pinot Noir 2020(1万6000円)
これは単一畑ではなくサンタ・リタ・ヒルズ・キュベの中から8~10樽を選んだものになります。
AVAものよりもより果実味が前面に出ていて明るい味わい。タンニンの一体感や余韻も感じられます。
8. La Rinconada Vineyard Pinot Noir 2019(1万8000円)
ここは砂利質でアルカリ性の土壌です。
ラズベリーやクランベリー、エレガントでしなやかなテクスチャー。シナモンのようなスパイスもわずかに感じられます。全房率は2/3くらいと高くなっています。
9. Sanford&Benedict Pinot Noir 2020(2万2000円)
粘土質の土壌です。La RinconadaとSanford&Benedictは隣り合った畑なのですが、土壌が異なるのが興味深いです。
ラシーヌでは1971年に植えたオリジナルプランティングの一部をもらっているそうです。
色濃く、赤果実にブラックベリーなど黒果実の風味、シナモン、複雑さが一番多くあり、非常に美味しい
ラシーヌのワインは、アルコール度数抑え目ですが、きっちり風味もあり、エレガントで美味しいものがそろっています。カリフォルニアのシャルドネ、ピノ・ノワールの中では、ブルゴーニュの名家が手掛けていることもあり、珍しくフランスワインファンにも人気の高いワインとなっています。
実はサンタ・リタ・ヒルズのワインは比較的アルコール度数は高くなりがち(非常に冷涼ですが太陽は当たるため、風味の成熟を待つと糖度も上がりがち)なのですが、それをうまく抑えているところが、非常に上手だと感じました。品質も安定して高く、安心して飲めるという点で、人気が高いのもなるほどと思わせるものがありました。
実は、ブルゴーニュのド・モンティーユのスタッフは半数以上はフランス以外の国の人だそうです。彼らは皆、世界でシャルドネややピノ・ノワールがどう栽培されているのかについて非常に興味を持っています。さまざまなバックグラウンドの人たちの専門知識を資産としています。その一人が米国出身のワインメーカーであるブライアン・シーヴ。2010年にド・モンティーユのセラーマスターになりました。
ブライアンなどと、どこがピノ・ノワールとシャルドネに向いているか、エレガントでフレッシュなシャルドネとピノ・ノワールが作れるのか考えました。フランスではマコンやラングドック、ジュラなども可能性はあると思いましたが、素晴らしいポテンシャルを持ったテロワールはどこにあるかを、まず米国で始めてみよう、だめだったら南半球を探してみよう、ということになりました。
そこで、エティエンヌとブライアンは1カ月かけて米国西海岸の4カ所の産地を回りました。その4カ所はオレゴンのウィラメット・ヴァレー、カリフォルニアのソノマ・コースト、サンタ・クルーズ・マウンテンズ、そしてサンタ・バーバラのサンタ・リタ・ヒルズです。ワインを試飲し、畑を見て回りました。どこも素晴らしいワインを作っていましたが、中でももっとも面白いのはサンタ・リタ・ヒルズだと思いました。その理由は、この4カ所のうちで一番冷涼であることと、土壌の多様さです。
サンタ・リタ・ヒルズはこの4カ所の中で一番南にあります。それでも一番冷涼なのは太平洋からの冷気を直接浴びる産地だからです。カリフォルニアの沿岸は寒流が流れており、海水の温度は非常に低くなります。ただ沿岸に沿って南北に沿岸山脈があり、それによって冷気が遮られるため、内陸の気温は高くなります。サンタ・リタ・ヒルズのところは沿岸山脈が東西向きになり、西からの冷気が遮るものなく入ってきます。これが、サンタ・リタ・ヒルズが北の産地よりも冷涼になる理由です。
ただ、内陸に進むとどんどん気温が上がります。1マイル(1.6km)内陸に行くと華氏で1度(摂氏0.4度ほど)気温が上がると言われています。したがって畑がどこにあるかが非常に重要になります。
第2の理由の土壌の多様さですが、サンタ・リタ・ヒルズには三つの主要な土壌があります。一つは砂、一つは粘土、そして三つ目が石灰質の土壌です。石灰質といってもブルゴーニュに見られる石灰岩ではなく、珪藻による珪藻土ですが、化学的特徴は似ています。余談ですが、サンタ・リタ・ヒルズでエレガントなシャルドネを造るワイナリーの名称「ダイアトム(Diatom)」は珪藻という意味です。
米国では数少ない石灰質の土壌があることと畑の向きや海からの距離で多様性が生まれるといったテロワールによって、この土地を選びました。
ワイナリーの設立は2016年、ワイン造りは2017年に始まりました。ウェンズロー(Wenzlau)とド・モンティーユ・エステート(De Montille Estate)の二つの自社畑があります。ウェンズローの方は既に単一畑ものが出ていますが、ド・モンティーユの方は植樹が2019年と若く、今後自社畑としてリリースしていく予定です。それ以外に、銘醸畑として知られるサンフォード&ベネディクト(Sanford & Bennedict)やラ・リンコナーダ(La Rinconada)など様々な栽培家からブドウを調達していると言います。ワインの醸造はサンタ・リタ・ヒルズ西側のロンポックにあるワイン・ゲットーという多くのワイナリーが集結している一種のカスタム・クラッシュで行っています。2026年には専用の醸造設備とテイスティングルームもできるとのことです。

ワインの試飲に入ります。
最初はスパークリングです。ラシーヌにはエティエンヌとブライアンのほか、シャンパーニュのピエール・ペテルスの醸造家で、様々なコンサルティングも手掛けているロドルフ・ペテルスも参画しています。ブラン・ド・ブランのエクストラ・ブリュットが造れるところを探していて、海からの潮風で塩味のニュアンスが出るサンタ・リタ・ヒルズが好適地だと考えたそうです。ロドルフは完璧主義で、収穫時のpHや醸造などについて極めて細かく指示を出しており、その通りに作っています。
1. NV Grand Reserve Chardonnay Sparkling Wine Sta. Rita Hills(希望小売価格、税抜き1万2500円、以下同)
ノンヴィンテージですが、今回のものは2020年をベースにして2018年と2019年のリザーブ・ワインが半分使われています。リザーブのワインはソレラになっているそうです。ドサージュは4g/Lとエクストラ・ブリュットになっています。畑は自社畑のウェンズローのほか、サンフォードが持つサンフォード&ベネディクトとラ・リンコナーダ、ザ・ヒルトが持つベントロック(Bentrock)のシャルドネを使っています。
イーストやブリオッシュ、青リンゴやレモンの香り。酸高く泡のきめ細かさを感じます。フレッシュでアフターに少し塩っぽさがあります。とてもきれいなブラン・ド・ブランらしいスパークリング。
エティエンヌがこのワインを家で友人に振る舞うと、ほとんどの人がシャンパーニュのブラン・ド・ブランだと思うそうです。最近はネタバレしてしまって、引っかかってくれなくなってしまったそうですが。
スパークリングとしては2026年に単一畑、単一ヴィンテージのものを出す予定です。2018年のワインでディスゴージまで6年熟成させています。より深い味わいになっているとのことです。
スパークリングの後はシャルドネ4種です。一つはサンタ・リタ・ヒルズのAVAもので、あとの3つは単一畑です。シャルドネの醸造はブルゴーニュとほとんど同じ手順を踏みます。収穫は夜間、人手で摘んでいます。ゆっくりとプレスし、澱とのコンタクトを長く保ちます。発酵は半分は小樽で半分は600Lのパンチョンを使います。樽はフランス製です。新樽はAVAもので10%、単一畑では20~25%。澱とともにステンレスタンクに移して5カ月熟成して瓶詰めします。
瓶詰め前に清澄をかけますが、面白いのはそのときにサンプルをブルゴーニュに送って、ブルゴーニュでどのように清澄するのかを決めているのだそうです。
AVAもののサンタ・リタ・ヒルズ・キュベはこのAVAの3種類の土壌のブドウをブレンドしています、このAVAのテロワールが感じられるワインです。
2. Sta. Rita Hills Cuvee Chardonnay 2020(1万500円)
熟した柑橘の風味、オレンジピールのようなちょっとした苦み、クリーム・ブリュレ。酸やや高くクリーミーで美味しい。
3. Wenslau Vineyard Chardonnay 2020(1万7500円)
ウェンズラウは砂質の土壌です。
クリーミーでフレッシュ、よりハーブの香りやアフターの塩味が感じられます。白桃の熟したニュアンスもあり、個性的です。
4. Bentrock Vineyard Chardonnay 2020(2万円)
ベントロックはザ・ヒルトの畑でサンタ・リタ・ヒルズの中では西寄りの涼しいところにあります。ここはアルカリ性の土壌です。
鮮烈な酸があり、柑橘の風味とハーブの香りが強く感じられます。一番ミネラル感が感じられるワイン
5. Sanford&Benedict Chardonnay 2020(2万円)
サンフォード&ベネディクトはサンタ・リタ・ヒルズで一番古い畑であり、銘醸畑として知られています。土壌は粘土質です。
少しオイリーなニュアンス、柑橘から白桃を感じます、他のシャルドネよりちょっとボリューム感があります。
4つのシャルドネに共通するのはフレッシュ感とミネラル感。アルコール度数は12.8~13.2(S&B)と現在のブルゴーニュよりも低くなっています。
ピノ・ノワールの試飲に移ります。
ピノ・ノワールのワイン造りもブルゴーニュとほぼ同じです。全房をやや多く使うのが特徴です。30%程度使っているとのこと。新樽率は15~20%。優しい抽出をこころがけていて、果帽の管理ではパンチダウンよりもポンピングオーバーを多くやるそうです。パンチダウンは果帽に圧力をかけることになるので全房の茎からの抽出が強くなってしまいます。ポンピングオーバーの方が自然な抽出ができるとのこと。
試飲ワインはシャルドネと同様、4種類です。
6. Sta. Rita Hills Cuvee Pinot Noir 2020(1万1500円)
シャルドネ同様、三つの土壌のブドウを組み合わせています。
ラズベリーやクランベリー。ちょっとグリップ感というか青っぽさを感じるのは全房のためでしょうか、エレガントですがチューイーな魅力もあります。
7. Saint Rose Pinot Noir 2020(1万6000円)
これは単一畑ではなくサンタ・リタ・ヒルズ・キュベの中から8~10樽を選んだものになります。
AVAものよりもより果実味が前面に出ていて明るい味わい。タンニンの一体感や余韻も感じられます。
8. La Rinconada Vineyard Pinot Noir 2019(1万8000円)
ここは砂利質でアルカリ性の土壌です。
ラズベリーやクランベリー、エレガントでしなやかなテクスチャー。シナモンのようなスパイスもわずかに感じられます。全房率は2/3くらいと高くなっています。
9. Sanford&Benedict Pinot Noir 2020(2万2000円)
粘土質の土壌です。La RinconadaとSanford&Benedictは隣り合った畑なのですが、土壌が異なるのが興味深いです。
ラシーヌでは1971年に植えたオリジナルプランティングの一部をもらっているそうです。
色濃く、赤果実にブラックベリーなど黒果実の風味、シナモン、複雑さが一番多くあり、非常に美味しい
ラシーヌのワインは、アルコール度数抑え目ですが、きっちり風味もあり、エレガントで美味しいものがそろっています。カリフォルニアのシャルドネ、ピノ・ノワールの中では、ブルゴーニュの名家が手掛けていることもあり、珍しくフランスワインファンにも人気の高いワインとなっています。
実はサンタ・リタ・ヒルズのワインは比較的アルコール度数は高くなりがち(非常に冷涼ですが太陽は当たるため、風味の成熟を待つと糖度も上がりがち)なのですが、それをうまく抑えているところが、非常に上手だと感じました。品質も安定して高く、安心して飲めるという点で、人気が高いのもなるほどと思わせるものがありました。

先日の記事のこぼれ話ですが、コルギンはプリチャード・ヒルに新しい畑を開墾しているそうです。おそらく、上の地図で「新しい畑」と記したところがそこだと思います。
コルギンのプリチャード・ヒルの地所は137エーカーあります。現在のIX Estateの畑は20エーカーで、地所全体の15%ほどに過ぎません。新しい畑は、地所の中のこれまで森だったところで、小川を挟んでIX Estateの反対側の丘にあります。プリチャード・ヒルは大きく分けると2つの丘からなるのですが、これは北東側の丘で、シャペレー(Chappellet)やコンティニュアム(Continuum)などああります。新しい畑はメランソン(Melanson)とコンティニュアムに挟まれた辺りになります。
土壌的にはIX Estateと同様、岩がごろごろしています。当初3年間は気温がIX Estateとどう変わるかなどを調べ、2016年から開墾を始めています。これまでの畑と大きく異なるのは斜面が北西向きであること。斜面は非常に急で低いところと高いところの標高差は80mくらいあるようです。気温はIX Estateより華氏1度くらい高くなるとのこと。
畑の面積は27ヘクタールほどと、IX Estateよりも広くなります。
植樹は5年前と2年前に行っています。2023年には5年前に植樹したブロックから1エーカーあたり0.65トンという極少量だけ収穫。2024年には1.5トン/エーカーと少し増えてきました。これらは発酵して現在樽に入っていますが、どうするかはまだ決めていません。おそらく最初はジュビレーションに使っていくことになると思います。
畑の名前は、現状IX Estate Eastと呼んでいますが、正式には決まっていません。
品種はカベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フラン、また少量のシラーを植えています。
こちらがどういうワインになっていくのか、また興味深いです。
ナパの超高級ワイン「コルギン・セラーズ(Colgin Cellars)」からCOOのニール・ベルナルディMWが来日し、ランチセミナーに参加してきました。


ニール・ベルナルディさんはUC Davisで学び、ニュージーランドやオレゴン、ワシントンでワインメーカーの経歴を積み、カリフォルニアではリトライを経てダックホーンの主任ワインメーカーを務めていました。15年間の間にマイグレーションやコスタ・ブラウンでのワイン造りなども経験してきました。2018年にはワイン・エンスージアスト誌の「40歳以下の40人」にも選ばれています。マスター・オブ・ワインには2024年に合格しています。ちなみに、マスター・オブ・ワインの論文テーマは「瓶内二次発酵のスパークリング・ワインにおける澱の攪拌の官能的影響」で、「かなりマニアックな内容」だそうです。コルギンで働き始めたのは2023年で、ナパのトップワイナリーで働けることが嬉しいと、素直に語っていました。
コルギンの創設者で現在の会長はアン・コルギンさん。美術品のオークショニアでサザビーズ・ロンドンで働いていました。ワイナリーは1992年創設。当時の夫は後にシュレーダー・セラーズを造ったフレッド・シュレーダー。当初はセント・ヘレナ東方(昨年策定されたクリスタル・スプリングスAVA内)のハーブ・ラムという畑のカベルネ・ソーヴィニヨンを作っており、初代ワインメーカーはヘレン・ターリーでした。
その後、フレッドともヘレンとも決別し、ハーブ・ラムも契約が切れて、新生コルギンがスタートしました。1996年にティクソン・ヒル(Tychson Hill)の一部を購入、1998年にはプリチャード・ヒルにIX Estate(ナンバーナイン・エステート)という畑を切り開きました(2002年が初ヴィンテージ)。アン・コルギンは9という数字が好きで、今の夫でCEOのジョー・ウェンダーと結婚したのも9月9日でした。ワインメーカーはマーク・オーベールを経てアリソン・トージエ(Allison Tauziet)が2007年から務めています。2017年にはLVMH傘下に入りましたが、コルギン夫妻が変わらずにワイナリーの指揮を取っています。

さて、アン・コルギンさんといえば深紅の衣装がトレードマーク。衣装だけでなく深紅にこだわりを持っています。1997年のワイン・スペクテーターの記事には次のように書かれています。

ちなみに、コルギンのロゴ、「O」の書体が横に向いています。これは彼女の唇を模しているのではないかと思っているのですが、ベルナルディさんは理由を「聞いたことがない」とのことでした。「今度聞いてみてね」と言っておきましたがどうでしょうか。
この赤い色のように「情熱的で魅力的、信じられないほどのワインパーソナリティであって、ナパの最上、すなわち世界の最上のワインを造るというしっかりとしたビジョンを持っている」というのがベルナルディさんの見るアン・コルギンさんです。

コルギンは現在、3つの畑から、カベルネ・ソーヴィニヨン系ブレンドワインを造っており、IX Estateからはシラーも作っています。また、セカンドワインとしてジュビレーション(Jubilation)というカベルネ系ワインを造っています。これら赤ワイン5種が全ラインアップです。
三つの畑のうちティクソン・ヒルとカリアド(Cariad)はセント・ヘレナAVAに属しています。IX EstateはAVAとしてはナパヴァレーですが、プリチャード・ヒルと呼ばれるエリアの畑です。ティクソン・ヒルとカリアドはナパヴァレーの西側の山すそであり、プリチャード・ヒルは東側の丘になります。場所は異なりますが、斜面の畑であることと、斜面の向きが東寄りということが共通しています。東向きの斜面は朝日をしっかり浴びますが、夕方の強い日差しをあまり受けないので、西向き斜面よりもワインがエレガントになります。
それぞれの特徴については各ワインのところで説明します。

Jubilation 2021(希望小売価格税抜き5万円、以下同)
コルギンの他のワインが単一畑を基本としているのに対して、これは若く飲んで美味しい樽を選んでブレンドしたものです。単一畑は土地の個性を表現しますが、ブレンドものは「クリエイティビティ」だといいます。ジュビレーションというのは「喜び」や「祝祭」といった意味があります。早く開けて楽しんでもらうワインです。
品種構成は53%CS 26%M 13%CF 8%PV。IX Estateのものが一番多く入っています。
レッド・チェリーにカシスの風味、なめらかなタンニンで、鉄や血のニュアンスを感じました。早飲みタイプといっても軽いワインではなく、複雑でかなりしっかりした味わいを持っています。
Tychson Hill 2021(12万5000円)
ティクソン・ヒルは歴史的に重要な畑です。1881年にナパで最初の女性ワイナリーオーナーだったジョセフィーヌ・ティクソンが開墾した畑です。当時は主にジンファンデルが植えられていました。その後、禁酒法時代にブドウは抜かれましたが、コルギンが新たに畑を作りました。カベルネソーヴィニヨンが中心で、ここのワインだけは品種名が入っています。
セント・ヘレナの街を出て少し北に行ったところで、ナパ・ヴァレーの谷幅が急に狭くなる辺りです。ハイウェイの西側のスプリング・マウンテンの麓の畑です。ハイウェイの脇はかなりフラットに見えますが、山に向かってどんどん斜面が急になります。畑の一番高いところと低いところの差は40m近くあります。土壌は石がゴロゴロしています。火山性の石が多いですが黒曜石もあります。写真はコルギンのサイトから拝借しています。


ブルーベリーの豊かなフレーバーにカシス、コーヒー、たばこ。コルギンのワインの中では唯一青黒果実系の風味が強く、やや骨太の味わいです。酸やや高くバランスがいい。
Cariad 2021(12万5000円)
ティクソン・ヒルとIX Estateはコルギンの自社畑ですが、カリアドはコルギンの畑の管理を請け負っているデイビッド・エイブリューの畑のブドウを使っています。大部分は銘醸畑として名高いマドローナ・ランチ(Madrona Ranch)のブドウで、一部エコトーン(Ecotone)など、他のエイブリューの畑のブドウも入っています。ティクソン・ヒルと同じセント・ヘレナの西よりであり、距離も3kmほどしか離れていませんが、ティクソン・ヒルが火山性中心の土壌であるのの対し、こちらは沖積性。川底が持ち上がったところで、斜面も一様でなくうねったような形になっています。
56%CS 22%CF 14%M 8%PVという構成。

ティクソン・ヒルと比べるとラズベリーやレッド・チェリーなど赤果実の風味を強く感じます。タンニン強くちょっと閉じている印象がありました。飲み頃まで時間かかりそうと感じましたが、同じワインを別の会(一般向けのディナー)で飲んだ方はカリアドを絶賛しておりましたので、ボトル差があったのかもしれません。
IX Estate 2021(12万5000円)
畑は有機栽培をしています。植樹した部分のほかに100エーカーの森が残っています。これは生物多様性や、野生のままの土地と開墾した土地とのバランス。益鳥を呼び寄せるなどの意味があります。
畑は標高335~427mと高く、霧がかからないので、日較差は小さくなります。西向きの斜面の多いプリチャードヒルの中で東向きの急斜面というのが大きな特徴になります。土壌は火山性の玄武岩が崩れたものが中心。土地を購入したときはここは森であり、一から開墾する必要がありました。岩が多く、20万トンもの岩を取り除いたといいます。大きなものではバスくらいのサイズの岩もあったとか。土地の購入費用よりも、開墾の方がコストがかかったそうです。

開墾中は、この大型のトラクター/ブルドーザーがずっと畑にあり、岩を砕いていました。アン・コルギンとジョー・ウェンダーの結婚式のときに、彼女はウェディング・ドレスでこのトラクターに乗って道を降りて行ったのだそうです。
品種比率は不明ですが、カベルネソーヴィニヨンが70%程度でカベルネ・フランが20%程度、メルローとプティ・ヴェルドが残りくらいが通例です。

四つの2021年のワインの中で、圧倒的に華やかさを持っているのがこのワイン。きれいな赤い果実の風味にシルクのようなタンニン。優美で長い余韻。
以前、アン・コルギンさんが来日したときに、コルギンのワインで何を表現したいと考えているか聞いてみたところ「ピュアでエレガントなワイン」と言っていました。そのイメージに一番合うのはやはりIX Estateだと改めて思いました。
IX Estate 2014(14万円)
蔵出しのオールド・ヴィンテージで2014年のものもいただきました。2014年は干ばつの2年目で、ブドウは小さな実を付け凝縮感があるいいヴィンテージでした。この凝縮感のためか、タンニンはシルキーでギュッと詰まったような印象。また10年を過ぎても華やかさは健在。赤果実に熟成によるマッシュルームや皮の香りも出てきています。もう10年は熟成のピークに向かっていくと思います。

実は2014年と2021年、「O」の字の色が変わっています。2017年から色を微妙に変えたとのこと。
最後のワインはIX Estateのシラー2021です(6万5000円)。
アン・コルギンは北ローヌのコートロティやエルミタージュのシラーが好きで、シャーヴからシラーを譲り受けて植えたと以前聞きました。シラーのブロックは4エーカー。IX Estateの特徴として、タンニンの強さがあるため、100%除梗して造っています。
カベルネ・ソーヴィニヨンと比べると、スミレの花やリコリス、ベイキング・パウダーの甘い香りが特徴的です。ブリーベリーやプラムの香り、タンニンは少しグリップがありストラクチャーを与えています。個人的にはものすごく好きなシラー。
この日は、今年のナパヴァレー・ワイン・ベスト・ソムリエ・アンバサダーに選ばれた山本麻衣花さんがいるマンダリンオリエンタル東京のSignatureというレストランでの食事も付いていました。コルギンのそれぞれのワインとのペアリングを麻衣花さんがシェフと考えて作ったという素晴らしいメニュー。




ニール・ベルナルディさんはUC Davisで学び、ニュージーランドやオレゴン、ワシントンでワインメーカーの経歴を積み、カリフォルニアではリトライを経てダックホーンの主任ワインメーカーを務めていました。15年間の間にマイグレーションやコスタ・ブラウンでのワイン造りなども経験してきました。2018年にはワイン・エンスージアスト誌の「40歳以下の40人」にも選ばれています。マスター・オブ・ワインには2024年に合格しています。ちなみに、マスター・オブ・ワインの論文テーマは「瓶内二次発酵のスパークリング・ワインにおける澱の攪拌の官能的影響」で、「かなりマニアックな内容」だそうです。コルギンで働き始めたのは2023年で、ナパのトップワイナリーで働けることが嬉しいと、素直に語っていました。
コルギンの創設者で現在の会長はアン・コルギンさん。美術品のオークショニアでサザビーズ・ロンドンで働いていました。ワイナリーは1992年創設。当時の夫は後にシュレーダー・セラーズを造ったフレッド・シュレーダー。当初はセント・ヘレナ東方(昨年策定されたクリスタル・スプリングスAVA内)のハーブ・ラムという畑のカベルネ・ソーヴィニヨンを作っており、初代ワインメーカーはヘレン・ターリーでした。
その後、フレッドともヘレンとも決別し、ハーブ・ラムも契約が切れて、新生コルギンがスタートしました。1996年にティクソン・ヒル(Tychson Hill)の一部を購入、1998年にはプリチャード・ヒルにIX Estate(ナンバーナイン・エステート)という畑を切り開きました(2002年が初ヴィンテージ)。アン・コルギンは9という数字が好きで、今の夫でCEOのジョー・ウェンダーと結婚したのも9月9日でした。ワインメーカーはマーク・オーベールを経てアリソン・トージエ(Allison Tauziet)が2007年から務めています。2017年にはLVMH傘下に入りましたが、コルギン夫妻が変わらずにワイナリーの指揮を取っています。

さて、アン・コルギンさんといえば深紅の衣装がトレードマーク。衣装だけでなく深紅にこだわりを持っています。1997年のワイン・スペクテーターの記事には次のように書かれています。
彼女は赤をこよなく愛し、ワインだけでなく、ワードローブにも赤を取り入れています。先日の昼食会では、39歳の引き締まったコルギンさんは、明るいチェリートーンのスーツに、小さな赤い悪魔が2つエンボス加工された黒いパンプス、そして深紅の口紅を身につけていました。「口紅なしでワインにサインしたことは一度もありません」と彼女はにっこりと笑い、コルギンのカベルネ・ソーヴィニヨンのラベルにキスをしながらサインしました。きっかけは、あるオークションでカップルが落札したワインにサインを求められたことだったそうですが、今はどうだかわかりませんが、かつてはこのキスマークが彼女のトレードマークになっていました。

ちなみに、コルギンのロゴ、「O」の書体が横に向いています。これは彼女の唇を模しているのではないかと思っているのですが、ベルナルディさんは理由を「聞いたことがない」とのことでした。「今度聞いてみてね」と言っておきましたがどうでしょうか。
この赤い色のように「情熱的で魅力的、信じられないほどのワインパーソナリティであって、ナパの最上、すなわち世界の最上のワインを造るというしっかりとしたビジョンを持っている」というのがベルナルディさんの見るアン・コルギンさんです。

コルギンは現在、3つの畑から、カベルネ・ソーヴィニヨン系ブレンドワインを造っており、IX Estateからはシラーも作っています。また、セカンドワインとしてジュビレーション(Jubilation)というカベルネ系ワインを造っています。これら赤ワイン5種が全ラインアップです。
三つの畑のうちティクソン・ヒルとカリアド(Cariad)はセント・ヘレナAVAに属しています。IX EstateはAVAとしてはナパヴァレーですが、プリチャード・ヒルと呼ばれるエリアの畑です。ティクソン・ヒルとカリアドはナパヴァレーの西側の山すそであり、プリチャード・ヒルは東側の丘になります。場所は異なりますが、斜面の畑であることと、斜面の向きが東寄りということが共通しています。東向きの斜面は朝日をしっかり浴びますが、夕方の強い日差しをあまり受けないので、西向き斜面よりもワインがエレガントになります。
それぞれの特徴については各ワインのところで説明します。
Jubilation 2021(希望小売価格税抜き5万円、以下同)
コルギンの他のワインが単一畑を基本としているのに対して、これは若く飲んで美味しい樽を選んでブレンドしたものです。単一畑は土地の個性を表現しますが、ブレンドものは「クリエイティビティ」だといいます。ジュビレーションというのは「喜び」や「祝祭」といった意味があります。早く開けて楽しんでもらうワインです。
品種構成は53%CS 26%M 13%CF 8%PV。IX Estateのものが一番多く入っています。
レッド・チェリーにカシスの風味、なめらかなタンニンで、鉄や血のニュアンスを感じました。早飲みタイプといっても軽いワインではなく、複雑でかなりしっかりした味わいを持っています。
Tychson Hill 2021(12万5000円)
ティクソン・ヒルは歴史的に重要な畑です。1881年にナパで最初の女性ワイナリーオーナーだったジョセフィーヌ・ティクソンが開墾した畑です。当時は主にジンファンデルが植えられていました。その後、禁酒法時代にブドウは抜かれましたが、コルギンが新たに畑を作りました。カベルネソーヴィニヨンが中心で、ここのワインだけは品種名が入っています。
セント・ヘレナの街を出て少し北に行ったところで、ナパ・ヴァレーの谷幅が急に狭くなる辺りです。ハイウェイの西側のスプリング・マウンテンの麓の畑です。ハイウェイの脇はかなりフラットに見えますが、山に向かってどんどん斜面が急になります。畑の一番高いところと低いところの差は40m近くあります。土壌は石がゴロゴロしています。火山性の石が多いですが黒曜石もあります。写真はコルギンのサイトから拝借しています。


ブルーベリーの豊かなフレーバーにカシス、コーヒー、たばこ。コルギンのワインの中では唯一青黒果実系の風味が強く、やや骨太の味わいです。酸やや高くバランスがいい。
Cariad 2021(12万5000円)
ティクソン・ヒルとIX Estateはコルギンの自社畑ですが、カリアドはコルギンの畑の管理を請け負っているデイビッド・エイブリューの畑のブドウを使っています。大部分は銘醸畑として名高いマドローナ・ランチ(Madrona Ranch)のブドウで、一部エコトーン(Ecotone)など、他のエイブリューの畑のブドウも入っています。ティクソン・ヒルと同じセント・ヘレナの西よりであり、距離も3kmほどしか離れていませんが、ティクソン・ヒルが火山性中心の土壌であるのの対し、こちらは沖積性。川底が持ち上がったところで、斜面も一様でなくうねったような形になっています。
56%CS 22%CF 14%M 8%PVという構成。

ティクソン・ヒルと比べるとラズベリーやレッド・チェリーなど赤果実の風味を強く感じます。タンニン強くちょっと閉じている印象がありました。飲み頃まで時間かかりそうと感じましたが、同じワインを別の会(一般向けのディナー)で飲んだ方はカリアドを絶賛しておりましたので、ボトル差があったのかもしれません。
IX Estate 2021(12万5000円)
畑は有機栽培をしています。植樹した部分のほかに100エーカーの森が残っています。これは生物多様性や、野生のままの土地と開墾した土地とのバランス。益鳥を呼び寄せるなどの意味があります。
畑は標高335~427mと高く、霧がかからないので、日較差は小さくなります。西向きの斜面の多いプリチャードヒルの中で東向きの急斜面というのが大きな特徴になります。土壌は火山性の玄武岩が崩れたものが中心。土地を購入したときはここは森であり、一から開墾する必要がありました。岩が多く、20万トンもの岩を取り除いたといいます。大きなものではバスくらいのサイズの岩もあったとか。土地の購入費用よりも、開墾の方がコストがかかったそうです。

開墾中は、この大型のトラクター/ブルドーザーがずっと畑にあり、岩を砕いていました。アン・コルギンとジョー・ウェンダーの結婚式のときに、彼女はウェディング・ドレスでこのトラクターに乗って道を降りて行ったのだそうです。
品種比率は不明ですが、カベルネソーヴィニヨンが70%程度でカベルネ・フランが20%程度、メルローとプティ・ヴェルドが残りくらいが通例です。

四つの2021年のワインの中で、圧倒的に華やかさを持っているのがこのワイン。きれいな赤い果実の風味にシルクのようなタンニン。優美で長い余韻。
以前、アン・コルギンさんが来日したときに、コルギンのワインで何を表現したいと考えているか聞いてみたところ「ピュアでエレガントなワイン」と言っていました。そのイメージに一番合うのはやはりIX Estateだと改めて思いました。
IX Estate 2014(14万円)
蔵出しのオールド・ヴィンテージで2014年のものもいただきました。2014年は干ばつの2年目で、ブドウは小さな実を付け凝縮感があるいいヴィンテージでした。この凝縮感のためか、タンニンはシルキーでギュッと詰まったような印象。また10年を過ぎても華やかさは健在。赤果実に熟成によるマッシュルームや皮の香りも出てきています。もう10年は熟成のピークに向かっていくと思います。
実は2014年と2021年、「O」の字の色が変わっています。2017年から色を微妙に変えたとのこと。
最後のワインはIX Estateのシラー2021です(6万5000円)。
アン・コルギンは北ローヌのコートロティやエルミタージュのシラーが好きで、シャーヴからシラーを譲り受けて植えたと以前聞きました。シラーのブロックは4エーカー。IX Estateの特徴として、タンニンの強さがあるため、100%除梗して造っています。
カベルネ・ソーヴィニヨンと比べると、スミレの花やリコリス、ベイキング・パウダーの甘い香りが特徴的です。ブリーベリーやプラムの香り、タンニンは少しグリップがありストラクチャーを与えています。個人的にはものすごく好きなシラー。
この日は、今年のナパヴァレー・ワイン・ベスト・ソムリエ・アンバサダーに選ばれた山本麻衣花さんがいるマンダリンオリエンタル東京のSignatureというレストランでの食事も付いていました。コルギンのそれぞれのワインとのペアリングを麻衣花さんがシェフと考えて作ったという素晴らしいメニュー。
造るワインのすべてが超高評価というモルレ・ファミリーのワインの正式輸入が始まりました。輸出担当をしているジュリアン・デュカス氏が来日してセミナーを開催しまいた。

まず、モルレのワインがどれくらい高い評価なのか紹介しておきましょう。モルレは様々な評論家からこれまで合計29回もの100点を取っており、中にはレイト・ハーヴェストのデザートワインも含まれています。この中で、ワイン・アドヴォケイトのレイティングで見ると、シャルドネとカベルネ・フラン、ホワイト・ブレンド(セミヨン中心)で最高100点、ピノ・ノワールとカベルネ・ソーヴィニヨンで最高99点、シラーで最高97点。100点が合計で7本となっています。ピノ・ノワールとシャルドネだけ、あるいはカベルネ・ソーヴィニヨンに特化したワイナリーはたくさんありますが、両方でこれだけ高い評価を得ているワイナリーはほとんどありません。
キャラクター的によく似ていて、関連も深く、競合になるのは可能性が高いのがピーター・マイケルです。ピーター・マイケルではワイン・アドヴォケイトの100点は10本あるもののシャルドネとピノ・ノワールの2種類。カベルネ・ソーヴィニヨンは最高99点、セミヨンが98点と、モルレは引けを取りません。
どちらもオールラウンダーのトップ中のトップと言っていいでしょう。
ちなみに、関連が深いというのは、モルレの創設者でワインメーカーでもあるリュック・モルレはピーター・マイケルの4代目ワインメーカーだったのです。2001年にワインメーカーに就任し、2005年まで続けました。2006年にピーター・マイケルを辞めようとしたところ、強く慰留され、結局次のワインメーカーにニコラス・モルレを招聘し、リュックもコンサルタントとして残ることでやっと認めてもらったのでした。現在は6代目のワインメーカーになっていますが、二人合わせると20年近くもの間、ピーター・マイケルのワインを支えてきたのです。リュックは現在もピーター・マイケルでコンサルティングを続けています。ワインにフランス語の名前を付けることなど、ほかにも共通点の多い二つのワイナリーです。
リュックはシャンパーニュのアイ村の近くの出身。シャンパーニュやブルゴーニュ、ボルドーで修行しました。妻のジョディはカリフォルニアのサクラメント出身。二人は1994年にパリで出会い、カリフォルニアにやってきました。そのときの所持金は800ドルしかなかったといいます。カリフォルニアではニュートンなどで働き、その後、前述のようにピーターマイケルのワインメーカーとして活躍し、2006年にモルレ・ファミリーを立ち上げました。ジョディは学校の先生をしていましたが、それをやめてワイナリーのジェネラル・マネジャになりました。
モルレ・ファミリーでは、品質に妥協しないこと、ワインにおける調和のセンス、そして家族経営を三つの柱としています。
モルレはシャルドネとピノ・ノワールについてはフォートロス・シーヴューにある契約畑のブドウを使っています。シラーはベネット・ヴァレー、セミヨンもソノマで調達しており、ソノマのイメージが強いですが、実はワイナリーはナパのセント・ヘレナにあります。また、カベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フランについては以前はナパのベクストファー・ト・カロンなどから調達していましたが、現在は自社畑のみになっています。
最初の自社畑はピーター・マイケルの本拠地でもあるナイツ・ヴァレー。Mon Chevalierという畑です。石と粘土の赤土でミネラル感と強固なタンニンがボルドーを彷彿とさせるようなワインができる畑です。
2008年にはナパのセント・ヘレナに畑とワイナリーを購入しました。マヤカマス山脈側の山すそで、火山性の土壌と沖積性の土壌が混じっている傾斜のある土地です。チャールズ・クリュッグのはす向かいあたりで、ちょうどナパヴァレーの幅が狭くなるあたりの畑です。
最も新しい畑が2015年に取得したオークヴィルの畑。ト・カロン・ヴィンヤードからハイウェイを挟んで向かい合うところ。オーパス・ワンから少し南になります。マヤカマス山脈からの沖積性土壌で砂利が多い土壌です。カベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フランを植えています。10.5ヘクタール。
畑の管理は、12人からなる専門のチームで行っています。サスティナブルかつ有機栽培を実践しており、除草剤などは使用していません。収穫はブドウの鮮度を落とさないために夜間に行い、冷蔵トラックで運びます。白ワイン用のブドウは房単位で選果します。房単位で選果するのは、白ワイン用のブドウを房のままプレスするためです。粒を外してしまうと、酸素に触れる時間がながくなってしまいます。赤ワイン用のブドウは粒単位で、2段階の選果を行います。
白は樽発酵・樽熟成、赤は600リットルのパンチョン(フレンチオーク)を2/3使い、自然に発酵させます。樽についてはこだわりを持っており、フランスのダナジュー社の樽を自身で米国に輸入しているとのこと。清澄・濾過はせずにボトル詰めします。コルクは一つひとつ、ブショネの原因となる「TCA」のチェックをしたものを使っています。
今回はシャルドネ2種、ピノ・ノワール2種、カベルネ・ソーヴィニヨン3種の計7種類のワインを試飲しました。個々のワインの説明と合わせて試飲コメントを紹介していきます。
Ma Douce Chardonnay 2020
ワインの名前の「マ・ドゥ―ス」は「私の愛しい人」という意味で妻ジョディにちなんでいます。ウエスト・ソノマ・コーストの中でも標高の高いところに位置するAVAフォートロス・シーヴューの畑のブドウを使ったシャルドネです。太平洋から近く、冷涼ですが、標高が高いため、霧はほとんどかからず、日照をしっかりと浴びます。シャルドネはウェンテ・クローン。熟成は85%新樽で12カ月。シュールリーでバトナージュもします。100%MLF。
白い花やヘーゼルナッツ。酸高く、柑橘強いですが、時間が経ち、温度が上がるとだんだん、クリームブリュレのような甘い香りが広がってきます。冷涼感と完熟という相反するような個性を併せ持つフォートロス・シーヴューらしさが出たワインです。
Ma Princesse Chardonnay 2021
名称の「マ・プリンセス」は「私のプリンセス」、すなわち娘のクレアのことを指しています。畑はロシアン・リバー・ヴァレーの川岸にあり、オールド・ウェンテ・クローンのシャルドネが植わっています。
フォートロス・シーヴューよりも温かなロシアン・リバー・ヴァレーの畑であり、ワインの色もやや濃く、味わいもより重厚で重層的です。柑橘に白桃柔らかい風味。酸高く、ミネラル感もあります。今回、やや温度を低めで供しているので、これも温度が上がるとクリームブリュレ感が出てきます。冷涼感はマ・ドゥ―スが上回りますが、複雑さはこちらが上に感じました。どちらも素晴らしいですが、個人的にはこちらを高く評価します。
この二つのシャルドネは奥さんと娘にちなんでいるわけですが、娘のワインの方が後から市場に投入されました。そのとき、奥さんのワインよりも価格が高かったので、奥さんの機嫌が悪くなったそうです。その後「Coup de Cœur」というバレル・セレクションのトップキュベを投入したことで、その問題は解消されたとのこと。
さらに余談になりますが、実はピーター・マイケルでも似たような話がありました。息子が結婚したときに、嫁が来たことを喜んで「Ma Belle-Fille(私の美しい娘)」というシャルドネを造ったのですが、実は奥さんにちなんだワインがなかったため、奥さんが機嫌を損ねたのでした。そこで、ピーター・マイケルがピノ・ノワールを始めたときに「Ma Danseuse(私のダンスパートナー)」というワインを造ったのでした。これはピーター・マイケルが奥さんとダンス教室で知り合ったことにちなんでいます。
En Famille Pinot Noir 2019
ワイン名の「アン・ファミーユ」は家族のこと。畑はマ・ドゥ―スと同じです。標高385~400mで南東向き斜面の畑。
赤い果実にちょっとアーシーな風味。しっかり熟していますが酸もあり、複雑な味わい。
Coteaux Nobles Pinot Noir 2020
ワイン名の「コトー・ノーブル」は「高貴な丘陵地帯」の意味。畑はアン・ファミーユと同じですが、標高が少し高く(400~430m)、斜面は南向きではありません。その分、アン・ファミーユよりも冷涼になります。
赤い果実にハーブのニュアンス。アン・ファミーユと比べると、やや線が細くエレガント。個人的にはアン・ファミーユの方が好きですが、エレガント好きならこちらを選ぶと思います。
最後はカベルネ・ソーヴィニヨン3本です。
Les Petits Morlet Cabernet Sauvignon 2019
自社畑の樹齢3~5年の若木のブドウを使ったエントリー向けのワイン。複数の畑をブレンドしており「Napa Valley」のAVA表記となります。85%新樽で16カ月の熟成。
ナパのカベルネ・ソーヴィニヨンとしては珍しいほどの青いニュアンスがあります。タンニンも強く、ボルドー的な印象が強い中、みずみずしい果実の香りがナパらしさを表現しています。
Mon Chevalier Cabernet Sauvignon 2019
前述のように「モン・シュヴァリエ(私の騎士)」はナイツ・ヴァレーの自社畑。ワインの名前は息子のポール・モルレにちなんでいます。ナイツ・ヴァレーは内陸で温暖ですが、標高150~200mほどのところで冷涼な風が届きます。
ブルーベリーにカシス、わずかにレッド・チェリー。コーヒーやシナモン、凝縮感強く複雑で多層的なワインです。
ところで、このワイン、ラベルに剣の絵が描かれています。もちろん「騎士」を模したものですが、左側の剣は実はスターウオーズのライトセーバーになっています。

Morlet Estate Cabernet Sauvignon 2018
最後のワインはナパのセント・ヘレナのカベルネ・ソーヴィニヨンで造ったカベルネ・ソーヴィニヨンです。
カシス、鉛筆の芯、皮革、チョコレート、酸やや高くなめらかなタンニン。凝縮感があり、バランス良く非常においしい。かすかに青さも感じます。モン・
シュヴァリエの方が複雑さがあり、熟成させるならそちらを選びたいですが、今飲むならバランスのよいこちらを選びます。
モルレのワインの輸入元はワインショップでもある勝田商店。フランスとカリフォルニアのハイエンドのワインを売るショップです。ショップでは今回の試飲に含まれていないトップキュベなども売られています。

まず、モルレのワインがどれくらい高い評価なのか紹介しておきましょう。モルレは様々な評論家からこれまで合計29回もの100点を取っており、中にはレイト・ハーヴェストのデザートワインも含まれています。この中で、ワイン・アドヴォケイトのレイティングで見ると、シャルドネとカベルネ・フラン、ホワイト・ブレンド(セミヨン中心)で最高100点、ピノ・ノワールとカベルネ・ソーヴィニヨンで最高99点、シラーで最高97点。100点が合計で7本となっています。ピノ・ノワールとシャルドネだけ、あるいはカベルネ・ソーヴィニヨンに特化したワイナリーはたくさんありますが、両方でこれだけ高い評価を得ているワイナリーはほとんどありません。
キャラクター的によく似ていて、関連も深く、競合になるのは可能性が高いのがピーター・マイケルです。ピーター・マイケルではワイン・アドヴォケイトの100点は10本あるもののシャルドネとピノ・ノワールの2種類。カベルネ・ソーヴィニヨンは最高99点、セミヨンが98点と、モルレは引けを取りません。
どちらもオールラウンダーのトップ中のトップと言っていいでしょう。
ちなみに、関連が深いというのは、モルレの創設者でワインメーカーでもあるリュック・モルレはピーター・マイケルの4代目ワインメーカーだったのです。2001年にワインメーカーに就任し、2005年まで続けました。2006年にピーター・マイケルを辞めようとしたところ、強く慰留され、結局次のワインメーカーにニコラス・モルレを招聘し、リュックもコンサルタントとして残ることでやっと認めてもらったのでした。現在は6代目のワインメーカーになっていますが、二人合わせると20年近くもの間、ピーター・マイケルのワインを支えてきたのです。リュックは現在もピーター・マイケルでコンサルティングを続けています。ワインにフランス語の名前を付けることなど、ほかにも共通点の多い二つのワイナリーです。
リュックはシャンパーニュのアイ村の近くの出身。シャンパーニュやブルゴーニュ、ボルドーで修行しました。妻のジョディはカリフォルニアのサクラメント出身。二人は1994年にパリで出会い、カリフォルニアにやってきました。そのときの所持金は800ドルしかなかったといいます。カリフォルニアではニュートンなどで働き、その後、前述のようにピーターマイケルのワインメーカーとして活躍し、2006年にモルレ・ファミリーを立ち上げました。ジョディは学校の先生をしていましたが、それをやめてワイナリーのジェネラル・マネジャになりました。
モルレ・ファミリーでは、品質に妥協しないこと、ワインにおける調和のセンス、そして家族経営を三つの柱としています。
モルレはシャルドネとピノ・ノワールについてはフォートロス・シーヴューにある契約畑のブドウを使っています。シラーはベネット・ヴァレー、セミヨンもソノマで調達しており、ソノマのイメージが強いですが、実はワイナリーはナパのセント・ヘレナにあります。また、カベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フランについては以前はナパのベクストファー・ト・カロンなどから調達していましたが、現在は自社畑のみになっています。
最初の自社畑はピーター・マイケルの本拠地でもあるナイツ・ヴァレー。Mon Chevalierという畑です。石と粘土の赤土でミネラル感と強固なタンニンがボルドーを彷彿とさせるようなワインができる畑です。
2008年にはナパのセント・ヘレナに畑とワイナリーを購入しました。マヤカマス山脈側の山すそで、火山性の土壌と沖積性の土壌が混じっている傾斜のある土地です。チャールズ・クリュッグのはす向かいあたりで、ちょうどナパヴァレーの幅が狭くなるあたりの畑です。
最も新しい畑が2015年に取得したオークヴィルの畑。ト・カロン・ヴィンヤードからハイウェイを挟んで向かい合うところ。オーパス・ワンから少し南になります。マヤカマス山脈からの沖積性土壌で砂利が多い土壌です。カベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フランを植えています。10.5ヘクタール。
畑の管理は、12人からなる専門のチームで行っています。サスティナブルかつ有機栽培を実践しており、除草剤などは使用していません。収穫はブドウの鮮度を落とさないために夜間に行い、冷蔵トラックで運びます。白ワイン用のブドウは房単位で選果します。房単位で選果するのは、白ワイン用のブドウを房のままプレスするためです。粒を外してしまうと、酸素に触れる時間がながくなってしまいます。赤ワイン用のブドウは粒単位で、2段階の選果を行います。
白は樽発酵・樽熟成、赤は600リットルのパンチョン(フレンチオーク)を2/3使い、自然に発酵させます。樽についてはこだわりを持っており、フランスのダナジュー社の樽を自身で米国に輸入しているとのこと。清澄・濾過はせずにボトル詰めします。コルクは一つひとつ、ブショネの原因となる「TCA」のチェックをしたものを使っています。
今回はシャルドネ2種、ピノ・ノワール2種、カベルネ・ソーヴィニヨン3種の計7種類のワインを試飲しました。個々のワインの説明と合わせて試飲コメントを紹介していきます。
Ma Douce Chardonnay 2020
ワインの名前の「マ・ドゥ―ス」は「私の愛しい人」という意味で妻ジョディにちなんでいます。ウエスト・ソノマ・コーストの中でも標高の高いところに位置するAVAフォートロス・シーヴューの畑のブドウを使ったシャルドネです。太平洋から近く、冷涼ですが、標高が高いため、霧はほとんどかからず、日照をしっかりと浴びます。シャルドネはウェンテ・クローン。熟成は85%新樽で12カ月。シュールリーでバトナージュもします。100%MLF。
白い花やヘーゼルナッツ。酸高く、柑橘強いですが、時間が経ち、温度が上がるとだんだん、クリームブリュレのような甘い香りが広がってきます。冷涼感と完熟という相反するような個性を併せ持つフォートロス・シーヴューらしさが出たワインです。
Ma Princesse Chardonnay 2021
名称の「マ・プリンセス」は「私のプリンセス」、すなわち娘のクレアのことを指しています。畑はロシアン・リバー・ヴァレーの川岸にあり、オールド・ウェンテ・クローンのシャルドネが植わっています。
フォートロス・シーヴューよりも温かなロシアン・リバー・ヴァレーの畑であり、ワインの色もやや濃く、味わいもより重厚で重層的です。柑橘に白桃柔らかい風味。酸高く、ミネラル感もあります。今回、やや温度を低めで供しているので、これも温度が上がるとクリームブリュレ感が出てきます。冷涼感はマ・ドゥ―スが上回りますが、複雑さはこちらが上に感じました。どちらも素晴らしいですが、個人的にはこちらを高く評価します。
この二つのシャルドネは奥さんと娘にちなんでいるわけですが、娘のワインの方が後から市場に投入されました。そのとき、奥さんのワインよりも価格が高かったので、奥さんの機嫌が悪くなったそうです。その後「Coup de Cœur」というバレル・セレクションのトップキュベを投入したことで、その問題は解消されたとのこと。
さらに余談になりますが、実はピーター・マイケルでも似たような話がありました。息子が結婚したときに、嫁が来たことを喜んで「Ma Belle-Fille(私の美しい娘)」というシャルドネを造ったのですが、実は奥さんにちなんだワインがなかったため、奥さんが機嫌を損ねたのでした。そこで、ピーター・マイケルがピノ・ノワールを始めたときに「Ma Danseuse(私のダンスパートナー)」というワインを造ったのでした。これはピーター・マイケルが奥さんとダンス教室で知り合ったことにちなんでいます。
En Famille Pinot Noir 2019
ワイン名の「アン・ファミーユ」は家族のこと。畑はマ・ドゥ―スと同じです。標高385~400mで南東向き斜面の畑。
赤い果実にちょっとアーシーな風味。しっかり熟していますが酸もあり、複雑な味わい。
Coteaux Nobles Pinot Noir 2020
ワイン名の「コトー・ノーブル」は「高貴な丘陵地帯」の意味。畑はアン・ファミーユと同じですが、標高が少し高く(400~430m)、斜面は南向きではありません。その分、アン・ファミーユよりも冷涼になります。
赤い果実にハーブのニュアンス。アン・ファミーユと比べると、やや線が細くエレガント。個人的にはアン・ファミーユの方が好きですが、エレガント好きならこちらを選ぶと思います。
最後はカベルネ・ソーヴィニヨン3本です。
Les Petits Morlet Cabernet Sauvignon 2019
自社畑の樹齢3~5年の若木のブドウを使ったエントリー向けのワイン。複数の畑をブレンドしており「Napa Valley」のAVA表記となります。85%新樽で16カ月の熟成。
ナパのカベルネ・ソーヴィニヨンとしては珍しいほどの青いニュアンスがあります。タンニンも強く、ボルドー的な印象が強い中、みずみずしい果実の香りがナパらしさを表現しています。
Mon Chevalier Cabernet Sauvignon 2019
前述のように「モン・シュヴァリエ(私の騎士)」はナイツ・ヴァレーの自社畑。ワインの名前は息子のポール・モルレにちなんでいます。ナイツ・ヴァレーは内陸で温暖ですが、標高150~200mほどのところで冷涼な風が届きます。
ブルーベリーにカシス、わずかにレッド・チェリー。コーヒーやシナモン、凝縮感強く複雑で多層的なワインです。
ところで、このワイン、ラベルに剣の絵が描かれています。もちろん「騎士」を模したものですが、左側の剣は実はスターウオーズのライトセーバーになっています。

Morlet Estate Cabernet Sauvignon 2018
最後のワインはナパのセント・ヘレナのカベルネ・ソーヴィニヨンで造ったカベルネ・ソーヴィニヨンです。
カシス、鉛筆の芯、皮革、チョコレート、酸やや高くなめらかなタンニン。凝縮感があり、バランス良く非常においしい。かすかに青さも感じます。モン・
シュヴァリエの方が複雑さがあり、熟成させるならそちらを選びたいですが、今飲むならバランスのよいこちらを選びます。
モルレのワインの輸入元はワインショップでもある勝田商店。フランスとカリフォルニアのハイエンドのワインを売るショップです。ショップでは今回の試飲に含まれていないトップキュベなども売られています。
カリフォルニアのローダイの生産者団体が、欧州ワインに対して関税が必要だとする記事を公開しています(WHY MANY CALIFORNIA WINEGROWERS ARE CALLING FOR TARIFFS ON IMPORTS)。
それと関連する、2024年に公開された記事(WINE DUTY DRAWBACK – ANOTHER DIRTY SECRET!)の内容を含めて紹介します。
ローダイなどカリフォルニアのセントラルヴァレーは、ワインの需要減少の直撃を受けています。過去2年間でカリフォルニア全体で60万~80万トンのブドウが収穫されないままになってしまいました。その大半がセントラルヴァレーです。カリフォルニアのワイン用ブドウ栽培農家の8割は独立系(特定の生産者との契約に依存しないこと)であり、セントラルヴァレーでは9割に達します。
ガロやブロンコなど、安価なワインを大量に作る生産者がこれらの農家にとってのバイヤーになるわけですが、近年は海外、特に欧州から安くワインを輸入するケースが多くなっています。この構造を変えるには関税が必要だというのが上記記事の骨子になります。
では、それら大手のワイナリーはなぜ欧州から安いバルクワインを調達するのかというと、そこには2つの理由があります。
その一つが、冒頭に挙げた2つ目の記事に書かれた関税と酒税をキックバックする制度です。これは欧州側ではなく米国側の制度による問題です。
米国の生産者は、海外にワインを輸出し、並行して海外からワインを輸入したとき、輸入したワインに支払われた関税と酒税分のキックバックを得られます。例えばあるワイナリーがオーストラリア産シャルドネを100万ガロン輸入し、カリフォルニア産白ワインを100万ガロン輸出した場合、輸入シャルドネに支払われた関税と物品税(酒税)の最大99%をキックバックされます。これによって輸入ワインを税金ゼロとして販売できるため、相対的にカリフォルニアワインの競争力はなくなり、栽培農家からの購入が減るわけです。そういえばフランジアなど、昔はカリフォルニアだけだったのが、今は他国のワインを使ったものが増えています。そこにはこういう理由があったわけですね。

この制度ができたのは2003年で、それ以降バルクワインの輸入が急増しているのが分かります。過去5年を見ても13億本のワインが輸入されています。

各社はいくらのキックバックを得ているのか公開していませんが、輸入量と輸出量を勘案すると、大手7社で2016年から2022年に1億7400万ドルのキックバックを得た計算になります。米国全体で実際にキックバックした額は2憶4000万ドル程度であり、この制度の恩恵を受ける大半は大手ワイナリーであることがわかります。
実は、カリフォルニアワイン協会もこの制度に対しては反対を唱えていません。ワインの輸出を促進するというのがその理由ですが、実際には輸出よりも輸入を促進しているというのがローダイの主張です。
もう一つの理由は欧州側にあります。多額の補助金によって、ワイナリーや栽培農家が恩恵を受けているということです。EUによるワイン産業の支援は年間10億ユーロ(11億3000万米ドル)以上、加盟国や地方自治体がプラスする額を含めると年間推定20億ユーロ(22億6000万米ドル)に達します。
これらの補助金は大きく分けると3つの形で使われます。一つがブドウの買い取り。余ったブドウを買い取って工業用アルコールの製造に使います。この買い取りがあるため、栽培農家にとっては栽培を減らすモチベーションがありません。
二つ目はブドウの引き抜き。フランス政府は1億2000万ユーロを拠出し、生産者に1ヘクタールあたり4000ユーロを支払い、約3万ヘクタールのブドウ畑(国のブドウ畑面積の約3.4%に相当)を撤去させました。これは長期的な生産調整を目的としていますが、2029年には植え替え禁止期間を過ぎるので、一時的な対策に終わる可能性もあります。
三つ目はブドウ畑の植樹への支援。EUは新規ブドウ畑の植樹支援に年間5億ユーロ以上を支出しています。地域によって異なりますが、ブドウ畑の開発費用の50%から75%が補助されます。これは、より生産性の高い畑への移行を促しているという面がありますが、その結果として、ブドウ畑の面積は減って行っていても、ブドウの生産量自体はほとんど変化しないということになっています。この制度は2045年まで続くことになっています。
結局、買い取りがあるため、農家にとっては生産量を減らすモチベーションは少なく、補助金などによって畑は減っても生産量は変わらないという図式が今後も続くことになります。

これ以外に、EUはマーケティング的にも支援を行っています。
例えば、ワイン・スペクテイターの4月30日号には、EUとイタリア政府の資金援助による全面広告が15件、部分ページ広告が3件掲載されています。この広告料は50万ドル以上になります。対照的に、米国のワイナリーによる全面広告は1件のみでした。この号ではイタリアワインが広範囲に取り上げられています。
このように欧州ワインは様々な恩恵をEUや各国政府から得ており、さらに前述のように大手ワイナリーが輸入するワインでは税金も実質的に免除になっています。このような構図を突き崩さないことにはカリフォルニアのセントラルヴァレーの栽培農家にとっては、非常に厳しい状況が続くことになります。輸入ワインに関税が必要だと、ローダイの団体が主張するのはそのためです。
この構図自体は今始まったわけではありませんが、2020年頃までは米国内の需要が伸びていたので、大きな問題になっていなかったのでしょう。ただ、関税を上げたとしても、その分がまたキックバックされてしまうのであれば意味がないので、本当に米国内のブドウ栽培農家を守りたいのであれば、まずは自国のキックバックの制度を何とかするのが先決ではないかという気もします。
こういった低価格ワイン周りの情報は日本に来る生産者(ほとんどがプレミアム)からは聞けない話なので、勉強になりましたし、考えさせられるものでした。
それと関連する、2024年に公開された記事(WINE DUTY DRAWBACK – ANOTHER DIRTY SECRET!)の内容を含めて紹介します。
ローダイなどカリフォルニアのセントラルヴァレーは、ワインの需要減少の直撃を受けています。過去2年間でカリフォルニア全体で60万~80万トンのブドウが収穫されないままになってしまいました。その大半がセントラルヴァレーです。カリフォルニアのワイン用ブドウ栽培農家の8割は独立系(特定の生産者との契約に依存しないこと)であり、セントラルヴァレーでは9割に達します。
ガロやブロンコなど、安価なワインを大量に作る生産者がこれらの農家にとってのバイヤーになるわけですが、近年は海外、特に欧州から安くワインを輸入するケースが多くなっています。この構造を変えるには関税が必要だというのが上記記事の骨子になります。
では、それら大手のワイナリーはなぜ欧州から安いバルクワインを調達するのかというと、そこには2つの理由があります。
その一つが、冒頭に挙げた2つ目の記事に書かれた関税と酒税をキックバックする制度です。これは欧州側ではなく米国側の制度による問題です。
米国の生産者は、海外にワインを輸出し、並行して海外からワインを輸入したとき、輸入したワインに支払われた関税と酒税分のキックバックを得られます。例えばあるワイナリーがオーストラリア産シャルドネを100万ガロン輸入し、カリフォルニア産白ワインを100万ガロン輸出した場合、輸入シャルドネに支払われた関税と物品税(酒税)の最大99%をキックバックされます。これによって輸入ワインを税金ゼロとして販売できるため、相対的にカリフォルニアワインの競争力はなくなり、栽培農家からの購入が減るわけです。そういえばフランジアなど、昔はカリフォルニアだけだったのが、今は他国のワインを使ったものが増えています。そこにはこういう理由があったわけですね。

この制度ができたのは2003年で、それ以降バルクワインの輸入が急増しているのが分かります。過去5年を見ても13億本のワインが輸入されています。

各社はいくらのキックバックを得ているのか公開していませんが、輸入量と輸出量を勘案すると、大手7社で2016年から2022年に1億7400万ドルのキックバックを得た計算になります。米国全体で実際にキックバックした額は2憶4000万ドル程度であり、この制度の恩恵を受ける大半は大手ワイナリーであることがわかります。
実は、カリフォルニアワイン協会もこの制度に対しては反対を唱えていません。ワインの輸出を促進するというのがその理由ですが、実際には輸出よりも輸入を促進しているというのがローダイの主張です。
もう一つの理由は欧州側にあります。多額の補助金によって、ワイナリーや栽培農家が恩恵を受けているということです。EUによるワイン産業の支援は年間10億ユーロ(11億3000万米ドル)以上、加盟国や地方自治体がプラスする額を含めると年間推定20億ユーロ(22億6000万米ドル)に達します。
これらの補助金は大きく分けると3つの形で使われます。一つがブドウの買い取り。余ったブドウを買い取って工業用アルコールの製造に使います。この買い取りがあるため、栽培農家にとっては栽培を減らすモチベーションがありません。
二つ目はブドウの引き抜き。フランス政府は1億2000万ユーロを拠出し、生産者に1ヘクタールあたり4000ユーロを支払い、約3万ヘクタールのブドウ畑(国のブドウ畑面積の約3.4%に相当)を撤去させました。これは長期的な生産調整を目的としていますが、2029年には植え替え禁止期間を過ぎるので、一時的な対策に終わる可能性もあります。
三つ目はブドウ畑の植樹への支援。EUは新規ブドウ畑の植樹支援に年間5億ユーロ以上を支出しています。地域によって異なりますが、ブドウ畑の開発費用の50%から75%が補助されます。これは、より生産性の高い畑への移行を促しているという面がありますが、その結果として、ブドウ畑の面積は減って行っていても、ブドウの生産量自体はほとんど変化しないということになっています。この制度は2045年まで続くことになっています。
結局、買い取りがあるため、農家にとっては生産量を減らすモチベーションは少なく、補助金などによって畑は減っても生産量は変わらないという図式が今後も続くことになります。

これ以外に、EUはマーケティング的にも支援を行っています。
例えば、ワイン・スペクテイターの4月30日号には、EUとイタリア政府の資金援助による全面広告が15件、部分ページ広告が3件掲載されています。この広告料は50万ドル以上になります。対照的に、米国のワイナリーによる全面広告は1件のみでした。この号ではイタリアワインが広範囲に取り上げられています。
このように欧州ワインは様々な恩恵をEUや各国政府から得ており、さらに前述のように大手ワイナリーが輸入するワインでは税金も実質的に免除になっています。このような構図を突き崩さないことにはカリフォルニアのセントラルヴァレーの栽培農家にとっては、非常に厳しい状況が続くことになります。輸入ワインに関税が必要だと、ローダイの団体が主張するのはそのためです。
この構図自体は今始まったわけではありませんが、2020年頃までは米国内の需要が伸びていたので、大きな問題になっていなかったのでしょう。ただ、関税を上げたとしても、その分がまたキックバックされてしまうのであれば意味がないので、本当に米国内のブドウ栽培農家を守りたいのであれば、まずは自国のキックバックの制度を何とかするのが先決ではないかという気もします。
こういった低価格ワイン周りの情報は日本に来る生産者(ほとんどがプレミアム)からは聞けない話なので、勉強になりましたし、考えさせられるものでした。
リッジ・ヴィンヤーズ(Ridge Vineyards)のヘッド・ワインメーカー兼COOであるジョン・オルニー氏が初来日し、セミナーに参加してきました。

オルニー氏のおじにリチャード・オルニーという人がおり『ロマネ・コンティ:神話になったワインの物語』(原題Romanee-Conti)という書籍を書いたワインと食事のライターをしていました。欧米ではかなり知名度の高い人だったそうです。その影響で、ジョン・オルニー氏もフランスでワインの勉強をし、ドメーヌ・タンピエ、シャーブ、マルセル・ラピエール、ドメーヌ・ド・ヴィレーヌといったワイナリーで修行しました。その後、バークレーにあるカーミット・リンチ(米国の伝説的なインポーター)のショップで働いていました。同じバークレーの著名レストラン「シェ・パニーズ」のアリス・ウォーターズとカーミット・リンチの推薦で1996年にリッジに入りました。
リッジはサンタ・クルーズ・マウンテンズのモンテベロとソノマのリットンスプリングスの2カ所にワイナリーを持っていますが、当初はモンテベロで働き、1999年からリットンスプリングスのワイナリーの改築に携わり、リットンスプリングスのワインメーカーとなりました。リットンスプリングスのワイナリーは藁と漆喰を使った省エネがユニークです(「名門ワイナリー2軒のサスティナブルへの取り組み」で紹介しています)。その後、2021年から現職に就いています。通訳の立花峰夫さんによると「欧州的な考え方をする人」だそうです
リッジは1959年に4人のスタンフォード大学工学部の卒業生が、自然に触れるために共同で土地を購入したことで始まりました。それ以前からカベルネ・ソーヴィニヨンのブドウ畑は存在しており、前オーナーが売却条件として畑の世話をすることを入れていたのだといいます。
そこでワインを半樽だけ仕込んでみました。とはいえ週末の別荘的に使っていただけなので、収穫してタンクに入れて放っておいただけだったのですが、自然に発酵してしかも、その味がすごく良かったのだそうです。ワインには複雑さもあり、それをこの場所にユニークなものとして受け取って62年にワイナリーを設立しました。
それ以来、単一畑にこだわってワインを造ることにしており、大本のサンタ・クルーズ・マウンテンズの畑モンテベロのほかにもカリフォルニア中を探し回って比類なき個性を持った畑を見つけてワインを造っていきました。その中でカリフォルニアの伝統的な品種であるジンファンデルも柱の一つとなっていきます。
リッジのワイン造りの基礎を築いたのが1969円から40年間ワインメーカーを務めたポール・ドレーパーです。欧州の有名な生産者のワイン造りを対話から学んできた人で、当時のカリフォルニアの大学で教えている現代的なアプローチに対して、プレインダストリー(前工業的)ワインメイキングと呼ぶようになりました。
これは「信念に基づく」ワインメイキングで、2011年からは、ワインの醸造時に入れた内容物をすべて表示することを自発的に始めています。
リッジのワイン造りでもう一つ重要なのがサスティナブル。前述のようにリットンスプリングスのワイナリーは藁と漆喰で造られています。藁は米を収穫した後の使い道のないものを調達しています。断熱性高く、夜の間に冷たい空気をため込んで昼は空気の出入りをなくすことでエアコンなしで温度を低く保てるようになりました。太陽光発電も取り入れ、ワイナリーで使う電力の2/3を賄っています。2021年にはIWCA(International Wineries for Climate Action)に加盟しており2年に1回、監査を受けいます。
畑では2000年前半から自社畑の有機栽培認証獲得始めており、今は自社畑のすべてが有機栽培認証を得ています。再生型農業も取り入れています。土壌の健康と大気中の二酸化炭素の土壌への固定が目的です。このほか有益昆虫の迎え入れや、有害な昆虫や齧歯動物のコントロールに鳥を使うといったこともしています。有益昆虫の例としては狩り蜂があり、コナカイガラムシの体に卵を産み付けて、殺してしまいます。
このほか、2022年からはボトルの重さを570gから465gへと18%削減しました。CO2排出に一番影響があるのがガラス瓶です。一般的には350gから1.2㎏なので、かなり軽いボトルになります。また、木箱の利用をやめ、トウモロコシを原料とした軽いボール紙の箱にしました。リサイクル可能で生分解可能だといいます。
今回は、リッジの代表的なワインであるジンファンデル・ベースのリットンスプリングス(Lytton Springs)とガイザーヴィル(Geyserville)、そしてモンテベロ(Monte Bello)のカベルネ・ソーヴィニヨンについて最新ヴィンテージと熟成したものを試飲しました。

ガイザーヴィルはソノマのアレキサンダー・ヴァレーにあり、1882年に植樹が始まりました。ジンファンデル以外ではカリニャンが多く、カリニャンの古いブロックは1891年に植樹されています。樹齢130年や140年を超える古い畑です。土壌は石が多く、砂地もあります。カリニャンは暑さに強く、やや低い糖度で成熟するので酸味を与えてくれます。リッジでは1966年からガイザーヴィルのワインを造っています。
2021 Geyserville
ザクロやブラックベリー、ローストしたナッツに、杉や腐葉土。ややざらっとしたタンニンがあり田舎っぽさを与えている。酸高く、アルコール度数も高いがそれを感じさせない。時間がたつとだんだん甘やかさがでてくる。
1999 Geyserville
マッシュルームに腐葉土といった熟成香が先に立ち、それからザクロやレッド・チェリーといった赤い果実の風味がやってくる。青系や黒系の果実はあまり感じない。酸やや高く、タンニンも比較的しっかりしている。甘やかで複雑。非常に美味しい。
あまり熟成には向かないと言われているジンファンデルで四半世紀を過ぎてこれだけきれいに熟成しているのには少し驚かされました。なお、今回のボトルは全部マグナムで、それも影響している可能性があります。
(余談ですが、かつてロバート・パーカーが「ジンファンデルは熟成しない」といって、それに対してポール・ドレイパーが反論したということがありました。結局、パーカーもリッジのジンファンデルについては熟成することを認めざるを得なくなったのですが、今回のワインを飲んでそのエピソードを思い出しました)

一方、リットン・スプリングスはガイザーヴィルから2.5kmほどしか離れていませんが、土壌は粘土質でやや重くなっています。ここはジンファンデル以外ではプティ・シラーが多くなっています。ワインは濃く、力強い風味があります。リッジでは1972年からここのワインを造っています。
2021 Lytton Springs
インクの香りや鉛筆の芯、黒い果実。しなやかなタンニンで、ガイザーヴィルよりも洗練されている。ストラクチャー強く、やや硬さがあり、もう数年熟成させたい。
1999 Lytton Springs
腐葉土やマッシュルームに黒果実。酸やや高く、タンニンもしっかりしている。十分に美味しいが、さらに熟成が可能だと思われる。
ガイザーヴィルもリットン・スプリングスもフィールドブレンドといって、畑に複数の品種が植えられていますが、前述のようにガイザーヴィルはカリニャンが多く、リットン・スプリングスはプティ・シラーが多く植わっています。これは偶然なのか意図的なのかが気になるところです。
フィールドブレンドの品種の選択について、文献などが残っているわけではなく、想像するしかないのですが、リットンのやや重い土壌ではカリニャンはあまりうまく育たないそうです。逆に、水はけよく温暖なアレキサンダー・ヴァレーの河岸段丘にあるガイザーヴィルでは、暑さに強く、酸を保持するカリニャンが向いています。また、付近の古い畑を調べてみると、同じアレキサンダー・ヴァレーでも、より温暖なところにカリニャンが多く植わっている傾向があるそうです。そういったことから、土壌や気候の向き不向きで品種を選択した可能性が高いのではとのことです。特に19世紀末にフィロキセラによって植え替えをよぎなくされたことで、より適性の高い品種に植え替えていった可能性が高いようです。
最後はフラッグシップであり、リッジの本拠地であるモンテベロです。カリフォルニアのカベルネ・ソーヴィニヨンの中でも、非常にユニークなワインです。標高600~800メートルと高いことが一つ。太平洋から32kmほどの距離で、冷涼感があること、痩せた石灰岩の土壌であること。
標高や太平洋の影響による冷涼さによって、モンテベロでは多すぎるくらいのタンニンをどう扱うかが醸造上の課題になってきます。モンテベロの畑には55の区画があり、別々に収穫して、発酵します。翌年1月くらいにブレンドのための試飲をし、一番強く深みがあり熟成しそうなものをモンテベロに入れます。より早く飲めるワインはエステートのカベルネに入れます。
熟成可能なワインを造るのに最も重要なのはバランスだそうです。色やタンニン、果実味、酸味、これらのバランスがよくてエレガントなものが一番長く熟成します。一般にはワインが大柄で濃く、タンニンがあれば長期間熟成すると考えがちですが、そうではないとのこと。
2021 Monte Bello
上品でエレガント。赤い果実、杉、タンニン強く今飲んでも美味しいが10年くらいはセラーリングしたい。
1997 Monte Bello
むちゃくちゃうまい、エレガント、赤果実、きれいなタンニン。熟成したカベルネでここまで美味しいものはめったに出会いません。
改めて、リッジのワインの熟成力の素晴らしさを体感できたセミナーでした。

左は大塚食品の黒川さん
オルニー氏のおじにリチャード・オルニーという人がおり『ロマネ・コンティ:神話になったワインの物語』(原題Romanee-Conti)という書籍を書いたワインと食事のライターをしていました。欧米ではかなり知名度の高い人だったそうです。その影響で、ジョン・オルニー氏もフランスでワインの勉強をし、ドメーヌ・タンピエ、シャーブ、マルセル・ラピエール、ドメーヌ・ド・ヴィレーヌといったワイナリーで修行しました。その後、バークレーにあるカーミット・リンチ(米国の伝説的なインポーター)のショップで働いていました。同じバークレーの著名レストラン「シェ・パニーズ」のアリス・ウォーターズとカーミット・リンチの推薦で1996年にリッジに入りました。
リッジはサンタ・クルーズ・マウンテンズのモンテベロとソノマのリットンスプリングスの2カ所にワイナリーを持っていますが、当初はモンテベロで働き、1999年からリットンスプリングスのワイナリーの改築に携わり、リットンスプリングスのワインメーカーとなりました。リットンスプリングスのワイナリーは藁と漆喰を使った省エネがユニークです(「名門ワイナリー2軒のサスティナブルへの取り組み」で紹介しています)。その後、2021年から現職に就いています。通訳の立花峰夫さんによると「欧州的な考え方をする人」だそうです
リッジは1959年に4人のスタンフォード大学工学部の卒業生が、自然に触れるために共同で土地を購入したことで始まりました。それ以前からカベルネ・ソーヴィニヨンのブドウ畑は存在しており、前オーナーが売却条件として畑の世話をすることを入れていたのだといいます。
そこでワインを半樽だけ仕込んでみました。とはいえ週末の別荘的に使っていただけなので、収穫してタンクに入れて放っておいただけだったのですが、自然に発酵してしかも、その味がすごく良かったのだそうです。ワインには複雑さもあり、それをこの場所にユニークなものとして受け取って62年にワイナリーを設立しました。
それ以来、単一畑にこだわってワインを造ることにしており、大本のサンタ・クルーズ・マウンテンズの畑モンテベロのほかにもカリフォルニア中を探し回って比類なき個性を持った畑を見つけてワインを造っていきました。その中でカリフォルニアの伝統的な品種であるジンファンデルも柱の一つとなっていきます。
リッジのワイン造りの基礎を築いたのが1969円から40年間ワインメーカーを務めたポール・ドレーパーです。欧州の有名な生産者のワイン造りを対話から学んできた人で、当時のカリフォルニアの大学で教えている現代的なアプローチに対して、プレインダストリー(前工業的)ワインメイキングと呼ぶようになりました。
これは「信念に基づく」ワインメイキングで、2011年からは、ワインの醸造時に入れた内容物をすべて表示することを自発的に始めています。
リッジのワイン造りでもう一つ重要なのがサスティナブル。前述のようにリットンスプリングスのワイナリーは藁と漆喰で造られています。藁は米を収穫した後の使い道のないものを調達しています。断熱性高く、夜の間に冷たい空気をため込んで昼は空気の出入りをなくすことでエアコンなしで温度を低く保てるようになりました。太陽光発電も取り入れ、ワイナリーで使う電力の2/3を賄っています。2021年にはIWCA(International Wineries for Climate Action)に加盟しており2年に1回、監査を受けいます。
畑では2000年前半から自社畑の有機栽培認証獲得始めており、今は自社畑のすべてが有機栽培認証を得ています。再生型農業も取り入れています。土壌の健康と大気中の二酸化炭素の土壌への固定が目的です。このほか有益昆虫の迎え入れや、有害な昆虫や齧歯動物のコントロールに鳥を使うといったこともしています。有益昆虫の例としては狩り蜂があり、コナカイガラムシの体に卵を産み付けて、殺してしまいます。
このほか、2022年からはボトルの重さを570gから465gへと18%削減しました。CO2排出に一番影響があるのがガラス瓶です。一般的には350gから1.2㎏なので、かなり軽いボトルになります。また、木箱の利用をやめ、トウモロコシを原料とした軽いボール紙の箱にしました。リサイクル可能で生分解可能だといいます。
今回は、リッジの代表的なワインであるジンファンデル・ベースのリットンスプリングス(Lytton Springs)とガイザーヴィル(Geyserville)、そしてモンテベロ(Monte Bello)のカベルネ・ソーヴィニヨンについて最新ヴィンテージと熟成したものを試飲しました。
ガイザーヴィルはソノマのアレキサンダー・ヴァレーにあり、1882年に植樹が始まりました。ジンファンデル以外ではカリニャンが多く、カリニャンの古いブロックは1891年に植樹されています。樹齢130年や140年を超える古い畑です。土壌は石が多く、砂地もあります。カリニャンは暑さに強く、やや低い糖度で成熟するので酸味を与えてくれます。リッジでは1966年からガイザーヴィルのワインを造っています。
2021 Geyserville
ザクロやブラックベリー、ローストしたナッツに、杉や腐葉土。ややざらっとしたタンニンがあり田舎っぽさを与えている。酸高く、アルコール度数も高いがそれを感じさせない。時間がたつとだんだん甘やかさがでてくる。
1999 Geyserville
マッシュルームに腐葉土といった熟成香が先に立ち、それからザクロやレッド・チェリーといった赤い果実の風味がやってくる。青系や黒系の果実はあまり感じない。酸やや高く、タンニンも比較的しっかりしている。甘やかで複雑。非常に美味しい。
あまり熟成には向かないと言われているジンファンデルで四半世紀を過ぎてこれだけきれいに熟成しているのには少し驚かされました。なお、今回のボトルは全部マグナムで、それも影響している可能性があります。
(余談ですが、かつてロバート・パーカーが「ジンファンデルは熟成しない」といって、それに対してポール・ドレイパーが反論したということがありました。結局、パーカーもリッジのジンファンデルについては熟成することを認めざるを得なくなったのですが、今回のワインを飲んでそのエピソードを思い出しました)

一方、リットン・スプリングスはガイザーヴィルから2.5kmほどしか離れていませんが、土壌は粘土質でやや重くなっています。ここはジンファンデル以外ではプティ・シラーが多くなっています。ワインは濃く、力強い風味があります。リッジでは1972年からここのワインを造っています。
2021 Lytton Springs
インクの香りや鉛筆の芯、黒い果実。しなやかなタンニンで、ガイザーヴィルよりも洗練されている。ストラクチャー強く、やや硬さがあり、もう数年熟成させたい。
1999 Lytton Springs
腐葉土やマッシュルームに黒果実。酸やや高く、タンニンもしっかりしている。十分に美味しいが、さらに熟成が可能だと思われる。
ガイザーヴィルもリットン・スプリングスもフィールドブレンドといって、畑に複数の品種が植えられていますが、前述のようにガイザーヴィルはカリニャンが多く、リットン・スプリングスはプティ・シラーが多く植わっています。これは偶然なのか意図的なのかが気になるところです。
フィールドブレンドの品種の選択について、文献などが残っているわけではなく、想像するしかないのですが、リットンのやや重い土壌ではカリニャンはあまりうまく育たないそうです。逆に、水はけよく温暖なアレキサンダー・ヴァレーの河岸段丘にあるガイザーヴィルでは、暑さに強く、酸を保持するカリニャンが向いています。また、付近の古い畑を調べてみると、同じアレキサンダー・ヴァレーでも、より温暖なところにカリニャンが多く植わっている傾向があるそうです。そういったことから、土壌や気候の向き不向きで品種を選択した可能性が高いのではとのことです。特に19世紀末にフィロキセラによって植え替えをよぎなくされたことで、より適性の高い品種に植え替えていった可能性が高いようです。
最後はフラッグシップであり、リッジの本拠地であるモンテベロです。カリフォルニアのカベルネ・ソーヴィニヨンの中でも、非常にユニークなワインです。標高600~800メートルと高いことが一つ。太平洋から32kmほどの距離で、冷涼感があること、痩せた石灰岩の土壌であること。
標高や太平洋の影響による冷涼さによって、モンテベロでは多すぎるくらいのタンニンをどう扱うかが醸造上の課題になってきます。モンテベロの畑には55の区画があり、別々に収穫して、発酵します。翌年1月くらいにブレンドのための試飲をし、一番強く深みがあり熟成しそうなものをモンテベロに入れます。より早く飲めるワインはエステートのカベルネに入れます。
熟成可能なワインを造るのに最も重要なのはバランスだそうです。色やタンニン、果実味、酸味、これらのバランスがよくてエレガントなものが一番長く熟成します。一般にはワインが大柄で濃く、タンニンがあれば長期間熟成すると考えがちですが、そうではないとのこと。
2021 Monte Bello
上品でエレガント。赤い果実、杉、タンニン強く今飲んでも美味しいが10年くらいはセラーリングしたい。
1997 Monte Bello
むちゃくちゃうまい、エレガント、赤果実、きれいなタンニン。熟成したカベルネでここまで美味しいものはめったに出会いません。
改めて、リッジのワインの熟成力の素晴らしさを体感できたセミナーでした。
左は大塚食品の黒川さん
サンタ・バーバラで数々の銘醸畑からすばらしいピノ・ノワールやシャルドネ(シラーも)を造るポール・ラトー(Paul Lato、ポール・ラトとも)。造るワインはどれもその畑のワインとしてトップクラスの評価を得ているほどの達人です。そのラトー氏がプライベートで初来日。開かれたワイン会に同席させていただきました。


Paul Lato Chardonnay 'Matinee' Santa Barbara 2020
最初のワインはシャルドネのマティネ(Matinee)です。マティネはフランス語で朝という意味です。このワインは元々レストラン用に作り始めたもので、市販は意図していませんでした。マティネにはまた映画や演劇での昼興行という意味があり、映画の場合だと午前中に見ると、割引価格になります。このワインはポール・ラトーのワインの入門として、単一畑のワインが高くて躊躇している人に格安で出しているといった意味合いもあります。
最大の問題は、これが本当に美味しいので、こればかりが売れてしまうということだそうです。実際、上品な樽感ときれいな酸、少しグリップの効いた味わいは入門としては十分以上。私も購入しました。
ラトー氏に言わせるとこの日のマティネは知的な感じがあり、「プレイボーイ誌のバニーガールが心理学の修士号を持っているみたい」だとラトー氏。知的な印象を受け、実際に哲学的な語りも多いラトー氏ですが、実はちょいちょいジョークを挟んできます。通訳の山本香奈さんも「どこまでが真面目に行っているのかわからん」とときどき悩んでいました(笑)。
また、この日は8人の小規模なディナーだったのですが、前日は20人くらいの大規模なディナーだったそうです。クリエイティブなマインドがあり「同じことを2回やるのは苦手」というラトー氏にとっては、二日同じスタイルでないのは良かったとのことでした。
ラトー氏はすべて買いブドウでワインを造っていますが、自社畑の計画はないのかと聞いたところ、自社畑を持つのにはいい面と悪い面があるとのこと。現在は13くらいの畑からブドウを買っており、畑を見回っていますが、自社畑を持つと、いろいろな畑を回るのは難しくなります。彼の性分にはブドウを買う方が合っているようです。また、契約する相手は「一緒に食事をして楽しい相手」に限るとのこと。どんなにいいブドウを作っている畑でも食事とワインと会話を一緒に楽しめる相手からでないと買う気にはならないそうです(実は例外もあるようですが、それは教えてもらえませんでした)。

ちなみにこのとき、サラミと生ハムにキャラメライズしたオレンジとブーラッタ・チーズを乗せたものを食べていたのですが、オレンジをキャラメライズしたことを激賞していました。確かにこのキャラメライズで、シャルドネの樽の風味と非常によく合っていました。美味しい。
Paul Lato Chardonnay 'Goldberg Variations' No.2 Hyde Vineyard 2019
2番目のワインはナパのカーネロスにある銘醸畑ハイド(Hyde)のシャルドネです。なめらかなテクスチャー、最初のワインよりも酸高くリッチでミネラル感もあり、レベルの高さが感じられます。
Goldberg Variationsとはバッハの「ゴルトベルク変奏曲」のことで、この曲は最初と最後の主題の間に30の変奏曲が挟まる形になっています。ラトー氏が住むサンタ・バーバラからハイド・ヴィンヤードのナパまでは車で6時間ほどもかかるため、他の畑のように頻繁に訪れることができません。収穫時期の見極めなどもきめ細かい対応が難しくなります。そのためラトー氏としてもこの畑のワインを造るかどうか葛藤があったのですが、コントロールしきれないことによるヴィンテージの差異は変奏曲として許容しようという考えになりました。それがこの名前の由来になります。
ワイン造りにはレシピは持たないが哲学はあるとのこと。
収穫のタイミングが一番重要で、早すぎても良くないし、遅すぎるのも良くない。その見極めを大事にしています。また、収穫したブドウからはまずフリーランジュースを取り、それからプレスしていきます。あまり軽すぎるのもストラクチャーが出ないので、フリーランだけにすることはないようです。プレスの強さも決まりがあるわけではなく、果汁の味を見ながら、決めています。樽熟は16~18カ月。新樽率は高く、会計士には目を付けられているとか。新樽率は高いですが、樽の風味はあくまでも上品に付けるだけなので、会計士には「これだけ新樽を使っているんだからもっと樽感を出せ」と言われているとか。
様々な畑のワインを造る上で、その畑が表現できるようにしたいと考えていますが、それは「すべての畑で同じレシピでワインを造る」ということではありません。例えばある畑では新樽率は30%くらいですが、Hydeでは70%ほども使います。Hydeのブドウはしっかりしていて新樽をしっかり受け止めてくれる。レシピを決めて同じ新樽率で造るのではなく、それぞれの畑にあった形にしています。
また、欧州出身でブルゴーニュのワインは大好きですが、ブルゴーニュのワインを真似たいとは思っていないそうです。テクニックとしては使う部分はありますが、カリフォルニアのワインとして素晴らしいものを造ろうとしています。
この後、ちょっと哲学的な話になります。ラトー氏がワイン造りで大事にしているものとして、ワインのエネルギーやバイブレーションがあるといいます。昨年ブルゴーニュを訪問したときにサントーバンからモンラッシェまで歩いたのだそうです。自分の足で歩きながら畑を見ることで、畑を直接感じられたのですが、そのときにプルミエクリュ以上の畑からはバイブレーションを感じたそうです。ブルゴーニュは元々修道院の僧侶によって作られてきました。僧侶ですから信仰という面があり、モットーとしては「オーラ・エ・ラボーラ(祈りなさい、そして働きなさい)」という言葉が使われます。この祈りのスピリチュアルな部分と地に足を着けて働くというところが波動なのだとラトー氏は考えています。そしてプルミエクリュとかグランクリュのすばらしさがそのバイブレーションではないかと理解しているとのことでした。
Paul Lato Chardonnay 'East of Eden' Pisoni Vineyard 2019
Paul Lato Pinot Noir 'Lancelot' Pisoni Vineyard 2019 (実際にはこのワインは最後に飲んでいますが説明の便宜上ここに持ってきます)
ピゾーニ・ヴィンヤードは多くのワイナリーにブドウを供給していますが、シャルドネを作っているのはピゾーニ自身を除くとポール・ラトーしかありません。1990年代からブドウを提供しているピゾーニにとってはラトー氏は新参者。なぜ、それだけの関係を築けたのでしょう。
ラトー氏がピゾーニのことを知ったのは雑誌記事を通してでしたが、ゲイリー・ピゾーニ氏に直接会うことができたのはそれから1年半後でした。ゲイリー氏もラトー氏も飲んで食べるのが大好きなので、それで打ち解けていきました。あるときゲイリー氏が飲みながら「誕生日はいつか」というのでそれを伝えたところ、占星術の本を調べて、ゲイリー氏と同じ星の生まれでさることがわかり、同じ星の兄弟じゃないかということで盛り上がりました。それでワインを一緒に作ろうという話になっていきました。ただ、ピゾーニのブドウは既に多くのワイナリーに割り当てられていて空きがありません。ゲイリー氏は「ピーター・マイケルの分を分けてやるよ。奴らは少し減ったって気づかないさ」と言ったのですが、栽培担当の長男マークが「やっぱりそれはだめだよ」と言って、一回おじゃんになりました。その後、2008年にゲイリー氏が「自分のところのを分けるよ」ということでピゾーニ用の区画から2トンを分けてもらいました。
ところが、当時まだまだラトー氏も無名であり、ほかに順番待ちしているワイナリーも多いことから、「なんであいつにわけてやるんだ」という抗議の電話がかかってきたそうです。それをゲイリー氏は「自分の畑なんだから誰に提供したっていいだろ」と言い返しました。
ピゾーニのピノ・ノワールには「ランスロット(Lancelot)」という名前が付いています。ランスロットとはアーサー王の伝説に登場する円卓の騎士の一人。11人の騎士がいるところに後からアーサー王が連れてきて、円卓の騎士に加わったそうです。そのとき、他の騎士から抗議があったものの、アーサー王は決めるのは自分だとし、ランスロット自身もその後、騎士として一番優れていることを証明していったといいます。後からピゾーニのワイナリーに加わった自身を騎士ランスロットに見立てての命名なのだそうです。リチャードギアの「トゥルー・ナイト」という映画でランスロットが描かれているとのこと。
一方、シャルドネですが、前述のように、ピゾーニの畑のシャルドネを作っているのはピゾーニとポール・ラトーしかありません(ほかにピゾーニが作っているルチアのエステート・シャルドネに一部使われています)。
毎年、収穫時期にブドウのサンプルをもらいにいくのですが、そのときにピゾーニの畑に素晴らしいシャルドネが植わっているのを見つけ、栽培担当のマークに「マーク、この素晴らしいブドウはどこに行くの」と聞いたところ、「ルチアに使う」とのことでした。ちょっとブドウの味を見てみたところ本当にいいブドウでした。そこでラトー氏はマークに「コルトンのことを知っているか?」と聞きました。コルトンはブルゴーニュのグラン・クリュの中で例外的に赤と白、両方を造ることができます(ほかにはミュジニーがあります)。「それをゲイリーに伝えてくれ」といいました。帰宅後、真夜中にゲイリーから電話がかかってきて「それは素晴らしいアイデアだ。このブロックを半々ずつピゾーニとポール・ラトーで使おう」と言ってくれたとのこと。こういった理由でピゾーニとポール・ラトーのシャルドネが誕生したのでした。なお「イースト・オブ・エデン」はモントレーのサリナス・ヴァレー(その東側の斜面がサンタ・ルシア・ハイランズ)に住んでいた作家スタインベックの小説の名前から取っています。
そのシャルドネですが、3つのシャルドネの中では一番パワフル。トーストの風味も一番強く、果実味も酸もしっかり。リッチでなめらか。余韻長く素晴らしいシャルドネです。
Paul Lato Pinot Noir 'Matinee' Santa Barbara 2021
ピノのマティネです。ラズベリーやレッド・チェリーの風味。明るいルビー色でやわらかい酸味。少しミネラル感もあります。エントリー品いてと水準以上のワイン。

ラトー氏は薄切りのマッシュルームに感激してマッシュルームをつまんで写真を撮っていました。
Paul Lato Pinot Noir 'Atticus' John Sebastiano Vineyard 2016
ジョン・セバスティアーノ・ヴィンヤードはサンタリタ・ヒルズの中央にある畑。一つの畑ですが、様々な方角の斜面があり、ブルゴーニュだったら27の別々な畑にするようなところ。単一畑のワインへのアプローチはブレンドによるマティネとは全く違います。マティネはいろいろな畑のものをブレンドしてトータルで美味しいワイン、難しくないワインを造ろうとしていますが、単一畑の方は畑が語り掛けるものを表現しています。ブレンドが色を足していく絵画だとしたら、単一畑は余計なものをそぎ落としていく彫刻のような感じなのだそうです。
畑のオーナーのジョン・セバスティアーノさんとラトー氏は仲が良く、一緒にブルゴーニュに行ったこともあるそうですが、そのワインには何らかヒーローの名前を付けたいということで選んだのが「アティカス」です。これは『アラバマ物語』という映画でグレゴリー・ペックが演じた主人公で弁護士をしており、公平で正直で勇気がある人だったそうです。
今回、ワインの名前の由来をそれぞれ伺うことができました。「初めて聞いた」と伝えたところ「ほとんど話したことないんだよ」とのこと。アメリカ人はあまり名前に関心を持たないそうです。ラトー氏にとっては名前を付けるのは大事なことで、それこそ神の啓示のように名前が下りてくるのを待つのだとか。長い時には名前が決まるまで1年半かかったワインもあったそうです。
ちょっと名前の話が長くなりましたが、ジョン・セバスティアーノのピノ・ノワールは2016年のワインで9年熟成しているためマッシュルームや腐葉土といった、熟成によるアロマが出ています。素晴らしい。特に熟成好きな人にとっては、たまらないワインだと思います。
6番目のワインは先ほど説明したピゾーニのピノ・ノワール。複雑でシルキー、赤い果実に青い果実が少し入り、アーシーなニュアンスもあります。ややタンニン強くエレガントというよりはパワフルなピノ・ノワール。ピゾーニらしさも十分に出たすばらしいピノ・ノワールでした。
最後にスペシャルなワインが登場。シラーとグルナッシュのブレンドのワインでラベルも変わっています。これもきれいで美味しいワイン。あまり飲む機会はないですが、ラトー氏、シラーも名手です。
また、ハッピーキャニオンのブドウからソーヴィニヨン・ブランを作り始めているとのこと。畑のオーナーは歌手のPinkだそうです。これも名前がなかなか決まらなかったのですが、あるときYoutubeを見ていたらオーソレミオの歌が流れてきて、それで「オーソレミオ」をワインの名前にするそうです。11月にワインができたら持ってくるよと言っていましたが実現するでしょうか。
ところで、今回突然の来日だったのですが、その理由も明らかになりました。前の週にピゾーニ家が来日していましたが、ゲイリーからラトー氏に一緒に行こうよと誘われていたのだそうです。
それはちょっと、というところだったのですが、今度は別れた奥さんが息子さんと一緒に来日するというので、「君一人では心配だ」という理由を付けて急遽チケットを取ってやってきたのだそうです。ゲイリーとも京都であって一緒に飲んだとのことでした。
終始笑いの絶えないワイン会で、予想以上に気さくなおじさんでした。
Paul Lato Chardonnay 'Matinee' Santa Barbara 2020
最初のワインはシャルドネのマティネ(Matinee)です。マティネはフランス語で朝という意味です。このワインは元々レストラン用に作り始めたもので、市販は意図していませんでした。マティネにはまた映画や演劇での昼興行という意味があり、映画の場合だと午前中に見ると、割引価格になります。このワインはポール・ラトーのワインの入門として、単一畑のワインが高くて躊躇している人に格安で出しているといった意味合いもあります。
最大の問題は、これが本当に美味しいので、こればかりが売れてしまうということだそうです。実際、上品な樽感ときれいな酸、少しグリップの効いた味わいは入門としては十分以上。私も購入しました。
ラトー氏に言わせるとこの日のマティネは知的な感じがあり、「プレイボーイ誌のバニーガールが心理学の修士号を持っているみたい」だとラトー氏。知的な印象を受け、実際に哲学的な語りも多いラトー氏ですが、実はちょいちょいジョークを挟んできます。通訳の山本香奈さんも「どこまでが真面目に行っているのかわからん」とときどき悩んでいました(笑)。
また、この日は8人の小規模なディナーだったのですが、前日は20人くらいの大規模なディナーだったそうです。クリエイティブなマインドがあり「同じことを2回やるのは苦手」というラトー氏にとっては、二日同じスタイルでないのは良かったとのことでした。
ラトー氏はすべて買いブドウでワインを造っていますが、自社畑の計画はないのかと聞いたところ、自社畑を持つのにはいい面と悪い面があるとのこと。現在は13くらいの畑からブドウを買っており、畑を見回っていますが、自社畑を持つと、いろいろな畑を回るのは難しくなります。彼の性分にはブドウを買う方が合っているようです。また、契約する相手は「一緒に食事をして楽しい相手」に限るとのこと。どんなにいいブドウを作っている畑でも食事とワインと会話を一緒に楽しめる相手からでないと買う気にはならないそうです(実は例外もあるようですが、それは教えてもらえませんでした)。
ちなみにこのとき、サラミと生ハムにキャラメライズしたオレンジとブーラッタ・チーズを乗せたものを食べていたのですが、オレンジをキャラメライズしたことを激賞していました。確かにこのキャラメライズで、シャルドネの樽の風味と非常によく合っていました。美味しい。
Paul Lato Chardonnay 'Goldberg Variations' No.2 Hyde Vineyard 2019
2番目のワインはナパのカーネロスにある銘醸畑ハイド(Hyde)のシャルドネです。なめらかなテクスチャー、最初のワインよりも酸高くリッチでミネラル感もあり、レベルの高さが感じられます。
Goldberg Variationsとはバッハの「ゴルトベルク変奏曲」のことで、この曲は最初と最後の主題の間に30の変奏曲が挟まる形になっています。ラトー氏が住むサンタ・バーバラからハイド・ヴィンヤードのナパまでは車で6時間ほどもかかるため、他の畑のように頻繁に訪れることができません。収穫時期の見極めなどもきめ細かい対応が難しくなります。そのためラトー氏としてもこの畑のワインを造るかどうか葛藤があったのですが、コントロールしきれないことによるヴィンテージの差異は変奏曲として許容しようという考えになりました。それがこの名前の由来になります。
ワイン造りにはレシピは持たないが哲学はあるとのこと。
収穫のタイミングが一番重要で、早すぎても良くないし、遅すぎるのも良くない。その見極めを大事にしています。また、収穫したブドウからはまずフリーランジュースを取り、それからプレスしていきます。あまり軽すぎるのもストラクチャーが出ないので、フリーランだけにすることはないようです。プレスの強さも決まりがあるわけではなく、果汁の味を見ながら、決めています。樽熟は16~18カ月。新樽率は高く、会計士には目を付けられているとか。新樽率は高いですが、樽の風味はあくまでも上品に付けるだけなので、会計士には「これだけ新樽を使っているんだからもっと樽感を出せ」と言われているとか。
様々な畑のワインを造る上で、その畑が表現できるようにしたいと考えていますが、それは「すべての畑で同じレシピでワインを造る」ということではありません。例えばある畑では新樽率は30%くらいですが、Hydeでは70%ほども使います。Hydeのブドウはしっかりしていて新樽をしっかり受け止めてくれる。レシピを決めて同じ新樽率で造るのではなく、それぞれの畑にあった形にしています。
また、欧州出身でブルゴーニュのワインは大好きですが、ブルゴーニュのワインを真似たいとは思っていないそうです。テクニックとしては使う部分はありますが、カリフォルニアのワインとして素晴らしいものを造ろうとしています。
この後、ちょっと哲学的な話になります。ラトー氏がワイン造りで大事にしているものとして、ワインのエネルギーやバイブレーションがあるといいます。昨年ブルゴーニュを訪問したときにサントーバンからモンラッシェまで歩いたのだそうです。自分の足で歩きながら畑を見ることで、畑を直接感じられたのですが、そのときにプルミエクリュ以上の畑からはバイブレーションを感じたそうです。ブルゴーニュは元々修道院の僧侶によって作られてきました。僧侶ですから信仰という面があり、モットーとしては「オーラ・エ・ラボーラ(祈りなさい、そして働きなさい)」という言葉が使われます。この祈りのスピリチュアルな部分と地に足を着けて働くというところが波動なのだとラトー氏は考えています。そしてプルミエクリュとかグランクリュのすばらしさがそのバイブレーションではないかと理解しているとのことでした。
Paul Lato Chardonnay 'East of Eden' Pisoni Vineyard 2019
Paul Lato Pinot Noir 'Lancelot' Pisoni Vineyard 2019 (実際にはこのワインは最後に飲んでいますが説明の便宜上ここに持ってきます)
ピゾーニ・ヴィンヤードは多くのワイナリーにブドウを供給していますが、シャルドネを作っているのはピゾーニ自身を除くとポール・ラトーしかありません。1990年代からブドウを提供しているピゾーニにとってはラトー氏は新参者。なぜ、それだけの関係を築けたのでしょう。
ラトー氏がピゾーニのことを知ったのは雑誌記事を通してでしたが、ゲイリー・ピゾーニ氏に直接会うことができたのはそれから1年半後でした。ゲイリー氏もラトー氏も飲んで食べるのが大好きなので、それで打ち解けていきました。あるときゲイリー氏が飲みながら「誕生日はいつか」というのでそれを伝えたところ、占星術の本を調べて、ゲイリー氏と同じ星の生まれでさることがわかり、同じ星の兄弟じゃないかということで盛り上がりました。それでワインを一緒に作ろうという話になっていきました。ただ、ピゾーニのブドウは既に多くのワイナリーに割り当てられていて空きがありません。ゲイリー氏は「ピーター・マイケルの分を分けてやるよ。奴らは少し減ったって気づかないさ」と言ったのですが、栽培担当の長男マークが「やっぱりそれはだめだよ」と言って、一回おじゃんになりました。その後、2008年にゲイリー氏が「自分のところのを分けるよ」ということでピゾーニ用の区画から2トンを分けてもらいました。
ところが、当時まだまだラトー氏も無名であり、ほかに順番待ちしているワイナリーも多いことから、「なんであいつにわけてやるんだ」という抗議の電話がかかってきたそうです。それをゲイリー氏は「自分の畑なんだから誰に提供したっていいだろ」と言い返しました。
ピゾーニのピノ・ノワールには「ランスロット(Lancelot)」という名前が付いています。ランスロットとはアーサー王の伝説に登場する円卓の騎士の一人。11人の騎士がいるところに後からアーサー王が連れてきて、円卓の騎士に加わったそうです。そのとき、他の騎士から抗議があったものの、アーサー王は決めるのは自分だとし、ランスロット自身もその後、騎士として一番優れていることを証明していったといいます。後からピゾーニのワイナリーに加わった自身を騎士ランスロットに見立てての命名なのだそうです。リチャードギアの「トゥルー・ナイト」という映画でランスロットが描かれているとのこと。
一方、シャルドネですが、前述のように、ピゾーニの畑のシャルドネを作っているのはピゾーニとポール・ラトーしかありません(ほかにピゾーニが作っているルチアのエステート・シャルドネに一部使われています)。
毎年、収穫時期にブドウのサンプルをもらいにいくのですが、そのときにピゾーニの畑に素晴らしいシャルドネが植わっているのを見つけ、栽培担当のマークに「マーク、この素晴らしいブドウはどこに行くの」と聞いたところ、「ルチアに使う」とのことでした。ちょっとブドウの味を見てみたところ本当にいいブドウでした。そこでラトー氏はマークに「コルトンのことを知っているか?」と聞きました。コルトンはブルゴーニュのグラン・クリュの中で例外的に赤と白、両方を造ることができます(ほかにはミュジニーがあります)。「それをゲイリーに伝えてくれ」といいました。帰宅後、真夜中にゲイリーから電話がかかってきて「それは素晴らしいアイデアだ。このブロックを半々ずつピゾーニとポール・ラトーで使おう」と言ってくれたとのこと。こういった理由でピゾーニとポール・ラトーのシャルドネが誕生したのでした。なお「イースト・オブ・エデン」はモントレーのサリナス・ヴァレー(その東側の斜面がサンタ・ルシア・ハイランズ)に住んでいた作家スタインベックの小説の名前から取っています。
そのシャルドネですが、3つのシャルドネの中では一番パワフル。トーストの風味も一番強く、果実味も酸もしっかり。リッチでなめらか。余韻長く素晴らしいシャルドネです。
Paul Lato Pinot Noir 'Matinee' Santa Barbara 2021
ピノのマティネです。ラズベリーやレッド・チェリーの風味。明るいルビー色でやわらかい酸味。少しミネラル感もあります。エントリー品いてと水準以上のワイン。
ラトー氏は薄切りのマッシュルームに感激してマッシュルームをつまんで写真を撮っていました。
Paul Lato Pinot Noir 'Atticus' John Sebastiano Vineyard 2016
ジョン・セバスティアーノ・ヴィンヤードはサンタリタ・ヒルズの中央にある畑。一つの畑ですが、様々な方角の斜面があり、ブルゴーニュだったら27の別々な畑にするようなところ。単一畑のワインへのアプローチはブレンドによるマティネとは全く違います。マティネはいろいろな畑のものをブレンドしてトータルで美味しいワイン、難しくないワインを造ろうとしていますが、単一畑の方は畑が語り掛けるものを表現しています。ブレンドが色を足していく絵画だとしたら、単一畑は余計なものをそぎ落としていく彫刻のような感じなのだそうです。
畑のオーナーのジョン・セバスティアーノさんとラトー氏は仲が良く、一緒にブルゴーニュに行ったこともあるそうですが、そのワインには何らかヒーローの名前を付けたいということで選んだのが「アティカス」です。これは『アラバマ物語』という映画でグレゴリー・ペックが演じた主人公で弁護士をしており、公平で正直で勇気がある人だったそうです。
今回、ワインの名前の由来をそれぞれ伺うことができました。「初めて聞いた」と伝えたところ「ほとんど話したことないんだよ」とのこと。アメリカ人はあまり名前に関心を持たないそうです。ラトー氏にとっては名前を付けるのは大事なことで、それこそ神の啓示のように名前が下りてくるのを待つのだとか。長い時には名前が決まるまで1年半かかったワインもあったそうです。
ちょっと名前の話が長くなりましたが、ジョン・セバスティアーノのピノ・ノワールは2016年のワインで9年熟成しているためマッシュルームや腐葉土といった、熟成によるアロマが出ています。素晴らしい。特に熟成好きな人にとっては、たまらないワインだと思います。
6番目のワインは先ほど説明したピゾーニのピノ・ノワール。複雑でシルキー、赤い果実に青い果実が少し入り、アーシーなニュアンスもあります。ややタンニン強くエレガントというよりはパワフルなピノ・ノワール。ピゾーニらしさも十分に出たすばらしいピノ・ノワールでした。
最後にスペシャルなワインが登場。シラーとグルナッシュのブレンドのワインでラベルも変わっています。これもきれいで美味しいワイン。あまり飲む機会はないですが、ラトー氏、シラーも名手です。
また、ハッピーキャニオンのブドウからソーヴィニヨン・ブランを作り始めているとのこと。畑のオーナーは歌手のPinkだそうです。これも名前がなかなか決まらなかったのですが、あるときYoutubeを見ていたらオーソレミオの歌が流れてきて、それで「オーソレミオ」をワインの名前にするそうです。11月にワインができたら持ってくるよと言っていましたが実現するでしょうか。
ところで、今回突然の来日だったのですが、その理由も明らかになりました。前の週にピゾーニ家が来日していましたが、ゲイリーからラトー氏に一緒に行こうよと誘われていたのだそうです。
それはちょっと、というところだったのですが、今度は別れた奥さんが息子さんと一緒に来日するというので、「君一人では心配だ」という理由を付けて急遽チケットを取ってやってきたのだそうです。ゲイリーとも京都であって一緒に飲んだとのことでした。
終始笑いの絶えないワイン会で、予想以上に気さくなおじさんでした。
ナパのカーネロスでピノ・ノワールやシャルドネを作っていたアケイシア(Acacia)。2016年に畑などをペジュー(Peju)に売却し、その後はPejuがカルメール(Calmere)というワイナリー名で運用していたようです。そたがって今回はペジューによる売却ということになります。リスト価格は1750万ドルです。
また、ソノマではロシアン・リバー・ヴァレーとアレキサンダー・ヴァレーに有機栽培の畑を持つメドロック・エームズ(Medlock Ames)が売りに出されています。こちらの価格は4400万ドル。メドロック・エームズは近年では再生可能型有機栽培(ROC)の認証を得るなど先駆的なワイナリーです。ただ、2019年には火事のためにチョーク・ヒルにある畑の植え替えが必要になり、畑の20%は樹齢6年以下という形になっています。
先日もダックホーンによるブランド集約の話がありましたが、今年はこういった売却の例も増えていきそうです。
また、ソノマではロシアン・リバー・ヴァレーとアレキサンダー・ヴァレーに有機栽培の畑を持つメドロック・エームズ(Medlock Ames)が売りに出されています。こちらの価格は4400万ドル。メドロック・エームズは近年では再生可能型有機栽培(ROC)の認証を得るなど先駆的なワイナリーです。ただ、2019年には火事のためにチョーク・ヒルにある畑の植え替えが必要になり、畑の20%は樹齢6年以下という形になっています。
先日もダックホーンによるブランド集約の話がありましたが、今年はこういった売却の例も増えていきそうです。
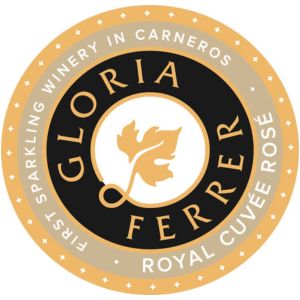
カーネロスのソノマ側で、スパークリング・ワインを造るグロリア・フェラー(Gloria Ferrer)が自社畑を有機栽培に転換して認証を得たと発表しました。畑の面積は338エーカーで、これはオークヴィルのト・カロンに匹敵する広さです。
例えば「カリフォルニアの有機栽培ブドウ畑、過去1年で1774エーカー増加」の記事によると2023年8月までの1年間にカリフォルニアの有機栽培認証「CCOF(California Certified Organic Farmers)」を取得した畑は1774エーカーでしたから、その2割弱ほどの面積を占めるという計算になります。
「CCOFオーガニック認証の取得は、グロリア・フェラーにとって決定的な瞬間であり、私たちの長期的なビジョンを力強く裏付けるものです。これは、土地への深い敬意だけでなく、責任ある再生型農業を通じてプレミアムスパークリングワインの未来をリードするという私たちのコミットメントを反映しています」と、グロリア・フェラーのゼネラルマネージャー、メラニー・シェーファーは述べています。「この節目は、私たちのブドウ園チームの長年にわたる献身的な努力と、環境、地域社会、そしてワインの完全性という最も重要なものを守るためのイノベーションへの継続的な投資の成果です」
グロリア・フェラーは2017年にはカリフォルニアのサスティナブル認証を畑とワイナリーの両方で得ており、今回の認証はそれに続くものとなります。
グロリア・フェラーでは有機栽培への転換と並行して、畑の植え替えを進めています。有機栽培をよりやりやすくするために、クローンのルートストックの組み合わせを最適化し、作業がしやすいようにしていくとのことです。
故ロバート・モンダヴィの次男で、ナパのプリチャード・ヒルでコンティニュアム(Continuum)を営むティム・モンダヴィが来日し、セミナーに参加してきました。2021年にはモンダヴィ家として100年目のヴィンテージとナパの歴史と共に歩んできたことを感じさせるセミナーでした。
最初にモンダヴィ家の歴史と現在のワイナリーを整理しておきます。ロバート・モンダヴィは家族でチャールズ・クリュッグ(Charles Krug)を営んでいましたが、そこを離れ(実際には追い出され)、1966年にロバート・モンダヴィ・ワイナリーを設立しました。ロバート・モンダヴィはナパを代表するワイナリーとして順調に成長し、ボルドーのシャトー・ムートン・ロートシルトとオーパス・ワンを始め、その後イタリアではフレスコバルディ家とテヌータ・ルーチェ、チリではエラスリス家とセーニャを始めました。イタリアではオルネライアも買収しました。
1993年には株式上場も果たしましたが、2000年代に入って業績不振や投資の失敗、またエンロンというエネルギー企業の会計スキャンダルから株主の要求が厳しくなったことなどにより、2004年にコンステレーション・ブランズに売却され、ロバート・モンダヴィの一家もワイナリーから離れることになりました。なお、コンステレーションは今年、ウッドブリッジやロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクションといった安価なブランドをザ・ワイン・グループに売却しています。上場については、最終的には売却の原因の一つになってしまったわけですが、上場当時は資金を得たことで畑の植え替えや上記のジョイント・ベンチャーなどができ、良かったとティムは語っています。
ワイナリー売却後、従来から不仲が伝えられていたティムとマイケルの兄弟は袂を分かち、ロバートはティム側に付きます。マイケルはマイケル・モンダヴィ・ファミリー・エステートを設立し、M by Michael Mondaviやスペルバウンドなど、幅広いブランドを展開しています。また、X JapanのYoshikiとのコラボによるY by Yoshikiのワインメーカーはマイケルの息子のロブ・モンダヴィJrが務めています。
また、ロバートが去った後のチャールズ・クリュッグは弟の故ピーターを中心に家族経営を続けており、現在はピーターの孫娘が中心になっています。チャールズ・クリュッグ以外にフォース・リーフやAloftなどのワイナリーも手掛け、幅広く活躍しています。
そして、今回の主役のティムですが、ロバート・モンダヴィ・ワイナリー売却は「心痛む出来事だった」というものの、翌2005年にロバートと共にコンティニュアムを立ち上げました。売却時の約束で当初数年間はモンダヴィの銘醸畑ト・カロンのブドウを使っていましたが、売却による資金もあったため新たな畑を探すことになりました。モンダヴィの畑はナパの西側マヤカマス山脈の麓の沖積扇状地にありましたが、新たな畑は東側にあるヴァカ山脈の火山性の土壌の斜面がいいと考えて探しました。そこで見つけたのがプリチャード・ヒルにあったクラウド・ヴューというワイナリーの畑でした。ロバートも畑を見に行きそこに決めました。ティムは「斜面の向きが南西など様々な方向にあり、ミネラルが豊富。当初考えていた以上に素晴らしい畑で、見つけられたのは幸運だったと思う」と語っています。
西のマヤカマスは元々海底だった海洋性の土壌が中心となりますが、ヴァカ山脈は鉄分が多く、見るからに赤い土地で、表土も1.5mほどと非常に浅いのが特徴です。マヤカマスではレッドウッドなど大きな樹が生えますが、ヴァカ山脈側は月桂樹やセージなどが多く、樹もあまり成長しません。ナパの中には様々な土壌がありますが、ヴァカ山脈側を選んだのはこういった痩せた土壌のためです。
また、コンティニュアムの畑は標高350~450mほどのところにあります。霧がかかるエリアよりも少し高いところにあるので夜でもあまり冷え込まないという特徴があります。また、日中は標高のために気温が低くなります。夏場では7℃ほども違うとのこと。昼と夜の寒暖差が比較的小さく、また日照が常にあるので、しっかり光合成ができる環境にあります。
2013年にはワイナリーも作り、栽培から醸造まですべてを賄う「エステート」になりました。これが現在のコンティニュアムです。また、ティムの二人の息子のカルロとダンテは、ナパから出てソノマ・コーストの冷涼地区でシャルドネとピノ・ノワールを作るレイン(Raen)を立ち上げ、今ではトップクラスの品質を誇っています。カルロが栽培、ダンテが醸造の担当です。カルロは無人操作できる電動トラクターとして人気のモナーク・トラクターの開発も手掛けています。そして、娘のキアラは2021年にソーヴィニヨン・ブランを作るセンティアム(Sentium)を始めています。キアラはコンティニュアムのラベルの絵も描いています。この絵はティムがト・カロン・ヴィンヤードに植えたカベルネ・フランの樹をかたどったものだとのこと。
今回はセンティアムの最新ヴィンテージとコンティニュアムの4ヴィンテージを試飲しました。
ロバート・モンダヴィが1966年にワイナリーを始めた後、最初に大きなヒットになったのがソーヴィニヨン・ブランでした。それまでソーヴィニヨン・ブランはとても軽い味わいか、甘口に仕上げられるようなものしかなかったのですが、樽熟成もして本格的なワインとして仕上げたものに「フュメ・ブラン」と名前を付けたのがそれ。特に前述のト・カロンの畑には1945年に植樹されたiブロックという古い区画があり、高品質なソーヴィニヨン・ブランを生み出しています。実はティムがモンダヴィで栽培の責任者になったころ、畑のマネージャーがこのブロックを収量が少ないということで引き抜こうと考えていたそうです。ティムは古い樹が高品質なブドウを作ると信じてそれを止めて今にいたります。センティアムはこのiブロックのフュメ・ブランにインスピレーションを受けています。使っている畑も1940年代と60年代に植樹されたという古い樹が植わっています。
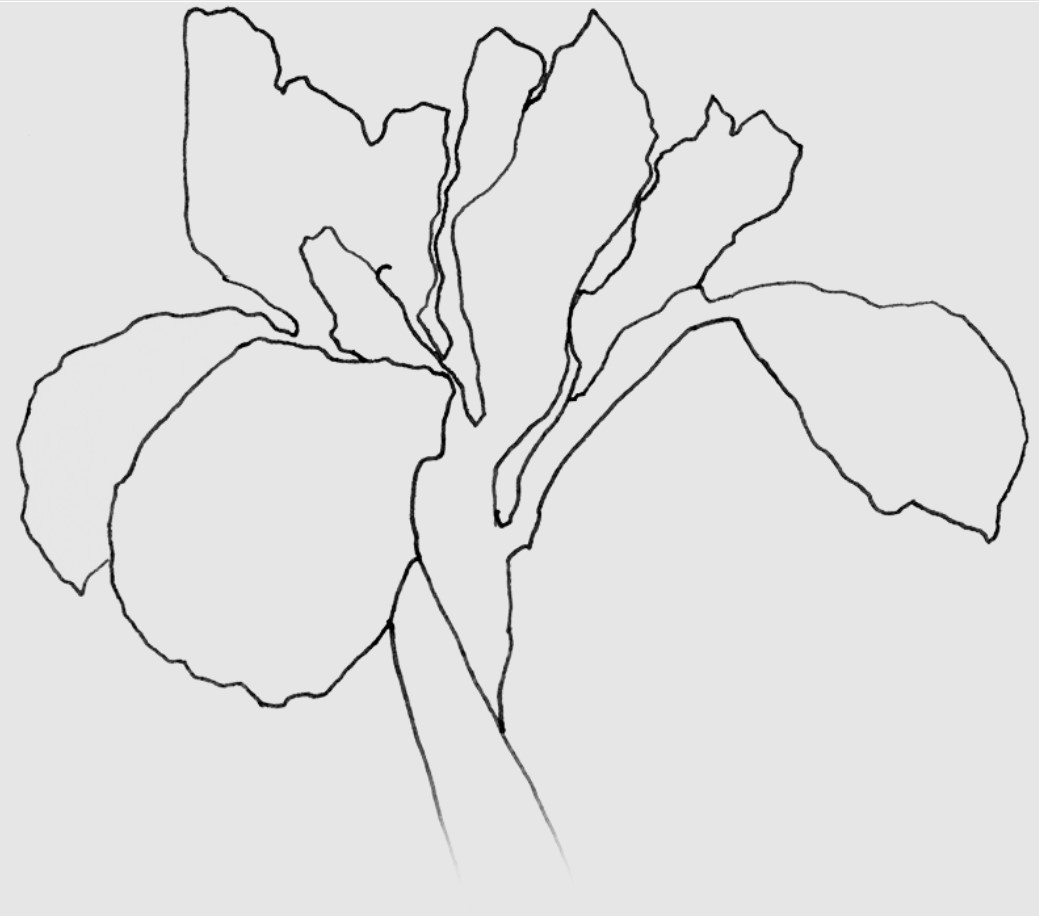
センティアムのラベルはキアラ自身が花を線画で描いたシンプルなもの。「野の花のように複雑で荘厳な自然とより調和して生きること」という、長女のカリッサ・モンダヴィによる詩も書かれています。畑はメンドシーノのレッドウッド・ヴァレーにあり、土壌に水晶が含まれており、ワインにミネラル感を与えています。
このミネラル感を生かすためにブドウは早めに収穫します。夜間に収穫してすぐに優しくプレス。一晩寝かした後、上澄みだけを発酵槽に入れます。発酵はニュートラルバレルとコンクリートタンク、ステンレスの樽を1/3ずつ使っています。小さな発酵容器を使って澱と一緒に熟成することでクリーミーな舌触りを得ています。ロワールのディディエ・ダグノーに似ているという評価をもらったそうです。
センティアム 2023はハーブや青い草のニュアンスもありながら、豊かな柑橘の風味、黄色い花やネクタリンんども感じられるエレガントでリッチな味わい。多層的な複雑さが感じられるのは古木のためでしょうか。高品質なソーヴィニヨン・ブランです。ティムは「最近のiブロックを超えていると思う」とのこと。
この後は、コンティニュアムの4ヴィンテージ垂直試飲です。2020年は山火事の影響で造られなかったため、2018、2019、2021、2022年となっています。
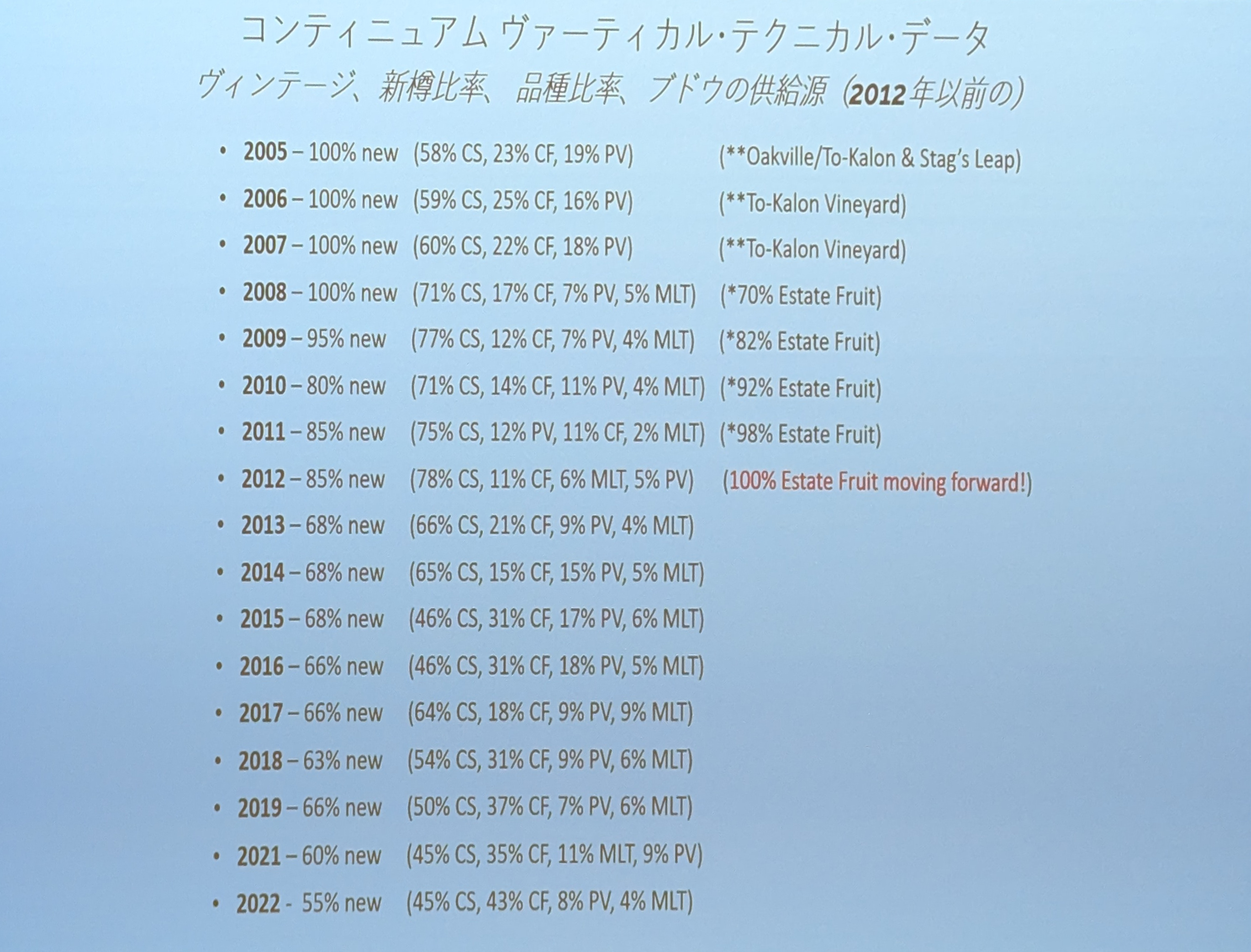
ヴィンテージごとのテクニカル・データを見ると、新樽率は当初の100%から55%にまで下がっています。また、カベルネ・ソーヴィニヨンの比率が、エステートのブドウを使い始めたころが70%程度だったのが現在は40%台まで下がっています。一方でカベルネ・フランの比率はだんだん上がっており、2022年にはカベルネ・ソーヴィニョンと2%しか違わない43%にまでなっています。品種ごとの比率が今後どうなっていくか聞いてみたところ、カベルネ・ソーヴィニョンとカベルネ・フランが45%ずつというのが、ターゲットになってくるのかもしれないとのことでした。
発酵には大樽とコンクリート・タンクを使っています。モンダヴィが中で初めて導入し、広く使われているステンレススチールのタンクは、タンニンの管理にあまり向かないのではないかとティム。コンクリート・タンクは味わいがまろやかになるとのことで、カベルネ・ソーヴィニョンや種が多くタニックになりがちなプティ・ヴェルドで使っています。コンクリートとオークの大樽の組み合わせが、ティムが作りたいワインには一番合っているのではないかと考えているそうです。
カベルネ・ソーヴィニョンはやはりファウンデーションなのでベースになる品種。カベルネ・フランは香り高く、タンニンしなやか、スイートネスを与えてくれます。プティ・ヴェルドは種が多く、コンクリートタンクで醸造することでまろやかになるとのこと。プティ・ヴェルドはスキンコンタクトを15~18日と短めにしています。コンティニュアムの畑の中で一番古いカベルネ・ソーヴィニョンは1991年に植えられたクローン7のブロックですが、これについてはスキンコンタクトを35~40日と長くしています。熟成時には樽に澱をなるべく多く入れます。テクスチャーをクリーミーにすると同時に色を鮮やかにします。ワインの酸化を防ぐという働きもあるそうです。
新樽率が下がってきていると書きましたが、これはこの畑の果実の特徴をよりストレートに表現したいといった目的があるそうです。また、熟成についてはブルゴーニュ的と考えているとのこと。コンティニュアムの畑は乾燥していてうどん粉が広がる恐れが非常に少ないため、フランスでよく使われている硫酸銅を含んだボルドー液を使う必要がほとんどありません。結果として澱引きもほとんどしなくていいとのこと。
4ヴィンテージの試飲メモです。
2018年
黒から赤の密度の濃い果実味に、スミレやモカ、ハーブやミネラルの風味。酸はやや高く、エレガント。タンニンはなめらかでシルキーなテクスチャー。素晴らしいワイン。ほぼ完ぺきといっていいでしょう。
2019年
この年はモンダヴィ家がワインを造り始めて100回目のヴィンテージだとのこと。赤果実が中心で、2018年よりも酸高くタニック。ポテンシャルはありますが飲み頃に入るまで、まだ数年かかりそうです。
2021年
2019年よりもさらに酸高くタンニンも強固です、赤果実はあまりなく、より熟した風味。かなり長熟型と思われます。
2022年
青黒果実。華やかでしなやか、果実味豊かでタンニンは比較的低く、今でも美味しく飲めます。
2022年は9月上旬に激しい熱波が来たため、それよりも収穫が遅いカベルネ・ソーヴィニヨンなどにとっては難しい年と言われています。多くの生産者が熱波をどうやりすごすのか、収穫してしまうかなど難しい選択を迫られました。その中でコンティニュアムの2022年はクオリティとしては非常に高いものがあり、2019や21とはスタイルが違いますが、非常に上手にまとめているのが印象的でした。ティム自身は2022年が一番好きと言っていたのも、そのあたりの理由があるのかもしれません。また、熱波について質問したところ、高台にあるということで、ヴァレーフロアの畑に比べると、その影響はだいぶ少なかったとのことでした。おそらく、栽培、醸造、どちらもいろいろな手を尽くした結果なのだろうと思うと、この2022年は、感銘を受けるワインと言っていいのではないかと感じました。

スタッグス・リープ・ワイナリー(Stags’ Leap Winery)の創設者であるカール・ドゥマーニ(Carl Doumani)が4月22日になくなりました。92歳でした。7年前からアルツハイマー病を患っており、昼寝中にそのまま亡くなられたそうです。波乱万丈な人生でしたが、平穏な最後を迎えられたようです。
カールの母親はカードゲームが得意で、父親は先物取引の業者でした。カールもその血を引き継いでギャンブラーとして育ち、生涯さまざまな賭けを打ちました。
1970年頃、ナパに家を持ちたいと土地を探しており、今のスタッグス・リープに400エーカーの土地と歴史的な建造物を紹介されました。彼は農業もワイン造りも経験ありませんでしたが、その建物で宿を開いてブドウを販売しようと考えて購入しました。

家は長年放置されており、大規模な改修が必要でした。ただ、規制の厳しいナパヴァレーで宿を開くのは難しく、結局家族でその家に引っ越してきました。畑には樹齢100年にもなるプティ・シラーが植わっており、植え替えの資金もなかったことから、それでワインを造ることにしました。
その後も平穏ではなく、担保にしていた土地開発の会社が倒産して、いとこが経営していたラスベガスのトロピカーナ・ホテルで総支配人として1年間働くといったこともありました。
また、パリスの審判で有名になったスタッグス・リープ・ワイン・セラーズ(Stag's Leap Wine Cellars)のウォーレン・ウィニアルスキーとはスタッグス・リープの名称を巡って裁判になりました。最終的にドゥマーニのワイナリーは「Stags'」、ウォーレン・ウィニアルスキーのワイナリーは「Stag's」、AVAの名称は「Stags」とアポストロフィで使い分けることになりました。
1980年代にはナパの好景気を満喫しました。シルヴァー・オークのジャスティン・マイヤーらと10人で「GONADS(無意味かつ放蕩な美食家協会)」を始め、月に一回ランチ会を開いていましたが、いろいろと問題を起こし、訴追などを避けるためにメキシコに移りました。それがきっかけで1995年にはエンカンタードというメスカルの製造・販売を始めました。
周囲が彼の基準についてきてくれなかったこともあり、ビジネスに嫌気がさして1997年にはワイナリーをベリンジャー(現トレジャリー・ワイン・エステーツ)に売却。元の土地の一部を保有して、新たなワイナリー「キホーテ(Quixote)」を興しました。キホーテはスペインの小説家セルバンテスの有名な小説「ドン・キホーテ」から取った名前で、波乱万丈な人生を送るカールにはぴったりでした。

このワイナリーはオーストリアの建築家フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサーによるもので、北米では唯一の彼の作品です。(1)直線を使わない、(2)屋根には草が生えている、(3)どの建物にも金の小塔がある(男性の象徴的意味合い)、(4)色こそ王様、といった設計のルールがあったとのこと。ワインのラベルもフンデルトヴァッサーのデザインです。
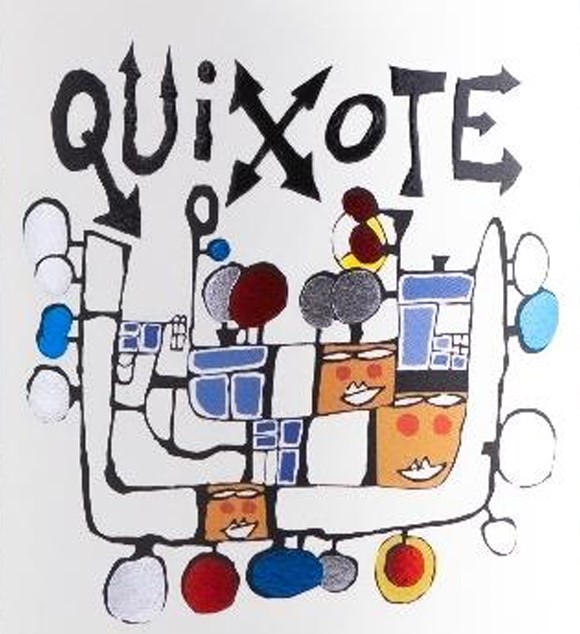
キホーテではまたプティ・シラーに注力しましたが、2014年に売却。2エーカーだけブドウ畑を残し、その後は「¿Como No?」という小さなワイナリーを営みましたが2018年に生産を中止しました。
謹んでお悔やみ申し上げます。

ダックホーン(Duckhorn)などのワイナリーを所有するダックホーン・ポートフォリオは5月6日、ブランドを今後集約していくと発表しました。ダックホーンのブランドには、元々ダックホーン家が展開していたカモ科の鳥をモチーフにしたブランド(ダックホーン、デコイ、ゴールデンアイ、パラダックス、マイグレーション、キャンヴァスバック、グリーンウイング、ポストマーク)のほか、買収したカレラ、コスタ・ブラウン、ソノマ・カトラーがあります。
今回の発表では買収した3ブランドのほか、ダックホーン、デコイ、ゴールデンアイ、グリーンウイングの計7ブランドに力を入れていきます。これら7ブランドで売り上げの96%を占めています。一方で、パラダックス、マイグレーション、キャンヴァスバック、ポストマークの4ブランドについては縮小・廃止していくとしています。すでに醸造したワインが約3ヴィンテージ分あることから、3年後をめどに廃止していくことになると思われます。それまではこれまでと同様に、販売していくとのこと。日本での販売も、まだ詳しいことは決まっていませんが同様になりそうです。
また、ナパにあるマイグレーションのテイスティング・ルーム、ソノマにあるソノマ・カトラーのテイスティング・ルーム、ワシントンのワラワラにあるキャンヴァスバックのテイスティング・ルームは2025年6月に廃止する予定です。ソノマ・カトラーについてはテイスティング・ルームは閉鎖しますが、ワイナリーの運営はこれまで通りに行われます。
米国におけるワインの需要が縮小傾向にあるため、このようなブランドの集約は今後、他の大手のワイナリーでも起こってくる可能性が高いのではと思います。
1990年代にラブコメの女王と言われていたのが女優のメグ・ライアン。その出演作の一つに「フレンチ・キス」という映画があり、ブドウの苗木をひそかに運ぶという話がその中で重要な役割を担っていました(当時はその意味はよく分かっていなかったのですが)。
植物を他国に持ち込むと、そこから病害虫などが広がってしまう可能性があります。例えば19世紀に欧州のブドウ畑を壊滅させたフィロキセラは欧州に運ばれた米国のブドウから広がりました。そのため、現在では検疫を通さないで植物を持ち込むことは固く禁じられています。とはいえ品質の高いブドウの樹が欲しいというニーズはなくならないので、密かに持ち込んだという話はいろいろ残っています。カリフォルニアでいえば、一番有名なのはロマネ・コンティから取ってきたと言われるカレラのピノ・ノワールで、その次に有名なのが、このピゾーニのピノ・ノワール。「ラ・ターシュ」の畑から拾ってきた枝を植えたと言われています。
その当人であるゲイリー・ピゾーニが初来日し、次男でワインメーカーのジェフ・ピゾーニとのセミナーに参加させていただきました。ジェフが来るのでということで参加したのですが(しかも、特別に中川ワインさんのスタッフ向けセミナーに同席させていただきました)、部屋に入ったら、これまで写真や動画で何度も見ていたゲイリー・ピゾーニ本人までいらっしゃったので、びっくりしました。貴重な機会ですので、苗木の話もうかがったわけですが、それは後の楽しみとして、ピゾーニ・ヴィンヤードの基本からおさらいしましょう。

ピゾーニ・ヴィンヤードがあるのは、モントレーのサンタ・ルシア・ハイランズAVA。現在はカリフォルニアで良質なピノ・ノワールが造られる代表的なAVAと目されていますが、この地域を有名にした立役者がこのピゾーニ・ヴィンヤードです。1990年代後半から、なんだかすごい畑があるらしいという噂が広がり、2000年代のピノ・ノワール・ブームで、後で紹介する兄弟的な畑とともに、サンタ・ルシア・ハイランズを牽引してきました。
元々、ピゾーニ家はワインを造る前からモントレーで牧畜や野菜作りをしていました。サンタ・ルシア・ハイランズのあるサリナス・ヴァレーは「世界のサラダボウル」と呼ばれるほど野菜作りが盛んな地域であり、レタスやトマト、セロリ、ブロッコリー、アスパラガスなど様々な野菜を育てていました。サリナス・ヴァレーの北西にはモントレー湾があり、そこから冷たい冷気が入ってきます。

特に、モントレー湾は水深が深く、非常に冷たい水が上がってきます。日本では高原野菜として標高の高いところで育てられることが多いレタスがサリナス・ヴァレーの代表的な産物であることからも、ここの涼しさがわかります。
カリフォルニアの沿岸には山脈が連なっており、サンタ・ルシア・ハイランズは沿岸山脈の東側の斜面になります。東向き斜面なので午前中の優しい太陽を浴びます。その点ではブルゴーニュと共通しています。このあたりの山脈は標高が高いので、太平洋から山脈を超えて冷気が来ることはほとんどなく、北側のモントレー湾から南に向かって風が吹いて冷気や冷たい霧を運んできます。特にサリナス・ヴァレーはモントレー湾に面した北側が広く、南に行くと狭くなる漏斗の形をしているので、霧は非常に厚くなります。湾に近い北側ほど涼しく、距離がある南は少し暖かくなります。霧がかかる高さは300mから330mほどのところで、夜の9~10時ころに霧が入ってきて、朝11時くらいには消えるそうです。
ピゾーニ・ヴィンヤードはサンタ・ルシア・ハイランズの中では最南端に近いので、比較的温暖になります。また標高は300~400m。低いところは霧がかかりますが、高いところはほとんど霧がかかりません、また強い風が吹き抜けるところでもあります。サンタ・ルシア・ハイランズの中でも特殊な畑と言えます。元々は放牧用に使っていた土地だそうです。
ジェフ・ピゾーニによると、サンタ・ルシア・ハイランズのピノ・ノワールはリッチなワインとピュアな果実味があり、ストラクチャーとパワー、エレガンスを共存しているといいます。
ゲイリーは若いころからワインが好きで、世界の様々なワインをコレクションしており、ブドウも育てたいと思っていましたが、父親の反対でなかなか実現しませんでした。ブドウを育てるなんて愚か者がすることだとまで言っていたそうですが、ゲイリーは「250ドル払ってブラックタイで参加するレタスの試食に招待されたことはあるの?」と反論し、最後は父親が折れて1982年からいよいよピノ・ノワールとシャルドネを栽培することになりました。ワイン造り自体は1978年からガレージレベルでやっていて、まだ幼かった二人の息子もそれを手伝っていたそうです。
そして、ピノ・ノワールを植えるとなったときに、ピノ・ノワールではクローンが重要だと気が付き、いろいろな人から一番いいクローンを得るにはブルゴーニュに行かないとと言われました。ゲイリーはフランス語も全くしゃべれず、現地に知り合いもいませんでしたが、ともかくブルゴーニュに行って2、3カ月を過ごしました。ある有名な畑で剪定した枝が地面にたくさん落ちているのを抱えてホテルの部屋に戻りました。そのままではかさばりすぎるので、芽のところだけ残して小さくカットして、それを500ほど作りました。
ただ、前述のように検疫を受けていないため、普通には税関を通れません。そこでその500個の芽をパンツの中に隠して飛行機に乗ったのです。いくら小さくカットしたとはいえ、それだけパンツに詰め込んだら、シティーハンターの冴羽獠状態です。さすがに税関の女性に怪しまれて、それは何だと触って確認しようとしたところ、ゲイリーは「どうしてもチェックしたいのか、俺はイタリア人だぞ」で乗り切ったとのこと。
その500本を数年かけて5000本、5万本と増やして畑を造っていきました。さらに植えた樹の中からいいものをマサル・セレクションとして選んで増やしているとのことです。
ちなみに、ピゾーニからは他のワイナリーにはクローンを売っていないそうです。盗もうとする人はときどきいるそうですが、3匹の大きな番犬がいるので大体成功しないとか。
前述のように、ピゾーニの畑は標高が高いところにあります。水源がなく、当初は車で麓から水を運んでいったそうです。ただ、雨も少なく灌漑が必要な土地であり、水源なしでは栽培は困難であり、井戸を掘ることになりました。表土が浅く、その下は固い花崗岩という土地で掘り進めるのも大変でしたが、6回目の挑戦でようやく水源を見つけました。ゲイリーは嬉しさのあまり、その水に飛び込んだそうです。水源を見つけたのは1991年ですので、畑を作ってから9年間は水を運んでいたことになります。

現在は、ピゾーニブランドのワインが有名になりましたが、元々栽培家として始めたので、今でも栽培を重視しています。15年ほど前からサスティナブルに取り組んでいます。除草剤や防虫剤などは使わず、養蜂などをしています。高品質なブドウを造るためにグリーン・ハーヴェストで収穫量を減らしているとのこと。
栽培は長男のマークが担当、醸造は次男のジェフが担当しています。ジェフはフレズノ州立大学で醸造を学び、ピーターマイケルで2年間修行した後、モントレーの他のワイナリーでも働き、ピゾーニでワインを造り始めました。醸造はサンタ・ルシア・ハイランズではなくソノマで行っています。当初はピーターマイケルのワイナリーを借りていたそうですが、今は別のところになっています。

醸造では天然酵母を使い100%全房、清澄やフィルターがけはしていません。
試飲に移ります。

ピゾーニで現在作っているブランドは三つ。Pisoniブランドは、Pisoni Vineyardのピノ・ノワールのためのブランド。現在はシャルドネも少量作っています(シャルドネの話は、Paul Latoのワインのときに書く予定です)。Lucia(ルチア、ルシア)ブランドは、Pisoni Vineyard以外の自社畑のピノ・ノワールとシャルドネ。三つ目のLucy(ルーシー)は買いブドウも含むピノ・ノワール、シャルドネ以外のワインのブランドになっています。Lucyでは三つのワインを造っていますが、「Pico Blanco(ピコ・ブランコ)」はモントレー湾の海洋環境保護団体、ロゼは女性の疾患究明、ガメイはモントレーの山火事の最前線で活動した消防団に収益の一部を寄付しています。
最初のワインはLucy Pico Blanco 2023(5200円)。ピノ・グリ86%、ピノ・ブラン14%のワインでサンタ・ルシア・ハイランズのほか、モントレーの中のやや温暖な地域であるアロヨ・セコのブドウを使っています。次の2024年からはシャローンのピノ・グリが入ってくるとのこと。
酸高く、熟した果実の風味があります。黄色い花や洋ナシ、ミネラル感もあります。
2番目はLucy Rose of Pinot Noir 2023(4900円)。2005年にLucyとして最初に作ったワインです。半分はセニエ、半分は直接圧搾によるロゼをブレンドしています。直接圧搾を半分使っているので色はやや薄めです。セニエは自社畑、直接圧搾は買いブドウを使っています。チャーミングでラズベリーの風味、バランス良く飲みやすいワイン。
3番目はLucy Gamay Noir 2023(5900円)。サンタルシアには花崗岩の土壌が点在しており、ガメイとは親和性が高いといいます。チャーミングなイチゴの味わい。少しジャミーでストラクチャーもありますが、酸がきれいで魅惑的なワイン。
pHは3.4とかなり低く、タンニンが低いので白ワインのような味わいだとのこと。収穫を遅くしても酸が残るそうです。
4番目からルチアに入ります。最初はLucia by Pisoni Chardonnay Estate 2023(9500円)です。
ピゾーニにはこれまで説明したピゾーニ・ヴィンヤードのほか、ロアー(Roar)のオーナーであるフランシオーニ家と共同所有しているゲイリーズ(Garys’)とソベラネス(Soberanes)の畑があります。フランシオーニ家のゲイリー・フランシオーニとゲイリー・ピゾーニは幼馴染で、Garys’と複数形の所有形になっているのは二人のゲイリーによる畑ということです。

このあたりの所有関係は分かりにくいので、上の図にまとめました。図中のSusan's Hillは今回は登場しませんが、Pisoni Vineyardの中の特別なブロックでシラーが植わっています。
Lucia by Pisoni Chardonnay Estateはピゾーニとソベラネスのシャルドネを半分ずつ使ったワインです。このワインは輸出用にはほとんど出しておらず、中川は特別だとのこと。ソベラネスもワイン・スペクテーターの「California's Best Chardonnay Vineyards」という記事で選ばれた11の畑の一つに入るほどの銘醸畑です。

ゲイリーズとソベラネスは隣り合っていて、サンタ・ルシア・ハイランズの中央あたり、ピゾーニとは逆に標高の低いところに畑があります。
シャルドネのクローンはオールドウェンテとモンラッシュ・クローンを使っているとのこと。ほぼフリーラン・ジュースしか使わないくらい優しくプレスをしてジュースを取り出しています。
シルキーなテクスチャーがありリッチでミネラル感のあるシャルドネ。酸もきれいでとても美味しい。これはコスパ高いと思います。
5番目はPisoni Estate Chardonnay 2022(17000円)。
ピゾーニの畑のシャルドネは自根で植えられています。バレルセレクションでいいものを選んだリザーブ的な位置付け。上のエステートシャルドネ以上にやわらかなテクスチャー。リッチで多層的な味わい、熟成が楽しめそうなワイン。非常に素晴らしいですが、逆に上のエステートのコスパもまたすごいと改めて思いました。
試飲はここで折り返して後半です。
6本目はLucia by Pisoni Pinot Noir Estate Cuvee 2022(10000円)。ピゾーニとゲイリーズ、ソベラネスの3つの畑のピノノワールをブレンドしています。2023からはGarys'のとなりのWindRock Vineyardという畑のブドウも入ります。ここもフランシオーニ家と共同オーナーの畑です。

フリーランジュースだけを使ったピノ・ノワール。後述のピゾーニの畑のピノ・ノワールががっしりとしたストラクチャーのあるワインになるのに対し、こちらはよりリッチでタンニンが柔らかく、なまめかしさがあります。赤系に黒系の果実の風味が重なり、緻密でパワフル。これも価格的に素晴らしいワイン。
7本目はLucia by Pisoni Pinot Noir Soberanes Vineyard 2022(12400円)。
ソベラネスとゲイリーズは隣り合っておりクローンはほぼ同じですが、ソベラネスが少し密植でうねの向きが違います。土壌はソベラネスの方だけ石がごろごろと転がっています。花崗岩系の土壌だとのこと。赤系に青系の果実の風味。果実感が強くしっかりしたストラクチャーがあります。ジェフによるとソベラネスはフローラルな印象があるとのこと。
8本目はLucia by Pisoni Pinot Noir Garys' Vineyard 2022(14000円)。
ソベラネスが石がごろごろしているのに対して、ゲイリーズも花崗岩ですが、より細かく崩れているとのこと。ゲイリーズは非常に骨太の味わいというイメージがありましたが、今回はエステートやソベラネスよりも赤果実感が強くジューシーな味わいに感じられました。
9本目はPisoni Estate Pinot Noir Pisoni Vineyard 2022(20000円)。
甘やかな香りで、リッチで複雑。ストラクチャーと凝縮感が強いが酸も高くエレガントさもあり、バランスはいい。素晴らしいワインだが、本当の魅力が発揮されるまでは数年かかりそうな感じ。
最後はLucia by Pisoni Syrah Soberanes VIneyard 2022(12000円)。
バニラやココナッツといった甘い樽の香りにジューシーな果実味。ホワイトペッパー、がっしりとしたタンニン。シラー好きにはたまらない美味しさ。
最後に、これがゲイリーが乗り回していることで有名なジープ。元々はゲイリーの父親がゲイリーの母にプレゼントした車だったそうです。父が運転して母は助手席で猟銃を構えて猟をしていたというので、お母さんも結構な豪傑だったようです。
植物を他国に持ち込むと、そこから病害虫などが広がってしまう可能性があります。例えば19世紀に欧州のブドウ畑を壊滅させたフィロキセラは欧州に運ばれた米国のブドウから広がりました。そのため、現在では検疫を通さないで植物を持ち込むことは固く禁じられています。とはいえ品質の高いブドウの樹が欲しいというニーズはなくならないので、密かに持ち込んだという話はいろいろ残っています。カリフォルニアでいえば、一番有名なのはロマネ・コンティから取ってきたと言われるカレラのピノ・ノワールで、その次に有名なのが、このピゾーニのピノ・ノワール。「ラ・ターシュ」の畑から拾ってきた枝を植えたと言われています。
その当人であるゲイリー・ピゾーニが初来日し、次男でワインメーカーのジェフ・ピゾーニとのセミナーに参加させていただきました。ジェフが来るのでということで参加したのですが(しかも、特別に中川ワインさんのスタッフ向けセミナーに同席させていただきました)、部屋に入ったら、これまで写真や動画で何度も見ていたゲイリー・ピゾーニ本人までいらっしゃったので、びっくりしました。貴重な機会ですので、苗木の話もうかがったわけですが、それは後の楽しみとして、ピゾーニ・ヴィンヤードの基本からおさらいしましょう。
ピゾーニ・ヴィンヤードがあるのは、モントレーのサンタ・ルシア・ハイランズAVA。現在はカリフォルニアで良質なピノ・ノワールが造られる代表的なAVAと目されていますが、この地域を有名にした立役者がこのピゾーニ・ヴィンヤードです。1990年代後半から、なんだかすごい畑があるらしいという噂が広がり、2000年代のピノ・ノワール・ブームで、後で紹介する兄弟的な畑とともに、サンタ・ルシア・ハイランズを牽引してきました。
元々、ピゾーニ家はワインを造る前からモントレーで牧畜や野菜作りをしていました。サンタ・ルシア・ハイランズのあるサリナス・ヴァレーは「世界のサラダボウル」と呼ばれるほど野菜作りが盛んな地域であり、レタスやトマト、セロリ、ブロッコリー、アスパラガスなど様々な野菜を育てていました。サリナス・ヴァレーの北西にはモントレー湾があり、そこから冷たい冷気が入ってきます。

特に、モントレー湾は水深が深く、非常に冷たい水が上がってきます。日本では高原野菜として標高の高いところで育てられることが多いレタスがサリナス・ヴァレーの代表的な産物であることからも、ここの涼しさがわかります。
カリフォルニアの沿岸には山脈が連なっており、サンタ・ルシア・ハイランズは沿岸山脈の東側の斜面になります。東向き斜面なので午前中の優しい太陽を浴びます。その点ではブルゴーニュと共通しています。このあたりの山脈は標高が高いので、太平洋から山脈を超えて冷気が来ることはほとんどなく、北側のモントレー湾から南に向かって風が吹いて冷気や冷たい霧を運んできます。特にサリナス・ヴァレーはモントレー湾に面した北側が広く、南に行くと狭くなる漏斗の形をしているので、霧は非常に厚くなります。湾に近い北側ほど涼しく、距離がある南は少し暖かくなります。霧がかかる高さは300mから330mほどのところで、夜の9~10時ころに霧が入ってきて、朝11時くらいには消えるそうです。
ピゾーニ・ヴィンヤードはサンタ・ルシア・ハイランズの中では最南端に近いので、比較的温暖になります。また標高は300~400m。低いところは霧がかかりますが、高いところはほとんど霧がかかりません、また強い風が吹き抜けるところでもあります。サンタ・ルシア・ハイランズの中でも特殊な畑と言えます。元々は放牧用に使っていた土地だそうです。
ジェフ・ピゾーニによると、サンタ・ルシア・ハイランズのピノ・ノワールはリッチなワインとピュアな果実味があり、ストラクチャーとパワー、エレガンスを共存しているといいます。
ゲイリーは若いころからワインが好きで、世界の様々なワインをコレクションしており、ブドウも育てたいと思っていましたが、父親の反対でなかなか実現しませんでした。ブドウを育てるなんて愚か者がすることだとまで言っていたそうですが、ゲイリーは「250ドル払ってブラックタイで参加するレタスの試食に招待されたことはあるの?」と反論し、最後は父親が折れて1982年からいよいよピノ・ノワールとシャルドネを栽培することになりました。ワイン造り自体は1978年からガレージレベルでやっていて、まだ幼かった二人の息子もそれを手伝っていたそうです。
そして、ピノ・ノワールを植えるとなったときに、ピノ・ノワールではクローンが重要だと気が付き、いろいろな人から一番いいクローンを得るにはブルゴーニュに行かないとと言われました。ゲイリーはフランス語も全くしゃべれず、現地に知り合いもいませんでしたが、ともかくブルゴーニュに行って2、3カ月を過ごしました。ある有名な畑で剪定した枝が地面にたくさん落ちているのを抱えてホテルの部屋に戻りました。そのままではかさばりすぎるので、芽のところだけ残して小さくカットして、それを500ほど作りました。
ただ、前述のように検疫を受けていないため、普通には税関を通れません。そこでその500個の芽をパンツの中に隠して飛行機に乗ったのです。いくら小さくカットしたとはいえ、それだけパンツに詰め込んだら、シティーハンターの冴羽獠状態です。さすがに税関の女性に怪しまれて、それは何だと触って確認しようとしたところ、ゲイリーは「どうしてもチェックしたいのか、俺はイタリア人だぞ」で乗り切ったとのこと。
その500本を数年かけて5000本、5万本と増やして畑を造っていきました。さらに植えた樹の中からいいものをマサル・セレクションとして選んで増やしているとのことです。
ちなみに、ピゾーニからは他のワイナリーにはクローンを売っていないそうです。盗もうとする人はときどきいるそうですが、3匹の大きな番犬がいるので大体成功しないとか。
前述のように、ピゾーニの畑は標高が高いところにあります。水源がなく、当初は車で麓から水を運んでいったそうです。ただ、雨も少なく灌漑が必要な土地であり、水源なしでは栽培は困難であり、井戸を掘ることになりました。表土が浅く、その下は固い花崗岩という土地で掘り進めるのも大変でしたが、6回目の挑戦でようやく水源を見つけました。ゲイリーは嬉しさのあまり、その水に飛び込んだそうです。水源を見つけたのは1991年ですので、畑を作ってから9年間は水を運んでいたことになります。
現在は、ピゾーニブランドのワインが有名になりましたが、元々栽培家として始めたので、今でも栽培を重視しています。15年ほど前からサスティナブルに取り組んでいます。除草剤や防虫剤などは使わず、養蜂などをしています。高品質なブドウを造るためにグリーン・ハーヴェストで収穫量を減らしているとのこと。
栽培は長男のマークが担当、醸造は次男のジェフが担当しています。ジェフはフレズノ州立大学で醸造を学び、ピーターマイケルで2年間修行した後、モントレーの他のワイナリーでも働き、ピゾーニでワインを造り始めました。醸造はサンタ・ルシア・ハイランズではなくソノマで行っています。当初はピーターマイケルのワイナリーを借りていたそうですが、今は別のところになっています。
醸造では天然酵母を使い100%全房、清澄やフィルターがけはしていません。
試飲に移ります。
ピゾーニで現在作っているブランドは三つ。Pisoniブランドは、Pisoni Vineyardのピノ・ノワールのためのブランド。現在はシャルドネも少量作っています(シャルドネの話は、Paul Latoのワインのときに書く予定です)。Lucia(ルチア、ルシア)ブランドは、Pisoni Vineyard以外の自社畑のピノ・ノワールとシャルドネ。三つ目のLucy(ルーシー)は買いブドウも含むピノ・ノワール、シャルドネ以外のワインのブランドになっています。Lucyでは三つのワインを造っていますが、「Pico Blanco(ピコ・ブランコ)」はモントレー湾の海洋環境保護団体、ロゼは女性の疾患究明、ガメイはモントレーの山火事の最前線で活動した消防団に収益の一部を寄付しています。
最初のワインはLucy Pico Blanco 2023(5200円)。ピノ・グリ86%、ピノ・ブラン14%のワインでサンタ・ルシア・ハイランズのほか、モントレーの中のやや温暖な地域であるアロヨ・セコのブドウを使っています。次の2024年からはシャローンのピノ・グリが入ってくるとのこと。
酸高く、熟した果実の風味があります。黄色い花や洋ナシ、ミネラル感もあります。
2番目はLucy Rose of Pinot Noir 2023(4900円)。2005年にLucyとして最初に作ったワインです。半分はセニエ、半分は直接圧搾によるロゼをブレンドしています。直接圧搾を半分使っているので色はやや薄めです。セニエは自社畑、直接圧搾は買いブドウを使っています。チャーミングでラズベリーの風味、バランス良く飲みやすいワイン。
3番目はLucy Gamay Noir 2023(5900円)。サンタルシアには花崗岩の土壌が点在しており、ガメイとは親和性が高いといいます。チャーミングなイチゴの味わい。少しジャミーでストラクチャーもありますが、酸がきれいで魅惑的なワイン。
pHは3.4とかなり低く、タンニンが低いので白ワインのような味わいだとのこと。収穫を遅くしても酸が残るそうです。
4番目からルチアに入ります。最初はLucia by Pisoni Chardonnay Estate 2023(9500円)です。
ピゾーニにはこれまで説明したピゾーニ・ヴィンヤードのほか、ロアー(Roar)のオーナーであるフランシオーニ家と共同所有しているゲイリーズ(Garys’)とソベラネス(Soberanes)の畑があります。フランシオーニ家のゲイリー・フランシオーニとゲイリー・ピゾーニは幼馴染で、Garys’と複数形の所有形になっているのは二人のゲイリーによる畑ということです。

このあたりの所有関係は分かりにくいので、上の図にまとめました。図中のSusan's Hillは今回は登場しませんが、Pisoni Vineyardの中の特別なブロックでシラーが植わっています。
Lucia by Pisoni Chardonnay Estateはピゾーニとソベラネスのシャルドネを半分ずつ使ったワインです。このワインは輸出用にはほとんど出しておらず、中川は特別だとのこと。ソベラネスもワイン・スペクテーターの「California's Best Chardonnay Vineyards」という記事で選ばれた11の畑の一つに入るほどの銘醸畑です。

ゲイリーズとソベラネスは隣り合っていて、サンタ・ルシア・ハイランズの中央あたり、ピゾーニとは逆に標高の低いところに畑があります。
シャルドネのクローンはオールドウェンテとモンラッシュ・クローンを使っているとのこと。ほぼフリーラン・ジュースしか使わないくらい優しくプレスをしてジュースを取り出しています。
シルキーなテクスチャーがありリッチでミネラル感のあるシャルドネ。酸もきれいでとても美味しい。これはコスパ高いと思います。
5番目はPisoni Estate Chardonnay 2022(17000円)。
ピゾーニの畑のシャルドネは自根で植えられています。バレルセレクションでいいものを選んだリザーブ的な位置付け。上のエステートシャルドネ以上にやわらかなテクスチャー。リッチで多層的な味わい、熟成が楽しめそうなワイン。非常に素晴らしいですが、逆に上のエステートのコスパもまたすごいと改めて思いました。
試飲はここで折り返して後半です。
6本目はLucia by Pisoni Pinot Noir Estate Cuvee 2022(10000円)。ピゾーニとゲイリーズ、ソベラネスの3つの畑のピノノワールをブレンドしています。2023からはGarys'のとなりのWindRock Vineyardという畑のブドウも入ります。ここもフランシオーニ家と共同オーナーの畑です。

フリーランジュースだけを使ったピノ・ノワール。後述のピゾーニの畑のピノ・ノワールががっしりとしたストラクチャーのあるワインになるのに対し、こちらはよりリッチでタンニンが柔らかく、なまめかしさがあります。赤系に黒系の果実の風味が重なり、緻密でパワフル。これも価格的に素晴らしいワイン。
7本目はLucia by Pisoni Pinot Noir Soberanes Vineyard 2022(12400円)。
ソベラネスとゲイリーズは隣り合っておりクローンはほぼ同じですが、ソベラネスが少し密植でうねの向きが違います。土壌はソベラネスの方だけ石がごろごろと転がっています。花崗岩系の土壌だとのこと。赤系に青系の果実の風味。果実感が強くしっかりしたストラクチャーがあります。ジェフによるとソベラネスはフローラルな印象があるとのこと。
8本目はLucia by Pisoni Pinot Noir Garys' Vineyard 2022(14000円)。
ソベラネスが石がごろごろしているのに対して、ゲイリーズも花崗岩ですが、より細かく崩れているとのこと。ゲイリーズは非常に骨太の味わいというイメージがありましたが、今回はエステートやソベラネスよりも赤果実感が強くジューシーな味わいに感じられました。
9本目はPisoni Estate Pinot Noir Pisoni Vineyard 2022(20000円)。
甘やかな香りで、リッチで複雑。ストラクチャーと凝縮感が強いが酸も高くエレガントさもあり、バランスはいい。素晴らしいワインだが、本当の魅力が発揮されるまでは数年かかりそうな感じ。
最後はLucia by Pisoni Syrah Soberanes VIneyard 2022(12000円)。
バニラやココナッツといった甘い樽の香りにジューシーな果実味。ホワイトペッパー、がっしりとしたタンニン。シラー好きにはたまらない美味しさ。
最後に、これがゲイリーが乗り回していることで有名なジープ。元々はゲイリーの父親がゲイリーの母にプレゼントした車だったそうです。父が運転して母は助手席で猟銃を構えて猟をしていたというので、お母さんも結構な豪傑だったようです。
昨年、コスパの高さで話題になったワインの一つがビッグ・スムースのカベルネ・ソーヴィニヨン。現地価格で実売18ドルするワインが1800円台と、1ドル100円でしたっけ(それにしても安いですが)と思ってしまうほどの値段。ワインも名前通りなめらかなテクスチャーで芳醇。1000円台とは思えない(実際本来は4000円とかするワインですから)クオリティで人気が爆発しました。
そのビッグ・スムースのジンファンデルが国内入荷しています。これも現地価格では実売18ドルからが1800円台と、相変わらず1ドル100円でしたっけ、それにしても安いけどという価格。リッチ系のジンファンデルを飲みたい人には「まずはこれ飲んで」という感じです。
ラベルはカベルネの赤に対しジンファンデルは紫、これはぜひ実物で触ってみて欲しいのですが、ビロードのような手触りで「スムース」感を出しています。
カベルネの方は、まだ在庫があるショップもありますが、売り切れ近そうな感じです。残念ながら両方売っているところは見つかりませんでした。
しあわせワイン倶楽部です。
柳屋です。
ドラジェです。
アティグスというショップは初めて見たような気がします。
タカムラです。
そのビッグ・スムースのジンファンデルが国内入荷しています。これも現地価格では実売18ドルからが1800円台と、相変わらず1ドル100円でしたっけ、それにしても安いけどという価格。リッチ系のジンファンデルを飲みたい人には「まずはこれ飲んで」という感じです。
ラベルはカベルネの赤に対しジンファンデルは紫、これはぜひ実物で触ってみて欲しいのですが、ビロードのような手触りで「スムース」感を出しています。
カベルネの方は、まだ在庫があるショップもありますが、売り切れ近そうな感じです。残念ながら両方売っているところは見つかりませんでした。
しあわせワイン倶楽部です。
柳屋です。
ドラジェです。
アティグスというショップは初めて見たような気がします。
タカムラです。
ナパのワイナリー「ザ・ヴァイス(The Vice)」の創設者でありワインメーカーであるマレック・アムラーニさんが来日し、ランチをご一緒させていただきました(余談ですが、彼のラストネームがアムラーニなのかアルマーニなのかアマローニなのかいつも忘れてしまいます。今回「アムラー」+「ニ」と覚えました)。ヴァイスの設立は2016年。まだ10年も経っていませんが、ナパでも大手の生産者の仲間入りをし、ナパヴァレー・ヴィントナーズのボードメンバーにも入っています。

マレックさんはモロッコの生まれ。父親がパイロットで幼少期から様々な国を旅行してきました(今まで行った国の数は65だそうです、ちなみにヴァイスのワインを輸出しているのは11カ国)。
彼の半生は驚くべきことばかりで「Vice Wine Company Founder Goes From Moroccan Street Dealer To Luxury Winemaker」に詳しくまとめられていますが、ここで簡単に記しておきます。
11歳で母親を亡くしてからは大麻の売買などに手を染めたこともありましたが、頭は良く16歳で高校を卒業して医学部に入学しました。しかし医学部は性に合わず、米国に行くことを考え、17歳でビザを取得してニューヨークに。そこから半年はホームレス生活をしていました。年齢を偽ってバーテンダーやウェイターをし、高級レストランのソムリエを経て酒販会社のセールス担当に上り詰めました。30歳になるまでに100万ドル以上の税金を払ったとのことです。
そこからワイン造りを始めることを考え、毎週末にニューヨークからナパに行く生活を続け、ナパで多くの生産者の知己を得ます。2013年からはニューヨークで少しずつワインを造りはじめます。そして2016年に本腰を入れてザ・ヴァイスを設立。ヴァイスとは「悪癖」のことであり、「自分を幸せにしてくれるのは自分の悪癖だ」ということから名付けたそうです。
ヴァイスは多種生産で、現在では60を超えるキュベを作っています。日本に輸入されているのも10種類以上あります。自身では畑を持たず、栽培家とのコネクションでブドウを調達しています。名前を出していませんが、驚くような畑のブドウが使われているワインもあります。
マレックさんとは関税の話などを含めていろいろとざっくばらんにお話ししてきましたが、ここでは飲んだワインを中心にお伝えします。

最初のワインはゲヴュルツトラミネールのオレンジワインです(5720円、税込み希望小売価格、以下同)。ヴァイスのワインは表ラベルは非常にシンプルなデザインのものが多く、裏ラベルに情報が載っていることがしばしばです。ですので、写真は表と裏の両方を載せています。
このオレンジワインは唯一残糖があるワインです。ヴァイスはナパでは唯一といっていいオレンジワインの生産者で(ほかにマサイアソンが少量作っていますが)、中でもこのゲビュルツのオレンジがヴァイスの中でも2番目に人気のあるワインで、特に若い世代に支持されているそうです。ゲヴュルツらしいライチの香りがあり、ほどよい甘みがスターターとしてぴったりです。オレンジワインとしては、フレッシュな味わいで中華前菜にもよく合いました。ちなみにゲヴュルツは、カーネロス産のものを使っていましたが、今はモントレーを中心にカーネロスとメンドシーノのブドウを少量使っているそうです。ラベルはカリフォルニア表記です。といっても実は表ラベルはポピーの絵が描かれているだけで、品種名も何も書いていません。ほとんどのコンシューマーはゲヴェルツトラミネールという品種名を知らないので、あえて情報は裏ラベルにしか入れていないとのことです。


次のワインはナパヴァレーのシャルドネです(7150円)。「エリース」という名前が付けられていますが、これはマレックさんの義理の母親の名前から取りました。彼女はシャルドネ好きでしたが、ここ15年ほど好きなシャルドネが見付からず、このシャルドネを作ったそうです。一番のポイントは100%フレンチオークの新樽で熟成していること。上品な樽の風味が高級感を与えてくれます。安いシャルドネはオークチップなどで香りを付けるので濃厚ですが、実際の新樽の上品さはでてきません。その代わり、樽のコストだけでワイン1本あたり4.5ドルにもなるそうです。マロラクティック発酵は30%に抑えており、フレッシュ感を残しているのもポイントで、バランスよく美味しいシャルドネです。私もシャルドネファンとして納得の1本となりました。


小籠包とエビのマヨネーズ炒め。

次のナパヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨンはヴァイスで一番生産量の多いワイン(7480円)。1万6000ケースほどを作っています。樽はアメリカン・オークとフレンチ・オークを半々。ブドウはカーネロス、クームズヴィルといった冷涼地域から、オークヴィル、セントヘレナのヴァレーフロア、そしてスプリング・マウンテン、アトラス・ピークといった山のブドウと6カ所から調達しています。
ワインの名前は「ザ・ハウス」。裏ラベルにはマレックさんの家から見える景色が描かれています。
まさに正統派のナパのカベルネ・ソーヴィニヨン。バランスもよく、ストラクチャーもあり、高級感も醸し出しています。

アルバリーニョのオレンジです(5720円)。アルバリーニョというと海のイメージがあると思いますが、これは逆でシエラネバダの山麓の畑のブドウを使っています。生産量少なく、ほとんど直販で売っているワインです。どちらかというと軽い味わいのことが多いアルバリーニョが醸しによって、花の香りなどが出てきてアロマティックなワインになってきています。バランスよく美味しい。実はこのワイン、凝った作りで半分はコンクリートエッグ、半分はステンレススチールタンクで醸造しておりステンレススチールの方だけ17日間醸しをしています。

次はオークヴィルのカベルネ・ソーヴィニヨン「99ヴァイセス」です(15950円)。オークヴィルの東側斜面の畑とのこと。オークヴィルは東も西もすごい畑ばかりですが、東といえばダラ・ヴァレやピーター・マイケル、ジョセフ・フェルプスのバッカスなど。弩級の畑が並ぶ地域です。正直に言って、ワインの品質的にも1万円台なら全然安いと思います。オークヴィルらしいリッチさとバランスの良さ、複雑さがあり素晴らしいカベルネ・ソーヴィニヨン。

次のワインは「ファイヴ・ピークス」というカベルネ・ソーヴィニヨン(19800円)。ナパには山のAVAが五つ(マウント・ヴィーダー、スプリング・マウンテン、ダイヤモンド・マウンテン、アトラス・ピーク、ハウエル・マウンテン)ありますが、これつの山のブドウをすべて使ったワイン。ナパ広しと言えども、五つの山のAVA全部を使ったワインはおそらくこれだけだろうとのことです。ボトルの横には標高も書いてあって面白い。実はこれも畑は聞けば「おー!」と思うようなところばかり。山らしいタンニンと深みがあります。長期熟成にも耐えられるワイン。
ちなみに、これは書いても大丈夫だと思いますが、スプリング・マウンテンは、先日廃業が発表されたニュートンのブドウを使っています。ヴァイスはニュートンのスプリング・マウンテンとヨントヴィルの畑のブドウを使う権利を得ているそうで、秀逸なブドウソースを手に入れたことになります。

最後はジンファンデル(9350円)。暖かいところで育つイメージが強いジンファンデルですが、これはナパで一番冷涼なカーネロスのジンファンデルを使っています。エレガントで美味しいジンファンデル。
マレックさん、ワインメーカーとして秀逸なワインを造っていますが、それだけでなく、ビジネスセンスがあり、様々な事象についてお話を伺えました。例えば関税の問題、ロー・アルコールやノー・アルコールのブームをどう考えるか、缶ワインは、マリファナは、などなど。話も面白く、さすが1代でここまでビジネスを広げてきただけのことはあると感じました。
ワイナリーの人に会うと、「ナパに来たらうちのワイナリーに寄ってね」と言われるのが普通ですが、彼の場合はそれだけでなく「声をかけてくれたら、ナパでどのワイナリーに行ったらいいかコンシェルジェをしてあげるよ」と言ってくれました。いろいろな栽培家とのコネクションもあることからの言葉かとは思いますが、そういった考えができるのも面白いと思いました。
セッティングいただいたオルカさん、ありがとうございました。

マレックさんはモロッコの生まれ。父親がパイロットで幼少期から様々な国を旅行してきました(今まで行った国の数は65だそうです、ちなみにヴァイスのワインを輸出しているのは11カ国)。
彼の半生は驚くべきことばかりで「Vice Wine Company Founder Goes From Moroccan Street Dealer To Luxury Winemaker」に詳しくまとめられていますが、ここで簡単に記しておきます。
11歳で母親を亡くしてからは大麻の売買などに手を染めたこともありましたが、頭は良く16歳で高校を卒業して医学部に入学しました。しかし医学部は性に合わず、米国に行くことを考え、17歳でビザを取得してニューヨークに。そこから半年はホームレス生活をしていました。年齢を偽ってバーテンダーやウェイターをし、高級レストランのソムリエを経て酒販会社のセールス担当に上り詰めました。30歳になるまでに100万ドル以上の税金を払ったとのことです。
そこからワイン造りを始めることを考え、毎週末にニューヨークからナパに行く生活を続け、ナパで多くの生産者の知己を得ます。2013年からはニューヨークで少しずつワインを造りはじめます。そして2016年に本腰を入れてザ・ヴァイスを設立。ヴァイスとは「悪癖」のことであり、「自分を幸せにしてくれるのは自分の悪癖だ」ということから名付けたそうです。
ヴァイスは多種生産で、現在では60を超えるキュベを作っています。日本に輸入されているのも10種類以上あります。自身では畑を持たず、栽培家とのコネクションでブドウを調達しています。名前を出していませんが、驚くような畑のブドウが使われているワインもあります。
マレックさんとは関税の話などを含めていろいろとざっくばらんにお話ししてきましたが、ここでは飲んだワインを中心にお伝えします。

最初のワインはゲヴュルツトラミネールのオレンジワインです(5720円、税込み希望小売価格、以下同)。ヴァイスのワインは表ラベルは非常にシンプルなデザインのものが多く、裏ラベルに情報が載っていることがしばしばです。ですので、写真は表と裏の両方を載せています。
このオレンジワインは唯一残糖があるワインです。ヴァイスはナパでは唯一といっていいオレンジワインの生産者で(ほかにマサイアソンが少量作っていますが)、中でもこのゲビュルツのオレンジがヴァイスの中でも2番目に人気のあるワインで、特に若い世代に支持されているそうです。ゲヴュルツらしいライチの香りがあり、ほどよい甘みがスターターとしてぴったりです。オレンジワインとしては、フレッシュな味わいで中華前菜にもよく合いました。ちなみにゲヴュルツは、カーネロス産のものを使っていましたが、今はモントレーを中心にカーネロスとメンドシーノのブドウを少量使っているそうです。ラベルはカリフォルニア表記です。といっても実は表ラベルはポピーの絵が描かれているだけで、品種名も何も書いていません。ほとんどのコンシューマーはゲヴェルツトラミネールという品種名を知らないので、あえて情報は裏ラベルにしか入れていないとのことです。

次のワインはナパヴァレーのシャルドネです(7150円)。「エリース」という名前が付けられていますが、これはマレックさんの義理の母親の名前から取りました。彼女はシャルドネ好きでしたが、ここ15年ほど好きなシャルドネが見付からず、このシャルドネを作ったそうです。一番のポイントは100%フレンチオークの新樽で熟成していること。上品な樽の風味が高級感を与えてくれます。安いシャルドネはオークチップなどで香りを付けるので濃厚ですが、実際の新樽の上品さはでてきません。その代わり、樽のコストだけでワイン1本あたり4.5ドルにもなるそうです。マロラクティック発酵は30%に抑えており、フレッシュ感を残しているのもポイントで、バランスよく美味しいシャルドネです。私もシャルドネファンとして納得の1本となりました。
小籠包とエビのマヨネーズ炒め。

次のナパヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨンはヴァイスで一番生産量の多いワイン(7480円)。1万6000ケースほどを作っています。樽はアメリカン・オークとフレンチ・オークを半々。ブドウはカーネロス、クームズヴィルといった冷涼地域から、オークヴィル、セントヘレナのヴァレーフロア、そしてスプリング・マウンテン、アトラス・ピークといった山のブドウと6カ所から調達しています。
ワインの名前は「ザ・ハウス」。裏ラベルにはマレックさんの家から見える景色が描かれています。
まさに正統派のナパのカベルネ・ソーヴィニヨン。バランスもよく、ストラクチャーもあり、高級感も醸し出しています。

アルバリーニョのオレンジです(5720円)。アルバリーニョというと海のイメージがあると思いますが、これは逆でシエラネバダの山麓の畑のブドウを使っています。生産量少なく、ほとんど直販で売っているワインです。どちらかというと軽い味わいのことが多いアルバリーニョが醸しによって、花の香りなどが出てきてアロマティックなワインになってきています。バランスよく美味しい。実はこのワイン、凝った作りで半分はコンクリートエッグ、半分はステンレススチールタンクで醸造しておりステンレススチールの方だけ17日間醸しをしています。

次はオークヴィルのカベルネ・ソーヴィニヨン「99ヴァイセス」です(15950円)。オークヴィルの東側斜面の畑とのこと。オークヴィルは東も西もすごい畑ばかりですが、東といえばダラ・ヴァレやピーター・マイケル、ジョセフ・フェルプスのバッカスなど。弩級の畑が並ぶ地域です。正直に言って、ワインの品質的にも1万円台なら全然安いと思います。オークヴィルらしいリッチさとバランスの良さ、複雑さがあり素晴らしいカベルネ・ソーヴィニヨン。

次のワインは「ファイヴ・ピークス」というカベルネ・ソーヴィニヨン(19800円)。ナパには山のAVAが五つ(マウント・ヴィーダー、スプリング・マウンテン、ダイヤモンド・マウンテン、アトラス・ピーク、ハウエル・マウンテン)ありますが、これつの山のブドウをすべて使ったワイン。ナパ広しと言えども、五つの山のAVA全部を使ったワインはおそらくこれだけだろうとのことです。ボトルの横には標高も書いてあって面白い。実はこれも畑は聞けば「おー!」と思うようなところばかり。山らしいタンニンと深みがあります。長期熟成にも耐えられるワイン。
ちなみに、これは書いても大丈夫だと思いますが、スプリング・マウンテンは、先日廃業が発表されたニュートンのブドウを使っています。ヴァイスはニュートンのスプリング・マウンテンとヨントヴィルの畑のブドウを使う権利を得ているそうで、秀逸なブドウソースを手に入れたことになります。

最後はジンファンデル(9350円)。暖かいところで育つイメージが強いジンファンデルですが、これはナパで一番冷涼なカーネロスのジンファンデルを使っています。エレガントで美味しいジンファンデル。
マレックさん、ワインメーカーとして秀逸なワインを造っていますが、それだけでなく、ビジネスセンスがあり、様々な事象についてお話を伺えました。例えば関税の問題、ロー・アルコールやノー・アルコールのブームをどう考えるか、缶ワインは、マリファナは、などなど。話も面白く、さすが1代でここまでビジネスを広げてきただけのことはあると感じました。
ワイナリーの人に会うと、「ナパに来たらうちのワイナリーに寄ってね」と言われるのが普通ですが、彼の場合はそれだけでなく「声をかけてくれたら、ナパでどのワイナリーに行ったらいいかコンシェルジェをしてあげるよ」と言ってくれました。いろいろな栽培家とのコネクションもあることからの言葉かとは思いますが、そういった考えができるのも面白いと思いました。
セッティングいただいたオルカさん、ありがとうございました。

Wine to Styleの試飲会から、美味しかったワインを紹介します。試飲会はなるべく網羅的に試飲しようとしていますが、Wine to Styleの試飲会は全部で372アイテムと非常に種類が多いため、基本的に米国のワインだけを試飲しています。なお、価格は税抜きの希望小売価格です。

シュラムスバーグのセカンド「ミラベル」のブリュット・ロゼ(5600円)。ロゼの華やかな色と、コクのあるボディ豊かな味わいが特徴。鶏肉などライトな肉料理にも合わせやすいスパークリング。

ユンヌ・ファム(Une Femme)という缶入りスパークリング。250mlで800円という手の出しやすい価格。「The Callie」はロゼで、ジューシーな味わい。

ボー・リバージュという、内陸のクラークスバーグにあるワイナリーのシュナンブランです(5800円)。クラークスバーグは内陸ですが、サンフランシスコ湾からの冷涼な空気が入ってくるところなので、気温は意外と低いのが特徴です。ボー・リバージュはワイン・アドヴォケイトのレビュアーであるウィリアム・ケリーのワイナリーです。とてもバランスのよい味わい。

人気ブランド「スリー・ガールズ」のソーヴィニヨン・ブランです(2700円)。この価格帯だと、あっさりしすぎているソーヴィニヨン・ブランもあるのですが、これはバランスよく、うまみも抜群です。

シルヴァラードのソーヴィニヨン・ブラン(4000円)は、カリフォルニアのソーヴィニヨン・ブランの中でも故人的にはベンチマーク的ワインだと思っています。ニュージーランドでもフランスでもないカリフォルニアらしさがあるソーヴィニヨン・ブランで、特になめらかなテクスチャーで高級感があります。

マッジオ・ファミリーのピノ・グリージョ(2380円)。酸がしっかりあり、コクもあるワインです。

アイ・ブランド&ファミリーのアルバリーニョ(4700円)。うま味が爆発しています。

もう一つアイ・ブランド&ファミリーからシャルドネです(5900円)。果実味の強さと「コク」がしっかりあるシャルドネ。

オレゴンのイヴニングランドのシャルドネ(6800円)。古い樹のブロックを使ったものもありますが、このスタンダードのシャルドネはコスパ抜群。しっかりした酸が特徴。

なんと、このご時世に8800円から6400円と2000円以上も値下げしたという、オレゴンのポンジーのシャルドネ。オレゴンの老舗ワイナリーで2021年に、シャンパーニュのボランジェがオーナーになっています。ミネラル感あるシャルドネ。この価格は安いです。
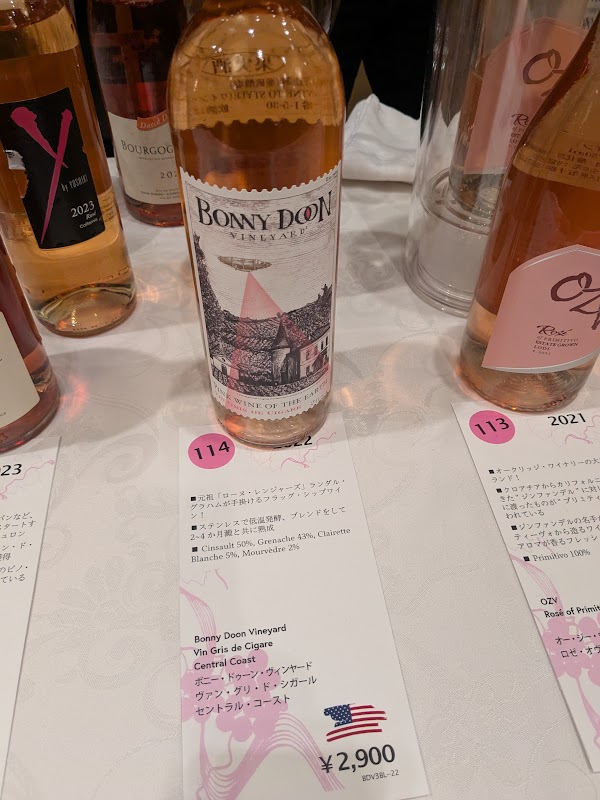
ボニー・ドゥーンのロゼワイン、「ヴァン・グリ・ド・シガール」(2900円)。ボニー・ドゥーンの「シガール」シリーズはどれを買ってもはずれはないですが、このロゼもコクがありうまい。結構しっかりタイプのロゼです。サンソー50%となかなか珍しい品種構成。

オレゴンのイヴニングランドのセカンドラベル「セイレム・ワイン・カンパニー」のピノ・ノワール(4600円)。複雑味もありワンランク上の味わい。

カリフォルニアとオレゴンでエレガントなピノ・ノワールやシャルドネを作るフェイラ。これはソノマ・コーストのピノ・ノワール(6800円)。エレガントですが、果実味もしっかりとあり美味しい。

サンタ・リタ・ヒルズのドメーヌ・ド・ラ・コートの下位ブランド(購入ブドウで造る)のサンディ。オーナーはオレゴンのイヴニングランドと同じ、ラジャ・パーとサシ・ムーアマンです。下位ブランドとはいえ、このAVA表記のピノ・ノワール(7300円)にはドメーヌ・ド・ラ・コートの自社畑のピノ・ノワールなど単一畑で使っている畑のものが入っており、中身はかなり高級。酸の高さと果実味や複雑さなどレベル高い。

同じオーナーのオレゴンのイヴニングランドのピノ・ノワール(7500円)。こちらも酸高く深みのある味わい。

オレゴンのポンジーのピノ・ノワール。これも9500円から7000円と2500円値下げしました。オレゴンらしいミネラル感のあるピノ・ノワール。

ナパのホールのメルロー(7300円)。甘やかさがあり、樽もほどよく利いたやわらかい味わいのメルロー。ナパのメルローに求められるものを体現しています。

ニューヨークのベデル・セラーズのカベルネ・フラン(4700円)。エレガント系のカベルネ・フランで、凝縮感はやや欠けていますが、少し甘やかさもあり美味しい。

パックスのシラー エル・ドラド・カウンティ(5900円)。内陸のシエラ・フット・ヒルズの標高の高いところで造られるシラー。暖かいのかと思いきや、冷涼感強く、少し青さも感じるエレガントなシラー。とてもいいです。

ジョッシュ・セラーズのジンファンデル(2600円)。2000円台のジンファンデルらしい甘やかさがありますが、それだけでなくコクもあり、バランスの良さも光ります。

フェイラのエーレン・ジョーダンが造る個人ブランド「デイ」のジンファンデル(5300円)。ジョッシュ・セラーズのジンファンデルとは大きく異なる酸がきれいなジンファンデル。凝縮感もあり緻密な味わい。

クルーズ・ワインの代表的ワイン「モンキー・ジャケット」(4900円)。カリニャンやヴァルディギエなどのブレンド。バランスよくジューシー。

クロスド・パスのレッド・ブレンド。1200円はWine to Styleのカリフォルニアワインでは最安です。少し甘やかで、酸もあり樽感も上々でコストパフォーマンス抜群です。

オーク・リッジのカベルネ・ソーヴィニヨン(2800円)。樽感しっかりあり、コクもあるワイン。コスパいいです。

ジョッシュ・セラーズのリザーブ バーボン・バレル・エイジド・カベルネ・ソーヴィニヨン(3600円)。バーボン樽で熟成させたカベルネ・ソーヴィニヨンで、樽の甘い香りが特徴的。まろやかで樽好きにはたまらないでしょう。

トゥエンティ・ロウズのリザーブ・カベルネ・ソーヴィニヨン(4500円)。この価格帯にしてはしっかりストラクチャーもあり、美味しい。

アイ・ブランド&ファミリーのペイザン オールド・ヴァイン カベルネ・ソーヴィニヨン(4600円)。上のトゥエンティ・ロウズは好対照のエレガント系カベルネ・ソーヴィニヨン。きれいで秀逸な酸が特徴的。

シルヴァラードのエステート・カベルネ・ソーヴィニヨン(8850円)。5000円クラスのカベルネとは一線を画すレベル。

ファー・ニエンテ系のブランドの一つのポスト&ビーム(11500円)。ファー・ニエンテ系列はいずれも高品質ですが、これも期待に背かないレベル。それでいて価格はファー・ニエンテ(3万円)の半分以下で、コスパは高い。

マヤカマスのカベルネ・ソーヴィニヨン(27000円)。この日のナンバーワンといってもいい素晴らしいカベルネ。クラシックスタイルを貫いており、ストラクチャーが見事。

コンティニュアム(51000円)。カベルネ・フランが35%入ったボルドー系ブレンド。フランのエレガントさがうまく表現されています。

ハンドレッド・エーカーのジェイソン・ウッドブリッジが10年ぶりに復活させたブランド「フォーチュネイト・サン」。右の「ザ・ディプロマット」(33000円)はボルドー系ブレンドで、タンニン強くスコラクチャ―のあるワイン。左の「ザ・ドリーマー」(33000円)はフレッシュでエレガントなカベルネ・ソーヴィニヨン。どちらも素晴らしい。

グリーン&レッドのジンファンデル チャイルズ・キャニオン・ヴィンヤード(7500円)。シェ・パニーズのハウスワインとして有名なワイナリーで、ジャミーでないジンファンデルを作っています。これはジューシーできれい。

グリーン&レッドのフラッグシップであるジンファンデル ヘミンウェイ・エステート・リザーブ(16500円)。しなやかさがありストラクチャー、バランス、どれをとっても一級品。

ザ・ヒルトのベントロック・ヴィンヤード ピノ・ノワール(15000円)。ザ・ヒルトはコスパが異常に高いエステートのシャルドネとピノ・ノワールを紹介することが多いですが、今回は本数の関係でそれはパスして単一畑ものを試飲。これはむちゃうまです。

ハーンのピノグリ(2850円)。フレッシュで美味しいです。

ハーンのピノ・ノワール(2850円)。エレガントできれい。果実味も秀逸でバランスがいいです。

スミス&フックのカベルネ・ソーヴィニヨン(4900円)。きれい系で美味しいカベルネ・ソーヴィニヨン。
シュラムスバーグのセカンド「ミラベル」のブリュット・ロゼ(5600円)。ロゼの華やかな色と、コクのあるボディ豊かな味わいが特徴。鶏肉などライトな肉料理にも合わせやすいスパークリング。
ユンヌ・ファム(Une Femme)という缶入りスパークリング。250mlで800円という手の出しやすい価格。「The Callie」はロゼで、ジューシーな味わい。
ボー・リバージュという、内陸のクラークスバーグにあるワイナリーのシュナンブランです(5800円)。クラークスバーグは内陸ですが、サンフランシスコ湾からの冷涼な空気が入ってくるところなので、気温は意外と低いのが特徴です。ボー・リバージュはワイン・アドヴォケイトのレビュアーであるウィリアム・ケリーのワイナリーです。とてもバランスのよい味わい。
人気ブランド「スリー・ガールズ」のソーヴィニヨン・ブランです(2700円)。この価格帯だと、あっさりしすぎているソーヴィニヨン・ブランもあるのですが、これはバランスよく、うまみも抜群です。
シルヴァラードのソーヴィニヨン・ブラン(4000円)は、カリフォルニアのソーヴィニヨン・ブランの中でも故人的にはベンチマーク的ワインだと思っています。ニュージーランドでもフランスでもないカリフォルニアらしさがあるソーヴィニヨン・ブランで、特になめらかなテクスチャーで高級感があります。
マッジオ・ファミリーのピノ・グリージョ(2380円)。酸がしっかりあり、コクもあるワインです。
アイ・ブランド&ファミリーのアルバリーニョ(4700円)。うま味が爆発しています。
もう一つアイ・ブランド&ファミリーからシャルドネです(5900円)。果実味の強さと「コク」がしっかりあるシャルドネ。
オレゴンのイヴニングランドのシャルドネ(6800円)。古い樹のブロックを使ったものもありますが、このスタンダードのシャルドネはコスパ抜群。しっかりした酸が特徴。
なんと、このご時世に8800円から6400円と2000円以上も値下げしたという、オレゴンのポンジーのシャルドネ。オレゴンの老舗ワイナリーで2021年に、シャンパーニュのボランジェがオーナーになっています。ミネラル感あるシャルドネ。この価格は安いです。
ボニー・ドゥーンのロゼワイン、「ヴァン・グリ・ド・シガール」(2900円)。ボニー・ドゥーンの「シガール」シリーズはどれを買ってもはずれはないですが、このロゼもコクがありうまい。結構しっかりタイプのロゼです。サンソー50%となかなか珍しい品種構成。
オレゴンのイヴニングランドのセカンドラベル「セイレム・ワイン・カンパニー」のピノ・ノワール(4600円)。複雑味もありワンランク上の味わい。
カリフォルニアとオレゴンでエレガントなピノ・ノワールやシャルドネを作るフェイラ。これはソノマ・コーストのピノ・ノワール(6800円)。エレガントですが、果実味もしっかりとあり美味しい。
サンタ・リタ・ヒルズのドメーヌ・ド・ラ・コートの下位ブランド(購入ブドウで造る)のサンディ。オーナーはオレゴンのイヴニングランドと同じ、ラジャ・パーとサシ・ムーアマンです。下位ブランドとはいえ、このAVA表記のピノ・ノワール(7300円)にはドメーヌ・ド・ラ・コートの自社畑のピノ・ノワールなど単一畑で使っている畑のものが入っており、中身はかなり高級。酸の高さと果実味や複雑さなどレベル高い。
同じオーナーのオレゴンのイヴニングランドのピノ・ノワール(7500円)。こちらも酸高く深みのある味わい。
オレゴンのポンジーのピノ・ノワール。これも9500円から7000円と2500円値下げしました。オレゴンらしいミネラル感のあるピノ・ノワール。
ナパのホールのメルロー(7300円)。甘やかさがあり、樽もほどよく利いたやわらかい味わいのメルロー。ナパのメルローに求められるものを体現しています。
ニューヨークのベデル・セラーズのカベルネ・フラン(4700円)。エレガント系のカベルネ・フランで、凝縮感はやや欠けていますが、少し甘やかさもあり美味しい。
パックスのシラー エル・ドラド・カウンティ(5900円)。内陸のシエラ・フット・ヒルズの標高の高いところで造られるシラー。暖かいのかと思いきや、冷涼感強く、少し青さも感じるエレガントなシラー。とてもいいです。
ジョッシュ・セラーズのジンファンデル(2600円)。2000円台のジンファンデルらしい甘やかさがありますが、それだけでなくコクもあり、バランスの良さも光ります。
フェイラのエーレン・ジョーダンが造る個人ブランド「デイ」のジンファンデル(5300円)。ジョッシュ・セラーズのジンファンデルとは大きく異なる酸がきれいなジンファンデル。凝縮感もあり緻密な味わい。
クルーズ・ワインの代表的ワイン「モンキー・ジャケット」(4900円)。カリニャンやヴァルディギエなどのブレンド。バランスよくジューシー。
クロスド・パスのレッド・ブレンド。1200円はWine to Styleのカリフォルニアワインでは最安です。少し甘やかで、酸もあり樽感も上々でコストパフォーマンス抜群です。
オーク・リッジのカベルネ・ソーヴィニヨン(2800円)。樽感しっかりあり、コクもあるワイン。コスパいいです。
ジョッシュ・セラーズのリザーブ バーボン・バレル・エイジド・カベルネ・ソーヴィニヨン(3600円)。バーボン樽で熟成させたカベルネ・ソーヴィニヨンで、樽の甘い香りが特徴的。まろやかで樽好きにはたまらないでしょう。
トゥエンティ・ロウズのリザーブ・カベルネ・ソーヴィニヨン(4500円)。この価格帯にしてはしっかりストラクチャーもあり、美味しい。
アイ・ブランド&ファミリーのペイザン オールド・ヴァイン カベルネ・ソーヴィニヨン(4600円)。上のトゥエンティ・ロウズは好対照のエレガント系カベルネ・ソーヴィニヨン。きれいで秀逸な酸が特徴的。
シルヴァラードのエステート・カベルネ・ソーヴィニヨン(8850円)。5000円クラスのカベルネとは一線を画すレベル。
ファー・ニエンテ系のブランドの一つのポスト&ビーム(11500円)。ファー・ニエンテ系列はいずれも高品質ですが、これも期待に背かないレベル。それでいて価格はファー・ニエンテ(3万円)の半分以下で、コスパは高い。
マヤカマスのカベルネ・ソーヴィニヨン(27000円)。この日のナンバーワンといってもいい素晴らしいカベルネ。クラシックスタイルを貫いており、ストラクチャーが見事。
コンティニュアム(51000円)。カベルネ・フランが35%入ったボルドー系ブレンド。フランのエレガントさがうまく表現されています。
ハンドレッド・エーカーのジェイソン・ウッドブリッジが10年ぶりに復活させたブランド「フォーチュネイト・サン」。右の「ザ・ディプロマット」(33000円)はボルドー系ブレンドで、タンニン強くスコラクチャ―のあるワイン。左の「ザ・ドリーマー」(33000円)はフレッシュでエレガントなカベルネ・ソーヴィニヨン。どちらも素晴らしい。
グリーン&レッドのジンファンデル チャイルズ・キャニオン・ヴィンヤード(7500円)。シェ・パニーズのハウスワインとして有名なワイナリーで、ジャミーでないジンファンデルを作っています。これはジューシーできれい。
グリーン&レッドのフラッグシップであるジンファンデル ヘミンウェイ・エステート・リザーブ(16500円)。しなやかさがありストラクチャー、バランス、どれをとっても一級品。
ザ・ヒルトのベントロック・ヴィンヤード ピノ・ノワール(15000円)。ザ・ヒルトはコスパが異常に高いエステートのシャルドネとピノ・ノワールを紹介することが多いですが、今回は本数の関係でそれはパスして単一畑ものを試飲。これはむちゃうまです。
ハーンのピノグリ(2850円)。フレッシュで美味しいです。
ハーンのピノ・ノワール(2850円)。エレガントできれい。果実味も秀逸でバランスがいいです。
スミス&フックのカベルネ・ソーヴィニヨン(4900円)。きれい系で美味しいカベルネ・ソーヴィニヨン。
ナパのワイナリー「シルヴァー・オーク(Silver Oak)」がCEOの交代を発表しました。オーナー兼CEOだったデイビッド・ダンカンが会長職になり、新しいCEOとしてジェレッド・フィックスを迎え入れます。フィックスはこれまで靴メーカー「トムス(Toms)」でCEOを務めていました。オーナー家以外のCEOは初となります。

シルヴァー・オークは大手プライベート・エクイティ会社のパトリコフから出資を受けたと見られていますが、デイビッド・ダンカンは、それについては口を閉ざしており、現在も家族経営の会社だとしています。
フィックス氏は大きな転身となりますが、過去にコンステレーションブランズやビームサントリーなどに勤務した経験があります。
この発表に先立ち、これまでナパヴァレーのワインメーカーだったローラ・オスクワレク(Laura Oskwarek)がワイン醸造ディレクターに就任し、ジャスティン・ヒリゴイエン(Justin Hirigoyen)」がワイン醸造担当副社長になると表明しています。ジャスティンはトゥーミーのワインメーカーを務めていましたが、これからはトゥーミーやシルヴァー・オーク、オーヴィッドなどの醸造および栽培を見ることになります。これまで11年間ワインメーカーを務めていたネイト・ワイスは3月にボーリュー・ヴィンヤード(BV)のジェネラル・マネジャ―兼シニア・ワインメーカーに就任する旨、発表されています。

シルヴァー・オークは大手プライベート・エクイティ会社のパトリコフから出資を受けたと見られていますが、デイビッド・ダンカンは、それについては口を閉ざしており、現在も家族経営の会社だとしています。
フィックス氏は大きな転身となりますが、過去にコンステレーションブランズやビームサントリーなどに勤務した経験があります。
この発表に先立ち、これまでナパヴァレーのワインメーカーだったローラ・オスクワレク(Laura Oskwarek)がワイン醸造ディレクターに就任し、ジャスティン・ヒリゴイエン(Justin Hirigoyen)」がワイン醸造担当副社長になると表明しています。ジャスティンはトゥーミーのワインメーカーを務めていましたが、これからはトゥーミーやシルヴァー・オーク、オーヴィッドなどの醸造および栽培を見ることになります。これまで11年間ワインメーカーを務めていたネイト・ワイスは3月にボーリュー・ヴィンヤード(BV)のジェネラル・マネジャ―兼シニア・ワインメーカーに就任する旨、発表されています。
2021年に公表された「フェアレスト・クリーチャー(Fairest Creature)」。トーマス・リヴァース・ブラウン、フィリップ・メルカ、ブノワ・トゥケという3人の著名ワインメーカーが、同じ畑のブドウからそれぞれワインを造るという「夢のプロジェクト」です。さらには、3人のワインからミシェル・ロランが最良の樽を選んでベスト・オブ・ザ・ベストのワインを造るという、とんでもないワインまでやってしまいます。当時もこんな記事を書いています。
ナパのトップ・ワインメーカー3人の競演!? 「夢の新プロジェクト」発進
実際のワインも高く評価されており、最初のリリースとなった2018年のヴィンテージで、ジェブ・ダナックが100点を2つ付けています。おそらく最初のヴィンテージで評論家から100点を得たのはこれが初めてだろうとのことです。2024年のプルミエ・ナパヴァレー・オークションでは最高価格で落札され、ロブ・レポートの21世紀のナパのベスト・カベルネという記事では5位にランクされています。
価格から言ってもレア度から言ってもさすがにとんでもなさすぎて、飲むことなどないだろうと思っていましたが、プロジェクトを始めたジェイソン・フー氏が来日してセミナーに参加する機会をいただきました。
まず、フェアレスト・クリーチャーというプロジェクト名ですが、シェイクスピアの最初のソネットから取ったものです。
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:
誰しも美しい者の子孫が増えて欲しいと思うもの
そうすればバラの美しさは死に絶えないから
親が時とともに艶を失っても
子がその美しい面影を伝え続けるだろう
<翻訳はシェイクスピアのソネット1 From fairest creaturesより>
ということで、美しい者のことを表しているのですが、このプロジェクトでは想像上の生き物としてのクリーチャー、特にジェイソン・フー氏の出身である中国の想像上の生き物がラベルに描かれており、ワインの名前もそこから取られています。それぞれのクリーチャーは各ワインメーカーのイメージになぞらえたものになっています。
ジェイソン・フー氏はシリコンバレーでエンジニアとして働き、マニアとしてナパはもちろんのことローヌやブルゴーニュなどのワインにのめり込んでいました。2013年には中国向けのワインのインポーターを始め、ナパのワインメーカーと知己を得るようになりました。「いいワインを造るには技術がいるが、素晴らしいワインを造るのは芸術だ」と言ったのはロバート・モンダヴィですが、ジェイソン・フー氏もエンジニアとして技術を学び、そしてフェアレスト・クリーチャーでは素晴らしいワインを造る芸術も大事にしていると語ります。
2017年にワイン造りをしたいと考えたのですが、畑やワイナリーを買うのでは面白くない。最高級のワインを造るためにはそれらを選べるポジションに身を置いておきたいということで、さまざまな畑のブドウをブレンドするスタイルを考えたとのことです。
3人のワインメーカーが口をそろえて言うのは、ジェイソン・フー氏のテイスティング能力が優れていること。彼自身もそこにはかなり自信を持っているようです。世界の素晴らしいワインを経験してきたことに裏打ちされているとフー氏はいいます。実はこのセミナーでは「61年のペトリュス」など、世界の最高レベルのワインの名前がボルドーに限らず、ローヌやブルゴーニュ、シャンパーニュなど次から次へと飛び出していました。少なくとも尋常ではないレベルのワインマニアであることは確かです。
彼が考える素晴らしいワインの条件の一つが「ウルトラバランス」。口に広がるフィーリングが3次元でどう広がるかが大事なのだそうです。2次元にしか広がらないものはバランスがとれていないとフー氏はいいます。このほか複雑さは凝縮感の一つであり、アロマがどれだけふくらむかも複雑さだと考えています。長熟性も重要な要素で、余韻がどれだけ伸びるかで想像。頑健性はフー氏が重視する要素の一つで、風味が変わっていかないこと。2時間とか3時間で変わる風味はあまり良くないといいます。頑健なワインはもっと長い時間をかけて変わっていくそうです。似た要素ではワインが長期間かけてどう変わっていくかというエボリューションも大事に考えています。
これだけいろいろな要素を評価する中で、アロマについては重視していません。アロマは変化していくというのが一つ、テクニックで操作できるというのがもう一つ。ミシェル・ロランも、フェアレスト・クリーチャーに来た最初の日に「アロマのことは忘れよう、変わっていくものだから」と言っていたそうです。
フェアレスト・クリーチャーのワインの話に入っていきます。今回は2021年のフェアレスト・クリーチャー4つに加えて、セカンドに相当する「デボーチー(Debauchee)」、熱波の影響でワインの品質が期待レベルまで上がらず、ワインメーカーごとのワインではなく全体で一つのワインにしてしまった2022年の「フロー・ステート(Flow State)」の計6本を試飲しました。
フェアレスト・クリーチャーでは現在ナパの9つの畑を使っています。ヴィンテージによっても使う畑は変わり、細かい情報は公開されていませんが、プリチャード・ヒルのマルティネズ、オークヴィルのテンチ、オークヴィル・ランチ、セント・ヘレナのセメタリー、エコトーン、クームズヴィルのコールドウェルなどナパ中心地の畑を中心にブドウを調達しています。このように銘醸地の畑のブドウをブレンドして作るのがフェアレスト・クリーチャーです。ブレンドこそがフェアレスト・クリーチャーのアセットなのだとフー氏はいいます。ボルドーの1級はブレンドのワインであり、トーマス・リヴァース・ブラウンがシュレーダーで造るフラッグシップの「オールド・スパーキー」もブレンドで最良のものを造っています。ローヌのシャプティエのフラッグシップも同様です。こうやってブレンドすることで、テロワールを超える「ファクターX」を持つようなワイン、それがフェアレスト・クリーチャーの目指すワインです。フィリップ・メルカもナパの様々なところの畑のブドウを使うことで、味にレイヤーができ、複雑味が増すんだと語っています。
使う畑には、それぞれ3つのブロックがあり、各ワインメーカーはどのブロックを使うのか選びます。斜面の上など暖かいところはトーマス・リヴァース・ブラウンが選ぶことが多く、フィリップ・メルカは冷涼なブロック、ブノワ・トゥケは中間のブロックを取ることが多いそうです。収穫もブロックごとに独立して行い、これもトーマスが一番最後になることが多いそうです。
できたワインの中からミシェル・ロランが最初に自身のブレンドに使う樽を選びます。ミシェル・ロランは年3回ナパに来るのですが、4月にヴィンテージの仕上がりを見て、5月に最終のブレンドを決めます、そして翌2月にワインがどう進化したかを確認するとのことで、これが重要なのだそうです。
残りの中から3人のワインメーカーがそれぞれ自分のワインをブレンドします。
最初のうちは「ミシェル・ロランが俺のを40%使ったよ。お前のは20%だけだったな」みたいなやり取りもあったようですが、基本的にはみなミシェル・ロランを信頼しているので、それでトラブルになるようなことはないそうです。また、そもそもブノワ・トゥケはミシェル・ロランの弟子なので、彼の言うことは絶対として聞くのですが、他の二人はそうではありません。トーマスはときどきミシェル・ロランのアドバイスを聞いてブレンドすることもありますが、フィリップ・メルカはアドバイスを聞くこともないし、ミシェル・ロランがメルカにアドバイスすることもないとか。
ちょっと脱線しましたが、3人のワインメーカーがワインをブレンドした後にもかなりのワインが残ります。そこからミシェル・ロランがブレンドして作るのが、セカンドワインの「Debauchee(デボシェ、ディボーチ)」で放蕩息子という意味があります。生産量は4000本程度。ラベルは3種類あり、3本セットで販売していますが、中身は全部一緒です。ラベルは毎年変わり、2021年はウォルフォードという女性向けのストッキングなどを販売している会社とコラボしていて、パッケージにはストッキングが1足同梱されています。Kei Meguroという日本人のアーティストが描いた鉛筆画のラベルになっています。国内未発売。

2021年のディボーチはかなりタンニン強く固さを感じます。酸も強め。時間が経つにつれて、花やおしろいなど、華やかさが出てきます。やや時間がかかるワインという印象でした。今飲むなら90点
次のワインは2022年のFlow Stateというワイン。前述のように2022年はこのワインしか造っていません。9月10日前後に猛烈な熱波が来て、ブドウの成長がストップしてしまいました。フェアレスト・クリーチャーとしてこれまでの形で各ワインメーカーが期待するレベルのワインを造るのが難しく、選果の段階で半分のブドウを落とし、またブレンドをすることでなんとかクオリティを保ったといいます。生産量も6000本にとどまりました(通常は各ワインメーカー3000本+マグナム500本)。ラベルは耳が1本しかない3匹のウサギがその耳をシェアする形で円をなしています。オリジナルはインドのものらしいです。
チョコレートや青果実に少しレッド・チェリーの風味が加わります。タンニン強く、タイトなワイン。濡れた石など少し鉱物的な印象。92点
いよいよ、2021年の三つのワインのテイスティングです。
最初はブノワ・トゥケのシン・フィン(ファイン)(Sine Fine)。ラベルは鳥のデザインですが体と羽根と尻尾は一つで頭が2つあります。2羽の鳥があまりにも愛し合って体が一つになってしまったという、愛の象徴だそうです。ブノワ・トゥケが非常に情熱を持ってワインを造る人であり、そのキャラクターが合うと考えたとのこと。また、最初のヴィンテージのときにブノワ・トゥケが結婚したのも理由の一つだそうです。
カカオやモカのフレーバー、花の香り、シルキーなタンニンで酸は高い。総じてバランスよくしなやかなテクスチャーが心地いいレベルの高いワイン。96点
次はトーマス・リヴァース・ブラウンのペリフェリオス(Perihelios)。角が生えたクジラが海から飛び出ている様子がラベルに描かれています。中国の荘子の著書の中に、鯤(クン)という巨大な魚が鵬(ホウ)という鳥に変身するという話があるところから造ったものだとのこと。信じられないほどの強さと大きさをトーマスのワインになぞらえています。
ブルーベリーやブラックベリー、チョコレート。極めてしなやかで緻密なテクスチャー。タンニンは強く大柄なワイン。パワーと繊細さが共存しており、長熟性も感じられる。97点
3本目はフィリップ・メルカのポリスプライン(Polyspline)。9尾のキツネのラベルです。日本では9尾のキツネというと魔力を持っているような、どちらかというと危険な存在にとらえられがちですが、中国では幸運や知恵の象徴となっています。
素晴らしくバランスよく、酸とタンニンがきれいで、余韻も極めて長い。ハーブやブラックベリーのアロマ。完成度の高いカベルネ・ソーヴィニヨン。99点
フー氏は立場上、どのワインが好きかは基本的に言わないのですが、2021年に関してはフィリップ・メルカ版が一番好きだとのこと。ストラクチャーがあって大きなワインだと感じているそうです。
また、フー氏によると3つのワインに共通するのはタンニンマネジメントが素晴らしいこと。タンニンマネジメントは細かい調整が必要ですが、何よりも畑で健康なブドウを育て、それをいつ収穫するかが一番重要だといいます。収穫したあとで、もっとこうしたいと思ってもほとんどできないのです。秘密兵器のようなものがあるわけではなくブドウ栽培からワインを造り上げるところまで一つひとつの選択をきちんとやっていくことがグレートなワインを作る上で必要です。
最後のワインはトリニセロス(Triniceros)。前述のように3人のワインメーカーが醸造した樽からベストのものをミシェル・ロランが選んでブレンドしたワインです。ミシェル・ロランは最初にこのプロジェクトを依頼されたとき、ワインメーカーが自分を殺したくなるのではないかと心配だったと、冗談を言っていました。
このワインはマグナムのみで500本しか作られません。トリニセロスというのは3本の角という意味で、3人のワインメーカーの象徴となっています。ラベルが貼ってあるのではなくボトルにエッチングが施されており、神話の「麒麟」に由来したクリーチャーのイメージが入っています。眼のところにはフー氏の誕生石であるアクアが入っているという凝りよう。
これだけはカベルネ・ソーヴィニヨン100%で造られています。ちなみに、フィリップ・メルカは毎年プティ・ヴェルドを少し入れます。彼はプティ・ヴェルドの扱いに長けており、「マスターオブ・プティ・ヴェルド」と言われているそうです。トーマスはカベルネ100%のことが多いのですが、2023年はカベルネ・フランを少し入れたとのこと。
2021年のトリニセロス、フー氏は「3人のワインメーカーが造ったワインとは別次元のワインで完璧な仕上がりを見せていると思う」とのこと。実際に飲んでみると本当に素晴らしい。先ほどのメルカのワインも完璧なバランスを見せており、100点クラスのクオリティがあると感じましたが、トリニセロスはその上を行くスケールの大きさがあります。テイスティングコメントを書くのは野暮な感じもしますが、果実味は強く、ブルーベリーなど青果実を感じます。タンニンのきめ細かさが素晴らしい。余韻長くバランスもよく非の打ち所がないワインでした。

さて、セミナーの後、ボトルの写真を撮っているときに、ボトルのネックに文字が書かれているのに気が付きました。文字といっても象形文字のような、古い字体です。フー氏に聞いてみたところ、中国の詩の一節が書かれているそうです。実はラベルにも絡んでいて面白い内容だったので、追加で紹介します(おそらくこれまでどこにも書かれていないと思います)。
ブノワ・トゥケの「シン・ファイン」のネックには白居易の「天长地久有时尽」という一節。これは「世界にはいつか終わりが来る」という意味です。ボトルには書かれていませんが、その次には「しかし愛は永遠だ」と続きます。これがラベルの愛するあまり体がつながってしまった鳥につながりますし、ワインの名前の「Sin Fine」(ラテン語で終わりがないという意味)にもつながります。
トーマス・リヴァース・ブラウンの「ペリヘリオス」に書かれているのは李白の「扶摇直上九万里」という一節。意味は「直ちに9万里の上空に駆け上がる」ということ。ワインの名前のPeriheliosはPerihelion(近日点)から派生した語で、近日点とは地球などの惑星が太陽を回る軌道の中で一番太陽に近いところを指します。これも上空に駆け上がるということから連想したものになっています。
フィリップ・メルカの「ポリスプライン」には「江月何年初照人」と書かれています。「長江の月が初めて人を照らしたのはいつのことだっただろう」といった意味です。これだけはワインの名前とは直接結びついていないようです。 スプライン(spline)という単語は、線/曲線を足して連続した不規則な曲線形状を作ることに関係しており、ポリ(poly)は多数の意味です。この名前はメルカのワインのエレガンスと関連していて、緩やかで長いカーブの感触と言った意味合いになります。
マグナムのトリニセロスは字体も他の三つと異なっています。漢書に書かれている「天之骄子不以小礼而自烦」という一節で「選ばれし者は小さな礼儀に煩わされることはない」という意味です。これは中国の胡民族について語ったもので、「胡」はフー氏の漢字表記です。こんな型破りなプロジェクトを始めたことを示唆しているようです。
最後に、フェアレスト・クリーチャーのワイン、極めてレアで買うのも100万円以上が必要と、ものすごく敷居が高いですが、いくつかのレストランで飲むことができます。日本では青山と六本木のウルフギャングステーキハウスでリストに載っているとのことです。
コンステレーション・ブランズが、ザ・ワイン・グループにいくつかのワインのブランドを売却しました。1カ月ほど前には、コンステレーションはワインから撤退するのではないかといった観測記事も出ていましたが、結果的には安価なブランドを売却して、プレミアムなブランドは保持することになっています。
売却したブランドは、ウッドブリッジ、シミ(SIMI)、ロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクション、メイオミ(Meiomi)、Jロジェ、クックスです。一方、ロバート・モンダヴィ・ワイナリー、ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニー、主レーターなど高価格帯のブランドはコンステレーションに残ります。ロバート・モンダヴィ・ワイナリーと、ロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクションは別々の会社が持つことになりました。
また、ブランドだけでなく、ローダイとモントレー、ソノマのヒールズバーグにある醸造設備や6600エーカーの所有あるいはレンタルしているブドウ畑もザ・ワイン・グループに移管しています。
売却したブランドは、ウッドブリッジ、シミ(SIMI)、ロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクション、メイオミ(Meiomi)、Jロジェ、クックスです。一方、ロバート・モンダヴィ・ワイナリー、ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニー、主レーターなど高価格帯のブランドはコンステレーションに残ります。ロバート・モンダヴィ・ワイナリーと、ロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクションは別々の会社が持つことになりました。
また、ブランドだけでなく、ローダイとモントレー、ソノマのヒールズバーグにある醸造設備や6600エーカーの所有あるいはレンタルしているブドウ畑もザ・ワイン・グループに移管しています。

トランプ米大統領が「解放の日」で関税政策を公表してから1週間経ちました。3月にはEUからのアルコールに対して200%の関税をかけるという脅しとともに「これは米国のワインとシャンパンのビジネスにとって素晴らしいことだ」とSNSに投稿しましたが、現状はアルコールを直接ターゲットにした関税ではなく、EUに一律20%の関税をかけるなどになっています。また、カナダでは、すでに報復として米国のアルコール飲料を店頭からはずしており、実質的にカナダ市場は閉じた形になっています。
これらを受けて、カリフォルニアワイン協会のロバート・コッホCEOは4月2日に次のように表明しています。
ワイン産業は人々を結びつけ、経済的価値を高め、全国の家族や農家の勤勉さと伝統を反映しています。
本日の新たな関税の発表は、米国のワイナリーがカナダへの再進出を困難にするだけです。カナダはこれまで最も重要な輸出市場でした。3月初旬、カナダは米国産ワインを全て棚から撤去し、販売を阻止し続けています。この紛争が長引くにつれ、業界がすでに大きな圧力にさらされている時期に経済不安が生じています。
これは単なる貿易の問題ではありません。人々、生活、そして何世代にもわたって築き上げられた農業の成功物語の問題です。私たちの産業が混乱すると、その影響はワイナリーをはるかに超えて、農場労働者、流通業者、中小企業、レストラン、そして全国のコミュニティ全体に及ぶのです。
ナパヴァレー・ヴィントナーズの顧問弁護士兼業界関係担当シニアディレクターのミシェル・ノビ氏は、ワインを貿易紛争に利用すべきではないと語り、カリフォルニアワイン協会の表明にも賛同の意を表しています。
実際、カナダは米国産ワインの輸出先の35%を占めていて、ここが閉ざされたことは大きなデメリットになっています。
特にカナダへの輸出が多いワシントン州はかなり危機的な状況に陥っている可能性があります。そうでなくても、ここ数年余剰ワインの問題に苦しんでおり、それに追い打ちをかけることになっています。
今回の関税は米国が輸入品にかけるものなので、日本などへの輸出品の価格にいますぐ影響することはありませんが、米国においてボトルや樽など、資材の多くが値上がりするのは確実であり、ワイン価格に転嫁されていくでしょう。
また、米国内では輸入品のアルコール類がすべて値上がりすることになります。米国製品のシェアが高い西海岸ではそれほど大きな影響はないかもしれませんが、欧州産のワインが多いニューヨークなど東海岸では値上がりの影響は大きいでしょう。それによって、カリフォルニアなどのワインの販売が伸びるかと言えば、そうではないと思います。今回の問題がなくても、近年はアルコール離れが進んでおり、特にZ世代では全く飲まない人や、グラス1杯だけなど、制限を付けて飲む人が増えています。アルコールの値段が上がることによって、ノンアルコール飲料へのシフトがさらに進んでいくでしょう。それはワイン業界全体にとって、後戻りできないほどの大きなダメージになってくると思います。
ナパのロバート・ビアーレ・ヴィンヤーズ(Robert Biale Vineyards)から創設者のボブ・ビアーレと妻のウェンディが来日し、ワイン会が開かれました。ロバート・ビアーレ、国内輸入はありますが、現在のインポーターとの契約が切れるため、新しいインタポーターを募集中だそうです。
ロバート・ビアーレはナパを代表するジンファンデルの生産者。ジンファンデルの古木の畑の維持にも力を入れており、古木の畑を登録するヒストリック・ヴィンヤード・ソサイエティのボードメンバーにも、リッジやターリー、ベッドロックなどと名を連ねています。

ウェルカムでいただいたのは2024年のROSATOというロゼ。サンジョヴェーゼが主体でジンファンデルをブレンドしています。全房で優しくプレスしたロゼで、イチゴなどのチャーミングな味わい。ビアーレ家はイタリアの出身ということで、イタリア系品種に思い入れがあるそうです。
次のワインは唯一の白。クレメンティーナ(Crementina)というワインで「Greco Biancco」という品種を使っています。これもイタリア系品種です。ビアーレの自社畑はオーク・ノールにありますが、プティ・シラーのブロックの状態が悪く、植え替えでごくわずかだけこの品種を育てています。
3つめからいよいよジンファンデルです。
ロバート・ビアーレの代名詞的ワインである「ブラック・チキン(Black Chicken)」。ボブの父親のアルドは、1929年生まれ。まだ少年だった1942年に父親が事故で亡くなってしまいました。当時、すでにナパに畑があり、ジンファンデルやプルーン、クルミなどを育てていました。ブドウは他のワイナリーに販売していたのですが、お金を少しでも多くかせぐために、アルドがワインを造って売ることを提案、納屋でワインを造り始めました。ただ、このワイン造りは許可を得ていないものだったので、内緒で取引をする必要があり、電話で「ブラック・チキン」と注文するのがワインのことだと決めたのでした。このコードネームをビアーレのワインの名前に付けました。今も自社畑のブドウを中心に、近隣の契約畑のブドウを加えてワインを造っています。
ワイン造りは、手作業で選果したあと、オープントップのファーメンターで2~4日低温で浸漬し、培養酵母で発酵。1日2~3回パンチダウン。発酵終了後は20%新樽で14カ月熟成しています。樽はブルゴーニュスタイルの樽を使っています。ボルドー系の樽と比べて樽材が厚く、空気を通しにくいという特徴があります。樽材が薄い方がタンニンは和らぐので、逆にストラクチャーを保つということのようです。

2016年のブラック・チキン・ジンファンデルは濃厚で、ザクロやブラック・チェリー、ブラックペッパー。ココナッツやハーブ。柔らかな酸があり、濃いだけではない良さがあります。
次は2022年のブラック・チキン・ジンファンデル。樽の甘い香りを感じますが、アメリカン・オークではなくフレンチ・オークを使っています。2016年よりも熟度高く、プラムや甘草、ヨーグルトのようなまろやかさがあります。
三つ目のジンファンデルはクームズヴィルのR.W.ムーアという畑のもの。ヴィンテージは2022年。「もっとワインを楽しもう」というのがコンセプトだそうです。チョコレートやプラム、レッド・チェリーなど。完熟した果物の美味しさを感じるワインです。
ジンファンデルの後はプティ・シラー(プティト・シラー)です。プティ・シラーはジンファンデルと並んで20世紀前半には一番よく植えられていた品種。濃厚でしっかりとした骨格のあるワインになります。ジンファンデルのブレンド用に使われることも多い品種です。個人的にも推しブドウ品種の一つ。
2015年はラザフォードの畑のプティ・シラー。タニックで超濃厚、プラム、チョコレート、ベーキング・スパイス。酸もあり、濃厚ワイン好きにはたまらないワインでしょう。理想的な年だったとのこと。
もう一つは2022年。この年はラザフォードの畑に加えて自社畑のプティ・シラーとナパのチャイルズ・ヴァレーのブドウを加えています。しっかりしたタンニンと酸。チョコレートケーキのような濃厚さと甘やかさ。
久しぶりに美味しいプティ・シラーを堪能しました。
この日のレストランはパレスホテルのグランド・キッチン。2023年にナパヴァレー・ワインのソムリエ・アンバサダーに選ばれた山田琢馬君がソムリエをしているレストランです。この日の料理は、琢馬君がビアーレのワインに合うようにシェフと考えたオリジナル・メニュー。

ジンファンデルにブリを合わせるなど、斬新ですがソースの味わいでしっかりと合っていておいしい。プティ・シラーには敢えて、料理ではなくチョコレートケーキを合わせるというのも良かったです。




ちなみに今回の来日はZAP(ジンファンデル・アドヴォケイツ・アンド・プロデューサーズ)主催のクルーズツアー(東京発着で2週間かけてアジアを回る)のためでした。
Zinfandel Advocates & ProducersJapan Spotlight Wine CruiseNow Sailing - Food & Wine Trails
ZAPがこんなツアーやっているんですね。知らなかったです。
ロバート・ビアーレはナパを代表するジンファンデルの生産者。ジンファンデルの古木の畑の維持にも力を入れており、古木の畑を登録するヒストリック・ヴィンヤード・ソサイエティのボードメンバーにも、リッジやターリー、ベッドロックなどと名を連ねています。
ウェルカムでいただいたのは2024年のROSATOというロゼ。サンジョヴェーゼが主体でジンファンデルをブレンドしています。全房で優しくプレスしたロゼで、イチゴなどのチャーミングな味わい。ビアーレ家はイタリアの出身ということで、イタリア系品種に思い入れがあるそうです。
次のワインは唯一の白。クレメンティーナ(Crementina)というワインで「Greco Biancco」という品種を使っています。これもイタリア系品種です。ビアーレの自社畑はオーク・ノールにありますが、プティ・シラーのブロックの状態が悪く、植え替えでごくわずかだけこの品種を育てています。
3つめからいよいよジンファンデルです。
ロバート・ビアーレの代名詞的ワインである「ブラック・チキン(Black Chicken)」。ボブの父親のアルドは、1929年生まれ。まだ少年だった1942年に父親が事故で亡くなってしまいました。当時、すでにナパに畑があり、ジンファンデルやプルーン、クルミなどを育てていました。ブドウは他のワイナリーに販売していたのですが、お金を少しでも多くかせぐために、アルドがワインを造って売ることを提案、納屋でワインを造り始めました。ただ、このワイン造りは許可を得ていないものだったので、内緒で取引をする必要があり、電話で「ブラック・チキン」と注文するのがワインのことだと決めたのでした。このコードネームをビアーレのワインの名前に付けました。今も自社畑のブドウを中心に、近隣の契約畑のブドウを加えてワインを造っています。
ワイン造りは、手作業で選果したあと、オープントップのファーメンターで2~4日低温で浸漬し、培養酵母で発酵。1日2~3回パンチダウン。発酵終了後は20%新樽で14カ月熟成しています。樽はブルゴーニュスタイルの樽を使っています。ボルドー系の樽と比べて樽材が厚く、空気を通しにくいという特徴があります。樽材が薄い方がタンニンは和らぐので、逆にストラクチャーを保つということのようです。
2016年のブラック・チキン・ジンファンデルは濃厚で、ザクロやブラック・チェリー、ブラックペッパー。ココナッツやハーブ。柔らかな酸があり、濃いだけではない良さがあります。
次は2022年のブラック・チキン・ジンファンデル。樽の甘い香りを感じますが、アメリカン・オークではなくフレンチ・オークを使っています。2016年よりも熟度高く、プラムや甘草、ヨーグルトのようなまろやかさがあります。
三つ目のジンファンデルはクームズヴィルのR.W.ムーアという畑のもの。ヴィンテージは2022年。「もっとワインを楽しもう」というのがコンセプトだそうです。チョコレートやプラム、レッド・チェリーなど。完熟した果物の美味しさを感じるワインです。
ジンファンデルの後はプティ・シラー(プティト・シラー)です。プティ・シラーはジンファンデルと並んで20世紀前半には一番よく植えられていた品種。濃厚でしっかりとした骨格のあるワインになります。ジンファンデルのブレンド用に使われることも多い品種です。個人的にも推しブドウ品種の一つ。
2015年はラザフォードの畑のプティ・シラー。タニックで超濃厚、プラム、チョコレート、ベーキング・スパイス。酸もあり、濃厚ワイン好きにはたまらないワインでしょう。理想的な年だったとのこと。
もう一つは2022年。この年はラザフォードの畑に加えて自社畑のプティ・シラーとナパのチャイルズ・ヴァレーのブドウを加えています。しっかりしたタンニンと酸。チョコレートケーキのような濃厚さと甘やかさ。
久しぶりに美味しいプティ・シラーを堪能しました。
この日のレストランはパレスホテルのグランド・キッチン。2023年にナパヴァレー・ワインのソムリエ・アンバサダーに選ばれた山田琢馬君がソムリエをしているレストランです。この日の料理は、琢馬君がビアーレのワインに合うようにシェフと考えたオリジナル・メニュー。
ジンファンデルにブリを合わせるなど、斬新ですがソースの味わいでしっかりと合っていておいしい。プティ・シラーには敢えて、料理ではなくチョコレートケーキを合わせるというのも良かったです。
ちなみに今回の来日はZAP(ジンファンデル・アドヴォケイツ・アンド・プロデューサーズ)主催のクルーズツアー(東京発着で2週間かけてアジアを回る)のためでした。
Zinfandel Advocates & ProducersJapan Spotlight Wine CruiseNow Sailing - Food & Wine Trails
ZAPがこんなツアーやっているんですね。知らなかったです。
カリフォルニアワイン協会が、ワインが当たるインスタグラム・キャンペーンを開始しています。
カリフォルニアワイン協会のインスタアカウントをフォローし、5月31日までにワインを楽しんでいる様子をインスタグラムにアップ。その際に上記インスタアカウントをタグ付け(投稿中に @calwinesjp を入れる)するだけです。
店舗のキャンペーンは同期間、関東と近畿で開催されており、それらの店舗での飲食や、そこで購入したワイン、関東・近畿の郷土料理や名所などを投稿に含めると、ポイントが高くなるそうです。
関東の参加店はこちら カリフォルニアワイン・プロモーション in 関東|カリフォルニアワイン協会
近畿の参加店はこちら カリフォルニアワイン・プロモーション in 近畿|カリフォルニアワイン協会
カリフォルニアワイン協会さん、今回のキャンペーンの情報は、インスタのこの投稿と、インスタのプロフィールからのキャンペーンへのリンクでしかたどり着けません。サイトのトップページからも行けないというのは、かなり厳しいです。地域ごとのキャンペーンは昨年11月からやっていたようですが、それも今回初めて知りました。もうちょっときちんとプロモーションしてほしいと思います。
カリフォルニアワイン協会のインスタアカウントをフォローし、5月31日までにワインを楽しんでいる様子をインスタグラムにアップ。その際に上記インスタアカウントをタグ付け(投稿中に @calwinesjp を入れる)するだけです。
店舗のキャンペーンは同期間、関東と近畿で開催されており、それらの店舗での飲食や、そこで購入したワイン、関東・近畿の郷土料理や名所などを投稿に含めると、ポイントが高くなるそうです。
関東の参加店はこちら カリフォルニアワイン・プロモーション in 関東|カリフォルニアワイン協会
近畿の参加店はこちら カリフォルニアワイン・プロモーション in 近畿|カリフォルニアワイン協会
カリフォルニアワイン協会さん、今回のキャンペーンの情報は、インスタのこの投稿と、インスタのプロフィールからのキャンペーンへのリンクでしかたどり着けません。サイトのトップページからも行けないというのは、かなり厳しいです。地域ごとのキャンペーンは昨年11月からやっていたようですが、それも今回初めて知りました。もうちょっときちんとプロモーションしてほしいと思います。
ワイン・スペクテーターのナパヴァレー支局長を長年務めていたジェームズ・ラウビー氏が3月22日、亡くなりました。死因は明らかにされていませんが、急死だったようです。73歳でした。

ジェームズ・ラウビーは、1983年にワイン・スペクテーターの編集者になり、ワイン・スペクテーター誌におけるカリフォルニアワインのレビューを一手に引き受けていました。濃厚で果実味豊かなスタイルのワインが全盛となった2000年代初頭においては特にロバート・パーカーと並んで、そのスタイル確立に大きな影響を与えました。ナパのカベルネもさることながら、個人的にはサイドウェイからのピノ・ノワールのブームにおいて、当時のコスタ・ブラウンのような酸が低くて濃厚なピノ・ノワールに高得点やワイン・オブ・ザ・イヤーにおける高い順位を与えたことが、「シラーのようなピノ・ノワール」と言われるピノ・ノワールの全盛につながったと思っています。
当時は米国ではまだ、酸が多くてデリケートなスタイルのピノ・ノワールを受け入れる土壌がなく、こういった濃厚スタイルを経てアメリカ人のテーストも徐々によりピノ・ノワールらしいスタイルを受け入れるようになったのだと思います。
レビューの点数だけでなく、記事でも大きな影響を与えてきました。特に印象に残っているものでいうと2000年4月30日号の「カルト・ワイン」特集。それまでもカルト・ワインという言葉は使われていましたが、ここでより明確にそのブームが形作られたと言っていいでしょう。表紙はスクリーミング・イーグル創設者のジーン・フィリップスさんでした。

業界の中心にありながら、業界に流されない人でもありました。100点法の採点の点数が各メディアでインフレ化していく中、ワイン・スペクテーターは今でもほとんど100点を付けないことで知られています。また、業界で物議を醸したテーマとしてはブショネの問題があります。ラウビーがブショネを指摘したワイナリーにはボーリュー・ヴィンヤード(BV)、ハンゼル、ガロ・オブ・ソノマ、シャトー・モンテレーナ、ピラー・ロックなどがあります。ブショネの原因物質であるTCAの検知には個人差が大きくあると言われており、ラウビーは極めて敏感だったようです。モンテレーナのブショネの場合、ラウビー以外はほとんどブショネと思わないレベルだったため、ワイナリーを糾弾することが本当にいいのかという話も出ていました。ですが、結局はワイナリー側が徹底した対策を行うことで、改善していったわけで、長い目で見れば彼の指摘は意味があったのだと思います。
2019年にスペクテーターからは引退しましたが、その後もナパに住んでいました。
ご冥福をお祈りします。

ジェームズ・ラウビーは、1983年にワイン・スペクテーターの編集者になり、ワイン・スペクテーター誌におけるカリフォルニアワインのレビューを一手に引き受けていました。濃厚で果実味豊かなスタイルのワインが全盛となった2000年代初頭においては特にロバート・パーカーと並んで、そのスタイル確立に大きな影響を与えました。ナパのカベルネもさることながら、個人的にはサイドウェイからのピノ・ノワールのブームにおいて、当時のコスタ・ブラウンのような酸が低くて濃厚なピノ・ノワールに高得点やワイン・オブ・ザ・イヤーにおける高い順位を与えたことが、「シラーのようなピノ・ノワール」と言われるピノ・ノワールの全盛につながったと思っています。
当時は米国ではまだ、酸が多くてデリケートなスタイルのピノ・ノワールを受け入れる土壌がなく、こういった濃厚スタイルを経てアメリカ人のテーストも徐々によりピノ・ノワールらしいスタイルを受け入れるようになったのだと思います。
レビューの点数だけでなく、記事でも大きな影響を与えてきました。特に印象に残っているものでいうと2000年4月30日号の「カルト・ワイン」特集。それまでもカルト・ワインという言葉は使われていましたが、ここでより明確にそのブームが形作られたと言っていいでしょう。表紙はスクリーミング・イーグル創設者のジーン・フィリップスさんでした。

業界の中心にありながら、業界に流されない人でもありました。100点法の採点の点数が各メディアでインフレ化していく中、ワイン・スペクテーターは今でもほとんど100点を付けないことで知られています。また、業界で物議を醸したテーマとしてはブショネの問題があります。ラウビーがブショネを指摘したワイナリーにはボーリュー・ヴィンヤード(BV)、ハンゼル、ガロ・オブ・ソノマ、シャトー・モンテレーナ、ピラー・ロックなどがあります。ブショネの原因物質であるTCAの検知には個人差が大きくあると言われており、ラウビーは極めて敏感だったようです。モンテレーナのブショネの場合、ラウビー以外はほとんどブショネと思わないレベルだったため、ワイナリーを糾弾することが本当にいいのかという話も出ていました。ですが、結局はワイナリー側が徹底した対策を行うことで、改善していったわけで、長い目で見れば彼の指摘は意味があったのだと思います。
2019年にスペクテーターからは引退しましたが、その後もナパに住んでいました。
ご冥福をお祈りします。
ナパのガーギッチ・ヒルズから創設者の故ミイェンコ「マイク」・ガーギッチの娘で現社長のヴァイオレット・ガーギッチさんが来日され、ディナーに参加しました。

ヴァイオレットさん。空手をやっているせいか、姿勢がいいです。
マイク・ガーギッチは今のクロアチアの出身。2歳でワインを飲み始めたといいます(水が衛生的でないので、消毒代わりに水にワインを混ぜて飲むそう)。3歳のときには実家でのワイン造りを手伝っていたとか。ただ、実家は貧乏で8年生を超えて進学したのは11人兄弟の中でマイク一人だったそうです。
ザグレブ大学でワイン造りを勉強し、サバティカルで米国に行ったことがある教授から「米国は夢を追えるところ」、「ナパはパラダイス」と聞き、米国移住を志します。
入国許可がなかなか得られず、カナダでしばらく働いてからようやく米国への許可を得て1958年にナパに着きました。ちなみにマイクのトレードマークのベレー帽は大学時代に傘が買えずに雨除けにかぶっていたのがきっかけでした。
ナパではBVのアンドレ・チェリチェフや当時の有名ワイナリーだったスーヴェランのリー・スチュワートの下で働き、ロバート・モンダヴィで職を得ました。そこで作った1969年のカベルネ・ソーヴィニヨンがベストカベルネ・ソーヴィニヨンに選ばれ、モンダヴィがこれで有名になったといいます。これがきっかけになり、当時再建を始めたばかりのシャトー・モンテレーナのジム・バレットがカベルネを造るためにマイクを雇ったのでした。ただ、カベルネ・ソーヴィニヨンを造るのには時間もお金もかかり、最低でも5年間はかかるという計画で、マイクがキャッシュ・フローのためにシャルドネを造ることを提案したのでした。その2ヴィンテージ目の1973年のシャルドネが、「パリスの審判」で一位になったのでした。
また、この当時、マイクのイタリア人の友人がガレージで作ったカベルネ・ソーヴィニヨンとジンファンデルを飲ませてもらったものが非常に素晴らしく、「素晴らしいブドウを手に入れて自然に作ったワインが一番いい」というフィロソフィーを持つようになりました。
パリスの審判の1年後にはコーヒーの会社を経営するオースティン・ヒルズがパートナーとなり、ガーギッチ・ヒルズを創設しました。最初のシャルドネはシカゴで1980年5月に開かれたシャルドネ・ショーダウンにおいて221種類の中で1位になり、キングオブシャルドネと呼ばれるようになりました。
ガーギッチ・ヒルズのこだわりの一つが畑。2003年にはすべて自社畑のブドウだけでワインを造るようになりました。1986年にクロアチアからやってきた甥のイーヴォが畑を見るようになり、彼の薦めで2000年からオーガニックな栽培に切り替え、2006年には認証を取りました。認証は取らなくても良かったのですが、自然派スーパーのホールフーズが、ロゴを入れたいというので認証を取りました。あくまでもいいブドウを造るのが目的なので、マーケティングのためではないと言います。認証に必要なレベルを大きく超えて実践しているので、認証機関が驚くほどだったとのこと。
ビオディナミは2003年に畑のウイルスにやられたブロックを植え替えるときに始めました。先駆者としてい知られるロワールのニコラ・ジョリーからそのやり方を聞いたマイクは、クロアチアの畑でやっていた農法と似ていると感じて、自社畑に導入しました。するとすぐに畑の状態が良くなり驚いたといいます。
2018年には再生可能型有機栽培「ROC」を始め、2023年に認証を取得しました。従来のオーガニックやビオディナミでは生きている土壌を作ることはできないと感じて、この方法を始めました。この農法の大きな特徴の一つが、基本的に土地をなるべく耕さないこと。土地を耕すと微生物を破壊し、二酸化炭素が空気中に放出されるためです。また、耕すことで土が流出するなどの問題も起こります。ROCを始めてから土壌の中の有機物がすぐに1%くらい増えたそうで、普通はそれだけ増えるのには何年もかかるので、UCデーヴィスの研究者も驚いたとのことでした。
耕すのがいいのか、耕さない方がいいのかについては、現状意見が分かれるところでもあります。例えばスクリーミング・イーグルでは耕す方がいいと思っているとのことでした。一方、ガーギッチ・ヒルズでは耕さない方がいいという、強い確信があります。2022年に1週間以上40数度の気温が続く熱波が来たとき、隣の耕している畑では温度が70度にもなったのに対し、ガーギッチの畑は39度までしか上がりませんでした。土の温度が70度にもなると土の中の微生物も死んでしまいます。また、同じ年、1日に250mmもの雨が降ったときに、隣の畑は水浸しになりましたが、ガーギッチの畑は大丈夫でした。下の写真にあるように、実際に土壌はふかふかで絨毯の上を歩いているかのようだとのことです。こういった実証を経て自信を持ってROCに取り組んでいます。ヴァイオレットさんによると、上記の状態を見たドミナス(ガーギッチのヨントヴィルの畑と隣り合わせの畑です)も、最近ROCに取り組み始めているそうです。
ガーギッチではこのようなROCによる状態の変化を専門の研究者を置いて調べてレポートする体制を取っています。ROCに最も熱心に取り組んでいるワイナリーの一つといっていいでしょう。

ナパでは多くの場合、樹齢が20年を過ぎると植え替えをしています。ただ、ブドウの樹もできるだけ長く生きるのが自然であり、ROCのアプローチが自然だと感じています。植え替えはコストがかかるということ以外に、樹齢が長いとブドウの味に複雑性が出てくるためです。
植え替えもブロック単位で行うのではなく1本ずつ行っています。現在、シャルドネの畑の植え替えをしているのですが、これはAxR1というフィロキセラへの耐性が低い台木を使っており、樹勢が落ちてきてしまっています。このときにすべてを植え替えるのではなく、1本単位に植え替えをします。「ディープ・イリゲーション」という土中の深いところに灌漑をして、根を下に伸ばすようにします。こうすると下の方にある砂地の土壌に根が届き、フィロキセラにやられないようになります。これはマイクが考えた方法で、今も80年代の木が残っているのだそうです。ジンファンデルでも1889年の樹が残っているといいます。

ワインの話に移ります。ガーギッチではバランスが取れてエレガントでフードフレンドリーなワインを作り続けています。最初のワインはフュメ・ブラン。先ほど、モントレーナのキャッシュフローのワインがシャルドネだったという話を紹介しましたが、ロバート・モンダヴィにとってはソーヴィニヨン・ブランがキャッシュフローのワインで、樽を使ってフュメ・ブランと名付けたものが大ヒットしました。このモンダヴィのフュメ・ブランを手掛けたのもマイク・ガーギッチでした。ガーギッチ・ヒルズでは、モンダヴィに敬意を表す意味を込めて、フュメ・ブランの名前を使い続けています(ただ、最近ではフュメ・ブランといっても知らない人も増えたのでソーヴィニヨン・ブランと併記しています)。
ガーギッチのフュメ・ブランはナパの南端のAVAであるロス・カーネロスと、カーネロスよりもさらに海に近く冷涼なアメリカン・キャニオンの畑のブドウを使っています。樽発酵樽熟成をしており、通常の樽のほか、フードルと呼ぶ大樽も使っています。ヴィンテージは2021年
酸が豊かで柑橘系のさわやかさとミネラル感、黄色い花の香り。樽香はほとんど感じませんがなめらかなテクスチャーが樽の雰囲気を感じさせます。高級感もあり美味しい。
近年は、アンフォラやコンクリート・エッグなど様々な発酵槽を併用してソーヴィニヨン・ブランを作るワイナリーも増えてきていますが、ガーギッチでは伝統的な方法を大事にして樽だけを使っています。実はコンクリート・エッグは導入したことがあるのですが、2年使ってやめてしまい、他のワイナリーに売ってしまったそうです。
次は2021年のシャルドネです。こちらも樽発酵しており、新樽と1年の樽と2年の樽を組み合わせて使っています。
軽いヴァニラの香りにマジパンと黄色い花の香り(このあたりがガーギッチのシャルドネには毎回感じられます)。柑橘にハチミツ、ちょっとトロピカルフルーツのニュアンスもあります。おだやかでバランスのいいシャルドネです。
赤は2019年のジンファンデルから。ガーギッチのジンファンデルはエレガントで、ジンファンデルだと気が付かない人が多いくらい。実際にジンファンデルを飲んだ人がワイナリーにワインを買いに来て「ピノ・ノワールをください」と言ったという話もあるくらいです(ガーギッチではピノ・ノワールは作っていません)。
ザクロやレッド・チェリー。合わせた料理が中華だったせいかもしれませんが黒酢のようなコクと酸を感じました。フォレストフロアや皮革のようなニュアンスもあり、エレガントで熟成も楽しめそうなジンファンデル。ジンファンデルというと濃くて甘いワインばかりと思っている方にはぜひこのジンファンデルを飲んでほしい。
最後は2019年のカベルネ・ソーヴィニヨン。ヨントヴィル、ラザフォード、カリストガの畑のブドウを使っています。古いものでは1959年に植えたカベルネのブロックも入っています。
ザクロにレッド・チェリー、ブラックチェリー、カシス。豊かな果実味がありミディアムボディでエレガントなカベルネ・ソーヴィニヨン。杉やタイムのニュアンスも。これもフードフレンドリーなカベルネ・ソーヴィニヨンです。



麻布台ヒルズの虎景軒(フージン)の料理も素晴らしく美味しかったです。特にジンファンデルにはよく合いました。
ヴァイオレットさん。空手をやっているせいか、姿勢がいいです。
マイク・ガーギッチは今のクロアチアの出身。2歳でワインを飲み始めたといいます(水が衛生的でないので、消毒代わりに水にワインを混ぜて飲むそう)。3歳のときには実家でのワイン造りを手伝っていたとか。ただ、実家は貧乏で8年生を超えて進学したのは11人兄弟の中でマイク一人だったそうです。
ザグレブ大学でワイン造りを勉強し、サバティカルで米国に行ったことがある教授から「米国は夢を追えるところ」、「ナパはパラダイス」と聞き、米国移住を志します。
入国許可がなかなか得られず、カナダでしばらく働いてからようやく米国への許可を得て1958年にナパに着きました。ちなみにマイクのトレードマークのベレー帽は大学時代に傘が買えずに雨除けにかぶっていたのがきっかけでした。
ナパではBVのアンドレ・チェリチェフや当時の有名ワイナリーだったスーヴェランのリー・スチュワートの下で働き、ロバート・モンダヴィで職を得ました。そこで作った1969年のカベルネ・ソーヴィニヨンがベストカベルネ・ソーヴィニヨンに選ばれ、モンダヴィがこれで有名になったといいます。これがきっかけになり、当時再建を始めたばかりのシャトー・モンテレーナのジム・バレットがカベルネを造るためにマイクを雇ったのでした。ただ、カベルネ・ソーヴィニヨンを造るのには時間もお金もかかり、最低でも5年間はかかるという計画で、マイクがキャッシュ・フローのためにシャルドネを造ることを提案したのでした。その2ヴィンテージ目の1973年のシャルドネが、「パリスの審判」で一位になったのでした。
また、この当時、マイクのイタリア人の友人がガレージで作ったカベルネ・ソーヴィニヨンとジンファンデルを飲ませてもらったものが非常に素晴らしく、「素晴らしいブドウを手に入れて自然に作ったワインが一番いい」というフィロソフィーを持つようになりました。
パリスの審判の1年後にはコーヒーの会社を経営するオースティン・ヒルズがパートナーとなり、ガーギッチ・ヒルズを創設しました。最初のシャルドネはシカゴで1980年5月に開かれたシャルドネ・ショーダウンにおいて221種類の中で1位になり、キングオブシャルドネと呼ばれるようになりました。
ガーギッチ・ヒルズのこだわりの一つが畑。2003年にはすべて自社畑のブドウだけでワインを造るようになりました。1986年にクロアチアからやってきた甥のイーヴォが畑を見るようになり、彼の薦めで2000年からオーガニックな栽培に切り替え、2006年には認証を取りました。認証は取らなくても良かったのですが、自然派スーパーのホールフーズが、ロゴを入れたいというので認証を取りました。あくまでもいいブドウを造るのが目的なので、マーケティングのためではないと言います。認証に必要なレベルを大きく超えて実践しているので、認証機関が驚くほどだったとのこと。
ビオディナミは2003年に畑のウイルスにやられたブロックを植え替えるときに始めました。先駆者としてい知られるロワールのニコラ・ジョリーからそのやり方を聞いたマイクは、クロアチアの畑でやっていた農法と似ていると感じて、自社畑に導入しました。するとすぐに畑の状態が良くなり驚いたといいます。
2018年には再生可能型有機栽培「ROC」を始め、2023年に認証を取得しました。従来のオーガニックやビオディナミでは生きている土壌を作ることはできないと感じて、この方法を始めました。この農法の大きな特徴の一つが、基本的に土地をなるべく耕さないこと。土地を耕すと微生物を破壊し、二酸化炭素が空気中に放出されるためです。また、耕すことで土が流出するなどの問題も起こります。ROCを始めてから土壌の中の有機物がすぐに1%くらい増えたそうで、普通はそれだけ増えるのには何年もかかるので、UCデーヴィスの研究者も驚いたとのことでした。
耕すのがいいのか、耕さない方がいいのかについては、現状意見が分かれるところでもあります。例えばスクリーミング・イーグルでは耕す方がいいと思っているとのことでした。一方、ガーギッチ・ヒルズでは耕さない方がいいという、強い確信があります。2022年に1週間以上40数度の気温が続く熱波が来たとき、隣の耕している畑では温度が70度にもなったのに対し、ガーギッチの畑は39度までしか上がりませんでした。土の温度が70度にもなると土の中の微生物も死んでしまいます。また、同じ年、1日に250mmもの雨が降ったときに、隣の畑は水浸しになりましたが、ガーギッチの畑は大丈夫でした。下の写真にあるように、実際に土壌はふかふかで絨毯の上を歩いているかのようだとのことです。こういった実証を経て自信を持ってROCに取り組んでいます。ヴァイオレットさんによると、上記の状態を見たドミナス(ガーギッチのヨントヴィルの畑と隣り合わせの畑です)も、最近ROCに取り組み始めているそうです。
ガーギッチではこのようなROCによる状態の変化を専門の研究者を置いて調べてレポートする体制を取っています。ROCに最も熱心に取り組んでいるワイナリーの一つといっていいでしょう。
ナパでは多くの場合、樹齢が20年を過ぎると植え替えをしています。ただ、ブドウの樹もできるだけ長く生きるのが自然であり、ROCのアプローチが自然だと感じています。植え替えはコストがかかるということ以外に、樹齢が長いとブドウの味に複雑性が出てくるためです。
植え替えもブロック単位で行うのではなく1本ずつ行っています。現在、シャルドネの畑の植え替えをしているのですが、これはAxR1というフィロキセラへの耐性が低い台木を使っており、樹勢が落ちてきてしまっています。このときにすべてを植え替えるのではなく、1本単位に植え替えをします。「ディープ・イリゲーション」という土中の深いところに灌漑をして、根を下に伸ばすようにします。こうすると下の方にある砂地の土壌に根が届き、フィロキセラにやられないようになります。これはマイクが考えた方法で、今も80年代の木が残っているのだそうです。ジンファンデルでも1889年の樹が残っているといいます。
ワインの話に移ります。ガーギッチではバランスが取れてエレガントでフードフレンドリーなワインを作り続けています。最初のワインはフュメ・ブラン。先ほど、モントレーナのキャッシュフローのワインがシャルドネだったという話を紹介しましたが、ロバート・モンダヴィにとってはソーヴィニヨン・ブランがキャッシュフローのワインで、樽を使ってフュメ・ブランと名付けたものが大ヒットしました。このモンダヴィのフュメ・ブランを手掛けたのもマイク・ガーギッチでした。ガーギッチ・ヒルズでは、モンダヴィに敬意を表す意味を込めて、フュメ・ブランの名前を使い続けています(ただ、最近ではフュメ・ブランといっても知らない人も増えたのでソーヴィニヨン・ブランと併記しています)。
ガーギッチのフュメ・ブランはナパの南端のAVAであるロス・カーネロスと、カーネロスよりもさらに海に近く冷涼なアメリカン・キャニオンの畑のブドウを使っています。樽発酵樽熟成をしており、通常の樽のほか、フードルと呼ぶ大樽も使っています。ヴィンテージは2021年
酸が豊かで柑橘系のさわやかさとミネラル感、黄色い花の香り。樽香はほとんど感じませんがなめらかなテクスチャーが樽の雰囲気を感じさせます。高級感もあり美味しい。
近年は、アンフォラやコンクリート・エッグなど様々な発酵槽を併用してソーヴィニヨン・ブランを作るワイナリーも増えてきていますが、ガーギッチでは伝統的な方法を大事にして樽だけを使っています。実はコンクリート・エッグは導入したことがあるのですが、2年使ってやめてしまい、他のワイナリーに売ってしまったそうです。
次は2021年のシャルドネです。こちらも樽発酵しており、新樽と1年の樽と2年の樽を組み合わせて使っています。
軽いヴァニラの香りにマジパンと黄色い花の香り(このあたりがガーギッチのシャルドネには毎回感じられます)。柑橘にハチミツ、ちょっとトロピカルフルーツのニュアンスもあります。おだやかでバランスのいいシャルドネです。
赤は2019年のジンファンデルから。ガーギッチのジンファンデルはエレガントで、ジンファンデルだと気が付かない人が多いくらい。実際にジンファンデルを飲んだ人がワイナリーにワインを買いに来て「ピノ・ノワールをください」と言ったという話もあるくらいです(ガーギッチではピノ・ノワールは作っていません)。
ザクロやレッド・チェリー。合わせた料理が中華だったせいかもしれませんが黒酢のようなコクと酸を感じました。フォレストフロアや皮革のようなニュアンスもあり、エレガントで熟成も楽しめそうなジンファンデル。ジンファンデルというと濃くて甘いワインばかりと思っている方にはぜひこのジンファンデルを飲んでほしい。
最後は2019年のカベルネ・ソーヴィニヨン。ヨントヴィル、ラザフォード、カリストガの畑のブドウを使っています。古いものでは1959年に植えたカベルネのブロックも入っています。
ザクロにレッド・チェリー、ブラックチェリー、カシス。豊かな果実味がありミディアムボディでエレガントなカベルネ・ソーヴィニヨン。杉やタイムのニュアンスも。これもフードフレンドリーなカベルネ・ソーヴィニヨンです。
麻布台ヒルズの虎景軒(フージン)の料理も素晴らしく美味しかったです。特にジンファンデルにはよく合いました。
サンタ・クルーズ・マウンテンズのマウント・エデンのオーナーであるジェフリー・パターソンさんが12年ぶりに来日し、セミナーを行いました。
前回の記事:サンタ・クルーズ・マウンテンズのテロワールを表現したMount Edenのワイン
サンタ・クルーズ・マウンテンズは、カリフォルニアの数あるAVAの中でも、非常に個性的なところであり、実は私の「推しAVA」の一つでもあります。策定されたのは1981年。カリフォルニア初のAVAであるナパ・ヴァレーと同じ年ですが、順番でいうとカリフォルニアで6番目。ソノマ・ヴァレー、マクドウェル・ヴァレー(メンドシーノ)と同じ日に策定されています。
何が個性的かというと、AVAの境界が標高で定められた初めてのAVAであるということ、山地のAVAで面積はナパの1.5倍くらいありながら、ブドウ畑はナパの30分の1にも満たない、ほんのわずかしかないということ、AVAの中でも場所によって気候などが大きく異なること、域内をサン・アンドレアス断層が横切っているため、土壌が極めて複雑なこと、基本的には冷涼な産地でありながら、カベルネ・ソーヴィニヨンでもトップクラスのワインが作られているということ、地域的にはセントラル・コーストに含まれているのですが、セントラル・コーストAVAからは特別に除外されていること……そのつかまえどころのなさから、ヴィナスのアントニオ・ガッローニは「カメレオンのようだ」と評しています。
有名なワイナリーとして、まず名前が挙がるのは、リッジ(Ridge)です。サンタ・クルーズ・マウンテンズの畑「モンテベッロ」はカリフォルニアきっての銘醸畑であり、トップクラスのカベルネ・ソーヴィニヨンやシャルドネなどが作られています。リッジというとジンファンデルも有名ですがジンファンデルの多くはソノマの畑を使っています。モンテベッロにもジンファンデルがありますが、かなりレアです。
このほか近年注目されているのはリース(Rhys)。きわめてエレガントで高品質なシャルドネとピノ・ノワールを作っています。
そして今回のマウント・エデンですが、シャルドネとピノ・ノワール、カベルネ・ソーヴィニヨンを同じ畑で作っています。しかもすべて極めて高品質。パーカーポイントではシャルドネとピノ・ノワールが最高96、カベルネ・ソーヴィニヨンが98点。ヴィナスではシャルドネとピノ・ノワールが最高97、カベルネ・ソーヴィニヨンが98。一つの畑でこの3品種のワールドクラスのワインを造っているというのは世界広しといってもここくらいしかないのではないでしょうか。
マウント・エデンはカリフォルニアワインの歴史の上でも重要なワイナリーです。歴史を紐解くと、ポール・マソンという人が1896年にサンタ・クルーズ・マウンテンズの麓(内陸側)のサラトガという町に40エーカーの土地を買ったことにさかのぼります。この人はブルゴーニュ出身で、シャルドネとピノ・ノワールを造ろうと、フランスにいって苗木を持ち帰ってブドウ畑を造りました。
このポール・マソンに師事していたのがマーティン・レイ。カリフォルニアワインの歴史に残る奇人変人の一人です。マーティン・レイは1936年にポール・マソンのワイナリーを買いますが、ポール・マソンはサラトガでなく、もっと標高の高いところに畑を造るべきだと諭し、42年に売却。45年にサンタ・クルーズ・マウンテンズの山中に作ったのがマーティン・レイ・ワイナリーで、これが現在のマウント・エデンです。マーティン・レイの畑はポール・マソンの畑からのシャルドネとピノ・ノワールが植えられました。ジェフリー・パターソンさんによると、おそらくルイ・ラトゥールのコルトンの畑からのものだろうとのことでした。
この、ポール・マソンが持ち込んだシャルドネとピノ・ノワールはマウント・エデン・クローンとして、現在はカリフォルニアの様々なワイナリーで使われています。特にシャルドネは写真にあるように、ブドウの実の大小の差が大きくなります。これはいわゆるミルランダージュ、結実不良であり、収量は少なくなりますが、逆に味わいの複雑さを出すのです。オールド・ウェンテと呼ばれるクローンと似た特質です。
マーティン・レイ・ワイナリーでは、マーティン・レイが極めてこだわりを持ってワインを造りましたが、SO2を添加しないなど個性が強く、ワインは時に素晴らしく美味しいのですが、失敗作も多く、ビジネスとしてはなかなか厳しいものがあったようです。マーティン・レイは1970年にワイナリーを売却、その後マウント・エデンと改名し、シャローンのリチャード・グラフがコンサルタントになりメリー・エドワーズなどがワインメーカーとして雇われましたが、いずれも長続きせず、安定しない状態が続きました。
そこへやってきたのがジェフリー・パターソンです。1981年にアシスタント・ワインメーカーとして雇われ、1982年には早くもワインメーカー兼ジェネラルマネージャーに就任しました。そこからが現在のマウント・エデンの始まりです。ジェフリーは2008年にワイナリーの最大株主になり、現在は息子がジェネラルマネージャー、娘はホスピタリティ担当と、家族で経営しています。
シャルドネは樽発酵・樽熟成をしています。マウント・エデンのワインはエステートのワイナリーのほか、近所にある「ドメーヌ・エデン」の畑のところにもあります。設備的にはドメーヌ・エデンの方が新しいものを入れていますが、樽発酵・樽熟成のシャルドネの場合は、温度調節できるタンクなどは必要としないので、全部マウント・エデンのワイナリーで作られています。
ワインの試飲はシャルドネ3種からです。今回はドメーヌ・エデンのワインはありませんでした。
最初のワインはエドナ・ヴァレーのシャルドネ2021年。このワインは唯一買いブドウで作っています。1985年からと、ジェフリー・パターソンになってすぐのころからのワインです。希望小売価格4800円と、マウント・エデンのラインアップの中では圧倒的に安いワインです。エドナ・ヴァレーは、一番冷涼なAVAと自称しており収穫は10月半ばくらいと非常に遅いのが特徴です。ワインは酸が豊かで、柑橘や黄色い花、ミネラル感を感じます。なめらかなテクスチャーで価格以上の高級感。非常にいいシャルドネです。
二つ目は2020年のエステート・シャルドネ(1万2000円)。ここの代表的なワインと言っていいでしょう。目が覚めるような鮮烈な酸と、対照的な柔らかいテクスチャー、柑橘から白桃、ナッツやハーブ、ビスケットに白い花。締りのあるきれいなシャルドネで味わいの複雑さとその幅広さが素晴らしいシャルドネです。芯の通った味わいと果実味に頼らない魅力は長熟向きです。2020年は干ばつでブドウの成熟が早く8月下旬に収穫していますが、品質は良かったとのこと。マウント・エデンの畑は灌漑をしておらず、山の斜面で元々水も少ないところなので、干ばつは影響が大きいようです。収量は1エーカー2トン未満と、かなり少ないです。
シャルドネの最後は2020年のリザーブ・シャルドネ(1万8000円)。リザーブ・シャルドネは2007年から作っているワインで、エステートの樽の中から11樽を選抜。全部まとめてステンレススティールタンクに入れて12カ月熟成します。前述のようにステンレススティールのタンクはドメーヌ・エデンの方のワイナリーにしかないので、そちらを使っています。この1年の間にブドウの澱がワインに溶け込んでなくなってしまうのだそうです。それによって、複雑さが出てきます。
エステートと比べて濃厚でオイリーなテクスチャー、トロピカルな味わい。柑橘にマンゴーやパパイヤ、黄色い花を感じます。長熟性という点ではエステートの方が上かもしれないとのこと。
次は2020年のエステートのピノ・ノワール(1万3000円)。35%全房を使っています。50%新樽、天然酵母で発酵。前述のように2020年は干ばつだったため、ピノ・ノワールも8月下旬に収穫しています。赤果実から黒果実の香り、酸高く、アーシーな風味、果実味もあるけどおとなしく、長期熟成でより魅力が発揮されるワインでしょう。
カベルネ・ソーヴィニヨンは2018年と、蔵出しの2005年の試飲です。カベルネ・ソーヴィニヨンはボルドー左岸のスタイル。冷涼なサンタ・クルーズ・マウンテンズで素晴らしいカベルネ・ソーヴィニヨンを作っているのはマウント・エデンとリッジだけと自負しています。カベルネ・ソーヴィニヨンもマーティン・レイの時代に最初に植えられており、エメット・リックスフォードという人がシャトー・マルゴーから持ち帰ったというラ・クエスタ・ヴィンヤードのカッティングを使っています。
2018年のカベルネ・ソーヴィニヨン(1万7500円)はカシス、ブラックベリー、杉やセージの風味、何よりも酸のきれいさが印象的なカベルネ・ソーヴィニヨンです。非常に長熟向き。実は酸はそれほど高くなく、高いタンニンと低いpHがそう感じさせるとのこと。
最後は蔵出しの2005年のカベルネ・ソーヴィニヨン。
ザクロやブラックベリー、セージやクローヴなどのハーブ、非常に複雑な味わいで素晴らしい。さすがの熟成力です。
ジェフリーさん、12年前は奥様と仲睦まじく来られていたのですが、別れてしまったとのことで、これはちょっと驚きでした。
マウント・エデン、ワインの造りもその魅力も12年前から変わっておらず、今では珍しいほどの長熟型ワインを造り続けています。一方で、今飲んでも十分魅力的でありサンタ・クルーズ・マウンテンズの質実剛健さを体現しているワイナリーだと思います。
インポーターのファインズによるパッツ&ホール(Patz & Hall)のセミナーに参加しました。実は個人的には初めてメーリング・リストに登録してワインを買ったのがパッツ&ホールでした。送料などが上がってしまってやめてしまったのですが、これまで一番多く飲んだワイナリーの一つだと思います。
パッツ&ホールは1988年、ドナルド・パッツとジェームズ・ホール、そして二人のパートナーの4人によって設立されました。ドナルド・パッツとジェームズ・ホールがナパのフローラ・スプリングスのセールス・マネジャーとワインメーカーとして働いていたときに意気投合したのがきっかけだったといいます。創設者の4人の中でワインメーカーのジェームズ・ホールだけは現在もオーナー兼名誉ワインメーカーとしてワイン造りに携わっています。一時期はワシントンのシャトー・サン・ミシェル傘下に入りましたが、2024年にジェームズ・ホールが買い戻したことで話題になりました(パッツ&ホール、創設者が大手ワイナリーから買い戻して独立)。
パッツ&ホールは、契約した畑のブドウを使ってワインを造る「ネゴシアン」タイプのワイナリーです。パッツ&ホールができたころはキスラーなど、ネゴシアンタイプのワイナリーの勃興時期でした。その後も2000年代のピノ・ノワールブームで人気になったコスタ・ブラウンやローリング、ブリュワー・クリフトンなど、ピノ・ノワールやシャルドネに力を入れるワイナリーではこのタイプが主流でした。しかし、その後多くは自社畑を手に入れて、そちらを中心とする方向に舵を切っています。パッツ&ホールもカーネロスに自社畑を所有していますが、あくまでもメインは契約畑であり、ウェブサイトでも栽培家を大きく取り上げています。ワインの裏ラベルにも栽培家への賛辞が書かれています。

現在は22種類のキュベを作っており、うち10種ほどが日本に輸入されています。ただ、ハイド・ヴィンヤードのピノ・ノワールなど、リクエストしてもごく少量しか輸入できないものもあるそうです。ブドウ畑はソノマのロシアン・リバー・ヴァレーとカーネロスが大部分を占めます。このほか、メンドシーノのアルダー・スプリングス(Alder Springs)、サンタ・ルシア・ハイランズのピゾーニ(Pisoni)とソベラネスの畑のブドウも使っています。
ワイン造りはどの畑でもほぼ同じです。
シャルドネ
・全房でプレス
・樽発酵、樽熟成。酸化を防ぐために樽の上部まで果汁で満たす
・新樽率は25%程度
・フルMLF
・シュール・リーで熟成
・フィルターなしでボトル詰め
ピノ・ノワール
・フリーラン・ジュースのみ
・約10%全房、オープントップの発酵槽利用
・新樽率は50%程度
・果房管理ではパンチング・ダウンとポンプオーバーを組み合わせたパンチング・オーバーという手法を導入
といった形になります。
樽材は3年間天然乾燥させた木を使った特注品(フランソワ・フレールとセガン・モロー)を使っています。ワインのスタイルはクラシックと言っていいでしょう。近年増えている酸が高く、エレガントで果実味控えめなタイプではなく、樽も果実味も十分に利いたタイプのワイです。
試飲に移ります。この日はシャルドネ2種類とピノ・ノワール4種類でした。
・ダットン・ランチ(Dutton Ranch)、シャルドネ2021(1万円)
ダットン・ランチはダットン家が持っている畑の総称で、グリーン・ヴァレーなどロシアン・リバー・ヴァレーにいくつもの畑を抱えています。適度な保水力があり、やわらかく非常に痩せているゴールドリッジ土壌の畑を多く持っています。私が買っていたころは、ダットン・ランチはパッツ&ホールのシャルドネの中でも一番陽性で、若いときから楽しめるワインでした。ダットン・ランチを有名にしたのはキスラーで、今もダットン・ランチのワインを造っていますが、パッツ&ホールが使っているのはキスラーが以前使っていた区画だそうです。
豊かな酸に柑橘系のフレーバー。白桃のようなちょっとトロピカルな風味もあります。樽香はおだやかで、なめらかなテクスチャー。
・ハイド・ヴィンヤード(Hyde Vineyard) シャルドネ2018(1万3500円)
カーネロスのナパサイドにある銘醸畑。キスラーやコングスガード、レイミー、ポール・ラトーなどそうそうたるワイナリーがブドウの供給を受ける、まさにカリフォルニアのグラン・クリュと呼ぶべき畑です。シャルドネではHyde-Wenteと呼ばれるクローンとHyde-Caleraと呼ばれるクローンのブロックがありますが、パッツ&ホールではHyde-Wenteの区画を使っています。
ミネラル感やベイキング・スパイスなど複雑味を感じる味わい。オレンジピールやネクタリンなど豊かな果実味も魅力的。さすがハイドと呼ぶべき高品質なシャルドネです。
ピノ・ノワールに移ります。
・チェノウェース・ランチ(Chenoweth Ranch)ピノ・ノワール 2018(1万5500円)
ロシアン・リバー・ヴァレー(グリーン・ヴァレー)の畑で、ダットン・ランチで畑の管理を任されていたチャーリー・チェノウェース氏の畑です。ブドウのほとんどをパッツ&ホールに提供しています。パッツのピノ・ノワールの中では最も収穫が早く果実味豊かになると言われています。
ラズベリーにレッド・チェリー、ブラックベリーのような黒果実の味わいもあり、果実の凝縮度の高さを感じます。テクスチャにもややねっとりした粘性の高さがあります。甘草や紅茶の味わいも。
・ギャップス・クラウン(Gap's Crown)ピノ・ノワール 2019(1万4000円)
強風で知られるペタルマ・ギャップの畑で、畑のオーナーはキスラーやスリー・スティックスを擁するビル・プライス。一番収穫が遅く、強風で果皮が厚くブドウの粒が小さくなるため、かなり濃い味わいのワインになります。収穫もここが一番遅いとのこと。
赤果実というよりもブラックベリーやブラック・チェリーのような黒果実主体の果実味。パワフルでスパイシー、ストラクチャーもあるピノ・ノワール。畑の個性が見事に表現されていると思います。
・ハイド・ヴィンヤード ピノ・ノワール(1万4000円)
パッツ&ホールのピノ・ノワールの中では一番エレガントで、ジェームズ・ホールはこのワインをシャンボール・ミュジニーに例えるといいます。Hyde-Caleraクローンを使っています。
赤い果実に甘草や紅茶のニュアンス。ベイキング・スパイスの香りもあります。少しタンニンを感じますがテクスチャはなめらか。
・ピゾーニ・ヴィンヤード(Pisoni Vineyard)ピノ・ノワール 2018(2万円)
パッツ&ホールは1990年代半ばからピゾーニのブドウの供給を受けている、ピゾーニのワインを造るワイナリーの中では最古参。ラターシュから持ってきたと言われるブドウは非常に濃厚で力強い味わいになります。標高が高く、午後には強い風が吹く場所で、ブドウはフルボディでストラクチャーを持ったものになります。ここだけは新樽率70%と高く、全房も20%使っています。
以前、ドナルド・パッツさんとのワイン会でピゾーニとのなれそめを聞いたのですが、以下のようなことでした。
自分(ドナルド・パッツ)は知り合いのところでPisoniのブドウで作ったワインを飲ませてもらい,これはいいと思った。パートナーのJames Hallは知り合いから「いい畑がある」と聞いてそこがPisoniだった。互いに別のルートから名前を知って,「契約したらよさそうな畑があるんだ」と同時に言ったのがPisoniだった。
果実味よりも先にウーロン茶のようなフレーバーを感じます。スパイシーで複雑。ブラック・チェリーにブラックベリー、ラズベリーの果実味が見え隠れするピノ・ノワール。ピゾーニらしさもちゃんとあり、個性的で素晴らしいピノ・ノワールです。
6種類試飲して感じたのは、前述のように作りはほぼ共通であるのにワインの味わいは大きく異なること。まさにテロワールをちゃんと表現したワインになっていると言っていいでしょう。久しぶりに飲んだピゾーニはさすがの実力でしたし、ハイドのシャルドネとピノ・ノワールも見事なできでした。

ダットン・ランチは実売8000円程度で、キスラーのダットンが3万円近くするのと比べてコスパもかなり高いです。
なかなか手に入らないハイドのシャルドネ
パッツ&ホール専用畑と言っていいチェノウェース。
これは安いですね。ショップはマリアージュ・ド・ケイ
ピゾーニ1万5000円台も安いです。これもマリアージュ・ド・ケイ
パッツ&ホールは1988年、ドナルド・パッツとジェームズ・ホール、そして二人のパートナーの4人によって設立されました。ドナルド・パッツとジェームズ・ホールがナパのフローラ・スプリングスのセールス・マネジャーとワインメーカーとして働いていたときに意気投合したのがきっかけだったといいます。創設者の4人の中でワインメーカーのジェームズ・ホールだけは現在もオーナー兼名誉ワインメーカーとしてワイン造りに携わっています。一時期はワシントンのシャトー・サン・ミシェル傘下に入りましたが、2024年にジェームズ・ホールが買い戻したことで話題になりました(パッツ&ホール、創設者が大手ワイナリーから買い戻して独立)。
パッツ&ホールは、契約した畑のブドウを使ってワインを造る「ネゴシアン」タイプのワイナリーです。パッツ&ホールができたころはキスラーなど、ネゴシアンタイプのワイナリーの勃興時期でした。その後も2000年代のピノ・ノワールブームで人気になったコスタ・ブラウンやローリング、ブリュワー・クリフトンなど、ピノ・ノワールやシャルドネに力を入れるワイナリーではこのタイプが主流でした。しかし、その後多くは自社畑を手に入れて、そちらを中心とする方向に舵を切っています。パッツ&ホールもカーネロスに自社畑を所有していますが、あくまでもメインは契約畑であり、ウェブサイトでも栽培家を大きく取り上げています。ワインの裏ラベルにも栽培家への賛辞が書かれています。

現在は22種類のキュベを作っており、うち10種ほどが日本に輸入されています。ただ、ハイド・ヴィンヤードのピノ・ノワールなど、リクエストしてもごく少量しか輸入できないものもあるそうです。ブドウ畑はソノマのロシアン・リバー・ヴァレーとカーネロスが大部分を占めます。このほか、メンドシーノのアルダー・スプリングス(Alder Springs)、サンタ・ルシア・ハイランズのピゾーニ(Pisoni)とソベラネスの畑のブドウも使っています。
ワイン造りはどの畑でもほぼ同じです。
シャルドネ
・全房でプレス
・樽発酵、樽熟成。酸化を防ぐために樽の上部まで果汁で満たす
・新樽率は25%程度
・フルMLF
・シュール・リーで熟成
・フィルターなしでボトル詰め
ピノ・ノワール
・フリーラン・ジュースのみ
・約10%全房、オープントップの発酵槽利用
・新樽率は50%程度
・果房管理ではパンチング・ダウンとポンプオーバーを組み合わせたパンチング・オーバーという手法を導入
といった形になります。
樽材は3年間天然乾燥させた木を使った特注品(フランソワ・フレールとセガン・モロー)を使っています。ワインのスタイルはクラシックと言っていいでしょう。近年増えている酸が高く、エレガントで果実味控えめなタイプではなく、樽も果実味も十分に利いたタイプのワイです。
試飲に移ります。この日はシャルドネ2種類とピノ・ノワール4種類でした。
・ダットン・ランチ(Dutton Ranch)、シャルドネ2021(1万円)
ダットン・ランチはダットン家が持っている畑の総称で、グリーン・ヴァレーなどロシアン・リバー・ヴァレーにいくつもの畑を抱えています。適度な保水力があり、やわらかく非常に痩せているゴールドリッジ土壌の畑を多く持っています。私が買っていたころは、ダットン・ランチはパッツ&ホールのシャルドネの中でも一番陽性で、若いときから楽しめるワインでした。ダットン・ランチを有名にしたのはキスラーで、今もダットン・ランチのワインを造っていますが、パッツ&ホールが使っているのはキスラーが以前使っていた区画だそうです。
豊かな酸に柑橘系のフレーバー。白桃のようなちょっとトロピカルな風味もあります。樽香はおだやかで、なめらかなテクスチャー。
・ハイド・ヴィンヤード(Hyde Vineyard) シャルドネ2018(1万3500円)
カーネロスのナパサイドにある銘醸畑。キスラーやコングスガード、レイミー、ポール・ラトーなどそうそうたるワイナリーがブドウの供給を受ける、まさにカリフォルニアのグラン・クリュと呼ぶべき畑です。シャルドネではHyde-Wenteと呼ばれるクローンとHyde-Caleraと呼ばれるクローンのブロックがありますが、パッツ&ホールではHyde-Wenteの区画を使っています。
ミネラル感やベイキング・スパイスなど複雑味を感じる味わい。オレンジピールやネクタリンなど豊かな果実味も魅力的。さすがハイドと呼ぶべき高品質なシャルドネです。
ピノ・ノワールに移ります。
・チェノウェース・ランチ(Chenoweth Ranch)ピノ・ノワール 2018(1万5500円)
ロシアン・リバー・ヴァレー(グリーン・ヴァレー)の畑で、ダットン・ランチで畑の管理を任されていたチャーリー・チェノウェース氏の畑です。ブドウのほとんどをパッツ&ホールに提供しています。パッツのピノ・ノワールの中では最も収穫が早く果実味豊かになると言われています。
ラズベリーにレッド・チェリー、ブラックベリーのような黒果実の味わいもあり、果実の凝縮度の高さを感じます。テクスチャにもややねっとりした粘性の高さがあります。甘草や紅茶の味わいも。
・ギャップス・クラウン(Gap's Crown)ピノ・ノワール 2019(1万4000円)
強風で知られるペタルマ・ギャップの畑で、畑のオーナーはキスラーやスリー・スティックスを擁するビル・プライス。一番収穫が遅く、強風で果皮が厚くブドウの粒が小さくなるため、かなり濃い味わいのワインになります。収穫もここが一番遅いとのこと。
赤果実というよりもブラックベリーやブラック・チェリーのような黒果実主体の果実味。パワフルでスパイシー、ストラクチャーもあるピノ・ノワール。畑の個性が見事に表現されていると思います。
・ハイド・ヴィンヤード ピノ・ノワール(1万4000円)
パッツ&ホールのピノ・ノワールの中では一番エレガントで、ジェームズ・ホールはこのワインをシャンボール・ミュジニーに例えるといいます。Hyde-Caleraクローンを使っています。
赤い果実に甘草や紅茶のニュアンス。ベイキング・スパイスの香りもあります。少しタンニンを感じますがテクスチャはなめらか。
・ピゾーニ・ヴィンヤード(Pisoni Vineyard)ピノ・ノワール 2018(2万円)
パッツ&ホールは1990年代半ばからピゾーニのブドウの供給を受けている、ピゾーニのワインを造るワイナリーの中では最古参。ラターシュから持ってきたと言われるブドウは非常に濃厚で力強い味わいになります。標高が高く、午後には強い風が吹く場所で、ブドウはフルボディでストラクチャーを持ったものになります。ここだけは新樽率70%と高く、全房も20%使っています。
以前、ドナルド・パッツさんとのワイン会でピゾーニとのなれそめを聞いたのですが、以下のようなことでした。
自分(ドナルド・パッツ)は知り合いのところでPisoniのブドウで作ったワインを飲ませてもらい,これはいいと思った。パートナーのJames Hallは知り合いから「いい畑がある」と聞いてそこがPisoniだった。互いに別のルートから名前を知って,「契約したらよさそうな畑があるんだ」と同時に言ったのがPisoniだった。
果実味よりも先にウーロン茶のようなフレーバーを感じます。スパイシーで複雑。ブラック・チェリーにブラックベリー、ラズベリーの果実味が見え隠れするピノ・ノワール。ピゾーニらしさもちゃんとあり、個性的で素晴らしいピノ・ノワールです。
6種類試飲して感じたのは、前述のように作りはほぼ共通であるのにワインの味わいは大きく異なること。まさにテロワールをちゃんと表現したワインになっていると言っていいでしょう。久しぶりに飲んだピゾーニはさすがの実力でしたし、ハイドのシャルドネとピノ・ノワールも見事なできでした。
オーパス・ワン(Opne One)は新しいワインメーカーとしてミーガン・ゾベック(Meghan Zobeck)を採用しました。これまでのワインメーカーのマイケル・シラッチ(Michael Silacci)がワインメーカーになったのは2001年だったので、24年ぶりの交代ということになります。マイケル・シラッチは今後3~6年はオーパス・ワンにとどまり、リプランティングや「ホリスティック・ファーミング」(土地や土壌をシステムとしてとらえて管理する農法)へのシフトに集中する予定です。

ミーガン・ゾベックはアメリカンフットボールのプロ選手の代理人からの転身というユニークな経歴。ワイン業界に身を投じたのは2012年で、まだ13年しかたっていません。スタッグス・リープ・ワイン・セラーズやスクリーミング・イーグルでインターンをした後、フィリップ・メルカのアシスタントを務め、その後トロワ・ノワ(Troix Noix、元アラウホのオーナーの娘であるジェイミー・アラウホのワイナリー)でワインメーカーを務め、2020年からはバージェス・セラー(Burgess Cellar)でワインメーカーになりました。バージェスのワイナリーは2020年の山火事で焼失しましたが、その後、シルバラード・トレイルにある元ルナの設備を使ってワインを造る一方、再生可能農法へのシフトを指導しました。これで名声が高まり、特に農法での実践がシラッチの目に留まったようです。
マイケル・シラッチの前のワインメーカーはロバート・モンダヴィの次男のティムでしたが、兄のマイケルと仲が悪く、ワインの品質も安定を欠いていました。シラッチがワインメーカーになり、ロバート・モンダヴィからコンステレーションに共同オーナーが変わってから品質は安定してよくなっています。
ミーガンのように、栽培に力を入れるワインメーカーは近年の流行りでもあり、新世代のワインメーカーの代表格となりました。

ミーガン・ゾベックはアメリカンフットボールのプロ選手の代理人からの転身というユニークな経歴。ワイン業界に身を投じたのは2012年で、まだ13年しかたっていません。スタッグス・リープ・ワイン・セラーズやスクリーミング・イーグルでインターンをした後、フィリップ・メルカのアシスタントを務め、その後トロワ・ノワ(Troix Noix、元アラウホのオーナーの娘であるジェイミー・アラウホのワイナリー)でワインメーカーを務め、2020年からはバージェス・セラー(Burgess Cellar)でワインメーカーになりました。バージェスのワイナリーは2020年の山火事で焼失しましたが、その後、シルバラード・トレイルにある元ルナの設備を使ってワインを造る一方、再生可能農法へのシフトを指導しました。これで名声が高まり、特に農法での実践がシラッチの目に留まったようです。
マイケル・シラッチの前のワインメーカーはロバート・モンダヴィの次男のティムでしたが、兄のマイケルと仲が悪く、ワインの品質も安定を欠いていました。シラッチがワインメーカーになり、ロバート・モンダヴィからコンステレーションに共同オーナーが変わってから品質は安定してよくなっています。
ミーガンのように、栽培に力を入れるワインメーカーは近年の流行りでもあり、新世代のワインメーカーの代表格となりました。

ダラ・ヴァレのマヤさんが、ワイナリーにおける業界向けテイスティングについて、昨今のナパ郡の方針に懸念を表明しており、SFクロニクルが記事で取り上げています。マヤさんはインスタグラムで以下のように記しています。
私は業界の問題の最前線に立ちたいわけでも、スポークスパーソンになりたいわけでもありません。そのことは私を知るほとんどの人は知っていることです。私はワイナリーや畑で静かに、自分の仕事に専念したいのです。しかし、私は私たちのビジネスのために戦い、姿勢を示さなければならない立場に追い込まれています。次の世代に確実に未来を残すために、私とともに身を挺して立ち向かってくれた業界の友人や同僚たちの支援に畏敬の念を感じるとともに、深く謙虚な気持ちになります。ワイン業界がこれ以上理不尽な規制を受けることに耐えられないという私の意見に賛同してくださる方は、次回3月25日(火)午前9時からのナパ郡監督委員会に出席してパブリックコメントを行うか、郡職員が貿易視察に対して取っている姿勢について懸念を表明するメールを書いてください。その際、不明な点などがあれば私に連絡してください。具体的に言うと、ダラ・ヴァレはテイスティング・ルームがなく一般の顧客は全く受け入れておりません。郡のルールでそうなっています。ただ、「トレード・ビジット」と呼ばれるような業界向けの訪問と試飲については受け入れています。テイスティング・ルームを持つワイナリーも、最大訪問者数は決められていますが、通常トレード・ビジットはそれとは別にカウントされています。実際、マヤさんが問い合わせたワイナリー20件ではどこもトレード・ビジットは訪問者数にはカウントされていませんでした。
ところが、昨今ナパ郡ではトレード・ビジットについても一般の顧客と同じように訪問者数にカウントしなければいけないというように運用が変わりつつあります。現実にはまだダラ・ヴァレなどでトレード・ビジットの受け入れが実際に禁止されたわけではないですが、ナパ郡の認識においてはルール違反ということになります。
今回の問題とは別に、ナパのフープス(Hoopes)は、テイスティング・ルームの許可が無効であるとして、即日閉鎖を求められています(フープス側は1990年までに作られた小規模ワイナリー向けの措置として認められていると主張しましたが、初審では敗訴しました)。
似たような裁判はほかにもあり、郡側が運用を恣意的に厳しくしているのではないかという見方もあります。
冒頭に書いたように、決して出たがりではなく、むしろ表に出るのを避けるタイプだったダラ・ヴァレがこういった動きに出るということが危機感の強さを表しているように思われます。
前回の続きです。

モンターニュ・ルース(Montagne Russe)は、ソノマを中心に高品質なワインを比較的リーズナブルな価格で出しているワイナリー。右から2番目のピノ・ノワールはソノマ・コーストの4つの銘醸畑のブレンド(6160円)。バランスよくジューシーで美味しい。その右のナパのカベルネ・ソーヴィニヨン「クレアーオブスキュア」は17600円と高額なワインですが、ブドウはもっとずっと高額なワインが作られる畑のものだとのこと。ジューシーで濃厚、緻密な味わいのカベルネ・ソーヴィニヨンです。

ワンストーンのロゼ・オブ・ピノノワール(3740円)はバランスよくコスパいいロゼです。

アーサーセラーズのピノ・ノワールはロシアン・リバー・ヴァレーのもので5200円と抜群のコストパフォーマンス。チェリーリッジのピノ・ノワール(6200円)はラインアップ中、一番エレガントな味わいで個人的にもリピート買いしているワイン。

カリフォルニアのシャルドネの7割を占めると言われているのがウェンテ(Wente)由来のクローン。ウェンテのワインの中でもやはり目立つのがシャルドネです。左のモーニング・フォグ(2513円)は少量のセミヨンとのブレンド。バランスよさが際立ちます。もう一つのレトロ リミテッド・リリース シャルドネは樽の風味を利かせたタイプのシャルドネ。これも2700円は安いです。

パッツ&ホールのソノマ・コースト ピノ・ノワール(10000円)。ダットン・ランチなど秀逸な畑のブレンド。ややリッチ系の味わいでうまみもあり、美味しい。

サンタ・バーバラのハッピー・キャニオンで造るスターレーンのカベルネ。このご時世に200円値下げしています(8500円)。
バランスよくおいしい。

冷涼なエドナ・ヴァレーで造るシャルドネ「トゥルー・マイス」(3000円)ですが、ワインは果実味豊かで樽の風味もある、リッチ系。シャルドネの2500円から3000円の領域は、コスパに優れたワインが多くあります。

写真がひどいですが、リッジのパソロブレス ジンファンデル(7200円)。7200円のワインにコスパというと変かもしれませんが、コスパ高い優れたジンファンデルです。

ダイアトム(Diatom)はブリュワー・クリフトンのグレッグ・ブリュワーが作るシャルドネ専門のブランド。樽を使わないきれいなシャルドネを造ります。ダイアトムとはサンタ・リタ・ヒルズの特徴の一つでもある珪藻土の土壌のこと。樽を使わないからあっさいしているのかというと、実は果実味豊かでリッチ系のあじわい。でももちろんきれいさもあります。

サンタ・バーバラのマージェラムのローヌ系ブレンド「M5」。赤と白があり、どちらも秀逸でした。
関係者の皆さん、お疲れさまでした。
モンターニュ・ルース(Montagne Russe)は、ソノマを中心に高品質なワインを比較的リーズナブルな価格で出しているワイナリー。右から2番目のピノ・ノワールはソノマ・コーストの4つの銘醸畑のブレンド(6160円)。バランスよくジューシーで美味しい。その右のナパのカベルネ・ソーヴィニヨン「クレアーオブスキュア」は17600円と高額なワインですが、ブドウはもっとずっと高額なワインが作られる畑のものだとのこと。ジューシーで濃厚、緻密な味わいのカベルネ・ソーヴィニヨンです。
ワンストーンのロゼ・オブ・ピノノワール(3740円)はバランスよくコスパいいロゼです。
アーサーセラーズのピノ・ノワールはロシアン・リバー・ヴァレーのもので5200円と抜群のコストパフォーマンス。チェリーリッジのピノ・ノワール(6200円)はラインアップ中、一番エレガントな味わいで個人的にもリピート買いしているワイン。
カリフォルニアのシャルドネの7割を占めると言われているのがウェンテ(Wente)由来のクローン。ウェンテのワインの中でもやはり目立つのがシャルドネです。左のモーニング・フォグ(2513円)は少量のセミヨンとのブレンド。バランスよさが際立ちます。もう一つのレトロ リミテッド・リリース シャルドネは樽の風味を利かせたタイプのシャルドネ。これも2700円は安いです。
パッツ&ホールのソノマ・コースト ピノ・ノワール(10000円)。ダットン・ランチなど秀逸な畑のブレンド。ややリッチ系の味わいでうまみもあり、美味しい。
サンタ・バーバラのハッピー・キャニオンで造るスターレーンのカベルネ。このご時世に200円値下げしています(8500円)。
バランスよくおいしい。
冷涼なエドナ・ヴァレーで造るシャルドネ「トゥルー・マイス」(3000円)ですが、ワインは果実味豊かで樽の風味もある、リッチ系。シャルドネの2500円から3000円の領域は、コスパに優れたワインが多くあります。
写真がひどいですが、リッジのパソロブレス ジンファンデル(7200円)。7200円のワインにコスパというと変かもしれませんが、コスパ高い優れたジンファンデルです。
ダイアトム(Diatom)はブリュワー・クリフトンのグレッグ・ブリュワーが作るシャルドネ専門のブランド。樽を使わないきれいなシャルドネを造ります。ダイアトムとはサンタ・リタ・ヒルズの特徴の一つでもある珪藻土の土壌のこと。樽を使わないからあっさいしているのかというと、実は果実味豊かでリッチ系のあじわい。でももちろんきれいさもあります。
サンタ・バーバラのマージェラムのローヌ系ブレンド「M5」。赤と白があり、どちらも秀逸でした。
関係者の皆さん、お疲れさまでした。
カリフォルニアワインの大試飲会「Aliveテイスティング」で美味しかったワイン、気になったワインを紹介します。なにしろワインが全部で700種類を超えるという大きな試飲会なので、さすがに全部を試飲することはできず、試飲したインポーターのものに限られていることをご承知おきください。

エレメンタル・ワインズ(Element「AL」 Wines)というのはコスパワインで有名なボーグルの新ブランド。リサイクルが容易で軽量なアルミニウムを使ったボトルです。長期熟成向きではありませんが、同社でのテストでは1年以内ではガラス瓶との品質的な差はなかったとのことです。ピノ・グリージョ、シャルドネ、ロゼ、ピノ・ノワールとありますが、個人的にはアルコール度数が11%と低く、さわやかでさっぱりと飲めるピノ・グリージョが一番イメージに合っている感じがしました。
写真なしですが、ボーグルのワインでは2022年のシャルドネも良かったです。どちらかというとリッチ系の味わい。2600円はコスパ高いです。

ザ・ヴァイス(The Vice)のオレンジ・オブ・アルバリーニョ。うまみたっぷりでさわやかさもあり美味しい。5200円。

C.G.ディアーリのジンファンデル。甘々系でなくバランスよい造り。3500円は非常にコスパ高いです。

ベンジャミン・シルバーのレッド・ブレンド(6000円)。複雑さあり、酸がきれい。

シックス・クローヴズの扱いは布袋ワインズから都光に変わりましたが、ワインは代わりありません。リンダヴィスタはスティーブマサイアソンの畑。ここのシャルドネは定番です。2022年はきれいでアロマティック、2023年はうまみを強く感じ、酸がやや高い。12000円。

懐かしのサンフォード。シャルドネはリッチですが、酸も高くきれい。ピノ・ノワールはバランスよく華やか。

ボーエン(Boen)は、ナパのケイマスのオーナーであるワグナー家のピノ・ノワールとシャルドネのブランド。かつてのメイオミ(Meiomi)の後継という位置づけです。ワグナー家のワインというとかなり濃いイメージがありますが、ここのシャルドネとピノはリッチではありますが、バランスよく美味しい。

冷涼なエドナ・ヴァレーで白品種を造るタンジェント。ソーヴィニヨン・ブラン、アルバリーニョ、ピノグリ、グリューナー・フェルトリーナー(これだけゾッカーブランド)がありますが、ソーヴィニヨン・ブランとアルバリーニョがお薦め。どちらも香り豊かで酸のきれいさが際立ちます。

ウィプラッシュ(Whiplash)は、ブレッド&バタ―で知られるWX Brandsの造るワインの一つ。WX Brandsのワインメーカーであるリンダ・トロッタは2018年にはノースベイ・ビジネス・ジャーナルによるナパヴァレー・ワインメーカー・オブ・ザ・イヤーに選ばれています。シャルドネ、ピノ・ノワール、ジンファンデル、カベルネ・ソーヴィニヨンが出ていましたが、個人的にはジンファンデルが良かったです(3500円)。果実味豊かですが、ストラクチャーもあり、エレガントにすら感じます。

エドナ・ヴァレーからもう一つバイリヤーナ(Baileyana)のシャルドネ(6000円)を紹介します。柑橘系の豊かな果実味にミネラル感があり、エドナヴァレーらしい酸もすばらしい。

アンディ・エリクソンがコンサルタントを務めるアルファオメガのソーヴィニヨン・ブラン(7400円)。パソロブレスのソーヴィニヨン・ブランは珍しいですが、あえてメジャー産地でないところのブドウを発掘するのがアンディ・エリクソンらしいところ(彼のリヴァイアサンもナパ以外のブドウで秀逸なボルドー系ブレンドを作っています)。ブラインドで飲んだらナパの高級ソーヴィニヨン・ブランと答えそうな、リッチな果実味と上品な酸があります。

ダットン・エステートのシャルドネ(11000円)。ソノマのグリーン・ヴァレー、ロシアン・リバー・ヴァレーに多数の畑を持つダットン・ランチの自社ブランド。さすがのレベルの高さです。

この試飲会のカベルネ系ワインの中でベストだったのが、この2つ。超有名コンサルタントのミシェル・ロランが自分の名前を付けて造る世界で唯一のワイナリーです。MRはカベルネ・ソーヴィニヨン(46000円)。ベクストファー・ト・カロンのブドウを使っているようです。リッチで芳醇。オークヴィルのカベルネのお手本的なワイン。ザ・ディベイト(The Debate,
40000円)は同じベクストファー・ト・カロンの畑ですが品種はカベルネ・フラン。ベクストファー・ト・カロンの畑の中でもカベルネ・フランは1割しかないとのこと。カベルネ・ソーヴィニヨン以上にリッチでタニック。パワフルなワイン。生産量はわずか100ケース。これは熟成させたらすごいワインになりそうです。
長くなるので、とりあえずここまで。
エレメンタル・ワインズ(Element「AL」 Wines)というのはコスパワインで有名なボーグルの新ブランド。リサイクルが容易で軽量なアルミニウムを使ったボトルです。長期熟成向きではありませんが、同社でのテストでは1年以内ではガラス瓶との品質的な差はなかったとのことです。ピノ・グリージョ、シャルドネ、ロゼ、ピノ・ノワールとありますが、個人的にはアルコール度数が11%と低く、さわやかでさっぱりと飲めるピノ・グリージョが一番イメージに合っている感じがしました。
写真なしですが、ボーグルのワインでは2022年のシャルドネも良かったです。どちらかというとリッチ系の味わい。2600円はコスパ高いです。
ザ・ヴァイス(The Vice)のオレンジ・オブ・アルバリーニョ。うまみたっぷりでさわやかさもあり美味しい。5200円。
C.G.ディアーリのジンファンデル。甘々系でなくバランスよい造り。3500円は非常にコスパ高いです。
ベンジャミン・シルバーのレッド・ブレンド(6000円)。複雑さあり、酸がきれい。
シックス・クローヴズの扱いは布袋ワインズから都光に変わりましたが、ワインは代わりありません。リンダヴィスタはスティーブマサイアソンの畑。ここのシャルドネは定番です。2022年はきれいでアロマティック、2023年はうまみを強く感じ、酸がやや高い。12000円。
懐かしのサンフォード。シャルドネはリッチですが、酸も高くきれい。ピノ・ノワールはバランスよく華やか。
ボーエン(Boen)は、ナパのケイマスのオーナーであるワグナー家のピノ・ノワールとシャルドネのブランド。かつてのメイオミ(Meiomi)の後継という位置づけです。ワグナー家のワインというとかなり濃いイメージがありますが、ここのシャルドネとピノはリッチではありますが、バランスよく美味しい。
冷涼なエドナ・ヴァレーで白品種を造るタンジェント。ソーヴィニヨン・ブラン、アルバリーニョ、ピノグリ、グリューナー・フェルトリーナー(これだけゾッカーブランド)がありますが、ソーヴィニヨン・ブランとアルバリーニョがお薦め。どちらも香り豊かで酸のきれいさが際立ちます。
ウィプラッシュ(Whiplash)は、ブレッド&バタ―で知られるWX Brandsの造るワインの一つ。WX Brandsのワインメーカーであるリンダ・トロッタは2018年にはノースベイ・ビジネス・ジャーナルによるナパヴァレー・ワインメーカー・オブ・ザ・イヤーに選ばれています。シャルドネ、ピノ・ノワール、ジンファンデル、カベルネ・ソーヴィニヨンが出ていましたが、個人的にはジンファンデルが良かったです(3500円)。果実味豊かですが、ストラクチャーもあり、エレガントにすら感じます。
エドナ・ヴァレーからもう一つバイリヤーナ(Baileyana)のシャルドネ(6000円)を紹介します。柑橘系の豊かな果実味にミネラル感があり、エドナヴァレーらしい酸もすばらしい。
アンディ・エリクソンがコンサルタントを務めるアルファオメガのソーヴィニヨン・ブラン(7400円)。パソロブレスのソーヴィニヨン・ブランは珍しいですが、あえてメジャー産地でないところのブドウを発掘するのがアンディ・エリクソンらしいところ(彼のリヴァイアサンもナパ以外のブドウで秀逸なボルドー系ブレンドを作っています)。ブラインドで飲んだらナパの高級ソーヴィニヨン・ブランと答えそうな、リッチな果実味と上品な酸があります。
ダットン・エステートのシャルドネ(11000円)。ソノマのグリーン・ヴァレー、ロシアン・リバー・ヴァレーに多数の畑を持つダットン・ランチの自社ブランド。さすがのレベルの高さです。
この試飲会のカベルネ系ワインの中でベストだったのが、この2つ。超有名コンサルタントのミシェル・ロランが自分の名前を付けて造る世界で唯一のワイナリーです。MRはカベルネ・ソーヴィニヨン(46000円)。ベクストファー・ト・カロンのブドウを使っているようです。リッチで芳醇。オークヴィルのカベルネのお手本的なワイン。ザ・ディベイト(The Debate,
40000円)は同じベクストファー・ト・カロンの畑ですが品種はカベルネ・フラン。ベクストファー・ト・カロンの畑の中でもカベルネ・フランは1割しかないとのこと。カベルネ・ソーヴィニヨン以上にリッチでタニック。パワフルなワイン。生産量はわずか100ケース。これは熟成させたらすごいワインになりそうです。
長くなるので、とりあえずここまで。
ここ数年、話題の絶えないフリーマン・ヴィンヤード&ワイナリー(Freeman Vineyard & Winery)と、そのオーナーでワインメーカーのアキコ・フリーマンさんですが、ワインメーカーが交代することが発表されました。新しいワインメーカーは赤星映司ダニエルさん。アキコさんは、ディレクター・オブ・ワインメイキングとして携わっていきます。

近年のフリーマン関係の記事をまとめておきます。
「レイト・ディスゴージやロゼ・スパークリングも造ってます」――フリーマン・アキコさんに訊く
フリーマンのアキコさん、農業への功績で表彰 国外女性では初
フリーマン夫妻、ハリス副大統領と岸田首相の昼食会招待で「仰天」
アキコ・フリーマンさんにまたも名誉、女性の「優秀ワイン醸造賞」受賞
フリーマンの新作リースリングなどをアキコさんと味わう

赤星さんはブラジルの生まれ、幼少期をチリで過ごし、ハワイ大学で生物学を学びました。日本には2年ほど住んだことがあり、会話は日本語で大丈夫ですが、読み書きは苦手とのことです。小さいころから周りのものを触って匂いを嗅いだり、味を確かめたりといったことが好きで、その経験がワインメーカーとして生きているそうです。幼少のころから家にはワインがあり、赤星さんもワインに親しんでいました。大学の卒業にあたって進路で悩んでいるときに、好きなワインと生物学を結びつけるものとしてワインメーカーになることを志し、改めてカリフォルニアでワインの勉強をしました。醸造を学んだカリフォルニア大学フレズノ校はアキコさんの師匠のエド・カーツマンの母校でもあり、エド・カーツマンの講義を赤星さんが受講したことがあると、以前聞いております。
ところで、カリフォルニアに来るときに、親戚でワインを造っていた人がいたらしいと聞き、調べてわかったのが長沢鼎との関係でした。長沢鼎は江戸時代末期に薩摩藩から英国に渡り、そこからニューヨーク、ソノマと渡り住んで「ブドウ王」とまで呼ばれた人です(カリフォルニアの「ブドウ王」長沢鼎のセミナーに参加しました、カリフォルニアの「ブドウ王」を産んだのは「あさが来た」の五代さんだったというびっくりぽんな話などを参照)。長沢が作ったワイナリー「ファウンテングローヴ(Fountaingrove)」は現在はAVAの名称として残っています。赤星さんは、親戚でワイン造りをするのは自分が最初かと思っていたら、大いなる先人がいたことがわかり驚いたそうです。赤星さんの曾祖父に当たる赤星鉄馬さんは、実際にファウンテングローヴを訪問しており、写真も残っています。


ワインメーカーとしては、グリーン&レッドやロンバウアーなどナパのワイナリーで働くことが多く、ソノマとは縁遠かったのですが、本人はピノ・ノワールが好きで、十数年前に日系のワイン業界の集まりで飲んだフリーマンのピノ・ノワールが鳥肌が立つほどおいしく、記憶に残っていたそうです。そして共通の知人からフリーマンがワインメーカーを探していることを聞き、メールで応募しました。その後カフェテリアで1時間半ほど話をし、最後にアキコさんが「うん、いいんじゃない」と言いました。それが採用OKとの意味でした。
2023年、24年と2ヴィンテージ一緒に作った感想として、アキコさんと赤星さんのワインの方向性がとても似ていることが分かったそうです。また、フリーマンでは毎年、ピノ・ノワールのトップキュベである「アキコズキュベ」のブレンドを、初代ワインメーカーのエド・カーツマンさんなど数人で作り、一番人気だったものを選んでいます。過去20年間ずっとアキコさんが勝ち続けていたのですが、2024年はアキコさんが自分の作ったブレンドだと思ったのが赤星さんので、それが選ばれたそうです。これも、ワインメーカーとして今後をゆだねるにあたって大きな意味があったようです。

このほかにも、アキコさんと赤星さんには縁があることがその後分かりました。写真の六本木にある国際文化会館。この敷地は岩崎弥太郎の家があったところですが、アキコさんの祖母が岩崎弥太郎の長女の姪なのです。そして、岩崎弥太郎にこの土地を売ったのが上記の赤星鉄馬だったのです。関東大震災で鉄馬の家が壊れてしまい、別のところに引っ越すときに弥太郎に譲ったという経緯でした。このことがわかって赤星さんがアキコさんにメッセージで伝えると「100年ぶりの再会ですね」と返事がきたということでした。
このように、様々な縁でつながった今回のワインメーカー就任。今後のフリーマンのワインにもさらに期待したいと思います。また、今回明らかになったのが、フリーマンに第3の畑ができるというニュース。アキコさんが東京に来ている間にケンさんから急に「買ったよ」という連絡が来たそうです。場所はおそらく下の地図でLittoraiのLの字のあたりではないかと思います。リトライの畑や幻ワイナリーの近くです。AVAでいうとロシアン・リバー・ヴァレーですが、現在セバストポール・ヒルズ(Sebastopol Hills)としてAVA申請している地域になります。まだブドウ畑でもなくリンゴ畑だったところであり、リンゴを引き抜くところから始めています。シャルドネやリースリングなど白品種の畑にしたいとのことです。おそらくここのワインがリリースされるのは4、5年後だと思いますが、ここが立ち上がるとエステートのブドウだけで95%くらいまかなえるようになるそうです。

ワインメーカー就任の発表会の後はテイスティングです。今回は特に新しいワインがあるわけではありませんが、ハリス前副大統領とのランチで提供したワイン3種などもありました。
・2022 光風リースリング ソノマ・コースト
「酸フェチ」だというアキコさんらしい、ドライで酸がきりりとしたリースリング。リンゴのさわやかさに、ピーチの熟した果実の風味もあります。ちょっとオイリーなテクスチャーが高級感を醸し出します。最初に試飲したのがちょうど1年前ですが、そのときよりも酸の落ち着きが感じられました。畑はロス・コブのアビゲイル。
次は2024年米国副大統領ランチの3本です。
・ 2020 ユーキ・エステートブラン・ド・ブランソノマ・コースト
このワインも3年ほど前のリリース時にいただいています。その後も何度か試飲しています。当初はスリムで鮮烈な酸が印象的でしたが、こちらも酸が大分落ち着いて、果実のうまみが出てきています。花の香りや白桃、オレンジピール。今が一番飲みごろかもしれません(と書きつつ、自分が持っているのはもう1年くらい寝かそうと思っています)。ブランドブランはこれが最初で、今後は予定がないため、貴重なワインです。
・ 2022 涼風シャルドネグリーン・ヴァレー・オブ・ロシアン・リヴァー・ヴァレー
このワインも先月、シャルドネ・セミナーで飲んでいます。柑橘に花梨、ビスケットの風味が心地よい、酸も高すぎず美味しいシャルドネです。畑はチャールズ・ハインツとダットン。
・ 2021 アキコズ・キュヴェピノ・ノワールウエスト・ソノマ・コースト
いつもながらバランスの良さを感じるワイン。赤系果実の香り豊かで酸もきれい。エレガント系ピノとして秀逸です。
最後に自社畑のピノ・ノワール2つです。
・ 2019 グロリア・エステート「輝」ピノ・ノワールグリーン・ヴァレー・オブ・ロシアン・リヴァー・ヴァレー
カリフォルニアらしい豊かな果実味を持つピノ・ノワール。赤い果実に、シナモンなどのスパイスを感じます。ロシアン・リバー・ヴァレーらしいワインといってもいいでしょう。
・2019 ユーキ・エステートピノ・ノワールソノマ・コースト
ユーキ・ヴィンヤードはウエスト・ソノマ・コーストの畑。このヴィンテージはまだウエスト・ソノマ・コーストが認定される前だったのでソノマ・コースト表記になっています。冷涼さと、「セイボリー」と言われるようなキノコ系のうまみやハーブの風味が特徴です。カシスやザクロなど果実の熟度もあり酸が豊か。

近年のフリーマン関係の記事をまとめておきます。
「レイト・ディスゴージやロゼ・スパークリングも造ってます」――フリーマン・アキコさんに訊く
フリーマンのアキコさん、農業への功績で表彰 国外女性では初
フリーマン夫妻、ハリス副大統領と岸田首相の昼食会招待で「仰天」
アキコ・フリーマンさんにまたも名誉、女性の「優秀ワイン醸造賞」受賞
フリーマンの新作リースリングなどをアキコさんと味わう

赤星さんはブラジルの生まれ、幼少期をチリで過ごし、ハワイ大学で生物学を学びました。日本には2年ほど住んだことがあり、会話は日本語で大丈夫ですが、読み書きは苦手とのことです。小さいころから周りのものを触って匂いを嗅いだり、味を確かめたりといったことが好きで、その経験がワインメーカーとして生きているそうです。幼少のころから家にはワインがあり、赤星さんもワインに親しんでいました。大学の卒業にあたって進路で悩んでいるときに、好きなワインと生物学を結びつけるものとしてワインメーカーになることを志し、改めてカリフォルニアでワインの勉強をしました。醸造を学んだカリフォルニア大学フレズノ校はアキコさんの師匠のエド・カーツマンの母校でもあり、エド・カーツマンの講義を赤星さんが受講したことがあると、以前聞いております。
ところで、カリフォルニアに来るときに、親戚でワインを造っていた人がいたらしいと聞き、調べてわかったのが長沢鼎との関係でした。長沢鼎は江戸時代末期に薩摩藩から英国に渡り、そこからニューヨーク、ソノマと渡り住んで「ブドウ王」とまで呼ばれた人です(カリフォルニアの「ブドウ王」長沢鼎のセミナーに参加しました、カリフォルニアの「ブドウ王」を産んだのは「あさが来た」の五代さんだったというびっくりぽんな話などを参照)。長沢が作ったワイナリー「ファウンテングローヴ(Fountaingrove)」は現在はAVAの名称として残っています。赤星さんは、親戚でワイン造りをするのは自分が最初かと思っていたら、大いなる先人がいたことがわかり驚いたそうです。赤星さんの曾祖父に当たる赤星鉄馬さんは、実際にファウンテングローヴを訪問しており、写真も残っています。


ワインメーカーとしては、グリーン&レッドやロンバウアーなどナパのワイナリーで働くことが多く、ソノマとは縁遠かったのですが、本人はピノ・ノワールが好きで、十数年前に日系のワイン業界の集まりで飲んだフリーマンのピノ・ノワールが鳥肌が立つほどおいしく、記憶に残っていたそうです。そして共通の知人からフリーマンがワインメーカーを探していることを聞き、メールで応募しました。その後カフェテリアで1時間半ほど話をし、最後にアキコさんが「うん、いいんじゃない」と言いました。それが採用OKとの意味でした。
2023年、24年と2ヴィンテージ一緒に作った感想として、アキコさんと赤星さんのワインの方向性がとても似ていることが分かったそうです。また、フリーマンでは毎年、ピノ・ノワールのトップキュベである「アキコズキュベ」のブレンドを、初代ワインメーカーのエド・カーツマンさんなど数人で作り、一番人気だったものを選んでいます。過去20年間ずっとアキコさんが勝ち続けていたのですが、2024年はアキコさんが自分の作ったブレンドだと思ったのが赤星さんので、それが選ばれたそうです。これも、ワインメーカーとして今後をゆだねるにあたって大きな意味があったようです。

このほかにも、アキコさんと赤星さんには縁があることがその後分かりました。写真の六本木にある国際文化会館。この敷地は岩崎弥太郎の家があったところですが、アキコさんの祖母が岩崎弥太郎の長女の姪なのです。そして、岩崎弥太郎にこの土地を売ったのが上記の赤星鉄馬だったのです。関東大震災で鉄馬の家が壊れてしまい、別のところに引っ越すときに弥太郎に譲ったという経緯でした。このことがわかって赤星さんがアキコさんにメッセージで伝えると「100年ぶりの再会ですね」と返事がきたということでした。
このように、様々な縁でつながった今回のワインメーカー就任。今後のフリーマンのワインにもさらに期待したいと思います。また、今回明らかになったのが、フリーマンに第3の畑ができるというニュース。アキコさんが東京に来ている間にケンさんから急に「買ったよ」という連絡が来たそうです。場所はおそらく下の地図でLittoraiのLの字のあたりではないかと思います。リトライの畑や幻ワイナリーの近くです。AVAでいうとロシアン・リバー・ヴァレーですが、現在セバストポール・ヒルズ(Sebastopol Hills)としてAVA申請している地域になります。まだブドウ畑でもなくリンゴ畑だったところであり、リンゴを引き抜くところから始めています。シャルドネやリースリングなど白品種の畑にしたいとのことです。おそらくここのワインがリリースされるのは4、5年後だと思いますが、ここが立ち上がるとエステートのブドウだけで95%くらいまかなえるようになるそうです。

ワインメーカー就任の発表会の後はテイスティングです。今回は特に新しいワインがあるわけではありませんが、ハリス前副大統領とのランチで提供したワイン3種などもありました。
・2022 光風リースリング ソノマ・コースト
「酸フェチ」だというアキコさんらしい、ドライで酸がきりりとしたリースリング。リンゴのさわやかさに、ピーチの熟した果実の風味もあります。ちょっとオイリーなテクスチャーが高級感を醸し出します。最初に試飲したのがちょうど1年前ですが、そのときよりも酸の落ち着きが感じられました。畑はロス・コブのアビゲイル。
次は2024年米国副大統領ランチの3本です。
・ 2020 ユーキ・エステートブラン・ド・ブランソノマ・コースト
このワインも3年ほど前のリリース時にいただいています。その後も何度か試飲しています。当初はスリムで鮮烈な酸が印象的でしたが、こちらも酸が大分落ち着いて、果実のうまみが出てきています。花の香りや白桃、オレンジピール。今が一番飲みごろかもしれません(と書きつつ、自分が持っているのはもう1年くらい寝かそうと思っています)。ブランドブランはこれが最初で、今後は予定がないため、貴重なワインです。
・ 2022 涼風シャルドネグリーン・ヴァレー・オブ・ロシアン・リヴァー・ヴァレー
このワインも先月、シャルドネ・セミナーで飲んでいます。柑橘に花梨、ビスケットの風味が心地よい、酸も高すぎず美味しいシャルドネです。畑はチャールズ・ハインツとダットン。
・ 2021 アキコズ・キュヴェピノ・ノワールウエスト・ソノマ・コースト
いつもながらバランスの良さを感じるワイン。赤系果実の香り豊かで酸もきれい。エレガント系ピノとして秀逸です。
最後に自社畑のピノ・ノワール2つです。
・ 2019 グロリア・エステート「輝」ピノ・ノワールグリーン・ヴァレー・オブ・ロシアン・リヴァー・ヴァレー
カリフォルニアらしい豊かな果実味を持つピノ・ノワール。赤い果実に、シナモンなどのスパイスを感じます。ロシアン・リバー・ヴァレーらしいワインといってもいいでしょう。
・2019 ユーキ・エステートピノ・ノワールソノマ・コースト
ユーキ・ヴィンヤードはウエスト・ソノマ・コーストの畑。このヴィンテージはまだウエスト・ソノマ・コーストが認定される前だったのでソノマ・コースト表記になっています。冷涼さと、「セイボリー」と言われるようなキノコ系のうまみやハーブの風味が特徴です。カシスやザクロなど果実の熟度もあり酸が豊か。
3月4日に、東京で行われたAliveテイスティングの生産者セミナーに出席しました。セミナーは午前と午後と2回行われて、それぞれ生産者が異なっていますが、私が参加した午前の部は
モデレーター/パネリスト:Greg Brewer, Brewer-Clifton
パネリスト:Spencer Shull, Fess Parker Winery
Isabelle Clendenen, Au Bon Climat
Pierre LaBarge, LaBarge Winery
AJ Fairbanks, Crown Point Vineyards
の5人でした。ただ、Pierre LaBargeさんは家庭の事情で急遽来日が取りやめになり、ビデオでの参加でした。
サンタ・バーバラ郡は、ロスアンゼルスから北に2時間ほどドライブしたところにあります。セントラル・コーストの一番南であり、約20年前のアカデミー賞脚色賞受賞映画「サイドウェイ」の舞台になったことでも知られています。

サンタ・バーバラがカリフォルニアの中でも特別なのは東西方向の海岸線を持っていること。大半が南北方向の海岸線のカリフォルニアで、ここだけが南北から直角に東西に折れ曲がる形になっています。沿岸に沿って走る沿岸山脈も東西方向に走るため、西の太平洋から山脈に遮られずに冷たい風が入ってくる、冷涼地域です。

また、緯度の低さから夏と冬との気温差が非常に小さいのも特徴で、ブドウの芽は早いところでは2月に芽吹くほど。カリフォルニアの中でも特に長い生育シーズンを誇ります。
域内には上の地図で示したように7つのAVAがあります。
ブドウ畑の面積は11000エーカー以上で、栽培品種は多い順に、シャルドネ、ピノ・ノワール、シラー、ソーヴィニヨン・ブラン、カベルネ・ソーヴィニヨン。合計75品種が作られています。
AVAの説明をしていきます。

サンタ・マリア・ヴァレーはカリフォルニアでナパヴァレーの次に策定された古いAVA。サンタ・バーバラのAVAの中では一番北になります。ここは何といっても銘醸畑ビエン・ナシード(Bien Nacido)があるところとして知られています。オー・ボン・クリマ(Au Bon Climat)も昔からここのブドウを多く使っており、ワイナリーも畑の横にあります。オー・ボン・クリマの自社畑ル・ボン・クリマや、ビエン・ナシードのオーナーであるミラー家のもう一つの畑ソロモン・ヒルズもこのAVA内です。

サンタ・イネズ・ヴァレーはサンタ・マリアと対をなす南側のAVAです。前述のように西の太平洋からの風が入ってくるのが特徴ですが、東の内陸に行くとどんどん気温が上がっていきます。ここの西端と東端では気温が大きくことなります。このように一つのAVAとして語るのが難しく、現在はこの中にさらに4つのAVAが作られています。現在ではサンタ・イネズと名乗るワインも減ってきているので、サブAVAで見ていきましょう。

サンタ・リタ・ヒルズはサンタ・イネズ内のAVAとしては一番西に在り、冷涼な地域です。海からの強い風が吹くことでも知られており、海風による塩味がワインに感じられることもしばしばあります。砂質土壌やチョーク質の珪藻土の土壌などが特徴となっています。今回のモデレーターであるグレッグ・ブリュワーのブリュワー・クリフトン、グレッグが以前ワインメーカーを務めていたメルヴィル、近年高品質のピノ・ノワールで人気急上昇のドメーヌ・ド・ラ・コート、スクリーミング・イーグルのオーナーが持つザ・ヒルトなど、人気ワイナリーが数多くあります。また、サンタ・マリア・ヴァレーのビエンナシードと並び称される銘醸畑サンフォード&ベネディクトがこのAVAにあります。

一つ内陸に入ったバラード・キャニオンは、カリフォルニアでは珍しい石灰岩の土壌があり、ローヌ系品種で知られています。ザ・ヒルトの兄弟ワイナリーであるホナタ(Jonata)が有名です。

バラード・キャニオンの東にあるロス・オリヴォス・ディストリクトはソーヴィニヨン・ブランやカベルネ・フラン、メルロー、ローヌ系品種などが作られています。

サンタ・イネズ・ヴァレーのサブAVAの中で一番内陸にある(すなわち、一番暖かい)のがハッピー・キャニオンです。ボルドー品種が中心に植えられています。国内で人気のワイナリー、スター・レーン(Star Lane)がこの地域にあります。

最後に紹介するAVAはアリソス・キャニオン。サンタ・イネズ・ヴァレーと、サンタ・マリア・ヴァレーに挟まれたところにあります。ここは2020年に策定された新しいAVAということもあり、様々な品種が実験的に栽培されています。例えばピクプールやメンシアといった、あまり有名でない品種も作られています。
続いて、セミナーに参加した個々のワイナリーの紹介です。

最初はフェス・パーカー(Fess Parker)。サンタ・バーバラのワイナリー団体に11番目に加盟した比較的古いワイナリーです。サンタ・リタ・ヒルズとサンタ・マリア・ヴァレーのブルゴーニュ品種、自社畑でのローヌ品種のワインを主に使っています。
ワイナリーはロス・オリボスにありますが、今回のワインはサンタ・リタ・ヒルズの自社畑アシュリーズ(Ashley's)のシャルドネ2023。太平洋から20kmで、砂質土壌。土壌が太陽からの熱を蓄えています。2023年は冷涼な年で、非常に生育期間が長く、収穫は11月の第1週! 100%樽発酵(37%新樽)で7カ月熟成しています。柑橘系の風味に、わずかにアプリコット。ブリオッシュ。リッチで豊かな風味ですが酸もしっかりあってバランスはいい。なめらかなテクスチャで、美味しいシャルドネでした。

次のワインは、モデレーターでもあるグレッグ・ブリュワーのブリュワー・クリフトンから2023年のサンタ・リタ・ヒルズ ピノ・ノワール。サンタ・リタ・ヒルズの4つの自社畑のブドウをブレンドしたものです。
ブリュワー・クリフトンは1996年にスティーブ・クリフトン(2016年にブリュワー・クリフトンをやめ自身のプロジェクトに専念)とともに設立しました。当時はグレッグはまだ25歳で全財産は12000ドル。それをすべて注ぎ込んでサンタ・リタ・ヒルズのワインに人生を賭けてきました。その過程では多くの人の手助けがありました。例えば、上記のフェス・パーカーを営むスペンサー家からは、安価で樽を分けてもらい、オー・ボン・クリマのジム・クレンデネンさんは世界中にサンタ・バーバラのワインをプロモートしてくれました。また、このセミナーには登壇していませんが、一緒に来日したマージェラムのダグ・マージェラムさんにも特別の感謝をささげました。ダグ・マージェラムさんはワイナリー以上にサンタ・バーバラのワインカスクというレストランのオーナーとして知られています。ワインカスクはサンタ・バーバラのワインの集積地であり、ほぼすべてのワイナリーがここで紹介されて世に広まっていっています。

実はブリュワー・クリフトンのラベルのロゴはワインカスクの天井の装飾を模したものだとのことで、それだけワインカスクとの深い結びつきがあることを示しています。
ブリュワー・クリフトンのコンセプトは土地に敬意を払い、捧げるというもの。ワイナリー設立当初から、テロワールの表現にこだわり、すべてのワインを同じレシピで造っていました(「復刻:2004年のBrewer-Cliftonワイン会実録」に2004年にうかがった話をまとめています)。
もう一つのこだわりが全房発酵。全房発酵によって「タンニンやストラクチャー、うまみを与えてくれる」ことを期待しています。茎からカリウムが出ることによって、pHは上がるのですが、サンタ・リタ・ヒルズは冷涼で酸が保持されるため、酸が弱くなることはありません。また、熟成に使う樽は10~25年使った古いもの。いわゆる樽のフレーバーは全く付かないものです。
サンタ・リタ・ヒルズにはほかにもドメーヌ・ド・ラ・コート、メルヴィルと全房比率が高い有名ワイナリーがあります。サンタ・リタ・ヒルズはピュアな果実の風味が強く、丸みのある味わいになりがちです。茎を加えることでストラクチャーを与えたいというのが、サンタ・リタ・ヒルズのピノ・ノワールで全房を使う例が目立つ理由だそうです。
ワインを飲んでみると、確かに「セイボリー」と言われるようなうまみが感じられます。紅茶やキノコの風味もあります。赤果実と酸も上品で美味しい。果実味が爆発するようなワインではありませんが、ピノ・ノワール好きに刺さりそうな味わいです。

3番目はオー・ボン・クリマ。故ジム・クレンデネンの長女のイザベルさんが代表で話します。いうまでもなくオー・ボン・クリマのフラッグシップであるピノ・ノワール「イザベル」の名前の元となったイザベルさんです。彼女には11年前にもお会いしています(イザベル嬢にイザベル注いでもらったから2月18日はABC記念日)。マンガが好きで日本語を勉強しており、今回のプレゼンも日本語で行いました。オー・ボン・クリマは前述のジム・クレンデネンが1982年に設立したワイナリーです。ジムの死後は、イザベルと弟のノックス、ワインメーカーのジム・エデルマン、セラーマスターのエンリケ・ロドリゲスの4人のチームで運営しています。ノックス君は将来はワインメーカーを目指しているそうですが、「今はアシスタントのアシスタントくらい」とイザベルさん。ただ、それでも父が若かりしころ、サンタ・バーバラ(当時はZaka Mesaで働いていた)、ブルゴーニュ、オーストラリアの3カ所での収穫を1年で経験したというエピソードにあやかり、昨年はニュージーランド、ブルゴーニュ、カリフォルニアで収穫体験をしてきたそうです。今回はノックス君も来日して、試飲会でワインを注ぎ、姉弟で大人気でした。
さてワインはオー・ボン・クリマのピノ・ノワール ノックス・アレキサンダー2020です。ビエン・ナシードのブドウに、その隣のランウェイという畑、サンタ・マリアにオー・ボン・クリマが所有する自社畑ル・ボン・クリマを加えています。「イザベル」はサンタ・バーバラからソノマまで、カリフォルニアの沿岸各地の畑のブドウをブレンドした、ブレンドによって最良のピノを目指したワインであるのに対し、こちらはサンタ・マリア・ヴァレーで最良のピノ・ノワールを目指しています。
まろやかな味わいで紅茶に、ラズベリーやハーブ、ナツメグやカルダモンといったスパイスを感じるのがノックスの特徴です。
ワインの作り自体はブリュワー・クリフトンと好対照で、ブリュワー・クリフトンの新樽ゼロに対して、こちらは新樽100%での熟成を行っています。全房はほとんど使わず、このヴィンテージは25%となっています。ビエン・ナシードの畑には独特なスパイスの風味があり。そのため全房を入れるとちょっと味が強すぎてしまうのだそうです。サンタ・マリアは全体的に同じ傾向があり、同じサンタ・バーバラといってもサンタ・リタ・ヒルズと対照的です。ちなみに、オー・ボン・クリマでは唯一100%全房発酵で作っているワインとしてラームドクラップというピノ・ノワールがあります。茎が完熟した年にしか作らないレアなワインですが、これまではサンタ・リタ・ヒルズのサンフォード・ベネディクトのブドウで作っていました。ただし2020年だけは例外的にビエン・ナシードで作ったそうです。こちらは未試飲ですが、どういう味わいになるのか興味深いです。
4番目のワイナリーはラバージュ(LaBarge)。サンタ・リタ・ヒルズのワイナリーです。2009年にピエール・ラバージュ4世が「土地の個性を映し出すワインを造る」ことを目指して創業しました。17エーカーの自社畑では、アルバリーニョ、ピノ・ノワール、グルナッシュ、シラーを栽培。すべてCCOFによる有機認証を取得しています。
ワインはグルナッシュ2021。ピエールはシネクアノンで働いたことがあり、それでグルナッシュに興味を持ったそうです。シネクアノンの畑Eleven Confessionsもサンタ・リタ・ヒルズにありますが、温暖な気候を好むグルナッシュの栽培地域としては非常に冷涼。ラバージュではブドウの実を半分くらいに減らすことでブドウを完熟させています。一方で、日光が当たりすぎるとブドウの実が白くなってしまうなど、気難しいところもあり、他の品種の3倍近くの労力が必要な品種だとのことです。使っているグルナッシュのクローンは、エドナ・ヴァレーのアルバン由来のものとフランス由来のものがあり、フランスのものは全房発酵に向き、アルバンのものは実のつけ方がルースで除梗に向くとのこと。23%全房を使っています。
ラバージュではグルナッシュを「ステロイド入りピノ・ノワール」と呼んでいるそうで、確かにアルコール度数は15.4%と高く、タンニンもしっかりしています。ただ、酸が高くアルコール度数の高さを感じさせないエレガントさがあります。パワフルだけどエレガントという面白いワイン。

最後のワイナリーはクラウン・ポイント(Crown Point)。最も温暖なハッピー・キャニオンにあり、カベルネ・ソーヴィニヨンなどのボルドー品種を作っています。
畑のあるところは標高290mと比較的高く、南向きの斜度が30度もある斜面です。岩が多く表土が浅いため、収穫量が自然に抑えられます。
ワインは2021年のカベルネ・ソーヴィニヨン。評論家のジェブ・ダナックは「これはほぼ完璧と言える仕上がりで、おそらくサンタ・バーバラ郡で味わった最高のボルドーブレンドだ」として98点を付けています。カベルネ・ソーヴィニヨン97%にプティ・ヴェルドが3%。新樽率50%で22カ月熟成しています。
カシスやブルーベリー、やや甘やかさがあり、やわらかなテクスチャ。とてもいいカベルネです。


サンタ・バーバラのワインはオー・ボン・クリマを除くとまだまだ日本で知られていないところがたくさんあります。非常にレベルの高いワインが多く、ピノ・ノワールやシャルドネだけ見ても魅力的なワイナリーが多数あります。今年のテーマ産地を機会に、人気が広がることを期待します。
モデレーター/パネリスト:Greg Brewer, Brewer-Clifton
パネリスト:Spencer Shull, Fess Parker Winery
Isabelle Clendenen, Au Bon Climat
Pierre LaBarge, LaBarge Winery
AJ Fairbanks, Crown Point Vineyards
の5人でした。ただ、Pierre LaBargeさんは家庭の事情で急遽来日が取りやめになり、ビデオでの参加でした。
サンタ・バーバラ郡は、ロスアンゼルスから北に2時間ほどドライブしたところにあります。セントラル・コーストの一番南であり、約20年前のアカデミー賞脚色賞受賞映画「サイドウェイ」の舞台になったことでも知られています。

サンタ・バーバラがカリフォルニアの中でも特別なのは東西方向の海岸線を持っていること。大半が南北方向の海岸線のカリフォルニアで、ここだけが南北から直角に東西に折れ曲がる形になっています。沿岸に沿って走る沿岸山脈も東西方向に走るため、西の太平洋から山脈に遮られずに冷たい風が入ってくる、冷涼地域です。

また、緯度の低さから夏と冬との気温差が非常に小さいのも特徴で、ブドウの芽は早いところでは2月に芽吹くほど。カリフォルニアの中でも特に長い生育シーズンを誇ります。
域内には上の地図で示したように7つのAVAがあります。
ブドウ畑の面積は11000エーカー以上で、栽培品種は多い順に、シャルドネ、ピノ・ノワール、シラー、ソーヴィニヨン・ブラン、カベルネ・ソーヴィニヨン。合計75品種が作られています。
AVAの説明をしていきます。

サンタ・マリア・ヴァレーはカリフォルニアでナパヴァレーの次に策定された古いAVA。サンタ・バーバラのAVAの中では一番北になります。ここは何といっても銘醸畑ビエン・ナシード(Bien Nacido)があるところとして知られています。オー・ボン・クリマ(Au Bon Climat)も昔からここのブドウを多く使っており、ワイナリーも畑の横にあります。オー・ボン・クリマの自社畑ル・ボン・クリマや、ビエン・ナシードのオーナーであるミラー家のもう一つの畑ソロモン・ヒルズもこのAVA内です。

サンタ・イネズ・ヴァレーはサンタ・マリアと対をなす南側のAVAです。前述のように西の太平洋からの風が入ってくるのが特徴ですが、東の内陸に行くとどんどん気温が上がっていきます。ここの西端と東端では気温が大きくことなります。このように一つのAVAとして語るのが難しく、現在はこの中にさらに4つのAVAが作られています。現在ではサンタ・イネズと名乗るワインも減ってきているので、サブAVAで見ていきましょう。

サンタ・リタ・ヒルズはサンタ・イネズ内のAVAとしては一番西に在り、冷涼な地域です。海からの強い風が吹くことでも知られており、海風による塩味がワインに感じられることもしばしばあります。砂質土壌やチョーク質の珪藻土の土壌などが特徴となっています。今回のモデレーターであるグレッグ・ブリュワーのブリュワー・クリフトン、グレッグが以前ワインメーカーを務めていたメルヴィル、近年高品質のピノ・ノワールで人気急上昇のドメーヌ・ド・ラ・コート、スクリーミング・イーグルのオーナーが持つザ・ヒルトなど、人気ワイナリーが数多くあります。また、サンタ・マリア・ヴァレーのビエンナシードと並び称される銘醸畑サンフォード&ベネディクトがこのAVAにあります。

一つ内陸に入ったバラード・キャニオンは、カリフォルニアでは珍しい石灰岩の土壌があり、ローヌ系品種で知られています。ザ・ヒルトの兄弟ワイナリーであるホナタ(Jonata)が有名です。

バラード・キャニオンの東にあるロス・オリヴォス・ディストリクトはソーヴィニヨン・ブランやカベルネ・フラン、メルロー、ローヌ系品種などが作られています。

サンタ・イネズ・ヴァレーのサブAVAの中で一番内陸にある(すなわち、一番暖かい)のがハッピー・キャニオンです。ボルドー品種が中心に植えられています。国内で人気のワイナリー、スター・レーン(Star Lane)がこの地域にあります。

最後に紹介するAVAはアリソス・キャニオン。サンタ・イネズ・ヴァレーと、サンタ・マリア・ヴァレーに挟まれたところにあります。ここは2020年に策定された新しいAVAということもあり、様々な品種が実験的に栽培されています。例えばピクプールやメンシアといった、あまり有名でない品種も作られています。
続いて、セミナーに参加した個々のワイナリーの紹介です。
最初はフェス・パーカー(Fess Parker)。サンタ・バーバラのワイナリー団体に11番目に加盟した比較的古いワイナリーです。サンタ・リタ・ヒルズとサンタ・マリア・ヴァレーのブルゴーニュ品種、自社畑でのローヌ品種のワインを主に使っています。
ワイナリーはロス・オリボスにありますが、今回のワインはサンタ・リタ・ヒルズの自社畑アシュリーズ(Ashley's)のシャルドネ2023。太平洋から20kmで、砂質土壌。土壌が太陽からの熱を蓄えています。2023年は冷涼な年で、非常に生育期間が長く、収穫は11月の第1週! 100%樽発酵(37%新樽)で7カ月熟成しています。柑橘系の風味に、わずかにアプリコット。ブリオッシュ。リッチで豊かな風味ですが酸もしっかりあってバランスはいい。なめらかなテクスチャで、美味しいシャルドネでした。
次のワインは、モデレーターでもあるグレッグ・ブリュワーのブリュワー・クリフトンから2023年のサンタ・リタ・ヒルズ ピノ・ノワール。サンタ・リタ・ヒルズの4つの自社畑のブドウをブレンドしたものです。
ブリュワー・クリフトンは1996年にスティーブ・クリフトン(2016年にブリュワー・クリフトンをやめ自身のプロジェクトに専念)とともに設立しました。当時はグレッグはまだ25歳で全財産は12000ドル。それをすべて注ぎ込んでサンタ・リタ・ヒルズのワインに人生を賭けてきました。その過程では多くの人の手助けがありました。例えば、上記のフェス・パーカーを営むスペンサー家からは、安価で樽を分けてもらい、オー・ボン・クリマのジム・クレンデネンさんは世界中にサンタ・バーバラのワインをプロモートしてくれました。また、このセミナーには登壇していませんが、一緒に来日したマージェラムのダグ・マージェラムさんにも特別の感謝をささげました。ダグ・マージェラムさんはワイナリー以上にサンタ・バーバラのワインカスクというレストランのオーナーとして知られています。ワインカスクはサンタ・バーバラのワインの集積地であり、ほぼすべてのワイナリーがここで紹介されて世に広まっていっています。

実はブリュワー・クリフトンのラベルのロゴはワインカスクの天井の装飾を模したものだとのことで、それだけワインカスクとの深い結びつきがあることを示しています。
ブリュワー・クリフトンのコンセプトは土地に敬意を払い、捧げるというもの。ワイナリー設立当初から、テロワールの表現にこだわり、すべてのワインを同じレシピで造っていました(「復刻:2004年のBrewer-Cliftonワイン会実録」に2004年にうかがった話をまとめています)。
もう一つのこだわりが全房発酵。全房発酵によって「タンニンやストラクチャー、うまみを与えてくれる」ことを期待しています。茎からカリウムが出ることによって、pHは上がるのですが、サンタ・リタ・ヒルズは冷涼で酸が保持されるため、酸が弱くなることはありません。また、熟成に使う樽は10~25年使った古いもの。いわゆる樽のフレーバーは全く付かないものです。
サンタ・リタ・ヒルズにはほかにもドメーヌ・ド・ラ・コート、メルヴィルと全房比率が高い有名ワイナリーがあります。サンタ・リタ・ヒルズはピュアな果実の風味が強く、丸みのある味わいになりがちです。茎を加えることでストラクチャーを与えたいというのが、サンタ・リタ・ヒルズのピノ・ノワールで全房を使う例が目立つ理由だそうです。
ワインを飲んでみると、確かに「セイボリー」と言われるようなうまみが感じられます。紅茶やキノコの風味もあります。赤果実と酸も上品で美味しい。果実味が爆発するようなワインではありませんが、ピノ・ノワール好きに刺さりそうな味わいです。
3番目はオー・ボン・クリマ。故ジム・クレンデネンの長女のイザベルさんが代表で話します。いうまでもなくオー・ボン・クリマのフラッグシップであるピノ・ノワール「イザベル」の名前の元となったイザベルさんです。彼女には11年前にもお会いしています(イザベル嬢にイザベル注いでもらったから2月18日はABC記念日)。マンガが好きで日本語を勉強しており、今回のプレゼンも日本語で行いました。オー・ボン・クリマは前述のジム・クレンデネンが1982年に設立したワイナリーです。ジムの死後は、イザベルと弟のノックス、ワインメーカーのジム・エデルマン、セラーマスターのエンリケ・ロドリゲスの4人のチームで運営しています。ノックス君は将来はワインメーカーを目指しているそうですが、「今はアシスタントのアシスタントくらい」とイザベルさん。ただ、それでも父が若かりしころ、サンタ・バーバラ(当時はZaka Mesaで働いていた)、ブルゴーニュ、オーストラリアの3カ所での収穫を1年で経験したというエピソードにあやかり、昨年はニュージーランド、ブルゴーニュ、カリフォルニアで収穫体験をしてきたそうです。今回はノックス君も来日して、試飲会でワインを注ぎ、姉弟で大人気でした。
さてワインはオー・ボン・クリマのピノ・ノワール ノックス・アレキサンダー2020です。ビエン・ナシードのブドウに、その隣のランウェイという畑、サンタ・マリアにオー・ボン・クリマが所有する自社畑ル・ボン・クリマを加えています。「イザベル」はサンタ・バーバラからソノマまで、カリフォルニアの沿岸各地の畑のブドウをブレンドした、ブレンドによって最良のピノを目指したワインであるのに対し、こちらはサンタ・マリア・ヴァレーで最良のピノ・ノワールを目指しています。
まろやかな味わいで紅茶に、ラズベリーやハーブ、ナツメグやカルダモンといったスパイスを感じるのがノックスの特徴です。
ワインの作り自体はブリュワー・クリフトンと好対照で、ブリュワー・クリフトンの新樽ゼロに対して、こちらは新樽100%での熟成を行っています。全房はほとんど使わず、このヴィンテージは25%となっています。ビエン・ナシードの畑には独特なスパイスの風味があり。そのため全房を入れるとちょっと味が強すぎてしまうのだそうです。サンタ・マリアは全体的に同じ傾向があり、同じサンタ・バーバラといってもサンタ・リタ・ヒルズと対照的です。ちなみに、オー・ボン・クリマでは唯一100%全房発酵で作っているワインとしてラームドクラップというピノ・ノワールがあります。茎が完熟した年にしか作らないレアなワインですが、これまではサンタ・リタ・ヒルズのサンフォード・ベネディクトのブドウで作っていました。ただし2020年だけは例外的にビエン・ナシードで作ったそうです。こちらは未試飲ですが、どういう味わいになるのか興味深いです。
4番目のワイナリーはラバージュ(LaBarge)。サンタ・リタ・ヒルズのワイナリーです。2009年にピエール・ラバージュ4世が「土地の個性を映し出すワインを造る」ことを目指して創業しました。17エーカーの自社畑では、アルバリーニョ、ピノ・ノワール、グルナッシュ、シラーを栽培。すべてCCOFによる有機認証を取得しています。
ワインはグルナッシュ2021。ピエールはシネクアノンで働いたことがあり、それでグルナッシュに興味を持ったそうです。シネクアノンの畑Eleven Confessionsもサンタ・リタ・ヒルズにありますが、温暖な気候を好むグルナッシュの栽培地域としては非常に冷涼。ラバージュではブドウの実を半分くらいに減らすことでブドウを完熟させています。一方で、日光が当たりすぎるとブドウの実が白くなってしまうなど、気難しいところもあり、他の品種の3倍近くの労力が必要な品種だとのことです。使っているグルナッシュのクローンは、エドナ・ヴァレーのアルバン由来のものとフランス由来のものがあり、フランスのものは全房発酵に向き、アルバンのものは実のつけ方がルースで除梗に向くとのこと。23%全房を使っています。
ラバージュではグルナッシュを「ステロイド入りピノ・ノワール」と呼んでいるそうで、確かにアルコール度数は15.4%と高く、タンニンもしっかりしています。ただ、酸が高くアルコール度数の高さを感じさせないエレガントさがあります。パワフルだけどエレガントという面白いワイン。
最後のワイナリーはクラウン・ポイント(Crown Point)。最も温暖なハッピー・キャニオンにあり、カベルネ・ソーヴィニヨンなどのボルドー品種を作っています。
畑のあるところは標高290mと比較的高く、南向きの斜度が30度もある斜面です。岩が多く表土が浅いため、収穫量が自然に抑えられます。
ワインは2021年のカベルネ・ソーヴィニヨン。評論家のジェブ・ダナックは「これはほぼ完璧と言える仕上がりで、おそらくサンタ・バーバラ郡で味わった最高のボルドーブレンドだ」として98点を付けています。カベルネ・ソーヴィニヨン97%にプティ・ヴェルドが3%。新樽率50%で22カ月熟成しています。
カシスやブルーベリー、やや甘やかさがあり、やわらかなテクスチャ。とてもいいカベルネです。
サンタ・バーバラのワインはオー・ボン・クリマを除くとまだまだ日本で知られていないところがたくさんあります。非常にレベルの高いワインが多く、ピノ・ノワールやシャルドネだけ見ても魅力的なワイナリーが多数あります。今年のテーマ産地を機会に、人気が広がることを期待します。
ロバート・モンダヴィの2人の孫、カルロとダンテ・モンダヴィが作ったことで知られているソノマ・コーストのレイン(Raen)のピノ・ノワールとシャルドネに、ジェームズ・サックリングが驚くほどの高評価を付けています。2月5日付けの週間レポートで記事が公開されています(RAEN Magic, Plus Taming Barbaresco's Difficult 2022: Weekly Tasting Report | JamesSuckling.com)。日本にもこの2023ヴィンテージが入荷してきています。
2023 Freestone Occidental Bodega Pinot Noir: 100 points
2023 Fort Ross-Seaview Charles Ranch Chardonnay: 100 points
2023 Fort Ross-Seaview Sea Field Pinot Noir: 99 points
2023 Sonoma Coast Royal St. Robert Pinot Noir: 99 points
2023 Sonoma Coast Lady Marjorie Chardonnay: 99 points
レインのピノ・ノワールは2023年のワイン・スペクテーター年間4位に選ばれるなど、すでに高い評価を得ていますが、正直に言って、まだまだ日本ではプロも含めて知られていないのが実情です。2月にはカルロが来日していますが、ほとんど話題に上がっていないようでした(私はちょうどナパの試験と重なっていけませんでした)。
モンダヴィ一家といえば、ナパがメインフィールドであり、カルロとダンテの父であるティム・モンダヴィはナパのぷリチャード・ヒルのコンティニュアム(Continuum)でワインを造っていますが、カルロとダンテは父ティムがロバート・モンダヴィ時代に作ったピノ・ノワールや、祖父ロバートと一緒に訪問したブルゴーニュの生産者(ルフレーヴやDRC)に影響を受けて、ピノ・ノワールをメインにしたワインを造るために冷涼なソノマ・コーストに移りました。また、何よりも栽培が大事ということで、「ワイングローワー」と名乗っています。
レインのピノ・ノワールの一つの特徴が全房発酵をメインとすること。これについて、カルロ・モンダヴィは以前、インタビュー(これもジェームズ・サックリングでした)に答えてこう語っています。
全房による複雑さもあり、長期熟成も可能だと思いますが、親しみやすさも持つワインです。
そろそろブルゴーニュ愛好家にも見つかってしまうのではないかという気もしますが、もっと知られてほしいと思う半面、入手困難になってほしくないという微妙な気持ちもなきにしもあらずです。
以下、2023年のワイン3種です。ショップは全てウメムラです。
100点のピノ・ノワールです。
100点のシャルドネです。
99点のピノ・ノワール(ロイヤル・セント・ロバート・キュヴェ)です。ワインの名前は祖父ロバートに敬意を表して付けたものです。
2023 Freestone Occidental Bodega Pinot Noir: 100 points
2023 Fort Ross-Seaview Charles Ranch Chardonnay: 100 points
2023 Fort Ross-Seaview Sea Field Pinot Noir: 99 points
2023 Sonoma Coast Royal St. Robert Pinot Noir: 99 points
2023 Sonoma Coast Lady Marjorie Chardonnay: 99 points
レインのピノ・ノワールは2023年のワイン・スペクテーター年間4位に選ばれるなど、すでに高い評価を得ていますが、正直に言って、まだまだ日本ではプロも含めて知られていないのが実情です。2月にはカルロが来日していますが、ほとんど話題に上がっていないようでした(私はちょうどナパの試験と重なっていけませんでした)。
モンダヴィ一家といえば、ナパがメインフィールドであり、カルロとダンテの父であるティム・モンダヴィはナパのぷリチャード・ヒルのコンティニュアム(Continuum)でワインを造っていますが、カルロとダンテは父ティムがロバート・モンダヴィ時代に作ったピノ・ノワールや、祖父ロバートと一緒に訪問したブルゴーニュの生産者(ルフレーヴやDRC)に影響を受けて、ピノ・ノワールをメインにしたワインを造るために冷涼なソノマ・コーストに移りました。また、何よりも栽培が大事ということで、「ワイングローワー」と名乗っています。
レインのピノ・ノワールの一つの特徴が全房発酵をメインとすること。これについて、カルロ・モンダヴィは以前、インタビュー(これもジェームズ・サックリングでした)に答えてこう語っています。
私は、全房がすべてのブドウ園でうまく育つとは思いません。また、すべての状況、すべてのヴィンテージでうまく育つとも限りません。全房なら、潜在アルコール度数が 12.5 ~ 13 パーセントで、早期収穫が可能になりますが、通常、総酸度が非常に高いため、茎から外すと、角張ってざらざらしたワインになってしまいます。房なので、茎に少量のカリウムがあり、それが酒石酸と結合して酒石酸水素カリウムを形成し、pH をわずかに上昇させて、この素晴らしい質感を生み出します。香りの高揚、新鮮さ、明るさ、そして口当たりの質感と豊かさという、これらすべての要素が得られ、私はそれが大好きです。
全房による複雑さもあり、長期熟成も可能だと思いますが、親しみやすさも持つワインです。
そろそろブルゴーニュ愛好家にも見つかってしまうのではないかという気もしますが、もっと知られてほしいと思う半面、入手困難になってほしくないという微妙な気持ちもなきにしもあらずです。
以下、2023年のワイン3種です。ショップは全てウメムラです。
100点のピノ・ノワールです。
100点のシャルドネです。
99点のピノ・ノワール(ロイヤル・セント・ロバート・キュヴェ)です。ワインの名前は祖父ロバートに敬意を表して付けたものです。
ニールセンIQが1月に発表したデータによると、2024年の米国のワイン市場は苦戦が続いています。

赤ワイン、白ワイン、ロゼ、スパークリングのすべてのセグメントが前年比マイナス。比較的マシな白ワインが1.6%減でしが、あとは5%前後という大きなマイナスになっています。なおこのなかでイタリアのプロセッコだけは2.5%増と近年の好調が続いています。
ワイン関連の他のセグメントを含めた市場規模と前年比を示したのが次の図です。

酒/梅酒が1.8%増というのも興味深いですが、それよりも3割近く伸びているセグメントが二つあるのが目立ちます。一つが一番下のノンアルコール・ワイン、もう一つが上から3番目のワイン・ベースRTDです。
RTDとはReady-to-Drinkの略で、缶入り飲料などそのまま飲めるタイプの飲料を示します。
「The Wine-Based RTDs We Are Too Embarrassed to Talk About | Meininger's International」という記事によると、ワインベースのRTDは、BarefootやSutter Homeといった従来のワイナリーも出していますが、より伸びているのがイタリア発のStella Rosaというブランドだそうです。低アルコールで甘く、フルーツフレーバーというカクテル系のワインで、2023年には400万ケースを販売したとか。これはケンドール・ジャクソンなどの大手ワイナリーを上回っています。XXLというフレーバードワインも創設2年で350万ケースに達したとのこと。
これらのフレーバードワインは、従来のワインの文脈からは無視されていますが、このように実際には米国市場でかなりの存在感を示すようになっています。
一方で、日本でも「「酒離れ」でもワイン人気 缶のスパークリング、若者支持」という記事が日経に出ていましたが、缶入りスパークリングが10年で14倍の市場になったそうです。米国とタイプは違いますがこちらもRTD系であり、パッケージングのフォーマットなどが今後のワイン市場において、より重要になってくることがうかがえます。

赤ワイン、白ワイン、ロゼ、スパークリングのすべてのセグメントが前年比マイナス。比較的マシな白ワインが1.6%減でしが、あとは5%前後という大きなマイナスになっています。なおこのなかでイタリアのプロセッコだけは2.5%増と近年の好調が続いています。
ワイン関連の他のセグメントを含めた市場規模と前年比を示したのが次の図です。

酒/梅酒が1.8%増というのも興味深いですが、それよりも3割近く伸びているセグメントが二つあるのが目立ちます。一つが一番下のノンアルコール・ワイン、もう一つが上から3番目のワイン・ベースRTDです。
RTDとはReady-to-Drinkの略で、缶入り飲料などそのまま飲めるタイプの飲料を示します。
「The Wine-Based RTDs We Are Too Embarrassed to Talk About | Meininger's International」という記事によると、ワインベースのRTDは、BarefootやSutter Homeといった従来のワイナリーも出していますが、より伸びているのがイタリア発のStella Rosaというブランドだそうです。低アルコールで甘く、フルーツフレーバーというカクテル系のワインで、2023年には400万ケースを販売したとか。これはケンドール・ジャクソンなどの大手ワイナリーを上回っています。XXLというフレーバードワインも創設2年で350万ケースに達したとのこと。
これらのフレーバードワインは、従来のワインの文脈からは無視されていますが、このように実際には米国市場でかなりの存在感を示すようになっています。
一方で、日本でも「「酒離れ」でもワイン人気 缶のスパークリング、若者支持」という記事が日経に出ていましたが、缶入りスパークリングが10年で14倍の市場になったそうです。米国とタイプは違いますがこちらもRTD系であり、パッケージングのフォーマットなどが今後のワイン市場において、より重要になってくることがうかがえます。
トランプ大統領がカナダとメキシコからの輸入品に25%の関税をかけはじめたことを受け、カナダのLCBO(オンタリオ州酒類管理委員会)は米国産アルコール飲料の撤去を決めました。
オンタリオ州では毎年10憶ドル相当に上る米国産アルコール飲料を輸入していました。既に輸入して小売店に並んでいる分も当面倉庫などに保管するとのことです。
オンタリオ州クラフトビール協会(OCB)も、トランプ大統領の関税導入を受けて米国産アルコールを除外する動きを強く支持すると述べています。
カナダの他の州もこれに追随する方向です。
オンタリオ州では毎年10憶ドル相当に上る米国産アルコール飲料を輸入していました。既に輸入して小売店に並んでいる分も当面倉庫などに保管するとのことです。
オンタリオ州クラフトビール協会(OCB)も、トランプ大統領の関税導入を受けて米国産アルコールを除外する動きを強く支持すると述べています。
カナダの他の州もこれに追随する方向です。
レーヴェンズウッド(レイヴェンズウッド、Ravenswood)の創設者であり「ジンファンデルのゴッドファーザー」と呼ばれたジョエル・ピーターソンが、5年ぶりに同ワイナリーに復帰すると、ワイン・スペクテーターが報じています(Zinfandel Icon Ravenswood Returns After a 5-Year Hiatus)。

ジョエル・ピーターソンは1976年にレーヴェンズウッドを設立。「軟弱なワインは作らない(No Wimpy Wines)」をモットーに、独自のジンファンデルのスタイルを築きました。ただ、出資者との間の金銭的な問題により、2001年にコンステレーション・ブランズに売却。その後もワイナリーにはとどまっていましたが、生産するワインが、安価なヴィントナーズ・ブレンドに集中する中で、現場からは遠ざかるようになりました。そして2019年にコンステレーションが30以上のブランドをガロに売却する方針を発表し(ガロ、コンステレーションからフランシスカン、レイヴェンズウッドなど30以上のブランドを取得)、2020年にはワイナリーやテイスティングルームが閉鎖し、オールド・ヒル・ランチなど、古木の畑との契約も終了して実質的に休眠状態になっていました。
なお、この間、ジョエル・ピーターソンは新たにワンス・アンド・フューチャーというブランドを立ち上げ、オールド・ヒル・ランチを含む単一畑のジンファンデルなどを製造しています。
その後、ガロ家のマット・ガロがブランドの再生を図るため、ジョエルに接触してきました。当初は懐疑的だったそうですが、議論を重ねるうちにガロがまじめに再生を図っていることがわかり、コンサルタントとして参画することになりました。ジョエルからのコメントは「しくじるんじゃねーぞ(Don’t F it up!)」だけだったとか。
当初は2022年ヴィンテージからの復活予定でしたが、2022年が熱波の影響であまりいいワインができず、2023年からとなりました。生産量は3400ケースで27ドルの「ドライクリーク・ヴァレー ジンファンデル」が1900ケース。あとはテルデスキ(Teldeschi)とマクマレイ(MacMurray)、モンテ・ロッソ(Monte Rosso)がそれぞれ500ケース。価格はモンテ・ロッソが70ドルであとは50ドルです。なお、モンテ・ロッソとマクマレイはガロが所有しています。
なお、ジョエルは今回の就任にあたり金銭的報酬を受けないとのこと。その分をジンファンデル・アドボケーツ&プロデューサーズ(ZAP)に寄付することにしています。
ジョエル・ピーターソンは1976年にレーヴェンズウッドを設立。「軟弱なワインは作らない(No Wimpy Wines)」をモットーに、独自のジンファンデルのスタイルを築きました。ただ、出資者との間の金銭的な問題により、2001年にコンステレーション・ブランズに売却。その後もワイナリーにはとどまっていましたが、生産するワインが、安価なヴィントナーズ・ブレンドに集中する中で、現場からは遠ざかるようになりました。そして2019年にコンステレーションが30以上のブランドをガロに売却する方針を発表し(ガロ、コンステレーションからフランシスカン、レイヴェンズウッドなど30以上のブランドを取得)、2020年にはワイナリーやテイスティングルームが閉鎖し、オールド・ヒル・ランチなど、古木の畑との契約も終了して実質的に休眠状態になっていました。
なお、この間、ジョエル・ピーターソンは新たにワンス・アンド・フューチャーというブランドを立ち上げ、オールド・ヒル・ランチを含む単一畑のジンファンデルなどを製造しています。
その後、ガロ家のマット・ガロがブランドの再生を図るため、ジョエルに接触してきました。当初は懐疑的だったそうですが、議論を重ねるうちにガロがまじめに再生を図っていることがわかり、コンサルタントとして参画することになりました。ジョエルからのコメントは「しくじるんじゃねーぞ(Don’t F it up!)」だけだったとか。
当初は2022年ヴィンテージからの復活予定でしたが、2022年が熱波の影響であまりいいワインができず、2023年からとなりました。生産量は3400ケースで27ドルの「ドライクリーク・ヴァレー ジンファンデル」が1900ケース。あとはテルデスキ(Teldeschi)とマクマレイ(MacMurray)、モンテ・ロッソ(Monte Rosso)がそれぞれ500ケース。価格はモンテ・ロッソが70ドルであとは50ドルです。なお、モンテ・ロッソとマクマレイはガロが所有しています。
なお、ジョエルは今回の就任にあたり金銭的報酬を受けないとのこと。その分をジンファンデル・アドボケーツ&プロデューサーズ(ZAP)に寄付することにしています。
ロバート・モンダヴィなど、数多くのワインブランドを保有するコンステレーション・ブランズ(Constellation Brands)が、ワインビジネスをすべて売却する方向で検討しているという記事がWineBusinessに出ていました(Constellation Eyeing Exit from Wine Business)。
記事によると、ワインビジネスの停滞と、メキシコ産ビールビジネスの成功によって、ワインビジネス売却の方向に動いているとのことです。現在の交渉では、セントラルヴァレーのワイン事業はデリカート・ファミリーに売却し、ナパヴァレーなど沿岸地域のブランドは、先日バタフライ・エクイティに買収され、上場を撤回したダックホーンに売却する方針とのこと。
3社はWineBusinessからの問い合わせに対してコメントを控えています。
コンステレーションは2024年8月にサンタ・バーバラのシー・スモークを買収しており、その金額を補うために低価格ブランドの一部を売却することを検討しているとしていました。CEOは当時、2024年末までにワイン業界は好転すると見ていましたが、実際には2024年11月30日までの3か月間で、ワインの売上が16.4%減の510万ケース、純売上高が2023年比14%減の4億3140万ドルと低迷が続いています。同じ期間に、ビールの出荷量は1.6%増の1億270万ケース相当となり、純売上高は3%増の20億3000万ドルでした。
2月にはウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイがコンステレーションに投資したことが明らかになっていますが、これもおそらくビールビジネスの好調を受けてのものと思われます。
記事によると、ワインビジネスの停滞と、メキシコ産ビールビジネスの成功によって、ワインビジネス売却の方向に動いているとのことです。現在の交渉では、セントラルヴァレーのワイン事業はデリカート・ファミリーに売却し、ナパヴァレーなど沿岸地域のブランドは、先日バタフライ・エクイティに買収され、上場を撤回したダックホーンに売却する方針とのこと。
3社はWineBusinessからの問い合わせに対してコメントを控えています。
コンステレーションは2024年8月にサンタ・バーバラのシー・スモークを買収しており、その金額を補うために低価格ブランドの一部を売却することを検討しているとしていました。CEOは当時、2024年末までにワイン業界は好転すると見ていましたが、実際には2024年11月30日までの3か月間で、ワインの売上が16.4%減の510万ケース、純売上高が2023年比14%減の4億3140万ドルと低迷が続いています。同じ期間に、ビールの出荷量は1.6%増の1億270万ケース相当となり、純売上高は3%増の20億3000万ドルでした。
2月にはウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイがコンステレーションに投資したことが明らかになっていますが、これもおそらくビールビジネスの好調を受けてのものと思われます。
ウエスト・ソノマ・コーストの旗手ロス・コブ氏が2年ぶりに来日してセミナーが開かれました。


ウエスト・ソノマ・コーストは2022年に策定された新しいAVA。ソノマ・コーストAVAがあまりにも広すぎ、ロシアン・リバー・ヴァレーなどの内陸の産地までも含んでいるため「真の冷涼な沿岸地域」として策定されたものです。
ウエスト・ソノマ・コーストの中央あたりにはフォートロス・シービューAVAが含まれています。マーカッシンやフラワーズ、ウェイフェアラーなどの有名ワイナリーを含むこの地域は標高が高く、霧がほとんどかからないため、極めて冷涼でありながら、太陽の光をしっかりと浴び、濃厚でパワフルなワインになりがちです。一方、この地域の南の方は標高が低いため、霧に覆われている時間が長く、エレガントなワインになります。コブのワインは基本的にウエスト・ソノマ・コーストの南部か、その東側のグリーンヴァレーなどの冷涼地域のブドウから作られており、カリフォルニアのピノ・ノワール、シャルドネの生産者の中でもエレガントさでいえばトップといっていいでしょう。

コブのワイナリーがあるのは地図で示したところ。ここにコーストランズ(Coastlands)という、ロス・コブの両親が1989年に最初に開墾した畑があります。太平洋からの距離は約6km、標高は300mあまりです。当時、ロス・コブは大学1年生。カリフォルニア大学サンタ・クルーズ校に通っていました。生物学を専攻していましたが、畑に興味を持ち土壌科学に転科しました。
両親の時代はワインはまだ作っておらず、ピノ・ノワールをWilliams-Selyemに売っていました。Williams-Selyemでは1994年から現在に至るまでコーストランズのピノ・ノワールを作っており、ワイン・アドヴォケイトで最高97点という高い評価を得ています。
ロス・コブ氏自身は大学卒業後、ソノマのフェラーリ・カラーノやウィリアムズ・セリエムなどで働き、2001年から「コブ・ワインズ」として自身のワインも作り始めています。現在は、コーストランズのほか、ワイナリーの500mほど南にあるドックス・ランチ(Doc's Ranch)、グリーン・ヴァレーのフリーマンのワイナリーのすぐ隣にあるアビゲイル(Abigail's)の自社畑を持ち、このほかメンドシーノを含めた10あまりの畑から単一畑のワインを造っています。
試飲の最初のワインはリースリング。メンドシーノにあるコール・ランチ(Cole Ranch)という畑。ここは
Cole Ranchという極めて小さなAVAに属す唯一の畑です。

リースリングは低温(10℃)で発酵せます。ステンレスタンクで発酵させ、小樽で熟成させます。残糖はありません。
Cole Ranch Riesling 2022
蜜の香りに青リンゴ、白い花。酸高く、ジューシーな味わい。残糖なしなのでキリリとした味わいです。92点
次はシャルドネ2本。H.Klopp Chardonnay 2020とDoc's Ranch JoAnn's Block Chardonnay 2020です。
H. Kloppの畑はロシアン・リバー・ヴァレーのセバストポール・ヒルズと呼ばれる地域にあります。ウエスト・ソノマ・コーストのマップの中で色が薄く表示されている右下のあたり。ここは元々AVAに含めたかった場所ですが、他のAVAとオーバーラップする領域が認められないように制度が変わったために、含められなかったところです。現在はSebastopol Hillsという名前でAVAを申請しています。
Klopp家は古くからこの地域で果樹園などをやっており1990年代からはブドウも作り始めました。2012年に新しい畑を増やすためにロス・コブに依頼をして、開発したのがこのシャルドネの畑で、シャルドネだけが植わっています。
樽発酵樽熟成で10%新樽で22カ月熟成しています。MLFは100%。アルコール度数12.3%というのはちょっと驚きました。
焼きリンゴやマシュマロ、蜜のような甘い香り、バニラ、オレンジ。香りにリッチ感はありますが、上述のようにアルコール度数は低く、味わいも濃すぎることなく、うまい。リッチで柑橘系の味わいのあるマウント・エデン・クローンやトロピカルな風味が出るロバート・ヤング・クローンの良さが引き出されているようです。素晴らしい。96点
Doc's RanchのJoAnn's Blockはわずか1エーカーのシャルドネのみのブロックです。一番スタンダードなウェンテ・クローンであるUCD5を使っています。
シュール・リーでうまみを引き出しているとのこと。MLF100%。
花の香り、クリーム・ブリュレ、複雑でリッチなワイン。92点
最後はピノ・ノワール3種です。Doc's Ranch 2019、Rice-Spivak 2021、Coastlands 2021。
Doc's Ranch 2019はシルキーなテクスチャーが印象的。赤い果実や花の香りがあり豊かな酸があります。93点
Rice-Spivak(ライス・スピーヴァック)はロシアン・リバー・ヴァレーに含まれる畑。少し低地にあり冷気がたまるため、非常に冷涼なところだといいます。ゴールドリッジと火山灰による土壌でアロマやミネラル感を感じやすいとのこと。
バランスよくきれいなワイン。赤い果実に少しコクがあって複雑、酸はDoc's Ranchよりちょっと低い。94点
最後はCoastlands 2021です。一番タンニンがあり、グリップを感じます。これも赤い果実に複雑な風味。ジューシーさと複雑さでこれが一番好きでした。95点
コブのワインは、どれもアルコール度数は低めですが、味わいは淡白でなく、しっかりとしたフレーバーがあります。これだけ低糖度でフェノール類はしっかりとたまるということは、やはりかなりの冷涼さがあることがうかがえます。今回6種類を試飲することで、改めてそのレベルの高さを感じました。

ウエスト・ソノマ・コーストは2022年に策定された新しいAVA。ソノマ・コーストAVAがあまりにも広すぎ、ロシアン・リバー・ヴァレーなどの内陸の産地までも含んでいるため「真の冷涼な沿岸地域」として策定されたものです。
ウエスト・ソノマ・コーストの中央あたりにはフォートロス・シービューAVAが含まれています。マーカッシンやフラワーズ、ウェイフェアラーなどの有名ワイナリーを含むこの地域は標高が高く、霧がほとんどかからないため、極めて冷涼でありながら、太陽の光をしっかりと浴び、濃厚でパワフルなワインになりがちです。一方、この地域の南の方は標高が低いため、霧に覆われている時間が長く、エレガントなワインになります。コブのワインは基本的にウエスト・ソノマ・コーストの南部か、その東側のグリーンヴァレーなどの冷涼地域のブドウから作られており、カリフォルニアのピノ・ノワール、シャルドネの生産者の中でもエレガントさでいえばトップといっていいでしょう。

コブのワイナリーがあるのは地図で示したところ。ここにコーストランズ(Coastlands)という、ロス・コブの両親が1989年に最初に開墾した畑があります。太平洋からの距離は約6km、標高は300mあまりです。当時、ロス・コブは大学1年生。カリフォルニア大学サンタ・クルーズ校に通っていました。生物学を専攻していましたが、畑に興味を持ち土壌科学に転科しました。
両親の時代はワインはまだ作っておらず、ピノ・ノワールをWilliams-Selyemに売っていました。Williams-Selyemでは1994年から現在に至るまでコーストランズのピノ・ノワールを作っており、ワイン・アドヴォケイトで最高97点という高い評価を得ています。
ロス・コブ氏自身は大学卒業後、ソノマのフェラーリ・カラーノやウィリアムズ・セリエムなどで働き、2001年から「コブ・ワインズ」として自身のワインも作り始めています。現在は、コーストランズのほか、ワイナリーの500mほど南にあるドックス・ランチ(Doc's Ranch)、グリーン・ヴァレーのフリーマンのワイナリーのすぐ隣にあるアビゲイル(Abigail's)の自社畑を持ち、このほかメンドシーノを含めた10あまりの畑から単一畑のワインを造っています。
試飲の最初のワインはリースリング。メンドシーノにあるコール・ランチ(Cole Ranch)という畑。ここは
Cole Ranchという極めて小さなAVAに属す唯一の畑です。

リースリングは低温(10℃)で発酵せます。ステンレスタンクで発酵させ、小樽で熟成させます。残糖はありません。
Cole Ranch Riesling 2022
蜜の香りに青リンゴ、白い花。酸高く、ジューシーな味わい。残糖なしなのでキリリとした味わいです。92点
次はシャルドネ2本。H.Klopp Chardonnay 2020とDoc's Ranch JoAnn's Block Chardonnay 2020です。
H. Kloppの畑はロシアン・リバー・ヴァレーのセバストポール・ヒルズと呼ばれる地域にあります。ウエスト・ソノマ・コーストのマップの中で色が薄く表示されている右下のあたり。ここは元々AVAに含めたかった場所ですが、他のAVAとオーバーラップする領域が認められないように制度が変わったために、含められなかったところです。現在はSebastopol Hillsという名前でAVAを申請しています。
Klopp家は古くからこの地域で果樹園などをやっており1990年代からはブドウも作り始めました。2012年に新しい畑を増やすためにロス・コブに依頼をして、開発したのがこのシャルドネの畑で、シャルドネだけが植わっています。
樽発酵樽熟成で10%新樽で22カ月熟成しています。MLFは100%。アルコール度数12.3%というのはちょっと驚きました。
焼きリンゴやマシュマロ、蜜のような甘い香り、バニラ、オレンジ。香りにリッチ感はありますが、上述のようにアルコール度数は低く、味わいも濃すぎることなく、うまい。リッチで柑橘系の味わいのあるマウント・エデン・クローンやトロピカルな風味が出るロバート・ヤング・クローンの良さが引き出されているようです。素晴らしい。96点
Doc's RanchのJoAnn's Blockはわずか1エーカーのシャルドネのみのブロックです。一番スタンダードなウェンテ・クローンであるUCD5を使っています。
シュール・リーでうまみを引き出しているとのこと。MLF100%。
花の香り、クリーム・ブリュレ、複雑でリッチなワイン。92点
最後はピノ・ノワール3種です。Doc's Ranch 2019、Rice-Spivak 2021、Coastlands 2021。
Doc's Ranch 2019はシルキーなテクスチャーが印象的。赤い果実や花の香りがあり豊かな酸があります。93点
Rice-Spivak(ライス・スピーヴァック)はロシアン・リバー・ヴァレーに含まれる畑。少し低地にあり冷気がたまるため、非常に冷涼なところだといいます。ゴールドリッジと火山灰による土壌でアロマやミネラル感を感じやすいとのこと。
バランスよくきれいなワイン。赤い果実に少しコクがあって複雑、酸はDoc's Ranchよりちょっと低い。94点
最後はCoastlands 2021です。一番タンニンがあり、グリップを感じます。これも赤い果実に複雑な風味。ジューシーさと複雑さでこれが一番好きでした。95点
コブのワインは、どれもアルコール度数は低めですが、味わいは淡白でなく、しっかりとしたフレーバーがあります。これだけ低糖度でフェノール類はしっかりとたまるということは、やはりかなりの冷涼さがあることがうかがえます。今回6種類を試飲することで、改めてそのレベルの高さを感じました。
しあわせワイン倶楽部でエチュードのピノ・ノワールとシャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨンが57%引きの激安になっています。現地価格よりもずっと安い大盤振る舞い。日本のインポーターの終売によるものなので、売り切れ次第終了します。
エチュードは1980年代にナパのカーネロスにトニー・ソーターが設立したワイナリーです。トニー・ソーターはダラ・ヴァレやスポッツウッド、アラウホ(現アイズリー)などナパの名だたるワイナリーの中でもトップクラスのワイナリーでワインメーカーを勤めていた人。1990年代からの「カルトワインブーム」の立役者の一人でした。
彼は元々ピノ・ノワールを作りたいと思っており、そこで設立したのがこのエチュード。エチュードには「練習」といった意味があり、ここでいろいろなピノ・ノワールを作りながら、いいピノのための学習を深めていっていました。
2000年代に入り、トニー・ソーターはワイナリーをベリンジャーに売却。現在はトレジャリー・ワイン・エステート傘下となっていますが、今もトニーの精神を引き継いでワインが作られています。トニー自身は現在はオレゴンで「ソーター」を設立して、ピノ・ノワールの探求を続けています。
今回セールのピノ・ノワールは「グレース・ベノワ・ランチ」の2020年。この畑は本拠地であるカーネロスの自社畑で様々なピノ・ノワールのクローンを植えています。ワイン・スペクテーターで92点、ヴィナスでは90点の評価。ヴィナスのレビューによると、濃厚パワフル系のピノ・ノワールのようです。現地47ドルが4510円と、1ドル100円だったっけ?と思わせる価格。
次のシャルドネも同じくグレース・ベノワ・ランチのもので2022年です。この畑、ピノ・ノワールが158エーカーに対して、シャルドネはわずか6エーカー。ワインも145ケースしか作られていません。ジェームズ・サックリングは1980年代や90年代のブルゴーニュのようだとして97点を付けています。なおヴィナスでは92点。どちらにしても高評価であることは間違いありません。現地40ドルがなんと3960円と税込み3000円台。
最後のワインは2019年のナパヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨン。実はエチュード、力を入れているのはピノ・ノワールなのですが、ナパのワイナリーでありカベルネの名手のトニー・ソーターが作っていたということもあり、カベルネ・ソーヴィニヨンもとても美味しい、というか常に高評価を続けていたのです。それもそのはずで、自社畑ではないですが、オークヴィルのヴァイン・ヒル・ランチ、クームズヴィルのメテオールなど垂涎の畑のブドウを使っています。このカベルネもジェームズ・サックリングは96点、ワイン・スペクテーターでも94点と非常に高評価。スペクテーターでは「ダークだがフレッシュで、マルベリーとブラックカラントの果実にアップルウッド、アニス、タバコが混じる。最初から最後まで素晴らしいエネルギーを示し、鉄のアクセントがフィニッシュまでしっかりとした感触を与える」としています。現地100ドルが税込み8910円と、1ドル80円換算(笑)。
今の為替を考えたらこの3倍の価格でもおかしくないワインです。だまされたと思って買ってください。
エチュードは1980年代にナパのカーネロスにトニー・ソーターが設立したワイナリーです。トニー・ソーターはダラ・ヴァレやスポッツウッド、アラウホ(現アイズリー)などナパの名だたるワイナリーの中でもトップクラスのワイナリーでワインメーカーを勤めていた人。1990年代からの「カルトワインブーム」の立役者の一人でした。
彼は元々ピノ・ノワールを作りたいと思っており、そこで設立したのがこのエチュード。エチュードには「練習」といった意味があり、ここでいろいろなピノ・ノワールを作りながら、いいピノのための学習を深めていっていました。
2000年代に入り、トニー・ソーターはワイナリーをベリンジャーに売却。現在はトレジャリー・ワイン・エステート傘下となっていますが、今もトニーの精神を引き継いでワインが作られています。トニー自身は現在はオレゴンで「ソーター」を設立して、ピノ・ノワールの探求を続けています。
今回セールのピノ・ノワールは「グレース・ベノワ・ランチ」の2020年。この畑は本拠地であるカーネロスの自社畑で様々なピノ・ノワールのクローンを植えています。ワイン・スペクテーターで92点、ヴィナスでは90点の評価。ヴィナスのレビューによると、濃厚パワフル系のピノ・ノワールのようです。現地47ドルが4510円と、1ドル100円だったっけ?と思わせる価格。
次のシャルドネも同じくグレース・ベノワ・ランチのもので2022年です。この畑、ピノ・ノワールが158エーカーに対して、シャルドネはわずか6エーカー。ワインも145ケースしか作られていません。ジェームズ・サックリングは1980年代や90年代のブルゴーニュのようだとして97点を付けています。なおヴィナスでは92点。どちらにしても高評価であることは間違いありません。現地40ドルがなんと3960円と税込み3000円台。
最後のワインは2019年のナパヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨン。実はエチュード、力を入れているのはピノ・ノワールなのですが、ナパのワイナリーでありカベルネの名手のトニー・ソーターが作っていたということもあり、カベルネ・ソーヴィニヨンもとても美味しい、というか常に高評価を続けていたのです。それもそのはずで、自社畑ではないですが、オークヴィルのヴァイン・ヒル・ランチ、クームズヴィルのメテオールなど垂涎の畑のブドウを使っています。このカベルネもジェームズ・サックリングは96点、ワイン・スペクテーターでも94点と非常に高評価。スペクテーターでは「ダークだがフレッシュで、マルベリーとブラックカラントの果実にアップルウッド、アニス、タバコが混じる。最初から最後まで素晴らしいエネルギーを示し、鉄のアクセントがフィニッシュまでしっかりとした感触を与える」としています。現地100ドルが税込み8910円と、1ドル80円換算(笑)。
今の為替を考えたらこの3倍の価格でもおかしくないワインです。だまされたと思って買ってください。
29回目となるプルミエ・ナパヴァレー・オークションが開かれ、2024年の300万ドルを超える330万ドルの総落札額を達成しました。ロットは合計194ロットでした。

プルミエ・ナパヴァレー・オークションはプロ向けのオークションで、6月に開催される一般向けのオークションとは大きく異なります。一般向けのオークションはディナーやツアーなどワイン以外のイベントを含むものが多くありますが、こちらはワインのみ。このオークション専用に作られたもので、ラベルもすべてのワイナリーで共通のデザインのものを使うことや本数の制限などもあります。ワインは後日リリースされることになります。ワイナリーはワインをオークション用に寄付し、収益はナパヴァレー・ヴィントナーズによって使われます。

トップロットはサイモン・ファミリーの2024カベルネ・ソーヴィニヨンで60ボトルが6万ドルでした。
他の高額ロットには以下のものがあります。
$55,000 for 60 bottles of The Mascot 2024 Cabernet Sauvignon
$50,000 for 120 bottles of Quintessa 2023 Cabernet Sauvignon
$50,000 for 60 bottles of Hourglass 2023 Cabernet Sauvignon
$49,000 for 240 bottles of JennaMarise Wines/Robert Foley Vineyards 2023 Cabernet Sauvignon
$48,000 for 240 bottles of Robert Mondavi To Kalon 2023 red blend
$46,000 for 240 bottles of Duckhorn Vineyards Three Palm Vineyard 2023 red blend
$40,000 for 240 bottles of Davies/Diamond Creek/ Diamond Mountain/Dyer/Lokoya/ Wallis Damond Mountain Six 2023 Cabernet Sauvignon
$45,000 for 120 bottles of Grgich Hills Estate/Spottwoode Estate Vineyard and Winery 2023 Cabernet Sauvignon
$36,000 for 60 bottles of Darioush 2023 Cabernet Sauvignon
$30,000 for 120 bottles for Favia 2023 Cabernet Sauvignon
$35,000 for 120 bottles of Raymond Vineyards 2023 Cabernet Sauvignon
$35,000 for 250 bottles of Silver Oak 2023 Cabernet Sauvignon
$35,000 for 60 bottles of Shafer Vineyards 2023 Cabernet Sauvignon
$40,000 for 60 bottles of Arkenstone Estate Winery Godus 2023 Cabernet Sauvignon.

プルミエ・ナパヴァレー・オークションはプロ向けのオークションで、6月に開催される一般向けのオークションとは大きく異なります。一般向けのオークションはディナーやツアーなどワイン以外のイベントを含むものが多くありますが、こちらはワインのみ。このオークション専用に作られたもので、ラベルもすべてのワイナリーで共通のデザインのものを使うことや本数の制限などもあります。ワインは後日リリースされることになります。ワイナリーはワインをオークション用に寄付し、収益はナパヴァレー・ヴィントナーズによって使われます。

トップロットはサイモン・ファミリーの2024カベルネ・ソーヴィニヨンで60ボトルが6万ドルでした。
他の高額ロットには以下のものがあります。
$55,000 for 60 bottles of The Mascot 2024 Cabernet Sauvignon
$50,000 for 120 bottles of Quintessa 2023 Cabernet Sauvignon
$50,000 for 60 bottles of Hourglass 2023 Cabernet Sauvignon
$49,000 for 240 bottles of JennaMarise Wines/Robert Foley Vineyards 2023 Cabernet Sauvignon
$48,000 for 240 bottles of Robert Mondavi To Kalon 2023 red blend
$46,000 for 240 bottles of Duckhorn Vineyards Three Palm Vineyard 2023 red blend
$40,000 for 240 bottles of Davies/Diamond Creek/ Diamond Mountain/Dyer/Lokoya/ Wallis Damond Mountain Six 2023 Cabernet Sauvignon
$45,000 for 120 bottles of Grgich Hills Estate/Spottwoode Estate Vineyard and Winery 2023 Cabernet Sauvignon
$36,000 for 60 bottles of Darioush 2023 Cabernet Sauvignon
$30,000 for 120 bottles for Favia 2023 Cabernet Sauvignon
$35,000 for 120 bottles of Raymond Vineyards 2023 Cabernet Sauvignon
$35,000 for 250 bottles of Silver Oak 2023 Cabernet Sauvignon
$35,000 for 60 bottles of Shafer Vineyards 2023 Cabernet Sauvignon
$40,000 for 60 bottles of Arkenstone Estate Winery Godus 2023 Cabernet Sauvignon.
スタッグス・リープ・ワイン・セラーズが、創設者で2024年になくなったウォーレン・ウィニアルスキーがナパのクームズヴィルに保有していたアルカディア・ヴィンヤード(Arcadia Vineyard)を取得しました。
ウォーレン・ウィニアルスキーは2007年にスタッグス・リープ・ワイン・セラーズをアンティノリとワシントンのシャトー・サン・ミシェルに売却して引退しました。その際、アルカディア・ヴィンヤードだけは自身の畑として残しており、スタッグス・リープ・ワイン・セラーズはアルカディアのブドウを自社のワインに使っていました。
スタッグス・リープ・ワイン・セラーズの現オーナーであるアンティノリは「この購入によってブドウ畑が元の場所に戻り、スタッグス・リープ・ワイン・セラーズで造られる全てのワインが、100%自社畑で栽培されるという目標に近づくことができる」とコメントしています。
ウォーレン・ウィニアルスキーは2007年にスタッグス・リープ・ワイン・セラーズをアンティノリとワシントンのシャトー・サン・ミシェルに売却して引退しました。その際、アルカディア・ヴィンヤードだけは自身の畑として残しており、スタッグス・リープ・ワイン・セラーズはアルカディアのブドウを自社のワインに使っていました。
スタッグス・リープ・ワイン・セラーズの現オーナーであるアンティノリは「この購入によってブドウ畑が元の場所に戻り、スタッグス・リープ・ワイン・セラーズで造られる全てのワインが、100%自社畑で栽培されるという目標に近づくことができる」とコメントしています。
ナパのスプリング・マウンテンにある名門ワイナリー「Newton Vineyard(ニュートン・ヴィンヤード)」がクローズすることが判明しました。ワイナリーのメーリングリスト・メンバーへのメールで明らかになりました。
ニュートンは2020年のグラス・ファイアーで大きな被害を受けました。ワイナリーや庭などが焼失したほか、74エーカーの畑も5エーカーを残して焼けてしまいました。下の写真は火事の前と後のものです。その後カリストガにテイスティングルームをオープンして、再起を狙っていましたが、親会社のLVMHがクローズを決めました。


ニュートンの創設者であるピーター・ニュートンは1960年代から70年代の近代ナパ勃興期に活躍した人。1964年にカリストガにスターリング・ヴィンヤーズをオープンし、リック・フォーマンをワインメーカーに据えて高品質なワインを造りました。1977年にリックと共にニュートン・ヴィンヤードを創設。リックの退任後はジョン・コングスガードをワインメーカーとして採用し、当時は非常に珍しかったノンフィルターのシャルドネなどを作って有名ワイナリーになりました。今はコングスガードで、カリフォルニアトップクラスのシャルドネを造るジョン・コングスガードですが、そのワイン造りの原点はニュートンにあります。
ジョン・コングスガードの後はピーターの妻のスー・フアがワインメーカーになりました。かつてはシャネルのモデルであり、臨床・産業心理学の学位、さらには医学博士でもあり、母国である中国語のほか、育った英語、さらにフランス語もできます。Newtonのワイナリや庭園のデザインも手がけたという才人。
2001年にワイナリーをLVMHに売却。その後はオーガニック栽培への転換などを進めました。映画「サイドウェイ」の日本版でも重要な役割を果たしました。
高品質な「山カベ」の代表的な生産者でもあり、「ノンフィルター」で時代を築いたニュートンが失われてしまうのは残念なことです。
ニュートンは2020年のグラス・ファイアーで大きな被害を受けました。ワイナリーや庭などが焼失したほか、74エーカーの畑も5エーカーを残して焼けてしまいました。下の写真は火事の前と後のものです。その後カリストガにテイスティングルームをオープンして、再起を狙っていましたが、親会社のLVMHがクローズを決めました。


ニュートンの創設者であるピーター・ニュートンは1960年代から70年代の近代ナパ勃興期に活躍した人。1964年にカリストガにスターリング・ヴィンヤーズをオープンし、リック・フォーマンをワインメーカーに据えて高品質なワインを造りました。1977年にリックと共にニュートン・ヴィンヤードを創設。リックの退任後はジョン・コングスガードをワインメーカーとして採用し、当時は非常に珍しかったノンフィルターのシャルドネなどを作って有名ワイナリーになりました。今はコングスガードで、カリフォルニアトップクラスのシャルドネを造るジョン・コングスガードですが、そのワイン造りの原点はニュートンにあります。
ジョン・コングスガードの後はピーターの妻のスー・フアがワインメーカーになりました。かつてはシャネルのモデルであり、臨床・産業心理学の学位、さらには医学博士でもあり、母国である中国語のほか、育った英語、さらにフランス語もできます。Newtonのワイナリや庭園のデザインも手がけたという才人。
2001年にワイナリーをLVMHに売却。その後はオーガニック栽培への転換などを進めました。映画「サイドウェイ」の日本版でも重要な役割を果たしました。
高品質な「山カベ」の代表的な生産者でもあり、「ノンフィルター」で時代を築いたニュートンが失われてしまうのは残念なことです。

オレゴンのヴァーナム・ヴィントナーズ(Varnum Vintners)が、オレゴンでは初となるノンアルコールのワインを発売しました。同ワイナリーは2024年にオレゴン初のノンアルコールワインを発売しています。
ヴァーナムはスピニング・コーンの技術を使って、フレーバーを保ったままアルコールを除去しています。ピノ・ノワールはオレゴンで一番広く栽培されている品種であり、ローアルコールやノンアルコールの重要性が高まる中でピノ・ノワールでのノンアルコールワインはオレゴンのワイン業界全体にとっても重要なカテゴリーになります。
価格は40ドル。これまで同社が出していたものではスパークリングの24ドルというのが一番高い設定でした。価格的にも「攻めた」ワインで、今後が注目されます。
ブルゴーニュのドメーヌ・デュジャックの共同経営者兼ワインメーカーであるジェレミー・セイス氏がナパのカベルネ・ソーヴィニヨンのワイナリーに参画しています。畑はトレイルサイド・ヴィンヤード。ラザフォードの東側にあり、長年ハイツ・セラーにブドウを供給してきています。

ハイツ・セラーのオーナーでもあるローレンス・ワイン・エステートのカールトン・マッコイ(ダラ・ヴァレのマヤさんの夫です)がジェレミーと2020年に始めたプロジェクトで、今月最初のワインがリリースされる予定です。「1960年代と1970年代のナパ・ヴァレーの栄光の時代へのオマージュであり、テロワール主導の熟成に値するスタイル」だと言います。

マッコイがトレイルサイドのオーナーになったのが2019年。7種類ある複雑な土壌から、テロワールを大事にしてワインを造る醸造家が必要だと思い、それで選んだのがジェレミーだとのことです。
醸造においてはナパでは一般的でない全房発酵や、果房を沈める手法などを取り入れているとか。
ちなみにジェレミーの妻はダイアナ・スノーデン・セイス。ナパのスノーデンやアッシュ・アンド・ダイヤモンズでワインメーカーをしています。

ハイツ・セラーのオーナーでもあるローレンス・ワイン・エステートのカールトン・マッコイ(ダラ・ヴァレのマヤさんの夫です)がジェレミーと2020年に始めたプロジェクトで、今月最初のワインがリリースされる予定です。「1960年代と1970年代のナパ・ヴァレーの栄光の時代へのオマージュであり、テロワール主導の熟成に値するスタイル」だと言います。

マッコイがトレイルサイドのオーナーになったのが2019年。7種類ある複雑な土壌から、テロワールを大事にしてワインを造る醸造家が必要だと思い、それで選んだのがジェレミーだとのことです。
醸造においてはナパでは一般的でない全房発酵や、果房を沈める手法などを取り入れているとか。
ちなみにジェレミーの妻はダイアナ・スノーデン・セイス。ナパのスノーデンやアッシュ・アンド・ダイヤモンズでワインメーカーをしています。
カリフォルニア州がCDFA(カリフォルニア州食品農業局)長官への勧告という形で、再生可能農業(Regenerative Agricuture)を定義しました(CDFA - Defining Regenerative Agriculture for State Policies and Programs)。
達成すべき具体的な目標としては以下の8点が挙げられています。
1. 土壌の健康、生物多様性、土壌有機物の向上
「健康な土壌プログラム」
2. 土壌の健康、炭素隔離、温室効果ガス削減のための保全的農業の拡大
「米国農務省自然資源保全局(USDA NRCS)の保全実践基準」 に基づく施策
3. 持続可能な害虫管理(IPM)の推進
「カリフォルニア州の持続可能な害虫管理加速化ロードマップ」
「カリフォルニア大学統合害虫管理プログラム(UC IPM)」
「USDA NRCSの害虫管理保全システム」
4. 農業における動物の福祉とケアの確保
「動物ケアプログラム(Animal Care Program)」
5. 健康的な地域社会の構築
「農業ビジョン(Ag Vision)」
6. 文化的・精神的伝統の保護と先住民主導の土地管理の支援
7. 他の目標への悪影響の最小化
8. 農家や牧場経営者の経済的持続可能性の確保
また、地域特性や文化に応じて以下の3点を考慮して適用していきます。
・利用可能な最善の科学と実践に基づくこと
・有機農業および伝統的な生態学的知識(TEK: Traditional Ecological Knowledge)を尊重すること
・持続可能な農業システムのための適切な選択肢を確保すること
この定義は、再生可能農業の認証などに即座につながるものではありません。今後の議論の礎になるようなものだと考えるのがよさそうです。
ただ、有機農業について、必須の条件としなかったことには残念だという声もすでに上がってきています。一方で、現在カリフォルニアの有機農業の比率が4%程度であり、それを必須にすると、ほとんどの生産者を置いてきぼりにしてしまって実効力がなくなるので仕方がないという考えもあるようです。
ROC(Regenerative Organic Certified)との関係がどうなっていくのかも定かではありません。
いろいろ議論があるところではありますが、まずは再生可能農業という言葉をより一般に通じるようにする道筋の一つとしては大きな意味があるのではないかと、個人的には感じています。
達成すべき具体的な目標としては以下の8点が挙げられています。
1. 土壌の健康、生物多様性、土壌有機物の向上
「健康な土壌プログラム」
2. 土壌の健康、炭素隔離、温室効果ガス削減のための保全的農業の拡大
「米国農務省自然資源保全局(USDA NRCS)の保全実践基準」 に基づく施策
3. 持続可能な害虫管理(IPM)の推進
「カリフォルニア州の持続可能な害虫管理加速化ロードマップ」
「カリフォルニア大学統合害虫管理プログラム(UC IPM)」
「USDA NRCSの害虫管理保全システム」
4. 農業における動物の福祉とケアの確保
「動物ケアプログラム(Animal Care Program)」
5. 健康的な地域社会の構築
「農業ビジョン(Ag Vision)」
6. 文化的・精神的伝統の保護と先住民主導の土地管理の支援
7. 他の目標への悪影響の最小化
8. 農家や牧場経営者の経済的持続可能性の確保
また、地域特性や文化に応じて以下の3点を考慮して適用していきます。
・利用可能な最善の科学と実践に基づくこと
・有機農業および伝統的な生態学的知識(TEK: Traditional Ecological Knowledge)を尊重すること
・持続可能な農業システムのための適切な選択肢を確保すること
この定義は、再生可能農業の認証などに即座につながるものではありません。今後の議論の礎になるようなものだと考えるのがよさそうです。
ただ、有機農業について、必須の条件としなかったことには残念だという声もすでに上がってきています。一方で、現在カリフォルニアの有機農業の比率が4%程度であり、それを必須にすると、ほとんどの生産者を置いてきぼりにしてしまって実効力がなくなるので仕方がないという考えもあるようです。
ROC(Regenerative Organic Certified)との関係がどうなっていくのかも定かではありません。
いろいろ議論があるところではありますが、まずは再生可能農業という言葉をより一般に通じるようにする道筋の一つとしては大きな意味があるのではないかと、個人的には感じています。

カリフォルニアの2024年のブドウ収穫の暫定レポートが公表されました(Lightest Crush in 20 Years: California Crushed 2.84 Million Tons of Wine Grapes in 2024)。
2024年にカリフォルニア州で収穫された(正確には収穫して圧搾された)ワイン用ブドウは284万トン。2023年の370万トンから23%減少しました。2004年に276万トンのワイン用ブドウが圧搾されて以来の少なさでした。

ブドウの価格もわずかですが下がっています。ただ、需要と供給の兼ね合いからすると、もう1段階下がってもおかしくない状況でした。それほど価格が下がらなかったのは、シーズン前から価格を決めて造るケースが意外と多いからだそうです、

品種別の収穫量を見ると、1位はシャルドネで2位がカベルネ・ソーヴィニョン。これまでと大きな変化はみられません。
ブドウ余りの時代で、2024年の低収量は生産調整という意味では良かったという意見もあるようです。
ちなみに、低価格ワインで知られるブロンコはセントラル・ヴァレーのスタニスラス郡で81人のレイオフを発表しています。セントラルヴァレーの作り手が一番大きな影響を受けています。
ナパには引く手あまたの著名ワインメーカーが数多くいますが、トップの一人と目されているのがブノワ・トゥケ。レアム(Realm)では10回を超えるパーカー100点を獲得しており、フィリップ・メルカ、トーマス・リヴァース・ブラウンと並んで「フェアレスト・クリーチャー」というトップワインメーカーを並べたプロジェクトにも選ばれています。
ナパのトップ・ワインメーカー3人の競演!? 「夢の新プロジェクト」発進
そのブノワ・トゥケが来日し、セミナーで彼個人のプロジェクトであるティーター・トッター(Teeter-Totter)とフェマン(Fait-Main)のワインを試飲しました。
ブノワ・トゥケはフランス・リヨンの出身。ボルドー大学で醸造を学び、ミシェル・ロランと知り合います。そしてミシェル・ロランから派遣されて研修として米国に来ました。アンディ・エリクソンの下でスクリーミング・イーグルやダラ・ヴァレ、オーヴィッド、ダンシング・ヘアといったワイナリーで働きます。その後、レアムのワインメーカーになり、100点ワインを輩出して注目を集めました。レアムでは現在は共同オーナーになっています。
ティーター・トッターはシーソーの意味。ラベルにはシーソーに乗ったネズミと象(ネズミの方が下がっている)という絵柄が描かれています。「シーソーに乗った小さなねずみ(ブノワが造るワイン)が、巨象(巨匠のワイン)に立ち向かう」という意味を込めているのだとか。リーズナブルな価格で高品質なワインを造ることを目的にしています。トーマス・リヴァース・ブラウンが作るダブルダイヤモンドあたりと、コンセプトや価格帯的には共通すると言っていいでしょう。2012年にブランドを始めたときは100ケースほどでしたが、現在は6000ケースほどにまで成長しています。
ティーター・トッターのシャルドネ ナパ・ヴァレー2022(7000円)から試飲しました。Beckstofferがカーネロスに持っている畑のブドウを使っています。おそらく下の「Carneros Creek Vineyard」です。ニュートンもここの単一畑を作っています。場所はハドソンとハイドのちょうど中間くらい。単一畑のワインですが、畑名を名乗っていないのは契約の関係だそう。単一畑を名乗る場合、契約が高くなるので、ワインを少しでも安くするために、「ナパ・ヴァレー」としています。

半分新樽、半分はステンレスタンクで発酵、100%マロラクティック発酵しています。シャルドネのワイン造りではミネラル感や低アルコール、酸、バランスを大事にしているそうです。
ミネラル感強く、ほのかなかんきつにピーチのフレーバー。酸高くエレガントなシャルドネです。ナパヴァレーとは言われなければ気がつかないかも。サンタ・クルーズ・マウンテンズあたりのシャルドネのイメージに近いです。
次はカベルネ・ソーヴィニョン ナパヴァレー2021(12000円)。こちらは2021年からラザフォードにあるBeckstoffer Georges III(ジョージズ・ザ・サード)の畑のカベルネ・ソーヴィニヨンを使っています。この畑はナパ開発の初期に大地主だったジョージ・ヨーントが娘婿のトーマス・ラザフォードに与えた土地の一部。最初の植樹は19世紀にさかのぼります。その後、ボーリュー・ヴィンヤード(BV)を経てアンディ・ベクストファーの畑になりました。銘醸畑の一つで、300エーカーとかなり広く、多くのワイナリーがここからブドウを調達しています。シャルドネ同様、ワインには畑名は記されていません。

ブノワ・トゥケが師匠であるミシェル・ロランから学んだことの一つとして、カベルネ・ソーヴィニョンに地元のブドウ、例えば南アフリカであればピノタージュ、を少しブレンドする、ということがあります。そこで、このワインもカベルネ・ソーヴィニョンのほか、ジンファンデル、プティ・シラー、シャルボノをそれぞれ5%ほど入れています。カベルネ・ソーヴィニョン以外の3品種はカリストガからでシャルボノは、トファネリ(ターリーなどが使用)の畑です。樹齢40年で無灌漑栽培されています。
なお、シャルボノについては、こちらをご覧ください:絶滅寸前、シャルボノに惹かれる人たち
プラムやチョコレート、黒鉛。香り高くスパイシー。パワフルで美味しい。酸もあり、濃密な味わいとスパイスが心地よい。これはコスパ高いと思います。
フェ・マンに移ります。「フェ・マン」はフランス語で手造りの意味だとのこと。ラベルには出身地であるリヨンの紋章が描かれています。彼がフランスからナパに来たときに、ナパで作られている品種はボルドーに近いけれど、ナパの地域の特性はむしろブルゴーニュ的だと感じたそうです。さまざまなテロワールが存在するというのがその理由で、テロワールを表現する「単一ヴィンテージ、単一畑」のワインを造るブランドがフェ・マンとなります。
今回は2021年のワインからナパヴァレーのカベルネ・ソーヴィニヨン(2万円)、ベクストファー・ミズーリ・ホッパー カベルネ・ソーヴィニョン(3万5000円)、ベクストファー・ラス・ピエドラス カベルネ・ソーヴィニョン(4万8000円)。そして2016年のベクストファー・ラス・ピエドラス カベルネ・ソーヴィニョンです。
ナパヴァレーのカベルネ・ソーヴィニヨンは2021年が最初のヴィンテージ。これだけは複数畑のブレンドです。単一畑として出しているベクストファー ラス・ピエドラス・ヴィンヤード(セント・ヘレナ)、ベクストファーミズーリ・ホッパー・ヴィンヤード(オークヴィル西側)、ティエラ・ロハ・ヴィンヤード(オークヴィル東側)の3つの畑を中心に、今後単一畑として候補になっている畑のブドウをブレンドしています。
ちなみに、ベクストファー・ラス・ピエドラスの、このワインに使っているブロックは、元々シュレーダーが使っていたところで、シュレーダーがコンステレーションの畑だけを使うことになって手放したところだとか。現在は植え替え中で樹齢が若いために、こちらに入れているそうです。(ブノワ・トゥケさん、結構こんなことまで話していいのということも話してくれます)
濃厚でリッチです。ブルーベリーなど青系果実を強く感じます。適度に酸も感じ、濃厚ですがバランスは悪くないです。
次はベクストファー・ミズーリ・ホッパーの2021年です。ミズーリ・ホッパーはオークヴィルの西側、有名なヴァイン・ヒル・ランチやドミナスのユリシーズの畑に隣接しています。沖積扇状地で表土が深く、樹勢が強くなるそうです。

顕著なカシスの香りに、とてもなめらかなタンニン。まさにト・カロンなどオークヴィルの西側の味わいです。リッチでふくよか、ナパのカベルネのお手本と言っていいでしょう。
次はベクストファー・ラス・ピエドラスの2021年。ラス・ピエドラスはセント・ヘレナの西側。これも有名なベクストファー・ドクター・クレーンの少し西にいったところにある畑です。かなり山に近いところで、畑に石がごろごろしています。これが「ラス・ピエドラス」(スペイン語の小石)の語源となっています。


この畑ではライヤー(Lyre)という、仕立ての方法を取っています。写真のように、枝をU字型に誘引して、その下にブドウの実が付くようにします。エアフローがいいのとブドウに日があたりすぎないというメリットがあります。ただ、これが最適な仕立てというわけではなく、今では他の仕立てでよりよい効果が得られる方法もあるそうですが、ここは歴史的にこの仕立てを続けています。
オークヴィルよりも温暖なセント・ヘレナですが、ワインの味わいはこちらの方が引き締まった印象です。赤果実もあり酸とタンニンがしっかりしています。この畑はカベルネ・ソーヴィニョンのクローンが4と337の2種類ありますが、2021年は337を多く使っていることもこのエレガントな印象につながっているようです。
最後に、ヴィンテージ違いで2016年のラス・ピエドラスです。やや固い印象の2021年に対して、2016年はタンニンが多少ほぐれて柔らかさが出てきていますが、まだまだ強いワインです。第3のアロマは感じません。この年は一番味わいが強いと言われているクローン4を多く使っており、それも味わいにつながっています。
ところで、今回は2021年の試飲でしたが、次の2022年は9月10日前後の熱波で難しいヴィンテージだったと言われています。40℃を超えるような熱波が一週間ほども続き、酸が落ちてしまったり、ブドウが「閉じた」状態になってしまったりしました。この熱波の前に収穫したか、熱波の後に収穫したかで、ワインの性格も大きく変わります。フェ・マンは熱波の前に収穫できたそうです。このほか、ハーランやダラ・ヴァレなどのプレミアムなワイナリーも早く摘んだとか。
9月上旬というのは熱波が起こりやすい時期なので、その前に収穫することが今後より大事になり、早く収穫できる畑を今後は選んでいきたいとのこと。ただ、これは早く摘めばいいというほど簡単な話ではありません。その時期に摘んでもフェノリックなどがちゃんと成熟していることが必要です。そのために、無灌漑での栽培や、早い時期に剪定することなどが必要で、栽培により手間をかけなければいけません。
ここまで説明してきたように、ティーター・トッターにしても、フェ・マンにしてもベクストファーの畑のブドウを多く使っています。引く手あまたの栽培家ですが、どうしてこれだけブドウの提供を受けられるようになったのか、質問してみました。
レアムの創設者がアンディ・ベクストファーと仲が良かったというのが最初にあり、またブノワ・トゥケが作るワインの高品質であることが加わっていい関係を築いたとのことでした。長年の信頼で培ったきずながあり、いまは欲しければもっともらうことも可能だとのこと。
最後に、今回の試飲では登場しなかったティエラ・ロハの畑について聞きました。この畑は2023年にナパにいったときに、訪問しています(ナパツアー4日目その1ーー畑作業をむちゃくちゃ楽しむ)。オークヴィルの東側の斜面の畑で、ダラ・ヴァッレの畑の下にあります。

ブノワ・トゥケによると、オーナーのリンダさんは子供をかわいがるようにブドウを扱っており、その精神と考えが彼とも合っているそうです。2021年から作り始めたワインですが、長く関係を続けていきたいとのこと。畑はヴァカ山脈系の火山性土壌で、色が赤く、ワインは力強く、ミネラル感を強く感じるそうです。


ナパのトップ・ワインメーカー3人の競演!? 「夢の新プロジェクト」発進
そのブノワ・トゥケが来日し、セミナーで彼個人のプロジェクトであるティーター・トッター(Teeter-Totter)とフェマン(Fait-Main)のワインを試飲しました。
ブノワ・トゥケはフランス・リヨンの出身。ボルドー大学で醸造を学び、ミシェル・ロランと知り合います。そしてミシェル・ロランから派遣されて研修として米国に来ました。アンディ・エリクソンの下でスクリーミング・イーグルやダラ・ヴァレ、オーヴィッド、ダンシング・ヘアといったワイナリーで働きます。その後、レアムのワインメーカーになり、100点ワインを輩出して注目を集めました。レアムでは現在は共同オーナーになっています。
ティーター・トッターはシーソーの意味。ラベルにはシーソーに乗ったネズミと象(ネズミの方が下がっている)という絵柄が描かれています。「シーソーに乗った小さなねずみ(ブノワが造るワイン)が、巨象(巨匠のワイン)に立ち向かう」という意味を込めているのだとか。リーズナブルな価格で高品質なワインを造ることを目的にしています。トーマス・リヴァース・ブラウンが作るダブルダイヤモンドあたりと、コンセプトや価格帯的には共通すると言っていいでしょう。2012年にブランドを始めたときは100ケースほどでしたが、現在は6000ケースほどにまで成長しています。
ティーター・トッターのシャルドネ ナパ・ヴァレー2022(7000円)から試飲しました。Beckstofferがカーネロスに持っている畑のブドウを使っています。おそらく下の「Carneros Creek Vineyard」です。ニュートンもここの単一畑を作っています。場所はハドソンとハイドのちょうど中間くらい。単一畑のワインですが、畑名を名乗っていないのは契約の関係だそう。単一畑を名乗る場合、契約が高くなるので、ワインを少しでも安くするために、「ナパ・ヴァレー」としています。

半分新樽、半分はステンレスタンクで発酵、100%マロラクティック発酵しています。シャルドネのワイン造りではミネラル感や低アルコール、酸、バランスを大事にしているそうです。
ミネラル感強く、ほのかなかんきつにピーチのフレーバー。酸高くエレガントなシャルドネです。ナパヴァレーとは言われなければ気がつかないかも。サンタ・クルーズ・マウンテンズあたりのシャルドネのイメージに近いです。
次はカベルネ・ソーヴィニョン ナパヴァレー2021(12000円)。こちらは2021年からラザフォードにあるBeckstoffer Georges III(ジョージズ・ザ・サード)の畑のカベルネ・ソーヴィニヨンを使っています。この畑はナパ開発の初期に大地主だったジョージ・ヨーントが娘婿のトーマス・ラザフォードに与えた土地の一部。最初の植樹は19世紀にさかのぼります。その後、ボーリュー・ヴィンヤード(BV)を経てアンディ・ベクストファーの畑になりました。銘醸畑の一つで、300エーカーとかなり広く、多くのワイナリーがここからブドウを調達しています。シャルドネ同様、ワインには畑名は記されていません。

ブノワ・トゥケが師匠であるミシェル・ロランから学んだことの一つとして、カベルネ・ソーヴィニョンに地元のブドウ、例えば南アフリカであればピノタージュ、を少しブレンドする、ということがあります。そこで、このワインもカベルネ・ソーヴィニョンのほか、ジンファンデル、プティ・シラー、シャルボノをそれぞれ5%ほど入れています。カベルネ・ソーヴィニョン以外の3品種はカリストガからでシャルボノは、トファネリ(ターリーなどが使用)の畑です。樹齢40年で無灌漑栽培されています。
なお、シャルボノについては、こちらをご覧ください:絶滅寸前、シャルボノに惹かれる人たち
プラムやチョコレート、黒鉛。香り高くスパイシー。パワフルで美味しい。酸もあり、濃密な味わいとスパイスが心地よい。これはコスパ高いと思います。
フェ・マンに移ります。「フェ・マン」はフランス語で手造りの意味だとのこと。ラベルには出身地であるリヨンの紋章が描かれています。彼がフランスからナパに来たときに、ナパで作られている品種はボルドーに近いけれど、ナパの地域の特性はむしろブルゴーニュ的だと感じたそうです。さまざまなテロワールが存在するというのがその理由で、テロワールを表現する「単一ヴィンテージ、単一畑」のワインを造るブランドがフェ・マンとなります。
今回は2021年のワインからナパヴァレーのカベルネ・ソーヴィニヨン(2万円)、ベクストファー・ミズーリ・ホッパー カベルネ・ソーヴィニョン(3万5000円)、ベクストファー・ラス・ピエドラス カベルネ・ソーヴィニョン(4万8000円)。そして2016年のベクストファー・ラス・ピエドラス カベルネ・ソーヴィニョンです。
ナパヴァレーのカベルネ・ソーヴィニヨンは2021年が最初のヴィンテージ。これだけは複数畑のブレンドです。単一畑として出しているベクストファー ラス・ピエドラス・ヴィンヤード(セント・ヘレナ)、ベクストファーミズーリ・ホッパー・ヴィンヤード(オークヴィル西側)、ティエラ・ロハ・ヴィンヤード(オークヴィル東側)の3つの畑を中心に、今後単一畑として候補になっている畑のブドウをブレンドしています。
ちなみに、ベクストファー・ラス・ピエドラスの、このワインに使っているブロックは、元々シュレーダーが使っていたところで、シュレーダーがコンステレーションの畑だけを使うことになって手放したところだとか。現在は植え替え中で樹齢が若いために、こちらに入れているそうです。(ブノワ・トゥケさん、結構こんなことまで話していいのということも話してくれます)
濃厚でリッチです。ブルーベリーなど青系果実を強く感じます。適度に酸も感じ、濃厚ですがバランスは悪くないです。
次はベクストファー・ミズーリ・ホッパーの2021年です。ミズーリ・ホッパーはオークヴィルの西側、有名なヴァイン・ヒル・ランチやドミナスのユリシーズの畑に隣接しています。沖積扇状地で表土が深く、樹勢が強くなるそうです。

顕著なカシスの香りに、とてもなめらかなタンニン。まさにト・カロンなどオークヴィルの西側の味わいです。リッチでふくよか、ナパのカベルネのお手本と言っていいでしょう。
次はベクストファー・ラス・ピエドラスの2021年。ラス・ピエドラスはセント・ヘレナの西側。これも有名なベクストファー・ドクター・クレーンの少し西にいったところにある畑です。かなり山に近いところで、畑に石がごろごろしています。これが「ラス・ピエドラス」(スペイン語の小石)の語源となっています。


この畑ではライヤー(Lyre)という、仕立ての方法を取っています。写真のように、枝をU字型に誘引して、その下にブドウの実が付くようにします。エアフローがいいのとブドウに日があたりすぎないというメリットがあります。ただ、これが最適な仕立てというわけではなく、今では他の仕立てでよりよい効果が得られる方法もあるそうですが、ここは歴史的にこの仕立てを続けています。
オークヴィルよりも温暖なセント・ヘレナですが、ワインの味わいはこちらの方が引き締まった印象です。赤果実もあり酸とタンニンがしっかりしています。この畑はカベルネ・ソーヴィニョンのクローンが4と337の2種類ありますが、2021年は337を多く使っていることもこのエレガントな印象につながっているようです。
最後に、ヴィンテージ違いで2016年のラス・ピエドラスです。やや固い印象の2021年に対して、2016年はタンニンが多少ほぐれて柔らかさが出てきていますが、まだまだ強いワインです。第3のアロマは感じません。この年は一番味わいが強いと言われているクローン4を多く使っており、それも味わいにつながっています。
ところで、今回は2021年の試飲でしたが、次の2022年は9月10日前後の熱波で難しいヴィンテージだったと言われています。40℃を超えるような熱波が一週間ほども続き、酸が落ちてしまったり、ブドウが「閉じた」状態になってしまったりしました。この熱波の前に収穫したか、熱波の後に収穫したかで、ワインの性格も大きく変わります。フェ・マンは熱波の前に収穫できたそうです。このほか、ハーランやダラ・ヴァレなどのプレミアムなワイナリーも早く摘んだとか。
9月上旬というのは熱波が起こりやすい時期なので、その前に収穫することが今後より大事になり、早く収穫できる畑を今後は選んでいきたいとのこと。ただ、これは早く摘めばいいというほど簡単な話ではありません。その時期に摘んでもフェノリックなどがちゃんと成熟していることが必要です。そのために、無灌漑での栽培や、早い時期に剪定することなどが必要で、栽培により手間をかけなければいけません。
ここまで説明してきたように、ティーター・トッターにしても、フェ・マンにしてもベクストファーの畑のブドウを多く使っています。引く手あまたの栽培家ですが、どうしてこれだけブドウの提供を受けられるようになったのか、質問してみました。
レアムの創設者がアンディ・ベクストファーと仲が良かったというのが最初にあり、またブノワ・トゥケが作るワインの高品質であることが加わっていい関係を築いたとのことでした。長年の信頼で培ったきずながあり、いまは欲しければもっともらうことも可能だとのこと。
最後に、今回の試飲では登場しなかったティエラ・ロハの畑について聞きました。この畑は2023年にナパにいったときに、訪問しています(ナパツアー4日目その1ーー畑作業をむちゃくちゃ楽しむ)。オークヴィルの東側の斜面の畑で、ダラ・ヴァッレの畑の下にあります。

ブノワ・トゥケによると、オーナーのリンダさんは子供をかわいがるようにブドウを扱っており、その精神と考えが彼とも合っているそうです。2021年から作り始めたワインですが、長く関係を続けていきたいとのこと。畑はヴァカ山脈系の火山性土壌で、色が赤く、ワインは力強く、ミネラル感を強く感じるそうです。
シリコンバレー・バンクによるワイン業界の分析レポートが発表されました。2024年にはワイナリーのテイスティングルーム経由での販売などDtC(Direct-to-Consumer)のチャネルが回復することが期待されていましたが、実際には低迷を続けており、需要低迷への打開策はあまり見えていないのが現状です。

上のグラフはプレミアムなワイナリーの成長率を2000年からプロっとしたものですが、コロナ禍での一時的な伸びはあったものの、成長率は低落傾向にあり、マイナスが常態化するのも遠い未来のことではなさそうです。

アンケート調査から昨年がいい年だったのか悪かったのかを集計したものを、この3年間で比較したグラフです。グラフの右の方ほど、前年が良かったことを示しますが、2022年は「A good year」から右が70%で「A disappointing year」から左が18%。それに対して昨年は「A good year」から右が29%で「A disappointing year」から左が50%。ネガティブな評価が上回っています。

実際のワイン消費量を見ても2020年はコロナ禍の巣ごもり需要で増えましたが、2021年以降はマイナス成長に陥っています。

ワイン消費が伸び悩む大きな理由が50代以下でのワイン人気の低さです。20代、30代、40代、50代、60代、70代のワインとビール、スピリッツその他の好みを聞いた結果として若年層ほど、スピリッツや「その他」の比率が高くなっています。健康志向でアルコールそのものを飲まなかったり、金銭的余裕がなくて比較的高額なワインに触手が伸びなかったりと、理由はさまざまですが、ともかく若い人のワイン消費の低迷がワイン全体に響いているのは確かです。若年層のビールやスピリッツ市場との競争に勝つため、新たなマーケティング戦略を構築する必要があると見られています。アルコールの健康への影響についても、厳しいガイドラインが今年発動されると見られており、低アルコールやノンアルコールワインの開発で、新たな市場を開拓する必要も出てくるでしょう。

アンケート結果では59%がオーバーサプライ状態であるとしています。現在の需要に応じた生産調整は必須の状況です。2024年のブドウの生産量は2008年以来の少なさでしたが、それでもオーバーサプライは続きます。2025年は市中在庫の調整が進むと見られていますが、2026年までずれこむという見方もあります。沿岸の高級ワインを算出するエリアではまだ状況は悪くありませんが、内陸の大量生産エリアでは売りに出ているブドウ畑にほとんど買い手がいないと言われています。どの産地においても、ブドウ価格は下がる可能性が高いです。
このレポートも以前は100ページを超える大著でしたが、2023年のシリコンバレー・バンク破綻を経て、昨年は60ページ、今年は40ページとだいぶ薄くなってしまいました。目を通すのはだいぶ楽になりましたが、読み応えというところでは少しさびしさを感じます。

上のグラフはプレミアムなワイナリーの成長率を2000年からプロっとしたものですが、コロナ禍での一時的な伸びはあったものの、成長率は低落傾向にあり、マイナスが常態化するのも遠い未来のことではなさそうです。

アンケート調査から昨年がいい年だったのか悪かったのかを集計したものを、この3年間で比較したグラフです。グラフの右の方ほど、前年が良かったことを示しますが、2022年は「A good year」から右が70%で「A disappointing year」から左が18%。それに対して昨年は「A good year」から右が29%で「A disappointing year」から左が50%。ネガティブな評価が上回っています。

実際のワイン消費量を見ても2020年はコロナ禍の巣ごもり需要で増えましたが、2021年以降はマイナス成長に陥っています。

ワイン消費が伸び悩む大きな理由が50代以下でのワイン人気の低さです。20代、30代、40代、50代、60代、70代のワインとビール、スピリッツその他の好みを聞いた結果として若年層ほど、スピリッツや「その他」の比率が高くなっています。健康志向でアルコールそのものを飲まなかったり、金銭的余裕がなくて比較的高額なワインに触手が伸びなかったりと、理由はさまざまですが、ともかく若い人のワイン消費の低迷がワイン全体に響いているのは確かです。若年層のビールやスピリッツ市場との競争に勝つため、新たなマーケティング戦略を構築する必要があると見られています。アルコールの健康への影響についても、厳しいガイドラインが今年発動されると見られており、低アルコールやノンアルコールワインの開発で、新たな市場を開拓する必要も出てくるでしょう。

アンケート結果では59%がオーバーサプライ状態であるとしています。現在の需要に応じた生産調整は必須の状況です。2024年のブドウの生産量は2008年以来の少なさでしたが、それでもオーバーサプライは続きます。2025年は市中在庫の調整が進むと見られていますが、2026年までずれこむという見方もあります。沿岸の高級ワインを算出するエリアではまだ状況は悪くありませんが、内陸の大量生産エリアでは売りに出ているブドウ畑にほとんど買い手がいないと言われています。どの産地においても、ブドウ価格は下がる可能性が高いです。
このレポートも以前は100ページを超える大著でしたが、2023年のシリコンバレー・バンク破綻を経て、昨年は60ページ、今年は40ページとだいぶ薄くなってしまいました。目を通すのはだいぶ楽になりましたが、読み応えというところでは少しさびしさを感じます。
カレラ(Calera)にとって日本市場は大のお得意先。以前聞いたときは生産量の6割もが日本に来ているとのことでした。米国でカレラが評価される前から日本では人気があったため、昔は日本人気を揶揄されることもあったほど。
そんなこともあり、カレラは日本限定のキュベを従来から作っていました。セントラル・コーストのワインに一部自社畑のワインを加えるというのが常道です。輸入元がエノテカに変わってからは、しばらくなかったのですが、このほど「ジェンセン・レガシー・キュベ」のシャルドネおよびピノ・ノワールが入ってきています。
ジェンセン・レガシー・キュヴェ・シャルドネ
ジェンセン・レガシー・キュヴェ・ピノ・ノワール
ただ、価格はシャルドネが6600円、ピノ・ノワールが7700円と、いずれもセントラル・コーストの価格+1000円とやや高です。
個人的にはピノ・ノワールでも4000円台で買える、JALUX向けだった「ジョシュ・ジェンセン・セレクション」を買うことを今はお薦めします。
そんなこともあり、カレラは日本限定のキュベを従来から作っていました。セントラル・コーストのワインに一部自社畑のワインを加えるというのが常道です。輸入元がエノテカに変わってからは、しばらくなかったのですが、このほど「ジェンセン・レガシー・キュベ」のシャルドネおよびピノ・ノワールが入ってきています。
ジェンセン・レガシー・キュヴェ・シャルドネ
ジェンセン・レガシー・キュヴェ・ピノ・ノワール
ただ、価格はシャルドネが6600円、ピノ・ノワールが7700円と、いずれもセントラル・コーストの価格+1000円とやや高です。
個人的にはピノ・ノワールでも4000円台で買える、JALUX向けだった「ジョシュ・ジェンセン・セレクション」を買うことを今はお薦めします。
中川ワインの試飲会から美味しかったワインを報告します。実はスクリーミング・イーグルと同じ日で、行く時間が遅かったため、いくつかのワインは飲み損ねました。

アルマ・デ・カトレアのソーヴィニヨン・ブラン(4800円)。服雑味があり、ワンランク上の味わい。

サンタ・クルーズ・マウンテンズのマウント・エデンが南の冷涼なエドナ・ヴァレーの畑で作るシャルドネ(4800円)。うま味ある味わいはサンタ・クルーズのものと共通性があるかもしれません。コスパ高い。

右はメリーヴェールのプレミアムラインであるプロファイルのシャルドネ「シルエット」(15000円)。酸がきれいでおいしい。左はトアー(Tor)のシャルドネ・キュヴェ・トルチアーナ(19000円)。うま味あり、バランスいい。すべてが高次元ですばらしい。シャルドネ講座で出したかった。

ホーニッグのソーヴィニヨン・ブラン(4000円)。カリフォルニアのソーヴィニヨン・ブランのお手本的ワインだと思います。

期せずしてソーヴィニヨン・ブランが並びました。ナパ・ハイランズのソーヴィニヨン・ブランは初輸入(4800円)。ナパらしいリッチな味わいがナパ・ハイランズらしくていいです。写真省きますが、カベルネもいつもながら安定した仕上がり。

ダックホーンのフラッグシップ・メルロー スリーパームス・ヴィンヤード2021です(15500円)。リッチでチョコレートの風味。

ダックホーンのカベルネ系のフラッグシップ「ディスカッション」(20000円)。リッチな味わい。非常にいいです。

中村倫久さんのノリアのピノ・ノワールは3種出ていましたが、一つは試飲できず、シャローンAVAのブロッソー(9000円)と、ロシアン・リバー・ヴァレーのウミノ・ヴィンヤード(9000円)の2本を試飲しました。これがどちらも素晴らしい。二つの個性も現れ、非常によくできています。

マックマニスの赤はメルローとプティ・シラーとジンファンデルが出ていました(2200円)。この中で一番良かったのがジンファンデル。ジンファンデルらしさが出ています。

ハドソンの「フェニックス」。メルロー中心のブレンドです(14500円)。リッチでこくのある味わいに。

ナパのシニョレッロが作るコスパ系ブランド「トリム」のカベルネ・ソーヴィニヨン(3000円)。2021年はローダイの畑を使っています。リッチでバランスもよく、3000円とは思えないレベルです。

初輸入のベッドロックのカベルネ・ソーヴィニヨン ソノマ(6500円)。バランスが素晴らしい。この価格とは思えないレベルのワイン。
アルマ・デ・カトレアのソーヴィニヨン・ブラン(4800円)。服雑味があり、ワンランク上の味わい。
サンタ・クルーズ・マウンテンズのマウント・エデンが南の冷涼なエドナ・ヴァレーの畑で作るシャルドネ(4800円)。うま味ある味わいはサンタ・クルーズのものと共通性があるかもしれません。コスパ高い。
右はメリーヴェールのプレミアムラインであるプロファイルのシャルドネ「シルエット」(15000円)。酸がきれいでおいしい。左はトアー(Tor)のシャルドネ・キュヴェ・トルチアーナ(19000円)。うま味あり、バランスいい。すべてが高次元ですばらしい。シャルドネ講座で出したかった。
ホーニッグのソーヴィニヨン・ブラン(4000円)。カリフォルニアのソーヴィニヨン・ブランのお手本的ワインだと思います。
期せずしてソーヴィニヨン・ブランが並びました。ナパ・ハイランズのソーヴィニヨン・ブランは初輸入(4800円)。ナパらしいリッチな味わいがナパ・ハイランズらしくていいです。写真省きますが、カベルネもいつもながら安定した仕上がり。
ダックホーンのフラッグシップ・メルロー スリーパームス・ヴィンヤード2021です(15500円)。リッチでチョコレートの風味。
ダックホーンのカベルネ系のフラッグシップ「ディスカッション」(20000円)。リッチな味わい。非常にいいです。
中村倫久さんのノリアのピノ・ノワールは3種出ていましたが、一つは試飲できず、シャローンAVAのブロッソー(9000円)と、ロシアン・リバー・ヴァレーのウミノ・ヴィンヤード(9000円)の2本を試飲しました。これがどちらも素晴らしい。二つの個性も現れ、非常によくできています。
マックマニスの赤はメルローとプティ・シラーとジンファンデルが出ていました(2200円)。この中で一番良かったのがジンファンデル。ジンファンデルらしさが出ています。
ハドソンの「フェニックス」。メルロー中心のブレンドです(14500円)。リッチでこくのある味わいに。
ナパのシニョレッロが作るコスパ系ブランド「トリム」のカベルネ・ソーヴィニヨン(3000円)。2021年はローダイの畑を使っています。リッチでバランスもよく、3000円とは思えないレベルです。
初輸入のベッドロックのカベルネ・ソーヴィニヨン ソノマ(6500円)。バランスが素晴らしい。この価格とは思えないレベルのワイン。
ナパのプレミアムなカベルネ・ソーヴィニヨンの中でも、ミステリアスな存在なのがスクリーミング・イーグルです。現在の市価が安くて50万円台。80万円台や90万円台で売っている店も珍しくなく、高額ワインの多いナパの中でもその存在は抜きんでています(現在はゴースト・ホースの方が価格が上回りますが、こちらはまだ知名度は低いと思います)。生産量も1000ケース足らずと非常に少なく、実際に飲んだという話もほとんど聞いたことがありません。
セカンド・ワインに当たる「ザ・フライト」(以前の名称はセカンド・フライト)にしても、輸入元の希望小売価格は最新ヴィンテージで税込み31万9000円と、ハーラン・エステートの35万円に迫るものがあります。
今回、スクリーミング・イーグルのエステート・マネージャーで、サンタ・バーバラのヒルトやホナタなども管轄するアルマン・ド・メグレ氏が来日し、ザ・フライトを垂直で試飲しながら、話をうかがいました。また、スクリーミング・イーグルとソーヴィニヨン・ブランについても1ヴィンテージずついただきました。アルマン氏にとっても、このように「ザ・フライト」を垂直試飲するのは初めてとのこと。「過去を振り返ることはあまりない」そうです。
ザ・フライトをセカンド・ワインと便宜上書きましたが、実際には別のワインと言った方がいいのかもしれません。カベルネ・ソーヴィニョンが主体のスクリーミング・イーグルに対して、ザ・フライトはメルローが6割くらい入るのが通例です。一般的にはメルローの比率を上げるのは、あまり熟成させなくても飲みやすいようにする、というのが目的ですが、ザ・フライトの場合はメルローだから飲みやすい、というのでもなさそうです。ちなみに、当初は「セカンド・フライト」としていたのを2015年から「ザ・フライト」と変えたのも、ワインを実際に飲んだ人から「これはセカンドではない」というフィードバックを得たからだそうです。実は生産量もスクリーミング・イーグルの方がやや多くて500~900ケース。ザ・フライトは450~800ケースです。また2022年は熱波で酸が落ちた影響でザ・フライトは作りませんでした。

スクリーミング・イーグルの畑はオークヴィルの東側。シルヴァラード・トレイルのすぐ西になります。シルヴァラード・トレイルから東はかなりの斜面になります。ジョセフ・フェルプスのバッカスやダラ・ヴァッレの畑など、距離的には近いですが、特にダラ・ヴァッレの畑は丘一つ上になり、下からは見えません。
また、南側に標高140mほどの丘があります。畑の標高が40数メートルですから100mくらい、畑より高いわけです。このように、ナパの東側のベンチランドの中でもスクリーミング・イーグルの畑はちょっとくぼんだところにあり、周囲よりも少し涼しいという特徴があるそうです。例えば、収穫時のpHは周辺の畑では4.0程度とかなり高くなりますが、スクリーミング・イーグルでは3.4~3.5にとどまります。
スクリーミング・イーグルの創設者はジーン・フィリップス。不動産業で成功し、ナパのオークヴィルに土地を購入したのが1986年。当初はブドウを他のワイナリーに卸していましたが、カベルネ・ソーヴィニョンのブロックの品質が高いことに気付いてワインを造り始め、ロバート・パーカーに認められて有名ワイナリーになりました。
ジーン・フィリップスは2006年にスクリーミング・イーグルを売却、実業家のスタン・クロエンケが購入しましたが、引き継ぎ時にはワイナリーのカギを渡されただけで、畑やワインについては何も教えてもらわなかったとのこと。一から学んでいくことになりました。そこで気付いたことの一つがここのメルローの秀逸さでした。ただ、メルローの栽培もカベルネ・ソーヴィニョンの栽培も同じようにされていたので、メルローは葉を多く残すなど、メルローに合った栽培をすることでさらに品質も上がっていきました。このメルローを中心とした2つのブロックがザ・フライトのコアになっています。なお、45エーカーの畑のうち23エーカーが1980年代に植樹したものので、現在はそれだけを使っています。18エーカーは2006年から2007年に植樹したもので、これまではブレンドに入れていませんが、そろそろ使い始めるかもしれないとのこと。あと、2014~16年に植樹した数ブロックがあります。
2010年には醸造設備を一新し、ブロックごとに醸造できるようになりました。畑は45のブロックに分けられており、栽培も醸造もそれぞれにあった形で行っています。1ブロックでも別醸造のものもあり、合計で150パッチに分けられています。2月初頭に前年のブレンドを行います。
さて、2012年に2007~2010年の「セカンド・フライト」をセットでリリースしたのが、このワインのスタートとなりました。スクリーミング・イーグ0ルは「名前に恥じない究極の品質を目指しており、そのために謙虚であり続けないといけないし、ナンバーワンを続けなければいけない」としているのに対し、ザ・フライトの方は「世界で一番おいしいメルロー主体のワイン」を目指しています。
なお、サンタ・バーバラのThe HiltとJonataも同様に世界最高のシャルドネやピノ・ノワール、シラーを目指しています。シャルドネは明らかにそのポテンシャルがありシラーもニューワールドのシラーでは最高レベルのポテンシャルがあると自負しています。ピノ・ノワールはまだ苦戦していますが、目標はそこに置いています。
こういった世界最高を目指す精神の現れはコルクにも「Fly High and Proud」として描かれています。

スクリーミング・イーグルでは栽培はオーガニックですが、特にオーガニックであることをうたってはいません。マーケティング的に使われるのは本意ではないとのこと。ビオディナミには従っていません。ただ、月や太陽が栽培において重要だという意味ではその精神に共感しているところもあるようです。
試飲に移ります。今回は2012、2014、2015、2016、2019、2020の6ヴィンテージです。2015と2016はWine to Styleの在庫から、残りの4本はワイナリーからマグナムで持参いただいています。
ナパの天候において重要なのは気温と夜間の冷涼さ、生育期間の長さであり、「敵」になるのは熱波や干ばつです。2012年は比較的暖かいヴィンテージ。雨もやや多い年です。
以下にコメントを記しますが、相対的にどれがいいと思ったかを示すために、便宜的に得点を入れます。ほかの回と比較するというより、今回のワインの比較用と思ってください。
2012年はカシスの香りに、ちょっとミンティな風味、花の香り。酸高くタンニン強い。そこそこ年月を経ているにもかかわらず、果実味が強く熟成によるアロマはまだほとんどでてきていません。96
2014年は2012年よりも酸が低く、ブルーベリーの香りが顕著。ストラクチャーのしっかりしたワイン。94
2015年はタンニンがしっかり。果実の味わいは2012年と2014年の中間くらい。93
2016年は赤系果実とブルーベリーの香り。これもタンニンは強く、やや閉じ気味に感じられました。95
2019年もちょっと閉じている感じがありましたが、パワフルで酸高くポテンシャルを感じます。赤系と黒系果実も豊か。97
2020年はバランスよく、酸高く赤果実も強い。タンニンも強い。96
ちなみに、同席した森覚さんはマグナムの12、14はメルローの特徴がまだあまりでてきておらず、750mlの15、16は開いていたとおっしゃっていました。また15年以降の最近のヴィンテージの方がメルローらしさがより出てきているとおっしゃっていました。赤系の果実を感じたのは最近のヴィンテージの方が多かったので、そのあたりがメルローらしいところなのかもしれません(メルロー難しくてよくわかりません)。
総じて言えることは、パワフルでストラクチャーがありタンニンも強い傾向にあること。飲み頃がいつになるのか聞いてみたところ「わからない」とのこと。私の感覚では2012年のものでもまだ10年くらいは寝かせた方がポテンシャルを発揮するような気がしました。メルロー中心のセカンドワインというと、早飲みタイプなのかと想像してしまいがちですが、ザ・フライトは早飲みワインではなく20年は熟成できるし、する価値があるワインだと思います。
アルマン氏はザ・フライトで感じてほしいこととして「メルローの個性と精密性。口に含んだときにアタックがあり、酸も感じられ、ミッドパレットにしっかりした果実味があり、余韻にちょっと田舎っぽさを含みながらも骨格とエレガンスがある」というところだと語っていました。
これまで、Wine to Styleの試飲会でザ・フライトを数回試飲していますが、あわただしい試飲会では1つのワインにかけられるのは数秒。そこで価値を見極めるのは難しく、これまで試飲会で良かったワインとして紹介したことはなかったと思います。今回じっくり試飲して、やっとそのスケールの大きさが理解できた感じがしました。
ところで、スクリーミング・イーグルの畑の中でメルローは東の方に多く植えられています。東の方は西向き斜面になるので、より太陽をよく浴びます。一般的にはメルローは比較的冷涼なところを好むと言われているので、西の方に植えるのが常道だと思いますが、スクリーミング・イーグルではそうはなっていません。
前述のように、スクリーミング・イーグルやザ・フライトに現在使っているのは1980年代に創設者のジーン・フィリップスが植えたブドウです。つまり、この選択をしたのもジーン・フィリップスです。アルマン氏に言わせると彼女は素晴らしいガーデナーだとのことで、彼女の直観によって植えられたのだそうです。ブロックの一つは過去に小川が流れていたところで、水はけ良く石がごろごろしているということで、これも粘土質などやや水を保持する土壌を好むといわれているメルロー向き土壌とは異なっています。このような理屈ではないところにスクリーミング・イーグルの魅力の一つがあるのかもしれません。
ザ・フライトの垂直試飲の後は、食事を取りながらソーヴィニヨン・ブランとスクリーミング・イーグルをいただきました。
ソーヴィニヨン・ブランは、一時期はカベルネ・ソーヴィニョンよりも高く取引されていたほどのレアワイン(Wine-Searcherのデータでは、今はカベルネ・ソーヴィニョンよりちょっと安いようです)。日本では100万円を超える値付けも珍しくありません。
ちなみに生産量は当初は20~50ケース。2016年以降は100~125ケースで、2019年は150ケースと過去最多だったとのこと。
ソーヴィニヨン・ブランを始めたのは試飲やメーカーズ・ディナーのときに白ワインも欲しいからだそうです。オーナーが代わった2006年に植樹して2010年からワインを造っています。この2010年はお世辞にもいいできではなかったそうですが、翌年以降は世に出せる品質になっていきました。最初は市販するつもりはなかったそうですが、レベルが上がったことで「Screaming Eagle」の名を冠することにしました。畑は1ヘクタールもなく、かつて川が流れていた少し粘土質の土壌だそうです。クローンはソーヴィニヨン・ムスケと、2つのソーヴィニヨン・ブランのクローンを使っています。
収穫は何度かに分けて行います。果実の色で収穫時期を決めますが、あえてまだ緑のものを含めることもあるそうです。収穫した果実は除梗してプレス。500~600リットルのフレンチオークの樽とステンレスの樽で発酵し、バトナージュもするそうです。10カ月樽熟成して、タンクに移して2~4カ月落ち着かせてからボトル詰めします。果実の美しさを残し、酸が出すぎないようにしているとのこと。収穫時のpHは2.9~3.2と非常に低く、酸の管理は一番難しいとのことです。MLFはヴィンテージによって行ったり行わなかったりします。
2020年のソーヴィニヨン・ブランを飲みました。第一印象は香りの高さでソーヴィニヨン・ムスケらしさがよく出ています。少し柑橘もありますが、メロンのような熟した果実の香りで、酸はやや低めに感じます。きれいでほのかな樽香。値段のことはさておき、トップクラスのソーヴィニヨン・ブランの一つであることは間違いありません。
さて、最後はいよいよスクリーミング・イーグル2021です。Vinousのアントニオ・ガッローニは100点を付けています。
青系と黒系の果実の香り。シルキーなタンニンで、スムーズ、丸い味わい。一方で酸も高くストラクチャーもあり、エネルギーを秘めた感じがします。ザ・フライトと比べて親しみやすく、飲みやすいワインですが、おそらく熟成によっても魅力が出てくるでしょう。98。
スクリーミング・イーグルの方が、ザ・フライトよりも飲み方を問わないように感じました。バーサタイルなワインという印象です。1ヴィンテージしか飲んでいないので、あくまでもこのワインだけの印象ではありますが。
スクリーミング・イーグルというとメーリング・リストに入った数少ない人しか買えないワインというイメージがありますが、実際にはメーリング・リストで売られているのは6割程度で、輸出分も3割くらいあるそうです(残りはごくわずかな米国内の流通)。メーリング・リストでごく限られた顧客だけが飲めるワインであるよりも、高級ホテルやレストランなどで、世界のトップワインと並んで飲んでもらうワインであることを重視したいとのことでした。なお、メーリング・リストは登録している人が亡くなっても、ほとんどの場合子供が親の名義で購入を続けるので、ほとんど空きは出てこないとのこと。
最後にワインメーカーのニック・ギスラソンについて伺いました。20代という若さでワインメーカーに抜擢されたニックですが、そのエピソードについて聞いてみました。
ニックはワインメーカーになる前、2010年からワイナリーで働き始めていました。2010年の収穫や醸造が一段落した12月に、それまでのワインメーカーだったアンディ・エリクソンが退任することになりました。退任の理由はアンディ自身が「スクリーミング・イーグルにはフルタイムのワインメーカーが必要だ」と考えたたmです。アルマン氏はその後4カ月で志望者20~25人とインタビューしましたが、エゴが強かったり、ワインのレジュメが決まっていて合わせる気がない人が多かったり、自分の履歴書に1行加えたいだけの人だったりと適任者ははなかなか見つかりませんでした。そのときにニックが「自分ではだめか」と聞いてきたそうです。
若いしどうだろうかと思ったのですが、ニックは「6カ月くれたら自分がワインメーカーとしてふさわしいことを証明する」と言い、彼を見ることにしました。
それで採用を中断したのですが。彼の働きぶりと才能が素晴らしく、年齢は関係ないがわかり、2011年に正式にワインメーカーとなりました。ただ最初の5年間は見た目が若すぎるので、雑誌のインタビューなど表には出さなかったそうです。
ニックは花火師として日本に来たことがあり、また今ではビール醸造も行っていますが、そのように多趣味なところも評価しているそうです。一つのことにのめり込むとほかが見えなくなるからで、奥さんと子供、花火師、ビールが彼にあるのがいいところだそうです。またワインと花火は「サプライズな表現」が大事といったところに共通点があると考えており、彼が作るスクリーミング・イーグルだからこそ、表現が豊かでサプライズの要素があるのだとか。
今回のワインだけでスクリーミング・イーグルが分かったなどとは微塵も思いませんが、貴重な体験ができたこと、ワインの一端にでも触れることができたことは大変勉強になりました。また、これまで真の価値があまりわからなかったザ・フライトも素晴らしいワインであることがわかり、非常に魅力を感じるようになりました。参加させていただいたWine to Styleさん、またご一緒いただいた皆様ありがとうございました。
最後の最後に、長くなったので紹介を省いてしまいましたが、マンダリンオリエンタル東京の中華も素晴らしく美味しかったです。点心とソーヴィニヨン・ブラン、スペアリブとスクリーミング・イーグルなど、素晴らしい組み合わせでした。




セカンド・ワインに当たる「ザ・フライト」(以前の名称はセカンド・フライト)にしても、輸入元の希望小売価格は最新ヴィンテージで税込み31万9000円と、ハーラン・エステートの35万円に迫るものがあります。
今回、スクリーミング・イーグルのエステート・マネージャーで、サンタ・バーバラのヒルトやホナタなども管轄するアルマン・ド・メグレ氏が来日し、ザ・フライトを垂直で試飲しながら、話をうかがいました。また、スクリーミング・イーグルとソーヴィニヨン・ブランについても1ヴィンテージずついただきました。アルマン氏にとっても、このように「ザ・フライト」を垂直試飲するのは初めてとのこと。「過去を振り返ることはあまりない」そうです。
ザ・フライトをセカンド・ワインと便宜上書きましたが、実際には別のワインと言った方がいいのかもしれません。カベルネ・ソーヴィニョンが主体のスクリーミング・イーグルに対して、ザ・フライトはメルローが6割くらい入るのが通例です。一般的にはメルローの比率を上げるのは、あまり熟成させなくても飲みやすいようにする、というのが目的ですが、ザ・フライトの場合はメルローだから飲みやすい、というのでもなさそうです。ちなみに、当初は「セカンド・フライト」としていたのを2015年から「ザ・フライト」と変えたのも、ワインを実際に飲んだ人から「これはセカンドではない」というフィードバックを得たからだそうです。実は生産量もスクリーミング・イーグルの方がやや多くて500~900ケース。ザ・フライトは450~800ケースです。また2022年は熱波で酸が落ちた影響でザ・フライトは作りませんでした。

スクリーミング・イーグルの畑はオークヴィルの東側。シルヴァラード・トレイルのすぐ西になります。シルヴァラード・トレイルから東はかなりの斜面になります。ジョセフ・フェルプスのバッカスやダラ・ヴァッレの畑など、距離的には近いですが、特にダラ・ヴァッレの畑は丘一つ上になり、下からは見えません。
また、南側に標高140mほどの丘があります。畑の標高が40数メートルですから100mくらい、畑より高いわけです。このように、ナパの東側のベンチランドの中でもスクリーミング・イーグルの畑はちょっとくぼんだところにあり、周囲よりも少し涼しいという特徴があるそうです。例えば、収穫時のpHは周辺の畑では4.0程度とかなり高くなりますが、スクリーミング・イーグルでは3.4~3.5にとどまります。
スクリーミング・イーグルの創設者はジーン・フィリップス。不動産業で成功し、ナパのオークヴィルに土地を購入したのが1986年。当初はブドウを他のワイナリーに卸していましたが、カベルネ・ソーヴィニョンのブロックの品質が高いことに気付いてワインを造り始め、ロバート・パーカーに認められて有名ワイナリーになりました。
ジーン・フィリップスは2006年にスクリーミング・イーグルを売却、実業家のスタン・クロエンケが購入しましたが、引き継ぎ時にはワイナリーのカギを渡されただけで、畑やワインについては何も教えてもらわなかったとのこと。一から学んでいくことになりました。そこで気付いたことの一つがここのメルローの秀逸さでした。ただ、メルローの栽培もカベルネ・ソーヴィニョンの栽培も同じようにされていたので、メルローは葉を多く残すなど、メルローに合った栽培をすることでさらに品質も上がっていきました。このメルローを中心とした2つのブロックがザ・フライトのコアになっています。なお、45エーカーの畑のうち23エーカーが1980年代に植樹したものので、現在はそれだけを使っています。18エーカーは2006年から2007年に植樹したもので、これまではブレンドに入れていませんが、そろそろ使い始めるかもしれないとのこと。あと、2014~16年に植樹した数ブロックがあります。
2010年には醸造設備を一新し、ブロックごとに醸造できるようになりました。畑は45のブロックに分けられており、栽培も醸造もそれぞれにあった形で行っています。1ブロックでも別醸造のものもあり、合計で150パッチに分けられています。2月初頭に前年のブレンドを行います。
さて、2012年に2007~2010年の「セカンド・フライト」をセットでリリースしたのが、このワインのスタートとなりました。スクリーミング・イーグ0ルは「名前に恥じない究極の品質を目指しており、そのために謙虚であり続けないといけないし、ナンバーワンを続けなければいけない」としているのに対し、ザ・フライトの方は「世界で一番おいしいメルロー主体のワイン」を目指しています。
なお、サンタ・バーバラのThe HiltとJonataも同様に世界最高のシャルドネやピノ・ノワール、シラーを目指しています。シャルドネは明らかにそのポテンシャルがありシラーもニューワールドのシラーでは最高レベルのポテンシャルがあると自負しています。ピノ・ノワールはまだ苦戦していますが、目標はそこに置いています。
こういった世界最高を目指す精神の現れはコルクにも「Fly High and Proud」として描かれています。
スクリーミング・イーグルでは栽培はオーガニックですが、特にオーガニックであることをうたってはいません。マーケティング的に使われるのは本意ではないとのこと。ビオディナミには従っていません。ただ、月や太陽が栽培において重要だという意味ではその精神に共感しているところもあるようです。
試飲に移ります。今回は2012、2014、2015、2016、2019、2020の6ヴィンテージです。2015と2016はWine to Styleの在庫から、残りの4本はワイナリーからマグナムで持参いただいています。
ナパの天候において重要なのは気温と夜間の冷涼さ、生育期間の長さであり、「敵」になるのは熱波や干ばつです。2012年は比較的暖かいヴィンテージ。雨もやや多い年です。
以下にコメントを記しますが、相対的にどれがいいと思ったかを示すために、便宜的に得点を入れます。ほかの回と比較するというより、今回のワインの比較用と思ってください。
2012年はカシスの香りに、ちょっとミンティな風味、花の香り。酸高くタンニン強い。そこそこ年月を経ているにもかかわらず、果実味が強く熟成によるアロマはまだほとんどでてきていません。96
2014年は2012年よりも酸が低く、ブルーベリーの香りが顕著。ストラクチャーのしっかりしたワイン。94
2015年はタンニンがしっかり。果実の味わいは2012年と2014年の中間くらい。93
2016年は赤系果実とブルーベリーの香り。これもタンニンは強く、やや閉じ気味に感じられました。95
2019年もちょっと閉じている感じがありましたが、パワフルで酸高くポテンシャルを感じます。赤系と黒系果実も豊か。97
2020年はバランスよく、酸高く赤果実も強い。タンニンも強い。96
ちなみに、同席した森覚さんはマグナムの12、14はメルローの特徴がまだあまりでてきておらず、750mlの15、16は開いていたとおっしゃっていました。また15年以降の最近のヴィンテージの方がメルローらしさがより出てきているとおっしゃっていました。赤系の果実を感じたのは最近のヴィンテージの方が多かったので、そのあたりがメルローらしいところなのかもしれません(メルロー難しくてよくわかりません)。
総じて言えることは、パワフルでストラクチャーがありタンニンも強い傾向にあること。飲み頃がいつになるのか聞いてみたところ「わからない」とのこと。私の感覚では2012年のものでもまだ10年くらいは寝かせた方がポテンシャルを発揮するような気がしました。メルロー中心のセカンドワインというと、早飲みタイプなのかと想像してしまいがちですが、ザ・フライトは早飲みワインではなく20年は熟成できるし、する価値があるワインだと思います。
アルマン氏はザ・フライトで感じてほしいこととして「メルローの個性と精密性。口に含んだときにアタックがあり、酸も感じられ、ミッドパレットにしっかりした果実味があり、余韻にちょっと田舎っぽさを含みながらも骨格とエレガンスがある」というところだと語っていました。
これまで、Wine to Styleの試飲会でザ・フライトを数回試飲していますが、あわただしい試飲会では1つのワインにかけられるのは数秒。そこで価値を見極めるのは難しく、これまで試飲会で良かったワインとして紹介したことはなかったと思います。今回じっくり試飲して、やっとそのスケールの大きさが理解できた感じがしました。
ところで、スクリーミング・イーグルの畑の中でメルローは東の方に多く植えられています。東の方は西向き斜面になるので、より太陽をよく浴びます。一般的にはメルローは比較的冷涼なところを好むと言われているので、西の方に植えるのが常道だと思いますが、スクリーミング・イーグルではそうはなっていません。
前述のように、スクリーミング・イーグルやザ・フライトに現在使っているのは1980年代に創設者のジーン・フィリップスが植えたブドウです。つまり、この選択をしたのもジーン・フィリップスです。アルマン氏に言わせると彼女は素晴らしいガーデナーだとのことで、彼女の直観によって植えられたのだそうです。ブロックの一つは過去に小川が流れていたところで、水はけ良く石がごろごろしているということで、これも粘土質などやや水を保持する土壌を好むといわれているメルロー向き土壌とは異なっています。このような理屈ではないところにスクリーミング・イーグルの魅力の一つがあるのかもしれません。
ザ・フライトの垂直試飲の後は、食事を取りながらソーヴィニヨン・ブランとスクリーミング・イーグルをいただきました。
ソーヴィニヨン・ブランは、一時期はカベルネ・ソーヴィニョンよりも高く取引されていたほどのレアワイン(Wine-Searcherのデータでは、今はカベルネ・ソーヴィニョンよりちょっと安いようです)。日本では100万円を超える値付けも珍しくありません。
ちなみに生産量は当初は20~50ケース。2016年以降は100~125ケースで、2019年は150ケースと過去最多だったとのこと。
ソーヴィニヨン・ブランを始めたのは試飲やメーカーズ・ディナーのときに白ワインも欲しいからだそうです。オーナーが代わった2006年に植樹して2010年からワインを造っています。この2010年はお世辞にもいいできではなかったそうですが、翌年以降は世に出せる品質になっていきました。最初は市販するつもりはなかったそうですが、レベルが上がったことで「Screaming Eagle」の名を冠することにしました。畑は1ヘクタールもなく、かつて川が流れていた少し粘土質の土壌だそうです。クローンはソーヴィニヨン・ムスケと、2つのソーヴィニヨン・ブランのクローンを使っています。
収穫は何度かに分けて行います。果実の色で収穫時期を決めますが、あえてまだ緑のものを含めることもあるそうです。収穫した果実は除梗してプレス。500~600リットルのフレンチオークの樽とステンレスの樽で発酵し、バトナージュもするそうです。10カ月樽熟成して、タンクに移して2~4カ月落ち着かせてからボトル詰めします。果実の美しさを残し、酸が出すぎないようにしているとのこと。収穫時のpHは2.9~3.2と非常に低く、酸の管理は一番難しいとのことです。MLFはヴィンテージによって行ったり行わなかったりします。
2020年のソーヴィニヨン・ブランを飲みました。第一印象は香りの高さでソーヴィニヨン・ムスケらしさがよく出ています。少し柑橘もありますが、メロンのような熟した果実の香りで、酸はやや低めに感じます。きれいでほのかな樽香。値段のことはさておき、トップクラスのソーヴィニヨン・ブランの一つであることは間違いありません。
さて、最後はいよいよスクリーミング・イーグル2021です。Vinousのアントニオ・ガッローニは100点を付けています。
青系と黒系の果実の香り。シルキーなタンニンで、スムーズ、丸い味わい。一方で酸も高くストラクチャーもあり、エネルギーを秘めた感じがします。ザ・フライトと比べて親しみやすく、飲みやすいワインですが、おそらく熟成によっても魅力が出てくるでしょう。98。
スクリーミング・イーグルの方が、ザ・フライトよりも飲み方を問わないように感じました。バーサタイルなワインという印象です。1ヴィンテージしか飲んでいないので、あくまでもこのワインだけの印象ではありますが。
スクリーミング・イーグルというとメーリング・リストに入った数少ない人しか買えないワインというイメージがありますが、実際にはメーリング・リストで売られているのは6割程度で、輸出分も3割くらいあるそうです(残りはごくわずかな米国内の流通)。メーリング・リストでごく限られた顧客だけが飲めるワインであるよりも、高級ホテルやレストランなどで、世界のトップワインと並んで飲んでもらうワインであることを重視したいとのことでした。なお、メーリング・リストは登録している人が亡くなっても、ほとんどの場合子供が親の名義で購入を続けるので、ほとんど空きは出てこないとのこと。
最後にワインメーカーのニック・ギスラソンについて伺いました。20代という若さでワインメーカーに抜擢されたニックですが、そのエピソードについて聞いてみました。
ニックはワインメーカーになる前、2010年からワイナリーで働き始めていました。2010年の収穫や醸造が一段落した12月に、それまでのワインメーカーだったアンディ・エリクソンが退任することになりました。退任の理由はアンディ自身が「スクリーミング・イーグルにはフルタイムのワインメーカーが必要だ」と考えたたmです。アルマン氏はその後4カ月で志望者20~25人とインタビューしましたが、エゴが強かったり、ワインのレジュメが決まっていて合わせる気がない人が多かったり、自分の履歴書に1行加えたいだけの人だったりと適任者ははなかなか見つかりませんでした。そのときにニックが「自分ではだめか」と聞いてきたそうです。
若いしどうだろうかと思ったのですが、ニックは「6カ月くれたら自分がワインメーカーとしてふさわしいことを証明する」と言い、彼を見ることにしました。
それで採用を中断したのですが。彼の働きぶりと才能が素晴らしく、年齢は関係ないがわかり、2011年に正式にワインメーカーとなりました。ただ最初の5年間は見た目が若すぎるので、雑誌のインタビューなど表には出さなかったそうです。
ニックは花火師として日本に来たことがあり、また今ではビール醸造も行っていますが、そのように多趣味なところも評価しているそうです。一つのことにのめり込むとほかが見えなくなるからで、奥さんと子供、花火師、ビールが彼にあるのがいいところだそうです。またワインと花火は「サプライズな表現」が大事といったところに共通点があると考えており、彼が作るスクリーミング・イーグルだからこそ、表現が豊かでサプライズの要素があるのだとか。
今回のワインだけでスクリーミング・イーグルが分かったなどとは微塵も思いませんが、貴重な体験ができたこと、ワインの一端にでも触れることができたことは大変勉強になりました。また、これまで真の価値があまりわからなかったザ・フライトも素晴らしいワインであることがわかり、非常に魅力を感じるようになりました。参加させていただいたWine to Styleさん、またご一緒いただいた皆様ありがとうございました。
最後の最後に、長くなったので紹介を省いてしまいましたが、マンダリンオリエンタル東京の中華も素晴らしく美味しかったです。点心とソーヴィニヨン・ブラン、スペアリブとスクリーミング・イーグルなど、素晴らしい組み合わせでした。
米国のトランプ大統領がカナダからの輸入品に25%の関税を課すと発表し、カナダ政府は報復として米国製品に25%の関税を課すことを表明しました。これに呼応して、オンタリオ州やブリティッシュ・コロンビア州では米国産や米国の共和党の強い州で作られたアルコール製品を店の棚から撤去するといったことも表明されています。
こういった状況についてカリフォルニアワイン協会のロバート・P・コッホ代表が声明を発表しています。
「カナダは米国ワインにとって最も重要な輸出市場であり、小売売上高は年間11億ドルを超えています。ワインは米国で最も付加価値の高い農産物輸出品の一つであるため、カナダ市場へのアクセスが失われれば、米国のワイン業界全体が打撃を受けます。私たちのワイナリーは、カナダ全土で数十年かけて市場シェアとブランドロイヤルティを築いてきました。今回の措置は、これらすべてを危険にさらします。さらに、すべてのアルコール飲料は現在市場で前例のない課題に直面しており、今回の関税と潜在的な製品撤去は、その影響を吸収するのが特に難しい状況です。私たちは、両政府が協力してこの紛争をできるだけ早く解決し、経済的損害を最小限に抑えるよう求めます」
米国のワイン業界は、長年ワインを貿易論争の道具にするべきではないと主張してきています。カリフォルニアワイン協会は、市場を問わず、全ての貿易報復リストからワインを除外することを強く主張しています。
こういった状況についてカリフォルニアワイン協会のロバート・P・コッホ代表が声明を発表しています。
「カナダは米国ワインにとって最も重要な輸出市場であり、小売売上高は年間11億ドルを超えています。ワインは米国で最も付加価値の高い農産物輸出品の一つであるため、カナダ市場へのアクセスが失われれば、米国のワイン業界全体が打撃を受けます。私たちのワイナリーは、カナダ全土で数十年かけて市場シェアとブランドロイヤルティを築いてきました。今回の措置は、これらすべてを危険にさらします。さらに、すべてのアルコール飲料は現在市場で前例のない課題に直面しており、今回の関税と潜在的な製品撤去は、その影響を吸収するのが特に難しい状況です。私たちは、両政府が協力してこの紛争をできるだけ早く解決し、経済的損害を最小限に抑えるよう求めます」
米国のワイン業界は、長年ワインを貿易論争の道具にするべきではないと主張してきています。カリフォルニアワイン協会は、市場を問わず、全ての貿易報復リストからワインを除外することを強く主張しています。
ナパの山地のカベルネ、通称山カベ専門で、パーカー100点9本と圧倒的な実績を誇るワイナリーがロコヤ(Lokoya)。そのワインメーカーのクリス・カーペンターが来日し、セミナーに参加しました。

まずは、ナパの基本的なところを抑えておきましょう。

ナパヴァレーの東側にヴァカ山脈、西側にマヤカマス山脈があります。ナパは南にサンパブロ湾があり、そこから冷たい空気や霧が内陸に入ってくるので、基本的には南ほど涼しくなります。また、西側と東側を比べると、マヤカマス山脈は太平洋からの空気も入ってくるのでヴァカ山脈側よりも涼しくなります。また、山の畑の多くは霧がかかる標高よりも高いところにあるので、霧の影響を受けません。谷底など霧がかかるところは夜に気温が大きく下がり午前中にあまり日照を受けませんが、山は気温はそれほど下がらず朝から日照をしっかり受けます。一方で、標高によって気温は上がりにくいので、日較差は小さくなります。
土壌はヴァカ山脈側は火山性土壌が中心で、マヤカマス山脈側は沖積性の土壌が多くなりますが、場所にもよるので一概には言い切れないところもあります。痩せた土地が多く、水はけがいいため、ブドウの実は小さく凝縮したものになります。また、タンニンも強くなります。
クリス・カーペンターはシカゴの出身、生物学を学び、卒業後は医療機器のセールスやバーで働くなどをしていましたが仕事に満足できなかったそうです。レストランと科学、創造性の三つを総合した仕事がないかと考えたときに、ワイン造りが見付かったとのこと。そうしてUCデーヴィスで学び、醸造と栽培の両方を勉強したとのこと。素晴らしいワインを造るには、まずは素晴らしいブドウがないと、ということで今でも栽培を一番大事にしています。ロコヤはジャクソン・ファミリーのワイナリーの一つであり、クリス・カーペンターはロコヤ以外にもいくつかのナパのワイナリーを担当しています。畑の管理も415エーカーに及びます。
前述のように、ワイン造りはまず素晴らしいブドウを育てることであり、場所を表現していることだといいます。醸造はできるだけシンプルに行います。さまざまな技術はありますが、どう栽培しているかが見えるようなワインを造りたいとのことです。
ワインのテイスティングに移ります。今回は2019年のワインを4つのAVAそれぞれについて試飲し、そのあとマウント・ヴィーダーについては2006、2010年と垂直で試飲します。最後に最新ヴィンテージの2021年からスプリング・マウンテンのカベルネを試飲します。ロコヤが作る4つのAVAを下の地図に示します。ワインはすべてカベルネソーヴィニヨン100%です。

最初の試飲はスプリング・マウンテンです。標高640mの自社畑イヴェルドン、標高300mの自社畑ワーテレに加え、契約栽培のスプリング・マウンテン・ヴィンヤード(標高550m)のブドウをブレンドしています。沖積土壌と火山性の土壌が混じっているのがこの地域の特徴でもあります。また、ロコヤのワイナリーはスプリング・マウンテンにあります。
カシスやブラックベリーに、レッド・チェリー、ブラッドオレンジ、バラの花など華やかな香りが特徴です。山のブドウだけあってタンニンも強く酸も高く、きれいで余韻の長いワイン。最初からびっくりするほど美味しいワインです。
次はダイヤモンド・マウンテン。スプリング・マウンテンの北側に隣接するAVAです。自社畑ライオライト・リッジ・ヴィンヤード (標高365m)、 自社畑ウォリス・ヴィンヤード (標高450m) に、契約栽培のアンドリュー・ジョフリー・ヴィンヤード (標高550m) をブレンドしています。黒曜石が土壌に含まれていてキラキラ光ることからこの名前が付いたと言われています。
スプリング・マウンテンよりも少し北にあることから少し温暖なAVAになります。畑の標高もスプリング・マウンテンより低いので、それも気温に関係しているかと思われます。赤系果実が感じられたスプリング・マウンテンと違い、ダイヤモンド・マウンテンは黒系から青系の果実、特にブルーベリーを強く感じます。チョコレートや黒鉛の風味もあり、ダークな印象。酸やタンニンはスプリング・マウンテンより少し控えめに感じられました。
3本目はヴァカ山脈側でロコヤが唯一造るハウエル・マウンテン。インポーター資料には「自社畑 W. S. キーズ・ヴィンヤード、ヴァカ山脈の北東に位置し標高556m、火山性のトゥーファ土壌 (火山灰堆積)と鉄分を含んだ赤い粘土」とあります。最初に植樹されたのは1888年という歴史ある畑です。
四つのワインの中で、これが一番リッチでパワフル。甘やかさも感じますが、一方で赤い果実の感じもあるのが面白い。酸は一番低く、タンニンは強いがシルキー。主張の強いワインなので好きな人とそうでない人には分かれるかもしれません。ちなみにジェブ・ダナックは100点、パーカー97点。
クリス・カーペンター本人はハウエル・マウンテンが一番好きだとのこと。グリーン・ノート(青っぽい風味)が感じられるところがいいと言っていましたが、私にはグリーン・ノートは分かりませんでした。
AVA水平試飲の最後はマウント・ヴィーダー。他の3つのAVAと比べるとかなり南にあり、ナパの山のAVAの中では一番冷涼と言われています。ワインもミントやセージなどハーブのニュアンスがあり、赤い果実に花の香り、酸高く、タンニンもガチガチに硬いです。非常に長塾型のワイン。最低10年くらいは置いてから飲みたいワインです。ちなみにジェブ・ダナックはこちらも100点を付けています。パーカー96+。
個人的には4つのAVAのワインの中でスプリング・マウンテンが一番良かったです。山らしい酸やタンニンに華やかな香り、もちろん熟成もできますが、今飲んでも十分に美味しい。
さて、一番長熟タイプのマウント・ヴィーダーは2010年と2006年も試飲しています。
2010年は酸高くきれいでエレガントな印象。タンニンはまだまだ強いです。2006年はミントの風味に赤果実、生肉のニュアンスも。やっぱりこれくらいは熟成させたい感じです。すばらしい。
最後に2021年のスプリング・マウンテンです。少し冷涼感がある2019年と比べると2021年は非常にパワフル。凝縮感もタンニンもものすごいレベルです。赤い果実はあまり感じられず、青系果実の風味が優性。すばらしいですが個人的には2019年のきれいさの方が良かったです。
山カベばかりをこれだけ並べて試飲する機会はめったにありません。特に4つのAVAの水平試飲はとても勉強にもなりました。ナパのカベルネ・ソーヴィニヨンの中で、ト・カロン・ヴィンヤードのカベルネ・ソーヴィニヨンなどヴァレーフロアのいわゆる「谷カベ」ももちろん素晴らしいですが、まったく個性の異なる「山カベ」もあるというのがナパの魅力の一つだと思います。山のワインは生産量が少ないものが多く、価格も高くなりがちですが、ぜひ体験してほしいワインです。

まずは、ナパの基本的なところを抑えておきましょう。

ナパヴァレーの東側にヴァカ山脈、西側にマヤカマス山脈があります。ナパは南にサンパブロ湾があり、そこから冷たい空気や霧が内陸に入ってくるので、基本的には南ほど涼しくなります。また、西側と東側を比べると、マヤカマス山脈は太平洋からの空気も入ってくるのでヴァカ山脈側よりも涼しくなります。また、山の畑の多くは霧がかかる標高よりも高いところにあるので、霧の影響を受けません。谷底など霧がかかるところは夜に気温が大きく下がり午前中にあまり日照を受けませんが、山は気温はそれほど下がらず朝から日照をしっかり受けます。一方で、標高によって気温は上がりにくいので、日較差は小さくなります。
土壌はヴァカ山脈側は火山性土壌が中心で、マヤカマス山脈側は沖積性の土壌が多くなりますが、場所にもよるので一概には言い切れないところもあります。痩せた土地が多く、水はけがいいため、ブドウの実は小さく凝縮したものになります。また、タンニンも強くなります。
クリス・カーペンターはシカゴの出身、生物学を学び、卒業後は医療機器のセールスやバーで働くなどをしていましたが仕事に満足できなかったそうです。レストランと科学、創造性の三つを総合した仕事がないかと考えたときに、ワイン造りが見付かったとのこと。そうしてUCデーヴィスで学び、醸造と栽培の両方を勉強したとのこと。素晴らしいワインを造るには、まずは素晴らしいブドウがないと、ということで今でも栽培を一番大事にしています。ロコヤはジャクソン・ファミリーのワイナリーの一つであり、クリス・カーペンターはロコヤ以外にもいくつかのナパのワイナリーを担当しています。畑の管理も415エーカーに及びます。
前述のように、ワイン造りはまず素晴らしいブドウを育てることであり、場所を表現していることだといいます。醸造はできるだけシンプルに行います。さまざまな技術はありますが、どう栽培しているかが見えるようなワインを造りたいとのことです。
ワインのテイスティングに移ります。今回は2019年のワインを4つのAVAそれぞれについて試飲し、そのあとマウント・ヴィーダーについては2006、2010年と垂直で試飲します。最後に最新ヴィンテージの2021年からスプリング・マウンテンのカベルネを試飲します。ロコヤが作る4つのAVAを下の地図に示します。ワインはすべてカベルネソーヴィニヨン100%です。

最初の試飲はスプリング・マウンテンです。標高640mの自社畑イヴェルドン、標高300mの自社畑ワーテレに加え、契約栽培のスプリング・マウンテン・ヴィンヤード(標高550m)のブドウをブレンドしています。沖積土壌と火山性の土壌が混じっているのがこの地域の特徴でもあります。また、ロコヤのワイナリーはスプリング・マウンテンにあります。
カシスやブラックベリーに、レッド・チェリー、ブラッドオレンジ、バラの花など華やかな香りが特徴です。山のブドウだけあってタンニンも強く酸も高く、きれいで余韻の長いワイン。最初からびっくりするほど美味しいワインです。
次はダイヤモンド・マウンテン。スプリング・マウンテンの北側に隣接するAVAです。自社畑ライオライト・リッジ・ヴィンヤード (標高365m)、 自社畑ウォリス・ヴィンヤード (標高450m) に、契約栽培のアンドリュー・ジョフリー・ヴィンヤード (標高550m) をブレンドしています。黒曜石が土壌に含まれていてキラキラ光ることからこの名前が付いたと言われています。
スプリング・マウンテンよりも少し北にあることから少し温暖なAVAになります。畑の標高もスプリング・マウンテンより低いので、それも気温に関係しているかと思われます。赤系果実が感じられたスプリング・マウンテンと違い、ダイヤモンド・マウンテンは黒系から青系の果実、特にブルーベリーを強く感じます。チョコレートや黒鉛の風味もあり、ダークな印象。酸やタンニンはスプリング・マウンテンより少し控えめに感じられました。
3本目はヴァカ山脈側でロコヤが唯一造るハウエル・マウンテン。インポーター資料には「自社畑 W. S. キーズ・ヴィンヤード、ヴァカ山脈の北東に位置し標高556m、火山性のトゥーファ土壌 (火山灰堆積)と鉄分を含んだ赤い粘土」とあります。最初に植樹されたのは1888年という歴史ある畑です。
四つのワインの中で、これが一番リッチでパワフル。甘やかさも感じますが、一方で赤い果実の感じもあるのが面白い。酸は一番低く、タンニンは強いがシルキー。主張の強いワインなので好きな人とそうでない人には分かれるかもしれません。ちなみにジェブ・ダナックは100点、パーカー97点。
クリス・カーペンター本人はハウエル・マウンテンが一番好きだとのこと。グリーン・ノート(青っぽい風味)が感じられるところがいいと言っていましたが、私にはグリーン・ノートは分かりませんでした。
AVA水平試飲の最後はマウント・ヴィーダー。他の3つのAVAと比べるとかなり南にあり、ナパの山のAVAの中では一番冷涼と言われています。ワインもミントやセージなどハーブのニュアンスがあり、赤い果実に花の香り、酸高く、タンニンもガチガチに硬いです。非常に長塾型のワイン。最低10年くらいは置いてから飲みたいワインです。ちなみにジェブ・ダナックはこちらも100点を付けています。パーカー96+。
個人的には4つのAVAのワインの中でスプリング・マウンテンが一番良かったです。山らしい酸やタンニンに華やかな香り、もちろん熟成もできますが、今飲んでも十分に美味しい。
さて、一番長熟タイプのマウント・ヴィーダーは2010年と2006年も試飲しています。
2010年は酸高くきれいでエレガントな印象。タンニンはまだまだ強いです。2006年はミントの風味に赤果実、生肉のニュアンスも。やっぱりこれくらいは熟成させたい感じです。すばらしい。
最後に2021年のスプリング・マウンテンです。少し冷涼感がある2019年と比べると2021年は非常にパワフル。凝縮感もタンニンもものすごいレベルです。赤い果実はあまり感じられず、青系果実の風味が優性。すばらしいですが個人的には2019年のきれいさの方が良かったです。
山カベばかりをこれだけ並べて試飲する機会はめったにありません。特に4つのAVAの水平試飲はとても勉強にもなりました。ナパのカベルネ・ソーヴィニヨンの中で、ト・カロン・ヴィンヤードのカベルネ・ソーヴィニヨンなどヴァレーフロアのいわゆる「谷カベ」ももちろん素晴らしいですが、まったく個性の異なる「山カベ」もあるというのがナパの魅力の一つだと思います。山のワインは生産量が少ないものが多く、価格も高くなりがちですが、ぜひ体験してほしいワインです。

ナパのオークヴィルにあるヴァイン・ヒル・ランチ(Vine Hill Ranch)は、ナパヴァレーの中でも有数の銘醸畑であり、今でもブドウの多くを他のワイナリーに販売しています。一方で、自社のワインブランドVine Hill Ranchもトップクラスの評価を得るにいたっています。そのヴァイン・ヒル・ランチについての記事が出ていました(Meet the Napa Valley Vineyard That Grows Some of the Region’s Best Grapes)。
ヴァイン・ヒル・ランチの歴史は1859年にまでさかのぼりますが、現在の形を作ったのは1959年に買収したフィリップス家によるものです。畑の大部分はカベルネ・ソーヴィニヨンで、このほかプティ・ヴェルドが少量植えられています。
現在、ヴァイン・ヒル・ランチの単一畑のワインを造っているワイナリーとしてはTor、Memento Mori、Kindsman Eades、Arrow & Branch、Annulus、Bond(Vecina)があります。このほかにもColgin、Accendo Cellars、Lail Vineyards、Simon Familyなどにブドウを売っています。
上の地図に示したように、畑はオークヴィルの西側、マヤカマス山脈の麓の沖積扇状地にあります。フィリップス家の土地は600エーカーもありますが、うち72エーカーばブドウ畑になっています。畑を管理しているのはマイク・ウルフで、この65年間で2人目の畑の管理者となっています。72エーカーは、ナパの畑の中ではかなり広い方ですが、ブロックごとに植密度や剪定、クローン、ルートストックなどが異なるため、それぞれに合った管理が必要になっています。特定のスタイルのブドウを育てるというよりも、キャノピー内の均一性に気を配っているとのことです。
この畑のブドウを使うワインメーカーは、水はけの良さや適度の冷涼感といったテロワールに加え、畑の管理のすばらしさでここを選んでいます。Torのトール・ケンワード氏はこの土地で造られるワインは旧世界の性格が強いと考えています。「私はその非常に独特な性格が大好きです。それは、前世紀のナパヴァレーの最高のワインを思い出させます」とケンワード氏は言います。
ブドウの85%は外部に販売していますが、15%は自社のワイナリーで使っています。ワインの大部分はメーリング・リストで販売され、フレンチ・ランドリーなどナパの著名なレストランにも卸されています。
2021年からはセカンドワインの「Baker & Hamilton Cabernet Sauvignon」を作っています。ヴァイン・ヒル・ランチのワインが300ドルするのに対し、こちらは125ドルとだいぶ安くなっています。この名前は、現オーナーのおじいさんのおじいさんに当たる人が作った会社名に由来しています。
InsightAce Analytic Pvt. Ltd. の最近のレポートによると、オーガニックワインの市場は 2021年に98億4000万米ドルと評価され、2030年までに250億7000万米ドルという驚異的な額に達すると予想されています。年平均成長率 (CAGR) は11.3%に達します(Organic wine market set to triple by 2030)。
オーガニックワインの市場を牽引しているのは「ミレニアル世代」(1980年代から1990年代前半に生まれた世代)。米国ではミレニアル世代のワイン愛好者の30%がオーガニックワインを高品質と考えています。
また、サスティナブルへの意識の高まりとあいまって、パッケージングへの関心も高くなってきています。ガラス瓶が主流であり続けてはいますが。缶入りワインの人気も高くなってきています。
オーガニックワインの市場を牽引しているのは「ミレニアル世代」(1980年代から1990年代前半に生まれた世代)。米国ではミレニアル世代のワイン愛好者の30%がオーガニックワインを高品質と考えています。
また、サスティナブルへの意識の高まりとあいまって、パッケージングへの関心も高くなってきています。ガラス瓶が主流であり続けてはいますが。缶入りワインの人気も高くなってきています。
ヴィナス(Vinous)でアントニオ・ガッローニがナパとソノマのレポートを相次いで公表しています。非常に極端に性格が分かれた2022年と2023年のヴィンテージについての所感をまとめておきます。
まず、2022年は「2つのヴィンテージ」と言われるように、一つの年ではありますが前半と後半で大きく性格が分かれます。その原因となったのが9月上旬の熱波で、40℃後半にもなるような異常な暑さが1週間近くも続きました。これによってブドウは酸が落ちてしまったり、成熟を止めてしまったり、場合によってはブドウの実の中で発酵が始まってしまうといったことまであったようです。この熱波の前に収穫したか、熱波を越えてから収穫したかが、大きなポイントとなっています。
一方、2023年は稀に見る涼しいヴィンテージでした。生育は通常の3週間遅れで進行し、11月に入っても収穫が続くところもありました。ただ、熱波や雨といった品質低下につながりやすいイベントは起こらず、安定した天候が続いたため、適熟の状態で収穫でき「一生に一度のヴィンテージ」とまで言われていました。
ナパの場合、2022年は熱波のときに「果実が熟しかけ」「完熟状態」「成熟のまだ手前」の3段階によって状況が分かれました。「果実が熟しかけ」の生産者は熱波の間に急いで収穫をし、いい状態のブドウを手に入れられました。「成熟のまだ手前」だった生産者は熱波の後、改めて成熟を待ちましたが今度は低温や雨といった事象にも悩まされました。一番問題だったのは熱波前に完熟に達してしまったところで、熱波によってレーズン化してしまうなどの問題が生じました。また熱波前に収穫をしようとしても必要な働き手が見つからずに収穫できなかったというところもあるようです。特にメルローでは問題が大きかったと見られます。
ソノマでも熱波の影響はありましたが、熱波による暑さはナパほどではなかったので、そこまで大きな問題にはなりませんでした。「2022年のピノは、濃厚で芳醇なワインであり、テクスチャーの強さが際立っています。2022年は熟したワインもあれば、粒状でやや粗いタンニンに暑さの影響が見られるワインもあります」とガッローニは記しています。やや大柄なワインになる傾向はあるものの、特別に難しい年ということでもなったようです。
一方、2023年ですが2022年とは逆にソノマの方が難しいヴィンテージとなりました。確かに雨も降らず、熱波もなく安定した天候が続きましたが、あまりにも冷涼な地域ではブドウが完熟できなかったところもありました。冷涼でブドウが完熟しないところが多かった2011年よりもさらに涼しかったという声も聞かれたようです。2022年のソノマは涼しい地域の方が高品質でしたが、2023年のソノマは涼しい地域では熟度が上がりにくく、暖かい地域の方がそうじてよくできていました。
2023年のナパはソノマのようなブドウが完熟しない問題もなかったので、いいヴィンテージであることは間違いないようです。
まず、2022年は「2つのヴィンテージ」と言われるように、一つの年ではありますが前半と後半で大きく性格が分かれます。その原因となったのが9月上旬の熱波で、40℃後半にもなるような異常な暑さが1週間近くも続きました。これによってブドウは酸が落ちてしまったり、成熟を止めてしまったり、場合によってはブドウの実の中で発酵が始まってしまうといったことまであったようです。この熱波の前に収穫したか、熱波を越えてから収穫したかが、大きなポイントとなっています。
一方、2023年は稀に見る涼しいヴィンテージでした。生育は通常の3週間遅れで進行し、11月に入っても収穫が続くところもありました。ただ、熱波や雨といった品質低下につながりやすいイベントは起こらず、安定した天候が続いたため、適熟の状態で収穫でき「一生に一度のヴィンテージ」とまで言われていました。
ナパの場合、2022年は熱波のときに「果実が熟しかけ」「完熟状態」「成熟のまだ手前」の3段階によって状況が分かれました。「果実が熟しかけ」の生産者は熱波の間に急いで収穫をし、いい状態のブドウを手に入れられました。「成熟のまだ手前」だった生産者は熱波の後、改めて成熟を待ちましたが今度は低温や雨といった事象にも悩まされました。一番問題だったのは熱波前に完熟に達してしまったところで、熱波によってレーズン化してしまうなどの問題が生じました。また熱波前に収穫をしようとしても必要な働き手が見つからずに収穫できなかったというところもあるようです。特にメルローでは問題が大きかったと見られます。
いくつかの例外はあるものの、2022年のワインは、例年のワインに比べて色、ボディ、タンニンが薄い。高熱で色が褪せ、タンニンが劣化し、最良の年のような躍動感のないワインとなった。糖度は前例のないレベルまで上昇し、2022年産ワインの多くはセラーでの調整が必要となった。これには、水と酸の追加、非常に軽いワインのためのマストのブリーディング、タンニンの追加など、さまざまな技術が含まれる。一部のワインは驚くほど新鮮で、おそらく2023年の果汁がブレンドされていると思われる。アルコール度数は、果実の収穫時期によってかなり異なる。と書かれています。ヴィンテージ表記を付けるにはAVA表記が付く場合は95%以上、つかない場合は85%以上がそのヴィンテージのブドウである必要があるので5%ないし15%、2023年のヴィンテージを加えた生産者もあるのでしょう。
ソノマでも熱波の影響はありましたが、熱波による暑さはナパほどではなかったので、そこまで大きな問題にはなりませんでした。「2022年のピノは、濃厚で芳醇なワインであり、テクスチャーの強さが際立っています。2022年は熟したワインもあれば、粒状でやや粗いタンニンに暑さの影響が見られるワインもあります」とガッローニは記しています。やや大柄なワインになる傾向はあるものの、特別に難しい年ということでもなったようです。
一方、2023年ですが2022年とは逆にソノマの方が難しいヴィンテージとなりました。確かに雨も降らず、熱波もなく安定した天候が続きましたが、あまりにも冷涼な地域ではブドウが完熟できなかったところもありました。冷涼でブドウが完熟しないところが多かった2011年よりもさらに涼しかったという声も聞かれたようです。2022年のソノマは涼しい地域の方が高品質でしたが、2023年のソノマは涼しい地域では熟度が上がりにくく、暖かい地域の方がそうじてよくできていました。
2023年のナパはソノマのようなブドウが完熟しない問題もなかったので、いいヴィンテージであることは間違いないようです。
試飲してみると、2023年は香りがよく、洗練されたワインだった。間違いなく、美しく並外れたワインがたくさんあるヴィンテージだ。今のところ、2023年が本当に素晴らしいヴィンテージだとは思っていないが、最終的には時が経てばわかるだろう。
米国の「酒類・タバコ税貿易管理局(TTB)」がアルコール飲料のラベル記載義務に関する新しい提案を公表しています。
Federal Register :: Major Food Allergen Labeling for Wines, Distilled Spirits, and Malt Beverages
それによると、主な変更点は二つあります。一つは栄養表示に関するもの。食品と同様に、カロリー、炭水化物、脂肪、タンパク質などの栄養成分表示を義務化する予定です。
もう一つはアレルゲンの表示。アルコール飲料に含まれるアレルゲン物質の表示も義務化される可能性があります。
これらはまだ決定したものではありませんが、おそらくそのまま義務化される可能性が高いでしょう。
Federal Register :: Major Food Allergen Labeling for Wines, Distilled Spirits, and Malt Beverages
それによると、主な変更点は二つあります。一つは栄養表示に関するもの。食品と同様に、カロリー、炭水化物、脂肪、タンパク質などの栄養成分表示を義務化する予定です。
もう一つはアレルゲンの表示。アルコール飲料に含まれるアレルゲン物質の表示も義務化される可能性があります。
これらはまだ決定したものではありませんが、おそらくそのまま義務化される可能性が高いでしょう。

ポルトガルのTree Flowers Solutionsという会社が、SO2(亜硫酸塩)の代わりに使う栗の花の粉末「Chestwine」を開発しました。
SO2は酸化防止剤と言われるように、ワインの酸化を防ぎ、微生物の増殖を妨げます。ワインの長期保存のためには欠かせない存在ですが、一方で人体に有害だとして嫌われてもいます。確かに大量に摂取すれば悪影響はあるでしょうが、現在ではSO2の利用はかなり抑えられており、実際に健康問題が起こる可能性は非常に低いと思います。とはいえ、人体に有害なものは少しでも摂取したくないという考えの人も少なからずおり、酸化防止剤無添加のワインが作られる動機にもなっています(正確には酸化防止剤としてはビタミンC=アスコルビン酸などもありますが、最も広く使われているのがSO2です。本記事のタイトルに酸化防止剤としているのも本来はSO2あるいは亜硫酸塩としないといけませんが、間違いは承知で敢えて使っています)。
その代替品として白羽の矢が立ったのが栗の雄花で、フェノール酸とタンニンを多く含んでおり、ワインの酸化や微生物の増殖を防ぐのに使えます。スペインのBraganza UniversityとPolytechnic Instituteが2017年に特許を取得しており、その後Philippe Ortegaという人が中心になって特許を買い取ってTree Flowers Solutionsの設立となりました。
Chestwineは粉末になっており、収穫後の移動やブドウの破砕、熟成やボトリングなどSO2と同様、様々な場面で利用できます。有機栽培の認証を取っており、オーガニックなワインに添加が可能です。
価格は最終的なワイン1ボトルあたり50セント以下と見込まれています。既にポルトガルとスペインなどでは初期ユーザーがおり、称賛を得ています。
Bodegas Mazuelaというリオハのワイナリーでは2024年に主要ワインのテンプラニーリョでCheswineを使い、結果に満足しているといいます。
フランスのロワール地方のDomaine Thetでは次のように語っています。「私たちは2つのシュナン・ブランワインを比較しました。1つは6ヘクトリットルの卵形の樽で1ヘクトリットルあたり30グラムのCheswineを使用して作られ、もう1つは同じジュースで1ヘクトリットルあたり2グラムのSO2を使用して作られました。 2つの製品は非常に異なっています。前者はより風味豊かでトロピカルフルーツの香りがより顕著であるのに対し、後者はより伝統的で、リンゴやライムグリーンの香りを想起させます」
このほかシャンパーニュやソーテルヌでもテスト使用が始まっているようです。
米国では食品医薬品局の認証を申請中です。米国では「Organic Wine」とラベルに称するにはSO2を使用しないことが必要となるため、これまでほとんどOrganic Wineはありませんでした。Chestwineを使えば、Organic Wineとしても認可されるので、Organicと銘打ちたい人には朗報となりそうです。
なお、コスト的にはボトル1本あたり50セント程度のもよう。低価格ワインには使いにくいですが、高級ワインであれば問題ないレベルと思われます。
杉本隆英さんと美代子さんの夫妻がプロデュースするシャトー・イガイタカハ。そのフラッグシップのピノ・ノワール「園(その)」は2013年からJALのファーストクラスでも提供されており、Vinousで94点を取ったこともある実力派ワインです。
ラベルに漢字をあしらったイガイタカハの「漢字シリーズ」は元々、ブリュワー・クリフトンやダイアトムのワインメーカーとして知られるグレッグ・ブリュワー氏とのコラボで始まったもの。いろいろと紆余曲折ありましたが、残念ながら2019ヴィンテージでグレッグは退任しています。
その間の歴史については、こちらの記事をご参照ください。
グレッグ・ブリュワー、シャトー・イガイタカハ「漢字ワイン」を退任
なお、この記事では今後はケネス・ガミア氏が園などを担当すると記していますが、実際にはポール・ラト氏が現在はワインを造っています。
シャトー・イガイタカハは今年で20周年。それを記念してバックヴィンテージであり、まさに飲み頃の2018年の園を特別価格1万円(税抜き)での販売を始めました。480本限定となっています。
ご購入はこちらから。
2018 シャトー・イガイタカハ 園ピノ・ノワール Ch.igai Takaha Sono Pinot Noir | Winelife ONLINE SHOP
ラベルに漢字をあしらったイガイタカハの「漢字シリーズ」は元々、ブリュワー・クリフトンやダイアトムのワインメーカーとして知られるグレッグ・ブリュワー氏とのコラボで始まったもの。いろいろと紆余曲折ありましたが、残念ながら2019ヴィンテージでグレッグは退任しています。
その間の歴史については、こちらの記事をご参照ください。
グレッグ・ブリュワー、シャトー・イガイタカハ「漢字ワイン」を退任
なお、この記事では今後はケネス・ガミア氏が園などを担当すると記していますが、実際にはポール・ラト氏が現在はワインを造っています。
シャトー・イガイタカハは今年で20周年。それを記念してバックヴィンテージであり、まさに飲み頃の2018年の園を特別価格1万円(税抜き)での販売を始めました。480本限定となっています。
ご購入はこちらから。
2018 シャトー・イガイタカハ 園ピノ・ノワール Ch.igai Takaha Sono Pinot Noir | Winelife ONLINE SHOP
年間100万ケースものワインを38のワイン・ブランドで生産し、さらに他社向けに100万ケース、それだけでなく特定クライアント向けのワインを65種類も作っているワイナリーがナパにあるのをご存じでしょうか。「フィオール・ディ・ソーレ(Fior di Sole)」という名前を聞いてピンと来なくても「カモミ」や「ベンド」「イーター」「アデュレーション」「ジ・アトム」といったブランド名は聴いたことがある人が多いのではないでしょうか。どれもコスト・パフォーマンスの高いワインを造ることで知られているブランドです。「Fior di Sole: The Largest Winery in Napa You've Never Heard Of」の内容を中心に紹介します。



これが自社ブランドの一覧です。私が知っているブランドは10余りですが、「Fior di Sole」で検索すると、ここに挙げられていないブランドも出てきます。おそらくは特定顧客向けに作っているワインが日本に流れてきているのではないかと思います。
フィオール・ディ・ソーレを設立したのはステファーノ・ミゴットとヴァレンティーナ・グオーロの夫妻。ミゴットはイタリアで父親から引き継いだワイナリーを12年間経営し、1997年にカリフォルニアに移住してきました。
ミゴットがカリフォルニアに来て最初に思ったのはカリフォルニアがイタリアに比べて技術的に遅れているということ。そこで彼がイタリアで使っていたフィルターなどの技術をカリフォルニアで提供する「ワインテック」という会社を最初に始めました。当初はあまり受け入れられなかったのですが、様々なワイナリーと付き合う中で、米国のワイン業界のことを学び、自身でのワイン造りにも取り掛かります。2008年にはナパの倉庫で、使われていないボトリングラインを見つけてそこをワイナリーにします。そうして始まったのがフィオール・ディ・ソーレです。
フィオール・ディ・ソーレでは最新鋭のボトリングラインを次々と導入すると共に、ボトリングラインでCCOFによる有機認証を得たり、水の使用量を通常の半分以下にする工夫をしたりと、環境面にも気を使っています。澱の回収サービスも行っており、澱を分析してヴィネガー生産やワイン生産に使うなどの再利用も行っています。カリフォルニア中のワイナリーがこのサービスを利用しているとのことです。
このほか、シャルマ方式のスパークリングワインを造る設備も備えています。
成長を続けるフィオール・ディ・ソーレ。ナパだけでなくカリフォルニアのコスパ系ワインを支える重要なワイナリーです。



これが自社ブランドの一覧です。私が知っているブランドは10余りですが、「Fior di Sole」で検索すると、ここに挙げられていないブランドも出てきます。おそらくは特定顧客向けに作っているワインが日本に流れてきているのではないかと思います。
フィオール・ディ・ソーレを設立したのはステファーノ・ミゴットとヴァレンティーナ・グオーロの夫妻。ミゴットはイタリアで父親から引き継いだワイナリーを12年間経営し、1997年にカリフォルニアに移住してきました。
ミゴットがカリフォルニアに来て最初に思ったのはカリフォルニアがイタリアに比べて技術的に遅れているということ。そこで彼がイタリアで使っていたフィルターなどの技術をカリフォルニアで提供する「ワインテック」という会社を最初に始めました。当初はあまり受け入れられなかったのですが、様々なワイナリーと付き合う中で、米国のワイン業界のことを学び、自身でのワイン造りにも取り掛かります。2008年にはナパの倉庫で、使われていないボトリングラインを見つけてそこをワイナリーにします。そうして始まったのがフィオール・ディ・ソーレです。
フィオール・ディ・ソーレでは最新鋭のボトリングラインを次々と導入すると共に、ボトリングラインでCCOFによる有機認証を得たり、水の使用量を通常の半分以下にする工夫をしたりと、環境面にも気を使っています。澱の回収サービスも行っており、澱を分析してヴィネガー生産やワイン生産に使うなどの再利用も行っています。カリフォルニア中のワイナリーがこのサービスを利用しているとのことです。
このほか、シャルマ方式のスパークリングワインを造る設備も備えています。
成長を続けるフィオール・ディ・ソーレ。ナパだけでなくカリフォルニアのコスパ系ワインを支える重要なワイナリーです。
ワインスペクテーターが2024年のヴァリューワイントップ10を発表しています。以下にリストと、日本で売っている場合のリンクを載せています。
1. SEGHESIO Zinfandel Sonoma County 2022
93 points | $26 | 112,500 cases made
2. ROEDERER ESTATE Brut Anderson Valley NV
93 points | $32 | California
3. RUFFINO Chianti Classico Ducale Riserva 2019
92 points | $25 | Italy
4. ARGYLE Pinot Noir Willamette Valley 2022
92 points | $28 | Oregon
5. ANTINORI Toscana Villa Antinori 2021
92 points | $25 | Italy
6. CRAGGY RANGE Sauvignon Blanc Martinborough Te Muna 2023
94 points | $26 | New Zealand
7. DRY CREEK Sauvignon Blanc Dry Creek Valley 2022
92 points | $25 | California
8. BODEGAS TERRAZAS DE LOS ANDES Malbec Mendoza Reserva 2022
91 points | $20 | Argentina
9. LA RIOJA ALTA Rioja Viña Alberdi Reserva 2019
91 points | $25 | Spain
10. FRANK FAMILY Chardonnay Carneros 2022
92 points | $40 | California
コスパワインなので、価格が大事ですが、国内で売っているものはドルの価格と比べて安いものが多くあります。ただ、1位のセゲシオジンファンデルについては3本で2万2000円ですから、1本あたり7000円くらいになり、米国の価格と比べてちょっと割高です。
2位のロデレールのブリュットは、日本では「カルテット」として売っているワイン。エノテカ輸入でエノテカでは5500円くらいですが、他のショップでは4000円前後と、米国の32ドルと比べてもかなり安く売っています。このスパークリング、とてもいいと思います。以前自宅セラーで3年ほど熟成したものを飲みましたが、さらによくなっていました。
あとはUSワインで国内で流通しているものはなさそうです。ドライクリークのソーヴィニヨン・ブランは大昔は輸入されていたと思いますが、今では見かけません。
1. SEGHESIO Zinfandel Sonoma County 2022
93 points | $26 | 112,500 cases made
2. ROEDERER ESTATE Brut Anderson Valley NV
93 points | $32 | California
3. RUFFINO Chianti Classico Ducale Riserva 2019
92 points | $25 | Italy
4. ARGYLE Pinot Noir Willamette Valley 2022
92 points | $28 | Oregon
5. ANTINORI Toscana Villa Antinori 2021
92 points | $25 | Italy
6. CRAGGY RANGE Sauvignon Blanc Martinborough Te Muna 2023
94 points | $26 | New Zealand
7. DRY CREEK Sauvignon Blanc Dry Creek Valley 2022
92 points | $25 | California
8. BODEGAS TERRAZAS DE LOS ANDES Malbec Mendoza Reserva 2022
91 points | $20 | Argentina
9. LA RIOJA ALTA Rioja Viña Alberdi Reserva 2019
91 points | $25 | Spain
10. FRANK FAMILY Chardonnay Carneros 2022
92 points | $40 | California
コスパワインなので、価格が大事ですが、国内で売っているものはドルの価格と比べて安いものが多くあります。ただ、1位のセゲシオジンファンデルについては3本で2万2000円ですから、1本あたり7000円くらいになり、米国の価格と比べてちょっと割高です。
2位のロデレールのブリュットは、日本では「カルテット」として売っているワイン。エノテカ輸入でエノテカでは5500円くらいですが、他のショップでは4000円前後と、米国の32ドルと比べてもかなり安く売っています。このスパークリング、とてもいいと思います。以前自宅セラーで3年ほど熟成したものを飲みましたが、さらによくなっていました。
あとはUSワインで国内で流通しているものはなさそうです。ドライクリークのソーヴィニヨン・ブランは大昔は輸入されていたと思いますが、今では見かけません。
ロスアンゼルスの山火事については、日本のニュースでも数多く取り上げられておりますが、ここでも報告しておきます。
現在、五つの山火事がロスアンゼルス近郊で発生しています。いずれも鎮火には至っていませんが、中でも大きいのがサンタモニカの西側で発生したパリセーズ・ファイア(Palisades Fire)とパサディナの北で発生したイートン・ファイア(Eaton Fire)。亡くなった方は11人以上。12300を超える建物が焼失したと見られています。
パリセーズ・ファイアの延焼範囲は22660エーカー(約91.5平方キロ)。コンテインは11%(延焼範囲の外枠の中で、それ以上火災が広がらないように食い止めているラインの比率のこと)。

イートン・ファイアの延焼範囲は14117エーカー(約57.1平方キロ)。コンテインは15%。

残りの3つのうち2つはコンテインが80%、76%とおおむね食い止めている状況で、もう一つはコンテインはゼロですが19エーカーと規模は小さいです。
特に高級住宅地を含んでいるのがパリセーズ・ファイアです。イートン・ファイアは少し規模が小さいですが、亡くなった方はこちらの方が多いようです。
カリフォルニアは11月から雨季で、一般的には山火事シーズンではないのですが、今年は南カリフォルニアで降雨量が少ないことと、気温が比較的高いこと、また強風で燃え広がるスピードが早いことが被害を拡大しているようです。
今回は保険による賠償金も天文学的な価格になりそうであり、今後の山火事に関する保険にも影響が大きいと思われます。2017年や2020年の山火事でも保険料問題は浮上していましたが、今回はさらに大きな問題に発展しそうな気がします。
現在、五つの山火事がロスアンゼルス近郊で発生しています。いずれも鎮火には至っていませんが、中でも大きいのがサンタモニカの西側で発生したパリセーズ・ファイア(Palisades Fire)とパサディナの北で発生したイートン・ファイア(Eaton Fire)。亡くなった方は11人以上。12300を超える建物が焼失したと見られています。
パリセーズ・ファイアの延焼範囲は22660エーカー(約91.5平方キロ)。コンテインは11%(延焼範囲の外枠の中で、それ以上火災が広がらないように食い止めているラインの比率のこと)。

イートン・ファイアの延焼範囲は14117エーカー(約57.1平方キロ)。コンテインは15%。

残りの3つのうち2つはコンテインが80%、76%とおおむね食い止めている状況で、もう一つはコンテインはゼロですが19エーカーと規模は小さいです。
特に高級住宅地を含んでいるのがパリセーズ・ファイアです。イートン・ファイアは少し規模が小さいですが、亡くなった方はこちらの方が多いようです。
カリフォルニアは11月から雨季で、一般的には山火事シーズンではないのですが、今年は南カリフォルニアで降雨量が少ないことと、気温が比較的高いこと、また強風で燃え広がるスピードが早いことが被害を拡大しているようです。
今回は保険による賠償金も天文学的な価格になりそうであり、今後の山火事に関する保険にも影響が大きいと思われます。2017年や2020年の山火事でも保険料問題は浮上していましたが、今回はさらに大きな問題に発展しそうな気がします。
カリフォルニアの沿岸の夏は本当に涼しいです。寒いといってもいいくらい。例えば、サンタ・クルーズの辺りの海に近いところの年間の気温を示したのが下のグラフです。8月でも昼間の最高気温が10℃台。一番気温が高い10月でも18℃。逆に一番気温が低い1月は13℃と年間を通してほとんど気温が変わりません。
ちなみに、カリフォルニアの沿岸ではラッコが見られるところがありますが、ラッコは水温15度以上のところでは生活できないそうなので、水温も年間通じてそれ以下であるのは確実です。

この涼しさはアラスカから流れてくる海流の影響であると、いつも説明していますが、それだけでなく地球の自転がかかわっているということをブラインドテイスティングで有名な田尻智之さんが、投稿されていました。
Note(WSET Level3 練習問題(番外編:カリフォルニアと沿岸湧昇) | The Planet of Wine)では、数式を使って分かりやすくモデル化して説明しています。
数式は見たくないという人も多いでしょうから、簡潔に説明します。西海岸では夏場、太平洋に高気圧、陸上に低気圧が生じ、結果として北寄りの風が長時間吹きます。風によって海面の水は北から南に力を受けますが、このときに地球の自転の影響で、風向きから90°右向きの方向に移動するような力が生じるのです(学生時代に地学を習った人は「コリオリの力」という名前を憶えているかもしれません)。北風に対して90°右向きですから東から西に向かう力になり、結果として海面の水は海岸から離れていきます。
海面の水が沿岸から離れる方向に移動することによって、海底から水が上がってきます。これを「沿岸湧昇」といいます。カリフォルニア近辺は海が深く、深海の水温は非常に低くなっています。この水が上がってくることで沿岸の水温が低くなるのです。
もちろん寒流で運ばれてくる冷たい水も大きく影響していますが、夏場の極端な涼しさについてはそれだけでは説明しきれないという感じは以前から持っておりました。この沿岸湧昇の影響が加わることで冬と変わらないような低温が続くというのは、すごく納得がいきます。
ちなみに、カリフォルニアの沿岸ではラッコが見られるところがありますが、ラッコは水温15度以上のところでは生活できないそうなので、水温も年間通じてそれ以下であるのは確実です。

この涼しさはアラスカから流れてくる海流の影響であると、いつも説明していますが、それだけでなく地球の自転がかかわっているということをブラインドテイスティングで有名な田尻智之さんが、投稿されていました。
沿岸付近の海水は、コリコリの力により西へ運ばれるのである。
— Tomo Blind Wine Tasting (@wine_planetary) January 3, 2025
運ばれた分の海水は深部から湧昇という形で補償されるのだが、深部からの水は冷たい。
そのため、カリフォルニアの沿岸付近は冷たく、霧が発達しやすい
なぜ西へ?と思う方へ、下記で数式で解説してます!笑https://t.co/JU9IymtreZ
Note(WSET Level3 練習問題(番外編:カリフォルニアと沿岸湧昇) | The Planet of Wine)では、数式を使って分かりやすくモデル化して説明しています。
数式は見たくないという人も多いでしょうから、簡潔に説明します。西海岸では夏場、太平洋に高気圧、陸上に低気圧が生じ、結果として北寄りの風が長時間吹きます。風によって海面の水は北から南に力を受けますが、このときに地球の自転の影響で、風向きから90°右向きの方向に移動するような力が生じるのです(学生時代に地学を習った人は「コリオリの力」という名前を憶えているかもしれません)。北風に対して90°右向きですから東から西に向かう力になり、結果として海面の水は海岸から離れていきます。
海面の水が沿岸から離れる方向に移動することによって、海底から水が上がってきます。これを「沿岸湧昇」といいます。カリフォルニア近辺は海が深く、深海の水温は非常に低くなっています。この水が上がってくることで沿岸の水温が低くなるのです。
もちろん寒流で運ばれてくる冷たい水も大きく影響していますが、夏場の極端な涼しさについてはそれだけでは説明しきれないという感じは以前から持っておりました。この沿岸湧昇の影響が加わることで冬と変わらないような低温が続くというのは、すごく納得がいきます。
1976年の「パリスの審判」は、カリフォルニアのみならず、ニューワールドのワイン生産者すべてに勇気を与え、その品質が急上昇するきっかけになりました。カリフォルニアワインの歴史の中でも、ゴールドラッシュ、禁酒法と並んで極めて重要な出来事であったのは間違いありません。
このイベントを成功させた影の功労者がジョアン・ディッケンソン・デピュイ(Joanne Dickenson DePuy)という人。その功績をまとめた記事が出ていました(Joanne Dickenson DePuy, the Woman Who Helped Change Napa Forever)。この人については、私もほとんど知りませんでした。パリスの審判のTimes誌の記事を書いたジョージ・テイバーによる書籍『パリスの審判 カリフォルニア・ワインVSフランス・ワイン』では主催者のスティーヴン・スパリエの右腕となって働いたパトリシア・ギャラガーについては詳しく書かれていたものの、この方にはほとんど触れられていなかったような気がします。

彼女の功績の一つは、カリフォルニアのワインを選びに来たスティーヴン・スパリエとパトリシア・ギャラガーに、ナパのワイナリーを紹介したこと。彼女が紹介した中に、白で1位を取ったモンテレーナや赤で1位を取ったスタッグスリープ・ワイン・セラーズも含まれていました。
それだけであれば、彼女が紹介せずとも、出会っていた可能性が高いと思いますが、さらに重要なことがあります。試飲会で使うワインをフランスに輸送するという重要な責務を背負ったのです。
彼女は1973年に「ワインツアーズ・インターナショナル」という会社を設立し、ナパからフランスの名産地へのツアーを企画しました。アンドレ・チェリチェフがガイドをするといったツアーまで行いました。そういったことから、スティーヴン・スパリエがナパに来たときのガイド役も務めたのでした。
試飲会用のワインは赤6種、白6種をそれぞれ3本。計3ケース分ありました。スティーヴン・スパリエはそれをフランスに送る手配をしていたのですが、フランスの関税法と航空規制で発送できないということが直前にわかり、デピュイにヘルプを求めたのです。ちょうどアンドレ・チェリチェフのツアーでフランスに行く直前だった彼女はそれを引き受けたのです。
ツアーメンバーが、それぞれの荷物の一部として運ぶ(映画『ボトルショック』ではそのように描かれていました)という案もありましたが、リスクが大きく却下。結局航空会社と粘り強く交渉して、貨物として運んでもらえることになりました。ワインは1本が破損したものの、残りは無事に到着し、試飲会も開催できました。
ちなみに、試飲会でモンテレーナが1位になったことをオーナーのジム・バレットはフランスのツアー中に知ったということがジョージ・ティーバーの書籍にも書かれていたと思いますが、このフランスのツアーこそ、上記のデピュイの主催によるアンドレ・チェリチェフのツアーだったのでした。
彼女は現在97歳。今もナパヴァレーの様々なイベントに活発に参加しているとのことです。
このイベントを成功させた影の功労者がジョアン・ディッケンソン・デピュイ(Joanne Dickenson DePuy)という人。その功績をまとめた記事が出ていました(Joanne Dickenson DePuy, the Woman Who Helped Change Napa Forever)。この人については、私もほとんど知りませんでした。パリスの審判のTimes誌の記事を書いたジョージ・テイバーによる書籍『パリスの審判 カリフォルニア・ワインVSフランス・ワイン』では主催者のスティーヴン・スパリエの右腕となって働いたパトリシア・ギャラガーについては詳しく書かれていたものの、この方にはほとんど触れられていなかったような気がします。

彼女の功績の一つは、カリフォルニアのワインを選びに来たスティーヴン・スパリエとパトリシア・ギャラガーに、ナパのワイナリーを紹介したこと。彼女が紹介した中に、白で1位を取ったモンテレーナや赤で1位を取ったスタッグスリープ・ワイン・セラーズも含まれていました。
それだけであれば、彼女が紹介せずとも、出会っていた可能性が高いと思いますが、さらに重要なことがあります。試飲会で使うワインをフランスに輸送するという重要な責務を背負ったのです。
彼女は1973年に「ワインツアーズ・インターナショナル」という会社を設立し、ナパからフランスの名産地へのツアーを企画しました。アンドレ・チェリチェフがガイドをするといったツアーまで行いました。そういったことから、スティーヴン・スパリエがナパに来たときのガイド役も務めたのでした。
試飲会用のワインは赤6種、白6種をそれぞれ3本。計3ケース分ありました。スティーヴン・スパリエはそれをフランスに送る手配をしていたのですが、フランスの関税法と航空規制で発送できないということが直前にわかり、デピュイにヘルプを求めたのです。ちょうどアンドレ・チェリチェフのツアーでフランスに行く直前だった彼女はそれを引き受けたのです。
ツアーメンバーが、それぞれの荷物の一部として運ぶ(映画『ボトルショック』ではそのように描かれていました)という案もありましたが、リスクが大きく却下。結局航空会社と粘り強く交渉して、貨物として運んでもらえることになりました。ワインは1本が破損したものの、残りは無事に到着し、試飲会も開催できました。
ちなみに、試飲会でモンテレーナが1位になったことをオーナーのジム・バレットはフランスのツアー中に知ったということがジョージ・ティーバーの書籍にも書かれていたと思いますが、このフランスのツアーこそ、上記のデピュイの主催によるアンドレ・チェリチェフのツアーだったのでした。
彼女は現在97歳。今もナパヴァレーの様々なイベントに活発に参加しているとのことです。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2258b790.029353de.2258b791.7f2b57a7/?me_id=1192052&item_id=10038461&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fricaoh%2Fcabinet%2F299999%2F1%2F209527.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144ff187.5845a648.144ff188.14027247/?me_id=1313045&item_id=10009523&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2F06708016%2F689lotte001_2white.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0292d6ed.405463b7.0292d8e1.9021330b/?me_id=1193924&item_id=10037075&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcellar%2Fcabinet%2Frakuten66%2F437969_y6.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/12f43816.c92f5075.12f43817.57e510ed/?me_id=1193687&item_id=10014368&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faben%2Fcabinet%2F02848488%2Fimgrc0094128856.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15f8a78d.44724680.15f8a78e.47ba2821/?me_id=1196405&item_id=10120244&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoscana%2Fcabinet%2Fw_vt042%2F10135473-n-s.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/038d95cb.9d9c8df1.038d95fa.d86f7c16/?me_id=1213315&item_id=10013048&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fco2s%2Fcabinet%2Fitem%2F201924%2F61009508_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15f8a78d.44724680.15f8a78e.47ba2821/?me_id=1196405&item_id=10140765&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoscana%2Fcabinet%2Fw_vt033%2F10196903-n.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0177b8fc.c1f5787f.0266e827.5145d07d/?me_id=1191797&item_id=10023265&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fumemura%2Fcabinet%2F18%2F16299290900905918_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3294883b.c2a988f6.3294883c.45807055/?me_id=1414700&item_id=10014277&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwinenation%2Fcabinet%2Fimage19%2F10033460_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0292d6ed.405463b7.0292d8e1.9021330b/?me_id=1193924&item_id=10037074&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcellar%2Fcabinet%2Frakuten66%2F437968_y6.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/163c83ed.2587c03a.163c83ee.7b29d7ba/?me_id=1238089&item_id=10010902&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fleluxe%2Fcabinet%2Fimage12%2Fnk513402192106_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01ddf55b.1536d5e2.026e53f6.f86bf59f/?me_id=1194829&item_id=10006133&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkitazawa%2Fcabinet%2F01485085%2Fimgrc0082113381.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10158949&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2025new3%2F2507-1-020_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/016be36e.352119e8.02647f54.69fc4439/?me_id=1206139&item_id=10000451&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyanagiyawine%2Fcabinet%2Fwine%2Fset%2Fcsset202511.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144ff187.5845a648.144ff188.14027247/?me_id=1313045&item_id=10008788&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2F06708016%2Fimgrc0107961795.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/016be36e.352119e8.02647f54.69fc4439/?me_id=1206139&item_id=10007107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyanagiyawine%2Fcabinet%2Fwine%2Fl%2Flincoln.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2258b790.029353de.2258b791.7f2b57a7/?me_id=1192052&item_id=10038433&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fricaoh%2Fcabinet%2F299999%2Fset%2F209812h06.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2258b790.029353de.2258b791.7f2b57a7/?me_id=1192052&item_id=10038434&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fricaoh%2Fcabinet%2F299999%2Fset%2F209813h06.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2258b790.029353de.2258b791.7f2b57a7/?me_id=1192052&item_id=10038444&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fricaoh%2Fcabinet%2F299999%2F1%2F209527.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2258b790.029353de.2258b791.7f2b57a7/?me_id=1192052&item_id=10002302&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fricaoh%2Fcabinet%2F199999%2F199907.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/163a766a.b2a8752f.163a766b.1feb8de8/?me_id=1335910&item_id=10000466&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwine-naotaka%2Fcabinet%2Fitem%2F414293.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/163a766a.b2a8752f.163a766b.1feb8de8/?me_id=1335910&item_id=10011656&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwine-naotaka%2Fcabinet%2Frakuten34%2F432104_sm.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14d9bcba.13d11e47.14d9bcbb.bbc4ff8d/?me_id=1200312&item_id=10050161&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwineuki%2Fcabinet%2Fdefault%2F11%2F02%2F1600001008365_01.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47a42bdc.8141f591.47a42bdd.902c4e9a/?me_id=1371394&item_id=10004395&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fatigus%2Fcabinet%2Fwineset%2F2024%2Fimgrc0131721708.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144ff187.5845a648.144ff188.14027247/?me_id=1313045&item_id=10009307&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2F06694665%2F07868219%2Fkenzo_yui.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144ff187.5845a648.144ff188.14027247/?me_id=1313045&item_id=10009184&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2Fshohin%2F06288737%2Funionsacre_gewurz.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144ff187.5845a648.144ff188.14027247/?me_id=1313045&item_id=10000237&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2F06708016%2F06708023%2Fimgrc0078704616.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/43db55eb.70906a69.43db55ec.57bdbc2b/?me_id=1372274&item_id=10007439&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpieroth-japan%2Fcabinet%2F06995846%2F9309808.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/014c28ee.d2bf7611.0264e2eb.31c14c5a/?me_id=1191946&item_id=10141035&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwassys%2Fcabinet%2F97%2F79768.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144ff187.5845a648.144ff188.14027247/?me_id=1313045&item_id=10009260&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2Fshohin%2F06288737%2Fbodkin_zin_ls.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10156315&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2024new5%2F2502-1-034_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10156214&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2024new5%2F2502-1-035_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10153406&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2024new2%2F2406-1-218_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10156232&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2024new5%2F2502-1-026_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10156243&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2024new5%2F2502-1-018_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10156291&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2024new5%2F2502-1-019_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144ff187.5845a648.144ff188.14027247/?me_id=1313045&item_id=10009119&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2Fshohin%2F06288737%2Fbigsmooth_ovzfld.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/016be36e.352119e8.02647f54.69fc4439/?me_id=1206139&item_id=10007041&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyanagiyawine%2Fcabinet%2Fwine%2Fb%2Fbigsmoothzin.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/044b75c5.13a7de85.044b75c6.eba85410/?me_id=1213379&item_id=10044228&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftamaki-web%2Fcabinet%2Fdragee31%2F20070101.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47a42bdc.8141f591.47a42bdd.902c4e9a/?me_id=1371394&item_id=10003666&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fatigus%2Fcabinet%2F06535577%2F06535603%2Fimgrc0124630353.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0177b7fc.b06f984c.0274226d.5ca674b6/?me_id=1193346&item_id=10446607&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwine-takamura%2Fcabinet%2Fnss_14%2F0833302005387.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0177b7fc.b06f984c.0274226d.5ca674b6/?me_id=1193346&item_id=10448160&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwine-takamura%2Fcabinet%2Fnss_15%2F4573542504382.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15eb146e.531fd5ff.15eb146f.6b6da372/?me_id=1225652&item_id=10011557&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwineschool%2Fcabinet%2F07798833%2Fimgrc0092330706.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1524436f.3dcc3b0f.15244370.33dc3ede/?me_id=1244964&item_id=10005442&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmariage-k%2Fcabinet%2F02572044%2Fcalifornia%2Fimgrc0142339204.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1524436f.3dcc3b0f.15244370.33dc3ede/?me_id=1244964&item_id=10005443&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmariage-k%2Fcabinet%2F02572044%2Fcalifornia%2F11567028%2Fimgrc0142340246.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/014c28ee.d2bf7611.0264e2eb.31c14c5a/?me_id=1191946&item_id=10151044&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwassys%2Fcabinet%2F24%2F72429.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1524436f.3dcc3b0f.15244370.33dc3ede/?me_id=1244964&item_id=10005461&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmariage-k%2Fcabinet%2F02572044%2Fcalifornia%2F11567028%2Fimgrc0142400788.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0177b8fc.c1f5787f.0266e827.5145d07d/?me_id=1191797&item_id=10042698&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fumemura%2Fcabinet%2F16%2F1114080325602916_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0177b8fc.c1f5787f.0266e827.5145d07d/?me_id=1191797&item_id=10042696&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fumemura%2Fcabinet%2F16%2F1116080325608316_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0177b8fc.c1f5787f.0266e827.5145d07d/?me_id=1191797&item_id=10042697&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fumemura%2Fcabinet%2F96%2F112408032560696_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144ff187.5845a648.144ff188.14027247/?me_id=1313045&item_id=10005935&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2F06694665%2F08683208%2Fimgrc0084885178.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144ff187.5845a648.144ff188.14027247/?me_id=1313045&item_id=10008920&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2F06694665%2F08683208%2Fetude_cdcarneros_800.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144ff187.5845a648.144ff188.14027247/?me_id=1313045&item_id=10008921&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2F06694665%2F08683208%2Fetude_csnv_800.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0292d6ed.405463b7.0292d8e1.9021330b/?me_id=1193924&item_id=10009460&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcellar%2Fcabinet%2Frakuten54%2F418076_y6.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0292d6ed.405463b7.0292d8e1.9021330b/?me_id=1193924&item_id=10009461&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcellar%2Fcabinet%2Frakuten54%2F418077_y6.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15f8a78d.44724680.15f8a78e.47ba2821/?me_id=1196405&item_id=10140053&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoscana%2Fcabinet%2Fw_vt032%2F10197369-n.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144ff187.5845a648.144ff188.14027247/?me_id=1313045&item_id=10005709&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2F06694665%2F07051192%2Fimgrc0092097714.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/43db55eb.70906a69.43db55ec.57bdbc2b/?me_id=1372274&item_id=10007781&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpieroth-japan%2Fcabinet%2F06995846%2F9323643.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1524436f.3dcc3b0f.15244370.33dc3ede/?me_id=1244964&item_id=10001014&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmariage-k%2Fcabinet%2F02572044%2Fcalifornia%2Fimgrc0103094889.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15c3740a.3e9ea750.15c3740b.5af4b546/?me_id=1215941&item_id=10009476&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmashimo%2Fcabinet%2Fimage1%2Fen10100067_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14d9bcba.13d11e47.14d9bcbb.bbc4ff8d/?me_id=1200312&item_id=10035968&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwineuki%2Fcabinet%2Ftam01%2Ftam051%2F1400001000501_01.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01fdb818.0640f8e0.03019e57.23afbb9e/?me_id=1195685&item_id=10062243&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fveritas%2Fcabinet%2Ft13%2Fobtzrm22_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)